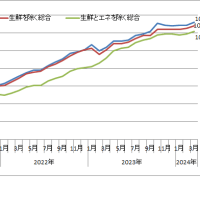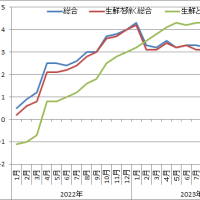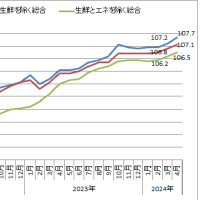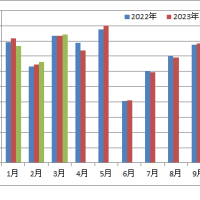このブログのよって立つ基盤は「付加価値」です。
上の緑の枠の下部のサブタイトルにも「付加価値をどう作りどう使うか」と書きましたが、私自身迷った時はここに帰って考えます。
付加価値というのは「人間によって付け加えられた価値」です。ですからこれは人間が使う事が出来ます。そして、どう使うか(種籾をどのくらい残しておくか)で明日の付加価値の大きさが決まります
太昔の話です。作物を育てるのには水が要ります川はありますが水は大雨であふれたり日照りで涸れたりしますから集落の人が集まって溜池を掘り水の供給の安定化を図ります。溜池が大きい方が収穫(付加価値)は安定して増えます。収穫は皆で分けます。
これを現代の企業に置き換えれば、企業の人々が働いて付加価値のある商品やサービスを提供し、社会を豊かに快適にしています。そして作った付加価値の一部を利益(資本形成)として確保し、企業の明日の発展に使います。
こうした付加価値の創造と分配の構図は、大昔から今日まで変わりません。変わったのは、貨幣が生まれ、付加価値は金額として計測可能になり、付加価値創造に参加する人が、集落の人から、経営者、従業員、株主、金融機関、コンサルタント、などと分業により多様になった事でしょう。
複雑化した参加者(スークホルダーズ)はみな人間です、そこで日本的経営では「人間中心の経営」が一つの柱です、も一つは「長期的視点の経営」です。これは昔の人が集落のいつまでも繁栄する事を願ったように、長続きしないと社会が困るからです。最近の概念ではSDGs(持続可能な発展目標)でしょう。
ところで、こんな事を書いたのも、この「経営」という基本概念は、国にも当てはまると考えるからです。
政治というのは、「国家を経営するための活動」に他なりません。企業も、社会も国も、総て人間集団です。
何処の国でも、政府の最大の目的は「経済成長」でしょう。経済成長というのはご存じのようにGDPが毎年何%増えるかです。そしてGDPというのは、その国が作り出した「付加価値」そのものです。
では、大昔の集落の人々と、企業に関わる人々と、日本の国民と、みんな同じ人間集団なのに何が違うかという事になります。
先ず、違うのは規模です、集落なら皆顔見知りですし中小企業でもそうでしょう。しかし大企業、国となりますとそうはいきません。
そこで、知らない人が集まった人間集団を纏めて経営するための方法として、歴史的にいろいろありましたが、今は民主主義が最もいいのではないかという事になっています。
こうした視点で考えますと、長い歴史の偶然の産物なのかもしれませんが、日本という国は、その日本的経営という思想の生まれてきた、縄文以来の1万数千年の歴史から見ても、企業経営の理念と、日本を経営する政治理念が、かなり本質的に、同時に合理的にしっくりと整合する「可能性」があるように感じられるのです。
今、残念ながら日本の政治は「混乱状態」そのもののようです。こうしたときに、日本が舶来崇拝で失敗した点は別枠にし、縄文以来の日本の優れた伝統文化に、多くのヒントがある事に気づく必要があるのではないかと思うところです。