所得格差と資産格差、日本の経験 2
昭和30年代から40年代にかけて、1948年第一次オイルショックが発生するまで、日本経済は高度成長の時代でした。神武景気、岩戸景気、戦後最大の不況といわれた40年不況を挟んで、いざなぎ景気と続きました。
しかしこの高度成長期、日本は資本蓄積不足でした。当時、大蔵省の法人企業統計によれば、法人企業・全産業の自己資本比率は、昭和30年代から低下の一途をたどり、50―51年度に17パーセント(製造業は51年度に僅か13%)まで下げ続け、その後漸く上昇を始めるという状態でした。
ここから解ることは、日本企業は金融機関からの借金経営で高成長を続けてはいましたが、財務比率の面から見れば、資本蓄積は全く成長に追いついていないという状況です。
それではなぜ、日本の銀行は財務比率の年々悪化する企業に融資を続けたのでしょうか。企業が成長さえすれば後から取り戻せると考えたのでしょうか。
その答えは、前回の最後に提起した「収益率が金利より低い企業がなぜ銀行から金を借りて仕事を続けたかと「表裏」の関係になります。
前回、昭和30年代の初期から日本の地価上昇は始まっていたことは書きました。そして、当時、日本の銀行が、土地担保がなければカネは貸さないというのはいわば常識でした。 そして地価は経済成長率・企業収益率を大きく超えて上昇していました。
土地担保で金を借り、土地を取得して工場を建て、ある程度の利益を上げれば、それを上回る大きな利益が地価上昇による含み資産として発生するわけです。
銀行は、その含み資産を評価して、さらに融資を増やし、企業は新たな投資が可能になるという図式でした。
地価が上昇する限り、企業にとって成長のために資金を得ること十分可能だったのです。
第一次オイルショック後の深刻な不況は、この構図に冷水をかけ、企業は本来業務で得た付加価値の中から資本蓄積をするという本来の企業経営に戻り、自己資本比率は上昇に転じることになったのでしょう。こうして高度成長期は終わったようです。
この、地価上昇によって、信用を創出し、それを活用して生産設備を拡大充実、実体経済を拡大(経済成長)するという方式は、高度成長を誇り、世界の工場と言われるまでになった中国でも活用されたように思います。
資産価値の上昇、資産の増殖が顕著でも、増殖した資産価値、つまり資本蓄積が、産業活動の原資として活用される場合には、必ずしも格差問題には直結しないように思われます。
社会を豊かにする産業活動(生産活動)は、人間が資本を活用して行うもので、使用できる資本が大きい方が「生産性はより早く上昇する」(生産性の上昇は、労働の資本装備率に比例する)というのは経験的にも、理論的にも正しいのでしょう。
ピケティの言うように、資本の増殖のスピードが経済成長を上回り、富が一部のものに集中するという過程は、増殖した資本を、経済成長のための資本装備率の向上に使うことによって、回避できるようです。
第二次大戦後、明らかにこうした「例外的な」時期があったということは、敗戦国で版図も資源も限られたドイツや日本が、目を見張る高度成長を実現し、格差社会を生まなかったという実績が、世界に注目され、先進国も途上国も、真面目に経済発展に取り組んだ結果だったと考えるのが事実に近いのではないでしょうか。
昭和30年代から40年代にかけて、1948年第一次オイルショックが発生するまで、日本経済は高度成長の時代でした。神武景気、岩戸景気、戦後最大の不況といわれた40年不況を挟んで、いざなぎ景気と続きました。
しかしこの高度成長期、日本は資本蓄積不足でした。当時、大蔵省の法人企業統計によれば、法人企業・全産業の自己資本比率は、昭和30年代から低下の一途をたどり、50―51年度に17パーセント(製造業は51年度に僅か13%)まで下げ続け、その後漸く上昇を始めるという状態でした。
ここから解ることは、日本企業は金融機関からの借金経営で高成長を続けてはいましたが、財務比率の面から見れば、資本蓄積は全く成長に追いついていないという状況です。
それではなぜ、日本の銀行は財務比率の年々悪化する企業に融資を続けたのでしょうか。企業が成長さえすれば後から取り戻せると考えたのでしょうか。
その答えは、前回の最後に提起した「収益率が金利より低い企業がなぜ銀行から金を借りて仕事を続けたかと「表裏」の関係になります。
前回、昭和30年代の初期から日本の地価上昇は始まっていたことは書きました。そして、当時、日本の銀行が、土地担保がなければカネは貸さないというのはいわば常識でした。 そして地価は経済成長率・企業収益率を大きく超えて上昇していました。
土地担保で金を借り、土地を取得して工場を建て、ある程度の利益を上げれば、それを上回る大きな利益が地価上昇による含み資産として発生するわけです。
銀行は、その含み資産を評価して、さらに融資を増やし、企業は新たな投資が可能になるという図式でした。
地価が上昇する限り、企業にとって成長のために資金を得ること十分可能だったのです。
第一次オイルショック後の深刻な不況は、この構図に冷水をかけ、企業は本来業務で得た付加価値の中から資本蓄積をするという本来の企業経営に戻り、自己資本比率は上昇に転じることになったのでしょう。こうして高度成長期は終わったようです。
この、地価上昇によって、信用を創出し、それを活用して生産設備を拡大充実、実体経済を拡大(経済成長)するという方式は、高度成長を誇り、世界の工場と言われるまでになった中国でも活用されたように思います。
資産価値の上昇、資産の増殖が顕著でも、増殖した資産価値、つまり資本蓄積が、産業活動の原資として活用される場合には、必ずしも格差問題には直結しないように思われます。
社会を豊かにする産業活動(生産活動)は、人間が資本を活用して行うもので、使用できる資本が大きい方が「生産性はより早く上昇する」(生産性の上昇は、労働の資本装備率に比例する)というのは経験的にも、理論的にも正しいのでしょう。
ピケティの言うように、資本の増殖のスピードが経済成長を上回り、富が一部のものに集中するという過程は、増殖した資本を、経済成長のための資本装備率の向上に使うことによって、回避できるようです。
第二次大戦後、明らかにこうした「例外的な」時期があったということは、敗戦国で版図も資源も限られたドイツや日本が、目を見張る高度成長を実現し、格差社会を生まなかったという実績が、世界に注目され、先進国も途上国も、真面目に経済発展に取り組んだ結果だったと考えるのが事実に近いのではないでしょうか。










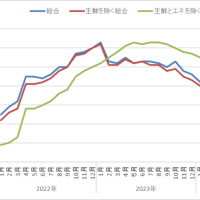
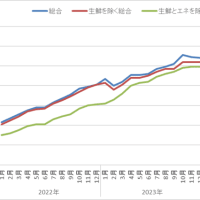









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます