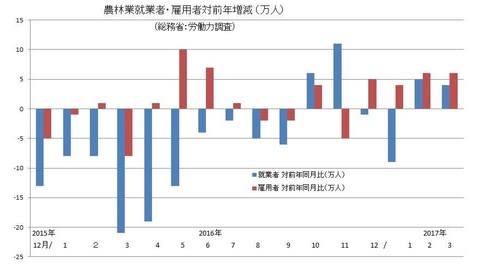伸び悩む月例給与、前年比0.3%、格差は縮小か
今朝、厚生労働省から「毎月勤労統計」の2017年7月分の速報が発表になりました。微妙な経済情勢の中で、なかなか伸びない日本の賃金ですが、どんな様子なのか、一寸見てみました。
先ず平均賃金が前年に比べどのくらい伸びているのかですが、調査産業計・一般労働者(パート含まず)平均で、所定内(月例給)は307,827円で前年比0.3%の伸び、所定外(残業代等)26,220円で0.4%の伸びとなっています。
春の賃上げはもう少しあったはずですが、平均賃金の上がらない理由は、こんなところでしょう。
賃金の高い高齢者が定年になり、初任給採用の新卒者が入るので、平均はあまり上がりません。高齢者の定年再雇用などでも賃金は下がります。これは年功賃金色の残る日本の賃金制度の結果です。
一方、パートタイム労働者は所定内が93,770円で、前年比1.1%の増加で、一般労働者より上がっていますが、一方、パートの平均労働時間は前年比1.3%下がっているので、時間当たり給与は前年比2.9%増となっています。
求人倍率の高さなどを反映して、パートの賃金は上昇傾向がはっきりしていますが、ここでは、賃金を上げて一般労働者との格差を縮めるのがいいという意見と、正規労働者(毎月勤労統計では一般労働者)を増やすべきだという意見とがあるでしょう。
パートタイム労働者比率は、0.08%ですが前年比で下がっていますから、これは良い傾向でしょう。
しかし、いずれにしても、賃金の伸びは、そう大きいものではありません。政府は賃金を上げて景気を回復させようとしているようですが、賃金は労使で決めるものですから、経済社会の環境でも大きく変わらなければ、大きな伸びなどは容易ではないでしょう。
今の大変不安定な内外情勢を考えて見れば、政府も、賃金引き上げ要請ばかりでなく、もう少し違った、世の中を広く見た経済政策、国民が何とか将来に期待を持つような総合政策が必要なように感じる人が少なくないのではないでしょうか。
今朝、厚生労働省から「毎月勤労統計」の2017年7月分の速報が発表になりました。微妙な経済情勢の中で、なかなか伸びない日本の賃金ですが、どんな様子なのか、一寸見てみました。
先ず平均賃金が前年に比べどのくらい伸びているのかですが、調査産業計・一般労働者(パート含まず)平均で、所定内(月例給)は307,827円で前年比0.3%の伸び、所定外(残業代等)26,220円で0.4%の伸びとなっています。
春の賃上げはもう少しあったはずですが、平均賃金の上がらない理由は、こんなところでしょう。
賃金の高い高齢者が定年になり、初任給採用の新卒者が入るので、平均はあまり上がりません。高齢者の定年再雇用などでも賃金は下がります。これは年功賃金色の残る日本の賃金制度の結果です。
一方、パートタイム労働者は所定内が93,770円で、前年比1.1%の増加で、一般労働者より上がっていますが、一方、パートの平均労働時間は前年比1.3%下がっているので、時間当たり給与は前年比2.9%増となっています。
求人倍率の高さなどを反映して、パートの賃金は上昇傾向がはっきりしていますが、ここでは、賃金を上げて一般労働者との格差を縮めるのがいいという意見と、正規労働者(毎月勤労統計では一般労働者)を増やすべきだという意見とがあるでしょう。
パートタイム労働者比率は、0.08%ですが前年比で下がっていますから、これは良い傾向でしょう。
しかし、いずれにしても、賃金の伸びは、そう大きいものではありません。政府は賃金を上げて景気を回復させようとしているようですが、賃金は労使で決めるものですから、経済社会の環境でも大きく変わらなければ、大きな伸びなどは容易ではないでしょう。
今の大変不安定な内外情勢を考えて見れば、政府も、賃金引き上げ要請ばかりでなく、もう少し違った、世の中を広く見た経済政策、国民が何とか将来に期待を持つような総合政策が必要なように感じる人が少なくないのではないでしょうか。