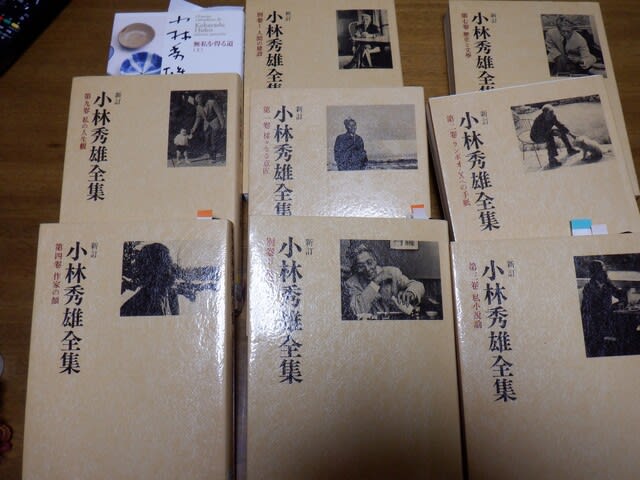
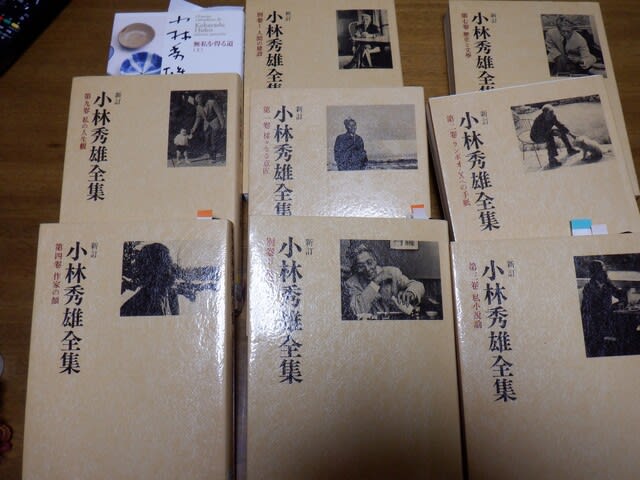
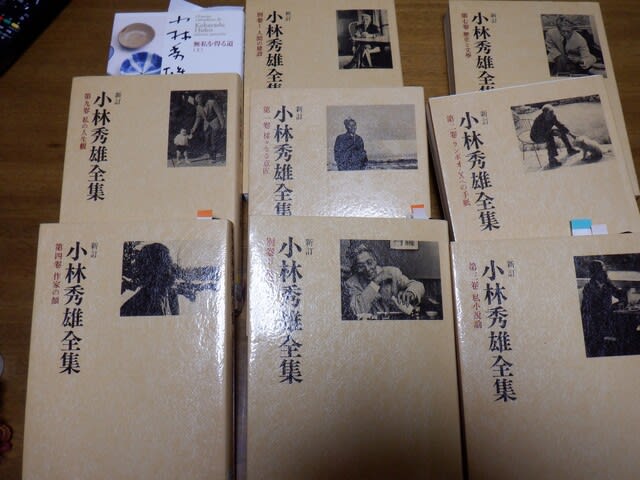

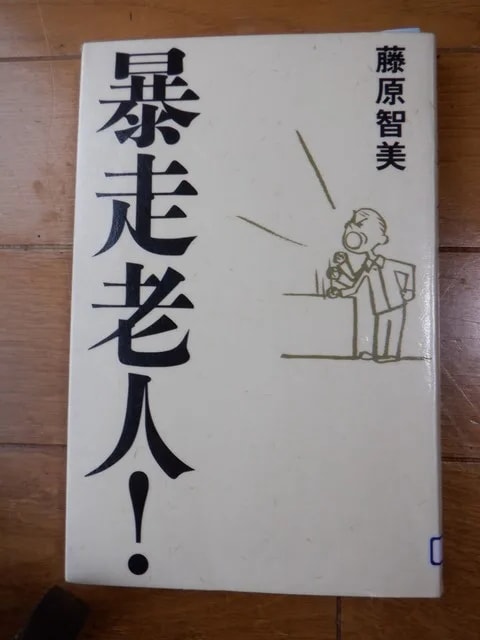
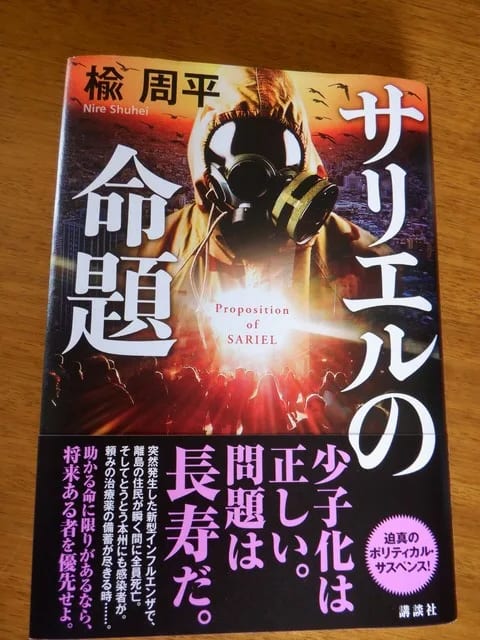
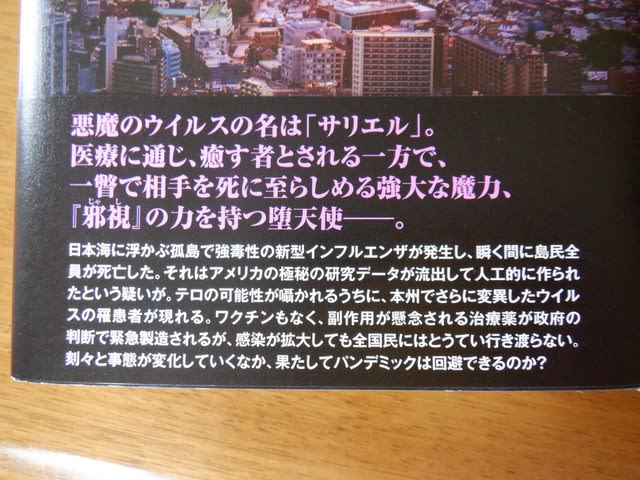





本を整理していたら、可愛い本に出会った。高田宏著「山へ帰った猫」である。高田氏の次男の猫の挿絵がすごく可愛いのだ。
高田氏の別荘が八ヶ岳にある。清里駅の隣、野辺山駅から下りて行くところで、どこかは分からないが、山荘より八ヶ岳の最高峰赤岳が見えるところにあるらしい。
赤岳を眺めてみたい。八ケ岳とはどういうところなのか行ってみたい。

愛する者に作る弁当は素晴らしい。
「今日も嫌がらせ弁当」が、今上映中と娘が教えてくれた。気になるねえ。娘を持つ身の上には気になる映画だろう。
イオンシネマ新小松へ行こうかと思ったが、9時45分からと16時からでは、どちらも食事を作る時間にかかるので難しい時間だ。せめて13時とか14時始まりなら・・。
本屋へ行くとその本があったので買ってしまった。すぐに読んで娘の家へ持っていく。

改訂版とある。何も考えずに買ってしまったが、改訂版ということはそうでないのもあるようだ。

「あいだあみつお」みたいな字で「ねむいんだもの」を、見たとき共感し笑ってしまった。だよね。よく頑張ってキャラ弁を作ったものだ。すごい。
かおりさんのブログで共感できたのは、「一人だとこうなるご飯」と、言うのがあって、それもやっぱりそうだよね。と、共感。
本を読んでいる最中、我が家の電話が鳴った。留守電にしてあるので放っておいた。固定電話にかかるのはろくでもないものばかりだ。
聞こえてきたのは「聖書では、与えられるよりも与えるほうがしあわせである・・云々」そうかね。与えてもらうほうが嬉しいけどね。と、言いたい気がしたが、この本を読んでいると、どうも与えるほうが楽しそうではあるな。
いつも山登りの時の心配がトイレである。けれど、なかなかその話はしにくい。登山は男の人の案内で行くことも多いので、言い出しにくく、女性が一緒の場合はほっとするところだ。昔は「花摘み」とか、「雉うち」に行くと言ったらしい。
その話を堂々と書いてくれたのは、かの有名な登山家である今井通子さんだ。登山家である前に、泌尿器科の医師である。両親と妹ふたりと弟の五人が眼科医という中でひとり、食卓で症例の話が出来ないという今井さん。
さて、わたしは朝トイレに行くと、午後2時か3時くらいまでは平気だが、調子の悪い時は困るのである。鞍掛山なら2時間なので大丈夫。富士写が岳は、ダム湖の管理事務所のトイレを借りてから登れば下りるまで大丈夫。しかし、先日のように雪山の場合不安だった。朝8時30分に登り、頂上で3時間作業に付き合って下りたので7時間大丈夫だった。しかし、前もって対策を練って、いざとなったらどうするか考えなくてはならない。そんなこんなで、トイレの問題は一番悩むところではある。その時は、歩くと汗も出て、水分も控えて、お腹にカイロを貼ったので効果はあった。しかし、頂上で太ももに痙攣が起きたのは水分不足かなと思った。寒いので温かいハーブティを持っていったので少しは飲んでいたが、その辺のところはどの程度どうなのかよく分からない。しかし、トイレの問題は深刻で、有名な女性登山家がトイレをするために滑落して亡くなったこともある。あだやおろそかには出来ない問題だ。
さて、本の話だが、今井通子さんの「マッターホルンの空中トイレ」は、読んだだけでも想像するに怖い。4000mの所に飛び出して作られているトイレで、空中にあるような形で、北壁に落ちるようになっているのだ。床の下が2000m、3000m見えるわけだ。
世界のトイレの写真入りで、単行本は「TOTO出版」だった。なるほどねえと思ったが、文庫本もあって、こちらは中央公論社である。やはりどんな山でも、個室の水洗トイレがあるとほっとする。文化的な生活を営んでいるので、野生にはなりきれない。女性として世界初の欧州三大北壁登攀その他、数々の記録を残している今井通子さんも、トイレは落ち着けるところがいいねと。そして、下品な話ではなく、医学的には大事な話だとおっしゃる。わたしがその話をすると、孫たちに下品だと言われるのはなぜか。
腰が痛くて眠れない。これもインフルの症状のひとつらしい。
セカオワの藤崎さんが書いた「ふたご」を、先日本屋へ立ち寄った時に、なんの躊躇もなく買ってしまった。セカオワの歌が好きなら、オリンピックの「サザンカ」の歌もまだ耳新しい今、聴くほどにせつないのはどこから来るのかを知りたいと思ったら買わずにはいられなかった。
夜眠れなくて、むさぼり読んで3時に寝た。明日も休みだと思うのと、読んでいると身体の痛みを忘れるからだった。
これは、深瀬と藤沢さんのことなんだろうと思った。まるで、映画を観ているような話の展開で途中で寝るわけにはいかない。居場所を音楽と仲間の中に見つけるまでのふたりの生きざまは、ずっと昔読んだ「ノルウェイの森」の悲しさに似ていた。でも、このふたりは居場所を見つけ、自分たちを表現できたのだ。読み終わって本を置いて目をつぶったら、頭の中がぐるぐるまわるようで辛かった。おかしな夢ばかり見た。


1956年2月24日から1957年8月22日まで「朝日新聞」に連載された井上靖著。
この単行本は2005年12月発行で、図書館で借りて読んだ。
実際にザイルが切れた事件があって、それをモチーフにしたようだが、読み始めてすぐ主人公魚津は友人小坂と大晦日に穂高の東壁に登る。山のことを知っている人は、穂高の東壁と言えば「氷壁」と、すぐに答えるだろう。さて、小説を読み始めて5分の1でザイルが切れるのであるが、その後、延々とそれについて書かれているのだ。ザイルがどうして切れたかという物理的な原因と、絡み合う女性問題。
ザイルが切れたというだけで、延々と長編を書けるというのは、やはり小説家の才能だ。
この後、延々と500ページ読破。はっはっは・・・最後は、切なく終わって、何だこれは!!と、思いつつ再版され、映画にもなるこの小説は、一体どうなるんだろうと興味をそそられて読めていく。それにしても、ふたりの男が惚れる八代夫人は、命をかけるほど魅力的だったのか?この辺が怪しい。無理がある。と、言いつつ久々に夜更かししてしまう本だった。
加賀市の仲間は白山が好きだというのには根拠がある。もちろんその美しく雄大な姿を毎日観ることもそうだが、深田久弥の存在も大きい。
先日のふるさと人物ロードで、数ある人から深田久弥と、中谷宇吉郎を選んで撮ることからも、私自身思い入れがある。深田久弥と言えば加賀市のみならず登山家で知らない人はいないと思う。加賀市の人にとってはふるさとの白山を絶賛する深田久弥を白山と同じくらい大切に思っている。
中谷宇吉郎もわたしにとっては、大好きな人だ。大学時代に弓道部に入っていたのだ。雪の科学館へ行ったとき写真があって知った。単純な理由である。しかし、もと石川県弓連の北村会長はよく言われた。弓引きに悪い人間はいないのだと。
さて、入院中に友達から借りた本を読み終えた。「私の小谷温泉」深田久弥の奥さんが書いた本である。まず、題名から間違えて読んでいた「おたりおんせん」と読むのだと分かった。そして、これを書いた深田志げ子さんは、後妻として入ったのであることを知った。また、先妻さんは女流作家だったそうだ。
志げ子さんの文章は優しく読みやすい。活動的で久弥さんを支え共に楽しい登山をしている。

深田久弥が留守中に、たくさん溜まった山の本を入れる小屋を建ててしまうと言う積極的な人で、またその事を久弥が大層喜んで「九山山房」と、呼んだあたりのふたりのあうんの呼吸が伺われる。
「日本百名山」が、完成した後に、お金が入って、九山山房を建て直そうかと思案している文章の後に、「中央アジアの旅も本小屋の改築も『日本百名山』が私たちに与えてくれた夢である」と、あったが、今やそれは日本の登山家に引き継がれた夢とも言えるのではないか。わたしは登山もしないのに「日本百名山」は、持っていて、行けもしない遠い山を思ったり、友達が登った山を探す。
さて、志げ子さんは女性の目から観る山と深田久弥について、共感できてとても興味深く読める。
題名がなぜ「私と久弥」ではないのか。内容は殆ど私と久弥であるのに。それは、信州の小谷温泉が出会って間もない頃の初めてのふたりの山旅だったからだ。それが二人にとって最高の思い出の山行きだったに違いない。この時はただならぬ仲だったとか。先に逝くと秘密がばらされますなあ。ちなみに、副題には「深田久弥とともに」と、ある。
わたしは殿と初めて登った山は「鞍掛山」だが、わたし達には冴えない題名が付いた。すでに事件簿をご覧の方はご存じと思うが「おとぼけ家族のプチ遭難」である。山へ行きたかったわたしに諦めが刷り込まれ、憧れの白山は遠く霞んでいくのであった。