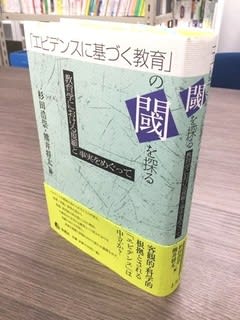
9月26日に、杉田浩崇・熊井将太編『「エビデンスに基づく教育」の閾を探る―教育学における規範と事実をめぐって』(春風社、2019年)が発行され、拙稿を第10章として載せていただきました。今回は、杉田・熊井著の紹介をさせてもらいます。私の関心からまとめていますので、そこはご注意を。もう少し編者の意図に沿って理解したい人は、同著の「はじめに」と「おわりに」で内容が手際よくまとめられていますので、読んでみて下さい。
さて、日本で「エビデンスに基づく教育」(Evidence-Based Education: EBE)が主張されるようになったのは、2000年代末頃からです(イギリスでは1990年代以降)。教育学では、2015年の日本教育学会編『教育学研究』第82巻第2号の特集「教育研究にとってのエビデンス」によって議論が始まったばかりと言っても良い状態です。EBEに対して、おおまかに推進派と反対派とがいますが、両者の議論はかみ合っていないことが多いようです。本書は、このような研究の現状を踏まえて、EBE推進・反対両派の対話を促進するプラットフォームをつくることを目指しています。そのための観点が「閾(いき)」です。本書は、自然科学史における非自然科学と自然科学との境界画定において「客観性」や「透明性」などを自然科学特有のものとして区分してきた過程と重ね合わせ、EBEをめぐる議論を境界線を引こうとする過程として捉え、その「閾」(境目)に注目することで何が排除、または強調されるようになるかを批判的に明らかにしようとしています。
本書は3部構成、全10章+はじめに・おわりにで構成されています。章構成は以下の通りです。
はじめに
第1章 「エビデンスに基づく教育」という問題圏―科学思想史からその磁場を問う(杉田浩崇)
第1部 教育政策・制度と「エビデンス」とのあいだ
第2章 教育政策においてエビデンスを「つかう」とはどういうことか(佐藤仁)
第3章 エビデンスを「つくる」ことと「つかう」こと(長谷川祐介)
第4章 教育政策・制度の中で教師はどのように「エビデンス」に応答しているか(熊井将太・杉田浩崇)
第2部 教育実践と「エビデンス」とのあいだ
第5章 EBEを実践で語ろう(森俊郎)
第6章 現象学的教育学を基盤とした教師教育における確信形成への省察の契機(宮原順寛)
第7章 エビデンスは幼児教育に何をもたらすのか(岡花祈一郎)
第3部 教育研究と「エビデンス」とのあいだ
第8章 「エビデンス」は中立的か? ―英米圏における批判的脳科学の射程(杉田浩崇)
第9章 「エビデンス・ベース」時代の教育実践研究 ―ジョン・ハッティのVisible Learningをめぐる議論から(熊井将太)
第10章 明治日本における教育研究 ―教育に関するエビデンス追究の起源を探る(白石崇人)
おわりに 「エビデンスに基づく教育」の展望 ―対話のプラットフォームをひらく
上記の通り、本書は、教育政策・制度と教育実践、教育研究それぞれについて、「エビデンス」との「閾」をさぐっています。第1章では、主にビースタ(G. Biesta)の理論と科学社会史(というよりも科学史理論にかかわる科学哲学)、そしてアクターネットワーク理論をもって、EBEの「閾」を問うことの重要性を主張しています。例えば、ビースタのいう「教育の学習化(learnification)」や「中断の教育学」などの理論から、「エビデンス」による境界画定によって、学習に対する効果的な介入ばかりに注目が集まり、教育の目的が問われなくなってしまったり、教師が教育的に望ましくないと判断したときにエビデンスに従って行動しないという権利を奪われてしまったりすることを指摘しています。また、境界画定過程や「閾」に注目する意義については、科学社会史・アクターネットワーク理論から導かれています。
第1部では、教育のエビデンスの「つかう」「つくる」「つたえる」場面の仕組みをそれぞれ検討して、それぞれの場面におけるエビデンスの性質や課題を明らかにしています。第2章では、政策科学の知見を踏まえて、教育政策においてエビデンスを「つかう」ことの意味を検討しています。まず、教育政策におけるエビデンスの役割は、政策の非合理性という文脈の中の合理性を高めることにありますが、政策過程の合理性を高めること自体が複雑であり、そもそも政策決定のモデルは多様であって合理性モデルはそのうちの一つにすぎないことを指摘します。また、他の要素と比べる時のエビデンスの優位性は、政策目標や政策決定・評価過程の種類によって決まるのであり、どのような教育が望ましいかという教育的価値や規範をめぐる議論を通してこそ高まっていくだろう、と主張しています。第3章では、量的研究、特に社会学や統計学の文脈で計量分析に従事する研究者が教育のエビデンスをどのように「つくる」か、その実態や課題を検討しています。計量分析においては、多様な現象から計量化可能な変数のみを取り出し、因果関係を想定してそのメカニズムを解明しようとして、因果関係を正しく証明できる良質な調査データを入手することに腐心することになります。データ収集を行うには、反実仮想やRCTなどの因果推論の分析方法によって、研究上の介入がなければ存在しなかった状況や個体群を作り出します。また、学校研究の場合、調査に協力する学校や教師に対して「なぜ調査を行うのか」という説明責任に応答する必要があるので、今後の量的研究は、教師の実践知と研究者の因果推論の知見とをあわせながら、学校現場にとって意味のある物語としてのエビデンスを作り出すことが求められると述べています。第4章では、エビデンスを「つたえる」現場をおさえるために、インタビュー調査を分析して、実際の学校教員がエビデンスをどのような文脈で位置づけているか検討しています。そして、エビデンスは、実際の学校・学級の文脈の中で育てたい児童生徒の姿や目指したい教師像、そして教師自身の達成感と結びつくことで広がっていくことを明らかにしています。また、目の前の子どもをよくするための教育実践を実現する主体として教師自身が意識している場合にはエビデンスを相対化することができますが、教師になった時からエビデンスの重要性を強調されている若手教員や、自分の実践に困難や不安を抱えている教員にとっては、エビデンスは正しいものとしてストレートに受け止めてしまって、エビデンスとの応答を自分なりの授業観を確立する出発点にできない可能性があると指摘しています。
第2部では、EBE推進派とEBE反対派(または慎重派)の立場から具体的にすべきことをそれぞれ検討しています。第5章では、学校でEBEを推進する立場から、EBEを推進するには具体的に何をすべきかについて検討しています。段階的な情報処理のための「5ステップ」と、効果的な介入のための思考形式である「SICO」(Student, Intervention, Comparison, Outcome)とを前提におきながら、読みの学習と対人関係に課題のあった中学一年生に対する実践(個別生徒に対するEBE実践)と、エビデンス・リテラシーの育成および学校改善サイクルの活用を進めた実践(校内研究におけるEBE実践)とを解説しています。第6章では、現象学の立場から、エピソード記述の重要性や「正しい判断」と「正しいと確信する判断」との違いなどを指摘し、教師教育においてエピソード(鯨岡峻)を協働的に省察することを通して「正しいと確信する判断」に近づくことを主張しています。第7章では、海外の就学前教育におけるエビデンス研究を通して、幼児教育に与えるエビデンスの影響について検討しています。特に、OECDやヘックマンなどが強調している社会情動的スキルについては、脳科学や経済学、心理学の知見と結びつくことでより強固に支持されるようになっており、この能力をより正確に測定しようとする研究や、産出されたスコアのみを問題にしてスコアが高くなるような活動や指導・支援を良いとする動向を生み出していると述べます。これが進むと、可視的な保育行為のみを評価して教師の自律性や専門職性が考慮されなくなるおそれがあると、著者は警鐘を鳴らしています。また、心理学・経済学は、教育をあくまで「介入」や「訓練」と見なしてエビデンスを産出しており、虐待やいじめなどの社会問題の原因を個人の情動を統制する能力不足に結びつけて、個人の感情などをも能力と見なしてそれらを外部から介入してコントロールすることを教育に求めてきているため、幼児教育では、目の前の子ども一人ひとりの中に育ちつつあるものを丁寧に読み取り、言語化していく作業が一層求められるようになっている、と述べています。
第3部では、エビデンスの受容・批判や科学的知見の研究などの観点から、EBEに対する向き合い方について教育哲学・教授学・教育史の立場からそれぞれ検討しています。第8章では、脳科学の受容をEBEの潮流の一つとして捉え、批判的脳科学の知見を踏まえて、脳科学の知見が埋め込まれている政治的・社会的文脈を問い、教育研究・実践に受容されるときの社会的な次元を検討しています。科学は、客観的・価値中立的な「自然」を明らかにするものというよりも自らを非科学と対置させながら「自然」なものとして規定するものであり、脳科学も同様です。脳科学の知見を批判するには、可視化されて「自然」なものと見なされる(自然化)と規範性を帯び、それをもとにして「正常/異常」という区分が設けられ、異常な脳に「介入」が要請されていくことなどを視野に入れる必要があると述べています。また、脳画像化技術の捉え方は脳科学者と患者とでは異なります。特に患者とってはそのエビデンスは、自分の過去を再構成し将来をイメージするように用いられ、新たなナラティブをもたらしています。これらのことを踏まえて、教育学は、脳科学が特定の理論的前提を伴っていることを前提にして、脳科学の「自然化」とその規範性との関係について反省的に捉ええるとともに、教師や親がどのような文脈で脳科学のエビデンスを位置づけて新たなナラティブを語り紡いでいるかを明らかにする必要がある、と提言しています。第9章では、ハッティのVisibule Learningをめぐるドイツ語圏における議論を通して、エビデンスベースの普及・浸透の進む時代における教育実践研究の課題やリスク、展望を検討しています。ドイツ語圏では、ハッティの研究方法とその確率的言明、教育目標・内容論の欠如について批判が行われています。ハッティへの批判はそのまま批判者側に返ってくる性質のもので、拠って立つ学問の固有性や社会的意味を問われていることを指摘しました。そこから、実証的研究を教授学の外にすえて対立的に捉えるのではなく、構成要因の一つとして、その発展が教授学概念のさらなる変容を促すものとして捉え、これまでの問い方・答え方を吟味していかなる枠組みで対応しようとしているか見極めることが大事であると結論づけています。第10章では、日本における教育に関するエビデンス追究の起源をたどるために、日本の教育研究の歴史において科学性を追究する動きがいつどのように始まったかを明らかにしています。日本の教育研究における科学性の追究は、早くは1880・1890年代、本格的には1900年代に始まっており、それは教育学の世界だけでなく、教師の専門職性の形成や教育政策過程とも関連しながら進んでいましたことを指摘しています。1900年代には、科学的根拠に基づく教育実践の追究が学者よりも教師に期待されるようになり、教師たちは科学的根拠の受け手や使い手ではなく、作り手として教育学の中に位置づけられる事態も発生しました。また、教師たちの教育研究はすでに教育学の意図を超えて独自に発展しており、科学的根拠を生産するだけではない意義(力量向上や問題解決、アイデンティティ形成にわたる意義)をもって多様化していたことも指摘しています。教育研究における科学性の追究の事実が1880〜1900年代の日本に認めることができるならば、今後、今回対象外にした1910年代以降から現代のEBE論争に至るまでの歴史を、教育研究における科学性追究の延長線上に位置づけてみる必要があると主張しています。
以上のように、本書は、エビデンスを「つかう」「つくる」「つたえる」の各場面や、EBE推進・反対・慎重の各立場、教育哲学、教授学、教育史、それから教育制度・政策学、教育社会学、幼児教育学、教師教育学の各分野から、EBEの性質や課題について詳しく明らかにしています。残された課題も山積していますが、本書は、EBEの規範性を明らかにして、教育政策・実践・研究の場それぞれでエビデンスやEBEにどのように向き合うべきか提言しようとした本と言えると思います。
本書の意義はこれから研究が進んでいく中ではっきりしてくるでしょう。個人的には、第10章はまだ研究の序章にしかたどりついていないと思っています。今後は、1910年代以降の教育研究の歴史的研究を進め、EBEの歴史性について明らかにし、EBEの歴史的意義を見極めたいところです。もちろん、自分一人でできることとは思っていませんので、関心をもつ人はいないかなあと思っています。EBE論争で交わされる言明、例えば「教育はエビデンスを軽視してきた」という言明はある意味で正しく、ある意味では間違っているし、「EBMのように、EBEこそ教師の専門職性や教育政策の確実性を確立させる」という言明も歴史的に必要な言い方であると同時に、使い古された言い方でもあります。EBEとは何なのか、教育学はどう受け止めて今後につなげていくべきかについては、1990・2000年代を出発点にして語ることでは、十分に明らかにならないことがあると思っています。EBEの意味を追究することは、教育学史研究、とくに狭義の教育学を超えた教育研究の歴史の研究が必要であり、教育学・教育研究の現在地と行き方を考えていくために欠かせないことだろうと思っています。














