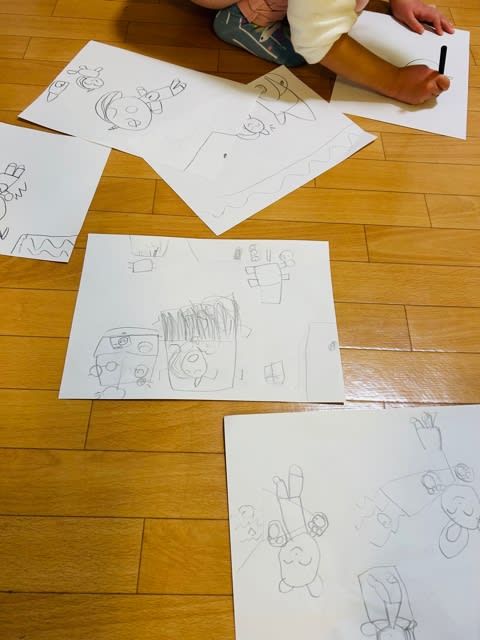2024年が暮れようとしております。皆さんの2024年はいかがだったでしょうか?
私の2024年は変化の年になりました。昨年の年末に新しい職場が決まり、大慌てで引っ越しや娘の保育園探しを進め始めた年始でした。ゼミ生や担当科目の引継ぎも苦労しました。何より、関係者には本当にご迷惑をおかけしました。特に、ゼミ生たちは様々に葛藤したはずです。しかし、最後は、「先生が長年の夢をかなえるんだから」と前向きにとらえて追い出してくれました。本当にありがとう。(写真はこの時ゼミ生からいただいたカップです)

4月からは広島大学教育学部で15年ぶりに働くことになりました。それまでの地方小規模私立大の教職課程担当教員としての働き方とはまったく違う働き方になったので、慣れるまでにちょっと時間がかかりました。しかし、これまで私が一番やりたかった仕事に集中できるようになったので、生活はとても充実していました。今年のゼミ生は学部3年生3名だけですが、皆優秀で、とても指導しがいのあるゼミ生たちです。後期からは外国人研究生1名を迎え、博士論文執筆を目指す本大学院卒業生もお1人、私のゼミに出入りするようになりました。来年度は、ゼミ生をはじめ指導学生が徐々に増えていく見込みです。
私が指導する学生たちは、教員になる人もいますが、それがゴールの人たちばかりではありません。特に広島大学教育学コースで大学院まで行く人は、教育学の研究者を目指し、多くは教職課程担当教員すなわち「先生の先生」になっていきます。私の仕事は、教育学の研究者として一人前に論文が書けるようにするのはもちろん、「先生の先生」として立派な働きのできる人を育てることです。最近、教育学コースで設けている教職課程担当教員養成プログラムの修了予定者が履修する最後の科目の初回がありました。私が科目担当になっているので、最初に話をする機会があったのですが、そこで「形式的作業に終えず、自分のために、将来出会う学生たちのために、そしてその将来の教師たちが出会う子どもたちのために、しっかり取り組んで下さい」と声をかけさせてもらいました。「『先生の先生』の先生」としての仕事。頑張ろうと思います。
さて、研究については、3月までに前年度の成果を出し切りました。『History of Education』誌掲載の英語論文は、6月にようやく紙媒体に掲載されたようです(実物を手にできていないので伝聞ですが)。これでいったん、鳥取短大・広島文教大での研究成果は形にし終えたと思います。これからは、広大の教員としての研究活動です。
6月からは学部1年生対象の「日本東洋教育史」の講義が始まり、自分なりの通史教育を始めました。テキストは講義開始に間に合わなかったので、形にするのは来年度になります。また基本的にKindle版で販売すると思いますが、今度はいずれ紙版も販売できるように画策中です(Kindle版の発売を先行させて、紙版の発売はタイミングをずらずかもしれません)。
4月から、研究が主要な業務の一つになったので、めいっぱい研究に取り組みました。結果として口頭発表を7つも形にしました。年頭からの発表も足すと、口頭発表9つです。これは間違いなく自己ベスト新記録。研究ではまだまだやりたいことがたくさんあるので、時間はいくらあっても足りないくらいです。今年の発表は久しぶりに史料にじっくり取り組んで準備しましたが、試論的な取り組みが多かったので、論文化できているものはまだありません。しかし、すでにいくつかは活字化が決まっており、3月までにはいくつか公表できそうです。
史料保存の取り組みも進展しました。まずは沼田家文書の保存活動が結了しました。故沼田實氏の実子の方々がお持ちだった分も含めて、ご遺族の御意向を受けて、すべて広島県立文書館に寄贈することができました。文書館に寄贈する前に、一部の史料を広島大学内で公開できたこともよかったと思います。院生・学生・教職員に日本教育史の仕事の一端を、実物展示で示すことができました。また、一部三原市内に残っていた沼田家文書の史料(三原小に寄贈したものを除く)も、最終確認して収集し、これも文書館に寄贈することができました。さらに、8月には、長野県飯山市で廃校予定三校の史料目録作りのお手伝いもできました。十分な戦力には、なれたと思いませんが、私自身にとっては史料保存活動の貴重な経験になりました。さらに、12月には、新たな史料群の整理にお声がけいただき、膨大な量の史料に圧倒されながら鋭意作業中です。
史料保存の活動に携わった経験は、後期の学部2年生対象科目「日本東洋教育史演習」の授業に活かすこともできました。史料に出会う機会は突然にやってきます。そのときに少しでも確実な手立てを講じることのできる人材を育てるために、出来ることを考えています。
来年度の仕事は今年度とはちょっと変わってくる見込みなので、今年のようにはいかないと思いますが、それでも研究と教育が一番の仕事であることには変わりありません。研究でも新しい取り組みをしていきたいと思っておりますし、これまでの仕事をとりまとめて新しい研究書も出していきたいです。
今年お世話になった方々に感謝しながら、2024年を締めくくりたいと思います。また来年もよろしくお願いします。