『武谷三男の生物学思想 「獲得形質の遺伝」と「自然とヒトに対する驕り』(伊藤康彦:著 風媒社)を読んだ。
タイトルでは武谷三男が強調されているが、内実は武谷を始めとする一群の科学者たちが、サブタイトルにあるような「獲得形質の遺伝」を主張するソ連(当時)のルィセンコの遺伝学説をどう受容し、どのようにそれから離反したのかの20世紀中葉の数十年のドラマである。

結論を言ってしまえば、遺伝子細胞の働きを無視した「獲得形質の遺伝」を唱えるルィセンコ学説とそれに依拠したソ連の農業生産の破綻は誰の目にも明らかな歴史的事実で、1960年代には生物学界からとっくに葬り去られた立場といえる。
いささかカリカチャライズしていうならば、親が身体を鍛えれば丈夫な子が生まれるとか、あるいは親が整形手術をすればそれが子にも受け継がれるといったたぐいのいわば疑似科学、ないしは政治的背景を伴った信仰といってもいい理論であったことは現在では明らかになっている。
もっともそれらがまことしやかな「科学的」な装飾や「哲学的」包装のもとに提示されたのであるから、とりわけ一定の党派性をもった科学者たちにとってはその足元を掬われる結果となったといっていい。
そうした過程を著者は、戦前から戦後にかけて、ルィセンコに同調した日本の科学者の記述を克明に追跡し、跡付けてゆく。その所作は、これでもか、これでもかといった作業の連続で、既にしてその歴史的生命をとっくに失ったはずの対象をかくも丁重に引っ張りだし、その醜悪さをいまさらのごとく確認することはないだろうという気すらする。
しかし、読み進むうちに、著者のこの根ほり葉ほりの記述が決して単なる後追いの作業ではないばかりか、極めてアクチュアルな問題を含むものであることがわかる。

このルィセンコ学説は、本場のソ連ではスターリンの支持を得て、さらにはその適用とされる農業実践上での「偉大な成果」を受けて、政府、党ご用達の生物学理論となり、それに同調せずメンデル=モルガンの遺伝学説を堅持した学者たちは学界から追放されたり逮捕されたり、獄中でその生命を失ったりさえしている。
今から振り返れば、それらは科学史上の一大スキャンダルであったことがわかる。
そうした過程と並行するようにわが国にもその理論が導入され(1930年代)、とりわけ戦後には、日本共産党の機関誌の『前衛』や新聞『赤旗』がそれを広く公認し、それに反対するメンデル=モルガンの遺伝学説を堅持する人たちを、ブルジョア的、資本主義的イデオロギーに毒されたエセ科学であると断罪するに及んで、広く日本の左翼的といわれる科学者を捉えていったのであった。
その科学者たちこそ、この書で俎上に載せられている武谷三男や、それに先行したり、あるいはそれに追従したりした人たちである。
しかし、そのルィセンコ学説も既に述べたように、次第に化けの皮が剥がれる。まずは実験に裏打ちされていない思い込みのみの空論であったことが明らかになり、農業実践での「偉大な成果」といわれたものも、実際には飢饉をもたらしかねない失敗の連続であったことが明らかになる。
日本でもこのルィセンコ学説に基づくヤロビ農法(あるいはミチューリン農法)が左翼が支配する日農などにより実践された時期があるが、それらは騒がれたほどの成果を上げることなく自然消滅状態となった。

さて、著書の方に戻ろう。著者はそうしたルイセンコ失脚後においても、それら日本の科学者(武谷ら)がどんな言説を弄していたのかを紹介しながらその虚妄さを暴きだしてゆくのだが、なぜ執拗とも思えるほどこれに関わりあった科学者たちの言動を追跡したのかについては二つの理由があるように思える。
そのひとつは、武谷を始めとする錚々たる科学者たちが、なぜ、こうした今から考えるとそれ自身エセ科学ないしは疑似科学でしかなかった理論にやすやすと同調したり、あるいはそれに同調しない科学者に対し、偏狭なブルジョアイデオロギーの持ち主であるといった決め付けや罵倒を行うことができたのだろうかいうことである。
そしてもうひとつは、このエセ科学が1960年代には完全に理論的にも実践的にも失脚し生物学上の舞台から去ったにもかかわらず、それを推進し、同調しなかった者たちを居丈高に恫喝までしていた科学者たち(武谷を始めとしたひとたち)が、その後も自己批判らしい自己批判もすることなく、あたかも自分たちがルィセンコ学説とは関わりがなかったかのように振舞い、口を拭い続けてきたことのもつ意味である。
著者はこの二つの様相を総括的に捉え、そこにみられる、自然は人間の意志に応じて変革しうるしまたそうすべきだという強い志向をいわゆる「科学主義」とし、そうした立場をこそ、この書のサブタイトルにあるように「自然とヒトに対する驕り」だとしてそれらを剔抉することを使命としているようである。

私はこの結論に決して反対ではない。しかし、ルィセンコ学説という「科学でさえなかった」疑似科学が、かくまでも力を持ったという出来事を「科学主義」批判でまとめ上げるためにはもうひとつの迂回路が必要なように思う。
それはルィセンコやその支持者たちが援用した弁証法的唯物論、ないしは唯物弁証法と称する「哲学的」バックボーンがはらむ形而上学そのものの確認とそれへの批判である。
著者も引用しているように、唯物弁証法は対象に迫る認識論的方法であると同時に、対象の構造そのものだとされる。ようするに、認識論と存在論は一致し、論理的なものは歴史的なものと一致するとされる。ここには認識のパラダイムやそのチェンジはもはやありえない。なぜなら、探求すべき対象と探求者、あるいはその探求の方法は同一の事象として融け合ってしまっているのであり、完全に悪しきヘーゲル主義の虜となってしまっているからである。
こうした立場を歴史や社会に適用したものが史的唯物論や唯物史観といわれるものであることはいうをまたない。著者も引用しているように、まことにこの立場は「自然の理論においても社会の理論においても特効薬」なのである。
かくして、その追求の方法と追求の対象とが同一の構造をもっているとするならば、その追求者はつねに真理や正義の側にあり、あとはその知見を広げてゆけばいいということになる。そしてそうした知見の前進は、その知見と同一の構造にある対象への限りなき接近であり、同時にそれら対象の支配の可能性を保証する。
著者のいう対象の支配、「自然とヒトに対する驕り」はまさにこうした過程を経て「科学主義」へと至るのである。著者はそれには触れないが、「科学的社会主義」と称されたものもまた、そうした共通の思想基盤をもって人の世を律しようとしたものであり、ここに私たちは、スターリンの個人の誤り云々という狭義のスターリニズムを越えた、より広義のスターリニズムの思想的基盤を見出すことができるのである。
科学による、しかもエセ科学、疑似科学による対象の、ときとしては人に対する生物学的支配は、ナチズムにも共通するものであり、ハンナ・アーレントの全体主義批判が、ナチズム同様にスターリニズムをもその俎上に乗せたのはまことにむべなるかなである。
ようするに対象の全的支配が可能であるし、それをなさねばならないとする立場である。
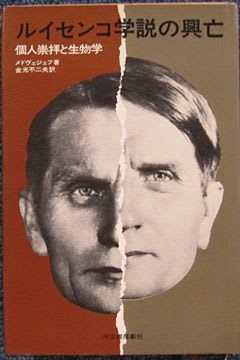
こうしたいくぶんの迂回を経て、私は著者の結論と一致する。
私のような文系人間は、ルィセンコ問題は一時期の生物学上のエピソードにとどまらず、弁証法的唯物論という一つの形而上学に侵食された当時のソ連のイデオロギーにあっては必然的であったとも思えるし、したがってこの書は、優れてスターリニズム批判の一断面を提示しているように思える。
なおこの書は、ルィセンコ学説を提唱する論者たちの見解と著者のそれとを対応させて論じるという方法はとらず、むしろ各論者たちの見解に即しながら、リテラシーを駆使した徹底したテキスト・クリークからなっていて、その意味で、当該論者たちをして自ら語らしめるものして説得力をもっている。
したがってその舌鋒は決して激越な様相は見せないが、当該論者たちがその論述で駆使する形容詞や接続詞の意味内容をも曖昧にすることなく問い、それに拠って問題の在処をより明確にするという点では非妥協的であり、その論点を明確にすることに成功している。
なお著者は、禁欲的にもここに取り上げられた事象を自然科学上の出来事の範囲にとどめているにもかかわらず、武谷らの自己批判なき変節ぶりは如実に示されていて、そこには明らかに自らの言説に対する倫理的ともいえる無責任が覆うべくもなく露呈している。
そして、この無責任体制は政治的左右を問わず、今日の私たちを呪縛しているものでもある。
戦争責任の曖昧さによる歴史修正主義が一方にあれば、他方にはこの書にも登場する日本共産党の「一貫して誤謬なし」という頬っ被りがある。この党が、相対的に正しいことを語っても人びとの信頼を得られない事実はまさにここに由来する。
ことほどさようにこの書の射程範囲は広い。
それは、自然科学でのひとつの学説の興亡にとどまらず、そのドラマを可能にした時代背景や政治的力学をも照射しているのである。
この書は、自然科学の専門書というより、タイトル通り「思想」を吟味する書である。その意味では自然科学系の人たちももちろんだが、文系の人にこそ読んでほしい。生物学の知識は高校程度、あるいはメンデルの法則を知っている程度で充分読了できる。
なお、ルィセンコやそれにくみする勢力からエセ科学の烙印を押されたメンデル=モルガン学説の発展が、遺伝子の実体的確認やそのDNAの解読を経由して、ルィセンコらが夢見て果たせなかった生物の「改革」や「生命の支配」へと肉薄しつつあるのは歴史の皮肉という他はない。こうした立場の「科学主義」が、改めて多くの問題を提起していることはいうまでもない。
タイトルでは武谷三男が強調されているが、内実は武谷を始めとする一群の科学者たちが、サブタイトルにあるような「獲得形質の遺伝」を主張するソ連(当時)のルィセンコの遺伝学説をどう受容し、どのようにそれから離反したのかの20世紀中葉の数十年のドラマである。

結論を言ってしまえば、遺伝子細胞の働きを無視した「獲得形質の遺伝」を唱えるルィセンコ学説とそれに依拠したソ連の農業生産の破綻は誰の目にも明らかな歴史的事実で、1960年代には生物学界からとっくに葬り去られた立場といえる。
いささかカリカチャライズしていうならば、親が身体を鍛えれば丈夫な子が生まれるとか、あるいは親が整形手術をすればそれが子にも受け継がれるといったたぐいのいわば疑似科学、ないしは政治的背景を伴った信仰といってもいい理論であったことは現在では明らかになっている。
もっともそれらがまことしやかな「科学的」な装飾や「哲学的」包装のもとに提示されたのであるから、とりわけ一定の党派性をもった科学者たちにとってはその足元を掬われる結果となったといっていい。
そうした過程を著者は、戦前から戦後にかけて、ルィセンコに同調した日本の科学者の記述を克明に追跡し、跡付けてゆく。その所作は、これでもか、これでもかといった作業の連続で、既にしてその歴史的生命をとっくに失ったはずの対象をかくも丁重に引っ張りだし、その醜悪さをいまさらのごとく確認することはないだろうという気すらする。
しかし、読み進むうちに、著者のこの根ほり葉ほりの記述が決して単なる後追いの作業ではないばかりか、極めてアクチュアルな問題を含むものであることがわかる。

このルィセンコ学説は、本場のソ連ではスターリンの支持を得て、さらにはその適用とされる農業実践上での「偉大な成果」を受けて、政府、党ご用達の生物学理論となり、それに同調せずメンデル=モルガンの遺伝学説を堅持した学者たちは学界から追放されたり逮捕されたり、獄中でその生命を失ったりさえしている。
今から振り返れば、それらは科学史上の一大スキャンダルであったことがわかる。
そうした過程と並行するようにわが国にもその理論が導入され(1930年代)、とりわけ戦後には、日本共産党の機関誌の『前衛』や新聞『赤旗』がそれを広く公認し、それに反対するメンデル=モルガンの遺伝学説を堅持する人たちを、ブルジョア的、資本主義的イデオロギーに毒されたエセ科学であると断罪するに及んで、広く日本の左翼的といわれる科学者を捉えていったのであった。
その科学者たちこそ、この書で俎上に載せられている武谷三男や、それに先行したり、あるいはそれに追従したりした人たちである。
しかし、そのルィセンコ学説も既に述べたように、次第に化けの皮が剥がれる。まずは実験に裏打ちされていない思い込みのみの空論であったことが明らかになり、農業実践での「偉大な成果」といわれたものも、実際には飢饉をもたらしかねない失敗の連続であったことが明らかになる。
日本でもこのルィセンコ学説に基づくヤロビ農法(あるいはミチューリン農法)が左翼が支配する日農などにより実践された時期があるが、それらは騒がれたほどの成果を上げることなく自然消滅状態となった。

さて、著書の方に戻ろう。著者はそうしたルイセンコ失脚後においても、それら日本の科学者(武谷ら)がどんな言説を弄していたのかを紹介しながらその虚妄さを暴きだしてゆくのだが、なぜ執拗とも思えるほどこれに関わりあった科学者たちの言動を追跡したのかについては二つの理由があるように思える。
そのひとつは、武谷を始めとする錚々たる科学者たちが、なぜ、こうした今から考えるとそれ自身エセ科学ないしは疑似科学でしかなかった理論にやすやすと同調したり、あるいはそれに同調しない科学者に対し、偏狭なブルジョアイデオロギーの持ち主であるといった決め付けや罵倒を行うことができたのだろうかいうことである。
そしてもうひとつは、このエセ科学が1960年代には完全に理論的にも実践的にも失脚し生物学上の舞台から去ったにもかかわらず、それを推進し、同調しなかった者たちを居丈高に恫喝までしていた科学者たち(武谷を始めとしたひとたち)が、その後も自己批判らしい自己批判もすることなく、あたかも自分たちがルィセンコ学説とは関わりがなかったかのように振舞い、口を拭い続けてきたことのもつ意味である。
著者はこの二つの様相を総括的に捉え、そこにみられる、自然は人間の意志に応じて変革しうるしまたそうすべきだという強い志向をいわゆる「科学主義」とし、そうした立場をこそ、この書のサブタイトルにあるように「自然とヒトに対する驕り」だとしてそれらを剔抉することを使命としているようである。

私はこの結論に決して反対ではない。しかし、ルィセンコ学説という「科学でさえなかった」疑似科学が、かくまでも力を持ったという出来事を「科学主義」批判でまとめ上げるためにはもうひとつの迂回路が必要なように思う。
それはルィセンコやその支持者たちが援用した弁証法的唯物論、ないしは唯物弁証法と称する「哲学的」バックボーンがはらむ形而上学そのものの確認とそれへの批判である。
著者も引用しているように、唯物弁証法は対象に迫る認識論的方法であると同時に、対象の構造そのものだとされる。ようするに、認識論と存在論は一致し、論理的なものは歴史的なものと一致するとされる。ここには認識のパラダイムやそのチェンジはもはやありえない。なぜなら、探求すべき対象と探求者、あるいはその探求の方法は同一の事象として融け合ってしまっているのであり、完全に悪しきヘーゲル主義の虜となってしまっているからである。
こうした立場を歴史や社会に適用したものが史的唯物論や唯物史観といわれるものであることはいうをまたない。著者も引用しているように、まことにこの立場は「自然の理論においても社会の理論においても特効薬」なのである。
かくして、その追求の方法と追求の対象とが同一の構造をもっているとするならば、その追求者はつねに真理や正義の側にあり、あとはその知見を広げてゆけばいいということになる。そしてそうした知見の前進は、その知見と同一の構造にある対象への限りなき接近であり、同時にそれら対象の支配の可能性を保証する。
著者のいう対象の支配、「自然とヒトに対する驕り」はまさにこうした過程を経て「科学主義」へと至るのである。著者はそれには触れないが、「科学的社会主義」と称されたものもまた、そうした共通の思想基盤をもって人の世を律しようとしたものであり、ここに私たちは、スターリンの個人の誤り云々という狭義のスターリニズムを越えた、より広義のスターリニズムの思想的基盤を見出すことができるのである。
科学による、しかもエセ科学、疑似科学による対象の、ときとしては人に対する生物学的支配は、ナチズムにも共通するものであり、ハンナ・アーレントの全体主義批判が、ナチズム同様にスターリニズムをもその俎上に乗せたのはまことにむべなるかなである。
ようするに対象の全的支配が可能であるし、それをなさねばならないとする立場である。
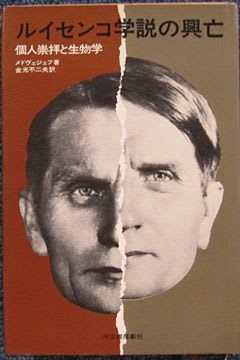
こうしたいくぶんの迂回を経て、私は著者の結論と一致する。
私のような文系人間は、ルィセンコ問題は一時期の生物学上のエピソードにとどまらず、弁証法的唯物論という一つの形而上学に侵食された当時のソ連のイデオロギーにあっては必然的であったとも思えるし、したがってこの書は、優れてスターリニズム批判の一断面を提示しているように思える。
なおこの書は、ルィセンコ学説を提唱する論者たちの見解と著者のそれとを対応させて論じるという方法はとらず、むしろ各論者たちの見解に即しながら、リテラシーを駆使した徹底したテキスト・クリークからなっていて、その意味で、当該論者たちをして自ら語らしめるものして説得力をもっている。
したがってその舌鋒は決して激越な様相は見せないが、当該論者たちがその論述で駆使する形容詞や接続詞の意味内容をも曖昧にすることなく問い、それに拠って問題の在処をより明確にするという点では非妥協的であり、その論点を明確にすることに成功している。
なお著者は、禁欲的にもここに取り上げられた事象を自然科学上の出来事の範囲にとどめているにもかかわらず、武谷らの自己批判なき変節ぶりは如実に示されていて、そこには明らかに自らの言説に対する倫理的ともいえる無責任が覆うべくもなく露呈している。
そして、この無責任体制は政治的左右を問わず、今日の私たちを呪縛しているものでもある。
戦争責任の曖昧さによる歴史修正主義が一方にあれば、他方にはこの書にも登場する日本共産党の「一貫して誤謬なし」という頬っ被りがある。この党が、相対的に正しいことを語っても人びとの信頼を得られない事実はまさにここに由来する。
ことほどさようにこの書の射程範囲は広い。
それは、自然科学でのひとつの学説の興亡にとどまらず、そのドラマを可能にした時代背景や政治的力学をも照射しているのである。
この書は、自然科学の専門書というより、タイトル通り「思想」を吟味する書である。その意味では自然科学系の人たちももちろんだが、文系の人にこそ読んでほしい。生物学の知識は高校程度、あるいはメンデルの法則を知っている程度で充分読了できる。
なお、ルィセンコやそれにくみする勢力からエセ科学の烙印を押されたメンデル=モルガン学説の発展が、遺伝子の実体的確認やそのDNAの解読を経由して、ルィセンコらが夢見て果たせなかった生物の「改革」や「生命の支配」へと肉薄しつつあるのは歴史の皮肉という他はない。こうした立場の「科学主義」が、改めて多くの問題を提起していることはいうまでもない。

















