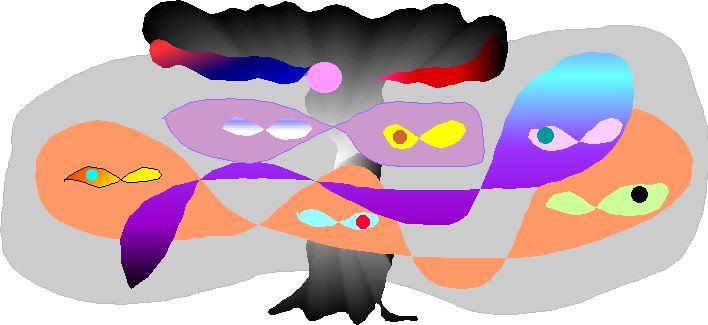以下は、私の若い友人、大野左紀子さんの近著に対する感想文である。
『アーティスト症候群 アートと職人、クリエーターと芸能人』 (明治書院)

著者を簡単に紹介しておくと、実は高校生の時に会った事があるのだがその経緯は省略するとして、いわゆる成人して会ったときには彼女はまさしくアーティストであった。自分も作品を発表し、ある塾で若いアーティスト志望者たちに教えてもいた。
新聞紙上などでも若手アーティストとして取り上げられ、物好きな私は、その個展を覗きに行った事がある。
その彼女が、数年前、そのアーティスト生活から足を洗ったのだ。
どんな経緯かなぁと思っていたらこの本が出た。いわば、彼女のアーティストからの決別宣言のようなものだ。
一方、世の中を見渡すとどこもかしこもアーティストだらけである。
ジャリタレがいつの間にかアーティストと呼ばれ、役者や歌手、お笑い芸人がやはりアーティストと称賛される。
これにクリエーターという呼び方も加えると、まさにゴマンではきかないほどである。10個石を投げればそのうち半分はそれらに当たりそうな勢いである。
それではそうしたアーティストやクリエーターとは何者で、どんな人たちなのかという、私のような素人に澱のように溜まっている疑問に迫ってくれるのがこの本である。
前半、世に氾濫するアーティスト、ないしはまさにその症候群に言及する彼女の舌鋒は鋭く面白い。
面白さのひとつは、アーティスト流行りの現状に対する著者の批判(悪口)にある。この人の悪口は巧い。ツツツツーと対象に近寄り、それをパッチンと叩いて戻ってくる、いわば、ヒット・アンド・アウエイの面白さである。
悪口のいい方が面白いだけではない。その内容が、私のような素人が、何だか違和感があるけどそれを正面切っていえないしなぁと口籠もっていた事柄を、極めて痛快にしかも適切に暴いてみせるからである。だから、それを読むと、ア、そうなんだ、それが私の違和感の中味だったのだと納得できてしまうのだ。

もちろん、これはアートではありません。キッズソフトでも描ける落書きです。
しかし、これは主として前半の叙述に関してである。
後半、アートという世界の現場から内在的に解きあかされる事柄と、それに対峙しながらその「水路」を離れるに至る著者の決意の瞬間は、地味だけれどこの書の中心をなすものである。
しかしそこで語られている問題は、いわゆるアートの世界の固有の問題ではないような気もする。アートの世界では、著者が明らかにしたようにもはやアップアップの状態であるのかもしれない。
しかし、表象の世界は広い。何か、物的対象を用いた表現であれ、言葉の戯れであれ、自分自身の立ち居振る舞いであれ、私たちは、常に既にそうした表出の世界で生きている。
そして、それへの自己言及的な配慮は、なにがしかのスノビズムを含みながら、狭義のアートに似た状況下にあるともいえるのではないだろうか。
著者のこの本自体がその一環としての新たな表出であることは疑いえないように思う。
以上が私の感想である。
言い添えるなら、私は今のところ二足歩行が可能だが、それが怪しくなってヨイヨイになったら絵でも描こうかと思っている。
絵画に生涯を賭けたアーティストからは噛み殺されそうな言い分だが、安心して欲しい、決して「アーティスト」と名乗る事はないだろうから。
いささか固い事を書いてきたが、著者の叙述がいかにユニークで面白いかを目次によって示しておこう。
*はじめに 一枚のチラシから
*美術家からアーティストへ
*アーティストだらけの音楽シーン
*芸能人アーティスト
*「たけしの誰でもピカソ」と「開運!なんでも鑑定団」
*職人とクリエーター
*「美」の職人アーティストたち
*私もアーティストだった
*「アーティストになりたい」というココロ
*あとがき
『アーティスト症候群 アートと職人、クリエーターと芸能人』 (明治書院)

著者を簡単に紹介しておくと、実は高校生の時に会った事があるのだがその経緯は省略するとして、いわゆる成人して会ったときには彼女はまさしくアーティストであった。自分も作品を発表し、ある塾で若いアーティスト志望者たちに教えてもいた。
新聞紙上などでも若手アーティストとして取り上げられ、物好きな私は、その個展を覗きに行った事がある。
その彼女が、数年前、そのアーティスト生活から足を洗ったのだ。
どんな経緯かなぁと思っていたらこの本が出た。いわば、彼女のアーティストからの決別宣言のようなものだ。
一方、世の中を見渡すとどこもかしこもアーティストだらけである。
ジャリタレがいつの間にかアーティストと呼ばれ、役者や歌手、お笑い芸人がやはりアーティストと称賛される。
これにクリエーターという呼び方も加えると、まさにゴマンではきかないほどである。10個石を投げればそのうち半分はそれらに当たりそうな勢いである。
それではそうしたアーティストやクリエーターとは何者で、どんな人たちなのかという、私のような素人に澱のように溜まっている疑問に迫ってくれるのがこの本である。
前半、世に氾濫するアーティスト、ないしはまさにその症候群に言及する彼女の舌鋒は鋭く面白い。
面白さのひとつは、アーティスト流行りの現状に対する著者の批判(悪口)にある。この人の悪口は巧い。ツツツツーと対象に近寄り、それをパッチンと叩いて戻ってくる、いわば、ヒット・アンド・アウエイの面白さである。
悪口のいい方が面白いだけではない。その内容が、私のような素人が、何だか違和感があるけどそれを正面切っていえないしなぁと口籠もっていた事柄を、極めて痛快にしかも適切に暴いてみせるからである。だから、それを読むと、ア、そうなんだ、それが私の違和感の中味だったのだと納得できてしまうのだ。

もちろん、これはアートではありません。キッズソフトでも描ける落書きです。
しかし、これは主として前半の叙述に関してである。
後半、アートという世界の現場から内在的に解きあかされる事柄と、それに対峙しながらその「水路」を離れるに至る著者の決意の瞬間は、地味だけれどこの書の中心をなすものである。
しかしそこで語られている問題は、いわゆるアートの世界の固有の問題ではないような気もする。アートの世界では、著者が明らかにしたようにもはやアップアップの状態であるのかもしれない。
しかし、表象の世界は広い。何か、物的対象を用いた表現であれ、言葉の戯れであれ、自分自身の立ち居振る舞いであれ、私たちは、常に既にそうした表出の世界で生きている。
そして、それへの自己言及的な配慮は、なにがしかのスノビズムを含みながら、狭義のアートに似た状況下にあるともいえるのではないだろうか。
著者のこの本自体がその一環としての新たな表出であることは疑いえないように思う。
以上が私の感想である。
言い添えるなら、私は今のところ二足歩行が可能だが、それが怪しくなってヨイヨイになったら絵でも描こうかと思っている。
絵画に生涯を賭けたアーティストからは噛み殺されそうな言い分だが、安心して欲しい、決して「アーティスト」と名乗る事はないだろうから。
いささか固い事を書いてきたが、著者の叙述がいかにユニークで面白いかを目次によって示しておこう。
*はじめに 一枚のチラシから
*美術家からアーティストへ
*アーティストだらけの音楽シーン
*芸能人アーティスト
*「たけしの誰でもピカソ」と「開運!なんでも鑑定団」
*職人とクリエーター
*「美」の職人アーティストたち
*私もアーティストだった
*「アーティストになりたい」というココロ
*あとがき