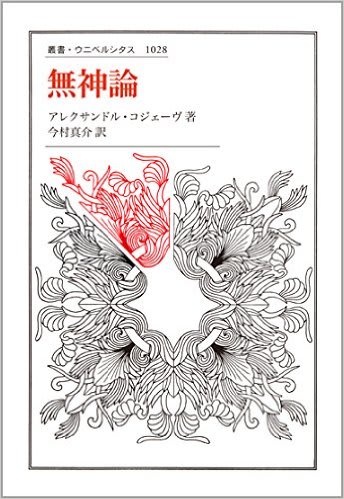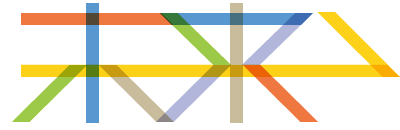おせちができました。
取り立ててうまいものはないのですが、田舎風の伝統的おせちの系列になります。


以下アトランダムに列記です。
・たつくり・ゆり根・金柑シロップ煮・くわい・酢れんこん・長芋白煮・ごぼうきんぴら・だし巻き・野菜五目煮・数の子・赤かぶ千枚漬け


ほかにお重に盛り込まない一品として、カモ燻製(既成品)のマリネー、牛もも肉ローストビーフ(自家製)、白菜漬け(自家製)のほか、既成品の変わりかまぼこ、わさび漬け、などなどです。
なお、ローストビーフは初チャレンジ。味見はこれから。


たくさん用意しましたが、かつての主婦同様、主夫である私も正月3が日の炊事労働から開放されようという魂胆です。
あ、でも、年越しそばと元朝のお雑煮も作らなければ・・・。
厨房男子は忙しい。