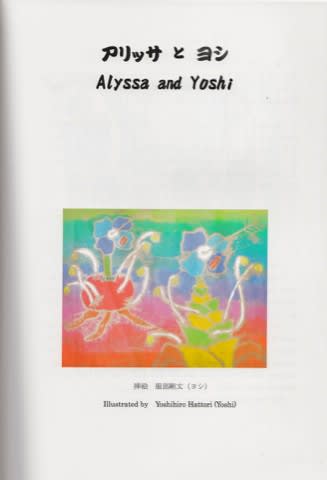20世紀の全体主義の勉強をしていて、その補強ないしは証言として読んだ。
『僕らはそこに居合わせた』がタイトルだが、サブタイトルは、「語り伝える、ナチス・ドイツ下の記憶」とあり、文字通り往時の記憶や、その後日談などにまつわる二〇編の文章からなっている。それらは、ナチス支配下を生きた10歳から17歳の普通のドイツ人少年少女をめぐる物語として展開される。

編著者のグードルン・パウゼヴァングは、ナチス・ドイツの敗戦時、17歳の少女で、叩き込まれた第三帝国のスローガンに心酔し、すべてを総統に捧げる決意をしていたという。だから、ヒトラー死亡のニュースを聴いた折には、「絶望のあまり涙を流した」とも語っている(「あとがき」より)。
そんな彼女は、戦後、教職などの傍ら文筆を生業とするようになるのだが、ナチス・ドイツ時代と向き合ったものを書くようになったのは、あのヒトラーの死以後、数十年を経過した1990年代になってからだという。このテーマがそれだけ彼女ににとって重かったことがみてとれる。

その頃になってやっと書きはじめた理由のひとつは、やっとそれを語ることができるようになったということと同時に、自分の周りにそれを語ることができる同年代のひとがどんどんっ減ってきて、今書いて置かなければ、歴史の古層に埋もれてしまうという危機感があったという。
「人生終盤は勇敢でなくっちゃね」というのが彼女の言葉だという。彼女は私より10歳上の90歳、傘寿を迎えた私にも十分通用する言葉である。

さて、本書に収められているナチス支配下を生きた10歳から17歳の普通のドイツ人少年少女をめぐる20編の物語だが、全体主義支配下の底辺の模様がよく描かれている。
その体制下では、ユダヤ人を始めとする劣等種族はその生存すら否定され、人間以下に貶められるが、総統に従い、迫害に加担したり、迫害行為を傍観したり、あるいはそれに関知しない素振りをして済ます人たちも、すべからく人間としての尊厳を剥奪され、それ以下のものに成り下がることは避けられない。
なぜなら、全体主義は、知識としてのイデオロギーの習得にとどまらず、その成員の一挙手一投足、思考や生活様式の隅々までその運動のファクターに組み込み、普段の参入を迫るからだ。ここにはもはや、公的、私的の区別すらないし、ニュートラルであることも許されない。
ここに収められた20編のエピソードも、そうした全体主義下のひとのありようをよく示している。その意味では、ハンナ・アーレントが、『全体主義の起源』で展開した全体主義論の、とりわけ、その裾野の市民段階での実情をよく記録しているといえる。

拉致されたユダヤ人一家の家に侵入し、彼らが用意した食事を、まだそのスープが冷めないうちに横取りしてありつくドイツ人一家の話に始まり、人種差別全盛期に、同じドイツ人でも劣等種に属すると教室で教師に宣告される少女の話、自分も関わった迫害の真実をひた隠しにして戦後を生きた人の話などなど様々なエピソードにあふれているが、それらのなかで、時折、そうした総迫害の時代に逆らって、あるいは隠れて、人間の尊厳を守った話が散見できるのが救いとなっている。
敗戦時、国民学校の一年生として、鬼畜米英やアジアでの劣等民族を征伐する大日本帝国の話を聞かされた私の世代としても、これらのエピソードはけっして無縁ではないと思いながら読んだ。
『僕らはそこに居合わせた』
グードルン・パウゼヴァング
高田ゆみ子訳
みすず書房
『僕らはそこに居合わせた』がタイトルだが、サブタイトルは、「語り伝える、ナチス・ドイツ下の記憶」とあり、文字通り往時の記憶や、その後日談などにまつわる二〇編の文章からなっている。それらは、ナチス支配下を生きた10歳から17歳の普通のドイツ人少年少女をめぐる物語として展開される。

編著者のグードルン・パウゼヴァングは、ナチス・ドイツの敗戦時、17歳の少女で、叩き込まれた第三帝国のスローガンに心酔し、すべてを総統に捧げる決意をしていたという。だから、ヒトラー死亡のニュースを聴いた折には、「絶望のあまり涙を流した」とも語っている(「あとがき」より)。
そんな彼女は、戦後、教職などの傍ら文筆を生業とするようになるのだが、ナチス・ドイツ時代と向き合ったものを書くようになったのは、あのヒトラーの死以後、数十年を経過した1990年代になってからだという。このテーマがそれだけ彼女ににとって重かったことがみてとれる。

その頃になってやっと書きはじめた理由のひとつは、やっとそれを語ることができるようになったということと同時に、自分の周りにそれを語ることができる同年代のひとがどんどんっ減ってきて、今書いて置かなければ、歴史の古層に埋もれてしまうという危機感があったという。
「人生終盤は勇敢でなくっちゃね」というのが彼女の言葉だという。彼女は私より10歳上の90歳、傘寿を迎えた私にも十分通用する言葉である。

さて、本書に収められているナチス支配下を生きた10歳から17歳の普通のドイツ人少年少女をめぐる20編の物語だが、全体主義支配下の底辺の模様がよく描かれている。
その体制下では、ユダヤ人を始めとする劣等種族はその生存すら否定され、人間以下に貶められるが、総統に従い、迫害に加担したり、迫害行為を傍観したり、あるいはそれに関知しない素振りをして済ます人たちも、すべからく人間としての尊厳を剥奪され、それ以下のものに成り下がることは避けられない。
なぜなら、全体主義は、知識としてのイデオロギーの習得にとどまらず、その成員の一挙手一投足、思考や生活様式の隅々までその運動のファクターに組み込み、普段の参入を迫るからだ。ここにはもはや、公的、私的の区別すらないし、ニュートラルであることも許されない。
ここに収められた20編のエピソードも、そうした全体主義下のひとのありようをよく示している。その意味では、ハンナ・アーレントが、『全体主義の起源』で展開した全体主義論の、とりわけ、その裾野の市民段階での実情をよく記録しているといえる。

拉致されたユダヤ人一家の家に侵入し、彼らが用意した食事を、まだそのスープが冷めないうちに横取りしてありつくドイツ人一家の話に始まり、人種差別全盛期に、同じドイツ人でも劣等種に属すると教室で教師に宣告される少女の話、自分も関わった迫害の真実をひた隠しにして戦後を生きた人の話などなど様々なエピソードにあふれているが、それらのなかで、時折、そうした総迫害の時代に逆らって、あるいは隠れて、人間の尊厳を守った話が散見できるのが救いとなっている。
敗戦時、国民学校の一年生として、鬼畜米英やアジアでの劣等民族を征伐する大日本帝国の話を聞かされた私の世代としても、これらのエピソードはけっして無縁ではないと思いながら読んだ。
『僕らはそこに居合わせた』
グードルン・パウゼヴァング
高田ゆみ子訳
みすず書房