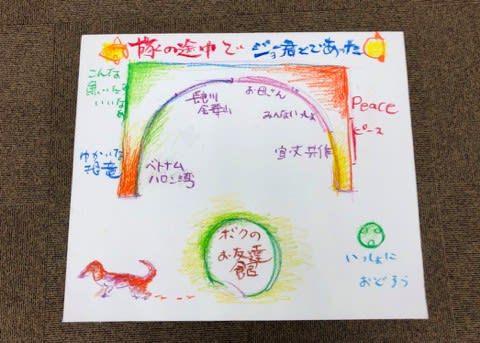充実した美術展だと思う。
近年の画家名を冠した美術展などでは、その画家の作品はそれほど多くはなく、その周辺や影響関係を示す前後の画家の作品を、学術的な追跡の装いのもとに展示し、もって作品の出展点数になんとかつじつまを合わせるようなものが多いが、これがそうではない。

画家の名を冠したというより、蒐集家の名を冠した美術館の展示内容をごっそりもってきたもので、集められたどれもが、その蒐集家・サミュエル・コートールド(1876ー1947)の一貫したコンセプト、好みやセンス(そして、その財力)に裏打ちされている。この蒐集そのものの内容がとても濃いというべきだろう。

彼は、繊維関係で財を成したイギリスの実業家で、その蒐集は1922年から30年代のはじめにかけての10年ほど間になされたものだという。当初、彼の邸宅を飾っていたそれらは、やがて美術館に寄贈され、それがロンドンのコートールド美術館となった。
その美術館が全面改装されるというので、今回はそのうちの60点の作品と24点の諸資料がやって来ることとなった。

私の好きなセザンヌのみで、完成作9点、未完のままのもの1点(「曲がり道」)、合わせて10点が展示されている。
このラインアップは、冒頭に述べたように、周辺の画家や時代を前後する画家を加えて、「セザンヌ展」が成立しそうなくらいだ。
セザンヌについてちょっと残念なのは、風景画が多く(もちろん、サントビクトワールは外せないが)、彼の独壇場ともいえるあの存在感豊かな静物、とりわけ、得も言われぬ色彩感をもった果物たちが競い合うそれが少なかったことだ。それに類するものは2点あったのだが、彼の他の静物画に比べ、いまいちボリューム感で劣っていた。
まあ、贅沢は言うまい。

セザンヌの未完成作、「曲がり道」は、なるほど、このように色を重ねてゆくのかとそのカンバスを眺め、さらにこれをどのように仕上げてゆくのかと想像するとけっこう楽しいものがある。きっとこんな感じになっていったのではという幻の「曲がり道」が私の空想の中で描かれてゆく。
帰宅してから、セザンヌの「曲がり道」を検索してみたら、2点ほどの完成品がでてきたが、いずれもこの未完成のものとは構図も遠近感も違っていて、別の場所だと断定できる。

セザンヌは、「サントビクトワール」に代表されるように、同じ対象をさまざまなバリエーションで描いているが、この「曲がり道」も、そのテーマに拘泥し、さまざまなものを描いたのではなかろうか。私の感想としては、この未完のものが仕上がっていたら、他の2点を凌駕したに違いないと思う。少なくとも、私の空想のなかの完成品は、他の2点より素晴らしい。
セザンヌといえば、晩年のハイデガーがその足跡を訪ねたというのをはるかむかしにハイデガー本人の文章か、あるいは伝記風に書かれたものかで読んだ記憶があって、彼の年表に当たってみたら、こんな記述があった。

「1966年9月5日-10日、プロヴァンスのル・トールでパルメニデスとヘラクレイトス講義。このゼミナールは1968年、1969年にも行われ、午前中に開かれ、午後はポール・セザンヌが描いたサント・ヴィクトワール山方面へのハイキングに出かけ、ハイデッガーは『初めから終わりまで、私独自の思索の道がその独自の仕方で』この道にふさわしいとした」
このハイキングにはフランスの詩人ルネ・シャールも同行したようだ。なおルネ・シャールは第二次大戦中は、レジスタンスの闘士として知られていたから、この旅は、かつてのナチス支持者とそれへの抵抗者とがともに歩んだことになり、戦後20年という年月を感じさせるものがある。

この折、ハイデガーは、セザンヌが何度も何度も「サントビクトワール」を描いたことをもちろん知っていて、その対象への迫り方と、自分の存在論(「ある」ということはどういうことであるか)への関わりとを二重写しにしていたのだろう。
私の曖昧な読書の曖昧な記憶では、ハイデガー一行は、セザンヌがそのカンバスを抱え写生に向かった山道をなぞりながら、その途次、セザンヌが大雨に打たれて倒れた地点に立ち止まり、感慨にふけったとあった。
セザンヌは、それがもとで死去したのが1906年だから、彼らの訪れはちょうど60年後のことになる。

セザンヌのところで長く立ち止まりすぎた。
このコートールド展は、他に、ゴッホ、モネ、ルノアール、ドガ、マネと印象派、及びポスト印象派のものが充実して集められていてそれぞれが面白い。
目玉は、ルノアールの「桟敷席」、マネの「フォリー=ベルジェールのバー」、それにセザンヌの「カード遊びをする人々」のようだが、それらが教科書に載るような著名な作品ということだろう。

このうち、マネの「フォリー=ベルジェールのバー」はやはり不思議な絵画である。バーのカウンターに並ぶ酒瓶やフルーツや花、そしてほぼ中央に立つ女性(バーメイド)以外はすべて鏡に写ったこちら側、つまりこの絵を観ている私たちの側なのである。本来なら、これを描いた画家も鏡に映るはずなのだがそれはない。
こうした視線の錯綜、その入れ子状の絵画としては、ベラスケスの「女官たち」を思い出すのもいいだろう。

こうした喧騒のなか、描かれた女性の、どこか物憂げで視線が定まらない表情が印象的だ。解説によれば、この時代、こうした女性はカウンターの客を酒肴でもてなすばかりでなく、しばしば自らの身体も売ったということだ。モーパッサンにいわせれば「酒と愛の売り子」ということらしい。
また、この女性の謎めいた表情から、「都市のマドンナ」ともいわれているようだ。
コートールド展全体の話に戻ろう。
会場内の随所の大きなパネルには、モノクロ写真で、これらの作品が美術館に集約される前、コートールド邸内のどんな部屋のどんな箇所に掲げられていたのかが示されていて、20世紀初頭の大ブルジョアの暮らし向きを彷彿とさせる仕掛けになっている。

充実した展示であったと思う。それは印象派前後の作品の蒐集に特化した美術館の収蔵品が、ほぼそのままやってくるという僥倖に恵まれたせいでもある。この時期、本家のコートールド美術館が全面改装に踏み切ってくれたことに感謝しなければならないだろう。
なお、この会場は、3ヶ月と少し前まで、「2019あいちトリエンナーレ」の会場だったところでもある。美術にもいろいろあるもんだ。
*インフォメーション
この美術展は愛知県美術館で3月15日(日)まで開催。
その後、3月28日(土)~6月21日(日)まで、神戸博物館で開催予定。