米LiftPort社は、地球近傍の軌道上と月面を結ぶ軌道エレベーター(月軌道エレベーター)を実現するために、一般の有志からの資金公募を行った。
同社の提案する月軌道エレベーターは、地球─月系のラグランジュ1と月面との間にテザーを結び、クライマーにより人や物資を運搬するもの。最終的には地球上の
静止軌道エレベーターも設けて、月と地球を往復する安価なルートの確立を図る。なお今回公募したのは、その実験のための資金。

同社はこれまで、静止軌道エレベーターの実現と営業を掲げてきたこともあるが、資金不足と要素技術の遅滞もあり依然として達成できず、実現の見通しは立っていないのが実情。そこで、より早期に実現できる可能性が高い月軌道エレベーターを短期目標に掲げ、一般市民からの資金調達を通じたPRを行うとともに、新たな存在意義と方向性を模索する狙いもあるとみられる。
同社によると、今月18日までに当初目標の8000ドルの14倍にあたる110000ドルが集まったという。(軌道エレベーター派 2012/9/27)
(以下は軌道エレベーター派の雑文です)
更新滞っていてお詫びします。今回は「ニュース」と「気になる記事」を併せた内容を書き散らかします。
さて今回の提案ですが、地球─月系のL1を重心に設ける軌道エレベーターであり、
高軌道エレベーターの一種とも言えますが、完成型は微妙に月から吊り下ろされるバランスになりますか。構想そのものは、軌道エレベーターのバリエーションの一つとして、ずいぶん昔から提唱されていたものであり、特に新しいモデルではありません。私もポケットブックで触れてますし。方法もL1を足場とし、そのまんまテザーケーブルを伸ばして造る典型的なブーツストラップ式。図によると全長25万km程度のようですね。月は自転周期が公転周期と同じなので、基本的に地球に同じ面を向けているのですが、それでも結構なブレがあるので、月面と直にくっつけてしまうというのは少々大胆な気もします。
第1世代のモデルであって
ピラーが剛体ではないから、月そのものに吸収してもらうなど、その辺は何らかの免振機構が設けられるのかも知れません。素材の要求強度も低く、少なくとも地球上に造るよりは現実味があるのでしょう。
月探査機などは、別にL1を通過して月へ向かうわけではないので(通常はもっと速いスピードでL1とは異なる「中間点」というのを通過していきます)、宇宙船などは任意の高度でエレベーターに取りつくのが合理的でしょう。少なくとも現代の技術では、それはそれで大変なはずですが、月周回軌道に送りこんだり帰ってきたりするのよりは低コストではあるのでしょうね。
とりわけ有人飛行の再開には役立つのではないかと。アポロ(サターンV)が月へ向かう際には、地球の重力を振り切るために大量の燃料を消費するので、当然莫大なコストを要するのですが、帰りは帰りでスピードが出すぎて結構大変なんですな。アポロの帰還船が地球に戻る時のスピードは、有人の移動体による史上最速のスピードとしてギネスにも認められていて、そのまま地球大気圏に突っ込むと燃え尽きる。このため、アポロの再突入カプセルは大気圏上層に浅く突入して、深入りせずに再び宇宙へ逃げるという「スキップ弾道」と呼ばれる行程を7、8回行って徐々にスピードを殺した後に地上に帰還しています。
LiftPortの月軌道エレベーターが実現すれば、こうした負担も軽減されるでしょうし、月の重力は地球の1/6で大気もないですから、人を載せたクライマーの運行も地球上よりは平易になると思われます。Liftportは将来的には、地球上に築く静止軌道エレベーターとのコラボで、この月軌道エレベーターの運用を想定しているそうですから、そういう時代が来ればいいと願うのは、いつものことであります。
今朝の朝日新聞によると、現在進行中の米大統領選では、ブッシュ政権がぶち上げた「月面回帰」に両党とも触れないという有様ですし、個人的には、軌道エレベーター業界を活気づけてくれるこういう話題が出てくるのは大歓迎なのですが、今は話半分以下に受け取った方がいいかも知れません。LiftPortといえば、以前は2018年までに軌道エレベーターを造って第1便をリフトオフさせるという大風呂敷を広げ、その後目標年を2030年代にシフト。さらに500万円程度の借金が返せず右往左往したりという話も耳にしましたから、今もさぞや青息吐息に違いない。今回の話でも「俺ら静止軌道エレベーターぶち上げてんだけどさあ、まだまだかかるわ」と正直に述べているあたり、結構泣けます。
だから今回の話も山師臭い雰囲気を感じる方も多いでしょう。Michael Laine 氏がプロモしていて、私4年前にちょっとだけお会いしたことがあるんですが、こんな人だったっけか。。。? しかし、この草の根運動には色々と苦しさが伝わってくるのは同志的な気持ちが沸くというか、他人事とは思えんわ。オービタってるなあ。でも月面着陸用ロボットにアームストロングと名付けるのはどうでしょうか。
庶民の力で本当に実現すれば素晴らしいんですがねえ。私も面白半分に寄付しようかと思ってたのですが、もう終わっちゃったかな? 皆さんには勧めませんが。










 軌道エレベーター(以下、発表内容に従い「宇宙エレベーター」と表記)の可能性について意見を交わす「宇宙エレベーターシンポジウム 誰もが行ける宇宙へ」が11月16日、東京都江東区の日本科学未来館で開かれ、約200人が参加した。
軌道エレベーター(以下、発表内容に従い「宇宙エレベーター」と表記)の可能性について意見を交わす「宇宙エレベーターシンポジウム 誰もが行ける宇宙へ」が11月16日、東京都江東区の日本科学未来館で開かれ、約200人が参加した。
 8月1~5日、静岡県富士宮市で、軌道エレベーター(または宇宙エレベーター)実現のための技術蓄積や実験を兼ねた「宇宙エレベーター技術競技会」(JSETEC2012)が開かれた。
8月1~5日、静岡県富士宮市で、軌道エレベーター(または宇宙エレベーター)実現のための技術蓄積や実験を兼ねた「宇宙エレベーター技術競技会」(JSETEC2012)が開かれた。 赤道付近に浮かぶ人工島から、空の果てへ伸びたケーブルカーのような乗り物に乗り、宇宙へ向かう。15分で地球の丸みが一望でき、次第に体が軽くなってゆく。途中のステーションには様々な研究施設が設けられ、高度約3万6000kmの「静止軌道」では、完全な無重力を体験できる。東京スカイツリー(R)を手がけた大手建設会社大林組(東京都港区)は、このような「宇宙エレベーター建設構想」を、2050年に実現可能として同社のPR誌に掲載した。
赤道付近に浮かぶ人工島から、空の果てへ伸びたケーブルカーのような乗り物に乗り、宇宙へ向かう。15分で地球の丸みが一望でき、次第に体が軽くなってゆく。途中のステーションには様々な研究施設が設けられ、高度約3万6000kmの「静止軌道」では、完全な無重力を体験できる。東京スカイツリー(R)を手がけた大手建設会社大林組(東京都港区)は、このような「宇宙エレベーター建設構想」を、2050年に実現可能として同社のPR誌に掲載した。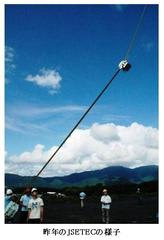 こうした中、日本では2008年に「日本宇宙エレベーター協会」(翌年、一般社団法人宇宙エレベーター協会に移行)が発足。同年日本で最初の学会を開いた。学会と並び同協会が力を入れるのが、関連技術の蓄積を視野に入れたレース形式の競技会。「宇宙エレベーター技術競技会」(JSETEC)と名付けられた大会では、風船から吊るされたひもを宇宙へ届くエレベーターに見立て、取り付けた機械の昇降性能を競う。昨年は静岡県富士宮市で、高度600mで実施し、大学の研究室や個人が自作の機械でしのぎを削り合った。
こうした中、日本では2008年に「日本宇宙エレベーター協会」(翌年、一般社団法人宇宙エレベーター協会に移行)が発足。同年日本で最初の学会を開いた。学会と並び同協会が力を入れるのが、関連技術の蓄積を視野に入れたレース形式の競技会。「宇宙エレベーター技術競技会」(JSETEC)と名付けられた大会では、風船から吊るされたひもを宇宙へ届くエレベーターに見立て、取り付けた機械の昇降性能を競う。昨年は静岡県富士宮市で、高度600mで実施し、大学の研究室や個人が自作の機械でしのぎを削り合った。
 iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。
iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。


