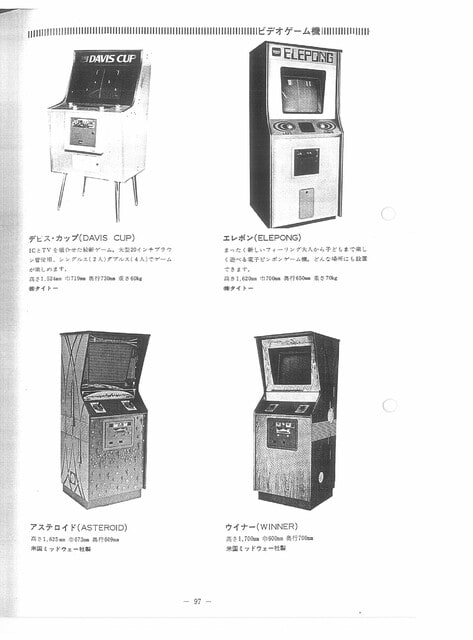セガは、元々スロットマシンをアジア・太平洋地区の米軍基地に売り込むことを目的に設立された会社でした。少なくとも1956年までは、米国Mills社の「ハイトップ」と呼ばれる筐体に入ったスロットマシンを販売していたようですが、その後すぐにそのコピーを製造して世界中に売るようになりました(関連記事:セガのスロットマシンに関する思いつき話)。
そのコピー品は、セガ設立の黒幕である「マーティン・ブロムリー」と言う人物が、Mills社が予備としてストックしてあった製造ツールを買い取って作ったものでした。しかし、Mills社はセガの機械を「ニセモノ」と非難し厳しく指弾する広告を業界誌に掲載しました。(関連記事:【衝撃】セガ製Mills機、実は海賊版だった!?)。
セガとしてはこの非難に対してなにかしらの言い分はあったのかもしれませんが、本当に後ろ暗いところがあったのかもしれません。真相は明らかではありませんが、セガは最終的に、少なくとも表面上はMills社製品には見えないオリジナルの筐体を開発しました。その新筐体に入った製品名は最後に必ず「スター」と付けられていたので、ワタシはこの筐体を「スター・シリーズ」と呼んでいます(関連記事:セガ60周年記念・1960年以前のプレセガ期(3) セガのスロットマシンその1)

Mills社のハイトップ筐体のコピー品(左)と、セガが開発した新筐体「スター・シリーズ」(右)。
「スター・シリーズ」は、世界のオールドゲームファンの間で、コレクティブルなオールドスロットマシンとして良く知られており、特に英国や欧州にコレクターが多いです。で、あるにもかかわらず、「スター・シリーズ」が初めて登場した時期はネット上を検索しても明快な答えが見つからず、拙ブログでも「1960年前後」とまでしか特定できていなかったのが長年の癪の種でした。
ある日、海外の業界誌で得た情報を端緒としてあちこち資料を辿っているうちに、日本で発行されている英字新聞、「朝日イブニングニュース」にセガの特集記事があることを知り、国会図書館に行って調べたところ、それは1962年5月16日の日付で、セガがコインマシンのトップメーカーとなったことを4ページに渡って特集した記事でした。

1962年5月16日発行の朝日イブニングニュース。「Sega Inc. Becomes Top Manufacturer of Coin Machines」との見出しで、4ページに渡ってセガの生い立ちや目覚ましい発展ぶりを紹介している特集記事の1ページ目。
ワタシの英語能力はお粗末なのでまだ全文を読み下せてはいませんが、4ページに渡る特集記事の比較的最初の方に、スター・シリーズに関する記述がありました。

「スター・シリーズ」に関する記述の部分(赤下線はワタシによる)。
この部分を超訳すると、こんな感じかと思います。
1959年、セガは「セガ・スター・マシン」という新しいユニークな新デザインのスロットマシンを発表した。これはスロットマシン業界で20年以上にわたる基本的デザインの最初の変更を取り入れたもので、すぐに成功を収めた。
つまるところ、ワタシがこれまで拙ブログにおいて「スター・シリーズ」と呼んでいた筐体が初めて世に出たのは1959年であることが判明しました。
この朝日イブニングニュースには他にもセガが最初に作ったAM機とか、セガがいかに先進的な企業であるかなど興味深い話があり、これらに付いてはいずれ拙ブログでご紹介したいと思いますが、先述したとおりワタシはまだすべて読み下してはいませんので、今回はとりあえず「スター・シリーズ」が初めて登場した年が判明したことを記録しておくにとどめておこうと思います。