おそらく、1971年のこと。当時小学生だったワタシは、新聞の社会面に、「ロタミント」というゲーム機で賭博を行っていた業者が逮捕されたという記事を発見しました。「ロタミント」とは初めて聞く言葉で、それがいったいどういうゲーム機なのかがたいそう気になり、父に聞いてみましたが、残念ながら父も知らないとのことでした。
それから5、6年経ち、ワタシが高校生となったころ、母校・大岡山小学校の近くの駄菓子屋の店頭で一台のゲーム機に出会います。それは、パチンコ台くらいの大きさの筐体が、粗末なパイプ椅子のようなスチールの脚の上に据え付けられており、前面には、外周にいくつもの数字が描かれた3枚の円盤が逆三角形に配置されてありました。10円硬貨を投入してボタンを押すと三つの円盤が回転するので、それぞれの円盤の下にあるボタンを押して回転を止め、所定の位置に現れた数字の配置によってメダルが払い出されるというものでした。
初めてこれを見た時、ワタシは、「これがロタミントか」と直感しました。なぜかはわかりませんが、とにかくそう直感したのです。ただ、思ったほど面白いと思わなかったのか、撤去されるまで数回遊んだくらいで、あまり熱中した記憶がありません。
長じた後、いろいろと調べてみると、ロタミントはもともとドイツ(当時は西ドイツ)の遊技機で、日本では1970年頃、ゲーム機業界の某という人がコンテナで輸入し、アンダーグラウンド市場に流したことで広まったようです。他のブログなどで読んだ話では、ロタミントで稼いだ人の中には、後に立派なゲームメーカーのエスタブリッシュメントとなった人も何人もいるようです。また、当時、廃棄されるロタミントを回収して売る業者だった自分を蔑んだ同業者を恨み、未だに犬猿の仲が続いている、などというような、ゲーム業界の相関関係の話もあるそうです。
ロタミントは、70年代の初頭にかなり流行したようです。現在、インターネットから参照できる最も古い警察白書である昭和48年(1973)版では、「また、新たに外国製ギャンブル機具によると博が出現しており、中には100円硬貨を投入し、簡単な機具の操作によって組み合わされる字や絵柄が特定のものとなった場合、最高40万円もの現金が受け取れるものもあり、この種のギャンブル機具をバーなどが客寄せに設置する傾向にあるので、取締りを強化している。」とあり、「外国製ギャンブル器具」としてロタミントの画像が掲載されています。

警察白書昭和48年版より、「外国製ギャンブル器具」。
ただ、この警察白書の記述で気になるのは、「100円硬貨を投入し(中略)最高40万円もの現金が受け取れる」という部分す。ロタミントには4000倍もの当たりを提供する能力はなかったと思うのですが。これについては、翌昭和49年版の警察白書に掲載されている、押収されたギャンブル器具の種類の円グラフを見ると、「ロタミント300台/スロットマシン263台/ダービー167台/その他416台」とあり、ロタミント以外のゲーム機賭博もあったことがうかがわれ、必ずしもロタミントでの事例ではないのかもしれないと思わされます。

警察白書昭和49年版より。
警察白書では、昭和50年(1975)版を最後にロタミントの画像または文字が消え、以降はスロットマシンとルーレットが主となり、それが昭和58年(1983)版に「ポーカー式テレビゲーム機」が登場するまで続きます。というわけで、ロタミントが活躍した期間は短いものでしたが、例えば法政大学出版局から出版されている「ものと人間の文化史 賭博」の第三巻で、日本における現代の賭博の態様のひとつとしてこの「ロタミント」に言及している部分がある(ただし、本文中ではなぜか「ロミタント」と記述されている)ように、その名はゲーム業界の黒歴史の代表のひとつとしてしっかりと記憶されています。
1980年ころ、パチンコ機メーカーは、このロタミントをパチンコ店で稼働できる仕様に改良した遊技機を開発し、警察の許可も取って、「ロータリーゲーム」という名前で売り出しました。ポストパチンコ機として大きな期待をかけていたであろうことは想像に難くありませんが、しかし全く人気が出ず、ごく短い期間で市場から姿を消すという、別の意味の黒歴史を作ってしまいました。
それから5、6年経ち、ワタシが高校生となったころ、母校・大岡山小学校の近くの駄菓子屋の店頭で一台のゲーム機に出会います。それは、パチンコ台くらいの大きさの筐体が、粗末なパイプ椅子のようなスチールの脚の上に据え付けられており、前面には、外周にいくつもの数字が描かれた3枚の円盤が逆三角形に配置されてありました。10円硬貨を投入してボタンを押すと三つの円盤が回転するので、それぞれの円盤の下にあるボタンを押して回転を止め、所定の位置に現れた数字の配置によってメダルが払い出されるというものでした。
初めてこれを見た時、ワタシは、「これがロタミントか」と直感しました。なぜかはわかりませんが、とにかくそう直感したのです。ただ、思ったほど面白いと思わなかったのか、撤去されるまで数回遊んだくらいで、あまり熱中した記憶がありません。
長じた後、いろいろと調べてみると、ロタミントはもともとドイツ(当時は西ドイツ)の遊技機で、日本では1970年頃、ゲーム機業界の某という人がコンテナで輸入し、アンダーグラウンド市場に流したことで広まったようです。他のブログなどで読んだ話では、ロタミントで稼いだ人の中には、後に立派なゲームメーカーのエスタブリッシュメントとなった人も何人もいるようです。また、当時、廃棄されるロタミントを回収して売る業者だった自分を蔑んだ同業者を恨み、未だに犬猿の仲が続いている、などというような、ゲーム業界の相関関係の話もあるそうです。
ロタミントは、70年代の初頭にかなり流行したようです。現在、インターネットから参照できる最も古い警察白書である昭和48年(1973)版では、「また、新たに外国製ギャンブル機具によると博が出現しており、中には100円硬貨を投入し、簡単な機具の操作によって組み合わされる字や絵柄が特定のものとなった場合、最高40万円もの現金が受け取れるものもあり、この種のギャンブル機具をバーなどが客寄せに設置する傾向にあるので、取締りを強化している。」とあり、「外国製ギャンブル器具」としてロタミントの画像が掲載されています。

警察白書昭和48年版より、「外国製ギャンブル器具」。
ただ、この警察白書の記述で気になるのは、「100円硬貨を投入し(中略)最高40万円もの現金が受け取れる」という部分す。ロタミントには4000倍もの当たりを提供する能力はなかったと思うのですが。これについては、翌昭和49年版の警察白書に掲載されている、押収されたギャンブル器具の種類の円グラフを見ると、「ロタミント300台/スロットマシン263台/ダービー167台/その他416台」とあり、ロタミント以外のゲーム機賭博もあったことがうかがわれ、必ずしもロタミントでの事例ではないのかもしれないと思わされます。

警察白書昭和49年版より。
警察白書では、昭和50年(1975)版を最後にロタミントの画像または文字が消え、以降はスロットマシンとルーレットが主となり、それが昭和58年(1983)版に「ポーカー式テレビゲーム機」が登場するまで続きます。というわけで、ロタミントが活躍した期間は短いものでしたが、例えば法政大学出版局から出版されている「ものと人間の文化史 賭博」の第三巻で、日本における現代の賭博の態様のひとつとしてこの「ロタミント」に言及している部分がある(ただし、本文中ではなぜか「ロミタント」と記述されている)ように、その名はゲーム業界の黒歴史の代表のひとつとしてしっかりと記憶されています。
1980年ころ、パチンコ機メーカーは、このロタミントをパチンコ店で稼働できる仕様に改良した遊技機を開発し、警察の許可も取って、「ロータリーゲーム」という名前で売り出しました。ポストパチンコ機として大きな期待をかけていたであろうことは想像に難くありませんが、しかし全く人気が出ず、ごく短い期間で市場から姿を消すという、別の意味の黒歴史を作ってしまいました。











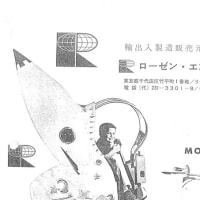








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます