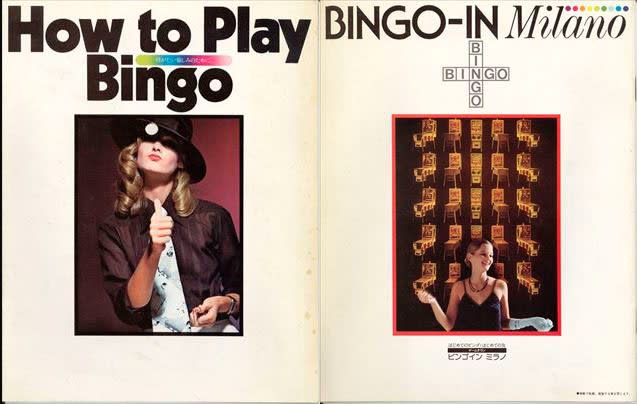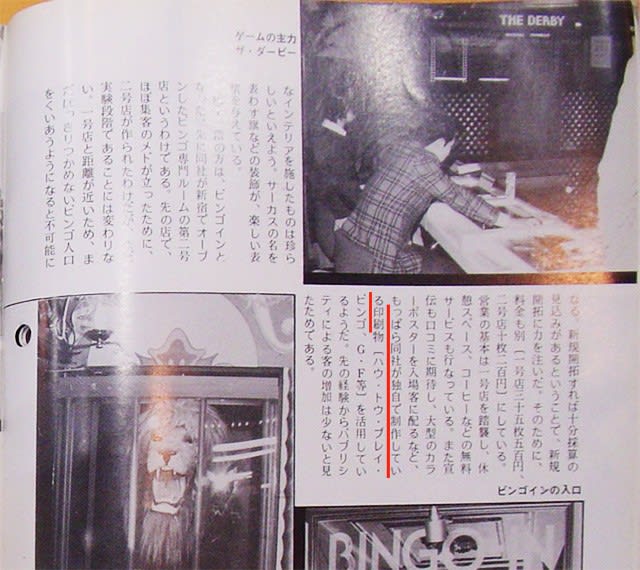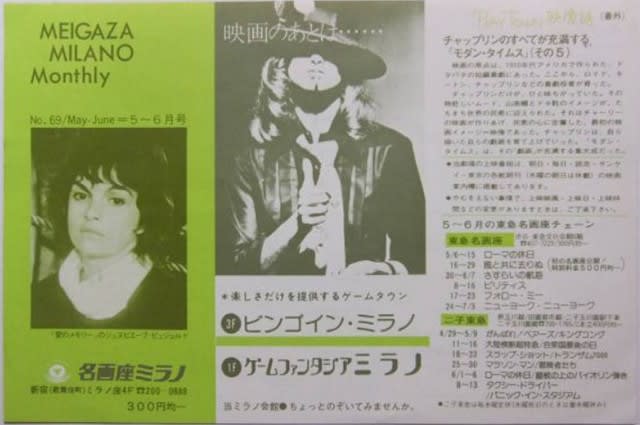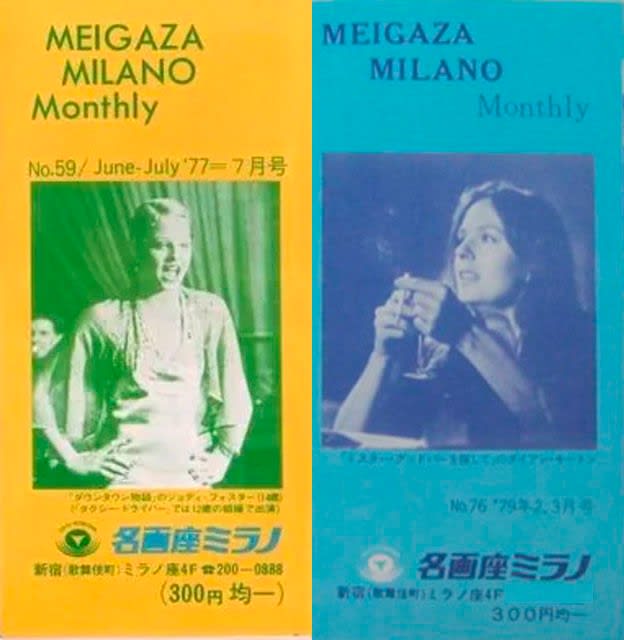「SEGA RETRO」の記事を書かれた方、ご理解下さりありがとうございます。もしあなたがワタシのあの記事で多少なりとも傷ついたのであれば大変申し訳なく思います。あの記事の意図は、ワタシのブログに起因する誤解に基づいた歴史が海外のウェブサイトで紹介されていることへの危惧と、その誤解を解く能力がワタシに欠けている焦りを表明するにとどまるもので、誤解を責め立てようなどとは全く意図しておりません。むしろワタシは、言葉の障壁を超えてAM業界の歴史を残そうと努力されている方に敬意を表します。
さて、この機会に改めて、「多分こうだったんじゃないか劇場」で述べられている内容のうち、オリンピアに直接関係する部分について、改めて創作部分を明確にしておこうと思います。まずは創作、フィクションから。
◆FICTION
(1)タイトーがサービスゲームズに倣ってスロットマシンの開発を決定したとする部分。
→タイトーがオリンピア、もしくはスロットマシンの製造を決めた動機も時期も全く不明。
(2)タイトーがスロットマシンの開発を1960年に始めている部分。
→資料(タイトーの社史本「遊びづくり四十年のあゆみ」)では、オリンピアが世に出るまでの経緯を説明する文脈で「1960年ごろから準備し」と記述しているが、その時期にスロットマシン、もしくはオリンピアの開発を始めたとは判断できない。
(3)実在する「パシフィック工業」をモデルとする「パン・パシフィック工業」の設立を1960年としている部分、並びに「ロイヤルクラウン」が1963年以前に作られていたとする部分。
→タイトーの公式見解ではパシフィック工業の設立年は1963年。それを信じるなら、パシフィック工業製品のシンボルである王冠エンブレムが付いている「ロイヤルクラウン」は1963年より前には存在しないはず。また1960年頃から準備を始め1964年に認可されたというオリンピアは、太東貿易が当初からスキルストップボタンを有する新たな風営機を目指して作っていたことになる(にわかには信じがたいストーリーではあるが)。
(4)タイトーはスロットマシンが売れなかったのでオリンピアに転用したとする部分。
→「ロイヤルクラウン」と「オリンピア」は、どちらが先に作られたかはわからない。ロイヤルクラウンは、オリンピア市場が確立した後にタイトーがセガを模倣して製造した可能性も否定できない(これもまたにわかには信じがたいストーリーではあるが)。
(5)タイトーの抗議に対しサービスゲームズは自社の優位性を以てタイトーに協業案を飲ませたとする部分。
→タイトーとセガの間でどんな協議が行われたかは全く不明。警察が仲立ちしたとの話を何かで見聞したことはあるがその真偽は不明。
**************************
◆TRUE
(1)オリンピアは、1964年に風俗第7号営業の遊技機として認可された事実。
→出典はタイトーの社史本「遊びづくり四十年のあゆみ」。
(2)オリンピアの類似機種を作り始めたサービスゲームズにタイトーが抗議した事実。
→出典はタイトーの社史本「遊びづくり四十年のあゆみ」。ただし「サービスゲームズ」の部分は原典では「日本娯楽物産など」としている。また、抗議の内容は不明。
(3)タイトーがスロットマシン「ロイヤルクラウン」を作った事実。
→出典は米国の業界誌「Cash Box」1968年7月号にタイトーが掲載した広告。
(4)タイトーの「ロイヤルクラウン」はセガのスロットマシンのコピーであると強く推認できる。
→海外のレトロゲームのフォーラムに、「ロイヤルクラウン」をセガまたはミルズ製と誤認している愛好家がいる。
(5)タイトーとセガが共同で「株式会社オリンピア」を設立したと強く推認できる。
→「株式会社オリンピア」は実在しており、日遊協の「パチスロ史~誕生から5号機まで~」では「販売はセガと太東貿易が行った(趣旨)」とある。
**************************
「たぶんこうだったんじゃないか劇場」は、長年の謎で今後も判明することはおそらくないと思われるオリンピアができるまでの経緯を、自分を納得させるために創作したストーリーです。
拙ブログではそれまで意図的なフィクションを掲載したことが無かったので、あたかも事実、もしくは多少なりとも合理性を伴った推理であると誤解されたことはあったかもしれません。そのような方々にはお詫び申し上げます。