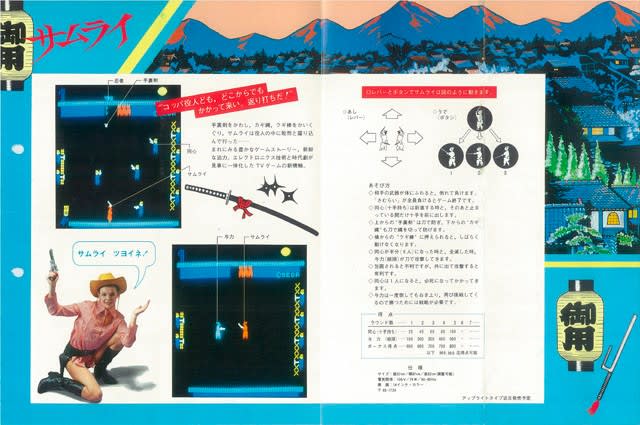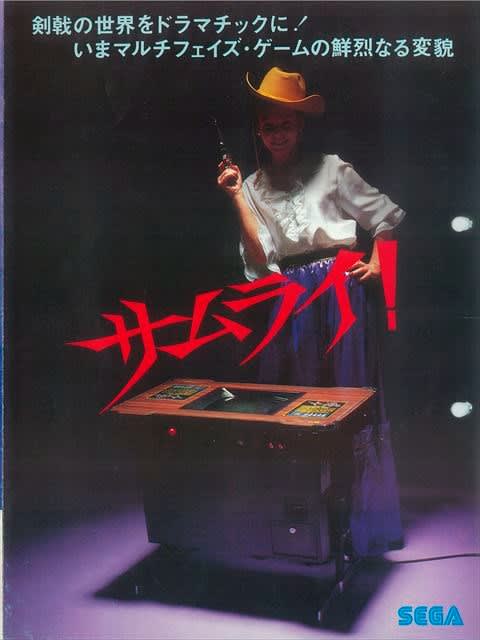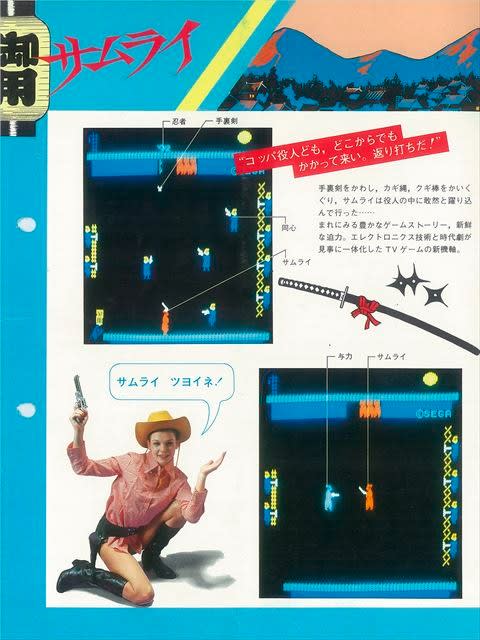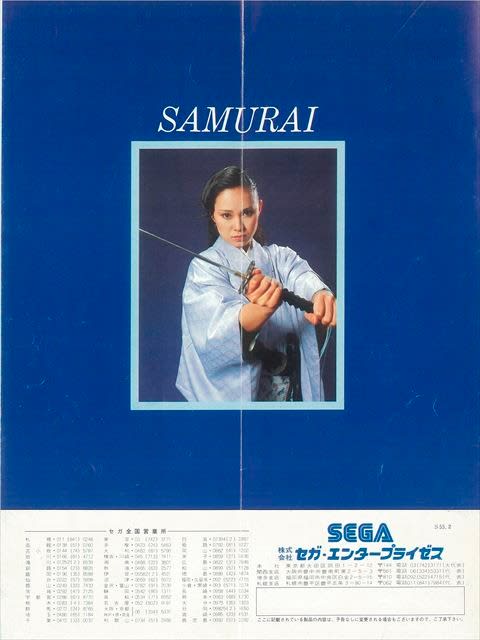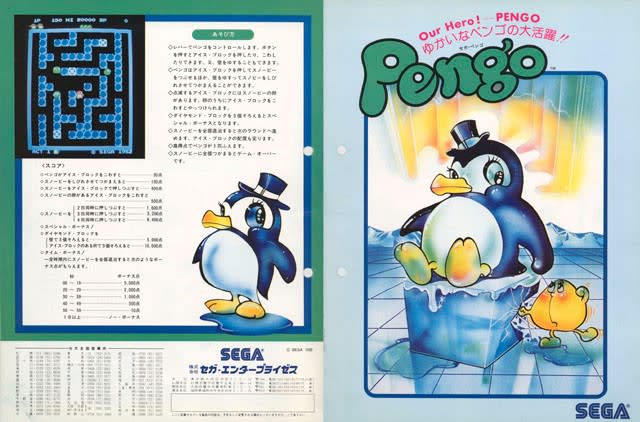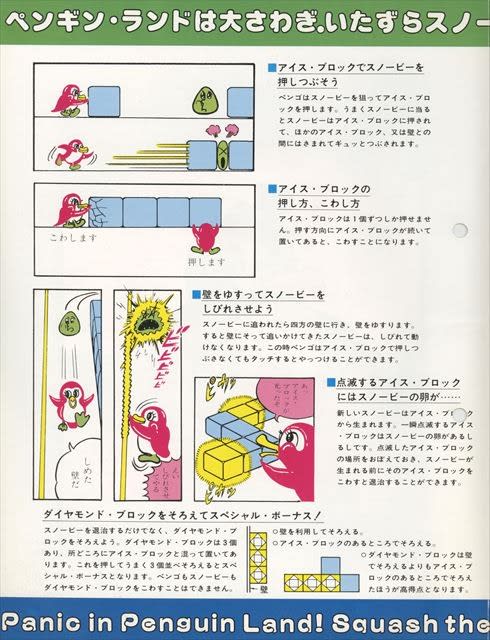昨日、東京・大田区の「大田区産業会館PIO」で開催された「レトロゲームサミット (略称レゲット)」に行ってきました。これは「レトロゲームを未来に繋ぐ即売会+ステージイベント」を謳うイベントです。

レトロゲームサミット(レゲット)の、今回のキービジュアル(なのか?)。一見して何の告知なのか想像しにくい。
レゲットは今年3月にも開催されており(関連記事:レトロゲームサミット (略称レゲット)に行ってきた)、この時は会場が狭くて場内も一方通行しかできず、来場者だけでなく係員もかなり大変そうでしたが、今回は前回比4倍(感覚値)の大ホールで行われ、巡回に苦労することは殆どありませんでした。

場内の様子。ニッチなジャンルなのに盛況。外国人やコスプレイヤーも結構見かける。向こうの壁面にはステージがあり、時々アイドルが出てきてにぎやかす。
即売会と言う趣旨から、レトロゲーム関連の様々なものが売られていましたが、私は今回「うすい本」を結構たくさん買って帰りました。

レゲットで買ったうすい本。
今回はその中から、お勧めしたいものをいくつかご紹介したいと思います。
①Mr. Do!大百科

Mr. Do! 大百科の表紙。
2022年3月にアップした記事「レトロビデオゲーム同人誌のご紹介」でご紹介した2冊の同人誌「MONACO GP大百科」及び「JUMP BUG大百科」と同じく、レトロゲーム勢界では著名なおにたまさんが主宰する「オニオン製作所」の新刊で、ユニバーサルのビデオゲーム「Mr. Do! (1982)」の本です。
単なるゲーム解説書ではなく、歴史や時代背景、関係者へのインタビューや周辺情報の「豆知識」にも多くのページが割かれていて、うすい本にも関わらず読みごたえがあります。この辺りはさすがおにたまさんの本と感心させられます。先の2冊とともに「一家に一冊」の名資料本です。
「Mr. Do! 大百科」販売の情報はこちらを参照してください。
②我が青春のテレビゲーム(第1~3集)

我が青春のテレビゲーム第1~3集の表紙。④は今回無料配布されていた第4集で、全8ページの超うすい本。
「ファミマガ(ファミリーコンピューターマガジン)」の2代目編集長だった山本直人さんの同人誌。山本さんの青春を彩った数々のAMビデオゲームの想い出や当時の社会状況を語った全43話が3集のうちに収められています。
でも、ただの懐古本ではありません。上質紙、全ページカラーであることも特筆しておくべきですが、ワタシが何より感服したのは、ワタシが往時さんざん遊んだり目にしたりしていた「スペースチェイサー」、「第3惑星」、「Warp 1」、「フィールドゴール」、「ストレートフラッシュ」など、これまでのレトロゲーム本ではほぼ無視されて来たゲームが、小さいながらもカラー画像とともに大量に言及されている点です。今の時代によくぞこれらに言及してくださったと感涙にむせんでいます。
「我が青春のテレビゲーム」販売の情報はこちらを参照してください。
③筐体ぼんシリーズ

筐体ぼんシリーズの一部。①セガの各種汎用筐体 ②ナムコのコンソレット筐体 ③タイトーのカナリー筐体 ④ナムコのポールポジションの筐体ぼんまである。
かつて「ゲーメスト」のライターだったと言う「きらり屋」さんの、ゲームではなくゲーム筐体の同人誌。筐体の仕様、機能、発売年等は資料としても優れていますが、これに加わるきらり屋さんの雑誌取材時のよもやま話やトリビアなどは存外に面白く、さすが元ライターと思わせられます。このシリーズは他にもたくさんあり、興味と予算の関係からそのごく一部の6冊を購入しました。
「筐体ぼんシリーズ」販売の情報はこちらを参照してください。
今回は全部で12冊のうすい本を購入しましたが、書かれている内容はどれも興味深くじっくり読んでしまうため、うすいのになかなか読み進みが捗りません。今回のワタシのレビューは部分的な読み齧りに頼っていますが、どれも面白いので、お勧めしておきたいと思います。