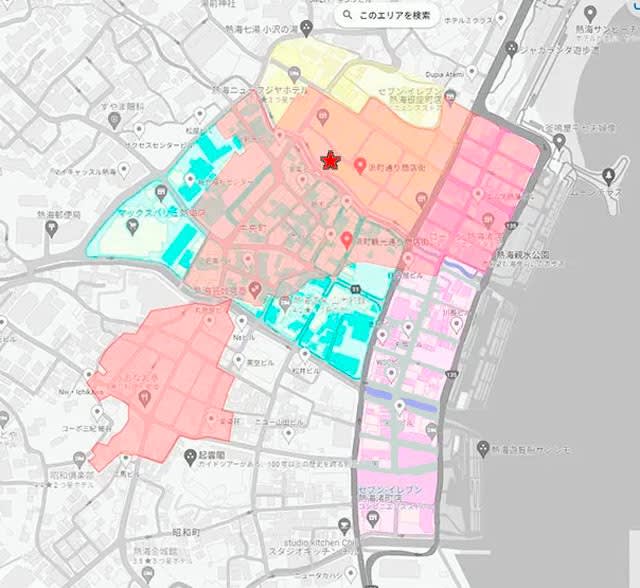新年明けましておめでとうございます。旧年中は多くの方々より貴重な情報やご意見をいただき、どうもありがとうございました。本年も引き続きご指導、ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
さて、今年の一発目は、1975年11月に刊行された「'76 遊戯機械名鑑」を主たる資料として、半世紀前、50年前のアーケード機を、今後何回かに分けてジャンルごとに見て行こうと思います。

'76 遊戯機械名鑑の表紙。刊行は1975年11月25日。
「'76 遊戯機械名鑑」は、5部に分かれており、第1部は「コインマシン」、以下、第2部が「メダルゲーム」、第3部が「小型乗り物機」、第4部が「大型遊園施設」、最後の第5部が「関連業者名簿」となっています。
第1部「コインマシン」は、さらに「ガン・ドライブゲーム機」、「ボールゲーム機」、「その他コインゲーム機」、「ジュークボックス他」に細分化されています。ビデオゲームは「その他のコインゲーム機」に分類されており、この頃のビデオゲームはまだそれだけで一章を設けられるほどの存在ではなかったようです。
【ガンゲーム】
「ガンゲーム」には14ページ56機種が掲載されていますが、旧型機も含まれています。「セガ・バルーン・ガン」や「セガ・バレット・マーク」などガンゲームをビデオ化した機種もごく少数含まれていますが、60年代から親しまれ続けているライフル銃が据え付けられているものも多く、1975年時点でもガンゲームはアーケードを支えるメインコンテンツだったことが窺われます。
もとは「ローゼン・エンタープライゼス」の「デイビッド・ローゼン」が米国から大量の中古ガンゲームを輸入して始まった日本のアーケード(関連記事:日本のゲーセンはいつから始まったのか?)ですが、ガンは比較的早い段階から国産品も作られるようになったジャンルで、'76 遊戯機械名鑑では、セガ、関西精機、三共精機(関連記事:「三共」についての備忘録(1) 三共以前の三共)、タイトーなど掲載機種の半分以上が国産品になっています。

「セガ・バレット・マーク」を含むページ。隣の「ガン・スモーク」は関西精機の最新鋭機で、ホログラム映像のガンマンが動く画期的なガンゲームだった。

「エレメカの雄」と言われた関西精機のガンゲームの一部。

古くから活躍していた三共も、いくつものガンゲームを作ってきた。

やはり老舗のタイトー、中村製作所のガンも見られる。
【ボールゲーム機】
「ボールゲーム機」はさらに「フリッパー」、「パチンコ」、「ボールゲーム」に細分化されています。いずれもガンゲームと同様、全ての機種が新製品というわけではありません。
「フリッパー」のほとんどは米国製ですが、セガの旧型機や三共精機の「ワールドシリーズ」、こまやの「ベースボール」など、国産品が僅かですが含まれています。フリッパー機に参入しようとした国内メーカーは、セガ以外にもいくつかありましたが、ガンゲームほど国産化が進むことはありませんでした。

フリッパーでは数少ない国産機であるセガの旧型機。このこの名鑑の中では「アリババ」が最も新しい1973年製。セガがゲーム機の電子化(SS化)に取り組んで再びフリッパーを売り出すのは1976年。
「パチンコ」は、風営転用機ばかりでなく、アーケード用に作られたもので、ハンドルで小さな球を弾き上げるゲーム機も含んでいます。1975年は風営機の「アレンジボール」(関連記事:シリーズ絶滅種:アレンジボールを記憶に留めておこう)が流行り出しており、アーケードにも多く転用されました。

「パチンコ」のページの一部。風営機からの転用である「アレンジボール」は他のページでも見られる。
(つづく)