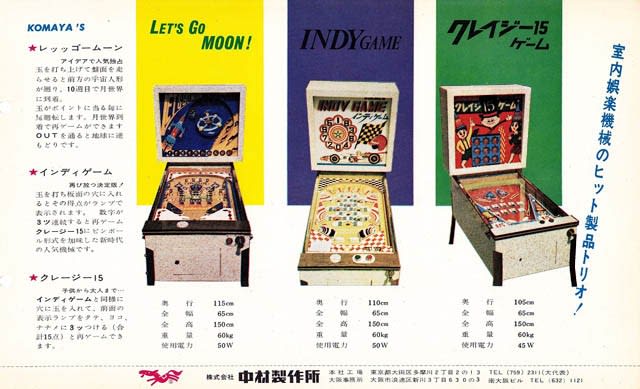セガは1972年に「プロボウラー(PRO BOWLER)」というボウリングゲームを発売しました。ワタシはこのゲームを、JR目黒駅の駅ビルの屋上でプレイしています(関連記事:商業施設の屋上の記憶(2) 目黒近辺)。当時のゲーム料金は1回10円から高いものでも30円が相場だったのに、プロボウラーは50円もしたので、小遣いの乏しい子供にとって気軽に遊べる機械ではありませんでした。


PRO BOWLERのフライヤー(英語版)。
この、テンピンボウリングを非常に良く再現したゲーム機は、しかしセガのオリジナルではなく、米国Williams社製のコピーであることは後に知りましたが、今回記事として取り上げるにあたってその辺も含めていろいろ調べていたところ、実はWilliamsも、拙ブログでは「ウィンターブック」というギャンブル機で何度か言及している米国Evans社(関連記事:初期の国産メダルゲーム機(4) 競馬ゲームその2・1975年の競馬ゲーム)が1939年以売り出した「Ten Strike」というボウリングゲームを元に作っていたことが判明しました。

Evans社の「Ten Strikes」の広告。出典はPinrepair.com
この画像を掲載している「Be a pin monkey」の記事を読むと、Evansは1955年に操業を停止し、このボウリングゲームのアイディアはWilliamsに買い取られ、1957年に「Williams Ten Strike」 の名で売り出されたとあります。Evansの「Ten Strike」は1ゲームを5フレームに圧縮してありましたが、Williamsはこれを10フレームと本来のルールに近づけました。
この後の1970年、Williamsはさらに「Williams Mini-Bowl」を売り出し、そしてセガは1972年にそのコピーである「PRO BOWLER」を売り出したという流れです。
更に調べを進めていたら、これらの詳しい話を、なんと日本語で、しかも2007年に既に書かれていたウェブサイトを発見してしまいました。
それは「ピンボールの階梯」というピンボールを解説したサイトで、該当する記事は「フリッパー・トピックス『セガのプロ・ボウラーとウィルのミニ・ボウル』」です。古いエレメカ機を日本語で解説しているとは珍しいと思って拝読したところ、実にたいへんよくできた記事でしたので、ぜひハイパーリンクから原文をお読みいただければと思います。「ピンボールの階梯」はたいへんに見事なサイトなので、URLのメモの意味も含めて、ここに記録させていただこうと思います。