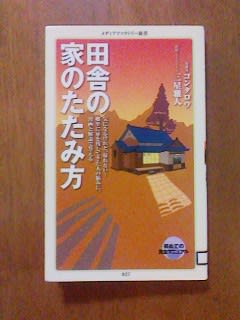「田舎の家をどうするか?」
こんな悩みは、父の世代(60代)ぐらいの悩みかと思っていたのですけれど、帰省した際に30代の私でも無関係ではいられないと危機感を持ってしまいました。
問題は「田舎の家」だけじゃなくて、私たち姉妹が把握しきれていない祖父母の代の「農地」。
最近までサラリーマンをしていた父ですが、農業をしていた若い頃の記憶があるので「あの山の近くにもあって、こっちの土地も貸していて……」と何気なく言うのですが、私も姉も妹も全く場所すら分からない。(泣)
ガンの手術から5年以上経っているとはいえ、いつ父がまた体調を崩すかは分からないというのに、母も「お母さんも全然分からないのよね」という状況。
・・・・・・まずいです。
さっそく父には『エンディングノート』(遺言ノート・いざというときのためのノート)を購入。
「農閑期に書いておいてね!!」「万が一の時にお母さんが困らないようにしてちょうだいね」と頼んできました。
同じ悩みを持っている同世代の人、けっこういるんじゃないかなぁ?
「祖父母までは田舎の農家」
「父はサラリーマンだけれど、相続した田舎の(資産価値のあまりない・売れないような)土地あり」
「孫世代は土地のことを全く知らない」
お心当たりありませんか?
『田舎の家のたたみ方』 (メディアファクトリー)は、漫画でいろいろな「田舎の家をどうするか?」というアイデアを紹介してくれる本です。まず第1歩として、「こんな問題があるんだな」「心の準備をしておかなくちゃ」と考えさせてくれます。
実際には、「家族内のコミュニケーションが一番大事である」ということに尽きるのですが。
「お父さんが突然死んだ時に困るんだから」なんて本当は考えたくないし言いたくないけれど……、ここで考えないで先送りすることのほうが不安で仕方がないから、父には「宿題」を頑張ってもらいましょう。
<関連ホームページ>
・東御市 空き家バンクとは
長野県・東御市の「空き家バンク」を紹介したページです。
田舎の空き家の活用法として、あちこちの自治体で始まっているようです。
こんな悩みは、父の世代(60代)ぐらいの悩みかと思っていたのですけれど、帰省した際に30代の私でも無関係ではいられないと危機感を持ってしまいました。
問題は「田舎の家」だけじゃなくて、私たち姉妹が把握しきれていない祖父母の代の「農地」。
最近までサラリーマンをしていた父ですが、農業をしていた若い頃の記憶があるので「あの山の近くにもあって、こっちの土地も貸していて……」と何気なく言うのですが、私も姉も妹も全く場所すら分からない。(泣)
ガンの手術から5年以上経っているとはいえ、いつ父がまた体調を崩すかは分からないというのに、母も「お母さんも全然分からないのよね」という状況。
・・・・・・まずいです。

さっそく父には『エンディングノート』(遺言ノート・いざというときのためのノート)を購入。
「農閑期に書いておいてね!!」「万が一の時にお母さんが困らないようにしてちょうだいね」と頼んできました。
同じ悩みを持っている同世代の人、けっこういるんじゃないかなぁ?
「祖父母までは田舎の農家」
「父はサラリーマンだけれど、相続した田舎の(資産価値のあまりない・売れないような)土地あり」
「孫世代は土地のことを全く知らない」
お心当たりありませんか?

『田舎の家のたたみ方』 (メディアファクトリー)は、漫画でいろいろな「田舎の家をどうするか?」というアイデアを紹介してくれる本です。まず第1歩として、「こんな問題があるんだな」「心の準備をしておかなくちゃ」と考えさせてくれます。
実際には、「家族内のコミュニケーションが一番大事である」ということに尽きるのですが。
「お父さんが突然死んだ時に困るんだから」なんて本当は考えたくないし言いたくないけれど……、ここで考えないで先送りすることのほうが不安で仕方がないから、父には「宿題」を頑張ってもらいましょう。
<関連ホームページ>
・東御市 空き家バンクとは
長野県・東御市の「空き家バンク」を紹介したページです。
田舎の空き家の活用法として、あちこちの自治体で始まっているようです。