🍓骨にトゲ(棘)のような骨ができることがあります。
この棘のような骨は骨棘(こつきょく)と呼ばれています。


🍓骨にトゲ(棘)のような骨ができることがあります。
この棘のような骨は骨棘(こつきょく)と呼ばれています。


🍓おそらく皆さんは骨梁(こつりょう)という言葉を聞いたことが無いでしょう。
骨梁は『骨の末端部によくみられる成熟した骨で、骨の板と柱の格子からできており、その構造によって皮質骨と比べて骨の材料が少ないにもかかわらず、かなりの強度を有している。』と説明されます。
下の図、左側は骨の断面図です。
その断面図にある骨梁をわかりやすく図式化したのが右の図になります。
骨の中には、強度の強い骨梁がしっかりと体重を受けられる形で張り巡らされているのです。

骨は実にうまく作られていますね。
下の図は骨梁の一部の拡大図です。

骨にできる穴(骨嚢胞)は、この骨梁部に強い力学的ストレスが加わった時に骨梁に骨折が起こり、その骨折を修復補強するためにまるで骨の中にピンポン玉ができるかのような修復を行い骨梁が再度骨折を起こさないように補強する目的で作られると考えられています(さらなる変形の予防)。
そして、骨嚢胞ができた後、骨の中に加わる力学的ストレスを骨嚢胞の壁に集中させることによって骨の他の部分にかかる力を少なくして変形を防いでいるようです。
そのイメージとしては下の図のようです。

A、変形性股関節症によって骨梁にストレスが加わる。
この話の内容も京都大学医学部整形外科の上尾先生達が報告しています。
元々は、骨梁に力学的ストレスが加わることが問題であり、その力学的ストレスを軽減することが骨の変形を未然に防ぐことになります。
その為に必要なのが、股関節に加わる衝撃を吸収するクッションの働きを高めることです。
衝撃を吸収するクッションの働きを高めることは可能ですので、その方法については後の項目で説明しましょう。
↓↓Click!↓↓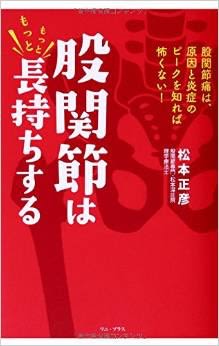

変形性股関節症を怖がらないでね

■宝塚市周辺の方は綾部先生にご相談ください!
■渋谷区周辺の方は芦沢先生にご相談ください!
まだまだ骨の話が続きますよ。
🍓骨に穴があくことがあります。
骨嚢胞(こつのうほう)と呼ばれています。
この骨嚢胞がある状態を骨嚢腫(こつのうしゅ)と呼ぶことがありますが、変形性股関節症では、一般的にかなり悪いことだととらえられています。
「骨に穴ができましたね。変形が進んだ証拠です。」
「骨の穴がつぶれるから、体重をかけないようにしましょう。穴がつぶれたら大変です。」
このような説明を受けることが一般的だと思います。
私は、多くの整形外科の先生方と接してきて、『骨にできた穴はつぶれることはありません。』と説明する先生方と一緒に仕事をしてきました。
従って、穴がつぶれるという発想は無かったのですが、まだまだ「骨の中の穴がつぶれたら大変です。」と説明する先生は多いと感じています。
ネットなどで骨嚢腫(単発性骨嚢腫)について調べると、『単発性骨嚢腫はどの年齢でも生じますが、主に子どもや20歳までの若年層に発症が多く、また、男児に発症が多いです。骨嚢腫が生じても無症状で経過することもあり、正確な発症頻度はわかっていません。』という説明もあり、そんなに悪い印象のことは書かれていません。
ところが、変形性股関節症で起こる骨嚢胞になると、とたんに悪者として説明される事が多いように感じます。
レントゲン写真で骨嚢胞を見ると、穴の周りが白く写っていることがわかります。
白く写るということは骨密度が高くて骨が固くなっていることを示しますので、骨の中に穴はできるのですが、その穴は固い骨に守られてつぶれないようになっていることがわかります。
数年後のレントゲン写真では、かつてあった骨の穴が無くなっていることも多々見られます。
京都大学医学部整形外科の上尾先生達は、骨嚢胞は悪いものなのか、それとも私達の身体を守ろうとしているのかを明らかにするために有限要素法を用いて理論的な解析を試みています。(臨床整形外科 1983.12月)
その文献の結語には次のように書かれています。
『形成された嚢胞は結果として骨頭の力学的強度を増し、生体防御反応のひとつであることが示唆された。』
この結語を分かりやすく説明すると、骨嚢胞は骨に加わる過度のストレスから骨を守るために骨の中に作られ、結果として骨の強度を増す身体の防御反応のひとつであるという意味です。
つまり、骨の中に穴があくということは、骨がつぶれやすくなるということではなく、その逆に骨がつぶれにくくなるように人間の身体に準備された自然治癒力のひとつであると言っているのです。
さらに驚くことに、変形が起こった大腿骨頭に加わる荷重ストレスは骨嚢胞の壁によって守られて、骨嚢胞は力学的に大腿骨頭の変形を防止していると考えらるのです。
この文献は今から30年以上も前の研究の報告になります。
30年以上も前ですよ!
びっくりでしょ?
骨にあいた穴が潰れることは0%ではないかもしれません。
ある股関節専門医は「整形外科医が一生のうち1人経験できるかどうかではないか?」と言っていました。
ほぼ0%に近い出来事を、普通に起こるかのように説明することは大きな問題です!
むしろ、「骨は絶対に潰れません。」と言い切ってよいレベルの話だと私は考えています。
レントゲン写真を見せられ、「足に体重をかけたら穴がつぶれますよ。」と言われたら患者はどう考えると思いますか?
骨の中の穴がつぶれないように足に体重をかけなくなるのではないでしょうか?
その結果、骨も筋肉も弱くなり、まるで進行するかのように変形性股関節症は悪化していくのです。
皆さんはどのように説明されましたか?
一般的に言われている、『骨嚢胞悪者説』なんて真っ赤な嘘で、むしろ『骨嚢胞正義の味方説』という感じなんですよ。
↓↓Click!↓↓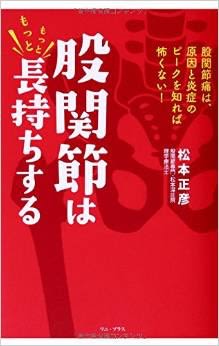

変形性股関節症を怖がらないでね

■宝塚市周辺の方は綾部先生にご相談ください!
■渋谷区周辺の方は芦沢先生にご相談ください!
私は今松本深圧院大阪店に来ています。
先日の日曜日に銀座店で勉強会を行いました。
その中で、YouTubeの勉強会も行いました。
最近有名になってきましたHipTuber田山陽平のYouTubeの今回の動画には私もちょこっと出演しています。
勉強の一貫として今回だけの出演になりますが、お時間がございましたら、是非ご覧ください。
よろしくお願いします。
🍓皆さんの中には骨折を経験した方も多いでしょう。
骨折をした場合、ご高齢の方でも新しい骨が出て骨折部はくっつき治癒します。
また、少し曲がってくっついてしまった骨も、いつの間にか真っすぐな骨になります。
この骨折の治る力は骨の中央部だけでなく、関節内の骨折でも同じです。
医学的常識として、骨には自然治癒力があり、その修復力で骨はくっつくのです。
ところが、なぜか膝関節や股関節の変形性関節症になると、急に骨の持つ自然治癒力の話が一切出なくなります。
いったい、骨の持つ治癒力はどこへ消えてしまうのでしょうか?
変形性股関節症が、まるでどんどん悪化する難病であるかのような説明が多いですね。
そうであるなら、国から難病指定されるものですが、一部を除いて難病指定にもなっていません。
おそらく、変形性股関節症は退行性変性というどんどん悪化する病気であると考えている先生が多いのだと思います。
この考え方は全く否定はできないのですが、変形性股関節症では骨を治すために炎症が起こっていることは明らかです。
変形性股関節症の方が、癌の検査のためPET検査を受けた時、「癌より股関節を心配した方がいいんじゃない?」と言われる方は多いです。
PET検査の結果、股関節に炎症が起こっている画像がはっきりと写っているのです。
また、股関節に炎症を示す熱感を訴える患者は多いし、私も患者の股関節周囲に熱感を確認したことは何度もあります。
このように、変形性股関節症では炎症が起こることは明らかです。
炎症は治る症状です。
骨が治ると炎症も治るのです。
患者の長期にわたる経過の中で、レントゲン写真の変化も多く確認してきました。
すると、股関節痛が出始めた頃から最も痛い頃までは骨の形も変わりますが、股関節痛が無くなると骨の変化は止まります。
皆さんの中にも、「1年前の骨と変化ありませんね。」とか「ここ4~5年骨に変化はありませんね。」と言われた方も多いと思います。
私は、変化が止まったら『骨は治った。』と考えます
変形して治るのです。
しかし、変形は進行性と考える先生は、『今は落ち着いているけど、骨が治ることはなく、いずれまた悪化する。』と考えるようです。
最近股関節痛が改善してきたある患者のレントゲン写真を見て、「綺麗になったね!」と感動する整形外科医がいました。
その患者の同じ頃のレントゲン写真を見て、「痛みが無くなることはあり得ません。気のせいです。」と言った整形外科医もいました。
どちらの先生も日本を代表する同じ大学の医学部出身の先生でした。
皆さんは、日本ではまだまだレントゲン写真に写った変形に対する考え方が、先生によってまちまちだということを理解していた方が良いと思います。
骨には穴があくことがあります。
また、骨にはトゲができることもあります。
そのような骨の変化に対する考え方も先生によってまちまちなのです。
その違いは、『骨は進行的に悪化するもの』と考えているか『骨は治るもの』と考えているかの違いだと思います。
常識的に考えると、骨は治るものです。
↓↓Click!↓↓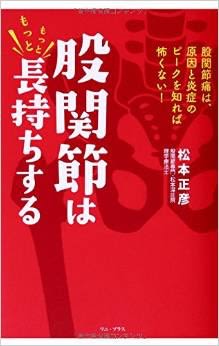

変形性股関節症を怖がらないでね

■宝塚市周辺の方は綾部先生にご相談ください!
■渋谷区周辺の方は芦沢先生にご相談ください!
股関節の中の組織について説明中です。
しばらく骨に関する話どすえ。
🍓骨の中の神経は非常に少ない。
骨の中に神経は存在しないという情報は非常に多いのですが、少ないながらに骨の中には痛みを感じる知覚神経は存在します。
骨の中の神経は非常に少ないので、骨自体が股関節痛に関与する確率は少ないと考えるのが常識でしょう。
関節包(股関節を包む袋)に存在する神経の1000分の1程度は骨の中にも神経は存在します。
また、少ないながらも骨の中を軟骨の下まで伸びた神経の35%ほどは軟骨の損傷を修復するために軟骨下の血管と共に、股関節関節面まで入り込むことは顕微鏡で確認されています。
従って、骨と骨が当たることで、股関節痛が起きる可能性はあります。
骨が当たって痛いという前提で考えた時、みなさんが悪い方の脚に体重をかけた時に、体重をかけるたびに骨と骨が当たり激痛が起こるはずです。
それも、歩く時の痛みは常時あり、しかも一定の痛みがあるはずです。
ところが、多くの患者の経過を見ていると、レントゲン写真では骨と骨が当たっていても痛くなく走れる方がいます。
また、歩く時の痛みも朝と夕方では大きく変化する方もいますし、昨日痛かったのに今日は痛くないという方も多く存在しました。
このような方の股関節痛の原因を、『骨と骨が当たるから痛い。』では説明できません。
私の経験では、圧倒的にこのようなケースが多いのです。
レントゲン写真だけで判断するのではなく、患者の動きを観察することで、股関節痛に骨はほとんど関係していないことがわかります。
皆さんの股関節痛は常に一定ですか?
また、レントゲン写真で骨と骨が当たっているように見えて、強い股関節痛を訴えていた方でも、時間と共に股関節痛が改善してくる方は多いです。
以上のようなケースを考えると、股関節痛の原因として骨の問題もあるかもしれませんが、ある一定の時期に限られ、神経の多い関節包が股関節痛に大いに関与すると考えた方が説明しやすくなります。
また、股関節痛の原因を考える時は、骨にも治る力があるという事実を考慮することも重要だということがわかります。
全てをふまえた上で、私は『骨は股関節痛に関係しない。』と言い続けています。
↓↓Click!↓↓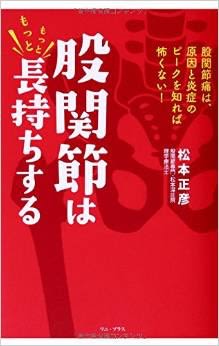

変形性股関節症を怖がらないでね

■宝塚市周辺の方は綾部先生にご相談ください!
■渋谷区周辺の方は芦沢先生にご相談ください!
続いて骨に関する話です。
🍓かつて私は整形外科病院で骨折を治す仕事をしていました。
その病院の方針で骨折を治すときには麻酔をかけずに行っていました。
骨折を治すときの痛みを「お産より痛かった。」と表現した患者もいました。
人の骨の周りには骨膜という薄い膜が覆っています。

この骨膜は関節になると膨らんで関節包と呼ばれます。
つまり、骨の部位によって名前が変わるだけで、骨膜=関節包と考えて下さい。
皆さんが骨折した時には、骨折と同時に骨膜も傷つきます。
完全に骨折した部分の骨の先端の形は刃物の様に鋭くなることもあります。
その刃物のような骨折部が骨膜を突き破るように転移した時激痛が起きるのです。
時には、骨折部が筋肉と皮膚まで突き破って外まで飛び出ることもあるいです。(複雑骨折)
骨折は、骨膜や筋肉や皮膚が傷つくから痛むのです。
骨膜、筋肉、皮膚には神経が多いですからね。
先の参考文献にもあったように、骨の中の神経は骨膜(関節包)の1000分の1の神経しかありません。
骨折時の痛みは、レントゲン写真だけを見ると折れた骨自体が痛むように感じますが、実は骨膜や筋肉といったレントゲン写真に写らない軟部組織の傷の痛みなのです。
↓↓Click!↓↓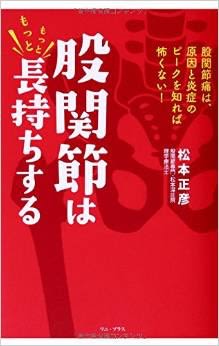

変形性股関節症を怖がらないでね

■宝塚市周辺の方は綾部先生にご相談ください!
■渋谷区周辺の方は芦沢先生にご相談ください!
今回から第二章となります。
このブログ上の文章は未熟でまだ硬い言葉が多いですが、本になる時はプロの力も借りて読みやすくしっかりした文章になるでしょう。
まだ出版社に話をしていませんが、ある程度形になれば企画書を出版社に送ろうと思います。
そこでOKが出るとも限りませんが、やるだけはやってみます。
前の第一章で発見した『股関節の中と外』という考え方。
今回からは股関節の中の詳細な解剖学的な説明になります。
できる限りシンプルに説明してみます。
🍓股関節の中の構成要素 骨
股関節の中はどのような組織で構成されているのでしょうか?
また、それらの組織には神経があるのでしょうか?
股関節は、人体の中でも人間の動作に深く関わり繰り返し使われる関節です。
股関節には、体を安定させたり関節内で起こる摩擦や衝撃のダメージを減らしたりする機能が備わっています。
股関節を構成する2つの骨の表面には、軟骨という5~7mm厚の水分の多い硬くてきめ細かなスポンジの様なもので覆われています。
また、股関節は関節包という袋に包まれており、その中は関節液と呼ばれる液体で満たされています。
関節包が骨に着く場所は強固になり関節唇(かんせつしん)と呼ばれています。
関節液は、関節を滑らか に動かす潤滑油の役割を果たすと共に、軟骨に酸素や栄養を与えています。
Castañeda氏(アリゾナ大学)らは、マウス大腿骨の構成要素の中の神経量の比率は、骨膜(関節包)を100とした時、骨膜:骨髄:皮質骨(骨質):軟骨=100:2:0.1:0と報告しています。
(Castañeda他 Neuroscience 2011)

股関節の中の構成要素
1、骨
2、軟骨
3、関節包(線維膜と滑膜)
まず最初に、骨について解剖学に基づいて説明します。
1、骨
股関節を構成する骨は2つです。
一つは、骨盤にある像の耳のような形の寛骨(かんこつ)です。
寛骨の下の部分が股関節になるのですが、この部分は臼(うす)の様に湾曲した凹みになっているので寛骨臼(かんこつきゅう)と呼ばれています。

もう一つの骨は、皆さんのももにある大腿骨(だいたいこつ)です。
大腿骨は、股関節に近づくと大転子(だいてんし)という場所で内側に45度曲がり股関節になります。
骨盤側の寛骨臼と対峙する大腿骨の部位は大腿骨頭(だいたいこっとう)と呼ばれています。
つまり、股関節を構成する骨の細かな名称は骨盤側の寛骨臼と大腿骨側の大腿骨頭になります。
では、この2つの骨の中に神経は有るのでしょうか?
様々な方法で記載されている情報の中では、『骨に神経はない』と書かれている情報の方が多いと思います。
また、解剖学の本で、骨の中の神経について詳細に書かれている本を見つけたことはありません。
意外と、骨の中の神経については研究が遅れているのかもしれません。
私は、その答えを求めていろんな文献を探してみました。
その中にはいくつかの文献で骨の中の神経について書かれている文献を発見できました。
その結果、2つの骨の中には痛みを感じる神経は有るのですが、関節包を100とした時0.1の比率の量しか骨(皮質骨)の中の神経量が無いと報告があり、骨の中の神経はあまりにも少なすぎて股関節痛の原因とは言い難いのではないかというのが私の結論です。
多くの患者さんと長期にわたって接していると、レントゲン写真では骨と骨が当たっているように見える方でも、股関節痛はなく走れる方がいます。
多くの患者は、「歩き出しが痛いが、歩いているうちに痛みが無くなります。」とか「歩き出しは痛くないが、長歩きすると痛くなってきます。」ということを考えると、骨と骨が当たって痛いとは考えられず、骨の中の神経が股関節痛の原因になっている可能性は非常に低いと考えています。
私は上記真実をふまえたうえでブログや本の中では『骨の中に神経無し。神経の無いところに痛みなし。』と書いています。
↓↓Click!↓↓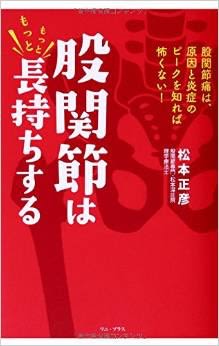

変形性股関節症を怖がらないでね

■宝塚市周辺の方は綾部先生にご相談ください!
■渋谷区周辺の方は芦沢先生にご相談ください!