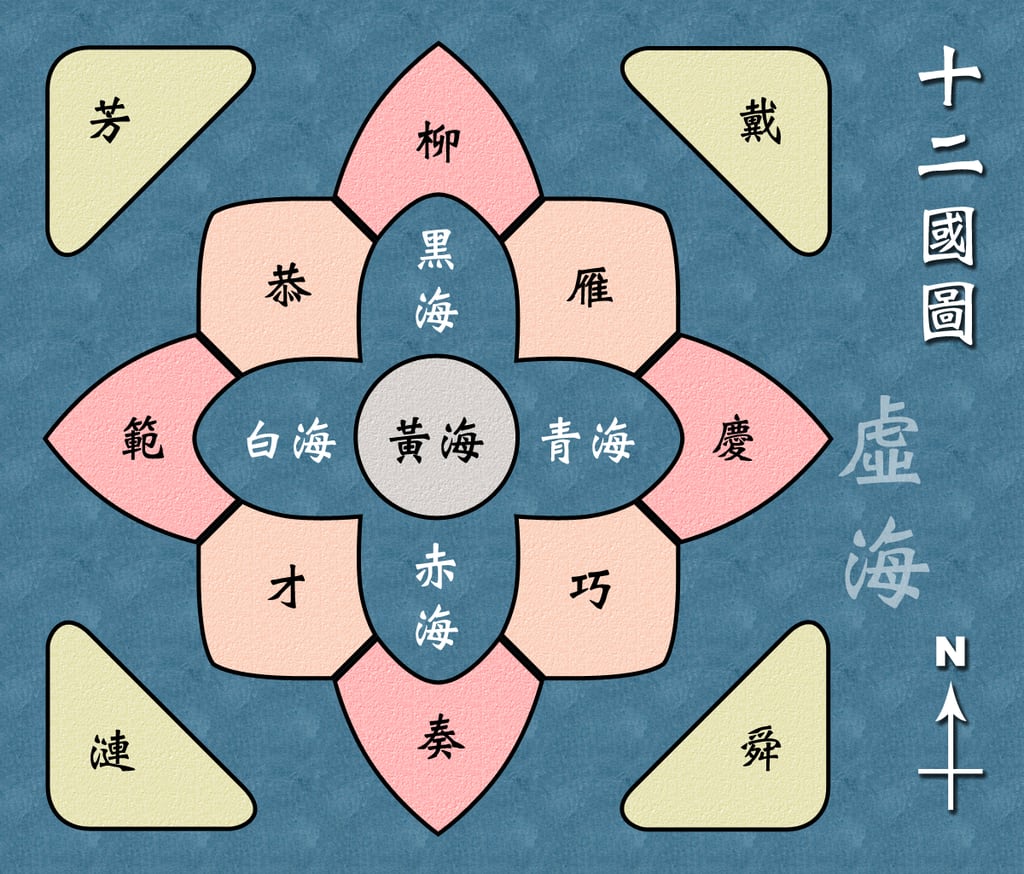
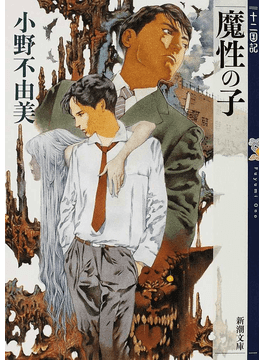 (ご購入はこちら)
(ご購入はこちら)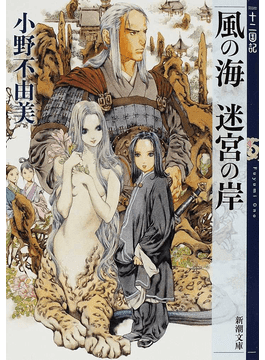 (ご購入はこちら)
(ご購入はこちら) (ご購入はこちら)
(ご購入はこちら)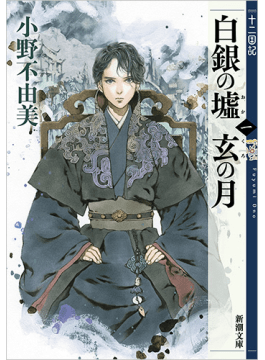 (ご購入はこちら)
(ご購入はこちら)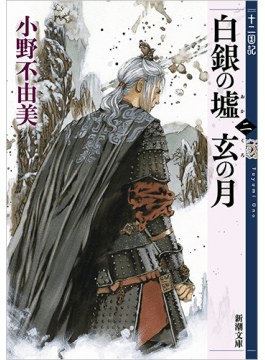 (ご購入はこちら)
(ご購入はこちら)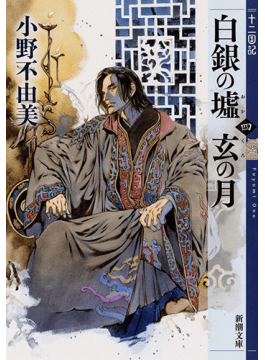 (ご購入はこちら)
(ご購入はこちら)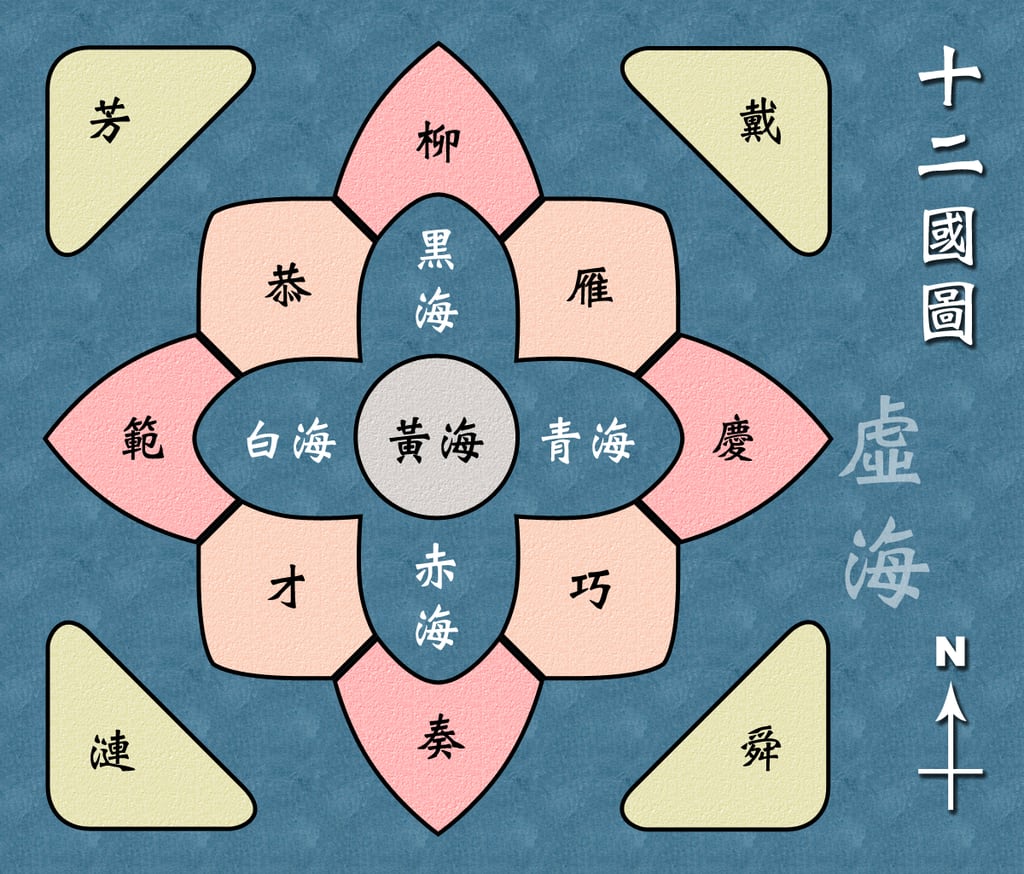
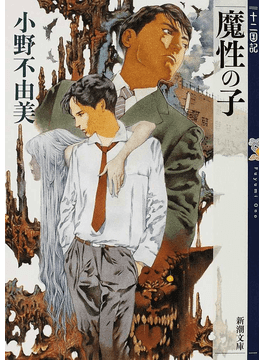 (ご購入はこちら)
(ご購入はこちら)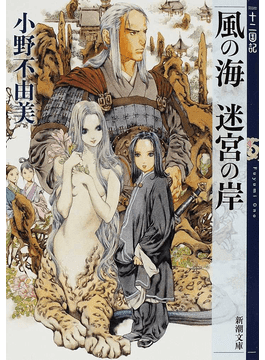 (ご購入はこちら)
(ご購入はこちら) (ご購入はこちら)
(ご購入はこちら)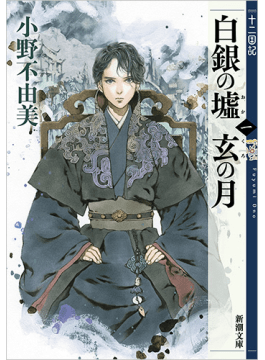 (ご購入はこちら)
(ご購入はこちら)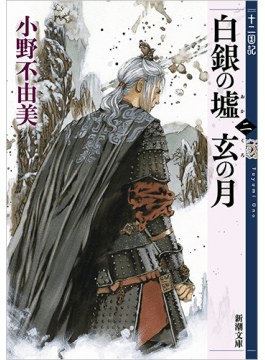 (ご購入はこちら)
(ご購入はこちら)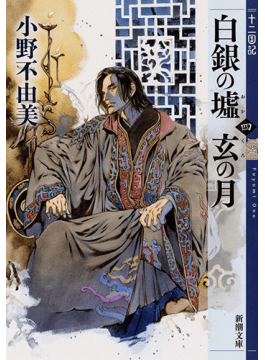 (ご購入はこちら)
(ご購入はこちら)ようやく『陸王』が文庫化されたので早速買って(3週間くらい届くのを待って)読みました。全750ページで、上下巻に分けた方が良さそうな厚みです。手に持って読み続けると手が疲れて来る重さですね。
『陸王』は、埼玉県行田市にある老舗足袋業者「こはぜ屋」の四代目社長が、斜陽産業で売上が下がることはあっても上がることはない中、会社存続のために足袋製造の技術を生かしたランニングシューズの開発を思い立ち、様々な人の支援を得ながら遂にトップランナーに認められるシューズの開発に成功するというサクセスストーリーですが、その話運びはマラソンのようです。故障を抱えて復帰のために走法を変える必要に迫られて、それでも頑張る茂木選手に共感して、彼のためのランニングシューズを開発したいと「こはぜ屋」の開発チームが奮闘します。もちろん様々な壁にぶち当たって、挫折しそうになったりするのですが、最後まで踏ん張って完走するマラソン選手と「こはぜ屋」の開発チームの姿が重なるように描かれていると思いました。
これまでの池井戸潤の作品には主人公がいきなり背水の陣を引かねばならない程の危機に陥り、強大な敵と戦って、最後には正義が勝つみたいな話運びが多かったように思いますが、この作品にはそれほどの強大な敵も登場しませんし、スタートも緩やかです。ライバル社からの嫌がらせや協力者の裏切りはあるものの、悪役は小物で、裏切る人は本当に已むに已まれず、良心の呵責に耐えながら自分の会社の存続のためにそうする感じで、スリリングなドラマ展開は皆無と言えます。新規事業を立ち上げるなら普通にぶつかるであろう困難とそれをひとつひとつ乗り越えていく地道な努力が丁寧に描かれていて、それによる感動を生み出しています。
また不肖の息子の商品開発を通しての成長ぶりもすてきですね。一生懸命やったからこそ得られるなにか。それが素晴らしい。
『茉莉花官吏伝 6 水は方円の器を満たす 』は湖州編の後編・完結編で、茉莉花は御史台の翔景と協力して見事に隣国シル・キタン国の侵略を退け、白楼国を完全勝利に導いた功績で(将来への期待値も含めて)ついに禁色の小物を授与され、彼女の国内での立身出世のベースができた感じです。また恋愛面でも、皇帝が彼女に対する気持ちをついに認めるなど大きな展開があり、ますます面白くなってきて、続きが楽しみです。
ただ、湖州編を5・6巻に分冊したことにはあまり納得がいきませんね。6巻は5巻の内容を復習する部分が比較的多いので、その部分を省けば薄っぺらでないまともな文庫1冊になったのではないかと思わずにはいられません。
前巻で予告された通り、赤奏国の「研修」から白楼国の首都に報告に戻ってきた茉莉花は、州牧の不正と州牧補佐の自殺について御史台が調査に入るという湖州に州牧補佐として派遣され、到着早々、翔景(しょうけい)と大虎(たいこ)という二人の男と出会います。翔景は御史台から監査のために湖州に入った役人ということで正体はすぐに明らかになりますが、大虎のほうは「湖州生まれでつい最近州庁舎で働くようになった胥吏」という身分にはそぐわない言葉遣いが怪しいので茉莉花は警戒します。
州牧補佐の死には謎が多く、事故とも自殺とも他殺とも言い切れるだけの決め手がないため、「自殺」として処理されたらしいのですが、溺死体で顔が潰されており、服装や持ち物で本人確認したということで、ミステリーファンにはすぐに「あ、これは死んでないな」とピンときます。もちろん茉莉花も御史台の翔景もその結論に至るまで結構な時間を要するのですが。また、茉莉花は些細なことから隣国のシル・キタン国が何か仕掛けているのではないかと疑いを持ち調査を始めます。
茉莉花官吏伝は紙書籍で揃えているので、5巻が届いた時まず「薄っぺらいな」と思わずにはいられませんでした。案の定湖州のエピソードの前編らしく、不穏な空気を残したまま「次巻へ続く」になっているので、後編が早く出ることを切に望みます。
アイザック・アシモフはSF作家だとばかり思ってましたが、推理小説も書いていたということを文藝春秋(2012)の『東西ミステリーベスト100』を介して知りました。この『黒後家蜘蛛の会』は海外編の66位にランクインしています。決して高いランキングではありませんが、ちょうど新版が出たばかり(2018年4月)ということで読んでみることにしました。推理短編集で、1巻に12編収録されています。1972年から1989年にかけて発表された作品群です。各巻それぞれに2~3編の未発表作品が収録されています。一度没になった作品か書下ろし作品だそうですが。
内容と感想
月に一度レストラン・ミラノに集まって会食する女人禁制の紳士クラブ『黒後家蜘蛛の会(ブラックウイドワーズ)』。メンバーは暗号専門家のトーマス・トランブル、特許弁護士のジェフリー・アヴァロン、推理小説家のイマニュエル・ルービン、有機化学者のジェイムズ・ドレイク、画家のマリオ・ゴンザロ、数学教師のロジャー・ホルステッド、そして給仕のヘンリー(・ジャクソン)。
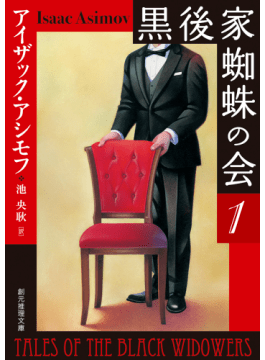 (購入はこちら)
(購入はこちら)
まだ連載が考えられていなかった第1作の「会心の笑い」だけは給仕のヘンリーが謎の張本人であるために、推察ではなく「回答」を提示していますが、それ以外の作品では紳士方があれこれと議論を交わした後にヘンリーが「おそれながら」と自分の推察を披露します。
話しのパターンは、食事が始まる前の会話、食事の様子(短い描写のことが多い)、ゲストの尋問、謎解きの議論、ヘンリーの締めとなっており、この定型が崩されることはほとんどありません。ミステリーは謎が最初に提示されることが多いですが、『黒後家蜘蛛の会』では食後のコーヒーが行き渡った後に、つまり中盤になってから、主にゲストによって初めて謎が提示されます。謎の範囲は広範で、殺人事件もなくはないですが、科学・文学・雑学・スパイ行為・その他の犯罪などが取り沙汰されます。そしてレストラン・ミラノのクラブルームにはありとあらゆる百科事典や人物名鑑などの資料が取り揃えられており、皆が議論している間にヘンリーがそれらを調べて回答を見つけて来るということもままあります。レストランにそんな資料が取り揃えられているものなのかどうか疑問に思ったりもしなくはないですが(笑)
 (購入はこちら)
(購入はこちら)
ミステリーというよりはとんち話やクイズに近いと思いますが、そうした謎解きそのものだけでなく、その前座や謎が出題されてからの議論の知的会話や、時になぜそれで友達なのか?と不思議に思うほど悪態をつき合う様子、あるいは推理小説家のイマニュエル・ルービンの友人としてさりげなくアシモフ自身が話題に上り、たいていはぼろくそにけなされるなどのご愛敬、そして各作品ごとにあるあとがきで「これは没になった」とか「題名を変えられた」とかどこで着想を得たとかそういったことが書かれており、これもまた楽しいのです。
 (購入はこちら)
(購入はこちら)
第3巻の「ミドル・ネーム」で『黒後家蜘蛛の会(ブラックウイドワーズ)』の創設エピソードが紹介されるのですが、奥さんから逃げ出して心休まる場所が欲しかったという願いが女人禁制の会となり、クラブの名前は、「黒後家蜘蛛は交尾の後で雌が雄を食い殺す習性があるが、自分たちは断固生き延びようという決意を込めて」決められたというのがまたおかしみがあります。男性読者はもしかするとここで共感するのかも知れませんが。
 (購入はこちら)
(購入はこちら)
第4巻ではシリーズの定型が破られ、女性が謎を持ちこむ「よきサマリア人」や、突然押しかけてきた若い客人の悩みを解決する「飛入り」などが収められています。こうした「例外」に対するメンバーの反応がまた愉快です。
 (購入はこちら)
(購入はこちら)
第5巻の前書きで、登場人物たちのモデルとなった人たちが実名で紹介されます。このシリーズの安楽椅子探偵とも言うべきヘンリーだけはモデルがいないそうですが。ルービンのモデルとなっているレスター・デル・レイはアシモフの親友で、周囲の人からもルービンは「生き写し」と評価されていたそうですが、本人だけは頑として似ていないと主張していた、とかいう裏話も面白いです。
作品としては5巻60編のうち第1作の「会心の笑い」が一番よかったと私は思います。たぶん種明かしが心底納得できるものであったので一番印象に残っているのだと思いますが。
『七月に流れる花』は『八月は冷たい城』と対を成す話で、夏流城(かなしろ)で緑色感冒に侵された肉親の死と向き合うための「林間学校」に参加する女子6人の物語ですが、転校してきたばかりで一切事情を知らないミチルという女の子の視点で描写されており、知らないことによる疎外感や不安や被害妄想が克明に表現されています。ミチルの父親が危篤状態となり、3度の鐘が鳴って、みんなでお地蔵様の前へ向かった時に、ようやくミチルにすべての事情が明かされます。
流れる花は「メメント・モリ(死を想え)」。緑色感冒で亡くなった人が男性なら白い花、女性なら赤い花がその人数分夏流城の水路に流されます。死者を悼む儀式としては「あり」だと思いますが、作中のようにその花たちを数えるのはちょっと悪趣味かもしれません。
読み終わって分かりましたが、読む順番を間違えました。『八月の冷たい城』を読んでしまった後だとミチル視点のミステリーがミステリーでなくなってしまうのです。彼女は緑色感冒のことも【夏の人】または【みどりおとこ】のことも、林間学校の意味も何も知らないわけですから。もう一つ参加者の女の子の一人が消えるというミステリーはありますけど、作品全体の面白さというかスリルみたいなものは『八月の冷たい城』の後だと半減してしまう気がします。
館シリーズの第9弾『奇面館の殺人』(2012、文庫は2015年発行)は、本シリーズの原点に返って、島田潔こと推理作家の鹿谷門実が探偵として活躍する本格ミステリーで、ファンとして納得できる作品です。
 (購入はこちら)
(購入はこちら)
あらすじ:舞台は1993年4月、東京都の山奥に建つ中村青司の館の一つである奇面館で、その名前から想像できるように故主人・影山透一の仮面のコレクションがあった。現主人の影山逸史はそこで奇妙な会合を3年前から開いており、その年鹿谷門実の同業者で顔立ちがそっくりの日向京介をその会合に招待するが、日向は急な病気のため、急遽鹿谷門実に代役を頼む。参加すれば謝礼金二百万円がもらえるという話なので、駆け出しの日向はそのお金をあきらめきれなかったのだ。鹿谷門実はその館が家の中村青司の手によるものだと知って、このなりすましに同意する。
奇面館では主人を始めとして客は全員仮面を被り、同じ服、同じスリッパを身につけることになっていた。使用人たちも仮面をつけていた。季節外れの吹雪のため、彼らは「吹雪の山荘」そのままにその館に閉じ込められてしまう。翌朝、影山逸史と思われる死体が壁一面に仮面がある「奇面の間」発見された。首なしだったため、誰の死体なのか確信をもって言うことができなかったのだ。指もすべて切り取られていた。
そして客たちは寝ている間に仮面を被せられ、しかも施錠されていたため、脱ぐことができない状態だった。
電話が壊され、しかもまだ吹雪いていたため警察に連絡することが叶わない中、鹿谷門実は捜査を始める。その行動が怪しまれたので、自分の正体を明かすところで前編が終わっています。
 (購入はこちら)
(購入はこちら)
後編では地道な探索や証言を集めて時系列作りなどで事件の形が徐々に明らかにされて行きます。中村青司のカラクリや抜け道が今回もふんだんに使われています。こうした手がかりから鹿谷門実が執事役の鬼丸の協力を得て事件を解明し、犯人を突き止める、というオーソドックスなストーリー展開でしたが、すべてが終わって鹿谷門実が日向京介に経緯を説明する際に明かされるあの会合の意味や集められた人たちの共通点が明かされ、本来のミステリーとは違った意味でびっくりさせられました。【あり得ない状況】だったことが最後に明かされるというか。そこに至って、そういえば鹿谷門実以外の客たちのフルネームは明かされていなかったなと思い至る私は鈍いのか...そういう意外性も面白かったです。
『ナオミとカナコ』(2017)は奥田英朗の作品としては珍しいサスペンスドラマです。望まない職場で憂鬱な日々を送るOLの直美は、あるとき、親友の加奈子が夫・達郎から酷い暴力を受けていることを知り、その顔にドス黒い痣を見て義憤に駆られ、達郎を排除する完全犯罪を夢想し始めます。「ナオミ」の章では、完全犯罪の計画と実行までが描かれ、「カナコ」の章でその後の展開が描かれます。彼女たちが考えた【完全犯罪】は、実は穴だらけで、後半大分追い詰められていきます。彼女らが逃げ切れるかどうかハラハラしながら一気に読めます。
DV夫から解放されるには、別居や離婚では往々にして十分とは言えず、シェルターに逃げ込んだりしてもいつか見つかってしまうのではないかと不安を抱えながら生きなけらばならないことがあります。だからいっそのこと二度と追いかけてこれないように夫を排除してしまおうとする発想はよく理解できます。しかしそれを本当に実行に移すとなると大ごとです。その大ごとを果たした彼女たちの堅い友情に畏敬の念を持つと同時に、最初から海外逃亡してもよかったのではないかと思わなくもないです。