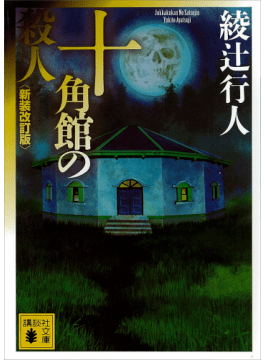『暗黒館の殺人』(2004年、文庫は2007年発行)は、上下巻の『時計館の殺人』に優る長編で、これまでの館シリーズの集大成とも言うべき様々な要素がまさに「詰め込まれて」います。
 (購入はこちら)
(購入はこちら)
熊本の山奥の湖に浮かぶ島に建つ暗黒館の主人浦登柳士郎の息子玄児に東京で出会い、浦登家の大切な儀式「ダリアの宴」のある日程に合わせて(それとは知らされずに)招かれる大学で建築を学ぶ「私」。
一方、実家に帰った折に叔父に中村青司がかかわった暗黒館の話を聞いて、単身暗黒館に向かった江南孝明は地震のために車で事故を起こし、やむなく「見るだけ」のつもりだった暗黒館に助けを求めて敷地内に入り込み、十角塔のバルコニーから転落して記憶障害を起こし、客室の一つで休養せざるを得ない状況に。
山中に横たわる死体、門番兼ボート運転手の謎めいた事故、外出したきり帰らない玄児の叔父、近隣の村から冒険のつもりで暗黒館を目指した中学生・市朗、不気味な闇に閉ざされたような暗黒館の外装と内部、開かずの間、謎めいた儀式...
様々な不気味なピースが散りばめられ、まだそれらがどうつながっていくのか分からないかなり長い導入部と言えます。
建築家の中村青司ばかりでなく、「水車館」を建てた「幻視の画家」藤波一成の絵や、「時計館」の主人古峨倫典の会社古峨精計社に特注したからくり時計、そして、「迷路館」の主人宮垣杳太郎の署名本が登場します。
 (購入はこちら)
(購入はこちら)
2巻では浦登(うらど)家の薄気味悪い〈ダリアの宴〉の様子やその他さまざまな過去や関係が断片的に開示され、ますます謎が深まっていきます。玄児が「悪いようにはしない」と言いながら真実をきちんと語ろうとしないのはなぜなのか。
そして起こる連続殺人。嵐で外界から途絶された暗黒館で瀕死の門番を殺したのは誰なのか。また早老症の子供を産んで精神を病んでしまった、玄児の叔母・望和(もわ)を誰が殺したのか。その動機は?
また、迷い込んだ少年市朗はどうなるのか?
「私」の古い母の記憶の意味は何か?
様々な疑問を残したまま次巻へ続きます。
 (購入はこちら)
(購入はこちら)
3巻ではついに浦登家の秘密が玄児によって明かされますが、そのおどろおどろしいこと!特にダリア自身の魔女的行為とその最後が凄まじいです。玄児の母、そして玄児自身の出生の秘密も尋常ではありません。闇に憑りつかれた一家ということですね。
「私」の過去やいまだにぼんやりしている江南の過去の記憶が何度もリフレインしますが、それらがどう暗黒館または浦登家に関わってくるのか、気になります。
また、「視点」の主体が何なのかも。
 (購入はこちら)
(購入はこちら)
この最終巻でついにすべての謎が明かされますが、江南孝明の「視点」の不思議と浦登家の「不死」にまつわる不思議だけは不思議のまま残るという恩田陸的ファンタジー的締めくくりで、これまでの館シリーズとは趣を異にしています。
作中で詩人の名「中也」で呼ばれていた「私」の正体・中村青司といい、浦登家に娘婿に入っていた建築家・征順の旧姓「中村」といい、「中也」と同じ時期に(33年前)暗黒館に着て十角塔から落ちて記憶障害になった「江南(えなみ)」と「現在」において十角塔から落ちて意識不明となっていた「江南(かわみなみ)」孝明の体験の重なりといい、様々な偶然や符合が招く不思議ワールド。そして後の中村青司の館たちの要素の全てを持ち合わせていた「暗黒館」はまさに「始まりの館」だったというエピソード・ゼロ的な位置づけ。まるで呪われているかのように凄惨な事件が起こる中村青司の館たちの元祖ともいえる館ならば、「場」のもたらす不思議も許容しうるということでしょうか。
この作品がいろいろと詰め込まれている「集大成」であることは分かりますが、いまいち納得できない違和感が残ります。やはり「探偵小説」的感覚で読んでいたのに、恩田陸的ファンタジーワールドの結末になったというところが腑に落ちないというか。「意外な展開で読者を驚かせる」という推理小説の使命(?)は果たしているのでしょうけど… なんというか、こういう騙され方は望んでいなかったというか。



















 もうホラーです。
もうホラーです。