最近、私は原田マハ氏の作品を集中的に読んでいる。
氏は美術館に勤務し、キュレーター、小説家として知られている。 早稲田大学美術史学卒。馬里邑美術館、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館に勤務後、2002年にフリーのキュレーターとして独立。文筆活動を開始した方。
作品は多数あるが、私は最初に読んだ「最果ての彼女」以降、「本日はお日柄もよく」「総理の夫」「マグダラ屋のマリア」「デトロイト美術館の軌跡」他を読んでいる。「奇跡の人」はその中の一冊。

(表紙でオディロン・ルドン作 花に囲まれた二人の少女 ヒューストン美術館 を見ることができる)
ヘレン・ケラーに関しては小学生の頃に読んだ簡単な自伝を介して大体のことは知っていたつもりでいた。「奇跡の人」とは、私はヘレン・ケラーその人を指していると誤解してきたが、本作を読んで彼女に苦難の末に言葉をもたらしたアン・サリヴァン女史のことであったことを知った。
原田マハ氏の本作『奇跡の人 The Miracle Worker』は、ヘレンとサリヴァンの物語を明治の津軽地方に置き換え再構築した作品。
物語は明治20年。弱視でありながら9歳の時にアメリカ留学の一向に組み入れられ、成人になって帰国した去場安が、両親が勧める結婚を断り、弘前で暮らす盲聾唖の6歳の少女れんの家庭教師として雇われる。
れんは弘前の名家に生まれたが、1歳に満たない時に熱病を患い、やっと助かったものの暗い蔵に閉じ込められ、手づかみで食事をとり、排泄の躾もできていない、まるで獣のような少女だった。
そんなれんを安は「気品と、知性と、尊厳を備えた人間になってもらうために」根気よく言葉と生活のマナーを教える。「水」を認識するまでの二人の姿は時に悲惨、壮絶であり、その間の流れは、まさに私たちがよく知るヘレンケラー著「奇跡の人 ヘレンケラー自伝」そのままである。この物語は「水」を認識した頃までの初期の話題で終わっている。
なぜ著者は、この物語を明治の津軽に置き換えたのか。
本作には「ヘレンケラー自伝」にはない、弘前地方の特有のふたつの風習、文化が挿入される。そのひとつは恐山の「イタコ」。もうひとつは、「ボサマ」と呼ばれる家々の玄関で音曲などを披露し、食べ物やお金を貰う流しの文化。「ボサマ」の一人である三味線弾きの少女・キワとの出会いである。イタコもキワも、盲目の女性である。
「イタコ」も「ボサマ」も津軽特有の風習、文化である。社会的身分としては最下層でありながら技術さえ磨けばなんとか食べていけるだけの扶助の文化が、津軽には存在していた。そうして自立している「ボサマ」の少女とれんを出会わせることで、レンが徐々に人間らしくなっていくのに大きく役立った。弱視、全盲の女性4人が真剣に生きる姿を見事に描出している。
だから本書は設定を明治の津軽にしなくてはならなかった。作者の慧眼といえよう。
津軽恐山の「イタコ」に関しては私も親しみを覚えている。小学4-5年頃お世話になったからである。医療の時代と死生観(8) 幼少時から死が身近にあった(3) 祈祷の手にゆだねられたことも
氏は美術館に勤務し、キュレーター、小説家として知られている。 早稲田大学美術史学卒。馬里邑美術館、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館に勤務後、2002年にフリーのキュレーターとして独立。文筆活動を開始した方。
作品は多数あるが、私は最初に読んだ「最果ての彼女」以降、「本日はお日柄もよく」「総理の夫」「マグダラ屋のマリア」「デトロイト美術館の軌跡」他を読んでいる。「奇跡の人」はその中の一冊。

(表紙でオディロン・ルドン作 花に囲まれた二人の少女 ヒューストン美術館 を見ることができる)
ヘレン・ケラーに関しては小学生の頃に読んだ簡単な自伝を介して大体のことは知っていたつもりでいた。「奇跡の人」とは、私はヘレン・ケラーその人を指していると誤解してきたが、本作を読んで彼女に苦難の末に言葉をもたらしたアン・サリヴァン女史のことであったことを知った。
原田マハ氏の本作『奇跡の人 The Miracle Worker』は、ヘレンとサリヴァンの物語を明治の津軽地方に置き換え再構築した作品。
物語は明治20年。弱視でありながら9歳の時にアメリカ留学の一向に組み入れられ、成人になって帰国した去場安が、両親が勧める結婚を断り、弘前で暮らす盲聾唖の6歳の少女れんの家庭教師として雇われる。
れんは弘前の名家に生まれたが、1歳に満たない時に熱病を患い、やっと助かったものの暗い蔵に閉じ込められ、手づかみで食事をとり、排泄の躾もできていない、まるで獣のような少女だった。
そんなれんを安は「気品と、知性と、尊厳を備えた人間になってもらうために」根気よく言葉と生活のマナーを教える。「水」を認識するまでの二人の姿は時に悲惨、壮絶であり、その間の流れは、まさに私たちがよく知るヘレンケラー著「奇跡の人 ヘレンケラー自伝」そのままである。この物語は「水」を認識した頃までの初期の話題で終わっている。
なぜ著者は、この物語を明治の津軽に置き換えたのか。
本作には「ヘレンケラー自伝」にはない、弘前地方の特有のふたつの風習、文化が挿入される。そのひとつは恐山の「イタコ」。もうひとつは、「ボサマ」と呼ばれる家々の玄関で音曲などを披露し、食べ物やお金を貰う流しの文化。「ボサマ」の一人である三味線弾きの少女・キワとの出会いである。イタコもキワも、盲目の女性である。
「イタコ」も「ボサマ」も津軽特有の風習、文化である。社会的身分としては最下層でありながら技術さえ磨けばなんとか食べていけるだけの扶助の文化が、津軽には存在していた。そうして自立している「ボサマ」の少女とれんを出会わせることで、レンが徐々に人間らしくなっていくのに大きく役立った。弱視、全盲の女性4人が真剣に生きる姿を見事に描出している。
だから本書は設定を明治の津軽にしなくてはならなかった。作者の慧眼といえよう。
津軽恐山の「イタコ」に関しては私も親しみを覚えている。小学4-5年頃お世話になったからである。医療の時代と死生観(8) 幼少時から死が身近にあった(3) 祈祷の手にゆだねられたことも










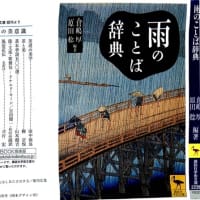



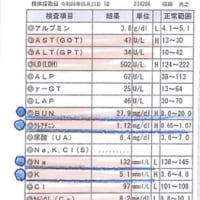




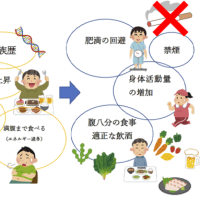






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます