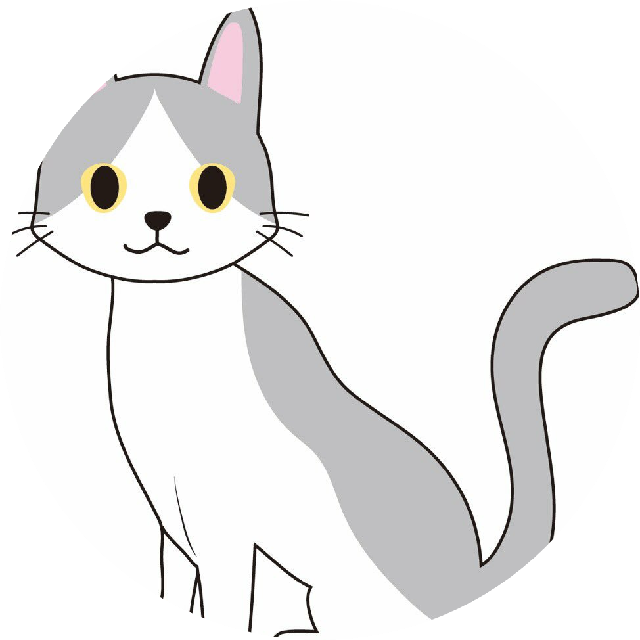橋本胖三郎『治罪法講義録 』・第七回講義
第七回講義(明治18年5月13日)
(はじめに)
前回は、私訴の対象者が①公訴の被告人、②民事担当人であることを説明しました。今回は③脏物(盗品)の占有者から説明します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(私訴の対象者③〜脏物の占有者)
第三 脏物(盗品)の占有者
脏物(盗品)の占有者も私訴の対象者となります。脏物とは、強盗、窃盗、詐欺などの財産犯の被害物品のことです。
脏物を占有する者が私訴の対象者となるのは、脏物は犯罪によって得た物品であり、所有者の正当な移転方法とはいえないからです。
脏物の占有者とは、犯罪者ではなく、犯罪者からその犯罪によって得た物品を買い受け、または譲り受け、あるいは交換によって得た者をいいます。
刑法附則第54条には「脏物が犯人の手にある時は、直ちに被害者に還付する。しかし、もし転々として他人の手にある時は、被害者の請求によって還給させるものとする」とあり、また同第55条第2項には「もし公商によらずに買い取った物品は、その還給を拒むことができない。ただし、その買取者は、売り手に対して転償を求めることができる」とあります。この両条によれば、公商によらずに脏物を買い取り、または譲り受けた者は、被害者の要求を拒むことができず、取戻の訴え(私訴)の対象者となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(私訴の対象者④〜犯罪者の相続人等)
第四 犯罪者の相続人
犯罪者の相続人は私訴の対象者となります。刑法附則第62条には「脏物の還給と損害の賠償は、本犯が死亡した場合はその相続人に対してこれを要求することができる」とあります。この条文によれば、本犯が死亡した場合には、その相続人に対して要求を行うことができるのは明らかです。また、本犯の相続人に対してだけでなく、本犯の民事担当人に対しても要求を行うことができると考えるべきです。そうであれば、その民事担当人が死亡した場合には、民事担当人の相続人に対しても要求ができると考えられます。
---
(例〜鉄道馬車会社)
例えば、鉄道馬車会社の御者が、不注意で馬車を御する際に他人に傷を負わせた場合、その被害者は鉄道馬車会社に対して損害賠償を求めることができます。その会社は御者の民事担当人の立場にあるからです。仮に、私訴が起こされる前にその会社が他人に譲渡された場合には、後の所有主、すなわちその会社を譲り受けた人に対して損害賠償を求めることとなります。
なぜなら、その譲受人は、民事担当人の相続者と異なるところがなく、会社に属するすべての権利と義務を引き継ぐ者であるため、その義務の一部である賠償の責任を免れることができないからです。
---
(フランス及びアメリカの法制度)
私訟は、犯罪者が死亡しているときには、その相続人に対して行うことができるとする国は、本邦(刑法附則に規定)及びフランスです。
このような訴訟を認めない国としてアメリカが挙げられます。アメリカでは、被害者または犯罪者のいずれかが死亡すると、私訴の権利が消滅します(アメリカ法原論を参照)。相続人に対して私訴を行うことができるか否かは世界共通ではありません。
相続人に対して私訴できることの当否については、ここでは論じません。これを論じるには哲学的な検討をしなければならず、法律学の範囲を逸脱するからです。これを論じることは後日に譲ることとします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第四章 公訴および私訴の施行に関する規則
前章では、公訴および私訴の対象者が誰であるかを論じました。本章では、公訴および私訴の手続きを説明します。
---
第一款 公訴の施行に関する規則
(検察官の公訴権)
検察官は定められた管轄の区別に従い、重罪、軽罪、違警罪について公訴を起こす任務を負っています。その行為を行う権限は法律によって付与されているため、他者の命令によって左右されることはなく、自らの意見に従い、これを行うか、行わないかを決定することができ、その権限は独立しています。
(検察官の公訴権濫用の防止方法)
検察官権限の独立性は、個人の専横や怠慢といったことで、公訴を提起すべきなのにそれをしないということが起こり得ます。そのため、法は、検察官の専横や怠慢を防止するための制度も定めています。
一つは行政権による監督、もう一つは私人による監督です。
前者は、司法卿または検事総長からの命令により検事に公訴を提起させるもので、行政権により検察官の専横と怠慢を防止するものです。
後者は、民事原告人に公訴提起権を与えるもので、私人に検察官の専横や怠慢を防止させるものです。
(フランスの制度)
フランス治罪法では、この二種類の監督方法のほかに、さらに控訴院による監督があります。フランス治罪法第9条では控訴院は検事に対して公訴を提起するよう命令することができまるのです。
フランスは行政権と司法権の分立を重視していますが、それにもかかわらずこのような条項を設けた理由は、検察官の怠慢を防ぐために他なりません。
検察官は行政官の監督に属しているため、重要な官吏または皇族の犯罪がある場合、その権威に屈して公訴を提起しないことがないとは言えません。そのようなことが起これば、法の厳明を維持することができません。そのために、独立不羈なる控訴院が検察官に対して起訴命令を下すことができるとしたのです。もっとも、この命令を行うのは極めて稀です。
(ナポレオンの弟への起訴命令)
一例を挙げると、ナポレオン第一世の威望が絶頂にあった時、その皇弟がある新聞記者を砲撃して負傷させたことがありました。
ところが、検察官はその権威を恐れて皇弟を起訴しなかったのです。控訴院はこの事件について特別に会議を開き、その決議をもって検察官に起訴命令を下したといいます。
(検察官に公訴提起権限が付与されている理由)
検察官は公訴権を独立自由に行使することができます。しかし、起訴を行うにあたっては法律に従うべきことは当然であり、また起訴を行うにあたっても常に社会の利害を考慮してこれを処理しなければなりません。一私人の些細な秘密を暴くことをもってその職務を全うしたとはいえないのです。
---
(検察官と裁判官の権限の対比)
検察官は公訴提起に関して絶大な権力を有しています。これに対抗する十分な権力を有する者が裁判官です。
この二者の職権は明確に区別されており、互いに侵すことはできません。すなわち検察官は裁判の領域に入ることはできません。また裁判官は起訴の領域を侵すことはできません。その例外は現行犯です。この場合は裁判官は検察官の起訴を待たずに直ちにこれを受理することができます。
このような例外を除き、検察官は裁判官の命令を受けず、裁判官は検察官の命令に従いません。二者が対峙して初めて公平な裁判が得られるのです。治罪法第158条第2項に「また検事の請求があったときは、いかなる場合でも臨検すべし」とあり、これは検察官の意見をもって裁判官を拘束するものですが、これは例外に属します。
---
(起訴の放棄をすべきではないこと)
検察官は一度起訴した以上は簡単にこれを放棄してはならず、裁判官の判決を受けなければなりません。一旦起訴した以上は国家および公衆の利益となるため、検察官個人の意見でこれを簡単に放棄できないからです。このような考え方は、治罪法にある放棄ができるとの明文に反するように見えますが、ここにいう放棄とは公訴権を放棄する意味ではなく、ただ検察官自身の意見を放棄する意味であると解釈すべきです。したがって裁判官は検察官がその意見を放棄した場合でも、判決を言い渡さなければならないのです。
(起訴の不当性を発見した場合の検察官の対処)
また、検察官が最初に起訴した時の考えと同じ判決を得たとしても、その後に起訴及び判決の不当性を発見した場合には、上訴して是正しなければなりません。公訴は検察官自身のためにするものではなく、国家のためにするものなので、自分の意見が誤っていることを悟った場合には、正しいものに従わなければならないからです。このことが公訴と私訴の大きな違いです。民事の訴訟においては、原告が請求したこと以上の理由により、上訴することはできません。
(検察官単独では起訴できない場合)
検察官が起訴を行うのに他の者の行為が必要な場合があります。①被害者の告訴が必要な場合です。また、②皇族、華族、勲章を帯びた者、位階のある者に対しては、直ちに公訴できず、あらかじめ上奏して裁定を待つ必要があります。その理由は、後日「公訴の停止について」という題目を設けて説明致しましょう。
以上、公訴の施行に関する規則を説明しました。次回には私訴の施行に関する規則を説明しましょう。