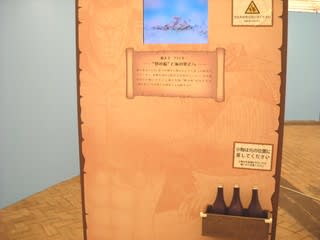【戻】
「この先左脇に小さな公園が有るでしょ?
1週間位前から、そこに幽霊が出るって噂が立ってるの。
髪が長くて、長いスカートはいてたって…実際に見たコがクラスに居て、話してくれたのよ」
ナミと一緒に線路沿いの細い道を歩いてく。
時折、踏み切りの音が甲高く響き、少し遅れて電車が横を、ガタンゴトンと過ぎてった。
道が次第に上り坂に変わる、線路よりも高くなった足場から右に顔を向けると、背の高い金網越しに屋根が低く連なって見えた。
家並みの上に棚引く雲が、夕陽に染まって赤い。
陽射しは未だギラギラと強く、道の左側に続く白い石壁には、俺とナミの影が真っ黒く焦げ付いていた。
石壁が途切れて、左に紫陽花に囲まれた公園が現れる。
住宅地の隙間に押し込まれた様な、砂場だけの四角く狭い公園だ。
「猫の額」ってのは、こういう場所を指して言うんだろう。
道より更に小高い公園内に入ったところで、ナミは漸く連れて来た理由を説明した。
「幽霊が出る…だァ?てめェは、んなくだんねェ理由で、人を此処まで連れて来やがったのか…!」
「だって1週間位の内に、もう何人も見てんのよ!見たコは時間までしっかり覚えてて、嘘とはとても思えなかった!」
呆れを通り越して怒りが湧いた。
しかし睨まれた当人には俺が何を怒ってるのか解らないらしく、言い訳するにもポイントが完璧にズレている。
「嘘っぽい怪談って解るじゃない?『友人に聞いた話なんだけどォ~』なんて出だしで、体験者をぼかしてさ。この場合見た本人がはっきり『見た!』って主張してんのよ。すっごく信憑性高いと思う!」
「噂が嘘だと疑ってるわけじゃねェ…幽霊が出ようが出まいが、どうだっていいんだよ!」
興奮して喋るのを遮り、叫んだ。
俺を見上げるナミの目が真ん丸に開く。
「ゾロって、肝試しは嫌い?」
その一言でブチリと切れた。
「帰るぞ!」
踵を返してさっさと階段を下りる。
道に出る直前で首だけ振り返ると、ナミは背中を向けて、門の側のベンチに座って居た。
断固帰らない態度かよ…何故そんなにもムキになるんだか。
大仰に溜息を吐いて、頭をガリガリと掻く。
不承不承ベンチの側まで戻り、膨れっ面してる女の肩を、軽く叩いた。
「おら、帰るぞって!」
「帰りたければ、どうぞ勝手にお帰り下さい!私は帰んないから…!」
手をはね除けプイと逸らした顔は、とても高2には見えない。
今度は少し力を強めて、肩を揺さ振った。
再びその手をはね除けられる、自然と俺の口からは大きな溜息が漏れた。
「お前は反抗期のガキか?そうまでムキになるほど肝試しがしてェのか?」
「ゾロこそ急に大人ぶっちゃって、まだ高校生のクセに、可愛げ無い!肝試しくらい気さくに付き合ってくれたっていいでしょ!?」
…高校生男子に可愛げ求めてんじゃねェよ。
売り言葉に買い言葉で返して、いっその事置いてっちまおうかと思ったが、中身はガキでも器は充分女だ。
寄って来るのは幽霊に限らず、公園に独り残してくわけにいかねェ。
仕方なく隣に腰掛けた。
「…帰るんじゃなかったの?」
すっかり不貞腐れた顔を向けるも、ナミは俺がゆったり座れるように、体を右にずらしてくれた。
「夕日が落ちるまでだ。落ちたら一緒に帰る、いいな!」
後ろ向きのまま、太陽を指差して言う。
日が沈む間際の黄昏時、公園はオレンジ色の光に満ちていた。
「けど、見たコが言うには、夜10時頃だったって話よ。塾帰りに横を通ったら、丈の長いスカートをはいた長い髪の女が、空ろな顔してうろうろと――」
「んな時間まで待ってられっか!ただのキ××イだったかもしれねェだろ!」
「でも1週間位、毎日出てるって噂で――」
「だからキ××イなんだろって!!…違っても、そんだけの証言で幽霊だと決め付けられっか!」
「それに紫陽花が――」
「紫陽花??」
公園を囲む紫陽花を見回してナミが話す。
「紫陽花って土の質によって色を変えるって言うじゃない?去年と色が違って妙に鮮やかだって言う人が居るのよ」
「紫陽花の根元に死体でも埋められてるってか?んな事言うなら掘ってみるか?」
「や!ちょっ!止めてよ!!本当に出て来たら恐いじゃない!!」
「恐いんなら、そもそも肝試しなんてしようとすんなよ、矛盾してるヤツだな」
昔からこいつは恐がりのクセに、ホラー映画を観ようとしてたっけ。
観る時は必ず俺とルフィを呼び、てめェの後ろに俺達を座らせた。
トイレに行く時は必ず俺かルフィのどっちかを付き添わせ、出て来るまでドアの前で立たせた。
普段勝気で威張ってる女が怯える様は可笑しくて、ルフィと2人でわざと前に座ったり、居なくなったりしたもんだ。
今こうして腕に縋り付いてると、懐かしく思い出しちまう。
意地悪い笑みになってたのか、ナミに頬を思い切り抓られた。
時折響く踏切と電車の音と、俺達の喋る声以外は、何も聞えない。
住宅地の狭間だってのに、薄気味悪かった。
公園を囲む紫陽花が、西日を受けて虹みてェに輝いてる。
赤に青に白にピンクに紫に…その色が刻々とぼんやりして来た。
後ろを振り向けば、夕日が屋根の向うに、半分位落ちている。
夏至間近の空は中々暗くならないが、日が落ちれば早い。
「…後5分ってとこか」
俺が呟いたのを聞き、ナミが唇をギュッと噛んだ。
膝の上に置いてる鞄から、携帯を取り出す。
「ルフィを呼ぶから、来るまで待って!」
「は?…寝込んでる奴呼び出そうとすんなよ。つか呼んでどうする積りだ?」
「だって3人だったら、ゾロも居てくれるでしょ?ルフィならもう復活してるだろうし、肝試ししてるって聞いたら、あいつ嬉々として駆け付けるわ!」
止める間も無くナミが携帯を耳に当てる。
機械的な女の音声が漏れ聞えた。
「電波の届かない場所ォ!?嘘ォ!?公園でかけてるのにィ!?」
「だから止めろって…薬呑んで寝てるだろうしって――おいっ!聞けよっっ!!」
「この辺妨害電波でも乱れ飛んでんのかしら?線路の近くだし――ちょっと離れた所でかけて来る…!!」
ベンチを立ち、公園内をうろちょろ移動してかけるも繋がらなかったらしく、ナミは終いにゃ公園の外に出て行った。
まったく……何を意地になってんだか。
独りベンチに残された俺は、既に何度目かの大きな溜息を吐いた。
――お前ら、付き合う気有んの?
同級の悪友からぶつけられた質問が頭に蘇った。
学校で或る時もよおしてトイレに寄った時だ。
個室から丁度出て来た奴と会った。
「…おう」
「よォ」
短く挨拶を交わして出て行こうとした矢先、背中に脈絡の無い質問をぶつけられた。
「お前ら、付き合う気有んの?」
「んあ?」と訊き直したものの、奴の言いたい事は理解出来た。
俺とルフィが、ナミと付き合う気が有るのかを、訊きたかったんだと。
「彼女、あんなに可愛くてスタイルも抜群なのに、何時までも恋人出来なくて可哀想じゃねェか!」
「知るか!俺達のせいじゃねェ!あいつの意思で付き合わねェだけだろ!」
「いいや!クソ野郎2人が集ってるせいで、傍に男が近寄れねェんだ!…ナミさん、可哀想に…!」
「クソ野郎はてめェだろうが!鼻擦るんだったら手ぐらい洗え!」
「クソなんてするか!コレ吸ってたに決まってるだろ!」
人差し指と中指を口に当てて、スパーと息を吐き出して見せる。
小学5年にして煙草の味を覚えたと自慢する奴は、男子連中の間では有名なヘビースモーカーだった。
「で、付き合う気は有んのか?」
にやけた表情が一瞬で真剣なものに変る。
「無ェよ!俺もルフィも、あいつの事は家族みてェに認識してる。ナミにしたって俺達を家族だと認識してっだろうさ」
「付き合う気が無ェんなら解放してやれよ。恋人になる気も無ェのに何時までも傍に居ちゃ、彼女をオールドミスにしちまう。彼女が許してるからって、無責任な関係に甘んじてるな。男なら白黒はっきりさせて、付き合う気が無ェんなら身を引け!後は俺が引き受けっから!」
「とどのつまり狙いはそれか?」
「あったりめェだろ、クソマリモン!」
ニヤニヤと軽薄な笑みを浮かべる、いけ好かない野郎だ。
まるで俺とルフィがナミを束縛して、恋人を作る邪魔してるみたいに言いやがって。
そんな真似1度もしたこた無ェ、俺達はあいつの保護者じゃない。
大体まだ高校生の内から、将来あいつがオールドミスになるかならないかなんて心配してんな!
先にてめェの進路の心配しやがれ!
なまじ幼馴染なのが不味い。
身も心も近くに在り過ぎて付き合う必要を感じねェ。
もしも離れてたなら、傍に居る為に付き合おうって気にもなるだろう。
女に育った姿を透かして、ガキの姿のナミが見える。
ナミにしたって俺達の後ろに、ガキのままの俺達が見えてるんだろう。
けれど俺達はナミよりも早く、心が大人に育っちまった。
ナミは体こそ俺達よりも早く育ったけど、心はガキのまま俺達を求めてる。
だから俺達は逃げる、ナミの心を裏切らない為に――
――カンカンカンという甲高い踏み切りの音で目が覚まされる。
ぼんやり考え込んでる内に日は落ちて、薄闇の下りた園内には外灯が点っていた。
ナミはまだ戻って来ない。
「…何処までかけに行ったんだ、あいつは!」
舌打ちをする、捜しに行こうとベンチを立った。
こういう時は携帯無いと不便だなと感じる。
その時ふと、砂場を挟んで奥のベンチに、気配を感じた。
公園内に外灯は2ヵ所、住宅に隣接する奥は、外灯に照らされていない。
俺はその場に立ったまま、目を凝らした。
――女が居る。
向うのベンチの後ろにも同じく紫陽花が咲いていて、最初俺は花が動いてるのかと錯覚した。
そうじゃなくて、それは女が着ている丈の長いスカートの柄だった。
紫陽花柄のスカートをはいた女が1人、四つん這いになってベンチの周りをぐるぐる回っている。
暫くすると今度は立ち上がり、またベンチの周りをぐるぐる回った。
一心不乱といった体で、見ている俺に気付きもしない。
日は落ちても蒸し暑さは消えず、俺の背中は汗でじっとり濡れた。
――丈の長いスカートをはいた長い髪の女が、空ろな顔してうろうろと。
腕時計で確認する。
まだ7時前だ。
女が独りで居たって不思議じゃない。
キ××イだろう、声をかけるな。
放っといてナミを捜しに行くんだ。
なのに俺は近付いて、声をかけていた。
「何してんだ?」
女が振り向いて俺を見る。
間近で見た顔は蒼白くなく、生気に満ちていて、ほっとした。
黒の半袖ブラウスに紫陽花柄のロングスカート、腰まで伸びてる長い黒髪。
格好から察するに二十歳前後、俺より年上だろう。
「…びっくりしたァ~!いきなり声かけて来るから…危ない人かと思っちゃった…!」
それはこっちの台詞だ。
しかし女の立場からすると、生死に関らず、誰も居ない公園で男から声をかけられるのは恐怖だろう。
俺は心持ち距離を保ち、改めて声をかけた。
「いや…何か探してるみてェだったから…手伝ってやろうか?」
ナミの事も気になるが、知人を優先して目の前で困ってる他人を放っぽるのは、人でなしな気がする。
ルフィを相手に長電話してるんだろうし、ルフィと話してるなら、何か有れば奴が駆けつける筈だ。
そう判断した俺は、目の前に居る女を優先する事に決めた。
「手伝ってくれるの?嬉しい!」
パッと女の顔が綻ぶ。
その顔を見て、俺は生きてる人間である事を確信した。
「1人じゃ見付けられなくて困ってたの!それで会った人に声をかけて手伝ってくれるよう頼んだんだけど、何故か皆血相変えて逃げてくの」
「そりゃきっと幽霊だと誤解されたんじゃねェか?この公園、1週間位出るって噂が流れてたらしいから」
「私が幽霊?酷い!それで皆、声をかけただけで逃げちゃったのね」
「ひょっとして1週間位前から、あんた此処でずっと探し回ってたのか?夜も?」
「ええ…どうしても見付けなくちゃいけなくて…夜に公園来るのは恐かったけど、時を選んでなんていられなかった」
「幽霊の正体見たり枯れ尾花」とは言うが、この女にしてみれば幽霊騒ぎが持ち上がったせいで、とんだ試練を味わったわけだ。
笑うのは酷だが、噴出すのを耐えるのに苦労した。
「で、何探してんだ?コンタクトレンズとか…」
物の影がどんどん濃くなる。
1度家に戻って懐中電灯を取りに行った方が良いかもしれない。
ナミが戻って来たら、取りに行ってくれるよう頼むか。
考えてるそこへ、ナミの金切り声が響いた。
「その女から離れて!!!ゾロ…!!!」
ナミは公園に1人で飛び込んで来た。
結局電話は繋がらなかったのか。
「早く離れるのよ、ゾロ…!!!」
「…ナミ?一体何だってんだ?」
外灯に照らされたナミの顔が強張っている。
離れた所からも震えているのが判った。
「おい、誤解すんなよ。この人はちゃんと生きてる!…丁度良い所に来たな。お前、ちょっと家に戻って懐中電灯を持って来て――」
笑いながら近付こうとして、足が止まった。
後ろから女に腕を掴まれている。
ゾッとするような冷たい手だった。
「おかしいと思わないの!?雨が降ったわけでもないのに、そんなにずぶ濡れで…!!!その人普通じゃない…早く離れて、ゾロ…!!!」
「……ずぶ濡れ?…何を言って……!」
まるで泣き叫ぶような声でナミが喚く。
その様子を見ていて、恐怖がじわじわと背中を這い登った。
出会った女の顔は生気に満ちていて、生きてる人間にしか思えなかった。
けれど今掴まれている腕に、濡れた感触を覚える。
体が硬直して振り向けない。
背後でゴボゴボと水が湧き出る音がする――足下に気配を感じて俯くと、地面が泥濘に変わっていた。
【続】
「この先左脇に小さな公園が有るでしょ?
1週間位前から、そこに幽霊が出るって噂が立ってるの。
髪が長くて、長いスカートはいてたって…実際に見たコがクラスに居て、話してくれたのよ」
ナミと一緒に線路沿いの細い道を歩いてく。
時折、踏み切りの音が甲高く響き、少し遅れて電車が横を、ガタンゴトンと過ぎてった。
道が次第に上り坂に変わる、線路よりも高くなった足場から右に顔を向けると、背の高い金網越しに屋根が低く連なって見えた。
家並みの上に棚引く雲が、夕陽に染まって赤い。
陽射しは未だギラギラと強く、道の左側に続く白い石壁には、俺とナミの影が真っ黒く焦げ付いていた。
石壁が途切れて、左に紫陽花に囲まれた公園が現れる。
住宅地の隙間に押し込まれた様な、砂場だけの四角く狭い公園だ。
「猫の額」ってのは、こういう場所を指して言うんだろう。
道より更に小高い公園内に入ったところで、ナミは漸く連れて来た理由を説明した。
「幽霊が出る…だァ?てめェは、んなくだんねェ理由で、人を此処まで連れて来やがったのか…!」
「だって1週間位の内に、もう何人も見てんのよ!見たコは時間までしっかり覚えてて、嘘とはとても思えなかった!」
呆れを通り越して怒りが湧いた。
しかし睨まれた当人には俺が何を怒ってるのか解らないらしく、言い訳するにもポイントが完璧にズレている。
「嘘っぽい怪談って解るじゃない?『友人に聞いた話なんだけどォ~』なんて出だしで、体験者をぼかしてさ。この場合見た本人がはっきり『見た!』って主張してんのよ。すっごく信憑性高いと思う!」
「噂が嘘だと疑ってるわけじゃねェ…幽霊が出ようが出まいが、どうだっていいんだよ!」
興奮して喋るのを遮り、叫んだ。
俺を見上げるナミの目が真ん丸に開く。
「ゾロって、肝試しは嫌い?」
その一言でブチリと切れた。
「帰るぞ!」
踵を返してさっさと階段を下りる。
道に出る直前で首だけ振り返ると、ナミは背中を向けて、門の側のベンチに座って居た。
断固帰らない態度かよ…何故そんなにもムキになるんだか。
大仰に溜息を吐いて、頭をガリガリと掻く。
不承不承ベンチの側まで戻り、膨れっ面してる女の肩を、軽く叩いた。
「おら、帰るぞって!」
「帰りたければ、どうぞ勝手にお帰り下さい!私は帰んないから…!」
手をはね除けプイと逸らした顔は、とても高2には見えない。
今度は少し力を強めて、肩を揺さ振った。
再びその手をはね除けられる、自然と俺の口からは大きな溜息が漏れた。
「お前は反抗期のガキか?そうまでムキになるほど肝試しがしてェのか?」
「ゾロこそ急に大人ぶっちゃって、まだ高校生のクセに、可愛げ無い!肝試しくらい気さくに付き合ってくれたっていいでしょ!?」
…高校生男子に可愛げ求めてんじゃねェよ。
売り言葉に買い言葉で返して、いっその事置いてっちまおうかと思ったが、中身はガキでも器は充分女だ。
寄って来るのは幽霊に限らず、公園に独り残してくわけにいかねェ。
仕方なく隣に腰掛けた。
「…帰るんじゃなかったの?」
すっかり不貞腐れた顔を向けるも、ナミは俺がゆったり座れるように、体を右にずらしてくれた。
「夕日が落ちるまでだ。落ちたら一緒に帰る、いいな!」
後ろ向きのまま、太陽を指差して言う。
日が沈む間際の黄昏時、公園はオレンジ色の光に満ちていた。
「けど、見たコが言うには、夜10時頃だったって話よ。塾帰りに横を通ったら、丈の長いスカートをはいた長い髪の女が、空ろな顔してうろうろと――」
「んな時間まで待ってられっか!ただのキ××イだったかもしれねェだろ!」
「でも1週間位、毎日出てるって噂で――」
「だからキ××イなんだろって!!…違っても、そんだけの証言で幽霊だと決め付けられっか!」
「それに紫陽花が――」
「紫陽花??」
公園を囲む紫陽花を見回してナミが話す。
「紫陽花って土の質によって色を変えるって言うじゃない?去年と色が違って妙に鮮やかだって言う人が居るのよ」
「紫陽花の根元に死体でも埋められてるってか?んな事言うなら掘ってみるか?」
「や!ちょっ!止めてよ!!本当に出て来たら恐いじゃない!!」
「恐いんなら、そもそも肝試しなんてしようとすんなよ、矛盾してるヤツだな」
昔からこいつは恐がりのクセに、ホラー映画を観ようとしてたっけ。
観る時は必ず俺とルフィを呼び、てめェの後ろに俺達を座らせた。
トイレに行く時は必ず俺かルフィのどっちかを付き添わせ、出て来るまでドアの前で立たせた。
普段勝気で威張ってる女が怯える様は可笑しくて、ルフィと2人でわざと前に座ったり、居なくなったりしたもんだ。
今こうして腕に縋り付いてると、懐かしく思い出しちまう。
意地悪い笑みになってたのか、ナミに頬を思い切り抓られた。
時折響く踏切と電車の音と、俺達の喋る声以外は、何も聞えない。
住宅地の狭間だってのに、薄気味悪かった。
公園を囲む紫陽花が、西日を受けて虹みてェに輝いてる。
赤に青に白にピンクに紫に…その色が刻々とぼんやりして来た。
後ろを振り向けば、夕日が屋根の向うに、半分位落ちている。
夏至間近の空は中々暗くならないが、日が落ちれば早い。
「…後5分ってとこか」
俺が呟いたのを聞き、ナミが唇をギュッと噛んだ。
膝の上に置いてる鞄から、携帯を取り出す。
「ルフィを呼ぶから、来るまで待って!」
「は?…寝込んでる奴呼び出そうとすんなよ。つか呼んでどうする積りだ?」
「だって3人だったら、ゾロも居てくれるでしょ?ルフィならもう復活してるだろうし、肝試ししてるって聞いたら、あいつ嬉々として駆け付けるわ!」
止める間も無くナミが携帯を耳に当てる。
機械的な女の音声が漏れ聞えた。
「電波の届かない場所ォ!?嘘ォ!?公園でかけてるのにィ!?」
「だから止めろって…薬呑んで寝てるだろうしって――おいっ!聞けよっっ!!」
「この辺妨害電波でも乱れ飛んでんのかしら?線路の近くだし――ちょっと離れた所でかけて来る…!!」
ベンチを立ち、公園内をうろちょろ移動してかけるも繋がらなかったらしく、ナミは終いにゃ公園の外に出て行った。
まったく……何を意地になってんだか。
独りベンチに残された俺は、既に何度目かの大きな溜息を吐いた。
――お前ら、付き合う気有んの?
同級の悪友からぶつけられた質問が頭に蘇った。
学校で或る時もよおしてトイレに寄った時だ。
個室から丁度出て来た奴と会った。
「…おう」
「よォ」
短く挨拶を交わして出て行こうとした矢先、背中に脈絡の無い質問をぶつけられた。
「お前ら、付き合う気有んの?」
「んあ?」と訊き直したものの、奴の言いたい事は理解出来た。
俺とルフィが、ナミと付き合う気が有るのかを、訊きたかったんだと。
「彼女、あんなに可愛くてスタイルも抜群なのに、何時までも恋人出来なくて可哀想じゃねェか!」
「知るか!俺達のせいじゃねェ!あいつの意思で付き合わねェだけだろ!」
「いいや!クソ野郎2人が集ってるせいで、傍に男が近寄れねェんだ!…ナミさん、可哀想に…!」
「クソ野郎はてめェだろうが!鼻擦るんだったら手ぐらい洗え!」
「クソなんてするか!コレ吸ってたに決まってるだろ!」
人差し指と中指を口に当てて、スパーと息を吐き出して見せる。
小学5年にして煙草の味を覚えたと自慢する奴は、男子連中の間では有名なヘビースモーカーだった。
「で、付き合う気は有んのか?」
にやけた表情が一瞬で真剣なものに変る。
「無ェよ!俺もルフィも、あいつの事は家族みてェに認識してる。ナミにしたって俺達を家族だと認識してっだろうさ」
「付き合う気が無ェんなら解放してやれよ。恋人になる気も無ェのに何時までも傍に居ちゃ、彼女をオールドミスにしちまう。彼女が許してるからって、無責任な関係に甘んじてるな。男なら白黒はっきりさせて、付き合う気が無ェんなら身を引け!後は俺が引き受けっから!」
「とどのつまり狙いはそれか?」
「あったりめェだろ、クソマリモン!」
ニヤニヤと軽薄な笑みを浮かべる、いけ好かない野郎だ。
まるで俺とルフィがナミを束縛して、恋人を作る邪魔してるみたいに言いやがって。
そんな真似1度もしたこた無ェ、俺達はあいつの保護者じゃない。
大体まだ高校生の内から、将来あいつがオールドミスになるかならないかなんて心配してんな!
先にてめェの進路の心配しやがれ!
なまじ幼馴染なのが不味い。
身も心も近くに在り過ぎて付き合う必要を感じねェ。
もしも離れてたなら、傍に居る為に付き合おうって気にもなるだろう。
女に育った姿を透かして、ガキの姿のナミが見える。
ナミにしたって俺達の後ろに、ガキのままの俺達が見えてるんだろう。
けれど俺達はナミよりも早く、心が大人に育っちまった。
ナミは体こそ俺達よりも早く育ったけど、心はガキのまま俺達を求めてる。
だから俺達は逃げる、ナミの心を裏切らない為に――
――カンカンカンという甲高い踏み切りの音で目が覚まされる。
ぼんやり考え込んでる内に日は落ちて、薄闇の下りた園内には外灯が点っていた。
ナミはまだ戻って来ない。
「…何処までかけに行ったんだ、あいつは!」
舌打ちをする、捜しに行こうとベンチを立った。
こういう時は携帯無いと不便だなと感じる。
その時ふと、砂場を挟んで奥のベンチに、気配を感じた。
公園内に外灯は2ヵ所、住宅に隣接する奥は、外灯に照らされていない。
俺はその場に立ったまま、目を凝らした。
――女が居る。
向うのベンチの後ろにも同じく紫陽花が咲いていて、最初俺は花が動いてるのかと錯覚した。
そうじゃなくて、それは女が着ている丈の長いスカートの柄だった。
紫陽花柄のスカートをはいた女が1人、四つん這いになってベンチの周りをぐるぐる回っている。
暫くすると今度は立ち上がり、またベンチの周りをぐるぐる回った。
一心不乱といった体で、見ている俺に気付きもしない。
日は落ちても蒸し暑さは消えず、俺の背中は汗でじっとり濡れた。
――丈の長いスカートをはいた長い髪の女が、空ろな顔してうろうろと。
腕時計で確認する。
まだ7時前だ。
女が独りで居たって不思議じゃない。
キ××イだろう、声をかけるな。
放っといてナミを捜しに行くんだ。
なのに俺は近付いて、声をかけていた。
「何してんだ?」
女が振り向いて俺を見る。
間近で見た顔は蒼白くなく、生気に満ちていて、ほっとした。
黒の半袖ブラウスに紫陽花柄のロングスカート、腰まで伸びてる長い黒髪。
格好から察するに二十歳前後、俺より年上だろう。
「…びっくりしたァ~!いきなり声かけて来るから…危ない人かと思っちゃった…!」
それはこっちの台詞だ。
しかし女の立場からすると、生死に関らず、誰も居ない公園で男から声をかけられるのは恐怖だろう。
俺は心持ち距離を保ち、改めて声をかけた。
「いや…何か探してるみてェだったから…手伝ってやろうか?」
ナミの事も気になるが、知人を優先して目の前で困ってる他人を放っぽるのは、人でなしな気がする。
ルフィを相手に長電話してるんだろうし、ルフィと話してるなら、何か有れば奴が駆けつける筈だ。
そう判断した俺は、目の前に居る女を優先する事に決めた。
「手伝ってくれるの?嬉しい!」
パッと女の顔が綻ぶ。
その顔を見て、俺は生きてる人間である事を確信した。
「1人じゃ見付けられなくて困ってたの!それで会った人に声をかけて手伝ってくれるよう頼んだんだけど、何故か皆血相変えて逃げてくの」
「そりゃきっと幽霊だと誤解されたんじゃねェか?この公園、1週間位出るって噂が流れてたらしいから」
「私が幽霊?酷い!それで皆、声をかけただけで逃げちゃったのね」
「ひょっとして1週間位前から、あんた此処でずっと探し回ってたのか?夜も?」
「ええ…どうしても見付けなくちゃいけなくて…夜に公園来るのは恐かったけど、時を選んでなんていられなかった」
「幽霊の正体見たり枯れ尾花」とは言うが、この女にしてみれば幽霊騒ぎが持ち上がったせいで、とんだ試練を味わったわけだ。
笑うのは酷だが、噴出すのを耐えるのに苦労した。
「で、何探してんだ?コンタクトレンズとか…」
物の影がどんどん濃くなる。
1度家に戻って懐中電灯を取りに行った方が良いかもしれない。
ナミが戻って来たら、取りに行ってくれるよう頼むか。
考えてるそこへ、ナミの金切り声が響いた。
「その女から離れて!!!ゾロ…!!!」
ナミは公園に1人で飛び込んで来た。
結局電話は繋がらなかったのか。
「早く離れるのよ、ゾロ…!!!」
「…ナミ?一体何だってんだ?」
外灯に照らされたナミの顔が強張っている。
離れた所からも震えているのが判った。
「おい、誤解すんなよ。この人はちゃんと生きてる!…丁度良い所に来たな。お前、ちょっと家に戻って懐中電灯を持って来て――」
笑いながら近付こうとして、足が止まった。
後ろから女に腕を掴まれている。
ゾッとするような冷たい手だった。
「おかしいと思わないの!?雨が降ったわけでもないのに、そんなにずぶ濡れで…!!!その人普通じゃない…早く離れて、ゾロ…!!!」
「……ずぶ濡れ?…何を言って……!」
まるで泣き叫ぶような声でナミが喚く。
その様子を見ていて、恐怖がじわじわと背中を這い登った。
出会った女の顔は生気に満ちていて、生きてる人間にしか思えなかった。
けれど今掴まれている腕に、濡れた感触を覚える。
体が硬直して振り向けない。
背後でゴボゴボと水が湧き出る音がする――足下に気配を感じて俯くと、地面が泥濘に変わっていた。
【続】