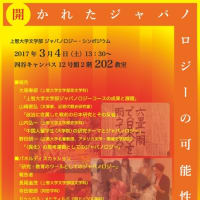ようやく春学期の授業がすべて終わり、夏期休暇まで数日となった。…といっても、会議やら書類作成やらいろいろあって、8月も下旬になるまで校務に忙殺されそうだ。それから毎年恒例の宗教史懇話会サマーセミナー、ゼミ旅行などをこなしているうちに、気がつけば秋の校務が始まっている…というパターンに陥るのは目にみえている。なんとか計画的に時間を作って、滞っている研究方面の作業を進展させなくてはならないが、健康上の問題など、今年は障害が多そうである。
それはともかく、一応は春学期の授業を振り返っておこうか。まずは、日本史特講「歴史学のアクチュアリティ」である。歴史学がさまざまな現代的問題に衝突し、他学問との論争を経験しながら変質してゆく様子を、ポストモダン的立場から、自分自身の「パラダイム構築史」として話していった。歴史修正主義、戦争責任問題、言語論的転回、他者表象の倫理など、理論的な話題がぎっしりだったので、学生たちはさぞかし辟易しただろう。しかし全講義の終了後、「いろいろと考えさせられるというか、揺るがされた授業でした。日常生活で反省することが多くなって、居心地が悪く感じることが多いような気がします。自分の想像できないようなことがたくさんあるということ、それをどうやって考えていくかというのが大切なのだと思いました。これからも、先生の授業を受けていた時のような状態にいられるように、いろいろ考えていきたいと思います」「この講義を受講して、興味深いお話を沢山聞かせていただき、本当に視野が広がった気がします。やはり色々な問題を考えることは非常に面白いです。多元的な世界において、色々なものの根底にあるのは倫理性のように思います。存在論より前に…。あと少しで大学も終わりますが、その後も、このような問題について考えていきたいと思います。僕はバカですので、一生勉強を続けていきたいです。先生にいただいたレジュメやその中の参考文献表は宝物になると思います。本当にありがとうございました」といったリアクションももらえたので、まあそれほどまずい授業でもなかったのだろう(あなた方のような学生さんに聴いていただけて、こちらも幸せです)。学生への語りかけ、質問への回答を通じて、自分が何を理解できていないか、現行の方法では何に立ち向かうことができないか、熟考を重ねることができた。
 シラバスの段階では、理論編と実践編を1:2程度の割合で話してゆく予定だったのだが、やはり理論編の解説に時間がかかり、本当の実践編は最終回の1回分のみとなってしまった。そこで仕方なく、3回分のレジュメを1回分で講義できるようにシェイプアップし、「臨床歴史学の試み」というタイトルを冠して総括することとした。「臨床」という言葉は、べつに誰かのベッドの横で聞き取り作業に勤しむということではなく、現在性・現場性を重視するといった程度の意味合いである。ヒントになったのは、ピエール・ブルデューの晩年の著作『世界の悲惨(La Misère du monde)』である。様々な〈場〉の下方・境界に位置づけられた人々に対し、その悲惨=境遇や憤懣・苦痛がいかなる社会的要因に由来するのか、何度も何度も話し合って気づかせ、そこから解放され自由になる方途をともに考える試み。しかし、人間の思考様式や行動様式が過去からの積み重ねによって規制されているのなら、歴史学的知を駆使してそれらを脱構築し、例えば〈創られた伝統〉のような捏造的歴史認識の束縛から現代人を解放して、豊かで多元的なポジションの構築に寄与することができるのではないか。歴史学のベクトルとは、近代以降、現在から過去へ向かうものでしかなかったが、〈臨床歴史学〉は、過去から現在を批判する視野を持つ。それは、前近代的な歴史認識であるpractical pastの自己同一性を、他者=死者からの視線によって彫琢したものであり、歴史学的成果を社会に開き(監視の目に供する)回路でもある。
シラバスの段階では、理論編と実践編を1:2程度の割合で話してゆく予定だったのだが、やはり理論編の解説に時間がかかり、本当の実践編は最終回の1回分のみとなってしまった。そこで仕方なく、3回分のレジュメを1回分で講義できるようにシェイプアップし、「臨床歴史学の試み」というタイトルを冠して総括することとした。「臨床」という言葉は、べつに誰かのベッドの横で聞き取り作業に勤しむということではなく、現在性・現場性を重視するといった程度の意味合いである。ヒントになったのは、ピエール・ブルデューの晩年の著作『世界の悲惨(La Misère du monde)』である。様々な〈場〉の下方・境界に位置づけられた人々に対し、その悲惨=境遇や憤懣・苦痛がいかなる社会的要因に由来するのか、何度も何度も話し合って気づかせ、そこから解放され自由になる方途をともに考える試み。しかし、人間の思考様式や行動様式が過去からの積み重ねによって規制されているのなら、歴史学的知を駆使してそれらを脱構築し、例えば〈創られた伝統〉のような捏造的歴史認識の束縛から現代人を解放して、豊かで多元的なポジションの構築に寄与することができるのではないか。歴史学のベクトルとは、近代以降、現在から過去へ向かうものでしかなかったが、〈臨床歴史学〉は、過去から現在を批判する視野を持つ。それは、前近代的な歴史認識であるpractical pastの自己同一性を、他者=死者からの視線によって彫琢したものであり、歴史学的成果を社会に開き(監視の目に供する)回路でもある。
ぼくは昨年7月、友人の加藤幸治さんに依頼され、震災後間もない東北で「震災を乗り越えてきた人々」という連続講演会に携わることとなった。ぼく以外の後援者はすべて東北在住の研究者であったから、東京でろくな被害にも遭っていない自分が一体何を話せばいいのか、何を語りうるのか、当事者性の壁を前に非常に悩んだ。その結果として出した答えが、被災した人々に浴びせられた様々な批判的言説を、歴史学的観点から相対化してゆくことだった。まず、「災害に関する教訓が活かされていない」という声には、古代から現代に至る列島社会が意外にも流動性の高いものであったことを示し、地域に密着した細かい知識が重要な災害情報は、もともと長期には伝承されにくいものであったと論じた。「なぜ高台に住まず海岸を選ぶのか」という疑問に対しては、列島の半定住状態が水辺から始まったこと、我々の心性には、氷河期終了後から水辺への親近感がやはり東アジア的な規模で構築されていることを、中国の古典から道教経典、少数民族の伝承、日本の和歌から昔話に至る種々の資料を提示しながら明らかにした。また天譴論に関しては、日本文学協会の大会シンポジウム「文学のリアリティ」において発表する機会を得、東アジアの長い歴史のなかで紀元前より存在し、大規模災害時に王権の正当化や社会不安の抑制のため、一時的に流行する「社会の防衛機制」であると述べた。これらの考察がどの程度有効に機能しえたかは、正直確認する手段がない。しかし、「歴史学のアクチュアリティ」を考えてゆくうえで、格好の検討材料にはなっているのではないかと思う。
授業では、最後に、「津波のあと潟になってしまった海岸部の地形をそのままに残そう」「これは人間が自然の懐深くに入り込みすぎた結果である」と発言している赤坂憲雄氏の見解にも触れた。私見では、三陸付近の海岸部からは泥炭層が検出されているので、海水の入り込んだ潟以外にも、多く低湿地林が広がっていたのではないかと考えている。それを切り払い、最終的に水田化していったのは、「自然の懐深くに入り込みすぎた」というより、海進と海退の繰り返しによる環境変化に適応して生活を営んできた結果なのだろう。そして古代国家以降の政府や地域首長が、長期にわたり米を税の主体に据えてきたことが影を落としている。もともとは南方系の植物であるイネが、なぜこれほどまでに東北で作り続けられ、現代に至るのか。そのことの意味を、もう一度しっかりと考えねばならないだろう。
〈臨床歴史学〉というタームを得て、何とかこの講義も本にまとめられるかな、という気がしてきた。しかし、順々に仕事を片付けてゆくとして、こちらにたどり着けるのは一体いつになるだろう。それまで出版社が待ってくれるかどうかが問題である。
それはともかく、一応は春学期の授業を振り返っておこうか。まずは、日本史特講「歴史学のアクチュアリティ」である。歴史学がさまざまな現代的問題に衝突し、他学問との論争を経験しながら変質してゆく様子を、ポストモダン的立場から、自分自身の「パラダイム構築史」として話していった。歴史修正主義、戦争責任問題、言語論的転回、他者表象の倫理など、理論的な話題がぎっしりだったので、学生たちはさぞかし辟易しただろう。しかし全講義の終了後、「いろいろと考えさせられるというか、揺るがされた授業でした。日常生活で反省することが多くなって、居心地が悪く感じることが多いような気がします。自分の想像できないようなことがたくさんあるということ、それをどうやって考えていくかというのが大切なのだと思いました。これからも、先生の授業を受けていた時のような状態にいられるように、いろいろ考えていきたいと思います」「この講義を受講して、興味深いお話を沢山聞かせていただき、本当に視野が広がった気がします。やはり色々な問題を考えることは非常に面白いです。多元的な世界において、色々なものの根底にあるのは倫理性のように思います。存在論より前に…。あと少しで大学も終わりますが、その後も、このような問題について考えていきたいと思います。僕はバカですので、一生勉強を続けていきたいです。先生にいただいたレジュメやその中の参考文献表は宝物になると思います。本当にありがとうございました」といったリアクションももらえたので、まあそれほどまずい授業でもなかったのだろう(あなた方のような学生さんに聴いていただけて、こちらも幸せです)。学生への語りかけ、質問への回答を通じて、自分が何を理解できていないか、現行の方法では何に立ち向かうことができないか、熟考を重ねることができた。
 シラバスの段階では、理論編と実践編を1:2程度の割合で話してゆく予定だったのだが、やはり理論編の解説に時間がかかり、本当の実践編は最終回の1回分のみとなってしまった。そこで仕方なく、3回分のレジュメを1回分で講義できるようにシェイプアップし、「臨床歴史学の試み」というタイトルを冠して総括することとした。「臨床」という言葉は、べつに誰かのベッドの横で聞き取り作業に勤しむということではなく、現在性・現場性を重視するといった程度の意味合いである。ヒントになったのは、ピエール・ブルデューの晩年の著作『世界の悲惨(La Misère du monde)』である。様々な〈場〉の下方・境界に位置づけられた人々に対し、その悲惨=境遇や憤懣・苦痛がいかなる社会的要因に由来するのか、何度も何度も話し合って気づかせ、そこから解放され自由になる方途をともに考える試み。しかし、人間の思考様式や行動様式が過去からの積み重ねによって規制されているのなら、歴史学的知を駆使してそれらを脱構築し、例えば〈創られた伝統〉のような捏造的歴史認識の束縛から現代人を解放して、豊かで多元的なポジションの構築に寄与することができるのではないか。歴史学のベクトルとは、近代以降、現在から過去へ向かうものでしかなかったが、〈臨床歴史学〉は、過去から現在を批判する視野を持つ。それは、前近代的な歴史認識であるpractical pastの自己同一性を、他者=死者からの視線によって彫琢したものであり、歴史学的成果を社会に開き(監視の目に供する)回路でもある。
シラバスの段階では、理論編と実践編を1:2程度の割合で話してゆく予定だったのだが、やはり理論編の解説に時間がかかり、本当の実践編は最終回の1回分のみとなってしまった。そこで仕方なく、3回分のレジュメを1回分で講義できるようにシェイプアップし、「臨床歴史学の試み」というタイトルを冠して総括することとした。「臨床」という言葉は、べつに誰かのベッドの横で聞き取り作業に勤しむということではなく、現在性・現場性を重視するといった程度の意味合いである。ヒントになったのは、ピエール・ブルデューの晩年の著作『世界の悲惨(La Misère du monde)』である。様々な〈場〉の下方・境界に位置づけられた人々に対し、その悲惨=境遇や憤懣・苦痛がいかなる社会的要因に由来するのか、何度も何度も話し合って気づかせ、そこから解放され自由になる方途をともに考える試み。しかし、人間の思考様式や行動様式が過去からの積み重ねによって規制されているのなら、歴史学的知を駆使してそれらを脱構築し、例えば〈創られた伝統〉のような捏造的歴史認識の束縛から現代人を解放して、豊かで多元的なポジションの構築に寄与することができるのではないか。歴史学のベクトルとは、近代以降、現在から過去へ向かうものでしかなかったが、〈臨床歴史学〉は、過去から現在を批判する視野を持つ。それは、前近代的な歴史認識であるpractical pastの自己同一性を、他者=死者からの視線によって彫琢したものであり、歴史学的成果を社会に開き(監視の目に供する)回路でもある。ぼくは昨年7月、友人の加藤幸治さんに依頼され、震災後間もない東北で「震災を乗り越えてきた人々」という連続講演会に携わることとなった。ぼく以外の後援者はすべて東北在住の研究者であったから、東京でろくな被害にも遭っていない自分が一体何を話せばいいのか、何を語りうるのか、当事者性の壁を前に非常に悩んだ。その結果として出した答えが、被災した人々に浴びせられた様々な批判的言説を、歴史学的観点から相対化してゆくことだった。まず、「災害に関する教訓が活かされていない」という声には、古代から現代に至る列島社会が意外にも流動性の高いものであったことを示し、地域に密着した細かい知識が重要な災害情報は、もともと長期には伝承されにくいものであったと論じた。「なぜ高台に住まず海岸を選ぶのか」という疑問に対しては、列島の半定住状態が水辺から始まったこと、我々の心性には、氷河期終了後から水辺への親近感がやはり東アジア的な規模で構築されていることを、中国の古典から道教経典、少数民族の伝承、日本の和歌から昔話に至る種々の資料を提示しながら明らかにした。また天譴論に関しては、日本文学協会の大会シンポジウム「文学のリアリティ」において発表する機会を得、東アジアの長い歴史のなかで紀元前より存在し、大規模災害時に王権の正当化や社会不安の抑制のため、一時的に流行する「社会の防衛機制」であると述べた。これらの考察がどの程度有効に機能しえたかは、正直確認する手段がない。しかし、「歴史学のアクチュアリティ」を考えてゆくうえで、格好の検討材料にはなっているのではないかと思う。
授業では、最後に、「津波のあと潟になってしまった海岸部の地形をそのままに残そう」「これは人間が自然の懐深くに入り込みすぎた結果である」と発言している赤坂憲雄氏の見解にも触れた。私見では、三陸付近の海岸部からは泥炭層が検出されているので、海水の入り込んだ潟以外にも、多く低湿地林が広がっていたのではないかと考えている。それを切り払い、最終的に水田化していったのは、「自然の懐深くに入り込みすぎた」というより、海進と海退の繰り返しによる環境変化に適応して生活を営んできた結果なのだろう。そして古代国家以降の政府や地域首長が、長期にわたり米を税の主体に据えてきたことが影を落としている。もともとは南方系の植物であるイネが、なぜこれほどまでに東北で作り続けられ、現代に至るのか。そのことの意味を、もう一度しっかりと考えねばならないだろう。
〈臨床歴史学〉というタームを得て、何とかこの講義も本にまとめられるかな、という気がしてきた。しかし、順々に仕事を片付けてゆくとして、こちらにたどり着けるのは一体いつになるだろう。それまで出版社が待ってくれるかどうかが問題である。