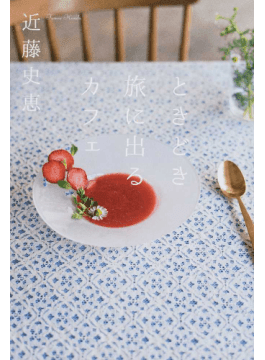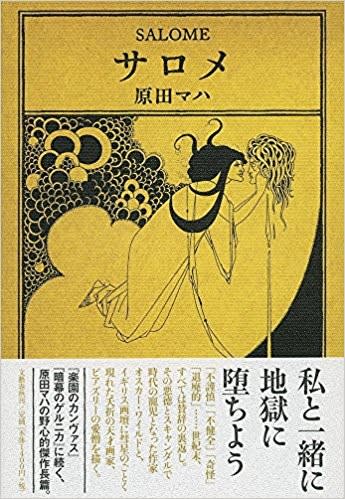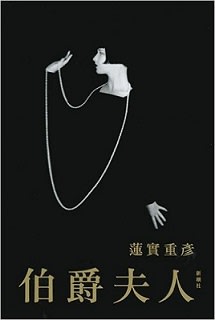読書気分(29年9月~11月)
今日はある会の10周年記念パーティー。
楽しい会になりそうですが、病気の私はもちろん参加できません。
一人ショボくれてブログ書くことにしました。
久しぶりの「読書気分」。この三ヶ月は長い入院もあったため、ほとんど本を読めていません。11月の終わりから読みやすそうな戯曲から少しずつ復活です。
29年9月に読んだ本
大竹昭子『間取りと妄想』
福井隆子『ある狂女の話』
☆大竹昭子『間取りと妄想』
家の間取りに異常に興味をもつ作者の、間取りに関わる13の短編が収録。間取りが深くかかわっている話もあれば、さらっと出てくる間取りもある。添付されている間取図を見ながら小説を読むというちょっと変わった趣向。
小説の中では本棚の奥に小さな窓をつけ隣の息子夫婦の浴室を覗いている「浴室と柿の木」が異色で面白い。建築や設計に興味があれば一層楽しく読めるかもしれない。
☆福井隆子『ある狂女の話』
幼少期を戦時下で過ごした俳人のエッセイ集。俳人らしく、芭蕉や俳句に関する考え方など評論的な文章も混じる。
29年11月に読んだ本
野田秀樹脚本『贋作・桜の森の満開の下』
ルイージ・ピランデッロ脚本『作者を探す六人の登場人物』(ピランデッロ戯曲集Ⅱより)
☆野田秀樹脚本『贋作・桜の森の満開の下』
野田秀樹演出で最近話題になった芝居の戯曲。芝居は見てはいないのだが、読書生活に戻るには読みやすいかと選んだもの。文章は短く字数も少ないのだがこれが中々の難物。事前に芝居見ていないと野田さんの世界には急には入れない。登場人物の名前だけで大混乱。これが芝居を観た人にはすごく面白かったらしい。坂口安吾の小説『桜の森の満開の下』や『夜長姫と耳男』などを下敷きにしているので、次はそちらに手を伸ばしたい。
☆ルイージ・ピランデッロ脚本『作者を探す六人の登場人物』
先日神奈川芸術劇場で見た『作者を探す六人の登場人物』の脚本。
もっと演劇論が表面にでた理窟っぼい戯曲を想像していたが、以外にシンプルで読みやすい。
言葉のこなれた軽いタッチの翻訳の印象からくるものかもしれない。ただこれを演劇として、どうしたら魅力的に見せられるのか私にはわからない。先日見た長塚演出で感じたことは、原作を読んでも払拭出来なかった。二人の子供の死のことも本を読んでも納得出来ず。
作者を離れた登場人物という発想はすごく面白く興味深いのだが。