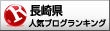時を遡る事、2012年5月26日。
その日は宮崎先生をおむかえして、「巨樹・巨木観察会~千々石・小浜編~」を行っていた。
観察会も終盤、小浜町金浜(かなはま)にあるアコウの巨木を観察して、バスへ戻る途上に撮影したものが表紙の写真です。
私は皆さんの最後尾を歩きながら、(赤い矢印の下)山の中腹に見えた鳥居が気になっていた。
『いづれ訪れよう』と思いながらも、なかなか機会に恵まれずにいた。

ということで(どういう事だ?)、行ってみました!
えっちらおっちら(古い表現だ)、坂道を登って鳥居の場所までたどり着きました。

神額には「天満神社」と書かれてあります。
鳥居から本殿まではこれまたきつい傾斜の階段を登ります。

これが本殿です。
本殿の右に造営の記念碑がありました。
「天満神社は金浜地区の産土神(うぶすながみ)として、大切に守り伝えられてきました。(略)
氏子一同知恵を出し合い、協力して社殿の造営が相成った。」

本殿の左には産土神の石碑が、

右には先の造営記念碑と、新しくなる前のものと思われる神額がありました。
そして、振り返ってみると、

絶景かな絶景かな(笑)
やはり神様は見晴らしの良い場所から私達の生活を見守ってくれているんですね。
その日は宮崎先生をおむかえして、「巨樹・巨木観察会~千々石・小浜編~」を行っていた。
観察会も終盤、小浜町金浜(かなはま)にあるアコウの巨木を観察して、バスへ戻る途上に撮影したものが表紙の写真です。
私は皆さんの最後尾を歩きながら、(赤い矢印の下)山の中腹に見えた鳥居が気になっていた。
『いづれ訪れよう』と思いながらも、なかなか機会に恵まれずにいた。

ということで(どういう事だ?)、行ってみました!
えっちらおっちら(古い表現だ)、坂道を登って鳥居の場所までたどり着きました。

神額には「天満神社」と書かれてあります。
鳥居から本殿まではこれまたきつい傾斜の階段を登ります。

これが本殿です。
本殿の右に造営の記念碑がありました。
「天満神社は金浜地区の産土神(うぶすながみ)として、大切に守り伝えられてきました。(略)
氏子一同知恵を出し合い、協力して社殿の造営が相成った。」

本殿の左には産土神の石碑が、

右には先の造営記念碑と、新しくなる前のものと思われる神額がありました。
そして、振り返ってみると、

絶景かな絶景かな(笑)
やはり神様は見晴らしの良い場所から私達の生活を見守ってくれているんですね。