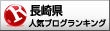時期的にそろそろカモ達が北上を始める。
カモを求めるのも、あと少しだ。
中尾川とトライアルでの買い物を済ませ、雲仙へ帰る途中でふと新田町に立ち寄ることにした。
新田町は、島原市役所から島原鉄道の線路を渡って海側に行ったところです。

海を望める場所に着きました。
以前ここには映画「まぼろしの邪馬台国」のロケ地だった看板があったのですが、なくなっています。
代わりに「古代の伝統漁法スクイ」のジオパーク看板が設置してありました。
見えている、この海の向きにスクイの石垣が設置されているようですが、潮が満ちていて分かりませんね。w

振り返ると道がカーブしてあり、先まで行けそうな道が続いています。
少しだけ進むと「島原海岸風致地区」の石柱と看板、それと教育委員会が設置した案内板があります。

「この区域一帯を三好屋新田といい、江戸時代の豪商三好屋が面積七町三反余り(約七万三千平方米)を干拓した土地です。
三好屋・中山要右衛門が天保八年(1837年)三月 藩主に内海新田の築き立てを願い出て許可され、翌九年九月工事を終了しました。初期は塩田として利用されて、同十年六月には塩十俵を上納しています。
この工事については次のようなエピソードがあります。
中山要右衛門は大商人で、天保七年の飢饉の年に城下の地主や商人はそれぞれ金、米、麦等を寄附しましたが、要右衛門は一向に聞き入れず「けちんぼ」「情け知らずの強欲じじい」といわれました。
この年干拓工事を始めて年寄りや女、子供に至るまで人夫として雇い、普通より高い賃金を支払いました。
このとき要右衛門は「一時の寄附では当座は助かるが、それが無くなればまた苦しい目にあう。工事に出ていれば長い期間助かるから、品物をやる一時の救いと比べて、どちらが本当の救い方といえるか」と人々に話したということです。(島原市教育委員会)」
本日、雲仙にてウグイスの初鳴きを確認しました。