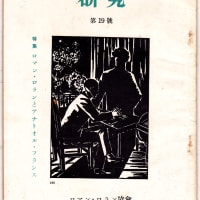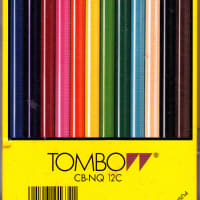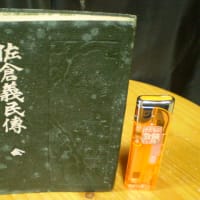脱藩後は、どうしていたのか。
「敏麿伝」では、「或いは吉備の地に潜み、或いは三田尻に通じ、或いは松山に隠れて種々活動をなせり」と記すのみ。
慶応元年、伊達宗城が藩内の人材登用策をとり、雄左衛門のことも聞き、代官、川名謙蔵は「庄屋職辞職後、姿をくらまし、京摂地方にありとの風説ありしが、目下、長州、或いは松山にありと聞こゆと奏上したり。宗城公は直ちに所在を探り、呼び戻すべく命ぜられたり」と書いてある。
「役地事件一夜説」(これは東京自由新聞の記事だろうか?わからない)は、無役地事件の経過を書いたものだが、この中で市村敏麿の経歴にふれ、そこで脱藩についてこういう記事がある。
「身を以って吉備の地に隠れしばらく潜匿し、長幕の一件おこるや(第一次長州征伐か?)、ひそかに三田尻の忠勇隊に通じ大になすところあらんとしたるも、長藩、議して恭順をとり、増田国司福原三太夫の首級を献じ、三条西東久世四条壬生の五卿太宰府に遷徒せらるるの報に接し、天を仰いで嘆息し、それより松山に隠れて時勢の転変をうかかげり」
はじめ、吉備にひそみ、後半、松山にひそむ。その間、長州の忠勇隊と連絡をとりあっていた、ということになる。
慶応2年正月には、伊達宗城に召しだされているので、慶応元年の暮れには、宇和島に帰っているものと思われる
敏麿が脱藩した文久3年後半から、元治元年、慶応元年という3年間は、草莽の志士、脱藩浪士にとっては、最悪最凶の年といってよい。
草莽が活躍できたのは、文久2年、3年、天誅組までだろう。8・18の政変で、長州藩は京都を追われ、京都政局は、薩摩、会津がリード、幕府がもりかえし、新撰組が志士を追いかけまわすという時代が続く。
池田屋事件、禁門の変(忠勇隊に参加した敏麿の仲間も戦死)、幕府の第一次の長州征伐と続く。しかも、外国艦隊にもやられ、攘夷ができないことも知る。長州藩の藩論も変わり、天誅組が頭にした中山忠光さえ、幕府をはばかってひそかに藩命で暗殺されてしまったほどだ。
桂小五郎は乞食に変装し、出石に隠れた時代だ。草莽にとって、命を維持するだけでも大変。地下活動せざるをえない。長州はすでに尊王攘夷の総本山で、倒幕勢力ではなくなりつつあった。草莽、脱藩浪士はたよるところがなくなった(この状況を大回転させたのが、あの高杉晋作だけど)。
慶応からは、もはや個人個人の草莽ではなくて、世の中は、組織、軍隊、藩の力で動く時代になりつつあった。敏麿が、藩からの出仕に応じたのも、こうした思いがあったにちがいない。
なお、忠勇隊とは、長州にいる脱藩浪士の集まりだ。土佐出身者が多いが、とにかく長州藩以外のものがここに集まった。はじめは真木和泉が総裁、隊長が松山深蔵、禁門の変で真木ら自刃したあとは、中岡慎太郎が隊長になっている。敏麿の友人、玉川壮吉もいる。だが、忠勇隊の名簿の中には、宇和島出身はなかったと思う。敏麿は、玉川たちとは連絡はしていたかもしれないが、忠勇隊には所属していなかったと思うのだが、どうだろう。1回か2回は顔を出したことはあるかな。
ちなみに、中岡慎太郎も、庄屋出身の大草莽だ。
なぜ松山にひそんでいたのか。松山は親藩で、幕府側の情報を探るには重要だったとは思うが、松山藩については何も知らないので、わからない。今度、調べておこう。
「敏麿伝」では、「或いは吉備の地に潜み、或いは三田尻に通じ、或いは松山に隠れて種々活動をなせり」と記すのみ。
慶応元年、伊達宗城が藩内の人材登用策をとり、雄左衛門のことも聞き、代官、川名謙蔵は「庄屋職辞職後、姿をくらまし、京摂地方にありとの風説ありしが、目下、長州、或いは松山にありと聞こゆと奏上したり。宗城公は直ちに所在を探り、呼び戻すべく命ぜられたり」と書いてある。
「役地事件一夜説」(これは東京自由新聞の記事だろうか?わからない)は、無役地事件の経過を書いたものだが、この中で市村敏麿の経歴にふれ、そこで脱藩についてこういう記事がある。
「身を以って吉備の地に隠れしばらく潜匿し、長幕の一件おこるや(第一次長州征伐か?)、ひそかに三田尻の忠勇隊に通じ大になすところあらんとしたるも、長藩、議して恭順をとり、増田国司福原三太夫の首級を献じ、三条西東久世四条壬生の五卿太宰府に遷徒せらるるの報に接し、天を仰いで嘆息し、それより松山に隠れて時勢の転変をうかかげり」
はじめ、吉備にひそみ、後半、松山にひそむ。その間、長州の忠勇隊と連絡をとりあっていた、ということになる。
慶応2年正月には、伊達宗城に召しだされているので、慶応元年の暮れには、宇和島に帰っているものと思われる
敏麿が脱藩した文久3年後半から、元治元年、慶応元年という3年間は、草莽の志士、脱藩浪士にとっては、最悪最凶の年といってよい。
草莽が活躍できたのは、文久2年、3年、天誅組までだろう。8・18の政変で、長州藩は京都を追われ、京都政局は、薩摩、会津がリード、幕府がもりかえし、新撰組が志士を追いかけまわすという時代が続く。
池田屋事件、禁門の変(忠勇隊に参加した敏麿の仲間も戦死)、幕府の第一次の長州征伐と続く。しかも、外国艦隊にもやられ、攘夷ができないことも知る。長州藩の藩論も変わり、天誅組が頭にした中山忠光さえ、幕府をはばかってひそかに藩命で暗殺されてしまったほどだ。
桂小五郎は乞食に変装し、出石に隠れた時代だ。草莽にとって、命を維持するだけでも大変。地下活動せざるをえない。長州はすでに尊王攘夷の総本山で、倒幕勢力ではなくなりつつあった。草莽、脱藩浪士はたよるところがなくなった(この状況を大回転させたのが、あの高杉晋作だけど)。
慶応からは、もはや個人個人の草莽ではなくて、世の中は、組織、軍隊、藩の力で動く時代になりつつあった。敏麿が、藩からの出仕に応じたのも、こうした思いがあったにちがいない。
なお、忠勇隊とは、長州にいる脱藩浪士の集まりだ。土佐出身者が多いが、とにかく長州藩以外のものがここに集まった。はじめは真木和泉が総裁、隊長が松山深蔵、禁門の変で真木ら自刃したあとは、中岡慎太郎が隊長になっている。敏麿の友人、玉川壮吉もいる。だが、忠勇隊の名簿の中には、宇和島出身はなかったと思う。敏麿は、玉川たちとは連絡はしていたかもしれないが、忠勇隊には所属していなかったと思うのだが、どうだろう。1回か2回は顔を出したことはあるかな。
ちなみに、中岡慎太郎も、庄屋出身の大草莽だ。
なぜ松山にひそんでいたのか。松山は親藩で、幕府側の情報を探るには重要だったとは思うが、松山藩については何も知らないので、わからない。今度、調べておこう。