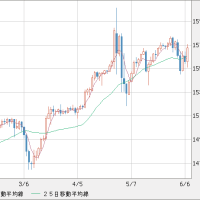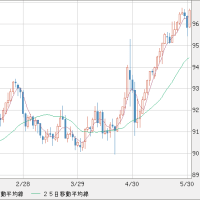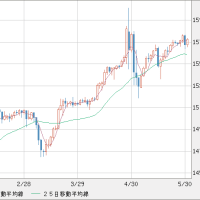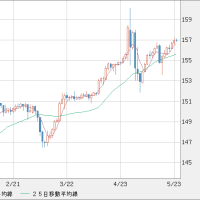矢張り、「復興を加速」と称した安倍首相の発言は嘘で、
投入した兆円規模の予算にもかかわらず
東日本大震災の被災地復興ははかばかしくない。
これも大方の予想通りであろう、
カネをいくら投入して公共事業を行っても、かつての生活が戻ってくる筈がないし
被災地には元々人口流出・減少が続いていた地域が多いこと、
そして福島原発事故は不可逆的かつ長年に及ぶ悪影響を与えていることから、
復興が容易でないことは初めから分かっていたことなのだが。
軽々しく大言壮語した安倍首相と、
社員に対して「高く評価されている」と豪語する東電社長の言葉が、
かつての暮らしを取り戻せない被災地の現状の前で
白々しく響くだけなのは至極当然のことと言える。
このままだと、建設業への降って湧いた特需と
仙台など一部の震災バブルに終わってしまいかねない。
多くの人々の命が失われ、コミュニティと生活が破壊された末に
そうした結果しか残らないのなら、「復興」という言葉に対する深い不信ばかりが残る。
▽ 安倍政権は、高額の公共事業による復興は失敗に終わるという過去の教訓を全く分かっていない
当ウェブログが前々から指摘してきた通りであろう。
「元々、東日本大震災の被災地は過疎に苦しんでいた地域が多く、
多くの識者が当該地域からの人口流出が起きると予想しており
「復興」どころか「復旧」すら困難であることは予想されていた」
「加えて原発事故による壮烈な風評被害で
福島とその近隣の第一次産業・観光業が凄まじい打撃を受けており、
深刻な影響は後々まで残ることになる」
「知られているように被災地支援の熱意と活動は漸減するものである。
被災地での日常回復も個々の状況や資質によって「まだら模様」となり、
被災による打撃が甚大であった人々、復興の動きに取り残された人々は
経済的にも心理的にもより苦しい状況に追い詰められつつある」
「寄付金でも「買って応援」でも彼らの苦境は改善されない。
まして、自民党が票田にカネをばら撒き、選挙に勝つための方便である
「国土強靭化」では復興が永遠に不可能なのは明白である。
(せいぜい彼ら利益共同体の「利権回復」でしかない)」
「陛下が震災の影響が色濃く残っている被災地の現状に心を痛め、
深い気遣いをされているのを聞いてしみじみと心打たれた後に、
安倍首相のいつもの空々しい言辞を聞いて猛然と怒りが込み上げてきた」
「復興が進んでいる一部の見た目の良い場所だけで物見遊山し、
震災が「新しいステージ」に入ったなどととんでもない嘘を吐く政治家は、
天皇陛下のお気持ちを踏みにじる叛逆者に限りなく近い」
「今、被災地は復興どころか復旧も不可能になりつつある。
それは様々な理由に基づくものだが、最大の理由の一つは安倍政権である」
「「国土強靭化」などと愚劣なプロパガンダを展開して
公共事業予算を全国津々浦々にバラ撒いたために
被災地に向かう筈の資材も労働者も一気に分散し、コストも高騰した」
「自民党のお家芸である業界買収策の余波で、
ただでさえ困難な復興が遅れに遅れ、
自民党と癒着している建設業界が優先するのは「ハコモノ」である。
生活再建は業界に及ぼす恩恵が少ないので後回しにされる」
「このようなことは、自民党の通弊として、
これまでの「実績」から見て分かり切った話だった」
「権力の監視どころか「権力の犬」になっている御用メディアは恥さらしである。
こうした被災地の実情を知っていたら、「新しいステージ」が嘘八百である位はすぐ分かる筈だ」
「口ではいいことを言うが、相変わらず中身が伴っていない安倍首相。
状況がかなり良い場所ばかり視察し、子供と一緒に写真に収まって
自分のイメージだけ良くしようとする魂胆が見え見えである」
「あのバラ撒き民主党よりも自民党は6兆円の予算を上積みしていた。
この巨額予算が、人口流出した被災地の巨大な建造物に化けたのである」
「震災復興がうまくいかなかったことは、この速報を見れば明白である。
安倍政権による「被害」はこれにとどまらない。
建設業ばかりに労働者が集中した被災地は、二度と立ち直れなくなる。
自前の産業を失い、産業が空洞化する。政治家に予算を求めて生きるしかなくなる」
「被災地には穏和な人が多く、支援を受けて感謝している。
だからはっきりと言わないのだが、本音は以下の通りだ。
「安倍首相は大嘘つきで、「新しいステージ」になど入っていない」
「安倍政権や自民党は、被災地よりも建設業界のために行動している」
「震災復興は失敗しており、復旧すら不可能になった」」
遠からず被災地での調査が行われるだろうから、
以上のような現実がはっきり示されるであろう。
▽ 地方で重要なのは「人」であり、土木建設で再生する自治体など存在しない
刻一刻と、「復興」という言葉が空しく響き、形骸化してゆくようになる。
「口だけ安倍政権が、経済ばかりか震災復興でも成果に乏しく、
寧ろ復興を妨害している様相が明らかになってきた」
「「被災地の復興に向けた取り組みを加速する」などとまた空々しい美辞麗句を語るが
映りの良い子供と一緒に御用メディアのテレビに映ってばかりで、
震災復興が思うように進んでいない苦い現実を誤摩化そうとしている」
「その見え透いた小細工も道理であり、人の少ない場所に巨大な土木工事ばかり進み、
自民党の票田である建設業界ばかりが儲かっているのが現実だからだ。
自民党の国土強靭化こそが震災復興を妨げる根源なのだから、誤摩化すしかない」
「国勢調査によれば、被災地の人口流出は加速している。
確かにインフラが失われてしまえば生活が困難になるから仕方のない面もあるが、
福島の深刻な人口減少をみれば、「復興に向けた取り組みを加速」などと大嘘をつくのは
とんでもない話であるばかりか、政権の重大な責任を認識すらしていない事実を示すものだ」
「また、岩手・宮城の人口減少トレンドは全く変わっていない。
「取り組みを加速」したつもりだけで、成果は乏しい低能の証拠であるのは明白だ」
確かに各所で素晴らしい支援活動や復興はあるが、
大勢は当ウェブログが指摘した通りの状況になりつつある。
↓ 参考
復興予算6兆円増額して人口減少が止まらず、安倍政権はもはや害悪 -「復興進んでいない」が住民の54%
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/d54f95e8d21729902e8ae49c5c25d54a
「震災で亡くなった人より震災後に移転した人が多い」- 安倍首相の言う「新しいステージ」は単なる妄想
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/3c13a5dbae5c3f0ac480048d45ffedf1
被災地の女性の貧困が深刻化、自営業者・パートの約7割が失業中 -「国土強靭化」で復興できる筈がない
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/af4ca12c6b88a24beb5dfa856ad6ee5f
▽ 元々被災地は、高齢化と人口減少によってコミュニティの維持にも問題を抱えていた
仮設で「いるだけ支援」=学生滞在、住人と交流―東日本大震災6年(時事通信)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017030700801&g=eqa
復興の中で、心打たれる活動は確かにある。
資金的な面で持続可能性がどうなのかという課題はあるが、
闇夜にも無数の星が輝くのと似て、未来に向けての種は
政治の凡庸や無策にも負けず芽を出している。
復興:「2020年度以降も」4割 42市町村長調査(毎日新聞)
http://mainichi.jp/articles/20170310/k00/00m/040/093000c.html
しかし、マクロとしての実態はこうだ。
矢張り「復興格差」が進んでおり、特に福島原発事故の悪影響が甚大である。
2020年に日本国民が東京五輪に束の間の熱狂を見せる時にも、
多くの被災地自治体は今と左程変わらない現実を痛感せざるを得なくなる。
社長「活動高い評価」=東京本社前で抗議集会も―東電(時事通信)
http://
対照的に、東電社長は意気軒昂である。
対社員の発言で対住民ではないということもあろうが、
被災地の現状を考えると相当暢気な内容である。
少なくとも、自分から「高い評価をいただいている」などと言い出さないのが常識だろう。
せめて「感謝」ならばまだ理解できるのだが、事故前と感覚が変わっていないのだろうか。
復興住宅:空室2割超…9市町 ニーズ変化、一般向けにも(毎日新聞)
http://mainichi.jp/articles/20170310/k00/00m/040/095000c.html
被災者は家族状況や仕事によっても事情が大きく異なるし、
歳月とともに考え方も変わってくるので復興住宅は判断の難しいところであるが、
うまくいっているようにはなかなか見えない。空室率4割というのは「失敗」であろう。
地震大国日本においては、後世の教訓となりそうな状況だ。
投入した兆円規模の予算にもかかわらず
東日本大震災の被災地復興ははかばかしくない。
これも大方の予想通りであろう、
カネをいくら投入して公共事業を行っても、かつての生活が戻ってくる筈がないし
被災地には元々人口流出・減少が続いていた地域が多いこと、
そして福島原発事故は不可逆的かつ長年に及ぶ悪影響を与えていることから、
復興が容易でないことは初めから分かっていたことなのだが。
軽々しく大言壮語した安倍首相と、
社員に対して「高く評価されている」と豪語する東電社長の言葉が、
かつての暮らしを取り戻せない被災地の現状の前で
白々しく響くだけなのは至極当然のことと言える。
このままだと、建設業への降って湧いた特需と
仙台など一部の震災バブルに終わってしまいかねない。
多くの人々の命が失われ、コミュニティと生活が破壊された末に
そうした結果しか残らないのなら、「復興」という言葉に対する深い不信ばかりが残る。
▽ 安倍政権は、高額の公共事業による復興は失敗に終わるという過去の教訓を全く分かっていない
 | 『震災復興 欺瞞の構図』(原田泰) |
当ウェブログが前々から指摘してきた通りであろう。
「元々、東日本大震災の被災地は過疎に苦しんでいた地域が多く、
多くの識者が当該地域からの人口流出が起きると予想しており
「復興」どころか「復旧」すら困難であることは予想されていた」
「加えて原発事故による壮烈な風評被害で
福島とその近隣の第一次産業・観光業が凄まじい打撃を受けており、
深刻な影響は後々まで残ることになる」
「知られているように被災地支援の熱意と活動は漸減するものである。
被災地での日常回復も個々の状況や資質によって「まだら模様」となり、
被災による打撃が甚大であった人々、復興の動きに取り残された人々は
経済的にも心理的にもより苦しい状況に追い詰められつつある」
「寄付金でも「買って応援」でも彼らの苦境は改善されない。
まして、自民党が票田にカネをばら撒き、選挙に勝つための方便である
「国土強靭化」では復興が永遠に不可能なのは明白である。
(せいぜい彼ら利益共同体の「利権回復」でしかない)」
「陛下が震災の影響が色濃く残っている被災地の現状に心を痛め、
深い気遣いをされているのを聞いてしみじみと心打たれた後に、
安倍首相のいつもの空々しい言辞を聞いて猛然と怒りが込み上げてきた」
「復興が進んでいる一部の見た目の良い場所だけで物見遊山し、
震災が「新しいステージ」に入ったなどととんでもない嘘を吐く政治家は、
天皇陛下のお気持ちを踏みにじる叛逆者に限りなく近い」
「今、被災地は復興どころか復旧も不可能になりつつある。
それは様々な理由に基づくものだが、最大の理由の一つは安倍政権である」
「「国土強靭化」などと愚劣なプロパガンダを展開して
公共事業予算を全国津々浦々にバラ撒いたために
被災地に向かう筈の資材も労働者も一気に分散し、コストも高騰した」
「自民党のお家芸である業界買収策の余波で、
ただでさえ困難な復興が遅れに遅れ、
自民党と癒着している建設業界が優先するのは「ハコモノ」である。
生活再建は業界に及ぼす恩恵が少ないので後回しにされる」
「このようなことは、自民党の通弊として、
これまでの「実績」から見て分かり切った話だった」
「権力の監視どころか「権力の犬」になっている御用メディアは恥さらしである。
こうした被災地の実情を知っていたら、「新しいステージ」が嘘八百である位はすぐ分かる筈だ」
「口ではいいことを言うが、相変わらず中身が伴っていない安倍首相。
状況がかなり良い場所ばかり視察し、子供と一緒に写真に収まって
自分のイメージだけ良くしようとする魂胆が見え見えである」
「あのバラ撒き民主党よりも自民党は6兆円の予算を上積みしていた。
この巨額予算が、人口流出した被災地の巨大な建造物に化けたのである」
「震災復興がうまくいかなかったことは、この速報を見れば明白である。
安倍政権による「被害」はこれにとどまらない。
建設業ばかりに労働者が集中した被災地は、二度と立ち直れなくなる。
自前の産業を失い、産業が空洞化する。政治家に予算を求めて生きるしかなくなる」
「被災地には穏和な人が多く、支援を受けて感謝している。
だからはっきりと言わないのだが、本音は以下の通りだ。
「安倍首相は大嘘つきで、「新しいステージ」になど入っていない」
「安倍政権や自民党は、被災地よりも建設業界のために行動している」
「震災復興は失敗しており、復旧すら不可能になった」」
遠からず被災地での調査が行われるだろうから、
以上のような現実がはっきり示されるであろう。
▽ 地方で重要なのは「人」であり、土木建設で再生する自治体など存在しない
 | 『奇跡の村 地方は「人」で再生する』(相川俊英,集英社) |
刻一刻と、「復興」という言葉が空しく響き、形骸化してゆくようになる。
「口だけ安倍政権が、経済ばかりか震災復興でも成果に乏しく、
寧ろ復興を妨害している様相が明らかになってきた」
「「被災地の復興に向けた取り組みを加速する」などとまた空々しい美辞麗句を語るが
映りの良い子供と一緒に御用メディアのテレビに映ってばかりで、
震災復興が思うように進んでいない苦い現実を誤摩化そうとしている」
「その見え透いた小細工も道理であり、人の少ない場所に巨大な土木工事ばかり進み、
自民党の票田である建設業界ばかりが儲かっているのが現実だからだ。
自民党の国土強靭化こそが震災復興を妨げる根源なのだから、誤摩化すしかない」
「国勢調査によれば、被災地の人口流出は加速している。
確かにインフラが失われてしまえば生活が困難になるから仕方のない面もあるが、
福島の深刻な人口減少をみれば、「復興に向けた取り組みを加速」などと大嘘をつくのは
とんでもない話であるばかりか、政権の重大な責任を認識すらしていない事実を示すものだ」
「また、岩手・宮城の人口減少トレンドは全く変わっていない。
「取り組みを加速」したつもりだけで、成果は乏しい低能の証拠であるのは明白だ」
確かに各所で素晴らしい支援活動や復興はあるが、
大勢は当ウェブログが指摘した通りの状況になりつつある。
↓ 参考
復興予算6兆円増額して人口減少が止まらず、安倍政権はもはや害悪 -「復興進んでいない」が住民の54%
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/d54f95e8d21729902e8ae49c5c25d54a
「震災で亡くなった人より震災後に移転した人が多い」- 安倍首相の言う「新しいステージ」は単なる妄想
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/3c13a5dbae5c3f0ac480048d45ffedf1
被災地の女性の貧困が深刻化、自営業者・パートの約7割が失業中 -「国土強靭化」で復興できる筈がない
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/af4ca12c6b88a24beb5dfa856ad6ee5f
▽ 元々被災地は、高齢化と人口減少によってコミュニティの維持にも問題を抱えていた
 | 『地方消滅 - 東京一極集中が招く人口急減』(増田寛也,中央公論新社) |
仮設で「いるだけ支援」=学生滞在、住人と交流―東日本大震災6年(時事通信)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017030700801&g=eqa
”高齢化が進む福島県の応急仮設住宅で、大学生が空き部屋に一定期間滞在し、避難者と交流する「いるだけ支援」が行われている。自治会の解散や退去者の増加でコミュニティーの崩壊が懸念される中、避難者からは「団地全体に活気が生まれた」と喜ぶ声が聞かれる。
東京電力福島第1原発事故後、福島県浪江町の住民が避難する福島市の「北幹線第一仮設住宅」には、福島大1年の高坂夏美さん(19)と2年の佐々木翔太郎さん(20)が滞在する。特別の技能や資格を持たない2人が続けているのは、住民との日常的な交流だ。
〔中略〕
佐々木さんは「被災地のために何かしたい」と思い、支援に参加。大学近くの寮に住んでいるため、通学時間は片道40~50分と延びたが、「苦労はない。いろいろな住民の方と知り合えたことがうれしい」と話す。住人の鎌田豊美さん(68)は「若い人たちがイベントなどを手伝ってくれ、大変助かる」と感謝した。
「いるだけ支援」を担うのは福島大の学生団体。2015年6月から取り組みを開始。福島、二本松両市の仮設住宅各1カ所に延べ計16人の学生を送り込み、2~4カ月間一緒に暮らした。代表で4年の久保香帆さん(22)によると、健康上の理由で外出できない人を見つけ、生活支援相談員の巡回対象に加えてもらうなど、孤独死防止にも一役買っている。
ただ、取り組みは福島大に限られている。同大の鈴木典夫教授(地域福祉)は「大学だけで行うのは難しい。NPO法人などにも積極的に参加してもらいたい」と訴えた。”
復興の中で、心打たれる活動は確かにある。
資金的な面で持続可能性がどうなのかという課題はあるが、
闇夜にも無数の星が輝くのと似て、未来に向けての種は
政治の凡庸や無策にも負けず芽を出している。
復興:「2020年度以降も」4割 42市町村長調査(毎日新聞)
http://mainichi.jp/articles/20170310/k00/00m/040/093000c.html
”東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県、宮城県、福島県の沿岸部計42市町村の首長に毎日新聞がアンケートしたところ、国が復興のめどとし、東京オリンピック・パラリンピックも開催される2020年度までに復興事業を終わらせる見込みが「ない」と答えた首長が約4割に上った。大半が東京電力福島第1原発事故で避難を強いられた福島県の首長で、原発事故からの復興が進んでいないことが浮き彫りになった。
国は2011年度からの5年間を「集中復興期間」、16年度からの5年間を「復興・創生期間」と位置づけ、震災10年となる20年度までに総額32兆円を投じて復興事業をほぼ終わらせ、復興庁も廃止する方針。その後も福島を中心に支援する姿勢を示すが、具体的な予算措置は未定だ。
〔中略〕
20年度までに復興事業が終わる見込みが「ない」と回答したのは、岩手2人、宮城1人に対し、福島は避難指示区域の自治体を含む13人。福島で「ある」と答えたのは新地町だけで、相馬市は「わからない」とした。終了できない理由について福島では大半の首長が原発事故の影響を挙げた。浪江町は「(今後)3年程度で復興事業が終わるとは思えない」とした上で「津波被災地と原発被災地では復興の速度が明らかに異なる」と指摘。帰還困難区域が町の96%を占める双葉町は「復興事業自体が始まっていない」とし、解除された川内村も「急激な人口減少と超少子高齢化」に直面していると訴えた。
岩手では陸前高田市と大槌町、宮城では山元町が「ない」と回答。陸前高田市は「新庁舎建設が21年度までかかる」ことを、大槌町は土地区画整理事業の遅れなどをそれぞれ理由に挙げた。山元町は「集団移転先でのコミュニティー形成や心の復興」などに長い歳月が必要だと訴えた。【栗田慎一】”
しかし、マクロとしての実態はこうだ。
矢張り「復興格差」が進んでおり、特に福島原発事故の悪影響が甚大である。
2020年に日本国民が東京五輪に束の間の熱狂を見せる時にも、
多くの被災地自治体は今と左程変わらない現実を痛感せざるを得なくなる。
社長「活動高い評価」=東京本社前で抗議集会も―東電(時事通信)
http://
”東京電力福島第1原発事故の発生から6年となるのに合わせて、広瀬直己社長は11日、同原発構内入り口近くにある新事務本館で訓示を行い、福島県内での社員の活動について「大変高い評価をいただいている」と述べた。
広瀬社長は「この6年で発電所(福島第1原発)は見違えるようになったと感じている」と廃炉作業の進展に手応えを示した。その上で、「一日でも早く地域の皆さんに古里に戻ってきてもらえるように頑張っていこう」と呼び掛けた。”
対照的に、東電社長は意気軒昂である。
対社員の発言で対住民ではないということもあろうが、
被災地の現状を考えると相当暢気な内容である。
少なくとも、自分から「高い評価をいただいている」などと言い出さないのが常識だろう。
せめて「感謝」ならばまだ理解できるのだが、事故前と感覚が変わっていないのだろうか。
復興住宅:空室2割超…9市町 ニーズ変化、一般向けにも(毎日新聞)
http://mainichi.jp/articles/20170310/k00/00m/040/095000c.html
”東日本大震災や東京電力福島第1原発事故の被災者が入居する災害公営住宅(復興住宅)がある岩手、宮城、福島3県の計54市町村のうち、9市町で空室率が2~4割に上ることが分かった。この9市町を含む18市町村は1割以上だった。復興の長期化などで被災者の住宅ニーズが変化したことが大きな要因とみられる。
〔中略〕
毎日新聞は岩手、宮城各県がまとめた各自治体の入居状況(1月末現在)の提供を受けた。福島県では、住宅を管理する県と各自治体に取材した。その結果、54市町村の計2万2686戸のうち、7%(1643戸)が空室だった。
宮城県塩釜市は空室率30%。80戸以上で被災者が入居する見込みがない。市復興推進課は「復興が長引く間に自宅を再建する人が増えた」と話す。同県気仙沼市や南三陸町も70~80戸で入居の見通しが立たない。岩手県陸前高田市は空室率が22%。市建設課は「高台造成が続いており、一度は復興住宅入居を表明したものの、自宅再建するか迷って入居に踏み切れない人がいる」と話す。
一方、岩手県では126戸が、宮城県でも269戸が死去や引っ越しで退去しており、空室増加につながっている。
公営住宅法は、災害発生から3年たつと被災者以外の復興住宅入居も認めている。東日本大震災は復興が長期化したため3年経過後も入居を認めてこなかったが、2015年秋、国が容認する見解を示した。
岩手県岩泉町、田野畑村、宮城県大崎市、南三陸町、涌谷町が既に一般向けに貸しており、岩手県大船渡市や宮城県気仙沼市など計5市町は来年度にも貸し始める。
福島県では、被災者以外に貸している自治体はない。〔中略〕【金森崇之】 ”
被災者は家族状況や仕事によっても事情が大きく異なるし、
歳月とともに考え方も変わってくるので復興住宅は判断の難しいところであるが、
うまくいっているようにはなかなか見えない。空室率4割というのは「失敗」であろう。
地震大国日本においては、後世の教訓となりそうな状況だ。