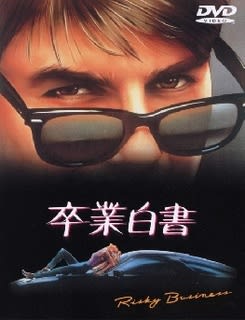贅沢なキャスティングにも関わらず、ほとんど機能していない。設定は絵空事で、展開は説得力を欠く。加えて余計なサブ・ストーリーが全体的な作劇を不格好なものにしてしまった。聞けば原作は舞台作品とのことだが、演劇における方法論を工夫も無く移設した居心地の悪さも感じられる。いずれにしろ、評価出来ない内容だ。
茨城県大洗町でタクシー会社を営む稲村家の母こはると3人の子供は、父親の酷い暴力に苦しんでいた。ある晩、耐えられなくなったこはるは夫を殺害する。そして子供たちに15年後の再会を誓って警察に出頭した。それからちょうど15年経った日に、こはるは家に帰ってくる。上京していた次男も加えて久々に一家が揃うことになったが、3人の子供はトラウマを抱えたまま幼い頃の夢とはまるで違う人生を歩んでいた。そんな中、堂下という男が新たにタクシー運転手として入社してくる。一見真面目そうだが、何やら訳ありの様子だ。やがて堂下は大きなトラブルを引き起こす。
こはるが犯した罪は情状酌量の余地が大きく、執行猶予抜きの10年以上の刑になることは、まずあり得ない。服役中に子供たちや親族が面会に行った形跡が無いのも、おかしなことだ。またこはるは出所後も何年も各地を転々としていたらしいが、その理由も“気持ちの整理を付けたいから”という曖昧なものである。
事件が起こった日から一家と会社は誹謗中傷に曝されるが、脅迫罪と威力業務妨害に問われる案件ながら、対策を講じた様子は見られない。離婚寸前の長男の境遇はイマイチ釈然としないし、さらには作家志望だった次男は、あろうことか身内の恥を全面開示させて小説のネタにしようとする。斯様に非合理的なモチーフが並べられた上に、堂下の突飛な行動が文字通り取って付けたように挿入される。
3人兄妹には屈託があったはずだが、その内面は深く描かれない。こはるや堂下も同様だ。その代わり、ヘンに説明的な(聞き取りにくい)セリフが声高に飛び交う。明らかな演劇的なメソッドだが、映画手法として昇華されていないばかりか、セリフの中身も要領を得ない。社員の一人でこはるの友人でもある柴田弓のエピソードに至っては、存在意義さえ見えない有様だ。
白石和彌の演出はどうもピリッとせず、平板な仕事ぶり。こはる役の田中裕子をはじめ、佐藤健に鈴木亮平、松岡茉優、筒井真理子、韓英恵、佐々木蔵之介など、配役は豪華。しかしながら、どのキャラクターもリアリティに欠け、血が通っていない。終わって、釈然としない気分で劇場を後にした。オススメできないシャシンだ。