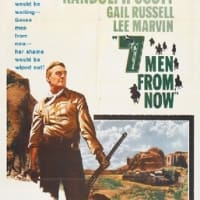今年で音楽用CDが出来てから25年経つという。25年前の82年8月17日、蘭フィリップス社が世界初のコンパクト・ディスクを西ドイツ・ハノーヴァー近郊の工場で製造。最初にプレスされたのはABBAの「The Visitors」だったらしい。同社のプレーヤー第一号機「CD100(写真参照)」をはじめ、各社のCDプレーヤーは同年末月に日本でも発売され、同時に150タイトルほどが発表された。それ以後、CDの世界での累計販売枚数は2千億枚に及んでいるという。
私が初めて聴いたCDプレーヤーが、その82年末に出た製品群であった。期待して接したのだが、印象は最悪。ギスギスした、それでいて情報量は少なめの、要するに“ボケた音”でしかなかった。少なくとも、まともなアナログプレーヤーで鳴らすレコードの音の足元にも及ばない低劣なものである。ところが、新しいメディアというものはイノベーションも早いのか、翌83年から発売されるようになった第二・第三世代のプレーヤーは格段に聴きやすい音になった。第一世代のプレーヤーはカセットデッキと同じようにCDを縦に装着する形式が多かったが、第二・第三世代からは現在と同じようにディスクをトレイに横向きに載せて装着するシステムになり、たぶんこの方が動作中のディスクが安定するからという理由もあったのかもしれない。で、我が家にCDプレーヤーが入ったのは84年からである。
そのプレーヤー(ONKYO製)は定価が14万円ほどだったと記憶しているが、それでも当時の相場では安価な部類であった。その頃で一番安いのがSONYやYAMAHAの10万円弱の製品で、一般ピープルが気軽に買えるような機器ではなかったのだ。
その状況が一変したのが85年である。この年、蘭フィリップス社がベルギーの工場で生産し、MARANTZブランドで売り出したCD-34という画期的な機種が出現する。価格は誰でも手が出せる59,800円。幅が32センチという今で言うミニコンポのサイズでありながら7kgもの自重で、振動対策にも気を遣ったガッチリとした構造を持つ、オーディオマニアも納得する仕様を誇った。当然の事ながら、この商品は爆発的に売れ、他のメーカーも一斉にその価格帯に追随したので、CDプレーヤーは音楽ファンの必需品としてまたたく間に認知されることになる。そしてはじめは一枚3千5百円、中には4千円以上のものもあったCDソフトの小売価格も、リーズナブルな線に落ち着いていく。
マニアの間では“CDの出現が我が国のピュア・オーディオの落日をもたらした”との定説があるらしいが、私はそうは思わない。もちろん、よく調整されたアナログプレーヤーで鳴らすレコードの音は今でもヘタなCDの音を凌駕することが少なくない。しかし、一般ピープルがそういうまともなアナログプレーヤーを入手することは、CDの出現前でさえ難しいことだったのだ。対してCDプレーヤーはディスクを入れてスイッチを押せば、レコードみたいな傷や静電気によるノイズもなく、内周で音が劣化することもなく、A面が終わったらディスクをひっくり返す手間もなく、どんな安いプレーヤーでも最低限の音は出てくるという意味で、インターフェースの簡便化による音楽ファンの裾野を広げた功績は大きいと思う。
当初、周波数特性が中途半端(高域が20KHzまで)である点が取り沙汰され、私もそれは問題だと思ったのだが、通常CDでもプレーヤーを追い込めば素晴らしい音が出てくることは実証済みだし、何よりスペック面をあげつらうより先に“取り扱いが便利”ということで膨大な数のソフトの量が流通してしまったことで“勝負あり”になってしまったのだ。
次世代音楽ソフトと言われたSACDやDVDオーディオがさっぱり普及しないのも、現行CDと比べてインターフェース面で変わらない点が原因である。そもそもソフトの数ではSACDやDVDオーディオは微々たるものだから、それらが主流になるはずもないのである。ちなみにDVDオーディオはすでに絶滅状態、SACDも撤退の噂を聞いている。
さて、本当に日本のピュア・オーディオの落日をもたらしたものは、CDの出現ではなくインターネットである。その要因は、アナログレコードもCDも、曲がりなりにもマスターテープの音を忠実にリスナーに届けようという意図で製作されたものであるのに対し、ネットからのダウンロードは、当初から圧縮されたスカスカの音である点だ。つまり“安かろう悪かろう”の商品が大手を振ってまかり通っているわけだ。しかも、CDとは違ってショップに行ってディスクを購入する必要もない。簡便性において他のどのメディアよりも勝っている。
“悪貨が良貨を駆逐する”という状況が音楽ソフトの世界でも起こっているわけで、しかも圧縮されたソースが幅広く流通するのならば最初から圧縮されてもいいようなスカスカの音造りをした楽曲しか送り手がリリースしないのも道理だ。昨今のJ-POPの絶望的なまでの録音の悪さ(まあ、すべてではないけど ^^;)もそれで頷ける。
欧米でも当然ネットからの音楽ソース提供は大きなトレンドになっているハズだが、ピュア・オーディオが大きく斜陽になったという話は聞かない。それどころか、次々と新しいメーカーが紹介されている。これは結局、音楽そのものが“文化”として根付いているかどうかの違いであろう。圧縮音源ではとても聴けないような“まっとうな音楽”を愛する者の絶対数が、日本と欧米とでは大きな差があるということだ。
まあ、別にネット配信が主流になろうと、音楽ファンにとっては関係ない。どんな音を好もうと、個人の勝手だ。しかし、それによりCDの小売市場が縮小してしまうのは、困る。CDはネット通販でも入手できるが、やっぱり現物を手に取って見たいし、話題の新譜をちゃんとした環境で心ゆくまで試聴したい。
CDが誕生して25年。たぶん“店で売られるパッケージ音楽ソフト”としてはCDが最後の形態になるだろう。いずれにしろ、大きな曲がり角に来ていることは確かだ(←何だか、ありがちな締めになって恐縮至極 ^^;)。