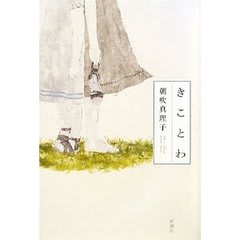葉山の海沿いにある別荘で、幼い日をともに過ごした貴子と永遠子。時は経ち、長い間疎遠になっていた二人は別荘の解体を機に再会する。記憶と現実とが交差する心理の動きを追う、第144回芥川賞受賞作。
作者のルックスと出自こそ話題になったが本書の評判は良くなく、たとえばAmazonのカスタマーレビュー欄なんかでは酷評が目立つ。しかし、私はそれほどヒドい小説だとは思わない。少なくとも、質的な低落傾向が顕著な昨今の芥川賞作品の中ではマシな部類である。
本作の売り物は、内面と時間経過との“非・シンクロニシティ”だと思う。人間の意識というものは、時系列的に配備された因果性とは無関係に変化する。その“移ろい”を散文的に綴った本書に、明確なドラマ性を求めること自体“お門違い”であろう。くだんのカスタマレビューの書き手の多くがそのあたりを分かっておらず、単に“物語性がない。退屈だ”みたいな、それこそ退屈極まりないコメントを羅列しているのには、苦笑せざるを得ない。
ただし、このような形式の小説は書き手に多大なテクニックを要求する。語彙も表現力も乏しい者が内面描写だけを書き連ねようとしても、ただの茶番に終わるのは言うまでもない。その点この作者は、非凡な文章構築力で巧みにハードルをクリアしてくる。冒頭の“永遠子は夢をみる。貴子は夢をみない”という、まさに読み手を夢路に誘うようなフレーズから始まり、優雅な身のこなしで対象から付かず離れずのインターバルを取りつつ、パステル調の美文を次から次へと繰り出してくるあたりは感心した。
ただし、この小説に難点が全くないかというと、それは違う。まず人間関係が分かりにくい。ヒロイン二人のそれぞれの家族の状況を把握するのに、かなり難儀した。そして何より、このような作風が果たして長続きするのかという、危惧の念を抱いたことも事実。高踏的なタッチは、陳腐化するのも早い。今後の展開を注視したいところだ。
あと関係ないが、案外これは映画化してみると面白いのではないかと思う。近年「かもめ食堂」とか「プール」とかいった“癒し系もどき映画”が散見されるが、そういうシャシンとは一線を画す硬質かつ静的な魅力のある作品に仕上がるかもしれない。もちろん、それなりの手腕を持った映像作家がメガホンを取ることが必須条件だ。