関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。
関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行
■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-0(導入編)
この記事、アクセスしにくくなっていたのでアゲてみます。
なお、現在、札所0番の愛鷹山 三明寺(さんみょうじ)様(沼津市大岡4051)が実質的な事務局対応(専用納経帳の頒布など)をされていますので、発願にトライされる方はまずはこちらの参拝をおすすめします。
→ 詳細はこちら。
-------------------------
2022/02/13に記事は一応完結していますが、札所の追加・変更があったのでリニューアルUPします。
伊豆八十八ヶ所霊場は、江戸時代開創と伝わる伊豆全域に広がる弘法大師霊場です。
ながらく巡拝者は途絶えていたものとみられますが、昭和50年に伊豆霊場振興会が設立され復興が始まりました。
初番発願所は伊豆の国市四日町の長徳寺(以前は伊豆市田沢の嶺松院)、八十八番結願所は修禅寺および修禅寺奥の院。
全行程は460㎞で札所は伊豆半島全域に及びますが、とくに南伊豆町に多く立地しています。
この霊場の巡拝ガイドブック『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(監修:伊豆霊場振興会)を参考に、歴史をたどってみます。
伊豆八十八ヶ所霊場は、江戸時代から明治初期にかけて多くの巡拝者を迎えたとみられる歴史ある霊場です。
伊豆には弘法大師の逸話が多く伝わります。
弘法大師が唐に渡られる前後14年の間に訪れた「桂山の山寺」は修禅寺であったともいわれ、この地で弘法大師霊場が隆盛する素地は、往古からすでにあったとみることができます。
結願所の修禅寺(福地山修禅萬安禅寺)は、大同二年(807年)弘法大師による開創と伝わり、その後約470年間は真言宗寺院として栄えました。
鎌倉時代、中国から蘭渓道隆禅師が入山して臨済宗に改宗。
さらに室町時代の応永九年(1489年)には、韮山城主北条早雲が遠州から隆渓繁紹禅師を招いて曹洞宗に改宗しています。
修禅寺の影響が強いとみられるこの霊場では、当初真言宗で、のちに禅宗に改めた寺院が多くあります。
禅宗メインでありながら御本尊は多彩で、札所によっては密寺の雰囲気を色濃く残していることも、この霊場の個性であり魅力であるかと思います。
昭和に入って霊場は衰退し無住の札所も増えましたが、昭和40年代頃、伊豆在住の田上東平氏が第28番札所「大江院」に霊場の納経帳が残されていることを知り、昭和50年に伊豆霊場振興会を設立されて霊場の復興が始まりました。
田上氏は第6番札所「金剛寺」でも明治22年の日付の木版を発見、平成に入って第21番「龍澤寺」で天保十五年(1844年)と彫られた巡拝祈念碑がみつかり、少なくとも江戸時代には巡拝されていたという裏付けがなされました。
温泉地や観光地にある札所も多く、公式WebもUPされ、このところの御朱印ブームもあって近年、巡拝者が増えている模様。
~ 江戸時代より巡礼されていた伊豆八十八ヶ所霊場 長い沈黙から 今、まさに蘇る ~
(巡拝ガイド表紙より)
さらに2021年6月、伊豆八十八ヶ所霊場を熱海を起点として回る「熱海御朱印物語」が企画され、詳細なガイドが紹介されています。
「神社仏閣に参拝した証に頂くのが『御朱印』で、お遍路の様に、お経を納める事で頂くのが『納経印』と言います。御朱印という姿形は一緒でも意味は違います。まずは気軽に『御朱印』を集めながら、伊豆半島を楽しんでみませんか。」(同Webより)という趣意で、「御朱印」を納経や読経から切り離し、参加者を広げようという試みは賛否両論あるのかもしれませんが、時代に見合ったかたちなのかもしれません。(→ リリース紹介の記事)
巡拝はマイカー利用が楽ですが、伊豆半島全域をカバーしている東海バスで、公共交通機関を利用した巡拝コースが設定されています。
〔 東海バスのパンフ掲載地図 〕
※ 一部現況と異なる内容があります。

〔 札所一覧 〕
※ 一部現況と異なる内容あり。追って修正します。


2020年秋、数年がかりで結願しましたので、拝受した御朱印をご紹介します。
この霊場はほぼ2巡しており、専用納経帳のほか、ほとんどの札所で書入・印判の御朱印をいただいていますので両方ご紹介します。
伊豆八十八ヶ所霊場の専用納経帳は、デフォルトで揮毫の札所本尊、山号寺号などの揮毫が印刷されており、これに主印(三寶印、御寶印)と札所印、寺院印などの捺印をいただいて完成します。
ご不在の場合でも堂内に印が備えてあればセルフで捺印し、完成することができます。
霊場振興会では専用納経帳での巡拝を推奨されている模様で(詳細は→こちら)、専用納経帳巡拝の場合、印があるところは自分で捺せ、ご不在の場合、条件によっては後日授与対応していただけるので、御朱印をコンプリートされたい向きには専用納経帳がおすすめです。
筆者は専用納経帳を松崎で入手し、修善寺でも入手できる可能性がありますが、確実に入手するには通販での購入をおすすめします。(詳細は→こちら)、

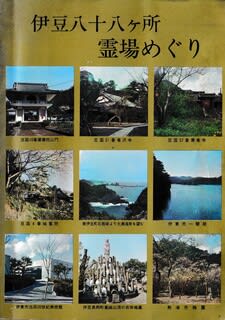
【写真 上(左)】 霊場ガイド-1
【写真 下(右)】 霊場ガイド-2


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 専用納経帳


【写真 上(左)】 パンフ類
【写真 下(右)】 チラシ
また、伊豆には伊豆横道(よこどお)三十三観音霊場という観音霊場もあります。
こちらは、伊豆に流されていた源頼朝公が源氏再興を決意し、その成就を祈りつつ「三十三観音」を巡ったのが始まりと伝わる古い霊場です。
いくつかの札所は伊豆八十八ヶ所と重複していますので、こちらについても御朱印をご紹介します。
また、札所で拝受したその他の御朱印についても併せてご紹介していきます。
せっかくなので、伊豆半島の霊場・札所について、その概要をみてみます。
【伊豆半島と霊場・札所】
伊豆半島は人口密度が高く、寺院も多かったためか複数の霊場が開創されています。
口伊豆(三島・沼津)方面では駿河一国観音霊場(駿河三十三観音)が現役。
古い霊場では御厨観音横道札所、駿豆両国横道三十三観音霊場、また、静岡梅花観音霊場、駿河一国百地蔵尊霊場などの札所も点在し、一部札所で御朱印を授与されています。
中伊豆には伊豆中道三十三観音霊場、中伊豆観音札所、伊豆長岡温泉七福神、伊豆天城七福神などの札所があり、こちらも一部ですが御朱印が授与されています。
西・南・東伊豆では、現役霊場として伊豆横道三十三観音霊場、円覚寺百観音霊場、伊豆国(下田南伊豆)七福神、稲取八ヶ寺めぐり、伊東温泉七福神などがあり、多くの札所で御朱印が授与されています。
とくに稲取や松崎エリアは御朱印にちなんだ観光振興に積極的で、御朱印関連イベントがしばしば企画されている模様。
〔稲取・松崎の御朱印企画のパンフ〕

現況不明の霊場に、熱海三弘法大師霊場、伊豆二十一ヶ所霊場、熱海六観音霊場、伊豆伊東六阿弥陀霊場などがあり、熱海三弘法大師霊場と熱海六観音霊場の札所はだいたい伊豆八十八ヶ所と重複していますが、伊豆二十一ヶ所霊場と伊豆伊東六阿弥陀霊場は伊東市内の地域霊場的な性格で、伊豆八十八ヶ所との札所重複は少なくなっています。
伊豆は日蓮宗・法華宗寺院も多く、多くの寺院で御首題あるいは御朱印を授与されています。
伊豆は、御朱印授与神社は比較的少ないエリアですが、それでも↑のとおり授与寺院多数で目移りします。
とくに南伊豆は東京方面からの交通の便がよくないので、せっかく来たのだからと、ついつい無理をしがちです。
しかし、伊豆八十八ヶ所霊場の巡拝じたいがかなりハードなので、他札所御朱印も一気にゲットとなるとおそらく時間切れ再訪という状況に陥ります(笑)
伊豆八十八ヶ所霊場の札所はしみじみと落ち着いたいいお寺さまが多いので、ここは欲張らずに八十八ヶ所に的を絞って回るのがベターかもしれません。
無住のお寺も多くなかなか手ごわいですが、伊豆の温泉めぐりと併せ、数年がかりでじっくり回っていくのも面白いかと思います。
なお、温泉レポをUPしているお湯については、適宜リンクを貼るかたちでこちらもご案内していきます。(休業中・廃業の施設を含みます。ご注意願います。)
ボリュームがあるので、時間をかけて連載でUPしていきます。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
第0番 愛鷹山 三明寺(沼津市大岡)
(旧)第1番 観富山 嶺松院(伊豆市田沢)
第1番 瑞応山 長徳寺(伊豆の国市四日町)
第2番 天城山 弘道寺(伊豆市湯ケ島)
第3番 妙高山 最勝院(伊豆市宮上)
第4番 泉首山 城富院(伊豆市城)
第5番 吉原山 玉洞院(伊豆市牧之郷)
第6番 大澤山 金剛寺(伊豆市大沢)
第7番 東嶽山 泉龍寺(伊豆市堀切)
第8番 養加山 益山寺(伊豆市堀切)
第9番 引摂山 澄楽寺(伊豆の国市三福)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
第10番 長谷山 蔵春院(伊豆の国市田京)
第11番 天與山 長源寺(伊豆の国市中)
第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(伊豆の国市古奈)
第13番 巨徳山 北條寺(伊豆の国市南江間)
第14番 龍泉山 慈光院(伊豆の国市韮山多田)
第15番 華頂峰 高岩院(伊豆の国市奈古谷)
第16番 金寶山 興聖寺(函南町塚本)
第17番 明王山 泉福寺(三島市長伏)
第18番 龍泰山 宗徳院(三島市松本)
第19番 君澤山 連馨寺(三島市広小路町)
第20番 福翁山 養徳寺(函南町平井)
第21番 圓通山 龍澤寺(三島市沢地)
第22番 龍泉山 宗福寺(三島市塚原新田)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
第23番 日金山 東光寺(熱海市伊豆山)
第24番 走湯山 般若院(熱海市伊豆山)
第25番 護国山 興禅寺(熱海市桜木町)
第26番 根越山 長谷寺(熱海市網代)
第27番 稲荷山 東林寺(伊東市馬場町)
第28番 伊雄山 大江院(伊東市八幡野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
第29番 大川山 龍豊院(東伊豆町大川)
第30番 金澤山 自性院(東伊豆町奈良本)
第31番 来宮山 東泉院(東伊豆町白田)
第32番 稲取山 善應院(東伊豆町稲取)
第33番 見海山 来迎院 正定寺(東伊豆町稲取)
別格旧第31番 宝林山 称念寺(河津町浜)
第34番 千手山 三養院(河津町川津筏場)
(旧)第35番 鳳儀山 栖足寺(河津町谷津)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
第35番 天城山 慈眼院(河津町梨本)
第36番 長運山 乗安寺(河津町谷津)
第37番 玉田山 地福院(河津町縄地)
第38番 興國山 禅福寺(下田市白浜)
第39番 西向山 観音寺(下田市須崎)
第40番 瑞龍山 玉泉寺(下田市柿崎)
第41番 富巖山 天気院 海善寺(下田市一丁目)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
第42番 大浦山 長楽寺(下田市三丁目)
第43番 乳峰山 大安寺(下田市四丁目)
第44番 湯谷山 廣台寺(下田市蓮台寺)
第45番 三壺山 向陽院(下田市河内)
第46番 砥石山 米山寺(下田市箕作)
第47番 保月山 龍門院(下田市相玉)
第48番 婆娑羅山 報本寺(下田市加増野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
第49番 神護山 太梅寺(下田市横川)
第50番 古松山 玄通寺(南伊豆町一條)
第51番 青谷山 龍雲寺(南伊豆町青市)
第52番 少林山 曹洞院(下田市大賀茂)
第53番 佛谷山 寶徳院(下田市吉佐美)
第54番 浦岳山 長谷寺(下田市田牛)
第55番 飯盛山 修福寺(南伊豆町湊)
第56番 養珠山 正善寺(南伊豆町手石)
第57番 東海山 青龍寺(南伊豆町手石)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
第58番 稲荷山 正眼寺(南伊豆町石廊崎)
(石室神社)(南伊豆町石廊崎)
第59番 瑞雲山 海蔵寺(南伊豆町入間)
第60番 龍燈山 善福寺(南伊豆町妻良)
第61番 臥龍山 法泉寺(南伊豆町妻良)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9
第62番 石屏山 法伝寺(南伊豆町二條)
第63番 五峰山 保春寺(南伊豆町加納)
第64番 金嶽山 慈雲寺(南伊豆町下賀茂)
第65番 田村山 最福寺(南伊豆町上賀茂)
第66番 波次磯山 岩殿寺(南伊豆町岩殿)
第67番 太梅山 安楽寺(南伊豆町上小野)
第68番 廬岳山 東林寺(南伊豆町下小野)
第69番 塔峰山 常石寺(南伊豆町蛇石)
第70番 医王山 金泉寺(南伊豆町子浦)
第71番 翁生山 普照寺(南伊豆町伊浜)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10
第72番 黒崎山 禅宗院(松崎町石部)
第73番 霊鷲山 常在寺(松崎町岩科南側)
第74番 嵯峨山 永禅寺(松崎町岩科北側)
第75番 岩科山 天然寺(松崎町岩科北側)
第76番 清水山 浄泉寺(松崎町松崎)
第77番 文覚山 圓通寺(松崎町宮内)
第78番 祥雲山 禅海寺(松崎町江奈)
第79番 曹源山 建久寺(松崎町建久寺)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11
第80番 萬法山 帰一寺(松崎町船田)
第81番 富貴野山 宝蔵院(松崎町門野)
第82番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
第83番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
第84番 正島山 法眼寺(西伊豆町仁科)
第85番 満行山 航浦院(沼津市西浦江梨)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-12
(旧)第85番 授寶山 大聖寺(西伊豆町安良里)
第86番 吉祥山 安楽寺(伊豆市土肥)
第87番 専修山 大行寺(沼津市戸田)
第88番 奥の院 正覚院(伊豆市修善寺)
第88番 福地山 修禅寺(修禅萬安禅寺)(伊豆市修善寺)
【 BGM 】
■ by your side - Wise feat. Nishino Kana
■ Waiting For Love feat.Noa - 中村舞子
■ SWEET MEMORIES 松田 聖子
なお、現在、札所0番の愛鷹山 三明寺(さんみょうじ)様(沼津市大岡4051)が実質的な事務局対応(専用納経帳の頒布など)をされていますので、発願にトライされる方はまずはこちらの参拝をおすすめします。
→ 詳細はこちら。
-------------------------
2022/02/13に記事は一応完結していますが、札所の追加・変更があったのでリニューアルUPします。
伊豆八十八ヶ所霊場は、江戸時代開創と伝わる伊豆全域に広がる弘法大師霊場です。
ながらく巡拝者は途絶えていたものとみられますが、昭和50年に伊豆霊場振興会が設立され復興が始まりました。
初番発願所は伊豆の国市四日町の長徳寺(以前は伊豆市田沢の嶺松院)、八十八番結願所は修禅寺および修禅寺奥の院。
全行程は460㎞で札所は伊豆半島全域に及びますが、とくに南伊豆町に多く立地しています。
この霊場の巡拝ガイドブック『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(監修:伊豆霊場振興会)を参考に、歴史をたどってみます。
伊豆八十八ヶ所霊場は、江戸時代から明治初期にかけて多くの巡拝者を迎えたとみられる歴史ある霊場です。
伊豆には弘法大師の逸話が多く伝わります。
弘法大師が唐に渡られる前後14年の間に訪れた「桂山の山寺」は修禅寺であったともいわれ、この地で弘法大師霊場が隆盛する素地は、往古からすでにあったとみることができます。
結願所の修禅寺(福地山修禅萬安禅寺)は、大同二年(807年)弘法大師による開創と伝わり、その後約470年間は真言宗寺院として栄えました。
鎌倉時代、中国から蘭渓道隆禅師が入山して臨済宗に改宗。
さらに室町時代の応永九年(1489年)には、韮山城主北条早雲が遠州から隆渓繁紹禅師を招いて曹洞宗に改宗しています。
修禅寺の影響が強いとみられるこの霊場では、当初真言宗で、のちに禅宗に改めた寺院が多くあります。
禅宗メインでありながら御本尊は多彩で、札所によっては密寺の雰囲気を色濃く残していることも、この霊場の個性であり魅力であるかと思います。
昭和に入って霊場は衰退し無住の札所も増えましたが、昭和40年代頃、伊豆在住の田上東平氏が第28番札所「大江院」に霊場の納経帳が残されていることを知り、昭和50年に伊豆霊場振興会を設立されて霊場の復興が始まりました。
田上氏は第6番札所「金剛寺」でも明治22年の日付の木版を発見、平成に入って第21番「龍澤寺」で天保十五年(1844年)と彫られた巡拝祈念碑がみつかり、少なくとも江戸時代には巡拝されていたという裏付けがなされました。
温泉地や観光地にある札所も多く、公式WebもUPされ、このところの御朱印ブームもあって近年、巡拝者が増えている模様。
~ 江戸時代より巡礼されていた伊豆八十八ヶ所霊場 長い沈黙から 今、まさに蘇る ~
(巡拝ガイド表紙より)
さらに2021年6月、伊豆八十八ヶ所霊場を熱海を起点として回る「熱海御朱印物語」が企画され、詳細なガイドが紹介されています。
「神社仏閣に参拝した証に頂くのが『御朱印』で、お遍路の様に、お経を納める事で頂くのが『納経印』と言います。御朱印という姿形は一緒でも意味は違います。まずは気軽に『御朱印』を集めながら、伊豆半島を楽しんでみませんか。」(同Webより)という趣意で、「御朱印」を納経や読経から切り離し、参加者を広げようという試みは賛否両論あるのかもしれませんが、時代に見合ったかたちなのかもしれません。(→ リリース紹介の記事)
巡拝はマイカー利用が楽ですが、伊豆半島全域をカバーしている東海バスで、公共交通機関を利用した巡拝コースが設定されています。
〔 東海バスのパンフ掲載地図 〕
※ 一部現況と異なる内容があります。

〔 札所一覧 〕
※ 一部現況と異なる内容あり。追って修正します。


2020年秋、数年がかりで結願しましたので、拝受した御朱印をご紹介します。
この霊場はほぼ2巡しており、専用納経帳のほか、ほとんどの札所で書入・印判の御朱印をいただいていますので両方ご紹介します。
伊豆八十八ヶ所霊場の専用納経帳は、デフォルトで揮毫の札所本尊、山号寺号などの揮毫が印刷されており、これに主印(三寶印、御寶印)と札所印、寺院印などの捺印をいただいて完成します。
ご不在の場合でも堂内に印が備えてあればセルフで捺印し、完成することができます。
霊場振興会では専用納経帳での巡拝を推奨されている模様で(詳細は→こちら)、専用納経帳巡拝の場合、印があるところは自分で捺せ、ご不在の場合、条件によっては後日授与対応していただけるので、御朱印をコンプリートされたい向きには専用納経帳がおすすめです。
筆者は専用納経帳を松崎で入手し、修善寺でも入手できる可能性がありますが、確実に入手するには通販での購入をおすすめします。(詳細は→こちら)、

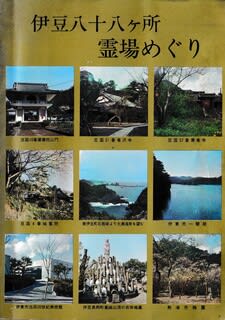
【写真 上(左)】 霊場ガイド-1
【写真 下(右)】 霊場ガイド-2


【写真 上(左)】 専用納経帳
【写真 下(右)】 専用納経帳


【写真 上(左)】 パンフ類
【写真 下(右)】 チラシ
また、伊豆には伊豆横道(よこどお)三十三観音霊場という観音霊場もあります。
こちらは、伊豆に流されていた源頼朝公が源氏再興を決意し、その成就を祈りつつ「三十三観音」を巡ったのが始まりと伝わる古い霊場です。
いくつかの札所は伊豆八十八ヶ所と重複していますので、こちらについても御朱印をご紹介します。
また、札所で拝受したその他の御朱印についても併せてご紹介していきます。
せっかくなので、伊豆半島の霊場・札所について、その概要をみてみます。
【伊豆半島と霊場・札所】
伊豆半島は人口密度が高く、寺院も多かったためか複数の霊場が開創されています。
口伊豆(三島・沼津)方面では駿河一国観音霊場(駿河三十三観音)が現役。
古い霊場では御厨観音横道札所、駿豆両国横道三十三観音霊場、また、静岡梅花観音霊場、駿河一国百地蔵尊霊場などの札所も点在し、一部札所で御朱印を授与されています。
中伊豆には伊豆中道三十三観音霊場、中伊豆観音札所、伊豆長岡温泉七福神、伊豆天城七福神などの札所があり、こちらも一部ですが御朱印が授与されています。
西・南・東伊豆では、現役霊場として伊豆横道三十三観音霊場、円覚寺百観音霊場、伊豆国(下田南伊豆)七福神、稲取八ヶ寺めぐり、伊東温泉七福神などがあり、多くの札所で御朱印が授与されています。
とくに稲取や松崎エリアは御朱印にちなんだ観光振興に積極的で、御朱印関連イベントがしばしば企画されている模様。
〔稲取・松崎の御朱印企画のパンフ〕

現況不明の霊場に、熱海三弘法大師霊場、伊豆二十一ヶ所霊場、熱海六観音霊場、伊豆伊東六阿弥陀霊場などがあり、熱海三弘法大師霊場と熱海六観音霊場の札所はだいたい伊豆八十八ヶ所と重複していますが、伊豆二十一ヶ所霊場と伊豆伊東六阿弥陀霊場は伊東市内の地域霊場的な性格で、伊豆八十八ヶ所との札所重複は少なくなっています。
伊豆は日蓮宗・法華宗寺院も多く、多くの寺院で御首題あるいは御朱印を授与されています。
伊豆は、御朱印授与神社は比較的少ないエリアですが、それでも↑のとおり授与寺院多数で目移りします。
とくに南伊豆は東京方面からの交通の便がよくないので、せっかく来たのだからと、ついつい無理をしがちです。
しかし、伊豆八十八ヶ所霊場の巡拝じたいがかなりハードなので、他札所御朱印も一気にゲットとなるとおそらく時間切れ再訪という状況に陥ります(笑)
伊豆八十八ヶ所霊場の札所はしみじみと落ち着いたいいお寺さまが多いので、ここは欲張らずに八十八ヶ所に的を絞って回るのがベターかもしれません。
無住のお寺も多くなかなか手ごわいですが、伊豆の温泉めぐりと併せ、数年がかりでじっくり回っていくのも面白いかと思います。
なお、温泉レポをUPしているお湯については、適宜リンクを貼るかたちでこちらもご案内していきます。(休業中・廃業の施設を含みます。ご注意願います。)
ボリュームがあるので、時間をかけて連載でUPしていきます。
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1
第0番 愛鷹山 三明寺(沼津市大岡)
(旧)第1番 観富山 嶺松院(伊豆市田沢)
第1番 瑞応山 長徳寺(伊豆の国市四日町)
第2番 天城山 弘道寺(伊豆市湯ケ島)
第3番 妙高山 最勝院(伊豆市宮上)
第4番 泉首山 城富院(伊豆市城)
第5番 吉原山 玉洞院(伊豆市牧之郷)
第6番 大澤山 金剛寺(伊豆市大沢)
第7番 東嶽山 泉龍寺(伊豆市堀切)
第8番 養加山 益山寺(伊豆市堀切)
第9番 引摂山 澄楽寺(伊豆の国市三福)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2
第10番 長谷山 蔵春院(伊豆の国市田京)
第11番 天與山 長源寺(伊豆の国市中)
第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(伊豆の国市古奈)
第13番 巨徳山 北條寺(伊豆の国市南江間)
第14番 龍泉山 慈光院(伊豆の国市韮山多田)
第15番 華頂峰 高岩院(伊豆の国市奈古谷)
第16番 金寶山 興聖寺(函南町塚本)
第17番 明王山 泉福寺(三島市長伏)
第18番 龍泰山 宗徳院(三島市松本)
第19番 君澤山 連馨寺(三島市広小路町)
第20番 福翁山 養徳寺(函南町平井)
第21番 圓通山 龍澤寺(三島市沢地)
第22番 龍泉山 宗福寺(三島市塚原新田)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3
第23番 日金山 東光寺(熱海市伊豆山)
第24番 走湯山 般若院(熱海市伊豆山)
第25番 護国山 興禅寺(熱海市桜木町)
第26番 根越山 長谷寺(熱海市網代)
第27番 稲荷山 東林寺(伊東市馬場町)
第28番 伊雄山 大江院(伊東市八幡野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4
第29番 大川山 龍豊院(東伊豆町大川)
第30番 金澤山 自性院(東伊豆町奈良本)
第31番 来宮山 東泉院(東伊豆町白田)
第32番 稲取山 善應院(東伊豆町稲取)
第33番 見海山 来迎院 正定寺(東伊豆町稲取)
別格旧第31番 宝林山 称念寺(河津町浜)
第34番 千手山 三養院(河津町川津筏場)
(旧)第35番 鳳儀山 栖足寺(河津町谷津)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5
第35番 天城山 慈眼院(河津町梨本)
第36番 長運山 乗安寺(河津町谷津)
第37番 玉田山 地福院(河津町縄地)
第38番 興國山 禅福寺(下田市白浜)
第39番 西向山 観音寺(下田市須崎)
第40番 瑞龍山 玉泉寺(下田市柿崎)
第41番 富巖山 天気院 海善寺(下田市一丁目)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6
第42番 大浦山 長楽寺(下田市三丁目)
第43番 乳峰山 大安寺(下田市四丁目)
第44番 湯谷山 廣台寺(下田市蓮台寺)
第45番 三壺山 向陽院(下田市河内)
第46番 砥石山 米山寺(下田市箕作)
第47番 保月山 龍門院(下田市相玉)
第48番 婆娑羅山 報本寺(下田市加増野)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7
第49番 神護山 太梅寺(下田市横川)
第50番 古松山 玄通寺(南伊豆町一條)
第51番 青谷山 龍雲寺(南伊豆町青市)
第52番 少林山 曹洞院(下田市大賀茂)
第53番 佛谷山 寶徳院(下田市吉佐美)
第54番 浦岳山 長谷寺(下田市田牛)
第55番 飯盛山 修福寺(南伊豆町湊)
第56番 養珠山 正善寺(南伊豆町手石)
第57番 東海山 青龍寺(南伊豆町手石)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8
第58番 稲荷山 正眼寺(南伊豆町石廊崎)
(石室神社)(南伊豆町石廊崎)
第59番 瑞雲山 海蔵寺(南伊豆町入間)
第60番 龍燈山 善福寺(南伊豆町妻良)
第61番 臥龍山 法泉寺(南伊豆町妻良)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9
第62番 石屏山 法伝寺(南伊豆町二條)
第63番 五峰山 保春寺(南伊豆町加納)
第64番 金嶽山 慈雲寺(南伊豆町下賀茂)
第65番 田村山 最福寺(南伊豆町上賀茂)
第66番 波次磯山 岩殿寺(南伊豆町岩殿)
第67番 太梅山 安楽寺(南伊豆町上小野)
第68番 廬岳山 東林寺(南伊豆町下小野)
第69番 塔峰山 常石寺(南伊豆町蛇石)
第70番 医王山 金泉寺(南伊豆町子浦)
第71番 翁生山 普照寺(南伊豆町伊浜)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-10
第72番 黒崎山 禅宗院(松崎町石部)
第73番 霊鷲山 常在寺(松崎町岩科南側)
第74番 嵯峨山 永禅寺(松崎町岩科北側)
第75番 岩科山 天然寺(松崎町岩科北側)
第76番 清水山 浄泉寺(松崎町松崎)
第77番 文覚山 圓通寺(松崎町宮内)
第78番 祥雲山 禅海寺(松崎町江奈)
第79番 曹源山 建久寺(松崎町建久寺)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-11
第80番 萬法山 帰一寺(松崎町船田)
第81番 富貴野山 宝蔵院(松崎町門野)
第82番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
第83番 照嶺山 東福寺(西伊豆町中)
第84番 正島山 法眼寺(西伊豆町仁科)
第85番 満行山 航浦院(沼津市西浦江梨)
伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-12
(旧)第85番 授寶山 大聖寺(西伊豆町安良里)
第86番 吉祥山 安楽寺(伊豆市土肥)
第87番 専修山 大行寺(沼津市戸田)
第88番 奥の院 正覚院(伊豆市修善寺)
第88番 福地山 修禅寺(修禅萬安禅寺)(伊豆市修善寺)
【 BGM 】
■ by your side - Wise feat. Nishino Kana
■ Waiting For Love feat.Noa - 中村舞子
■ SWEET MEMORIES 松田 聖子
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-19 (C.極楽寺口-2)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)
■ 同-16 (B.名越口-11)
■ 同-17 (B.名越口-12)
■ 同-18 (C.極楽寺口-1)から。
53.行時山 光則寺(こうそくじ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市長谷3-9-7
日蓮宗
御本尊:十界曼荼羅(『鎌倉市史 社寺編』)
司元別当:山王社(長谷)
札所:小田急沿線花の寺四季めぐり第33番
光則寺は、日蓮聖人、日朗上人ゆかりの日蓮宗寺院です。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。
文応元年(1260年)7月、日蓮聖人は『立正安国論』を幕臣の宿屋光則を通じて前執権北条時頼に提出しました。
しかし、この論は幕府に異見するものとされ、他宗からも反感を買い、日蓮聖人は数々の法難を受けられました。
「龍口(たつのくち)法難」もそのひとつです。
Wikipediaを参考にその経緯を追ってみます。
文永八年(1271年)9月12日、鎌倉幕府は幕府や諸宗を批判したとの咎で松葉ヶ谷の草庵で日蓮聖人を捕縛連行して佐渡國への流罪を申し渡しました。
9月13日子丑の刻、日蓮聖人は申し渡しに相違して、鎌倉口の頸の座(現・龍ノ口)に引き出され、あわや斬首の危機となりましたが、「不思議の奇瑞」により難を遁れたと伝わります。
その後、日蓮聖人は愛甲郡依智郷(現・厚木市)の佐渡守護代・本間六郎左衛門重連の館に移送され、一ヶ月後に佐渡に配流となりました。
「龍口法難」の際、日朗上人をはじめとする日蓮聖人の弟子達も迫害を受けました。
日朗上人(1245-1320年)は下総國海上郡能手郷に生まれたといい、父は平賀氏(平賀有国)、母は姓印東氏と伝わります。
建長六年(1254年)に鎌倉松葉ヶ谷で日蓮聖人の弟子となったといいます。
日蓮六老僧の一人で筑後房、大国阿闍梨とも称され、日朗門流・池上門流・比企谷門流の祖となりました。
文永八年(1271年)の「龍口法難」の際には、日蓮上人の有力檀越・四条金吾頼基らとともに幕臣・宿屋光則邸の土牢に押し込みとなりました。
四條金吾(左衛門尉)頼基は北条一族・名越(江間)家の執事で、建長五年(1253年)日蓮聖人に帰依して有力檀越となりました。
日蓮聖人の代表著作『開目抄』は佐渡から頼基に送られ、門下に広められたとも。
屋敷は光則寺のそば、長谷の収玄寺にあったといい、法名を収玄院日頼上人といいます。
なお、光則寺を四條金吾の屋敷跡とする資料もみられます。
宿屋光則(やどやみつのり)は、北条得宗家の被官で鎌倉幕府5代執権・北条時頼の家臣でした。
『吾妻鏡』(弘長3年11月22日條)は、時頼の臨終の際に看病を許された得宗被官7人の一人に挙げているので、時頼側近とみられます。
文応元年(1260年)7月、日蓮聖人の『立正安国論』は光則を経て時頼に提出されたといいい、日蓮聖人は『立正安国論』を光則邸(現・光則寺)で光則に委ねたともいいます。
「龍口法難」の際には日朗上人、四条金吾頼基らを自邸裏山の土牢に押し込みましたが、次第に日蓮聖人の教えに感化し、のちに自邸を日朗聖人を開山として寺となし、光則寺と号しました。
『新編相模國風土記稿』には、日朗上人が獄卒に訴え度々土牢を抜け出し佐渡の日蓮聖人のもとに向かったとありますが、主人の許可を得ずして獄卒が因人を逃すとは考えにくいので、光則は日朗上人の佐渡出向を許したか、あるいは黙認していたとみられます。
なお、日蓮聖人の佐渡配流赦免状も日朗上人がもたらしたという説がありますが、異論もあるようです。
光則寺の開山は日蓮聖人の佐渡からのご帰還(文永十一年(1274年)3月)後とみられます。
江戸時代、古田兵衛少輔重恒の室、大梅院常学日通が堂宇を再興したので、大梅寺とも呼ばれます。
樹齢約150年のカイドウをはじめ花の寺として知られ、小田急沿線花の寺四季めぐり第33番の札所にもなっています。
境内には大橋太郎通貞の土牢と伝える古墳もあります。
「歴史資料としての日蓮聖人遺文について」(小西日遶氏/PDF)等によると、大橋太郎通貞(貞経とも)は九州・豊後国の平家方の武将で、頼朝公の勘気を蒙り、領地を没収され鎌倉由比浜の土牢(光則寺山内の土牢?)に十二年間捕らえられていたといいます。
その妻は懐妊して豊後国(肥後国とも)におりましたが、無事男の子を産み落としました。
妻は夫は戦乱のなかすでに命を落としたと考え、夫の供養を子に託すため幼くして山寺に預けました。
子は昼夜に怠りなく法華経を読誦したので、ついに法華経一部を暗誦できるようになりました。
ある日その子は豊後を出て、鎌倉に至りました。
その子は八幡神の本地は霊山で法華経を説いた教主釈尊と信じ、父の生死を知る願いをかけつつ鶴岡八幡宮の宮前で法華経を誦したところ、読経の声は殿中に切々と響きわたり、
涙を流す人さえいたそうです。
ちょうど八幡宮を詣でていた頼朝公の奥方はその読経の声に尊さを感じ、その子を保護しました。
法華経を信じていた頼朝公は、その子を召し出して法華経の内で不審に思う経文について逐一尋ねたところ、その子はよどみなくこれに応えたそうです。
頼朝公は感じ入り、その子を持仏堂の読経僧としました。
ある日、囚人の首が切られると聞いてその子が涙を流したので、頼朝公がその理由を尋ねると、その子は自分は大橋太郎通貞の子で、父親は鎌倉で捕らえられているかもしれぬという懸念を話しました。
おりしも、その日に斬られることとなっていた囚人はかの大橋太郎通貞で、これを知った頼朝公は急ぎ梶原景時を刑場につかわして、刑の執行をとりやめました。
頼朝公は法華経の功徳に感じ入り、その子に様々な布施を与え、大橋太郎通貞にはもとの領地を安堵したといいます。
また、山内の稲荷社は鎮守で、建長四年(1252年)宿屋光則が上京の折、感得した木像の神躰を勧請して山内に建立と伝わります。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
光則寺 附宿屋光則𦾔跡
光則寺は、行時山と号す。大佛へ行道左にあり。此所を宿屋とも云ふ。相伝ふ、平時頼家臣、宿屋左衛門光則入道西信が宅地なりと。昔日蓮、龍口にて首の座に及ぶ時、弟子日朗・日心二人、檀那四條金吾、父子四人、安國寺にて召捕て、光則に預け給ひ、土籠に入らる。日蓮不思議の奇瑞有て害を免る。因て光則信を起し、宅地に草庵を結び、日朗を開山祖とす。光則が父の名を行時と云。近年、古田兵衛少輔重恆が後室、大梅院再興す。故に今大梅寺とも云なり。堂に、日蓮・日朗の木像、光則・四條金吾父子四人の像もあり。
妙本寺の末寺なり。
日朗土籠 寺の北の方、山上にあり。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
光則寺 附宿屋光則𦾔跡
大佛へ行道の左の方、執権北條時頼の家臣、宿屋左衛門光則入道西信が宅地なりといふ。昔日蓮上人、龍の口にて刑に臨首の座に及ぶ時、弟子日朗・日心二人、檀那四條金吾父子四人、安國寺にて召捕、光則に預け給ひ土牢に入らる。日蓮、不思議の奇瑞有て害を遁る。因て光則も信を起し、宅地を以て草庵とし、日朗を開山となし、光則が父の名を行時といふゆえ、父の名を山号とし、我名を寺号とす。
中古以来、古田兵衛少輔重恆が後室大梅院、再興すといふ。故に今は大梅寺とも号するよし。
堂内に、日蓮上人・日朗の木像、光則・四條金吾父子四人の像も有。
妙本寺末なり。
日朗が土牢、寺の北の方なる山上にあり。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
光則寺
行時山と号す。法華宗大町妙本寺末
寺域はもともと北條時頼が臣宿屋左衛門光則入道西信が宅地なり。故に今も域内ばかりを宿屋と号す。
昔日蓮龍の口にて刑に臨し時弟子日朗・日眞二人檀那四條金吾父子四人を光則に預られ、
土の牢に入らる然るに日蓮不思議の奇瑞有て害を免れしかば是より光則深く渇仰し、宅地に一宇を営み、光則が父の名を行時と云ひしが故其名を山号とし、我名を寺号とし、日朗(元應二年(1320年)正月廿一日寂す)を開山始祖とすと云へり、其後、古田兵衛少輔重恒が室、堂宇を再興せり、故に或は大梅院とも唱ふ
本尊三寶を安ず 日蓮坐長一尺日法作の像あり(略)
稲荷社
境内の鎮守なり、愛敬稲荷と云ふ、縁起に拠るに往昔鍛冶宗近一條帝の勅により一振の劔を鍛し時、藤森の稲荷に祈誓しけるに神其懇誠を感じ、合鎚を助け給ひしとぞ、かくて其劔を捧げしに叡慮ありて宗近を賞し給ふ、かゝりしかば宗近崇敬の余り神躰を彫刻し、宅地に安じて合鎚稲荷と号しけり、其後建長四年(1252年)宿屋光則、北條時頼の旨を受け京に到て宗尊親王を迎まいらせし時我君守護の為宗近の劔を求けるに或夜此神霊童子に現じて一振の劔を授くと夢みしに覚て後枕上に小祠あり、開き見れば木像の神躰なり、光則奇異の思をなし鎌倉に帰り当社を造立せしと云ふ
開山堂
日朗・日眞、及四條金吾頼基、同左衛門・南條平七郎・中務三郎左衛門等の木像を置く
土牢
寺後の山上にあり文永八年(1271年)九月日蓮囚はれし時、日朗・日眞、及四條金吾頼基等四人を宿屋光則に預られ、此に繋累せらる(中略)かくて日蓮不思議の奇瑞ありて戮を宥められ、愛甲郡依智郷本間六郎左衛門重連が許にあり、十月三日依智より日朗等に書状を贈る(中略)同九日再窟中に離別の書翰を投ず 同九日、別送日朗状云日蓮波明日、佐渡國江罷也(中略)日朗窟中に在て吾師患難の惨に堪ず、獄吏に対ひ一度師の謫居を訪ひ再獄所に帰らん事を請けるに獄吏も其心の切なるに感じて是を許す、日朗殊に喜び潜に遁れ出て佐州の配所に至る事数度に及ぶ(中略)同十年(1273年)閏五月赦免あり
今窟内に日朗の像及び五輪塔あり
宿屋左衛門光則墓
寺後の山腹にあり 当時のものとは見えず 中古冥福のために建しなるべし、光則は北條時頼の臣なり
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
行時山光則寺と号する。日蓮宗。もと妙本寺末。
開山、日朗。開基、宿屋光則。
本尊、十界曼荼羅。
境内地1370坪
本堂・庫裏・山門等あり
寺伝に、宿屋光則は北条の被官、その父の名を行時といった。山号・寺号はこれによる。
文応元年(1264年)七月十六日、日蓮は立正安国論を宿屋光則の手を経て前執権時頼に上った。
光則は大覚禅師に参禅もしている。
文応八年(1271年)九月、日蓮佐渡に配流となったとき、日朗等を預って寺の後山にある土牢に入れた。後入信して宅を寺としたという。いまも寺のあるところを宿屋と呼んでいる。
江戸時代、古田兵衛少輔重恒の室、大梅院常学日通が堂宇を再興したので、大梅寺ともよぶという。
今の本堂は慶安三年(1650年)の建立と伝え、大震災後修理を加えた。
境内に大橋太郎通貞の土牢と伝える古墳がある。
■ 山内掲示(鎌倉市)
宗派 日蓮宗
山号寺号 行時山光則寺
建立 文永11年(1274)頃
開山 日朗上人
開基 宿谷光則
『立正安国論』などによって日蓮聖人が佐渡へ流された時、弟子の日朗上人も、北条時頼の家臣であった宿谷光則の屋敷に捕らえられました。
やがて光則は、日蓮聖人に帰依し、屋敷を光則寺としたと伝えられています。
境内の裏山には日朗上人が捕らえられていたと伝わる土牢が残っています。
境内には法華教の信者だった宮沢賢治の『雨ニモマケズ』の詩碑があり、樹齢二百年といわれるカイドウの古木をはじめ、四季折々さまざまな花が見られる鎌倉有数の花の寺です。
■ 山内掲示(日朗上人の土の牢)
文永十一年(1274年)頃に建立された光則寺は、もともとは北条時頼の側近・宿屋光則の屋敷であったが、日蓮聖人が佐渡へ流された時、高弟・日朗上人も捕らえられ、この邸内の土の牢に監禁されたといわれています。
その後、光則は次第に日蓮聖人に帰依し、日蓮赦免後は日朗上人を開山に光則寺を創建した。
この土の牢は700年以上の歴史を刻んでいると推定されています。
-------------------------
江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏高徳院にかけては、平日も観光客で賑わう鎌倉きっての観光スポットです。
しかし観光客が向かうのは鎌倉大仏が長谷観音(長谷寺)で、鎌倉大仏と長谷観音のあいだに位置する光則寺へ向かう人は多くはありません。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 霊跡碑-1
「長谷観音前」交差点の1つ北側の信号から、西側の山寄りに向かって参道が伸びています。
参道入口に「日蓮聖人 立正安国論 上書 霊跡」の碑が建っています。


【写真 上(左)】 霊跡碑-2
【写真 下(右)】 宿屋氏邸址碑
数百mの長い参道で、光則寺の山内の懐は、南の長谷寺よりもふかくなっています。
参道途中に「日蓮聖人立正安國論進献霊跡」の碑とお題目碑。
また、「宿谷左衛門 宿屋?光則 邸址」の石碑も建っています。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 山門前
【写真 下(右)】 山門


【写真 上(左)】 山門上部
【写真 下(右)】 山門扁額
さらに進むとやや開けて門柱があり、左右の門柱は山号・寺号の標となっています。
古木の先にある山門は、切妻屋根青銅本瓦棒葺でおそらく四脚門。
朱塗りで上部に精緻な龍つきの本蟇股を設え、「宿谷」の扁額を掲げています。
山門脇には「日蓮聖人 第七百遠忌報恩」の石碑。
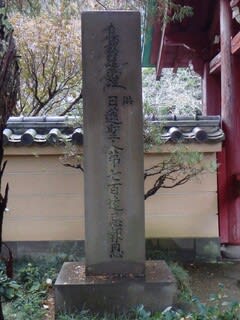

【写真 上(左)】 遠忌報恩碑
【写真 下(右)】 山内-1
山門をくぐった山内は緑濃く、背後に山肌をみせて趣があります。
数基の石碑の向こうに本堂が見えます。


【写真 上(左)】 山内-2
【写真 下(右)】 本堂
本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股を置いています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
向拝正面桟唐戸のうえに「師孝第一」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 日朗上人土牢への石段
【写真 下(右)】 土牢
本堂向かって右手の階段のうえに日朗上人の土牢があり、説明板もあります。
山内には宿屋光則の墓と大橋太郎通貞の土牢もあり、歴史の香りゆたかです。
〔 光則寺の御首題・御朱印 〕
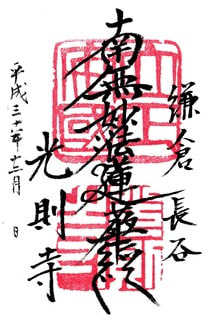

【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
54.海光山 慈照院 長谷寺(はせでら)
公式Web
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市長谷3-11-2
浄土宗系単立
御本尊:十一面観世音菩薩
司元別当:
札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第4番、鎌倉三十三観音霊場第4番、相州二十一ヶ所霊場第12番、鎌倉六阿弥陀霊場第2番、鎌倉・江ノ島七福神(大黒天)
長谷寺は鎌倉有数の古刹で、長谷観音として広く知られています。
公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。
開創は奈良時代の天平八年(736)と伝え、聖武天皇の治世下に勅願所と定められた鎌倉有数の古刹です。本尊は十一面観世音菩薩像。木彫仏としては日本最大級(高さ)の尊像で、坂東三十三所観音霊場の第四番に数えられる当山は、東国を代表する観音霊場の象徴としてその法灯を今の世に伝えています。
創建の時期や経緯については関連史料が少ないですが、天平八年(736年)、大和長谷寺の開基・德道上人を藤原房前が招いて十一面観世音菩薩像を御本尊として開山といいます。
海光山新長谷寺と号す、本尊十一面観音は長二丈六尺、和州長谷の観音と同木同作なりと
元正天皇の御宇(715-724年)、德道上人が大和長谷の山中に楠の巨木が倒れ香と瑞光を発しているのを見て、この霊木に観世音菩薩像を彫刻し、末世の衆生に結縁せしめるべく誦経礼念されました。
すると、老翁二人が来て我等で尊像を彫刻しようと云われたので、德道上人は歓喜しました。
德道上人は十一面大悲の尊像の彫刻を依頼すると二翁はわずか三日で尊像を彫り上げたといいます。
あるいは、かの二翁は「天照大神・春日明神なり、衆生利益の大願を成就せしめん為にここに来たりて彫刻せり」と告げ忽然と姿を消されたとも。
ときに養老五年(721年)三月のことといいます。
藤原北家の祖・房前卿は勅を奉じて長谷に下向し、僧行基(668-749年)を導師としてこの霊像の開眼供養の法会を修したといいます。
一説には霊像は二軀彫られ、一軀は長谷にとどめて長谷寺の御本尊となりました。
もう一軀は有縁の地に出現して衆生を済度し給へと海中に流され、十六年のちの天平八年(736年)6月三浦郡長井村の海上に現出されたといいます。
この吉祥は聖武帝の叡聞に達し、房前卿は德道上人を鎌倉に遣わして開山とし、海光山新長谷寺を号しました。
あるいは、尊像は馬入に流れ寄せ、いっときは飯山にあったのを、忍性(1217-1303年)と大江広元(1148-1225年)が鎌倉・長谷に移したともありますが、年代が合わないという説もあります。
康永元年(1342年)、足利尊氏公が御本尊を修飾、明徳三年(1392年)には足利義満公が後光を造立し、伝・行基作の御像をお前立として安置と伝わります。
慶長五年(1600年)関ヶ原の戦いの前に徳川家康公の御参あり 同十二年(1607年)には堂宇を修整、これを期に浄土宗に改宗し当時の住持・住持玉誉春宗を中興開山としています。
正保二年(1645年)酒井讃岐守忠勝が再修復し、再中興を辨秋(元禄七年(1694年)寂)としています。
以降も鎌倉を代表する名刹として参詣者を集め、坂東三十三箇所(観音霊場)第4番の札所にもなっています。
最近ではアート・音楽・食を融合した期間・人数限定イベント「長谷寺 NIGHT TABLE」を開催されるなど、新たな取り組みが注目を集めています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
長谷観音堂
海光山と号す。額に、長谷寺、子純筆とあり。子純筆、在杉本寺下。板東巡礼札所第四番なり。光明寺の末寺なり。相伝、此観音大和長谷より流木に流され、馬入へ流れ寄たるを上て、飯山に有しを、忍性と、大江廣元と謀て、此所に移すと、按ずるに忍性伝に健保後年に生、十六にて出家すとあり。廣元は、嘉禄元年(1225年)に卒す。時に忍性漸九 なり。旦【釋書】に、弘長の始、相陽に入とあれば、此事不審。又云、和州長谷の観音と此観音とは、一木の楠にて作れり。和州の観音は木本、此像は木末也。十一面観音にて、長二丈六尺二分、春日作。
按ずるに、春日と云は佛師の名なり。佛像のみにあらず。●の假面にも春日が作数多あり。(中略)
阿彌陀 作者不知
十一面像 詫間法眼作
如意輪像 安阿彌作
勢至像 安阿彌作 此像も畠山重忠が、持佛堂の本尊と云伝ふ。
聖徳太子像 作者不知
和州長谷開山徳道上人像 自作
毎年六月十七日、当寺の会にて貴賤老少参詣多し、寺領二貫文あり。
鶴岡一鳥居より十八町許あり。
慈照院 本堂の北東にあり。
慈眼院 本堂の東にあり。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
観音堂
海光山新長谷寺と号す、本尊十一面観音は長二丈六尺、和州長谷の観音と同木同作なりとぞ、縁起に拠に元正天皇の御宇(715-724年)德道上人和州長谷の山中に巨木の倒れ臥たるより異香常に薫と瑞光の現するを見て是を怪み其所に往て視るに十丈余の楠なり(中略)德道殊に悦び、かゝる霊木にて観音菩薩の像を彫刻し、末世の衆生に結縁せしめ普く救世の大悲を蒙らしめん事を志願して霊木に向ひ誦経礼念す(中略)
玆(ここ)に老翁二人来たりて我等尊像を彫刻しまいらせんと云ふ、德道歓喜し、二翁の姓名を尋るに稽文會稽首勳と云へる佛工なりと答ふ、德道卽十一面大悲の尊像を彫刻せんと請けるに二翁承諾して彼木を両斷となし纔(わずか)に三日を経て二躰を成就し、或は
天照大神・春日明神なり、衆生利益の大願を成就せしめん為に爰(ここ)に来たりて彫刻せりと告て忽雲中に化し去ぬ、時に養老五年(721年)三月なり(中略)
藤原房前勅を奉じて和州長谷に下向し、僧行基を導師として開眼供養の法会を修す(中略)
斯て一軀は其地にとゞめ、一軀は有縁の地に出現し、衆生を済度し給へと海中の波濤に泛(うか)ぶ、後十六年を経て天平八年(736年)六月十八日当國三浦郡長井村の海上に現出す、此事叡聞に達し藤原房前再僧德道を迎て開山とし、海光山新長谷寺と称すと云へり
按ずるに、佛像二軀を彫刻せしと云ふこと、菅公の長谷寺縁起に記されず、其他にも所見なければ、疑なきにあらざれど、其頃模造して此地に霊場を開きし、古刹なる事は知るべし、今姑く本文は、爰の縁起に従ふ、又或説に、此観音大和の長谷より、洪水に流され、馬入に流れ寄たるを上て、飯山に有しを、忍性(1217-1303年)と大江廣元と謀て此所に移すと云ふ、忍性が行状略頌に合考するに、年代合せず謬なり
康永元年(1342年)三月尊氏佛躰を修飾し箔を彩り、玅相を修治して荘厳を加へ、明徳三年(1392年)十二月義満後光を造立す、
行基作の同像(長八尺)を前立とし傍に勢至(座像長五尺、安阿彌作、畠山重忠が、持佛堂の本尊と云伝ふ)、如意輪(座像長二尺五寸作同上)、大黒(長三尺五寸弘法作)、恵比寿(運慶作)及び三十三身の観音像(各長三尺五寸義政の寄附と云ふ)、愛敬地蔵(座像長三尺、二位禅尼の寄附と云ふ)、大日(座像金佛、長三尺五寸八分)、彌勒(座像長二尺)並に開山德道(長三尺自作)等の像を置く(中略)
慶長五年(1600年)関原役の前東照宮御参あり 同十二年(1607年)更に命ありて堂宇を修整せらる
正保二年(1645年)酒井讃岐守忠勝資財を抛て再修復せり
中興を春宗(慶安元年(1648年)正月七日寂)、再中興を辨秋と云ふ 元禄七年(1694年)三月十七日寂す、当山七世中興、本尊並諸尊佛具等再建せしとぞ
板東札所第四なり(中略)
彌陀堂 本尊坐像長一尺 元は大町村内に建しを元禄年間(1688-704年)当寺寂譽が時此に移すと云ふ
五社明神社 神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀す、村の鎮守なり
荒神社 神躰は運慶作観音の尊像、海中より出現の時佛躰に蝕せしめ、社を勧請すと伝へ貝柄荒神と唱ふ
辨天社 巌窟の内に安ず 長一尺五寸、弘法作、或は運慶作とも云ふ(中略)
別当二院
慈照院 浄土宗材木座光明寺末 本尊彌陀を安ず
慈照(眼?)院 本寺前に同じ 本尊は彌陀 開山を明譽と云ふ
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
海光山慈照院長谷寺と号する。浄土宗。もと光明寺末。いま単立宗教法人。
開山、德道。開基、藤原前房。天平八年(736年)の草創と云う。
中興、玉譽春宗、再中興、弁秋。
本尊、十一面観世音菩薩。
境内地2026.77坪
観音堂・拝観所・阿弥陀堂・大黒堂・鐘楼・客殿・庫裏・寺務所等あり
板東巡礼札所第四番。大和の長谷寺を本とすることは明らかである。
正治二年(1200年)に大江広元が重ねて寺を建てたという。
ともかく鎌倉末期にかなり大きな堂があったことは想像してよいと思う。
■ 山内掲示(鎌倉市)
宗派 単立(浄土宗)
山号寺号 海光山慈照院長谷寺
建立 天平8年(736)
開山 徳道上人
本尊の十一面観音像は日本最大級の木造の仏像です。
寺伝によると。開山の徳道上人が大和国(奈良県)初瀬の山中で見つけた樟の巨大な霊木から、二体の観音像が造られました。
一体は大和長谷寺の観音像となり、残る一体が衆生済度の願いが込められ海に流されたといいます。その後、三浦半島の長井浦(現在の初声あたり)に流れ着いた観音像を遷し、建立されたのが長谷寺です。
境内の見晴台からは鎌倉の海が一望でき、また、二千株を超えるアジサイをはじめ、四季折々の花木を楽しめます。
-------------------------
長谷周辺では、鎌倉大仏高徳院とならぶメジャーな観光スポットです。
駐車場はありますが、常時混雑気味で夕方は閉山時間の30分前に営業終了となり翌朝まで出庫できなくなるので要注意です。


【写真 上(左)】 参道-1
【写真 下(右)】 参道-2
山内は三段構成で、登るにしたがい変化のある景色を堪能できる美しい寺院です。
山内案内はこちら。

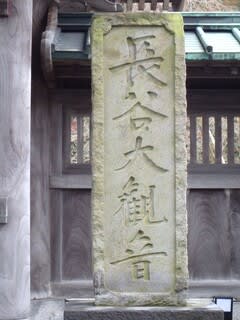
【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 長谷大観音の石標


【写真 上(左)】 出世開運大黒天の石標と山門
【写真 下(右)】 門前の観音様と地蔵尊
県道から相当の幅員で引きこんだ山門前は、門前に伸びる松の木の存在感もあいまって、さすがに名刹の風格があります。
山門前には寺号標、長谷大観音の石標、出世開運大黒天の石標と観音様&地蔵尊が御座します。


【写真 上(左)】 山門-1
【写真 下(右)】 山門-2


【写真 上(左)】 山門見上げ
【写真 下(右)】 山門妻部
山門は切妻屋根青銅本瓦棒葺の堂々たる四脚門で常閉。妻部に大瓶束を置くしっかりとした意匠です。
山内口は左手通用門でこちらが拝観受付となっています。
受付を抜けると左手が以前の授与所。(現在、御朱印授与は本堂(観音堂)となっている模様。)
その脇に明治の文芸評論家・高山樗牛(たかやまちょぎゅう)の碑は、樗牛がこの地に居住したゆかりによるもの。
正面に妙智池、放生池を配した緑濃い庭園は四季折々の風情が楽しめ、花の寺としても知られています。
寺務所から右手方向に、和み地蔵、大黒堂、書院、辨天窟(堂)と露仏や堂宇が並び、こちらが一段目(下境内)となっています。


【写真 上(左)】 早春の下境内-1
【写真 下(右)】 早春の下境内-2


【写真 上(左)】 秋の山内
【写真 下(右)】 上境内への階段
寺務所は旧別当の慈照院と思われますが詳細不明。
その横に御座の「和み地蔵」はかわいい表情で、人気の撮影スポットです。
良縁地蔵、ふれ愛観音、梶山観音など多彩な露仏が御座し、稀少な相州二十一ヶ所霊場の札所標もありました。


【写真 上(左)】 寺務所
【写真 下(右)】 良縁地蔵


【写真 上(左)】 ふれ愛観音・梶山観音
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場札所標


【写真 上(左)】 大黒堂
【写真 下(右)】 大黒堂の扁額
大黒堂は、もともと応永十九年(1412年)銘の尊像が堂宇本尊でしたが、いまは観音ミュージアムに収蔵されています。
現在の堂宇本尊は「出世・開運授け大黒天」、「さわり大黒天」で、鎌倉・江の島七福神巡り(大黒天霊場)の札所となっています。


【写真 上(左)】 辨天堂と弁天窟入口
【写真 下(右)】 辨天堂の扁額
大黒堂の対面には辨天堂と辨天窟。
弘法大師御参籠と伝わる弁天窟の内壁には弁財天、十六童子が彫られ、宇賀神も安置されています。
『新編相模國風土記稿』に「辨天社 巌窟の内に安ず 長一尺五寸、弘法作、或は運慶作とも云ふ」とある八臂辨財天ゆかりの窟とみられますが、こちらの尊像は現在観音ミュージアムに収蔵されています。(通常非公開)


【写真 上(左)】 辨天窟
【写真 下(右)】 卍池


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 地蔵堂の扁額
庭園を抜けて斜め右手上方に進むと地蔵堂で、このあたりが二段目(上境内)の入口になります。
木々がうっそうと繁り、パワスポ的イメージのある一画です。
宝形造の地蔵堂には子孫繁栄ご利益の「福徳地蔵尊」が御座し、堂宇を囲むように地蔵尊が安置されています。


【写真 上(左)】 かきがら稲荷の鳥居
【写真 下(右)】 かきがら稲荷
さらに上方に進むとかきがら稲荷。
寺伝によると、御本尊の十一面観世音菩薩像が海上を流れている際、御尊体をお守りするためにかきがらが付着し、尊像をお導きしたといわれています。
その「かきがら」をお祀りしているお社で、「かきがら絵馬」は人気の絵馬となっています。
なお、かつて山内に御鎮座で長谷村の鎮守であった五社明神社(神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀)は明治20年、甘縄神明宮境内に御遷座されています。

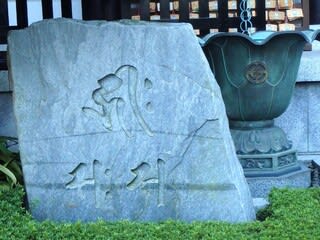
【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 阿弥陀三尊碑
鐘楼の梵鐘は、文永元年(1264年)銘の鎌倉で3 番目に古い作例とされ国の重要文化財に指定、現在は観音ミュージアムで収蔵・展示されています。
現在の梵鐘は昭和59 年に新鋳されたもので、毎朝時を告げる鐘として鎌倉市民に親しまれています。
さて、いよいよ長谷寺の核心部です。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂
【写真 下(右)】 阿弥陀堂の扁額
二層の楼閣の阿弥陀堂。
こちらに奉安の阿弥陀如来坐像は、源頼朝公が42 歳の厄除け祈願のために造立と伝わり「厄除阿弥陀」とも呼ばれます。
本像は近隣に所在した旧誓願寺の御本尊だったとされ、鎌倉六阿弥陀霊場の札所本尊となっています。
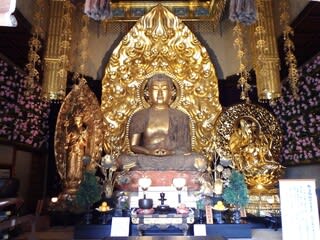

【写真 上(左)】 阿弥陀仏
【写真 下(右)】 本堂(観音堂)


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂(観音堂)入口
本堂(観音堂)も二層楼閣の堂々たる堂宇で、堂内にて参拝できます。
御本尊の十一面観音菩薩立像は像高9.18m、台座を数えると12mにも及び、木造では最大級の仏像とされます。
頭上に十一の尊顔、右手に錫杖、左手に花瓶を執られ、磐座に立たれる「長谷寺式十一面観音菩薩」です。
堂内右手には、弘法大師坐像が御座され、おそらくこちらが相州二十一ヶ所霊場札所本尊とみられます。
観音堂は幾度となく再建され、関東大震災でも甚大な被害を受けましたが、昭和61年再建がなっています。


【写真 上(左)】 長谷観音の扁額
【写真 下(右)】 観音ミュージアム
観音ミュージアムでは、数々の寺宝が観音菩薩信仰の教義とあわせ展示されています。
十一面観音菩薩立像(前立観音)は御本尊の前に祀られていた尊像で、江戸時代の造立と
されますが、行基作とも伝わる旧像の再興仏のようです。
三十三応現身像は室町時代造立とみられ、足利義政公の寄附とも伝わり鎌倉市指定文化財です。
長谷寺縁起絵巻は制作年(弘治三年(1557年)が判明する唯一の資料として神奈川県指定文化財となっています。
開山徳道上人坐像、「長谷寺」の寺号が確認できる最古(文永元年(1264年))の梵鐘や十一面観音懸仏なども展示されています。
観音ミュージアムサイトについては、→ こちらをご覧ください。


【写真 上(左)】 見晴台からの眺望-1
【写真 下(右)】 見晴台からの眺望-2
海側にせり出すようにある見晴台からは鎌倉の街並みと由比ガ浜、三浦半島から伊豆大島まで見渡せる眺望が楽しめ、その隣にある飲食所「海光庵」とともに人気スポットとなっています。


【写真 上(左)】 海光庵
【写真 下(右)】 上境内
山際に寄ったところに経蔵(輪蔵)。
輪蔵とは堂内の回転式書架で、中には一切経(大蔵経)が収められており、書架を一回転することで一切経をすべて読誦した功徳が得られるとされます。
輪蔵は正月三が日、8月10日(四萬六阡日)など特定の日のみ回すことができます。


【写真 上(左)】 経蔵
【写真 下(右)】 経蔵の向拝


【写真 上(左)】 経蔵の扁額
【写真 下(右)】 輪蔵
なお、観音ミュージアム前には四天王が御座しますが、主尊は複雑な印相につき不明です。


【写真 上(左)】 四天王と主尊
【写真 下(右)】 眺望散策路入口
経蔵からさらに登ると三段目の眺望散策路です。
平成のはじめに紫陽花が植栽され、いまでは40種類以上、約2500株の紫陽花が咲く鎌倉有数の紫陽花スポットとなっています。
ここからは見晴台を凌ぐ眺望が楽しめます。


【写真 上(左)】 散策路からの眺望-1
【写真 下(右)】 散策路からの眺望-2
御朱印は本堂(観音堂)で拝受できます。
混雑するので、前に御朱印帳をお預けし番号札をいただいて参拝後に受け取るのがベターかと思います。
また、複数の霊場札所を兼ねておられるので、霊場御朱印の申告は必須となります。
〔 長谷寺の御首題・御朱印 〕
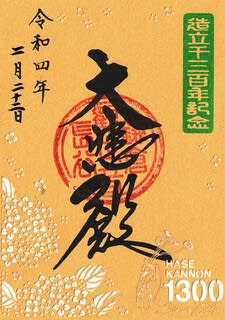
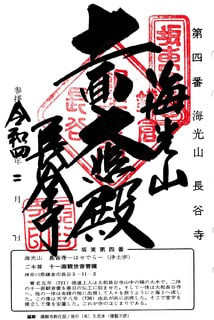
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印(造立千三百年記念)
【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印
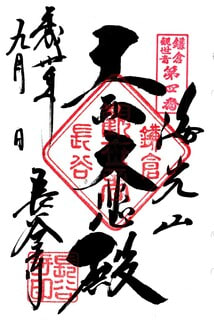

【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印
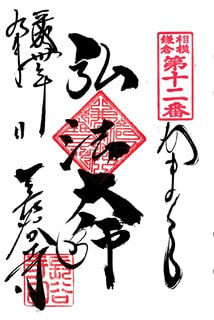
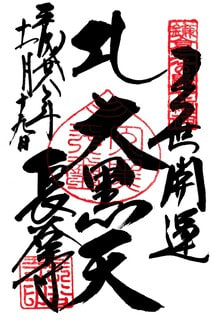
【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉・江ノ島七福神(大黒天)の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-20 (C.極楽寺口-3)へつづく。
【 BGM 】
■ 空が凪いだら/After Calm - 凪葵(Nagi)
■ Sign - 幾田りら
■ おはよう、僕の歌姫 -Happy End Ver. - Covered by Cereus
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)
■ 同-16 (B.名越口-11)
■ 同-17 (B.名越口-12)
■ 同-18 (C.極楽寺口-1)から。
53.行時山 光則寺(こうそくじ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市長谷3-9-7
日蓮宗
御本尊:十界曼荼羅(『鎌倉市史 社寺編』)
司元別当:山王社(長谷)
札所:小田急沿線花の寺四季めぐり第33番
光則寺は、日蓮聖人、日朗上人ゆかりの日蓮宗寺院です。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。
文応元年(1260年)7月、日蓮聖人は『立正安国論』を幕臣の宿屋光則を通じて前執権北条時頼に提出しました。
しかし、この論は幕府に異見するものとされ、他宗からも反感を買い、日蓮聖人は数々の法難を受けられました。
「龍口(たつのくち)法難」もそのひとつです。
Wikipediaを参考にその経緯を追ってみます。
文永八年(1271年)9月12日、鎌倉幕府は幕府や諸宗を批判したとの咎で松葉ヶ谷の草庵で日蓮聖人を捕縛連行して佐渡國への流罪を申し渡しました。
9月13日子丑の刻、日蓮聖人は申し渡しに相違して、鎌倉口の頸の座(現・龍ノ口)に引き出され、あわや斬首の危機となりましたが、「不思議の奇瑞」により難を遁れたと伝わります。
その後、日蓮聖人は愛甲郡依智郷(現・厚木市)の佐渡守護代・本間六郎左衛門重連の館に移送され、一ヶ月後に佐渡に配流となりました。
「龍口法難」の際、日朗上人をはじめとする日蓮聖人の弟子達も迫害を受けました。
日朗上人(1245-1320年)は下総國海上郡能手郷に生まれたといい、父は平賀氏(平賀有国)、母は姓印東氏と伝わります。
建長六年(1254年)に鎌倉松葉ヶ谷で日蓮聖人の弟子となったといいます。
日蓮六老僧の一人で筑後房、大国阿闍梨とも称され、日朗門流・池上門流・比企谷門流の祖となりました。
文永八年(1271年)の「龍口法難」の際には、日蓮上人の有力檀越・四条金吾頼基らとともに幕臣・宿屋光則邸の土牢に押し込みとなりました。
四條金吾(左衛門尉)頼基は北条一族・名越(江間)家の執事で、建長五年(1253年)日蓮聖人に帰依して有力檀越となりました。
日蓮聖人の代表著作『開目抄』は佐渡から頼基に送られ、門下に広められたとも。
屋敷は光則寺のそば、長谷の収玄寺にあったといい、法名を収玄院日頼上人といいます。
なお、光則寺を四條金吾の屋敷跡とする資料もみられます。
宿屋光則(やどやみつのり)は、北条得宗家の被官で鎌倉幕府5代執権・北条時頼の家臣でした。
『吾妻鏡』(弘長3年11月22日條)は、時頼の臨終の際に看病を許された得宗被官7人の一人に挙げているので、時頼側近とみられます。
文応元年(1260年)7月、日蓮聖人の『立正安国論』は光則を経て時頼に提出されたといいい、日蓮聖人は『立正安国論』を光則邸(現・光則寺)で光則に委ねたともいいます。
「龍口法難」の際には日朗上人、四条金吾頼基らを自邸裏山の土牢に押し込みましたが、次第に日蓮聖人の教えに感化し、のちに自邸を日朗聖人を開山として寺となし、光則寺と号しました。
『新編相模國風土記稿』には、日朗上人が獄卒に訴え度々土牢を抜け出し佐渡の日蓮聖人のもとに向かったとありますが、主人の許可を得ずして獄卒が因人を逃すとは考えにくいので、光則は日朗上人の佐渡出向を許したか、あるいは黙認していたとみられます。
なお、日蓮聖人の佐渡配流赦免状も日朗上人がもたらしたという説がありますが、異論もあるようです。
光則寺の開山は日蓮聖人の佐渡からのご帰還(文永十一年(1274年)3月)後とみられます。
江戸時代、古田兵衛少輔重恒の室、大梅院常学日通が堂宇を再興したので、大梅寺とも呼ばれます。
樹齢約150年のカイドウをはじめ花の寺として知られ、小田急沿線花の寺四季めぐり第33番の札所にもなっています。
境内には大橋太郎通貞の土牢と伝える古墳もあります。
「歴史資料としての日蓮聖人遺文について」(小西日遶氏/PDF)等によると、大橋太郎通貞(貞経とも)は九州・豊後国の平家方の武将で、頼朝公の勘気を蒙り、領地を没収され鎌倉由比浜の土牢(光則寺山内の土牢?)に十二年間捕らえられていたといいます。
その妻は懐妊して豊後国(肥後国とも)におりましたが、無事男の子を産み落としました。
妻は夫は戦乱のなかすでに命を落としたと考え、夫の供養を子に託すため幼くして山寺に預けました。
子は昼夜に怠りなく法華経を読誦したので、ついに法華経一部を暗誦できるようになりました。
ある日その子は豊後を出て、鎌倉に至りました。
その子は八幡神の本地は霊山で法華経を説いた教主釈尊と信じ、父の生死を知る願いをかけつつ鶴岡八幡宮の宮前で法華経を誦したところ、読経の声は殿中に切々と響きわたり、
涙を流す人さえいたそうです。
ちょうど八幡宮を詣でていた頼朝公の奥方はその読経の声に尊さを感じ、その子を保護しました。
法華経を信じていた頼朝公は、その子を召し出して法華経の内で不審に思う経文について逐一尋ねたところ、その子はよどみなくこれに応えたそうです。
頼朝公は感じ入り、その子を持仏堂の読経僧としました。
ある日、囚人の首が切られると聞いてその子が涙を流したので、頼朝公がその理由を尋ねると、その子は自分は大橋太郎通貞の子で、父親は鎌倉で捕らえられているかもしれぬという懸念を話しました。
おりしも、その日に斬られることとなっていた囚人はかの大橋太郎通貞で、これを知った頼朝公は急ぎ梶原景時を刑場につかわして、刑の執行をとりやめました。
頼朝公は法華経の功徳に感じ入り、その子に様々な布施を与え、大橋太郎通貞にはもとの領地を安堵したといいます。
また、山内の稲荷社は鎮守で、建長四年(1252年)宿屋光則が上京の折、感得した木像の神躰を勧請して山内に建立と伝わります。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
光則寺 附宿屋光則𦾔跡
光則寺は、行時山と号す。大佛へ行道左にあり。此所を宿屋とも云ふ。相伝ふ、平時頼家臣、宿屋左衛門光則入道西信が宅地なりと。昔日蓮、龍口にて首の座に及ぶ時、弟子日朗・日心二人、檀那四條金吾、父子四人、安國寺にて召捕て、光則に預け給ひ、土籠に入らる。日蓮不思議の奇瑞有て害を免る。因て光則信を起し、宅地に草庵を結び、日朗を開山祖とす。光則が父の名を行時と云。近年、古田兵衛少輔重恆が後室、大梅院再興す。故に今大梅寺とも云なり。堂に、日蓮・日朗の木像、光則・四條金吾父子四人の像もあり。
妙本寺の末寺なり。
日朗土籠 寺の北の方、山上にあり。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
光則寺 附宿屋光則𦾔跡
大佛へ行道の左の方、執権北條時頼の家臣、宿屋左衛門光則入道西信が宅地なりといふ。昔日蓮上人、龍の口にて刑に臨首の座に及ぶ時、弟子日朗・日心二人、檀那四條金吾父子四人、安國寺にて召捕、光則に預け給ひ土牢に入らる。日蓮、不思議の奇瑞有て害を遁る。因て光則も信を起し、宅地を以て草庵とし、日朗を開山となし、光則が父の名を行時といふゆえ、父の名を山号とし、我名を寺号とす。
中古以来、古田兵衛少輔重恆が後室大梅院、再興すといふ。故に今は大梅寺とも号するよし。
堂内に、日蓮上人・日朗の木像、光則・四條金吾父子四人の像も有。
妙本寺末なり。
日朗が土牢、寺の北の方なる山上にあり。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
光則寺
行時山と号す。法華宗大町妙本寺末
寺域はもともと北條時頼が臣宿屋左衛門光則入道西信が宅地なり。故に今も域内ばかりを宿屋と号す。
昔日蓮龍の口にて刑に臨し時弟子日朗・日眞二人檀那四條金吾父子四人を光則に預られ、
土の牢に入らる然るに日蓮不思議の奇瑞有て害を免れしかば是より光則深く渇仰し、宅地に一宇を営み、光則が父の名を行時と云ひしが故其名を山号とし、我名を寺号とし、日朗(元應二年(1320年)正月廿一日寂す)を開山始祖とすと云へり、其後、古田兵衛少輔重恒が室、堂宇を再興せり、故に或は大梅院とも唱ふ
本尊三寶を安ず 日蓮坐長一尺日法作の像あり(略)
稲荷社
境内の鎮守なり、愛敬稲荷と云ふ、縁起に拠るに往昔鍛冶宗近一條帝の勅により一振の劔を鍛し時、藤森の稲荷に祈誓しけるに神其懇誠を感じ、合鎚を助け給ひしとぞ、かくて其劔を捧げしに叡慮ありて宗近を賞し給ふ、かゝりしかば宗近崇敬の余り神躰を彫刻し、宅地に安じて合鎚稲荷と号しけり、其後建長四年(1252年)宿屋光則、北條時頼の旨を受け京に到て宗尊親王を迎まいらせし時我君守護の為宗近の劔を求けるに或夜此神霊童子に現じて一振の劔を授くと夢みしに覚て後枕上に小祠あり、開き見れば木像の神躰なり、光則奇異の思をなし鎌倉に帰り当社を造立せしと云ふ
開山堂
日朗・日眞、及四條金吾頼基、同左衛門・南條平七郎・中務三郎左衛門等の木像を置く
土牢
寺後の山上にあり文永八年(1271年)九月日蓮囚はれし時、日朗・日眞、及四條金吾頼基等四人を宿屋光則に預られ、此に繋累せらる(中略)かくて日蓮不思議の奇瑞ありて戮を宥められ、愛甲郡依智郷本間六郎左衛門重連が許にあり、十月三日依智より日朗等に書状を贈る(中略)同九日再窟中に離別の書翰を投ず 同九日、別送日朗状云日蓮波明日、佐渡國江罷也(中略)日朗窟中に在て吾師患難の惨に堪ず、獄吏に対ひ一度師の謫居を訪ひ再獄所に帰らん事を請けるに獄吏も其心の切なるに感じて是を許す、日朗殊に喜び潜に遁れ出て佐州の配所に至る事数度に及ぶ(中略)同十年(1273年)閏五月赦免あり
今窟内に日朗の像及び五輪塔あり
宿屋左衛門光則墓
寺後の山腹にあり 当時のものとは見えず 中古冥福のために建しなるべし、光則は北條時頼の臣なり
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
行時山光則寺と号する。日蓮宗。もと妙本寺末。
開山、日朗。開基、宿屋光則。
本尊、十界曼荼羅。
境内地1370坪
本堂・庫裏・山門等あり
寺伝に、宿屋光則は北条の被官、その父の名を行時といった。山号・寺号はこれによる。
文応元年(1264年)七月十六日、日蓮は立正安国論を宿屋光則の手を経て前執権時頼に上った。
光則は大覚禅師に参禅もしている。
文応八年(1271年)九月、日蓮佐渡に配流となったとき、日朗等を預って寺の後山にある土牢に入れた。後入信して宅を寺としたという。いまも寺のあるところを宿屋と呼んでいる。
江戸時代、古田兵衛少輔重恒の室、大梅院常学日通が堂宇を再興したので、大梅寺ともよぶという。
今の本堂は慶安三年(1650年)の建立と伝え、大震災後修理を加えた。
境内に大橋太郎通貞の土牢と伝える古墳がある。
■ 山内掲示(鎌倉市)
宗派 日蓮宗
山号寺号 行時山光則寺
建立 文永11年(1274)頃
開山 日朗上人
開基 宿谷光則
『立正安国論』などによって日蓮聖人が佐渡へ流された時、弟子の日朗上人も、北条時頼の家臣であった宿谷光則の屋敷に捕らえられました。
やがて光則は、日蓮聖人に帰依し、屋敷を光則寺としたと伝えられています。
境内の裏山には日朗上人が捕らえられていたと伝わる土牢が残っています。
境内には法華教の信者だった宮沢賢治の『雨ニモマケズ』の詩碑があり、樹齢二百年といわれるカイドウの古木をはじめ、四季折々さまざまな花が見られる鎌倉有数の花の寺です。
■ 山内掲示(日朗上人の土の牢)
文永十一年(1274年)頃に建立された光則寺は、もともとは北条時頼の側近・宿屋光則の屋敷であったが、日蓮聖人が佐渡へ流された時、高弟・日朗上人も捕らえられ、この邸内の土の牢に監禁されたといわれています。
その後、光則は次第に日蓮聖人に帰依し、日蓮赦免後は日朗上人を開山に光則寺を創建した。
この土の牢は700年以上の歴史を刻んでいると推定されています。
-------------------------
江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏高徳院にかけては、平日も観光客で賑わう鎌倉きっての観光スポットです。
しかし観光客が向かうのは鎌倉大仏が長谷観音(長谷寺)で、鎌倉大仏と長谷観音のあいだに位置する光則寺へ向かう人は多くはありません。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 霊跡碑-1
「長谷観音前」交差点の1つ北側の信号から、西側の山寄りに向かって参道が伸びています。
参道入口に「日蓮聖人 立正安国論 上書 霊跡」の碑が建っています。


【写真 上(左)】 霊跡碑-2
【写真 下(右)】 宿屋氏邸址碑
数百mの長い参道で、光則寺の山内の懐は、南の長谷寺よりもふかくなっています。
参道途中に「日蓮聖人立正安國論進献霊跡」の碑とお題目碑。
また、「宿谷左衛門 宿屋?光則 邸址」の石碑も建っています。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 山門前
【写真 下(右)】 山門


【写真 上(左)】 山門上部
【写真 下(右)】 山門扁額
さらに進むとやや開けて門柱があり、左右の門柱は山号・寺号の標となっています。
古木の先にある山門は、切妻屋根青銅本瓦棒葺でおそらく四脚門。
朱塗りで上部に精緻な龍つきの本蟇股を設え、「宿谷」の扁額を掲げています。
山門脇には「日蓮聖人 第七百遠忌報恩」の石碑。
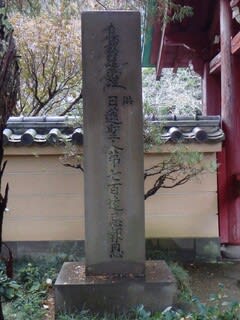

【写真 上(左)】 遠忌報恩碑
【写真 下(右)】 山内-1
山門をくぐった山内は緑濃く、背後に山肌をみせて趣があります。
数基の石碑の向こうに本堂が見えます。


【写真 上(左)】 山内-2
【写真 下(右)】 本堂
本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股を置いています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
向拝正面桟唐戸のうえに「師孝第一」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 日朗上人土牢への石段
【写真 下(右)】 土牢
本堂向かって右手の階段のうえに日朗上人の土牢があり、説明板もあります。
山内には宿屋光則の墓と大橋太郎通貞の土牢もあり、歴史の香りゆたかです。
〔 光則寺の御首題・御朱印 〕
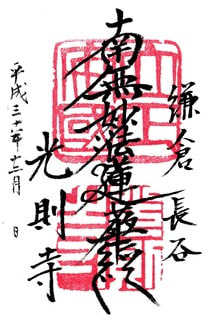

【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
54.海光山 慈照院 長谷寺(はせでら)
公式Web
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市長谷3-11-2
浄土宗系単立
御本尊:十一面観世音菩薩
司元別当:
札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第4番、鎌倉三十三観音霊場第4番、相州二十一ヶ所霊場第12番、鎌倉六阿弥陀霊場第2番、鎌倉・江ノ島七福神(大黒天)
長谷寺は鎌倉有数の古刹で、長谷観音として広く知られています。
公式Web、鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。
開創は奈良時代の天平八年(736)と伝え、聖武天皇の治世下に勅願所と定められた鎌倉有数の古刹です。本尊は十一面観世音菩薩像。木彫仏としては日本最大級(高さ)の尊像で、坂東三十三所観音霊場の第四番に数えられる当山は、東国を代表する観音霊場の象徴としてその法灯を今の世に伝えています。
創建の時期や経緯については関連史料が少ないですが、天平八年(736年)、大和長谷寺の開基・德道上人を藤原房前が招いて十一面観世音菩薩像を御本尊として開山といいます。
海光山新長谷寺と号す、本尊十一面観音は長二丈六尺、和州長谷の観音と同木同作なりと
元正天皇の御宇(715-724年)、德道上人が大和長谷の山中に楠の巨木が倒れ香と瑞光を発しているのを見て、この霊木に観世音菩薩像を彫刻し、末世の衆生に結縁せしめるべく誦経礼念されました。
すると、老翁二人が来て我等で尊像を彫刻しようと云われたので、德道上人は歓喜しました。
德道上人は十一面大悲の尊像の彫刻を依頼すると二翁はわずか三日で尊像を彫り上げたといいます。
あるいは、かの二翁は「天照大神・春日明神なり、衆生利益の大願を成就せしめん為にここに来たりて彫刻せり」と告げ忽然と姿を消されたとも。
ときに養老五年(721年)三月のことといいます。
藤原北家の祖・房前卿は勅を奉じて長谷に下向し、僧行基(668-749年)を導師としてこの霊像の開眼供養の法会を修したといいます。
一説には霊像は二軀彫られ、一軀は長谷にとどめて長谷寺の御本尊となりました。
もう一軀は有縁の地に出現して衆生を済度し給へと海中に流され、十六年のちの天平八年(736年)6月三浦郡長井村の海上に現出されたといいます。
この吉祥は聖武帝の叡聞に達し、房前卿は德道上人を鎌倉に遣わして開山とし、海光山新長谷寺を号しました。
あるいは、尊像は馬入に流れ寄せ、いっときは飯山にあったのを、忍性(1217-1303年)と大江広元(1148-1225年)が鎌倉・長谷に移したともありますが、年代が合わないという説もあります。
康永元年(1342年)、足利尊氏公が御本尊を修飾、明徳三年(1392年)には足利義満公が後光を造立し、伝・行基作の御像をお前立として安置と伝わります。
慶長五年(1600年)関ヶ原の戦いの前に徳川家康公の御参あり 同十二年(1607年)には堂宇を修整、これを期に浄土宗に改宗し当時の住持・住持玉誉春宗を中興開山としています。
正保二年(1645年)酒井讃岐守忠勝が再修復し、再中興を辨秋(元禄七年(1694年)寂)としています。
以降も鎌倉を代表する名刹として参詣者を集め、坂東三十三箇所(観音霊場)第4番の札所にもなっています。
最近ではアート・音楽・食を融合した期間・人数限定イベント「長谷寺 NIGHT TABLE」を開催されるなど、新たな取り組みが注目を集めています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
長谷観音堂
海光山と号す。額に、長谷寺、子純筆とあり。子純筆、在杉本寺下。板東巡礼札所第四番なり。光明寺の末寺なり。相伝、此観音大和長谷より流木に流され、馬入へ流れ寄たるを上て、飯山に有しを、忍性と、大江廣元と謀て、此所に移すと、按ずるに忍性伝に健保後年に生、十六にて出家すとあり。廣元は、嘉禄元年(1225年)に卒す。時に忍性漸九 なり。旦【釋書】に、弘長の始、相陽に入とあれば、此事不審。又云、和州長谷の観音と此観音とは、一木の楠にて作れり。和州の観音は木本、此像は木末也。十一面観音にて、長二丈六尺二分、春日作。
按ずるに、春日と云は佛師の名なり。佛像のみにあらず。●の假面にも春日が作数多あり。(中略)
阿彌陀 作者不知
十一面像 詫間法眼作
如意輪像 安阿彌作
勢至像 安阿彌作 此像も畠山重忠が、持佛堂の本尊と云伝ふ。
聖徳太子像 作者不知
和州長谷開山徳道上人像 自作
毎年六月十七日、当寺の会にて貴賤老少参詣多し、寺領二貫文あり。
鶴岡一鳥居より十八町許あり。
慈照院 本堂の北東にあり。
慈眼院 本堂の東にあり。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
観音堂
海光山新長谷寺と号す、本尊十一面観音は長二丈六尺、和州長谷の観音と同木同作なりとぞ、縁起に拠に元正天皇の御宇(715-724年)德道上人和州長谷の山中に巨木の倒れ臥たるより異香常に薫と瑞光の現するを見て是を怪み其所に往て視るに十丈余の楠なり(中略)德道殊に悦び、かゝる霊木にて観音菩薩の像を彫刻し、末世の衆生に結縁せしめ普く救世の大悲を蒙らしめん事を志願して霊木に向ひ誦経礼念す(中略)
玆(ここ)に老翁二人来たりて我等尊像を彫刻しまいらせんと云ふ、德道歓喜し、二翁の姓名を尋るに稽文會稽首勳と云へる佛工なりと答ふ、德道卽十一面大悲の尊像を彫刻せんと請けるに二翁承諾して彼木を両斷となし纔(わずか)に三日を経て二躰を成就し、或は
天照大神・春日明神なり、衆生利益の大願を成就せしめん為に爰(ここ)に来たりて彫刻せりと告て忽雲中に化し去ぬ、時に養老五年(721年)三月なり(中略)
藤原房前勅を奉じて和州長谷に下向し、僧行基を導師として開眼供養の法会を修す(中略)
斯て一軀は其地にとゞめ、一軀は有縁の地に出現し、衆生を済度し給へと海中の波濤に泛(うか)ぶ、後十六年を経て天平八年(736年)六月十八日当國三浦郡長井村の海上に現出す、此事叡聞に達し藤原房前再僧德道を迎て開山とし、海光山新長谷寺と称すと云へり
按ずるに、佛像二軀を彫刻せしと云ふこと、菅公の長谷寺縁起に記されず、其他にも所見なければ、疑なきにあらざれど、其頃模造して此地に霊場を開きし、古刹なる事は知るべし、今姑く本文は、爰の縁起に従ふ、又或説に、此観音大和の長谷より、洪水に流され、馬入に流れ寄たるを上て、飯山に有しを、忍性(1217-1303年)と大江廣元と謀て此所に移すと云ふ、忍性が行状略頌に合考するに、年代合せず謬なり
康永元年(1342年)三月尊氏佛躰を修飾し箔を彩り、玅相を修治して荘厳を加へ、明徳三年(1392年)十二月義満後光を造立す、
行基作の同像(長八尺)を前立とし傍に勢至(座像長五尺、安阿彌作、畠山重忠が、持佛堂の本尊と云伝ふ)、如意輪(座像長二尺五寸作同上)、大黒(長三尺五寸弘法作)、恵比寿(運慶作)及び三十三身の観音像(各長三尺五寸義政の寄附と云ふ)、愛敬地蔵(座像長三尺、二位禅尼の寄附と云ふ)、大日(座像金佛、長三尺五寸八分)、彌勒(座像長二尺)並に開山德道(長三尺自作)等の像を置く(中略)
慶長五年(1600年)関原役の前東照宮御参あり 同十二年(1607年)更に命ありて堂宇を修整せらる
正保二年(1645年)酒井讃岐守忠勝資財を抛て再修復せり
中興を春宗(慶安元年(1648年)正月七日寂)、再中興を辨秋と云ふ 元禄七年(1694年)三月十七日寂す、当山七世中興、本尊並諸尊佛具等再建せしとぞ
板東札所第四なり(中略)
彌陀堂 本尊坐像長一尺 元は大町村内に建しを元禄年間(1688-704年)当寺寂譽が時此に移すと云ふ
五社明神社 神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀す、村の鎮守なり
荒神社 神躰は運慶作観音の尊像、海中より出現の時佛躰に蝕せしめ、社を勧請すと伝へ貝柄荒神と唱ふ
辨天社 巌窟の内に安ず 長一尺五寸、弘法作、或は運慶作とも云ふ(中略)
別当二院
慈照院 浄土宗材木座光明寺末 本尊彌陀を安ず
慈照(眼?)院 本寺前に同じ 本尊は彌陀 開山を明譽と云ふ
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
海光山慈照院長谷寺と号する。浄土宗。もと光明寺末。いま単立宗教法人。
開山、德道。開基、藤原前房。天平八年(736年)の草創と云う。
中興、玉譽春宗、再中興、弁秋。
本尊、十一面観世音菩薩。
境内地2026.77坪
観音堂・拝観所・阿弥陀堂・大黒堂・鐘楼・客殿・庫裏・寺務所等あり
板東巡礼札所第四番。大和の長谷寺を本とすることは明らかである。
正治二年(1200年)に大江広元が重ねて寺を建てたという。
ともかく鎌倉末期にかなり大きな堂があったことは想像してよいと思う。
■ 山内掲示(鎌倉市)
宗派 単立(浄土宗)
山号寺号 海光山慈照院長谷寺
建立 天平8年(736)
開山 徳道上人
本尊の十一面観音像は日本最大級の木造の仏像です。
寺伝によると。開山の徳道上人が大和国(奈良県)初瀬の山中で見つけた樟の巨大な霊木から、二体の観音像が造られました。
一体は大和長谷寺の観音像となり、残る一体が衆生済度の願いが込められ海に流されたといいます。その後、三浦半島の長井浦(現在の初声あたり)に流れ着いた観音像を遷し、建立されたのが長谷寺です。
境内の見晴台からは鎌倉の海が一望でき、また、二千株を超えるアジサイをはじめ、四季折々の花木を楽しめます。
-------------------------
長谷周辺では、鎌倉大仏高徳院とならぶメジャーな観光スポットです。
駐車場はありますが、常時混雑気味で夕方は閉山時間の30分前に営業終了となり翌朝まで出庫できなくなるので要注意です。


【写真 上(左)】 参道-1
【写真 下(右)】 参道-2
山内は三段構成で、登るにしたがい変化のある景色を堪能できる美しい寺院です。
山内案内はこちら。

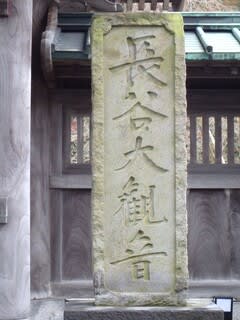
【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 長谷大観音の石標


【写真 上(左)】 出世開運大黒天の石標と山門
【写真 下(右)】 門前の観音様と地蔵尊
県道から相当の幅員で引きこんだ山門前は、門前に伸びる松の木の存在感もあいまって、さすがに名刹の風格があります。
山門前には寺号標、長谷大観音の石標、出世開運大黒天の石標と観音様&地蔵尊が御座します。


【写真 上(左)】 山門-1
【写真 下(右)】 山門-2


【写真 上(左)】 山門見上げ
【写真 下(右)】 山門妻部
山門は切妻屋根青銅本瓦棒葺の堂々たる四脚門で常閉。妻部に大瓶束を置くしっかりとした意匠です。
山内口は左手通用門でこちらが拝観受付となっています。
受付を抜けると左手が以前の授与所。(現在、御朱印授与は本堂(観音堂)となっている模様。)
その脇に明治の文芸評論家・高山樗牛(たかやまちょぎゅう)の碑は、樗牛がこの地に居住したゆかりによるもの。
正面に妙智池、放生池を配した緑濃い庭園は四季折々の風情が楽しめ、花の寺としても知られています。
寺務所から右手方向に、和み地蔵、大黒堂、書院、辨天窟(堂)と露仏や堂宇が並び、こちらが一段目(下境内)となっています。


【写真 上(左)】 早春の下境内-1
【写真 下(右)】 早春の下境内-2


【写真 上(左)】 秋の山内
【写真 下(右)】 上境内への階段
寺務所は旧別当の慈照院と思われますが詳細不明。
その横に御座の「和み地蔵」はかわいい表情で、人気の撮影スポットです。
良縁地蔵、ふれ愛観音、梶山観音など多彩な露仏が御座し、稀少な相州二十一ヶ所霊場の札所標もありました。


【写真 上(左)】 寺務所
【写真 下(右)】 良縁地蔵


【写真 上(左)】 ふれ愛観音・梶山観音
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場札所標


【写真 上(左)】 大黒堂
【写真 下(右)】 大黒堂の扁額
大黒堂は、もともと応永十九年(1412年)銘の尊像が堂宇本尊でしたが、いまは観音ミュージアムに収蔵されています。
現在の堂宇本尊は「出世・開運授け大黒天」、「さわり大黒天」で、鎌倉・江の島七福神巡り(大黒天霊場)の札所となっています。


【写真 上(左)】 辨天堂と弁天窟入口
【写真 下(右)】 辨天堂の扁額
大黒堂の対面には辨天堂と辨天窟。
弘法大師御参籠と伝わる弁天窟の内壁には弁財天、十六童子が彫られ、宇賀神も安置されています。
『新編相模國風土記稿』に「辨天社 巌窟の内に安ず 長一尺五寸、弘法作、或は運慶作とも云ふ」とある八臂辨財天ゆかりの窟とみられますが、こちらの尊像は現在観音ミュージアムに収蔵されています。(通常非公開)


【写真 上(左)】 辨天窟
【写真 下(右)】 卍池


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 地蔵堂の扁額
庭園を抜けて斜め右手上方に進むと地蔵堂で、このあたりが二段目(上境内)の入口になります。
木々がうっそうと繁り、パワスポ的イメージのある一画です。
宝形造の地蔵堂には子孫繁栄ご利益の「福徳地蔵尊」が御座し、堂宇を囲むように地蔵尊が安置されています。


【写真 上(左)】 かきがら稲荷の鳥居
【写真 下(右)】 かきがら稲荷
さらに上方に進むとかきがら稲荷。
寺伝によると、御本尊の十一面観世音菩薩像が海上を流れている際、御尊体をお守りするためにかきがらが付着し、尊像をお導きしたといわれています。
その「かきがら」をお祀りしているお社で、「かきがら絵馬」は人気の絵馬となっています。
なお、かつて山内に御鎮座で長谷村の鎮守であった五社明神社(神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀)は明治20年、甘縄神明宮境内に御遷座されています。

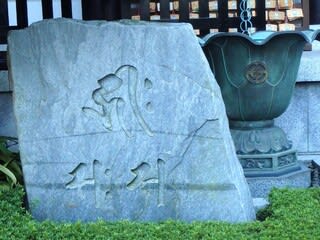
【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 阿弥陀三尊碑
鐘楼の梵鐘は、文永元年(1264年)銘の鎌倉で3 番目に古い作例とされ国の重要文化財に指定、現在は観音ミュージアムで収蔵・展示されています。
現在の梵鐘は昭和59 年に新鋳されたもので、毎朝時を告げる鐘として鎌倉市民に親しまれています。
さて、いよいよ長谷寺の核心部です。


【写真 上(左)】 阿弥陀堂
【写真 下(右)】 阿弥陀堂の扁額
二層の楼閣の阿弥陀堂。
こちらに奉安の阿弥陀如来坐像は、源頼朝公が42 歳の厄除け祈願のために造立と伝わり「厄除阿弥陀」とも呼ばれます。
本像は近隣に所在した旧誓願寺の御本尊だったとされ、鎌倉六阿弥陀霊場の札所本尊となっています。
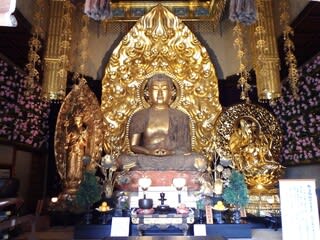

【写真 上(左)】 阿弥陀仏
【写真 下(右)】 本堂(観音堂)


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂(観音堂)入口
本堂(観音堂)も二層楼閣の堂々たる堂宇で、堂内にて参拝できます。
御本尊の十一面観音菩薩立像は像高9.18m、台座を数えると12mにも及び、木造では最大級の仏像とされます。
頭上に十一の尊顔、右手に錫杖、左手に花瓶を執られ、磐座に立たれる「長谷寺式十一面観音菩薩」です。
堂内右手には、弘法大師坐像が御座され、おそらくこちらが相州二十一ヶ所霊場札所本尊とみられます。
観音堂は幾度となく再建され、関東大震災でも甚大な被害を受けましたが、昭和61年再建がなっています。


【写真 上(左)】 長谷観音の扁額
【写真 下(右)】 観音ミュージアム
観音ミュージアムでは、数々の寺宝が観音菩薩信仰の教義とあわせ展示されています。
十一面観音菩薩立像(前立観音)は御本尊の前に祀られていた尊像で、江戸時代の造立と
されますが、行基作とも伝わる旧像の再興仏のようです。
三十三応現身像は室町時代造立とみられ、足利義政公の寄附とも伝わり鎌倉市指定文化財です。
長谷寺縁起絵巻は制作年(弘治三年(1557年)が判明する唯一の資料として神奈川県指定文化財となっています。
開山徳道上人坐像、「長谷寺」の寺号が確認できる最古(文永元年(1264年))の梵鐘や十一面観音懸仏なども展示されています。
観音ミュージアムサイトについては、→ こちらをご覧ください。


【写真 上(左)】 見晴台からの眺望-1
【写真 下(右)】 見晴台からの眺望-2
海側にせり出すようにある見晴台からは鎌倉の街並みと由比ガ浜、三浦半島から伊豆大島まで見渡せる眺望が楽しめ、その隣にある飲食所「海光庵」とともに人気スポットとなっています。


【写真 上(左)】 海光庵
【写真 下(右)】 上境内
山際に寄ったところに経蔵(輪蔵)。
輪蔵とは堂内の回転式書架で、中には一切経(大蔵経)が収められており、書架を一回転することで一切経をすべて読誦した功徳が得られるとされます。
輪蔵は正月三が日、8月10日(四萬六阡日)など特定の日のみ回すことができます。


【写真 上(左)】 経蔵
【写真 下(右)】 経蔵の向拝


【写真 上(左)】 経蔵の扁額
【写真 下(右)】 輪蔵
なお、観音ミュージアム前には四天王が御座しますが、主尊は複雑な印相につき不明です。


【写真 上(左)】 四天王と主尊
【写真 下(右)】 眺望散策路入口
経蔵からさらに登ると三段目の眺望散策路です。
平成のはじめに紫陽花が植栽され、いまでは40種類以上、約2500株の紫陽花が咲く鎌倉有数の紫陽花スポットとなっています。
ここからは見晴台を凌ぐ眺望が楽しめます。


【写真 上(左)】 散策路からの眺望-1
【写真 下(右)】 散策路からの眺望-2
御朱印は本堂(観音堂)で拝受できます。
混雑するので、前に御朱印帳をお預けし番号札をいただいて参拝後に受け取るのがベターかと思います。
また、複数の霊場札所を兼ねておられるので、霊場御朱印の申告は必須となります。
〔 長谷寺の御首題・御朱印 〕
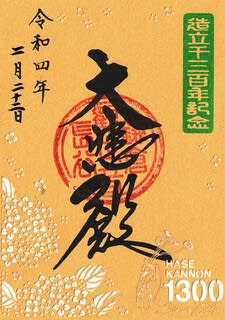
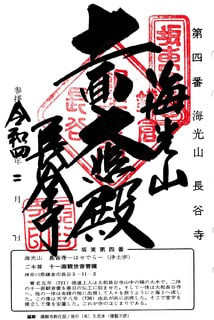
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印(造立千三百年記念)
【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印
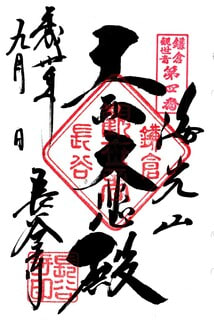

【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印
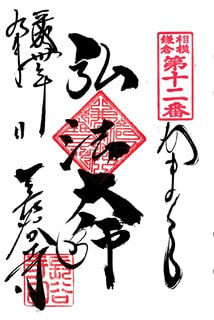
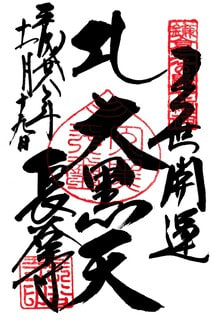
【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉・江ノ島七福神(大黒天)の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-20 (C.極楽寺口-3)へつづく。
【 BGM 】
■ 空が凪いだら/After Calm - 凪葵(Nagi)
■ Sign - 幾田りら
■ おはよう、僕の歌姫 -Happy End Ver. - Covered by Cereus
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-18 (C.極楽寺口-1)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)
■ 同-16 (B.名越口-11)
■ 同-17 (B.名越口-12)から。
市内各所に寺社が立地する鎌倉市ですが、鎌倉駅西の市役所通りから由比ヶ浜にかけての御成町、和田塚、笹目町エリアは一種の寺社空白地帯となっています。
ここからは西に転じて長谷、極楽寺、腰越方面の寺社を「極楽寺口」としてくくりまとめていきます。
51.甘縄神明宮(あまなわしんめいぐう)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市長谷1ー12ー1
主祭神:天照大御神
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
元別当:甘縄院(臨済宗妙心寺末)
甘縄神明宮は、甘縄神明神社とも呼ばれ鎌倉市最古の神社とされています。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。
甘縄神明宮は、和銅三年(710年)行基菩薩の草創、染谷太郎太夫時忠の創建と伝わり、鎌倉最古のお社といわれます。
「鎌倉史跡・寺社データベース」様によると、「染屋太郎大夫時忠邸址碑」(鎌倉市長谷2-4-6)には、「染屋太郎太夫時忠は藤原鎌足の玄孫にあたり、南都の東大寺・良弁僧正の父であり、文武天皇の御時より聖武天皇の神亀年間に至る間、鎌倉に居住し、関東八国の僧追捕使となって、東夷を鎮め、由比の長者と称された(中略)甘縄新明宮の別当甘縄院は時忠の開基であるという」との旨の碑文がみえるとのこと。
東大寺の開山・良辨僧正(689-774年)の父で、関東八国の僧追捕使とは相当な大物です。
「鎌倉むかし物語」様の「由比の長者」では、由井の里の長者・染屋太郎太夫時忠の娘が鷲にさらわれたという逸話が紹介されています。
良辨僧正も幼い頃鷲にさらわれたという逸話が残り、なんらかの関連を示唆しています。
『新編相模國風土記稿』にも、甘縄神明宮の別当神興山甘縄院は、天平年中(729-749年)行基の草創にして開基は染谷太郎太夫時忠とあります。
『鎌倉市史 社寺編』には、源頼義公(河内源氏2代、988-1075年)が相模守として下向の折に上野介直方の女を娶り、当社に祈って八幡太郎義家公を甘縄の地に生んだと伝えるとあります。
平上野介直方は平忠常の乱(長元元年(1028年))の際、討伐に赴いた桓武平氏国香流の軍事貴族で、鎌倉に所領を得て居館を構えたといいます。
長元三年(1030年)、源頼信公・頼義公父子は忠常を降伏させ、頼義公は長元九年(1036年)相模守に任ぜられ相模国に下向しました。
当時、鎌倉には平直方が拠っていましたが、直方は自身が平定できなかった忠常を頼義公が降伏させたことを尊んで、息女を輿入れさせ、鎌倉・大蔵の拠点と在鎌倉の郎党を譲り渡したといいます。
頼義公は直方の息女とのあいだに、八幡太郎義家公、賀茂次郎義綱公、新羅三郎義光公の3人の子息をもうけました。
通説では、義家公は河内國石川郡壺井(現・大阪府羽曳野市)の香炉峰の館に生まれたとされますが、『鎌倉市史 社寺編』には「(義家公は)当社(甘縄神明宮)に祈って八幡太郎義家を甘縄の地に生んだと伝える。」とあります。
また、『神奈川県神社誌』には、「康平六年(1063年)(頼義公が)当社を修復、義家も永保元年(1081年)に修復を加えた」とあります。
八幡太郎義家公生誕の地とすると、そこは源家の聖地です。
頼朝公は甘縄神明宮を尊崇してしばしば参詣し、文治二年(1186年)10月には社殿を修理監督し、落慶の行事に自ら臨んでいます。
『吾妻鏡』には、北条政子や3代将軍源実朝公の参詣も記されています。
北条政子は鶴岳宮(鶴岡八幡宮)と甘縄明神(甘縄神明宮)を同日に参詣しています。(「 文治五年(1189年)十月十七日、御臺所御参詣鶴岳宮幷甘縄明神」)
『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)には「是(甘縄神明宮)は古へより伊勢の別宮」とあります。
『承久記』には「日本国の帝位は伊勢天照太神・八幡大菩薩の御計ひ」と記され、伊勢の天照太神、八幡大菩薩(八幡神)はすこぶる重要な神として尊崇されていたことがわかります。
気になるのは実朝公参詣の條に「建保三年(1215年)四月二日、令詣甘縄神明幷日吉別宮等給」とあることです。
つまり、実朝公は甘縄の甘縄神明宮と日吉別宮(山王社)を同時に詣でています。
『新編相模國風土記稿』の(甘縄)山王社の條には「大佛陸奥守貞直の勧請と云ふ」とあります。
大佛貞直(元弘三年(1333年没)は鎌倉末期の北条一門で、実朝公(1192-1219年)とは時代が合いません。
実朝公は大佛貞直勧請前の日吉別宮(山王社)に参詣していたことになり、この点は『風土記稿』の筆者も気になったらしく「思ふに(山王)社は古くより、此に在て、貞直が再興勧請せしなるべし」との説を展開しています。
甘縄神明宮周辺には、安達藤九郎盛長の屋敷があったとされます。(異説あり)
安達氏は藤原氏魚名(山蔭)流ともされますが、安達盛長の父は小野田兼広とも小野田兼盛とも伝わり、小野田姓のようですが詳細不明です。
安達盛長の兄は藤原遠兼とされ、父親の小野田姓から藤原姓に復姓も考えられますが詳細不明。
しかも弟の盛長は安達姓を名乗っており、どうも整理がつきません。
また、藤原遠兼の子は足立遠元で、土着した武蔵国足立郡から名乗ったとされるので、安達氏、足立氏の系譜はわかりにくくなっています。
安達盛長は生え抜きの東国武将とはいい難いですが、源頼朝公の乳母・比企尼の長女・丹後内侍を妻とし、旗揚げ前から源頼朝公の信任を得ていたと伝わります。
丹後内侍はもとは京で二条院に女房として仕え、官吏や右筆の招聘窓口となっていたとみられ、頼朝公の初期右筆・藤原邦通は、丹後内侍のルートで招かれたといいます。
一説には、伊豆で頼朝公と北条政子の仲をとり持ったのは盛長だとも。
治承四年(1180年)8月の頼朝公挙兵に従い、石橋山の戦いの後に頼朝公とともに安房に逃れ、下総国の豪族・千葉常胤を説得して味方につけたとされます。
頼朝公鎌倉入りののち、元暦元年(1184年)頃から上野国奉行人となり、文治五年(1189年)奥州合戦に従軍して戦功をあげ、陸奥国安達郡と出羽国大曽根荘を賜わりました。
盛長は、『吾妻鏡』では”藤九郎(盛長)”と記されることが多く、だとすると安達の名字は所領の”安達郡”由来かもしれません。
甥とされる足立遠元は武蔵国足立郡に確かな拠点を築いており、代表的な武蔵武士として知られています。
盛長と足立遠元の関係はよくわかりませんが、遠元は武官、盛長は頼朝公側近として協力しつつ頼朝公を支えていたのかもしれません。
幕府開府後も頼朝公の信任厚く、甘縄にあった盛長邸を頼朝公がしばしば訪れた記録が残ります。
文治二年(1186年)6月、丹後内侍罹病の際、頼朝公は盛長邸に丹後内侍を見舞っているので、盛長・丹後内侍夫婦と頼朝公の私的なつながりが強かったかと。
『吾妻鏡』には「還向便路藤九郎盛長屋敷」という記載があり、「還向」は神仏に参詣して帰ること、「便路」は便利な道を指すので、盛長邸への頼朝公来訪は甘縄神明宮参詣を兼ねた側面もあったかと思います。
正治元年(1199年)1月の頼朝公逝去後、出家して蓮西と名乗りましたが、同年4月、2代将軍・源頼家公の宿老として十三人の合議制の一人となり幕政に参画しています。
梶原景時の弾劾(梶原景時の変)でも大きな役割を担ったとされますが、生涯無位無官のままとみられています。
「神明様」(しんめいさま)と呼ばれ、長谷の鎮守として鎌倉の庶民にも尊崇された甘縄神明宮は、明治6年村社に列格し、明治20年、長谷寺の鎮守であった五社明神社(神明・春日・白山・稲荷・天神)を合祀しています。
関東大震災で本殿は半潰、拝殿は全潰しましたが、昭和12年に再建されています。
なお、別当の神輿山甘縄院は山下にあり、当初は神輿山円徳寺を号しました。
和銅三年(710年)八月行基の草創といい、染屋時忠が山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立開基と伝わります。
京都妙心寺末の臨済宗寺院で御本尊は地蔵菩薩。
中興は京都妙心寺の独園和尚(宝永六年(1709年)寂)で、伝来の義家公木像を修復したといいます。
明治の神仏分離により甘縄院は廃されています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
甘縄明神
甘(甘或作海女)縄明神は、佐佐目谷の西、路の北にある茂林なり。天照大神を勧請す。神主は小池氏也。【東鑑】に、文治二年(1186年)正月二日、二品(頼朝)幷に御臺所、甘縄神明の宮に御参とあり。又甘縄明神奉幣の事、往々見へたり。里俗或は誤てたまなはと云者あり。(中略)此地より西の方は長谷村也。東北の山に隋て、無量寺谷まで甘縄の内なり。
塔辻
里俗の云、由井長者太夫時忠と云者、三歳の児を鷲につかまれ、方々尋求て、道路に棄たる骨肉のある所ごとに、是や我子の骨肉ならんかとて、菩提の為に立たる石塔也。(中略)大織冠の玄孫に、染谷太郎太夫時忠、南都良辨の父也。文武天皇の御宇より、聖武天皇の御宇に至るまで鎌倉に居住し、東八箇國の總追捕使となりて、東夷を鎮むとあり。是ならんか。然れども未詳。良辨の父とはいへども、【元亨釋書】にも不載。【釋書】に、良辨は近州志賀里人、或は相州の人とも云と有。又鷲につかまれし事もあれば、相似たるにや。
藤九郎盛長屋敷
甘縄明神の前、東の方を云。【東鑑】に、治承四年(1180年)十二月廿日、武衛御行始めとして、藤九郎盛長が、甘縄の家に入御し給ふとあり。其後往々見へたり。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
甘縄神明宮
佐々目が谷の西の路北に、樹木茂りたる社地なり。是は古へより伊勢の別宮と称し、【東鑑】にも記せり。神主小池氏。文治二年(1186年)正月二日、二品(頼朝)並に御臺所、甘縄神明宮御参とあり。其後も奉幣の事往々出たり。地名を甘縄と号するゆへ、宮号にも古く唱へ来れり。又同年十月廿日甘縄神明寶殿修理せられ、今日四面に荒垣をゆひ、幷鳥居を建らる。盛長の沙汰とし、二品監臨と給ふ。(以下略)
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
神明宮
【東鑑】に伊勢別宮とある是なり 里俗は甘縄明神と唱ふ神躰は義家の守護神と云伝へ秘して開扉を許さず、義家の木像をも安ぜり、長一尺五寸、束帯の坐像なり、文治二年(1186年)正月頼朝当社に参詣あり
【東鑑】曰、文治二年(1186年)正月二日、二品幷御臺所、御参甘縄神明宮、以御還向便路藤九郎盛長屋敷 是歳十月社殿を修理し(中略)文治五年(1189年)十月十七日、御臺所御参詣鶴岳宮幷甘縄明神(中略)建保三年(1215年)四月實朝参詣あり
建保三年(1215年)四月二日、令詣甘縄神明幷日吉別宮等給、御還向之次、入御安達右衛門尉景盛家、今当村の鎮守にして年々九月十六日神事あり。
末社 疱瘡神 稲荷四
別当甘縄院
神興山と号す、臨済宗京都妙心寺末 本尊地蔵を安ず、天平年中(729-749年)行基の草創にして開基は染谷太郎太夫時忠と云ふ、境内より江山臨眺の景尤佳なり
山王社
光則寺持 大佛陸奥守貞直が勧請と云ふ 按ずるに、【東鑑】建保三年(1215年)の條に、甘縄神明幷日吉別宮等に、参詣せしめ、還路の次、安達右衛門尉景盛が家に、入御ありと見ゆ、景盛が亭跡、神明社の東にあり、さては日吉の別宮と云ふ、当社なるべし、されど大佛貞直が、勧請と云ふ、合期せず、貞直は、北条陸奥守宣時が三男、民部少輔宗泰が子にて、元弘三年(1333年)五月、由井濱の戦に討死す、建保を距る事、百年に過たりさては時代合せず、思ふに社は古くより、此に在て、貞直が再興勧請せしなるべし
■ 神奈川県神社誌(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
祭神 天照大御神
境内社 五社明神(天照大御神 倉稲魂命 伊邪那美命 菅原道真公) 秋葉社
社殿 本殿(神明造銅板葺)一棟一宇 幣殿 拝殿(入母屋造銅板葺・千木・鰹魚木・向拝付)二棟一宇
境内坪数 127.04坪
『相州鎌倉郡神輿山甘縄寺神明宮縁起略』(正徳二年(1712年)銘)によれば、和銅三年(710年)八月行基の草創になり、染屋太郎時忠が山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立したことにはじまるという。
また源頼義が当社に祈って八幡太郎義家を当地に生み、康平六年(1063年)当社を修復、義家も永保元年(1081年)に修復を加えたという。
『吾妻鏡』によれば、伊勢別宮として源頼朝が崇敬し、文治二年(1186年)十月社殿を修理し、四面に荒垣及び鳥居を建て、また建久五年(1194年)までに三度参詣している。夫人政子は二度、実朝も一度参詣している。
『相模風土記』には「神明宮、里俗甘縄明神と唱う」「別当臨済宗甘縄院」とある。
明治維新の神仏分離により、別当甘縄院は廃絶し、神明宮は明治六年十二月村社に列格され、明治二十年五月、五社明神社を合併し、明治四十年四月神饌幣帛料供進神社に指定された。
昭和七年社号を甘縄神明神社と改称した。旧社殿は大正十二年の関東大震災に倒潰し、現社殿は昭和十二年九月新築復興した。長谷区の氏神社である。
宝物 神輿・一基、義家座像・一体
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
甘縄神明神社
もとは神明社或は神明宮と称したが昭和七年九月二十一日、今の名に改めた。
祭神は天照大御神のほか倉稲魂命・伊邪那美命・武甕槌命・菅原道真公を配祀する。例祭九月十四日。元指定村社。長谷の鎮守。境内地127.04坪。
本殿・拝殿・摂社稲荷社・社務所・神輿庫等あり。(中略)
勧請年月未詳。『吾妻鏡』によれば、伊勢別宮であり、源頼朝は三度、政子は二度、実朝は一度参詣しており、文治二年(1186年)十月二十四日には社殿を修理し、四面に荒垣及び鳥居を建て、頼朝自らその場に臨んだことがわかる。
いま社蔵する『相州鎌倉郡神輿山甘縄寺神明宮縁起略』の写しによれば、ここは和銅三年(710年)八月行基の草創で、染屋時忠が山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立し、後源頼義が相模守として下向、上野介直方の女をめとり、当社に祈って八幡太郎義家を甘縄の地に生んだと伝える。
また中興は宝永六年(1709年)六月二十六日に寂した京都妙心寺の独園和尚で、社殿・寺舎を造替し、弟子瑞峯祖堂を住持とし、また義家の像を修復させたという。(中略)
この寺を別当甘縄院といい、その本尊は地蔵であった。神仏分離により寺は廃滅したという。いまは寺の痕跡もない。
明治二十年五月二十五日、長谷寺の鎮守であった五社明神社、祭神は神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀している。
大正十二年の震災で本殿半潰、拝殿全潰し、昭和十二年九月新築した。
甘縄神明神社がここにまつられた理由は、此の地が大庭御厨の飛地であったか、或は大庭氏の一族梶原氏、鎌倉氏などの地であったことによると思われるが、(以下略)
■ 境内掲示(甘縄神明神社略誌)(抜粋)
御祭神
天照大神
伊邪那岐尊(白山) 倉稲魂命(稲荷)
武甕槌命(春日) 菅原道真公(天神)
御由緒
和銅三年(710年) 染屋太郎太夫時忠の創建です
永保元年(1081年) 源義家公が社殿を再建せらる
源頼朝公政子の方實朝公など武家の崇敬が篤く 古来伊勢別家と尊称せられている鎌倉で最も古い神社です。
社殿の裏山は御輿ヶ嶽(見越ヶ嶽とも書く)と云い古くから歌によまれています
源頼義は相模守として下向の節 当宮に祈願し一子八幡太郎義家が生まれたと伝えられています
都にははや吹ぬらし 鎌倉の御輿ヶ崎 秋の初風
-------------------------
江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏高徳院にかけては、平日も観光客で賑わう鎌倉きっての観光スポットです。
しかし「長谷観音前」から鎌倉駅方面への神奈川県道311号鎌倉葉山線(旧大町大路)に入る観光客は多くはありません。
源氏や頼朝公とふかいゆかりをもつ甘縄神明宮ですが、訪れる観光客はさほど多くないとみられます。
実際、筆者の参拝時も「長谷」駅から大仏にかけてはかなりの雑踏でしたが、甘縄神明宮は終始筆者のみの参拝でした。


【写真 上(左)】 県道からの参道
【写真 下(右)】 社号標-1
県道から目立たない路地を山側に入るので、知らない観光客はまず気づきません。
県道沿いの木の社号標の文字は消えかかっていますが、かろうじて「長谷鎮守 甘縄神明宮」と読めます。(Web記事によるといまは新しくなっている模様。)

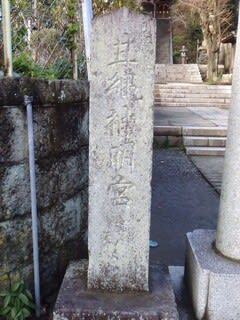
【写真 上(左)】 鳥居
【写真 下(右)】 社号標-2


【写真 上(左)】 参道-1
【写真 下(右)】 参道-2
民家の間を進む参道の正面に石造の神明鳥居、その横にも社号標があります。
鳥居をくぐった右手にさらに社号標があり、ここから石段まじりの参道が伸びています。
ひとつめの石段右手には鎌倉町青年団による「安達盛長邸址」の石碑。
参道脇の「玉縄桜」は有名なようで、ソメイヨシノより早く咲くそうです。
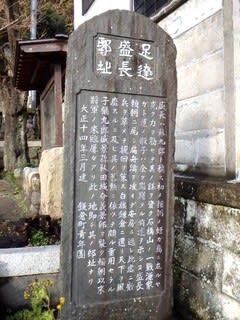

【写真 上(左)】 「安達盛長邸址」の石碑
【写真 下(右)】 手水舎


【写真 上(左)】 参道-3
【写真 下(右)】 神輿庫
その先の左手に立派な手水舎。
石灯籠一対を抜けると急な石段がはじまります。
階段上り口の左手には8代執権・北条時宗公産湯・二條公爵愛用の井があり、子宝や子供の健やかな成長に御利益があるそうです。


【写真 上(左)】 参道-4
【写真 下(右)】 拝殿
登った正面が拝殿で、殿前に立派な狛犬一対。
ここまでくるとまわりはうっそうとした社叢で、神さびた雰囲気に包まれています。
拝殿からは長谷の町と由比ガ浜が一望できます。


【写真 上(左)】 斜めからの拝殿
【写真 下(右)】 拝殿扁額
拝殿は切妻造銅板葺流れ向拝で、急な屋根勾配と照りのバランスがよく、棟には千木と鰹魚木をおいて引き締まったイメージ。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に本蟇股を置き、向拝見上げに社号扁額を掲げています。
拝殿背後に奥まった石垣上の山際には本殿があります。
こちらの様式は不明ですが青銅葺の棟に千木と鰹魚木をおき、照り気味の屋根のフォルムが秀麗。


【写真 上(左)】 本殿
【写真 下(右)】 秋葉神社への参道
俯瞰写真がなく位置関係が不明ですが、おそらく拝殿よこに五社神社、拝殿向かって右手の急な階段を登ると火防御守護の秋葉神社が御鎮座。
五社神社は明治20年5月、長谷寺の鎮守であった五社明神社(御祭神、神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀)を御遷座のお社です。


【写真 上(左)】 五所神社
【写真 下(右)】 五所神社の扁額


【写真 上(左)】 秋葉神社
【写真 下(右)】 秋葉神社の扁額
近くには川端康成の旧宅があり、小説「山の音」に登場する神社として描かれているとのこと。
境内には「当宮では御朱印は行っておりません」の掲示がありますが、筆者は大町の八雲神社にて拝受しています。
ただし、現在も授与されているかは不明です。

〔 甘縄神明宮の御朱印 〕

52.獅子吼山 清浄泉寺 高徳院(こうとくいん/鎌倉大仏)
公式Web
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市長谷4-2-28
浄土宗
御本尊:阿弥陀三尊
司元別当:
札所:鎌倉三十三観音霊場第23番、鎌倉六阿弥陀霊場第1番
鎌倉大仏は鎌倉唯一の国宝です。
「鎌倉大仏」の方が通りでいいですが、正式には大異山高徳院清浄泉寺を号し、大仏は高徳院の御本尊です。
鎌倉大仏(高徳院)については膨大な史料・資料がみつかるので、公式Web、『新編鎌倉志』 『新編相模國風土記稿』、文化遺産オンライン、山内掲示などに絞ってまとめます。
記事ネタも膨大なので、適宜端折っていきます。
鎌倉大仏の特徴については、こちらをご覧ください。
『吾妻鏡』などによると、鎌倉大仏は建長四年(1252年)8月に鋳造を始めた金銅の「八丈釈迦如来像」であるといい、文永元年(1264年)8月以前に完成とみられ、当初は大仏殿も備えていました。
しかし造立当時の史料に乏しく、尊像の(原型)作者すら特定されていません。
また、寺院の開基・開山も不詳です。
『吾妻鏡』の通常の書きぶりからすると、これほどの大事業を幕府が支援したとすると詳細な記述を残す筈ですが、大仏の造立開始について記すのみで、この点も鎌倉大仏のナゾを深める一因となっています。
鎌倉大仏の前身寺院については、別当であった高徳院からたどるのが有効です。
『新編相模國風土記稿』の「別当高徳院」の條には、天平年中(729-749年)に行基菩薩がこの地に浄泉寺を開基し、高座郡の国分寺との関係を示唆する記述があります。
全国の国分寺の大もとは大和国の東大寺(華厳宗)ですから、この説を信じると創立時は華厳宗系列ということになります。
じっさい、高徳院山内入口の石碑には「聖武帝艸創東三十三箇國總國分寺」と彫られていますが、『新編相模國風土記稿』では「往古の國分寺跡とするは非なり」と断じています。
さらに史料には「此地もと真言宗」とあり「建長寺持分」とあるので、真言宗から臨済宗建長寺末に転じた可能性があります。
『新編相模國風土記稿』は「【東鑑】に暦仁元年(1238年)、大佛造立の事を載せ、之より梵刹ありし事、初見なし、且舊は建長寺の持なりしと云へば、古より清浄泉寺の有しと云ふ疑べし」とし、「寺号を云はざれば、明證を得がたし、今本文起立の事、姑く寺伝に従ふ」として、前身寺院についてはサジを投げた感じの書きぶりとなっています。
(【建長寺過去帳】には「大佛開山、大素和尚諱は素一とあり。素一は中興開山なりと云ふ。」とあるようです。)
なお、『吾妻鏡』には、暦仁元年(1238年)、深沢の地(現・大仏所在地)にて僧・浄光の勧進により大仏堂建立が始められ、寛元元年(1243年)に開眼供養が行われ、大仏は木造であったという記述がありますが、上記の建長四年(1252年)造立開始の金銅の「八丈釈迦如来像」を現在の鎌倉大仏とし、「釈迦如来」は「阿弥陀如来」の誤記と解釈するのが定説です。
なお、現地掲示には源頼朝公の侍女・稲多野局(いたののつぼね)が発起し、僧・浄光の勧進で造ったとあります。
ときどき「大仏はお釈迦さまですか?」と訊く人がいますが、大仏の定義は「大きな仏像」なので、阿弥陀さまもいれば観音さまもいます。
→ 日本の主な大仏(Wikipedia)
ちなみに、奈良の大仏は毘盧遮那仏、牛久大仏は阿弥陀如来、上野大仏は釈迦如来です。
鎌倉大仏は阿弥陀如来とされていますが、釈迦如来、あるいは毘盧遮那仏としている史料もあります。
山内の与謝野晶子歌碑
かまくらや みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におはす 夏木立かな
では、鎌倉大仏は釈迦牟尼(釈迦如来)として詠みこまれています。
鎌倉公式観光ガイドWebには「大仏のところどころに金箔が残っているのをわずかに見ることができますが、つくられた当時は、これが全部に施されていたといいます。」とあります。
長谷の山裾の緑に映える黄金の大仏は、多くの人々の尊崇を集めたと思います。
大仏殿は嘉元三年(1305年)頃に倒壊し、元徳元年(1329年)再建したものの建武元年(1334年)に大風で倒壊。応安二年(1369年)にも大風で倒壊し以降は再建の記録がないとされ、以降は「露坐の大仏」となりました。
明応七年(1498年)の大地震で損壊との記録もあって、鎌倉大仏の歴史はまさに災害の歴史です。
鎌倉大仏は南北朝期から江戸前期にかけて建長寺の管理下に置かれていたといいます。
現地掲示によると、大仏殿、大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていたとのこと。
元禄十六年(1703年)の大地震で破損しましたが、正徳二年(1712年)に浅草の豪商・野島新左衛門(泰祐)から寄進を受け、正徳年間(1711-1716年)に増上寺祐天上人によって復興され、別当は新左衛門の法名から高徳院と命名されたといいます。
よって、臨済宗から浄土宗に転じたのは正徳年間(1711-1716年)とみる説があります。
祐天上人は浄土宗の名刹・光明寺の「奥之院」として位置づけたといい、享保十八年(1733年)大仏を復興し開眼供養を行った養国上人が、高徳院の初代住職となっています。
江戸時代末期まで、鎌倉大仏の別当・高徳院の御本尊は、惠心作とも伝わる長一尺五寸の阿弥陀如来木像であったとみられます。
つまり、山内には鎌倉大仏である阿弥陀如来金銅仏(露仏)と、別当高徳院の御本尊である阿弥陀如来木像が安されていたことになります。
山内には鎮守社である八幡・春日・雨寶童子三神合殿、秋葉社、天神社、辨天社、疱瘡神社が御鎮座され、神仏習合の様相を呈していたとみられます。
江戸時代初期には欧州からの宣教師や平戸商館長などが訪れているので、この当時から鎌倉の名所であったことがわかります。
安政六年(1859年)に横浜港が開港、外国人居留地の外国人の出向範囲が40km程に制限されたため、範囲内の鎌倉は行楽地として人気を集め、なかでも鎌倉大仏はマストスポットだったようです。
鎌倉大仏(国宝銅造阿弥陀如来坐像)は高徳院の御本尊で像高約11.3m、重量約121t の巨像です。
数々の災害に見舞われながらもほぼ造立当初の像容を保ち、わが国の仏教芸術史上すこぶる重要な価値を有することから国宝に指定されています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
大佛
大異山浄泉寺と号す。此所を深澤と云。大佛の坐像、長三丈五尺、膝の通りにて横五間半、袖口より指の末まで二尺七寸余あり。建長寺持分なり。
【東鏡】曰、暦仁元年(1238年)三月廿三日、相模國深澤里大佛殿の事始なり。僧浄光、尊卑緇素を勧請して、此営作を企つ。
同五月十八日、大佛の御頭擧奉る。周八丈あり。(中略)
寛元元年(1243年)六月十六日、深澤村に一宇の精舎を建立し、八丈餘の阿彌陀の像を安す。今日供養をのぶ。導師は、卿の僧正良信、讃衆十人、勧進の聖人浄光坊、此六年の間都鄙を勧進す。卑尊を奉加せずと云事なしとあり。是皆頼経将軍の時也。
又建長四年(1252年)八月十七日、深澤里にて釋迦如来の像を鋳奉ると有。宗尊親王の時なり。
今の銅佛是なりと云ふ、或云此銅像も何の頃にや亡失し、今の大佛は廬舎那佛なり、此佛を改め造りし来由は詳ならずと云ふ、今何れが是なるを知らず、暫く異同を注して、考證に備ふ(中略)
源親行【東関紀行】に、由比の浦に阿彌陀の大佛を作りたてまつる。事の起りを尋ぬるに、本は遠江國人浄光と云者有。過にし延應(1239-1240年)の比に関東尊卑を勧て佛像を作る。此阿彌陀は八丈の長、木像也とあり。按ずるに暦仁元年(1238年)に、浄光造作の像も八丈の阿彌陀佛とあり。延應は暦仁の次の年なり。所謂六年の内なれば【東鑑】に符合せり。其佛は何れの時か滅亡して、今の大佛は金銅廬遮那佛なり。【東鑑】に所謂、建長四年(1252年)に鋳たる佛か。堂なし。(中略)
【建長寺過去帳】に、大佛開山、大素和尚諱は素一とあり。素一は中興開山なりと云ふ。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(長谷村)大佛・獅子吼山(寺は大異山と号す)
清浄泉寺と号す、金堂の廬舎那仏なり(注釈略)
彌陀(木像長一尺二寸、天竺傳来と云ふ)を腹籠とす、抑当佛殿は沙門浄光普く募縁して営作を企て、暦仁元年(1238年)三月遂に此地に新造の事始あり 【東鏡】曰、暦仁元年(1238年)三月廿二日、相模國深澤里、大佛堂事始也、僧浄光令勧進、尊卑緇素、企此営作云々
五月大佛の妙好相始て成る 五月十八日、相模國深澤里大佛御頭奉擧之、周八丈也(中略)
寛元元年(1243年)六月落成して供養あり(寛元元年(1243年)六月十六日深澤村建立一宇精舎、安八丈餘阿彌陀像、今日展供養導師卿僧正良信、讃衆十人、勧進聖人浄光房、此六年之間勧進都鄙卑尊莫不奉加
此時造立の佛像は木像なり(注釈略)
建長四年(1252年)八月改て金銅の佛像を鑄る 【東鑑】曰、建長四年(1252年)八月十七日、今日、当彼岸第七日、深澤里奉鑄始金銅八丈釋迦如来像、按ずるに、是宗尊親王の時にして、今の銅佛是なりと云ふ、或云此銅像も何の頃にや亡失し、今の大佛は廬舎那佛なり、此佛を改め造りし来由は詳ならずと云ふ、今何れが是なるを知らず、暫く異同を注して、考證に備ふ(中略)
明應四年(1495年)八月由井濱の海水激奔して又佛殿破壊に及べり 其後はたゞ礎石のみを存して佛像は露座せり(中略)今に至て猶堂再建に及ばず(略)
古は建長寺の持なりしが今は別当を置て高徳院と云ふ
鎮守社 八幡・春日・雨寶童子三神を合祀す
秋葉社 天神社 辨天社 疱瘡神社
仁王門 獅子吼山の額を掲ぐ、
國分寺碑 聖武帝艸創東三十三箇國總國分寺と彫す、往古の國分寺跡とするは非なり、事は高徳院の條に辨ず
別当高徳院
浄土宗 材木座村光明寺末 此地もと真言宗、浄泉寺の舊趾にて其先天平年中(729-749年)行基浄泉寺を開基しけるに 其後星霜を経て明應年中(1492-1501年)廃寺となり
按ずるに所蔵に、正喜二年九月、勝壽院別當、權少都最信が記せし、清浄泉寺建立序次之記の写曰、艸創本願聖武帝也、天平九年(737年)丁丑三月、創建東國總國分寺、斯乃東之國分寺、建立之權輿也、内道場之本尊、釋迦・薬師・觀世音之三尊(中略)開山沙門行基菩薩、以本願皇帝・行基菩薩・良辨僧正・菩薩僧正之四哲、以称國分寺草創同心之四聖(中略)
按ずるに、今高座郡國分寺に、國分寺の舊蹟あり、彼條に詳なり、当寺を東國總國分寺と云、最非り、浮屠氏の妄誕往々此の如し、又按ずるに、【東鑑】に暦仁元年(1238年)、大佛造立の事を載せ、之より梵刹ありし事、初見なし、且舊は建長寺の持なりしと云へば、古より清浄泉寺の有しと云ふ疑べし、【注畫賛】に、文應元年(1260年)十月十一日、通状遣十箇所、所謂建長寺道隆、極楽寺良觀、大佛別当云々也、と見えたれば、其頃別当ありしと覚ゆれど、寺号を云はざれば、明證を得がたし、今本文起立の事、姑く寺伝に従ふ)
大佛のみ有しを近世正徳年間(1711-1716年)増上寺主顯譽祐天再興の志を発せしに江戸神田に在る商買、野島新左衛門祐天に帰依し、資財を捨て共に当寺を興立し、山号を獅子吼と改め寺号は清浄泉寺の舊に從ひ、宗旨を改て光明寺の末に屬す、故に祐天を中興の開祖とし、松参詮察を第二世とし新左衛門を中興の開基とす
本尊彌陀 木像長一尺五寸、惠心作を安ず、又同像(是も惠心作、座像五十五分)及び愛染(行基の作なり、宗尊親王、大佛傳前に一宇を建て、安ぜし像なりと云ふ)の像を置く(略)
■ 山内掲示(国宝鎌倉大佛因由)(抜粋)
この大佛像は阿弥陀仏である。源頼朝の侍女であったといわれる稲多野局(いたののつぼね)が発起し、僧浄光が勧進(資金集め)して造った。零細な民間の金銭を集積して成ったもので、国家や王侯が資金を出して作(ママ)ったものではない。
始めは木造で暦仁元年(1238年)に着工し六年間で完成したが、宝治元年(1247年)大風で倒れたので、再び資金を集め、建長四年(1252年)に至って現在の青銅の像を鋳造し、大仏殿を造って安置した。(中略)大仏殿は建武元年(1334年)と應安二年(1369年)とに大風に倒れ、その都度復興したが、明應七年(1498年)の海潮に流失以来は復興せず、露像として知られるに至った。(略)
■ 山内掲示(鎌倉市教育委員会)(抜粋)
高徳院本尊の「鋳造阿弥陀如来坐像」は鎌倉大仏とも呼ばれ、国宝に指定されています。
日本有数の銅造大仏で、建長4年(1252年)に鋳造を始めたと史料にみえる「金銅八丈釈迦如来像」がこの大仏であるとされています。
完成時期はわかっていませんが、文永5年(1268年)ごろまでには大仏殿も建てられていたと考えられ、管理していた寺院は大仏殿、大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていました。
大仏殿は災害により何度か倒壊し、その度に大仏の修理が行われたようです。(中略)
大仏は15世紀末以降、現在と同じように露坐となり、相次ぐ災害によって荒廃しました。
高徳院は、正徳二年(1712年)に増上寺の祐天上人、浅草の商人・野嶋新左衛門らが大仏の復興を発願して建立した寺院です。復興された大仏の開眼供養は、天文二年(1737年)に高徳院住職の養国上人によって行われ、今に至っています。
-------------------------
江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏にかけてはいつも観光客であふれています。
修学旅行では鎌倉大仏はマストらしく、シーズンには学生も多くみられて賑わいます。


【写真 上(左)】 賑わう紅葉の参道
【写真 下(右)】 めずらしく空いている参道
参道入口に「總國分寺」と刻まれた石碑。
参道は幅員のある石畳で、どこか神社(大社)の参道のようです。


【写真 上(左)】 「總國分寺」の石碑
【写真 下(右)】 仁王門への参道


【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 仁王門の扁額
すこし進むと仁王門。
切妻屋根銅板本瓦棒葺三間一戸の八脚門は、朱塗りの丸柱で風格があります。
両脇間に仁王尊を安置し、見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 門
【写真 下(右)】 手水舎
も少し進むと門で遮られ、左手に券売所と入場門があります。
むろん拝観料が必要です。
門を入ってすぐに手水舎。

高徳院の山内は広いですがシンプルで、右手正面に鎌倉大仏、その右手に授与所&売店、大仏の裏手に観月堂と右手奥に与謝野晶子の歌碑があります。


【写真 上(左)】 山内-1
【写真 下(右)】 山内-2


【写真 上(左)】 国宝の碑
【写真 下(右)】 正面から
大仏は台座に座し、衣を通肩にまとい、上品上生の定印を結ばれています。


【写真 上(左)】 斜めから
【写真 下(右)】 背面
来迎印ではなく定印を結んでいるので密教系の尊像とする説もみられますが、浄土宗でも定印阿弥陀如来像はいくらも見られるので、筆者的にはこの説は疑問です。
整った面立ちで軽くうつむき、イケメンの大仏として知られています。
別料金ですが、大仏の胎内を拝観することもできます。


【写真 上(左)】 六字御名号の碑
【写真 下(右)】 観月堂-1
観月堂は、朝鮮王宮にあったものを大正13年山一合資会社(後の山一證券)社長だった杉野喜精が寄贈した建物です。
江戸幕府2代将軍徳川秀忠公が所持していたとされる聖観世音菩薩像を安置し、鎌倉三十三観音霊場第23番の札所となっています。
切妻造?本瓦葺の風格ある建物ですが、柵があるので向拝まで近づくことはできません。


【写真 上(左)】 観月堂-2
【写真 下(右)】 観音霊場札所標
御朱印は大仏の向かって右の授与所にて拝受しました。
オリジナル御朱印帳の頒布があり、現在は両面の絵御朱印も授与されているようです。
なお、公式Webによると御朱印帳書入れは15時までのようです。
〔 高徳院の御朱印 〕

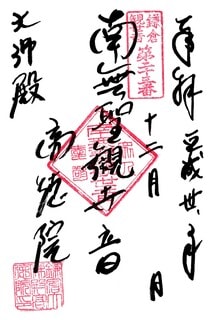
【写真 上(左)】 御本尊(鎌倉大仏)の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-19 (C.極楽寺口-2)へつづく。
【 BGM 】
■ KOKIA - ありがとう… (KOKIA's Version)
■ 中山美穂 - ただ泣きたくなるの
■ Kalafina - far on the water(LIVE)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)
■ 同-16 (B.名越口-11)
■ 同-17 (B.名越口-12)から。
市内各所に寺社が立地する鎌倉市ですが、鎌倉駅西の市役所通りから由比ヶ浜にかけての御成町、和田塚、笹目町エリアは一種の寺社空白地帯となっています。
ここからは西に転じて長谷、極楽寺、腰越方面の寺社を「極楽寺口」としてくくりまとめていきます。
51.甘縄神明宮(あまなわしんめいぐう)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市長谷1ー12ー1
主祭神:天照大御神
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社
元別当:甘縄院(臨済宗妙心寺末)
甘縄神明宮は、甘縄神明神社とも呼ばれ鎌倉市最古の神社とされています。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。
甘縄神明宮は、和銅三年(710年)行基菩薩の草創、染谷太郎太夫時忠の創建と伝わり、鎌倉最古のお社といわれます。
「鎌倉史跡・寺社データベース」様によると、「染屋太郎大夫時忠邸址碑」(鎌倉市長谷2-4-6)には、「染屋太郎太夫時忠は藤原鎌足の玄孫にあたり、南都の東大寺・良弁僧正の父であり、文武天皇の御時より聖武天皇の神亀年間に至る間、鎌倉に居住し、関東八国の僧追捕使となって、東夷を鎮め、由比の長者と称された(中略)甘縄新明宮の別当甘縄院は時忠の開基であるという」との旨の碑文がみえるとのこと。
東大寺の開山・良辨僧正(689-774年)の父で、関東八国の僧追捕使とは相当な大物です。
「鎌倉むかし物語」様の「由比の長者」では、由井の里の長者・染屋太郎太夫時忠の娘が鷲にさらわれたという逸話が紹介されています。
良辨僧正も幼い頃鷲にさらわれたという逸話が残り、なんらかの関連を示唆しています。
『新編相模國風土記稿』にも、甘縄神明宮の別当神興山甘縄院は、天平年中(729-749年)行基の草創にして開基は染谷太郎太夫時忠とあります。
『鎌倉市史 社寺編』には、源頼義公(河内源氏2代、988-1075年)が相模守として下向の折に上野介直方の女を娶り、当社に祈って八幡太郎義家公を甘縄の地に生んだと伝えるとあります。
平上野介直方は平忠常の乱(長元元年(1028年))の際、討伐に赴いた桓武平氏国香流の軍事貴族で、鎌倉に所領を得て居館を構えたといいます。
長元三年(1030年)、源頼信公・頼義公父子は忠常を降伏させ、頼義公は長元九年(1036年)相模守に任ぜられ相模国に下向しました。
当時、鎌倉には平直方が拠っていましたが、直方は自身が平定できなかった忠常を頼義公が降伏させたことを尊んで、息女を輿入れさせ、鎌倉・大蔵の拠点と在鎌倉の郎党を譲り渡したといいます。
頼義公は直方の息女とのあいだに、八幡太郎義家公、賀茂次郎義綱公、新羅三郎義光公の3人の子息をもうけました。
通説では、義家公は河内國石川郡壺井(現・大阪府羽曳野市)の香炉峰の館に生まれたとされますが、『鎌倉市史 社寺編』には「(義家公は)当社(甘縄神明宮)に祈って八幡太郎義家を甘縄の地に生んだと伝える。」とあります。
また、『神奈川県神社誌』には、「康平六年(1063年)(頼義公が)当社を修復、義家も永保元年(1081年)に修復を加えた」とあります。
八幡太郎義家公生誕の地とすると、そこは源家の聖地です。
頼朝公は甘縄神明宮を尊崇してしばしば参詣し、文治二年(1186年)10月には社殿を修理監督し、落慶の行事に自ら臨んでいます。
『吾妻鏡』には、北条政子や3代将軍源実朝公の参詣も記されています。
北条政子は鶴岳宮(鶴岡八幡宮)と甘縄明神(甘縄神明宮)を同日に参詣しています。(「 文治五年(1189年)十月十七日、御臺所御参詣鶴岳宮幷甘縄明神」)
『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)には「是(甘縄神明宮)は古へより伊勢の別宮」とあります。
『承久記』には「日本国の帝位は伊勢天照太神・八幡大菩薩の御計ひ」と記され、伊勢の天照太神、八幡大菩薩(八幡神)はすこぶる重要な神として尊崇されていたことがわかります。
気になるのは実朝公参詣の條に「建保三年(1215年)四月二日、令詣甘縄神明幷日吉別宮等給」とあることです。
つまり、実朝公は甘縄の甘縄神明宮と日吉別宮(山王社)を同時に詣でています。
『新編相模國風土記稿』の(甘縄)山王社の條には「大佛陸奥守貞直の勧請と云ふ」とあります。
大佛貞直(元弘三年(1333年没)は鎌倉末期の北条一門で、実朝公(1192-1219年)とは時代が合いません。
実朝公は大佛貞直勧請前の日吉別宮(山王社)に参詣していたことになり、この点は『風土記稿』の筆者も気になったらしく「思ふに(山王)社は古くより、此に在て、貞直が再興勧請せしなるべし」との説を展開しています。
甘縄神明宮周辺には、安達藤九郎盛長の屋敷があったとされます。(異説あり)
安達氏は藤原氏魚名(山蔭)流ともされますが、安達盛長の父は小野田兼広とも小野田兼盛とも伝わり、小野田姓のようですが詳細不明です。
安達盛長の兄は藤原遠兼とされ、父親の小野田姓から藤原姓に復姓も考えられますが詳細不明。
しかも弟の盛長は安達姓を名乗っており、どうも整理がつきません。
また、藤原遠兼の子は足立遠元で、土着した武蔵国足立郡から名乗ったとされるので、安達氏、足立氏の系譜はわかりにくくなっています。
安達盛長は生え抜きの東国武将とはいい難いですが、源頼朝公の乳母・比企尼の長女・丹後内侍を妻とし、旗揚げ前から源頼朝公の信任を得ていたと伝わります。
丹後内侍はもとは京で二条院に女房として仕え、官吏や右筆の招聘窓口となっていたとみられ、頼朝公の初期右筆・藤原邦通は、丹後内侍のルートで招かれたといいます。
一説には、伊豆で頼朝公と北条政子の仲をとり持ったのは盛長だとも。
治承四年(1180年)8月の頼朝公挙兵に従い、石橋山の戦いの後に頼朝公とともに安房に逃れ、下総国の豪族・千葉常胤を説得して味方につけたとされます。
頼朝公鎌倉入りののち、元暦元年(1184年)頃から上野国奉行人となり、文治五年(1189年)奥州合戦に従軍して戦功をあげ、陸奥国安達郡と出羽国大曽根荘を賜わりました。
盛長は、『吾妻鏡』では”藤九郎(盛長)”と記されることが多く、だとすると安達の名字は所領の”安達郡”由来かもしれません。
甥とされる足立遠元は武蔵国足立郡に確かな拠点を築いており、代表的な武蔵武士として知られています。
盛長と足立遠元の関係はよくわかりませんが、遠元は武官、盛長は頼朝公側近として協力しつつ頼朝公を支えていたのかもしれません。
幕府開府後も頼朝公の信任厚く、甘縄にあった盛長邸を頼朝公がしばしば訪れた記録が残ります。
文治二年(1186年)6月、丹後内侍罹病の際、頼朝公は盛長邸に丹後内侍を見舞っているので、盛長・丹後内侍夫婦と頼朝公の私的なつながりが強かったかと。
『吾妻鏡』には「還向便路藤九郎盛長屋敷」という記載があり、「還向」は神仏に参詣して帰ること、「便路」は便利な道を指すので、盛長邸への頼朝公来訪は甘縄神明宮参詣を兼ねた側面もあったかと思います。
正治元年(1199年)1月の頼朝公逝去後、出家して蓮西と名乗りましたが、同年4月、2代将軍・源頼家公の宿老として十三人の合議制の一人となり幕政に参画しています。
梶原景時の弾劾(梶原景時の変)でも大きな役割を担ったとされますが、生涯無位無官のままとみられています。
「神明様」(しんめいさま)と呼ばれ、長谷の鎮守として鎌倉の庶民にも尊崇された甘縄神明宮は、明治6年村社に列格し、明治20年、長谷寺の鎮守であった五社明神社(神明・春日・白山・稲荷・天神)を合祀しています。
関東大震災で本殿は半潰、拝殿は全潰しましたが、昭和12年に再建されています。
なお、別当の神輿山甘縄院は山下にあり、当初は神輿山円徳寺を号しました。
和銅三年(710年)八月行基の草創といい、染屋時忠が山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立開基と伝わります。
京都妙心寺末の臨済宗寺院で御本尊は地蔵菩薩。
中興は京都妙心寺の独園和尚(宝永六年(1709年)寂)で、伝来の義家公木像を修復したといいます。
明治の神仏分離により甘縄院は廃されています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
甘縄明神
甘(甘或作海女)縄明神は、佐佐目谷の西、路の北にある茂林なり。天照大神を勧請す。神主は小池氏也。【東鑑】に、文治二年(1186年)正月二日、二品(頼朝)幷に御臺所、甘縄神明の宮に御参とあり。又甘縄明神奉幣の事、往々見へたり。里俗或は誤てたまなはと云者あり。(中略)此地より西の方は長谷村也。東北の山に隋て、無量寺谷まで甘縄の内なり。
塔辻
里俗の云、由井長者太夫時忠と云者、三歳の児を鷲につかまれ、方々尋求て、道路に棄たる骨肉のある所ごとに、是や我子の骨肉ならんかとて、菩提の為に立たる石塔也。(中略)大織冠の玄孫に、染谷太郎太夫時忠、南都良辨の父也。文武天皇の御宇より、聖武天皇の御宇に至るまで鎌倉に居住し、東八箇國の總追捕使となりて、東夷を鎮むとあり。是ならんか。然れども未詳。良辨の父とはいへども、【元亨釋書】にも不載。【釋書】に、良辨は近州志賀里人、或は相州の人とも云と有。又鷲につかまれし事もあれば、相似たるにや。
藤九郎盛長屋敷
甘縄明神の前、東の方を云。【東鑑】に、治承四年(1180年)十二月廿日、武衛御行始めとして、藤九郎盛長が、甘縄の家に入御し給ふとあり。其後往々見へたり。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
甘縄神明宮
佐々目が谷の西の路北に、樹木茂りたる社地なり。是は古へより伊勢の別宮と称し、【東鑑】にも記せり。神主小池氏。文治二年(1186年)正月二日、二品(頼朝)並に御臺所、甘縄神明宮御参とあり。其後も奉幣の事往々出たり。地名を甘縄と号するゆへ、宮号にも古く唱へ来れり。又同年十月廿日甘縄神明寶殿修理せられ、今日四面に荒垣をゆひ、幷鳥居を建らる。盛長の沙汰とし、二品監臨と給ふ。(以下略)
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
神明宮
【東鑑】に伊勢別宮とある是なり 里俗は甘縄明神と唱ふ神躰は義家の守護神と云伝へ秘して開扉を許さず、義家の木像をも安ぜり、長一尺五寸、束帯の坐像なり、文治二年(1186年)正月頼朝当社に参詣あり
【東鑑】曰、文治二年(1186年)正月二日、二品幷御臺所、御参甘縄神明宮、以御還向便路藤九郎盛長屋敷 是歳十月社殿を修理し(中略)文治五年(1189年)十月十七日、御臺所御参詣鶴岳宮幷甘縄明神(中略)建保三年(1215年)四月實朝参詣あり
建保三年(1215年)四月二日、令詣甘縄神明幷日吉別宮等給、御還向之次、入御安達右衛門尉景盛家、今当村の鎮守にして年々九月十六日神事あり。
末社 疱瘡神 稲荷四
別当甘縄院
神興山と号す、臨済宗京都妙心寺末 本尊地蔵を安ず、天平年中(729-749年)行基の草創にして開基は染谷太郎太夫時忠と云ふ、境内より江山臨眺の景尤佳なり
山王社
光則寺持 大佛陸奥守貞直が勧請と云ふ 按ずるに、【東鑑】建保三年(1215年)の條に、甘縄神明幷日吉別宮等に、参詣せしめ、還路の次、安達右衛門尉景盛が家に、入御ありと見ゆ、景盛が亭跡、神明社の東にあり、さては日吉の別宮と云ふ、当社なるべし、されど大佛貞直が、勧請と云ふ、合期せず、貞直は、北条陸奥守宣時が三男、民部少輔宗泰が子にて、元弘三年(1333年)五月、由井濱の戦に討死す、建保を距る事、百年に過たりさては時代合せず、思ふに社は古くより、此に在て、貞直が再興勧請せしなるべし
■ 神奈川県神社誌(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
祭神 天照大御神
境内社 五社明神(天照大御神 倉稲魂命 伊邪那美命 菅原道真公) 秋葉社
社殿 本殿(神明造銅板葺)一棟一宇 幣殿 拝殿(入母屋造銅板葺・千木・鰹魚木・向拝付)二棟一宇
境内坪数 127.04坪
『相州鎌倉郡神輿山甘縄寺神明宮縁起略』(正徳二年(1712年)銘)によれば、和銅三年(710年)八月行基の草創になり、染屋太郎時忠が山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立したことにはじまるという。
また源頼義が当社に祈って八幡太郎義家を当地に生み、康平六年(1063年)当社を修復、義家も永保元年(1081年)に修復を加えたという。
『吾妻鏡』によれば、伊勢別宮として源頼朝が崇敬し、文治二年(1186年)十月社殿を修理し、四面に荒垣及び鳥居を建て、また建久五年(1194年)までに三度参詣している。夫人政子は二度、実朝も一度参詣している。
『相模風土記』には「神明宮、里俗甘縄明神と唱う」「別当臨済宗甘縄院」とある。
明治維新の神仏分離により、別当甘縄院は廃絶し、神明宮は明治六年十二月村社に列格され、明治二十年五月、五社明神社を合併し、明治四十年四月神饌幣帛料供進神社に指定された。
昭和七年社号を甘縄神明神社と改称した。旧社殿は大正十二年の関東大震災に倒潰し、現社殿は昭和十二年九月新築復興した。長谷区の氏神社である。
宝物 神輿・一基、義家座像・一体
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
甘縄神明神社
もとは神明社或は神明宮と称したが昭和七年九月二十一日、今の名に改めた。
祭神は天照大御神のほか倉稲魂命・伊邪那美命・武甕槌命・菅原道真公を配祀する。例祭九月十四日。元指定村社。長谷の鎮守。境内地127.04坪。
本殿・拝殿・摂社稲荷社・社務所・神輿庫等あり。(中略)
勧請年月未詳。『吾妻鏡』によれば、伊勢別宮であり、源頼朝は三度、政子は二度、実朝は一度参詣しており、文治二年(1186年)十月二十四日には社殿を修理し、四面に荒垣及び鳥居を建て、頼朝自らその場に臨んだことがわかる。
いま社蔵する『相州鎌倉郡神輿山甘縄寺神明宮縁起略』の写しによれば、ここは和銅三年(710年)八月行基の草創で、染屋時忠が山上に神明宮、麓に神輿山円徳寺を建立し、後源頼義が相模守として下向、上野介直方の女をめとり、当社に祈って八幡太郎義家を甘縄の地に生んだと伝える。
また中興は宝永六年(1709年)六月二十六日に寂した京都妙心寺の独園和尚で、社殿・寺舎を造替し、弟子瑞峯祖堂を住持とし、また義家の像を修復させたという。(中略)
この寺を別当甘縄院といい、その本尊は地蔵であった。神仏分離により寺は廃滅したという。いまは寺の痕跡もない。
明治二十年五月二十五日、長谷寺の鎮守であった五社明神社、祭神は神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀している。
大正十二年の震災で本殿半潰、拝殿全潰し、昭和十二年九月新築した。
甘縄神明神社がここにまつられた理由は、此の地が大庭御厨の飛地であったか、或は大庭氏の一族梶原氏、鎌倉氏などの地であったことによると思われるが、(以下略)
■ 境内掲示(甘縄神明神社略誌)(抜粋)
御祭神
天照大神
伊邪那岐尊(白山) 倉稲魂命(稲荷)
武甕槌命(春日) 菅原道真公(天神)
御由緒
和銅三年(710年) 染屋太郎太夫時忠の創建です
永保元年(1081年) 源義家公が社殿を再建せらる
源頼朝公政子の方實朝公など武家の崇敬が篤く 古来伊勢別家と尊称せられている鎌倉で最も古い神社です。
社殿の裏山は御輿ヶ嶽(見越ヶ嶽とも書く)と云い古くから歌によまれています
源頼義は相模守として下向の節 当宮に祈願し一子八幡太郎義家が生まれたと伝えられています
都にははや吹ぬらし 鎌倉の御輿ヶ崎 秋の初風
-------------------------
江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏高徳院にかけては、平日も観光客で賑わう鎌倉きっての観光スポットです。
しかし「長谷観音前」から鎌倉駅方面への神奈川県道311号鎌倉葉山線(旧大町大路)に入る観光客は多くはありません。
源氏や頼朝公とふかいゆかりをもつ甘縄神明宮ですが、訪れる観光客はさほど多くないとみられます。
実際、筆者の参拝時も「長谷」駅から大仏にかけてはかなりの雑踏でしたが、甘縄神明宮は終始筆者のみの参拝でした。


【写真 上(左)】 県道からの参道
【写真 下(右)】 社号標-1
県道から目立たない路地を山側に入るので、知らない観光客はまず気づきません。
県道沿いの木の社号標の文字は消えかかっていますが、かろうじて「長谷鎮守 甘縄神明宮」と読めます。(Web記事によるといまは新しくなっている模様。)

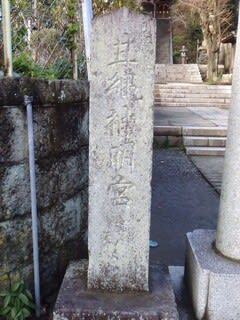
【写真 上(左)】 鳥居
【写真 下(右)】 社号標-2


【写真 上(左)】 参道-1
【写真 下(右)】 参道-2
民家の間を進む参道の正面に石造の神明鳥居、その横にも社号標があります。
鳥居をくぐった右手にさらに社号標があり、ここから石段まじりの参道が伸びています。
ひとつめの石段右手には鎌倉町青年団による「安達盛長邸址」の石碑。
参道脇の「玉縄桜」は有名なようで、ソメイヨシノより早く咲くそうです。
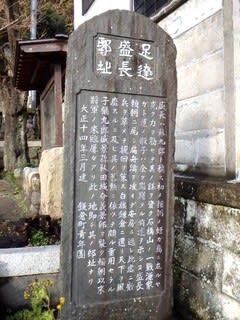

【写真 上(左)】 「安達盛長邸址」の石碑
【写真 下(右)】 手水舎


【写真 上(左)】 参道-3
【写真 下(右)】 神輿庫
その先の左手に立派な手水舎。
石灯籠一対を抜けると急な石段がはじまります。
階段上り口の左手には8代執権・北条時宗公産湯・二條公爵愛用の井があり、子宝や子供の健やかな成長に御利益があるそうです。


【写真 上(左)】 参道-4
【写真 下(右)】 拝殿
登った正面が拝殿で、殿前に立派な狛犬一対。
ここまでくるとまわりはうっそうとした社叢で、神さびた雰囲気に包まれています。
拝殿からは長谷の町と由比ガ浜が一望できます。


【写真 上(左)】 斜めからの拝殿
【写真 下(右)】 拝殿扁額
拝殿は切妻造銅板葺流れ向拝で、急な屋根勾配と照りのバランスがよく、棟には千木と鰹魚木をおいて引き締まったイメージ。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に本蟇股を置き、向拝見上げに社号扁額を掲げています。
拝殿背後に奥まった石垣上の山際には本殿があります。
こちらの様式は不明ですが青銅葺の棟に千木と鰹魚木をおき、照り気味の屋根のフォルムが秀麗。


【写真 上(左)】 本殿
【写真 下(右)】 秋葉神社への参道
俯瞰写真がなく位置関係が不明ですが、おそらく拝殿よこに五社神社、拝殿向かって右手の急な階段を登ると火防御守護の秋葉神社が御鎮座。
五社神社は明治20年5月、長谷寺の鎮守であった五社明神社(御祭神、神明・春日・白山・稲荷・天神を合祀)を御遷座のお社です。


【写真 上(左)】 五所神社
【写真 下(右)】 五所神社の扁額


【写真 上(左)】 秋葉神社
【写真 下(右)】 秋葉神社の扁額
近くには川端康成の旧宅があり、小説「山の音」に登場する神社として描かれているとのこと。
境内には「当宮では御朱印は行っておりません」の掲示がありますが、筆者は大町の八雲神社にて拝受しています。
ただし、現在も授与されているかは不明です。

〔 甘縄神明宮の御朱印 〕

52.獅子吼山 清浄泉寺 高徳院(こうとくいん/鎌倉大仏)
公式Web
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市長谷4-2-28
浄土宗
御本尊:阿弥陀三尊
司元別当:
札所:鎌倉三十三観音霊場第23番、鎌倉六阿弥陀霊場第1番
鎌倉大仏は鎌倉唯一の国宝です。
「鎌倉大仏」の方が通りでいいですが、正式には大異山高徳院清浄泉寺を号し、大仏は高徳院の御本尊です。
鎌倉大仏(高徳院)については膨大な史料・資料がみつかるので、公式Web、『新編鎌倉志』 『新編相模國風土記稿』、文化遺産オンライン、山内掲示などに絞ってまとめます。
記事ネタも膨大なので、適宜端折っていきます。
鎌倉大仏の特徴については、こちらをご覧ください。
『吾妻鏡』などによると、鎌倉大仏は建長四年(1252年)8月に鋳造を始めた金銅の「八丈釈迦如来像」であるといい、文永元年(1264年)8月以前に完成とみられ、当初は大仏殿も備えていました。
しかし造立当時の史料に乏しく、尊像の(原型)作者すら特定されていません。
また、寺院の開基・開山も不詳です。
『吾妻鏡』の通常の書きぶりからすると、これほどの大事業を幕府が支援したとすると詳細な記述を残す筈ですが、大仏の造立開始について記すのみで、この点も鎌倉大仏のナゾを深める一因となっています。
鎌倉大仏の前身寺院については、別当であった高徳院からたどるのが有効です。
『新編相模國風土記稿』の「別当高徳院」の條には、天平年中(729-749年)に行基菩薩がこの地に浄泉寺を開基し、高座郡の国分寺との関係を示唆する記述があります。
全国の国分寺の大もとは大和国の東大寺(華厳宗)ですから、この説を信じると創立時は華厳宗系列ということになります。
じっさい、高徳院山内入口の石碑には「聖武帝艸創東三十三箇國總國分寺」と彫られていますが、『新編相模國風土記稿』では「往古の國分寺跡とするは非なり」と断じています。
さらに史料には「此地もと真言宗」とあり「建長寺持分」とあるので、真言宗から臨済宗建長寺末に転じた可能性があります。
『新編相模國風土記稿』は「【東鑑】に暦仁元年(1238年)、大佛造立の事を載せ、之より梵刹ありし事、初見なし、且舊は建長寺の持なりしと云へば、古より清浄泉寺の有しと云ふ疑べし」とし、「寺号を云はざれば、明證を得がたし、今本文起立の事、姑く寺伝に従ふ」として、前身寺院についてはサジを投げた感じの書きぶりとなっています。
(【建長寺過去帳】には「大佛開山、大素和尚諱は素一とあり。素一は中興開山なりと云ふ。」とあるようです。)
なお、『吾妻鏡』には、暦仁元年(1238年)、深沢の地(現・大仏所在地)にて僧・浄光の勧進により大仏堂建立が始められ、寛元元年(1243年)に開眼供養が行われ、大仏は木造であったという記述がありますが、上記の建長四年(1252年)造立開始の金銅の「八丈釈迦如来像」を現在の鎌倉大仏とし、「釈迦如来」は「阿弥陀如来」の誤記と解釈するのが定説です。
なお、現地掲示には源頼朝公の侍女・稲多野局(いたののつぼね)が発起し、僧・浄光の勧進で造ったとあります。
ときどき「大仏はお釈迦さまですか?」と訊く人がいますが、大仏の定義は「大きな仏像」なので、阿弥陀さまもいれば観音さまもいます。
→ 日本の主な大仏(Wikipedia)
ちなみに、奈良の大仏は毘盧遮那仏、牛久大仏は阿弥陀如来、上野大仏は釈迦如来です。
鎌倉大仏は阿弥陀如来とされていますが、釈迦如来、あるいは毘盧遮那仏としている史料もあります。
山内の与謝野晶子歌碑
かまくらや みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におはす 夏木立かな
では、鎌倉大仏は釈迦牟尼(釈迦如来)として詠みこまれています。
鎌倉公式観光ガイドWebには「大仏のところどころに金箔が残っているのをわずかに見ることができますが、つくられた当時は、これが全部に施されていたといいます。」とあります。
長谷の山裾の緑に映える黄金の大仏は、多くの人々の尊崇を集めたと思います。
大仏殿は嘉元三年(1305年)頃に倒壊し、元徳元年(1329年)再建したものの建武元年(1334年)に大風で倒壊。応安二年(1369年)にも大風で倒壊し以降は再建の記録がないとされ、以降は「露坐の大仏」となりました。
明応七年(1498年)の大地震で損壊との記録もあって、鎌倉大仏の歴史はまさに災害の歴史です。
鎌倉大仏は南北朝期から江戸前期にかけて建長寺の管理下に置かれていたといいます。
現地掲示によると、大仏殿、大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていたとのこと。
元禄十六年(1703年)の大地震で破損しましたが、正徳二年(1712年)に浅草の豪商・野島新左衛門(泰祐)から寄進を受け、正徳年間(1711-1716年)に増上寺祐天上人によって復興され、別当は新左衛門の法名から高徳院と命名されたといいます。
よって、臨済宗から浄土宗に転じたのは正徳年間(1711-1716年)とみる説があります。
祐天上人は浄土宗の名刹・光明寺の「奥之院」として位置づけたといい、享保十八年(1733年)大仏を復興し開眼供養を行った養国上人が、高徳院の初代住職となっています。
江戸時代末期まで、鎌倉大仏の別当・高徳院の御本尊は、惠心作とも伝わる長一尺五寸の阿弥陀如来木像であったとみられます。
つまり、山内には鎌倉大仏である阿弥陀如来金銅仏(露仏)と、別当高徳院の御本尊である阿弥陀如来木像が安されていたことになります。
山内には鎮守社である八幡・春日・雨寶童子三神合殿、秋葉社、天神社、辨天社、疱瘡神社が御鎮座され、神仏習合の様相を呈していたとみられます。
江戸時代初期には欧州からの宣教師や平戸商館長などが訪れているので、この当時から鎌倉の名所であったことがわかります。
安政六年(1859年)に横浜港が開港、外国人居留地の外国人の出向範囲が40km程に制限されたため、範囲内の鎌倉は行楽地として人気を集め、なかでも鎌倉大仏はマストスポットだったようです。
鎌倉大仏(国宝銅造阿弥陀如来坐像)は高徳院の御本尊で像高約11.3m、重量約121t の巨像です。
数々の災害に見舞われながらもほぼ造立当初の像容を保ち、わが国の仏教芸術史上すこぶる重要な価値を有することから国宝に指定されています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
大佛
大異山浄泉寺と号す。此所を深澤と云。大佛の坐像、長三丈五尺、膝の通りにて横五間半、袖口より指の末まで二尺七寸余あり。建長寺持分なり。
【東鏡】曰、暦仁元年(1238年)三月廿三日、相模國深澤里大佛殿の事始なり。僧浄光、尊卑緇素を勧請して、此営作を企つ。
同五月十八日、大佛の御頭擧奉る。周八丈あり。(中略)
寛元元年(1243年)六月十六日、深澤村に一宇の精舎を建立し、八丈餘の阿彌陀の像を安す。今日供養をのぶ。導師は、卿の僧正良信、讃衆十人、勧進の聖人浄光坊、此六年の間都鄙を勧進す。卑尊を奉加せずと云事なしとあり。是皆頼経将軍の時也。
又建長四年(1252年)八月十七日、深澤里にて釋迦如来の像を鋳奉ると有。宗尊親王の時なり。
今の銅佛是なりと云ふ、或云此銅像も何の頃にや亡失し、今の大佛は廬舎那佛なり、此佛を改め造りし来由は詳ならずと云ふ、今何れが是なるを知らず、暫く異同を注して、考證に備ふ(中略)
源親行【東関紀行】に、由比の浦に阿彌陀の大佛を作りたてまつる。事の起りを尋ぬるに、本は遠江國人浄光と云者有。過にし延應(1239-1240年)の比に関東尊卑を勧て佛像を作る。此阿彌陀は八丈の長、木像也とあり。按ずるに暦仁元年(1238年)に、浄光造作の像も八丈の阿彌陀佛とあり。延應は暦仁の次の年なり。所謂六年の内なれば【東鑑】に符合せり。其佛は何れの時か滅亡して、今の大佛は金銅廬遮那佛なり。【東鑑】に所謂、建長四年(1252年)に鋳たる佛か。堂なし。(中略)
【建長寺過去帳】に、大佛開山、大素和尚諱は素一とあり。素一は中興開山なりと云ふ。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(長谷村)大佛・獅子吼山(寺は大異山と号す)
清浄泉寺と号す、金堂の廬舎那仏なり(注釈略)
彌陀(木像長一尺二寸、天竺傳来と云ふ)を腹籠とす、抑当佛殿は沙門浄光普く募縁して営作を企て、暦仁元年(1238年)三月遂に此地に新造の事始あり 【東鏡】曰、暦仁元年(1238年)三月廿二日、相模國深澤里、大佛堂事始也、僧浄光令勧進、尊卑緇素、企此営作云々
五月大佛の妙好相始て成る 五月十八日、相模國深澤里大佛御頭奉擧之、周八丈也(中略)
寛元元年(1243年)六月落成して供養あり(寛元元年(1243年)六月十六日深澤村建立一宇精舎、安八丈餘阿彌陀像、今日展供養導師卿僧正良信、讃衆十人、勧進聖人浄光房、此六年之間勧進都鄙卑尊莫不奉加
此時造立の佛像は木像なり(注釈略)
建長四年(1252年)八月改て金銅の佛像を鑄る 【東鑑】曰、建長四年(1252年)八月十七日、今日、当彼岸第七日、深澤里奉鑄始金銅八丈釋迦如来像、按ずるに、是宗尊親王の時にして、今の銅佛是なりと云ふ、或云此銅像も何の頃にや亡失し、今の大佛は廬舎那佛なり、此佛を改め造りし来由は詳ならずと云ふ、今何れが是なるを知らず、暫く異同を注して、考證に備ふ(中略)
明應四年(1495年)八月由井濱の海水激奔して又佛殿破壊に及べり 其後はたゞ礎石のみを存して佛像は露座せり(中略)今に至て猶堂再建に及ばず(略)
古は建長寺の持なりしが今は別当を置て高徳院と云ふ
鎮守社 八幡・春日・雨寶童子三神を合祀す
秋葉社 天神社 辨天社 疱瘡神社
仁王門 獅子吼山の額を掲ぐ、
國分寺碑 聖武帝艸創東三十三箇國總國分寺と彫す、往古の國分寺跡とするは非なり、事は高徳院の條に辨ず
別当高徳院
浄土宗 材木座村光明寺末 此地もと真言宗、浄泉寺の舊趾にて其先天平年中(729-749年)行基浄泉寺を開基しけるに 其後星霜を経て明應年中(1492-1501年)廃寺となり
按ずるに所蔵に、正喜二年九月、勝壽院別當、權少都最信が記せし、清浄泉寺建立序次之記の写曰、艸創本願聖武帝也、天平九年(737年)丁丑三月、創建東國總國分寺、斯乃東之國分寺、建立之權輿也、内道場之本尊、釋迦・薬師・觀世音之三尊(中略)開山沙門行基菩薩、以本願皇帝・行基菩薩・良辨僧正・菩薩僧正之四哲、以称國分寺草創同心之四聖(中略)
按ずるに、今高座郡國分寺に、國分寺の舊蹟あり、彼條に詳なり、当寺を東國總國分寺と云、最非り、浮屠氏の妄誕往々此の如し、又按ずるに、【東鑑】に暦仁元年(1238年)、大佛造立の事を載せ、之より梵刹ありし事、初見なし、且舊は建長寺の持なりしと云へば、古より清浄泉寺の有しと云ふ疑べし、【注畫賛】に、文應元年(1260年)十月十一日、通状遣十箇所、所謂建長寺道隆、極楽寺良觀、大佛別当云々也、と見えたれば、其頃別当ありしと覚ゆれど、寺号を云はざれば、明證を得がたし、今本文起立の事、姑く寺伝に従ふ)
大佛のみ有しを近世正徳年間(1711-1716年)増上寺主顯譽祐天再興の志を発せしに江戸神田に在る商買、野島新左衛門祐天に帰依し、資財を捨て共に当寺を興立し、山号を獅子吼と改め寺号は清浄泉寺の舊に從ひ、宗旨を改て光明寺の末に屬す、故に祐天を中興の開祖とし、松参詮察を第二世とし新左衛門を中興の開基とす
本尊彌陀 木像長一尺五寸、惠心作を安ず、又同像(是も惠心作、座像五十五分)及び愛染(行基の作なり、宗尊親王、大佛傳前に一宇を建て、安ぜし像なりと云ふ)の像を置く(略)
■ 山内掲示(国宝鎌倉大佛因由)(抜粋)
この大佛像は阿弥陀仏である。源頼朝の侍女であったといわれる稲多野局(いたののつぼね)が発起し、僧浄光が勧進(資金集め)して造った。零細な民間の金銭を集積して成ったもので、国家や王侯が資金を出して作(ママ)ったものではない。
始めは木造で暦仁元年(1238年)に着工し六年間で完成したが、宝治元年(1247年)大風で倒れたので、再び資金を集め、建長四年(1252年)に至って現在の青銅の像を鋳造し、大仏殿を造って安置した。(中略)大仏殿は建武元年(1334年)と應安二年(1369年)とに大風に倒れ、その都度復興したが、明應七年(1498年)の海潮に流失以来は復興せず、露像として知られるに至った。(略)
■ 山内掲示(鎌倉市教育委員会)(抜粋)
高徳院本尊の「鋳造阿弥陀如来坐像」は鎌倉大仏とも呼ばれ、国宝に指定されています。
日本有数の銅造大仏で、建長4年(1252年)に鋳造を始めたと史料にみえる「金銅八丈釈迦如来像」がこの大仏であるとされています。
完成時期はわかっていませんが、文永5年(1268年)ごろまでには大仏殿も建てられていたと考えられ、管理していた寺院は大仏殿、大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていました。
大仏殿は災害により何度か倒壊し、その度に大仏の修理が行われたようです。(中略)
大仏は15世紀末以降、現在と同じように露坐となり、相次ぐ災害によって荒廃しました。
高徳院は、正徳二年(1712年)に増上寺の祐天上人、浅草の商人・野嶋新左衛門らが大仏の復興を発願して建立した寺院です。復興された大仏の開眼供養は、天文二年(1737年)に高徳院住職の養国上人によって行われ、今に至っています。
-------------------------
江ノ電「長谷」駅から鎌倉大仏にかけてはいつも観光客であふれています。
修学旅行では鎌倉大仏はマストらしく、シーズンには学生も多くみられて賑わいます。


【写真 上(左)】 賑わう紅葉の参道
【写真 下(右)】 めずらしく空いている参道
参道入口に「總國分寺」と刻まれた石碑。
参道は幅員のある石畳で、どこか神社(大社)の参道のようです。


【写真 上(左)】 「總國分寺」の石碑
【写真 下(右)】 仁王門への参道


【写真 上(左)】 仁王門
【写真 下(右)】 仁王門の扁額
すこし進むと仁王門。
切妻屋根銅板本瓦棒葺三間一戸の八脚門は、朱塗りの丸柱で風格があります。
両脇間に仁王尊を安置し、見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 門
【写真 下(右)】 手水舎
も少し進むと門で遮られ、左手に券売所と入場門があります。
むろん拝観料が必要です。
門を入ってすぐに手水舎。

高徳院の山内は広いですがシンプルで、右手正面に鎌倉大仏、その右手に授与所&売店、大仏の裏手に観月堂と右手奥に与謝野晶子の歌碑があります。


【写真 上(左)】 山内-1
【写真 下(右)】 山内-2


【写真 上(左)】 国宝の碑
【写真 下(右)】 正面から
大仏は台座に座し、衣を通肩にまとい、上品上生の定印を結ばれています。


【写真 上(左)】 斜めから
【写真 下(右)】 背面
来迎印ではなく定印を結んでいるので密教系の尊像とする説もみられますが、浄土宗でも定印阿弥陀如来像はいくらも見られるので、筆者的にはこの説は疑問です。
整った面立ちで軽くうつむき、イケメンの大仏として知られています。
別料金ですが、大仏の胎内を拝観することもできます。


【写真 上(左)】 六字御名号の碑
【写真 下(右)】 観月堂-1
観月堂は、朝鮮王宮にあったものを大正13年山一合資会社(後の山一證券)社長だった杉野喜精が寄贈した建物です。
江戸幕府2代将軍徳川秀忠公が所持していたとされる聖観世音菩薩像を安置し、鎌倉三十三観音霊場第23番の札所となっています。
切妻造?本瓦葺の風格ある建物ですが、柵があるので向拝まで近づくことはできません。


【写真 上(左)】 観月堂-2
【写真 下(右)】 観音霊場札所標
御朱印は大仏の向かって右の授与所にて拝受しました。
オリジナル御朱印帳の頒布があり、現在は両面の絵御朱印も授与されているようです。
なお、公式Webによると御朱印帳書入れは15時までのようです。
〔 高徳院の御朱印 〕

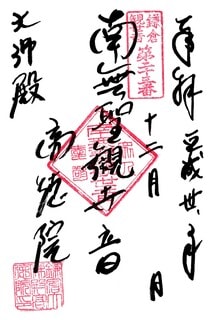
【写真 上(左)】 御本尊(鎌倉大仏)の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-19 (C.極楽寺口-2)へつづく。
【 BGM 】
■ KOKIA - ありがとう… (KOKIA's Version)
■ 中山美穂 - ただ泣きたくなるの
■ Kalafina - far on the water(LIVE)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-17 (B.名越口-12)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)
■ 同-16 (B.名越口-11)から。
49.中座山 大聖院 教恩寺(きょうおんじ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市材木座1-4-29
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
司元別当:
札所:鎌倉三十三観音霊場第12番
教恩寺は、源平合戦の艶やかな歴史を辿れる時宗寺院です。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
教恩寺は知阿上人を開山に、後北条氏三代・北条氏康(大聖寺殿東陽岱公)が開基となり光明寺境内に建立した寺院が創始といいます。
もともとこの場所には光明寺の末寺・善昌寺がありましたが廃寺となり、延宝六年(1678年)、貴誉上人のときに光明寺境内の北の山際にあった教恩寺を移築と伝わります。
教恩寺は平重衡とのゆかりで知られています。
平重衡(たいらのしげひら、1157-1185年)は、平清盛の五男で母は清盛の継室・平時子。
順調に昇進を重ね、治承三年(1179年)、23歳で左近衛権中将に進み「三位中将」と称されました。
『吾妻鏡』などでは「三品羽林(さんぽんうりん)重衡」とも。
治承四年(1180年)5月、以仁王の挙兵に際し、重衡は甥の維盛とともに大将軍として出陣してこれを鎮圧しました。
平清盛は南都寺院の旧来の特権を無視して検断を行ったため南都寺院側は強く反発、とくに強大な勢力を誇った東大寺、興福寺、園城寺とははげしく対立しました。
治承四年(1180年)12月11日、清盛の命により園城寺を攻撃して焼き払ったのが重衡です。
ついで12月28日、重衡の軍勢は南都へ攻め入って火を放ち、興福寺、東大寺の堂塔伽藍を一宇残さず焼き尽して多くの僧侶が焼死し、東大寺大仏も焼け落ちました。
この一連の騒乱を「南都焼討」といいます。
なお、治承五年(1181年)閏2月の清盛死去後、政権を継いだ平宗盛は東大寺・興福寺との融和を図り、両寺の再建を赦したため東大寺は建久六年(1195年)頃、興福寺は建暦二年(1212年)頃にはある程度の復興をみたといいます。
重衡は清盛死去後も平家軍の中核を担い、治承五年(1181年)3月、大将軍として墨俣川の戦いに臨んで源行家・義円軍を破り、源氏の侵攻を食い止めました。
しかし寿永二年(1183年)5月の倶利伽羅峠の戦い、6月の篠原の戦いで平維盛軍が源義仲勢に大敗し、重衡は妻の輔子とともに都落ちしました。
重衡は都落ちののちも平家方の中心武将として活躍し、寿永二年(1183年)10月の水島の戦いで足利義清、同年11月の室山の戦いで源行家を破りました。
しかし、寿永三年(1184年)源範頼・義経軍が攻め上ると情勢は悪化し、同年2月の一ノ谷の戦いでついに重衡軍も大敗し、重衡は馬を射られて捕らえられました。
重衡を捕らえた武将として、『平家物語』では梶原景季と庄高家、『吾妻鏡』では梶原景時と庄家長が記されています。
京へ護送された重衡は土肥実平の監視下に置かれ、同年3月梶原景時によって鎌倉へと護送されました。
重衡は鎌倉で頼朝公と引見しましたが、頼朝公は重衡の器量に感心して厚遇したといいます。
---------------------------------
『新刊吾妻鏡 巻2-3』(国立国会図書館)
壽永三年(1184年)三月小廿八日丁巳
被請本三位中將 藍摺直垂引立烏帽子 於廊令謁給 仰云 且為奉慰君御憤 且為●父尸骸之耻 試企石橋合戦以降 令對治平 氏之逆乱如指掌 仍及面拝 不屑眉目也 此上者 謁槐門之事 亦無疑者歟 羽林答申曰 源平為天下警衛之處 頃年之間 當家獨為朝廷之計 昇進者八十餘輩 思其繁榮者 二十餘年也。而今運命之依縮 為囚人参入上者 不能左右 携弓馬之者 為敵被虜 強非耻辱 早可被處斬罪云云 無纎介之憚 奉問答 聞者莫不感 其後被召預狩野介云云 今日就武家輩事 於自仙洞被仰下事者 不論是非 可成敗 至武家帶道理事者 追可奏聞之旨 被定云云
---------------------------------
『吾妻鏡』によると、重衡は頼朝公に対して「武運尽きて囚人の身となったからには、あれこれ申し開くこともありません。弓馬に携わる者が、敵の捕虜になる事はけっして恥ではない。早く斬罪になされよ」と堂々と述べ、周囲の人々はその毅然とした態度に感じ入ったといいます。
狩野宗茂に預けられた重衡は北条政子からも厚遇を受け、重衡をもてなすために侍女の千手の前を側につけたといいます。
千手の前はこの平家の貴公子に惹かれ、ふたりは時をおかず結ばれたとも。
ある日、頼朝公は重衡を慰めるために宴を設け、工藤祐経が鼓を打ち、千手の前は琵琶を弾き、重衡が横笛を吹いて、弦楽の風雅を愉しむ様が『平家物語』に描かれています。
教恩寺には、重衡が千手前と酒宴のときに酌み交わした盃が寺宝として伝わっています。
元暦二年(1185年)3月、壇ノ浦の戦いで平氏は滅亡しましたが、重衡の妻の輔子は助け上られ捕虜となり、山城国日野に隠栖しました。
同年6月、「南都焼討」の恨みをもつ南都衆徒の強硬な要求を受け、重衡はやむなく南都に引き渡されることになり、源頼兼の護送で南都に入り東大寺に引き渡されました。
『平家物語』には、一行が輔子が住む日野の近くを通った際、重衡が「せめて一目、妻と会いたい」と願って許され、涙ながらの別れを交わした場面が描かれています。
元暦二年(1185年)3月23日、重衡は木津川畔にて斬首、奈良坂にある般若寺門前で梟首されました。享年29と伝わります。
なお、重衡は斬首前に法然上人と面会し、受戒したという説があります。
妻の輔子は重衡の遺骸を引き取って荼毘に付し、日野に墓を建てました。
その後輔子は大原に隠棲した建礼門院に仕え、後白河法皇の大原御幸に立ち会い、建礼門院の最期を阿波内侍とともに看取っています。
重衡の死の3年後、千手の前は若くしてこの世を去りました。
人々は、亡き重衡を恋慕したあげくの憂死と噂したといいます。
平家の公達は美形揃いともいいますが、なかでも維盛、重衡、敦盛の3人は平家を代表するイケメンとして知られています。
姿が美しいだけでなく、重衡はこまやかな心遣いをする人物で、ウィットに富み、彼のまわりは笑いが絶えなかったともいいます。
舞にも堪能で、後白河上皇の50歳の祝賀の儀では維盛と重衡が青海波を華麗に舞ったといいます。(他者説あり)
また当代一流の歌人としても知られ、『玉葉和歌集』に選歌された勅撰歌人でもあります。
『玉葉和歌集』巻第8 旅歌
住みなれし 古き都の 恋しさは 神もむかしに 思ひしるらむ
このような人物が女性にもてないわけがありません。
江戸時代の『平家公達草紙』によると、重衡が都落ちの際、式子内親王の御所に別れの挨拶に訪れた際には、大勢の女房たちが涙にくれたとあります。
南都の大寺院を焼き打ちして多くの人々の命を奪い、大仏さえもも焼き払っているのですからふつうに考えれば大悪人です。
しかし、重衡を悪し様に伝える史料類は調べた限りではほとんど見当たりません。
能の演目「重衡」では南都焼討した重衡の苦悩が描かれています。
ここでは重衡が木津川畔で斬首される際に、今生の最期に仏を拝みたいと頼み、阿弥陀如来に念仏を唱える場面がでてきます。
また、斬首の前に法然上人に出会い帰依したという伝承もあり、重衡が南都焼討の罪障をふかく苦悩していた姿が浮かびます。
教恩寺の阿弥陀三尊像は源頼朝公が重衡に対して「一族の冥福を祈るように」と授けといい、重衡はこの尊像をふかく信仰したといいます。
『新編鎌倉志』には「本尊阿彌陀、運慶作。相伝ふ。平重衡囚れに就て、此本尊を礼し、臨終正念を祈りしかば、彌陀の像、打ちうなづきけるとなん。」とあります。
生涯の多くを京で過ごした平重衡ゆかりの寺院は関東にはほとんどないですが、教恩寺はその貴重な一寺といえましょう。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
教恩寺
教恩寺は寶海山と号す。米町の内にあり。時宗。藤澤道場の末寺なり。
里老の云、本は光明寺の境内、北の山ぎわに有しを延寶六年(1678年)に、貴譽上人此地に移す。
元此地に善昌寺と云て光明寺の末寺あり。廃亡したる故に、教恩寺を此に移し。元教恩寺の跡を、所化寮とせり。
本尊阿彌陀、運慶作。相伝ふ。平重衡囚れに就て、此本尊を礼し、臨終正念を祈りしかば、彌陀の像、打ちうなづきけるとなん。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
米町の内にあり。は寶海山と号す。時宗藤澤清浄光寺の末也。
土人いふ、もとは光明寺境内の山際に有しを、延寶六年(1678年)爰に移せり。
此所は善昌寺と云光明寺末寺の廃せし所なり。
本尊阿彌陀 運慶作といふ。
寺寶
盃一箇 伝へいふ 平重衡、千壽前と酒宴の盃なりといふ。
内外黒ぬり。内に梅花の蒔絵あり。大いさ、今時の平皿の如くにて浅し。木薄く軽し。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(大町村)教恩寺
中座町にあり、中座山(【鎌倉志】に寶海山とあり、貞享已後改しにや) 大聖院と号す 本寺前(藤澤清浄光寺)に同じ、開山は知阿 開基は俗称を伝へず、大聖院東陽岱公とのみ伝ふ、是北條左京大夫氏康の法名にて今大住郡栗原村萬松寺に其牌あり 大聖寺殿東陽岱公、元龜二年(1571年)十月三日と記せり又同寺所蔵、天正二年(1574年)の文書に、大聖院様号御位牌所云々とあり 剏建の年代を伝へざれど、是に拠て推考すべし、【鎌倉志】里老の言を引て舊は光明寺の境内北の山際に在しを延寶六年(1678年)僧貴譽此地に移す、元此地に善昌寺と云ふ光明寺の末寺あり、其寺廃蕪せしが故当寺を爰に移し元の当寺蹟を所化寮とすと記せり、三尊の彌陀 運慶作、を本尊とす、寺伝に是は元暦元年(1184年)平家没落の時三位中将重衡囚れて鎌倉に在し程賴朝が授興の霊像にて重衡が帰依佛なりと伝ふ、当寺安置の来由伝はらず
【寺寶】
盃三口 共に重衡の盃と云ふ
【鎌倉志】には一口と挙げ、重衡千手前と、酒宴の時の盃なりと記せり、按ずるに、【東鑑】元暦元年(1184年)四月廿日の條に曰、本三位中将、依武衡御免、有沐浴之儀、其後及乗燭之期、称為慰徒然披遣藤判官代邦通、工藤一﨟祐經、官女一人号千手前等、於羽林之方、剰被副送竹葉上林已下、羽林殊喜悦、遊興移剋、祐經打鼓歌今様、女房弾琵琶、羽林和横笛、先吹五常楽、為下官以可為後生楽由称之、次吹皇●急、謂往生急、凡於事莫不催興、及夜半女房欲帰、羽林暫抑留之而盃及朗詠、燭暗數行寞氏涙、夜深四面楚歌聲云々、其後各帰参御前、武衡令問酒宴次第給云々、又武衡令持宿衣一領於千手前、更被送遣、其上以祐經、邊鄙士女還可有其興歟、御在國之程、可被召置之由被仰云々、更に拠ば、此宴席に用し物なるべし
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
中座山大聖院教恩寺と号する。時宗。藤澤清浄光寺。
開山、知阿。開基、北条氏康。
本尊、阿弥陀如来。
境内地355.31坪。本堂・庫裏・山門あり。
『新編鎌倉志』には山号を寶海山とし、もと光明寺の境内にあったという説を述べている。
-------------------------
神奈川県道311号鎌倉葉山線(旧大町大路)と小町大路が交差する「大町四つ角」交差点から311号を西に進み一本目の路地を北に入った正面で、あたりは住宅地です。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号板
正面に切妻屋根銅板本瓦棒葺四脚門の山門で、門柱には寺号板、中備にはボリューム感ある十六羅漢(裏面は牡丹)の彫刻が刻まれています。


【写真 上(左)】 十六羅漢
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 天水鉢の「隅切角に三」
山内は緑ゆたかでしっとりと落ち着いた空気感。
重衡と千手の前の哀恋を伝える寺院にふさわしいたたずまいです。
石畳の参道正面に本堂。本堂前には時宗の宗紋「隅切角に三」。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂はおそらく切妻造銅板葺流れ向拝で、屋根勾配が急で照り気味なので勢いを感じます。
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に精緻な龍の彫刻を置いています。
虹梁持ち送りにも鳥の彫刻を置き、見どころの多い向拝です。


【写真 上(左)】 向拝の彫刻
【写真 下(右)】 斜めからの向拝
向拝正面桟唐戸のうえに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 御朱印所
中尊は御本尊の阿弥陀三尊(阿弥陀如来、聖観世音菩薩、勢至菩薩各立像)で、平重衡が囚われの身でふかく信仰したという尊像です。
運慶作とも伝わり、「木造 阿弥陀如来及び両脇侍立像」として神奈川県指定文化財に指定されています。
観音堂は見当たらないので、鎌倉三十三観音霊場第12番の札所本尊。聖観世音菩薩は本堂内に奉安とみられます。
御朱印は本堂向かって左の授与所にて拝受しました。
〔 教恩寺の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
50.帰命山 延命寺(えんめいじ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市材木座1-1-3
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:
札所:鎌倉三十三観音霊場第11番、鎌倉二十四地蔵霊場第23番
延命寺は、北条時頼公ゆかりの浄土宗寺院です。
鎌倉公式観光ガイドWeb、『鎌倉札所めぐり』(メイツ出版)、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
延命寺は、鎌倉幕府第5代執権北条時頼公(1227-1263年)の夫人の創建といいます。
時頼夫人の念持佛・身代り地蔵尊を奉安する地蔵堂として正慶年間(1332-1333年)に建立、専蓮社昌誉能公を開山ないし中興開山といいます。
北条時頼公の正室は大江広元四男・毛利季光の息女。継室は北条重時の息女・葛西殿、側室は讃岐局、辻殿などが記録に残りますが、当山草創夫人が誰なのかは伝わっていません。
当山の身代り地蔵尊(裸地蔵尊)は時頼夫人をしばしば救われたといい、双六の勝負で窮地に陥った夫人を救ったという逸話が遺っています。
この双六の勝負にまつわる逸話もあって、参詣客を集めたともいわれています。
身代り地蔵尊(裸地蔵尊)は等身大の女性のお姿をされ、双六盤の上安置された地蔵尊で、運慶作とも伝わります。
また、北条政子像とする研究者もいるようです。
また、赤穂浪士の岡島八十右衛門の息子が当山住職をであった縁により、忠臣蔵にまつわる寺宝も有していたといいます。
鎌倉三十三観音霊場第11番、鎌倉二十四地蔵霊場第23番の札所につき、霊場巡拝者の来山も多いとみられます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
延命寺
延命寺は、米町にあり。浄土宗。安養院の末寺なり。
堂に立像の地蔵を安ず。俗に裸地蔵と云ふ。又前出地蔵とも云。裸形にて双六局を踏せ、厨子に入、衣を著せてあり。参詣の人は裸にして見するなり。(略)
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
延命寺
米町の西にあり。浄土宗安養院末なり。
堂に立像の地蔵を安す。土俗裸地蔵といふ。又は前出し地蔵ともいふ。裸形にて双六局をふみ、厨子入、衣を着せたり。参詣のものに裸にして見する所なり。(略)
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(大町村)延命寺
米町にあり、帰命山と号す 前寺(安養院)末
本尊彌陀 立像長二尺二寸五分、運慶作 及び地蔵 立像長五尺二寸 是も同(運慶)作と伝ふ を安ず、此像は北條時頼の夫人が念持佛にて身代地蔵と称す、夫人此佛徳にて無實の難を遁れし事あり 故に身代の称起れりと云ふ 或は裸地蔵の唱へありて(中略)
是より北條氏代々の念持佛なりしが正慶年中(1332-1333年)更に一宇を建立して安置せしと伝へ、即其時の記今猶ありと云ふ、此餘淺野内匠頭長矩の臣四十六士の画像を置く 寺伝に彼の士の内、岡嶋八十右衛門の三男、当寺の住職たりし故、安ずるなりと云ふ
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
帰命山延命寺と号する。浄土宗、もと安養院末。
開山、専蓮社昌誉能公。
本尊、阿弥陀如来。
境内地365.49坪。本堂・庫裏・山門・倉庫あり。
ここには北条時頼室の念持仏であったという身代地蔵がある。(中略)
寺仏に、赤穂四十七士のうち岡島八十右衛門の三男が住持であったと伝え、義士銘々伝があり、義士の画像もあったが今はない。
-------------------------
神奈川県道311号鎌倉葉山線(旧大町大路)が横須賀線を渡ってすぐの滑川沿い、若宮大路「下馬」交差点の東側で、「鎌倉」駅にもほど近いところ。


【写真 上(左)】 滑川
【写真 下(右)】 山内入口


【写真 上(左)】 寺号標-1
【写真 下(右)】 寺号標-2
山内入口に寺号標。門柱にも寺号標があります。
山内はこぢんまりとしていて、入母屋造銅板本瓦棒葺妻入りの本堂が、観音・地蔵両霊場の拝所です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
妻部千鳥破風の下が向拝で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股を置き、左右の身舎には花頭窓を配しています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 案内
中尊の御本尊は運慶作とも伝わる阿弥陀如来坐像で、北鎌倉の圓應寺の閻魔王像の木余り
でつくられたとされ「木あまりの像」とも「日あまりの」像とも呼ばれます。
その向かって右手に奉安の聖観世音菩薩立像は、鎌倉三十三観音霊場第11番の札所本尊です。
左手には北条時頼公夫人の守護佛・身代わ地蔵尊((裸地蔵尊))を奉安で、こちらは鎌倉二十四地蔵霊場第23番の札所本尊です。
堂内右手には弥陀三尊と両大師が奉安されています。
御朱印は本堂向かって右手の庫裏にて拝受しました。
〔 延命寺の御首題 〕

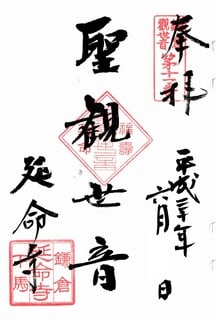
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
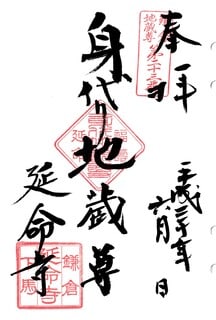
鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-18 (C.極楽寺口-1)へつづく。
【 BGM 】
■ 西風の贈り物 - 志方あきこ
■ あなたの夜が明けるまで - 春吹そらの(covered by)
■ 私にはできない - Eiーvy
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)
■ 同-16 (B.名越口-11)から。
49.中座山 大聖院 教恩寺(きょうおんじ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市材木座1-4-29
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
司元別当:
札所:鎌倉三十三観音霊場第12番
教恩寺は、源平合戦の艶やかな歴史を辿れる時宗寺院です。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
教恩寺は知阿上人を開山に、後北条氏三代・北条氏康(大聖寺殿東陽岱公)が開基となり光明寺境内に建立した寺院が創始といいます。
もともとこの場所には光明寺の末寺・善昌寺がありましたが廃寺となり、延宝六年(1678年)、貴誉上人のときに光明寺境内の北の山際にあった教恩寺を移築と伝わります。
教恩寺は平重衡とのゆかりで知られています。
平重衡(たいらのしげひら、1157-1185年)は、平清盛の五男で母は清盛の継室・平時子。
順調に昇進を重ね、治承三年(1179年)、23歳で左近衛権中将に進み「三位中将」と称されました。
『吾妻鏡』などでは「三品羽林(さんぽんうりん)重衡」とも。
治承四年(1180年)5月、以仁王の挙兵に際し、重衡は甥の維盛とともに大将軍として出陣してこれを鎮圧しました。
平清盛は南都寺院の旧来の特権を無視して検断を行ったため南都寺院側は強く反発、とくに強大な勢力を誇った東大寺、興福寺、園城寺とははげしく対立しました。
治承四年(1180年)12月11日、清盛の命により園城寺を攻撃して焼き払ったのが重衡です。
ついで12月28日、重衡の軍勢は南都へ攻め入って火を放ち、興福寺、東大寺の堂塔伽藍を一宇残さず焼き尽して多くの僧侶が焼死し、東大寺大仏も焼け落ちました。
この一連の騒乱を「南都焼討」といいます。
なお、治承五年(1181年)閏2月の清盛死去後、政権を継いだ平宗盛は東大寺・興福寺との融和を図り、両寺の再建を赦したため東大寺は建久六年(1195年)頃、興福寺は建暦二年(1212年)頃にはある程度の復興をみたといいます。
重衡は清盛死去後も平家軍の中核を担い、治承五年(1181年)3月、大将軍として墨俣川の戦いに臨んで源行家・義円軍を破り、源氏の侵攻を食い止めました。
しかし寿永二年(1183年)5月の倶利伽羅峠の戦い、6月の篠原の戦いで平維盛軍が源義仲勢に大敗し、重衡は妻の輔子とともに都落ちしました。
重衡は都落ちののちも平家方の中心武将として活躍し、寿永二年(1183年)10月の水島の戦いで足利義清、同年11月の室山の戦いで源行家を破りました。
しかし、寿永三年(1184年)源範頼・義経軍が攻め上ると情勢は悪化し、同年2月の一ノ谷の戦いでついに重衡軍も大敗し、重衡は馬を射られて捕らえられました。
重衡を捕らえた武将として、『平家物語』では梶原景季と庄高家、『吾妻鏡』では梶原景時と庄家長が記されています。
京へ護送された重衡は土肥実平の監視下に置かれ、同年3月梶原景時によって鎌倉へと護送されました。
重衡は鎌倉で頼朝公と引見しましたが、頼朝公は重衡の器量に感心して厚遇したといいます。
---------------------------------
『新刊吾妻鏡 巻2-3』(国立国会図書館)
壽永三年(1184年)三月小廿八日丁巳
被請本三位中將 藍摺直垂引立烏帽子 於廊令謁給 仰云 且為奉慰君御憤 且為●父尸骸之耻 試企石橋合戦以降 令對治平 氏之逆乱如指掌 仍及面拝 不屑眉目也 此上者 謁槐門之事 亦無疑者歟 羽林答申曰 源平為天下警衛之處 頃年之間 當家獨為朝廷之計 昇進者八十餘輩 思其繁榮者 二十餘年也。而今運命之依縮 為囚人参入上者 不能左右 携弓馬之者 為敵被虜 強非耻辱 早可被處斬罪云云 無纎介之憚 奉問答 聞者莫不感 其後被召預狩野介云云 今日就武家輩事 於自仙洞被仰下事者 不論是非 可成敗 至武家帶道理事者 追可奏聞之旨 被定云云
---------------------------------
『吾妻鏡』によると、重衡は頼朝公に対して「武運尽きて囚人の身となったからには、あれこれ申し開くこともありません。弓馬に携わる者が、敵の捕虜になる事はけっして恥ではない。早く斬罪になされよ」と堂々と述べ、周囲の人々はその毅然とした態度に感じ入ったといいます。
狩野宗茂に預けられた重衡は北条政子からも厚遇を受け、重衡をもてなすために侍女の千手の前を側につけたといいます。
千手の前はこの平家の貴公子に惹かれ、ふたりは時をおかず結ばれたとも。
ある日、頼朝公は重衡を慰めるために宴を設け、工藤祐経が鼓を打ち、千手の前は琵琶を弾き、重衡が横笛を吹いて、弦楽の風雅を愉しむ様が『平家物語』に描かれています。
教恩寺には、重衡が千手前と酒宴のときに酌み交わした盃が寺宝として伝わっています。
元暦二年(1185年)3月、壇ノ浦の戦いで平氏は滅亡しましたが、重衡の妻の輔子は助け上られ捕虜となり、山城国日野に隠栖しました。
同年6月、「南都焼討」の恨みをもつ南都衆徒の強硬な要求を受け、重衡はやむなく南都に引き渡されることになり、源頼兼の護送で南都に入り東大寺に引き渡されました。
『平家物語』には、一行が輔子が住む日野の近くを通った際、重衡が「せめて一目、妻と会いたい」と願って許され、涙ながらの別れを交わした場面が描かれています。
元暦二年(1185年)3月23日、重衡は木津川畔にて斬首、奈良坂にある般若寺門前で梟首されました。享年29と伝わります。
なお、重衡は斬首前に法然上人と面会し、受戒したという説があります。
妻の輔子は重衡の遺骸を引き取って荼毘に付し、日野に墓を建てました。
その後輔子は大原に隠棲した建礼門院に仕え、後白河法皇の大原御幸に立ち会い、建礼門院の最期を阿波内侍とともに看取っています。
重衡の死の3年後、千手の前は若くしてこの世を去りました。
人々は、亡き重衡を恋慕したあげくの憂死と噂したといいます。
平家の公達は美形揃いともいいますが、なかでも維盛、重衡、敦盛の3人は平家を代表するイケメンとして知られています。
姿が美しいだけでなく、重衡はこまやかな心遣いをする人物で、ウィットに富み、彼のまわりは笑いが絶えなかったともいいます。
舞にも堪能で、後白河上皇の50歳の祝賀の儀では維盛と重衡が青海波を華麗に舞ったといいます。(他者説あり)
また当代一流の歌人としても知られ、『玉葉和歌集』に選歌された勅撰歌人でもあります。
『玉葉和歌集』巻第8 旅歌
住みなれし 古き都の 恋しさは 神もむかしに 思ひしるらむ
このような人物が女性にもてないわけがありません。
江戸時代の『平家公達草紙』によると、重衡が都落ちの際、式子内親王の御所に別れの挨拶に訪れた際には、大勢の女房たちが涙にくれたとあります。
南都の大寺院を焼き打ちして多くの人々の命を奪い、大仏さえもも焼き払っているのですからふつうに考えれば大悪人です。
しかし、重衡を悪し様に伝える史料類は調べた限りではほとんど見当たりません。
能の演目「重衡」では南都焼討した重衡の苦悩が描かれています。
ここでは重衡が木津川畔で斬首される際に、今生の最期に仏を拝みたいと頼み、阿弥陀如来に念仏を唱える場面がでてきます。
また、斬首の前に法然上人に出会い帰依したという伝承もあり、重衡が南都焼討の罪障をふかく苦悩していた姿が浮かびます。
教恩寺の阿弥陀三尊像は源頼朝公が重衡に対して「一族の冥福を祈るように」と授けといい、重衡はこの尊像をふかく信仰したといいます。
『新編鎌倉志』には「本尊阿彌陀、運慶作。相伝ふ。平重衡囚れに就て、此本尊を礼し、臨終正念を祈りしかば、彌陀の像、打ちうなづきけるとなん。」とあります。
生涯の多くを京で過ごした平重衡ゆかりの寺院は関東にはほとんどないですが、教恩寺はその貴重な一寺といえましょう。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
教恩寺
教恩寺は寶海山と号す。米町の内にあり。時宗。藤澤道場の末寺なり。
里老の云、本は光明寺の境内、北の山ぎわに有しを延寶六年(1678年)に、貴譽上人此地に移す。
元此地に善昌寺と云て光明寺の末寺あり。廃亡したる故に、教恩寺を此に移し。元教恩寺の跡を、所化寮とせり。
本尊阿彌陀、運慶作。相伝ふ。平重衡囚れに就て、此本尊を礼し、臨終正念を祈りしかば、彌陀の像、打ちうなづきけるとなん。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
米町の内にあり。は寶海山と号す。時宗藤澤清浄光寺の末也。
土人いふ、もとは光明寺境内の山際に有しを、延寶六年(1678年)爰に移せり。
此所は善昌寺と云光明寺末寺の廃せし所なり。
本尊阿彌陀 運慶作といふ。
寺寶
盃一箇 伝へいふ 平重衡、千壽前と酒宴の盃なりといふ。
内外黒ぬり。内に梅花の蒔絵あり。大いさ、今時の平皿の如くにて浅し。木薄く軽し。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(大町村)教恩寺
中座町にあり、中座山(【鎌倉志】に寶海山とあり、貞享已後改しにや) 大聖院と号す 本寺前(藤澤清浄光寺)に同じ、開山は知阿 開基は俗称を伝へず、大聖院東陽岱公とのみ伝ふ、是北條左京大夫氏康の法名にて今大住郡栗原村萬松寺に其牌あり 大聖寺殿東陽岱公、元龜二年(1571年)十月三日と記せり又同寺所蔵、天正二年(1574年)の文書に、大聖院様号御位牌所云々とあり 剏建の年代を伝へざれど、是に拠て推考すべし、【鎌倉志】里老の言を引て舊は光明寺の境内北の山際に在しを延寶六年(1678年)僧貴譽此地に移す、元此地に善昌寺と云ふ光明寺の末寺あり、其寺廃蕪せしが故当寺を爰に移し元の当寺蹟を所化寮とすと記せり、三尊の彌陀 運慶作、を本尊とす、寺伝に是は元暦元年(1184年)平家没落の時三位中将重衡囚れて鎌倉に在し程賴朝が授興の霊像にて重衡が帰依佛なりと伝ふ、当寺安置の来由伝はらず
【寺寶】
盃三口 共に重衡の盃と云ふ
【鎌倉志】には一口と挙げ、重衡千手前と、酒宴の時の盃なりと記せり、按ずるに、【東鑑】元暦元年(1184年)四月廿日の條に曰、本三位中将、依武衡御免、有沐浴之儀、其後及乗燭之期、称為慰徒然披遣藤判官代邦通、工藤一﨟祐經、官女一人号千手前等、於羽林之方、剰被副送竹葉上林已下、羽林殊喜悦、遊興移剋、祐經打鼓歌今様、女房弾琵琶、羽林和横笛、先吹五常楽、為下官以可為後生楽由称之、次吹皇●急、謂往生急、凡於事莫不催興、及夜半女房欲帰、羽林暫抑留之而盃及朗詠、燭暗數行寞氏涙、夜深四面楚歌聲云々、其後各帰参御前、武衡令問酒宴次第給云々、又武衡令持宿衣一領於千手前、更被送遣、其上以祐經、邊鄙士女還可有其興歟、御在國之程、可被召置之由被仰云々、更に拠ば、此宴席に用し物なるべし
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
中座山大聖院教恩寺と号する。時宗。藤澤清浄光寺。
開山、知阿。開基、北条氏康。
本尊、阿弥陀如来。
境内地355.31坪。本堂・庫裏・山門あり。
『新編鎌倉志』には山号を寶海山とし、もと光明寺の境内にあったという説を述べている。
-------------------------
神奈川県道311号鎌倉葉山線(旧大町大路)と小町大路が交差する「大町四つ角」交差点から311号を西に進み一本目の路地を北に入った正面で、あたりは住宅地です。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号板
正面に切妻屋根銅板本瓦棒葺四脚門の山門で、門柱には寺号板、中備にはボリューム感ある十六羅漢(裏面は牡丹)の彫刻が刻まれています。


【写真 上(左)】 十六羅漢
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 天水鉢の「隅切角に三」
山内は緑ゆたかでしっとりと落ち着いた空気感。
重衡と千手の前の哀恋を伝える寺院にふさわしいたたずまいです。
石畳の参道正面に本堂。本堂前には時宗の宗紋「隅切角に三」。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂はおそらく切妻造銅板葺流れ向拝で、屋根勾配が急で照り気味なので勢いを感じます。
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に精緻な龍の彫刻を置いています。
虹梁持ち送りにも鳥の彫刻を置き、見どころの多い向拝です。


【写真 上(左)】 向拝の彫刻
【写真 下(右)】 斜めからの向拝
向拝正面桟唐戸のうえに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 御朱印所
中尊は御本尊の阿弥陀三尊(阿弥陀如来、聖観世音菩薩、勢至菩薩各立像)で、平重衡が囚われの身でふかく信仰したという尊像です。
運慶作とも伝わり、「木造 阿弥陀如来及び両脇侍立像」として神奈川県指定文化財に指定されています。
観音堂は見当たらないので、鎌倉三十三観音霊場第12番の札所本尊。聖観世音菩薩は本堂内に奉安とみられます。
御朱印は本堂向かって左の授与所にて拝受しました。
〔 教恩寺の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
50.帰命山 延命寺(えんめいじ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市材木座1-1-3
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:
札所:鎌倉三十三観音霊場第11番、鎌倉二十四地蔵霊場第23番
延命寺は、北条時頼公ゆかりの浄土宗寺院です。
鎌倉公式観光ガイドWeb、『鎌倉札所めぐり』(メイツ出版)、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
延命寺は、鎌倉幕府第5代執権北条時頼公(1227-1263年)の夫人の創建といいます。
時頼夫人の念持佛・身代り地蔵尊を奉安する地蔵堂として正慶年間(1332-1333年)に建立、専蓮社昌誉能公を開山ないし中興開山といいます。
北条時頼公の正室は大江広元四男・毛利季光の息女。継室は北条重時の息女・葛西殿、側室は讃岐局、辻殿などが記録に残りますが、当山草創夫人が誰なのかは伝わっていません。
当山の身代り地蔵尊(裸地蔵尊)は時頼夫人をしばしば救われたといい、双六の勝負で窮地に陥った夫人を救ったという逸話が遺っています。
この双六の勝負にまつわる逸話もあって、参詣客を集めたともいわれています。
身代り地蔵尊(裸地蔵尊)は等身大の女性のお姿をされ、双六盤の上安置された地蔵尊で、運慶作とも伝わります。
また、北条政子像とする研究者もいるようです。
また、赤穂浪士の岡島八十右衛門の息子が当山住職をであった縁により、忠臣蔵にまつわる寺宝も有していたといいます。
鎌倉三十三観音霊場第11番、鎌倉二十四地蔵霊場第23番の札所につき、霊場巡拝者の来山も多いとみられます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
延命寺
延命寺は、米町にあり。浄土宗。安養院の末寺なり。
堂に立像の地蔵を安ず。俗に裸地蔵と云ふ。又前出地蔵とも云。裸形にて双六局を踏せ、厨子に入、衣を著せてあり。参詣の人は裸にして見するなり。(略)
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
延命寺
米町の西にあり。浄土宗安養院末なり。
堂に立像の地蔵を安す。土俗裸地蔵といふ。又は前出し地蔵ともいふ。裸形にて双六局をふみ、厨子入、衣を着せたり。参詣のものに裸にして見する所なり。(略)
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(大町村)延命寺
米町にあり、帰命山と号す 前寺(安養院)末
本尊彌陀 立像長二尺二寸五分、運慶作 及び地蔵 立像長五尺二寸 是も同(運慶)作と伝ふ を安ず、此像は北條時頼の夫人が念持佛にて身代地蔵と称す、夫人此佛徳にて無實の難を遁れし事あり 故に身代の称起れりと云ふ 或は裸地蔵の唱へありて(中略)
是より北條氏代々の念持佛なりしが正慶年中(1332-1333年)更に一宇を建立して安置せしと伝へ、即其時の記今猶ありと云ふ、此餘淺野内匠頭長矩の臣四十六士の画像を置く 寺伝に彼の士の内、岡嶋八十右衛門の三男、当寺の住職たりし故、安ずるなりと云ふ
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
帰命山延命寺と号する。浄土宗、もと安養院末。
開山、専蓮社昌誉能公。
本尊、阿弥陀如来。
境内地365.49坪。本堂・庫裏・山門・倉庫あり。
ここには北条時頼室の念持仏であったという身代地蔵がある。(中略)
寺仏に、赤穂四十七士のうち岡島八十右衛門の三男が住持であったと伝え、義士銘々伝があり、義士の画像もあったが今はない。
-------------------------
神奈川県道311号鎌倉葉山線(旧大町大路)が横須賀線を渡ってすぐの滑川沿い、若宮大路「下馬」交差点の東側で、「鎌倉」駅にもほど近いところ。


【写真 上(左)】 滑川
【写真 下(右)】 山内入口


【写真 上(左)】 寺号標-1
【写真 下(右)】 寺号標-2
山内入口に寺号標。門柱にも寺号標があります。
山内はこぢんまりとしていて、入母屋造銅板本瓦棒葺妻入りの本堂が、観音・地蔵両霊場の拝所です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
妻部千鳥破風の下が向拝で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股を置き、左右の身舎には花頭窓を配しています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 案内
中尊の御本尊は運慶作とも伝わる阿弥陀如来坐像で、北鎌倉の圓應寺の閻魔王像の木余り
でつくられたとされ「木あまりの像」とも「日あまりの」像とも呼ばれます。
その向かって右手に奉安の聖観世音菩薩立像は、鎌倉三十三観音霊場第11番の札所本尊です。
左手には北条時頼公夫人の守護佛・身代わ地蔵尊((裸地蔵尊))を奉安で、こちらは鎌倉二十四地蔵霊場第23番の札所本尊です。
堂内右手には弥陀三尊と両大師が奉安されています。
御朱印は本堂向かって右手の庫裏にて拝受しました。
〔 延命寺の御首題 〕

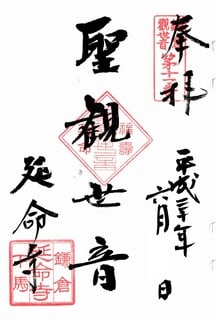
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
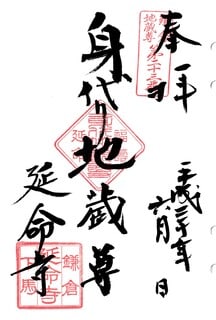
鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-18 (C.極楽寺口-1)へつづく。
【 BGM 】
■ 西風の贈り物 - 志方あきこ
■ あなたの夜が明けるまで - 春吹そらの(covered by)
■ 私にはできない - Eiーvy
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-16 (B.名越口-11)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)から。
47.法華山 本興寺(ほんこうじ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市大町2-5-32
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
司元別当:
札所:
本興寺は、大町二丁目の歴史ある日蓮宗寺院です。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
本興寺は、延元元年(1336年)「九老僧」の一人天目上人が開基建立し、日蓮聖人が辻説法の途中に休息された地に因んで「休息山本興寺」を号しました。
永徳二年(1382年)、2世日什上人が法華山と改め、開山は日什上人とされています。
日蓮聖人の鎌倉辻説法の由緒地・大町にあるため「辻の本興寺」とも呼ばれます。
当山は宗派的に複雑な変遷をたどっています。
開山・美濃阿闍梨天目上人(1256-1337年)は、日蓮六老僧・日朗上人の弟子「九老僧」の一人で日盛、上法房とも称します。
法華山 本興寺(横浜市泉区)公式Webには
「天目上人は、法華経二十八品のうち、前半十四品の迹門と後半十四品の本門では説相が異なると「迹門不読説」を主張しており、天目上人の弟子達も同じ主張をしておりましたが、日什門流の開祖である日什大正師の教化にふれ改派に至りました。」とあります。
この記述は「本迹勝劣」の概念がわからないと理解できません。
ただし、「本迹勝劣」は法華宗の本義にかかわる重要なことがらなので、Wikipediaの内容に従って概略のみまとめてみます。
・所依の法華経を構成する二十八品(28章)は前半の「迹門」、後半の「本門」に二分される。
・二十八品全体を一体のものとして扱うべきとするのが一致派。(釈尊を本仏とする)
・「本門」に法華経の極意があるとするのが勝劣派。
・勝劣派は「釈尊を本仏とする勝劣派」と「日蓮聖人を本仏とする勝劣派」に分かれる。
・「勝劣五派」とは、日興門流(富士門流、興門派)、日什門流(妙満寺派)、日陣門流(本成寺派)、日隆門流(八品派)、日真門流(本隆寺派)をさす。
天目上人は「迹門不読説」を唱えられ、当山2世の日什上人は「釈尊を本仏とする勝劣派」の日什門流の流祖です。
日什上人(1314年-1392年)について、京都妙満寺公式Webには以下のとおりあります。
---------------------------------
19歳で比叡山に登られ「玄妙」と号され、38歳の時には三千人の学僧の学頭となり、「玄妙能化」と称されました。
故郷の会津に戻られた日什上人は66歳のとき、日蓮聖人の御書『開目抄』『如説修行鈔』に触れられ、直ちに日蓮聖人を師と仰ぎ、名を「日什」と改められました。
下総中山の法華経寺にこもられ、不惜身命の布教を誓われた日什上人は、永徳元年(1381)京に上られ関白・二条良基卿と対面し、「洛中弘法の綸旨」と「二位僧都」の官位を賜わりました。
関東でも、関東管領・足利義満公などに諌暁を繰り返され、宗旨と修行の方軌を示されて日什門流を開かれました。
---------------------------------
日什門流は顕本法華宗(総本山・妙満寺)につながり、顕本法華宗の宗祖は日什上人です。
「鎌倉市史 社寺編」によると、天正十九年(1591年)、徳川家康公は当山に寺領五百五十文を寄進しています。
文明十三年(1481年)、当山16世日泰上人は大旦那酒井清伝によって堂を建立とありますが、「千葉市Web資料」によると酒井清伝は上総国土気の武将です。
Wikipediaには「上総酒井氏の祖は酒井清伝と称される人物で、この人物については、16世紀の東金城主酒井胤敏および土気城主酒井胤治が揃って酒井氏の祖として清伝の名前を挙げている。」とあるので、上総酒井氏の祖(酒井定隆?)とみられます。
酒井清伝(定隆)は法華宗(妙満寺派)の日泰上人に帰依した熱心な法華宗信者で、上総北部の平定後数年で領内のほとんどの寺院を法華宗へと改宗させた(上総七里法華)とする伝説があります。
「上総七里法華」は、江戸時代初期に不受不施を唱えた寺院があるといいます。
永禄二年(1559年)、清伝の子酒井胤治とその子政茂も当山を修造、その費用寄進者には生実御所・足利高基の室もいて、造営のため奥州や越中からも僧が鎌倉に来たとあるので、「上総七里法華」が主体となって大々的に改修が行われたのでは。
『鎌倉市史 社寺編』はまた、当山27世から妙満寺27世となった(Wikipedia)日経上人は、慶長の初年(1596年-)に倒壊した堂を慶長四年(1599年)再興したと記しています。
しかし慶長十三年(1608年)、日経上人は「不受不施」を説いたため、江戸幕府より弾圧を受けました。(慶長の法難)
不受不施派は以降も幕府の厳しい詮議を受けたため、万治三年(1660年)当山30世日顕上人により鎌倉郡飯田村に寺基を移したのが、現在の横浜市泉区上飯田町の本興寺といいます。
寛文十年(1670年)、比企谷妙本寺照幡院日逞上人が宗祖辻説法旧地の衰退を嘆き、徳川家より寺領の寄付を受けて、鎌倉の辻の旧地に本興寺を再興したといいます。
日什門流は「釈尊を本仏とする勝劣派」、妙本寺は日朗門流(比企谷門流)で「釈尊を本仏とする一致派」とされますから、複雑な門流を経由していることがわかります。
なお、日什門流の名刹・飯田本興寺は顕本法華宗本山でしたが、明治政府の宗教政策により日蓮宗と合同し、現在も日蓮宗本山(由緒寺院)の寺格を誇っています。
寛文十年(1670年)といえば将軍家綱公の治世。
名刹妙本寺の末寺で家綱公のお墨付きを得たとなれば、江戸時代の寺院経営は安定していたとみられ、明治の神仏分離も乗り切って、「辻の本興寺」の名跡をいまに伝えています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(大町村)本興寺
辻町にあり、法華山と号す 本寺前に同じ(妙本寺末)、古は京妙満寺の末なりしが、中興の後今の末となると云ふ
本尊三寶祖師を安ぜり、開山を日什(明徳三年(1392年)二月廿八日寂す)中興を日逞と云ふ(延寶三年(1675年)五月十七日寂す)天正十九年(1591年)十一月寺領五百五十文の御朱印を賜へり
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
法華山本興寺と号する。日蓮宗。もと妙本寺末。
開山、日什。中興開山、日逞
本尊、三宝祖師
境内地523.82坪。本堂・庫裏・太子堂・渡廊下・山門あり。
もと京都の妙満寺末。日什は明徳三年(1392年)二月廿八日寂、日逞は延寶三年(1675年)五月十七日寂。
天正十九年(1591年)十一月、徳川家康は寺領五百五十文を寄進した。
文明十三年(1481年)六月、当寺十六世日泰は大旦那酒井清伝によって、堂を建立した。(中略)
清伝の子酒井胤治とその子政茂が、永禄二年(1559年)修造した。この時の住持は日芸である。
修理の費用は胤治をはじめその一族がだしたが、その中には生実御所足利高基の室もいて(中略)造営のためには奥州や越中からも僧が鎌倉に来ている。
慶長の初年(1596年-)に再び倒壊した堂を復興するため、日経が僧俗にすすめて(中略)慶長四年(1599年)再興した。
■ 山内掲示(縁起碑)
本興寺略縁起 日蓮大聖人 辻説法之𦾔地
日蓮大聖人鎌倉御弘通の当時 此の地点は若宮小路に至る辻なるにより 今猶辻の本興寺と称す 御弟子天目上人聖躅を継いで又此地に折伏説法あり 實に当山の開基なり 後年日什上人(顕本法華宗開祖)留錫せられ 寺観大いに面目を改む 常楽院日経上人も亦 当寺の第廿七世なり
■ 法華山 本興寺(横浜市泉区)公式Webより
本興寺は、日蓮大聖人の直弟子である天目上人が鎌倉に開創したお寺です。
大聖人が辻説法の途中、休息された地として、『休息山本興寺』と称していました。
天目上人は、法華経二十八品のうち、前半十四品の迹門と後半十四品の本門では説相が異なると「迹門不読説」を主張しており、天目上人の弟子達も同じ主張をしておりましたが、日什門流の開祖である日什大正師の教化にふれ改派に至りました。
その後、弘和2年(1382年)に『法華山 本興寺』と改称しました。
以後、日什大正師を当山の事実上の開祖としております。
また、現在本興寺のある飯田は、弘安5年(1282年)に日蓮大聖人が池上でご入滅後、ご遺骨を身延に奉じる途次、10月20日頃にご一泊された地と伝えられています。
(中略)
万治3年(1660年)に現在の地(泉区上飯田町)にお寺の一切を移されたとされています。
-------------------------
小町大路が横須賀線を渡る踏切のすぐ北側に参道があり、山内北側は旧車小路に面しています。
参道入口には「日蓮大聖人辻説法之𦾔地」の石碑(縁起碑)が建っています。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 縁起碑


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山門
山門手前左手にお題目が刻まれた寺号標。
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、門柱は朱塗りの丸柱です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 飾り瓦
山内正面が入母屋造桟瓦葺流れ向拝の整った意匠の本堂。
軒上の飾り瓦の獅子の表情がいい味を出しています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 鎮守?
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股を置いています。
向拝正面は端正な唐桟戸。
山内に御鎮座の朱塗りの一間社流造のお社と石祠は当山鎮守でしょうか。
御首題は、参拝時本堂前におられたご住職からこころよく授与いただけましたが、こちらやこちらの記事によるとご不在が多そうです。
〔 本興寺の御首題 〕

48.由比若宮(鶴岡八幡宮元宮・元鶴岡八幡宮)(ゆいのわかみや)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市材木座1-7
御祭神:応神天皇
※■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1でも触れています。
由比若宮は鶴岡八幡宮の元宮で、頼朝公や鎌倉幕府にとってすこぶる重要な神社です。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
康平六年(1063年)源頼義公が、奥州安倍氏征伐(前九年の役)にあたり、京の石清水八幡宮に戦捷を祈願されました。
征伐が成り京に帰る帰途、鎌倉に立ち寄られ由比郷鶴岡に源氏の守り神である石清水八幡宮の御祭神を勧請されて創祀といいます。
永保元年(1081年)には、頼義公の子八幡太郎義家公が修復したとも伝わります。
治承四年(1180年)10月7日(11日とも)、鎌倉に入られた源頼朝公は、まず由比郷の鶴岡八幡宮を遙拝され、そののちに鎌倉の経営に着手したといいます。
同月11日、(伊豆山)走湯山の専光坊良暹が鎌倉に到着すると、12日には小林郷北山に建てた宮廟に(由比郷の)鶴岡八幡宮を遷し、同時に良暹を当座の別当としました。
これが現在の若宮(下宮)の始まりで、頼朝公は同社を「鶴岡八幡新宮若宮」と称されました。
つまり、康平六年(1063年)源頼義公創祀の(由比郷)鶴岡八幡宮を、治承四年(1180年)10月に源頼朝公が現在の若宮(下宮)に御遷座ということになります。
【 由比元宮と鶴岡八幡宮の関係 】
両社の関係については、史料によりニュアンスが異なりますが、だいたいつぎのとおりです。
・康平六年(1063年)源頼義公が(由比郷)鶴岡八幡宮を創祀。
・治承四年(1180年)鎌倉に入られた頼朝公が(由比郷)鶴岡八幡宮を今の若宮(下宮)の地に御遷座。
・(由比郷)鶴岡に御鎮座だったが、小林郷北山(現社地)に遷したのちも「鶴岡」を号した。
・建久二年(1191年)11月、若宮(下宮)の上方の地に建てた本宮社殿に石清水八幡宮の御神体を勧請。若宮及び末社等の遷宮も行われた。
『新編相模國風土記稿』の「(山之内庄 鶴岡 五)下ノ宮」の條に意味深な記述があります。
それは「社僧が語った」という内容で、頼義公が由比郷に祀った鶴岡八幡宮は石清水八幡宮からの勧請ながら、私の勧請だったので「別宮」の意味で「若宮」と称している。
これに対して(鶴岡八幡宮)上宮は、頼朝公が勅許を得て(公式に)勧請されたので直に「八幡宮」と称しているというのです。
また、下宮の神躰を上宮に遷して下宮は空殿となったところ、後世「若宮」の称に因んで(応神帝/誉田別命)の御子の仁徳帝(大鷦鷯命)を勧請せしめたとも。
これに対して『新編相模國風土記稿』の著者は、【東鏡】によると建久二年3月に若宮以下火災に罹りしとき、新たに上宮を造立、若宮および末社等もことごとく再建されて10月には上下両宮ともに(石清水八幡宮)から遷宮ありとあるので、「下宮は空殿となった」というのは誤謬であると断じています。
しかし、康平六年(1063年)源頼義公の勧請を多くの史料・資料が「潜かに(ひそかに)」と記しているのは、上記の社僧の「私の勧請」という説明とニュアンスが重なります。
由比元宮と鶴岡八幡宮の関係がわかりにくくなっているのは、「別宮」「新宮」「若宮」の意味が錯綜しているためと思われます。
たとえば「別宮」・「若宮」は、「本宮」(石清水八幡宮)から私に勧請した宮の意で使われています。
「新宮」は「本宮」からの分社で「若宮」も同じ意味に用いられることがあるといいます。
また、八幡社では「本宮」の御祭神・誉田別命(応神帝)に対し「若宮」では御子の仁徳帝(大鷦鷯命)を祀る例が多くみられます。
頼朝公が由比郷から小林郷に遷座された八幡宮を「鶴岡八幡新宮若宮」と称したことが混乱のもととも思えますが、『鎌倉市史 社寺編』に記されている「由比郷に勧請されていた石清水八幡宮の分社のまた分社として鶴岡八幡新宮若宮と称したのであろう。」という見解がわかりやすいように思えます。
この考えをとると、由比郷鶴岡の八幡宮は「鶴岡八幡本宮若宮」になるかとも思いますが、これを記した史料は存在しない模様です。
【 由比若宮の御祭神 】
由比若宮の御祭神を記した史料や公的資料はほとんどありませんが、境内縁起書には「祭神 応神天皇」とあります。
しかし、Web記事ではつぎのふたつの記載がみられます。
1.応神天皇
2.応神天皇、比売神、神功皇后
康平六年(1063年)、源頼義公が由比郷鶴岡に勧請されたのは石清水八幡宮です。
このとき勧請された御祭神は、つぎの2パターンが考えられるので、ここから↑の2説が出てきているかと思います。
1.石清水八幡宮の中御前御祭神:誉田別命(応神天皇)
2.石清水八幡宮の八幡三所大神
(中御前:誉田別命(応神天皇)、西御前:比咩大神(比売神)、東御前:息長帯姫命(神功皇后))
いずれにしても主祭神は応神天皇ですから、この時点では「若宮」は称せず、由比郷鶴岡に御鎮座の八幡宮ということで「鶴岡八幡宮」を称したのではないかと思いました。
しかし、そうではないかもしれません。
石川県白山市若宮に源頼義公建立と伝わる若宮八幡宮があります。
石川県神社庁のWeb資料によると、こちらの御祭神は応神天皇で、由緒に「康平6年(1063)鎮守府将軍 源頼義の建立と言われる。源頼義が奥州を平定し、石清水八幡宮を相州鎌倉郡由比郷鶴岡の地に勧請し、次いでこの加賀松任の地に国守富樫介に造営を命じ」とあります。
由比若宮と同年に源頼義公が建立し、おそらく石清水八幡宮からの勧請で御祭神は応神天皇。そして社号は「若宮八幡宮」です。
こちらの「若宮」の社号は「本宮(石清水八幡宮)から勧請した『若宮』」から来ているとも思われます。
となると、あるいは由比若宮も当初から「若宮」を称していたのかもしれません。
---------------------------------
ここからはほとんど筆者の推測です。
・治承四年(1180年)頼朝公が小林郷に造営し(由比郷)鶴岡八幡宮から御遷座のお社は、石清水八幡宮から勧請したため「若宮」を称した。
・頼朝公が石清水八幡宮からの勧請社を「若宮」を称した以上、由比郷の八幡宮も「(由比)若宮」と称した。(あるいは当初から「若宮」を称していた。)
・康平六年(1063年)頼朝公が造営した「本社」(上社)には、改めて石清水八幡宮から八幡三所大神(中御前:誉田別命(応神天皇)、西御前:比咩大神(比売神)、東御前:息長帯姫命(神功皇后))を勧請。このとき、旧「若宮」の御祭神が合祀?されたかは不明。
・新しい「若宮」(下宮)には石清水八幡宮から仁徳天皇、履中天皇・仲媛命・磐之媛命の四柱を勧請し、ここに(若宮=仁徳天皇)が成立。
となると、気になるのは小林郷北山に御遷座されたのちの由比の鶴岡八幡宮です。
『新編相模國風土記稿』に「旦頼義の勧請する所、石清水の本宮たらば、若宮の称呼ありとも、頼朝祖先の祀る所を廃して、更に勧請すべき謂なし」とあり、頼朝公が祖先の祀る所(頼義公勧請の由比若宮)を廃するいわれはないと断じています。
『新編相模國風土記稿』には「其𦾔地なれば今に祠ありて鶴岡八幡社職の持とす」「由比宮の𦾔地は、由比濱大鳥居の東にあり、今に小社を存し社外の末社に属す」とあり、由比若宮の祠は鶴岡八幡宮の社外末社で鶴岡八幡社職が奉仕していたことを伝えます。
鶴岡八幡宮境内には由比若宮遥拝所があることから、昔もいまも元宮たる神社として尊崇されているものとみられます。


【写真 上(左)】 由比若宮遙拝所(鶴岡八幡宮境内)
【写真 下(右)】 同
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新刊吾妻鏡 巻1』(国立国会図書館)
治承四年(1180年)十月十一日庚寅
卯尅御臺所入御鎌倉 景義奉迎之 去夜自伊豆國阿岐戸郷 雖令到着給 依日次不宜 止宿稻瀬河邊民居給云々 又走湯山住侶專光房良暹 依兼日御契約参着 是武衛年來御師檀也
治承四年(1180年)十月十二日辛卯
快晴 寅尅 為崇祖宗 點小林郷之北山搆宮廟 被奉遷鶴岳(岡)宮於此所 以專光房暫為別當職 令景義執行宮寺事 武衛此間潔齋給 當宮御在所 本新両所用捨 賢慮猶危給之間 任神鑒 於寳前自令取鬮給 治定當砌訖 然而未及花搆之餝 先作茅茨之営 本社者 後冷泉院御宇 伊豫守源朝臣頼義奉勅定 征伐安倍貞任之時 有丹祈之旨 康平六年秋八月 潜勧請石淸水 建瑞籬於當國由比郷 今号之下若宮 永保元年二月 陸奥守同朝臣義家加修復 今又奉遷小林郷 致●繁礼奠云々
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
下宮𦾔地
下宮𦾔地は、由比濱大鳥居の東にあり、【東鏡】に、頼朝卿、鎌倉に入給ふ時、先遙に鶴岡の八幡宮を拝み奉るとあるは、此所に有し時也。此所に有し社を、今の若宮の地に遷し奉らん為に、本・新両所の用捨を、賽前にて籤を取、今の若宮の地に治定し給ふ。本と有は此所の事、新とあるは今の若宮の事なり。爰を鶴岡と云ゆへに、小林へ遷して後も、鶴岡の若宮と云なり。鶴岡の條下と照し見るべし。
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
鶴岡八幡宮
鶴岡八幡宮は、【東鏡】に、本社は、伊豫守源頼義、勅を奉て、安倍貞任征伐の時、丹新の旨有て、康平六年(1063年)秋八月、潜に石清水を勧請し、瑞籬を当國由比郷に建。今此を下宮の𦾔跡と云也。永保元年(1081年)二月、陸奥守源義家、修復を加ふ。其後治承四年(1180年)十月十二日、源頼朝、祖宗を崇めんがために、小林郷の北の山を點じて宮廟を構へ、鶴岡由比の宮を此所に遷し奉る。(中略)
由比濱下の宮の𦾔地を、昔しは鶴が岡と云なり。【東鏡】に、治承四年(1180年)十月七日、頼朝先遙に鶴岡の八幡宮ををがみ奉るとあるは、由比濱の宮なり。小林郷に遷して後も、又鶴岡の八幡宮と云傳へたり。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
若宮𦾔地
由比濱大鳥居の東の方にあり、此邊を往昔は鶴岡と号しける𦾔地なり。右大将家、治承四年(1180年)十月鎌倉に入給ふ最初、まづ遙に八幡宮を拝み奉るとあるは、爰に鎮座の宮殿をいふ。是則天喜年中(1053-1058年)、源頼義朝臣当所へ初て勧請の社頭なり。頼朝卿、今の地へ移し給はんとせらるゝ砌、本新両所決しかたく、神前にて籤を取給ふとあるも此地にて、本といふは爰の𦾔地をさし、新とは今の社地をさす。神監に任て、今の地に治定せしと云云。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(大町村)下若宮
辻町の西にあり、往昔当所を鶴岡と号す 今𦾔号を失ふ
康平六年(1063年)八月、頼義潜に石清水の神官を模して此所に勧請ありしを治承四年(1180年)頼朝鎌倉に入て当所の宮を小林松ヶ岡に遷し、夫より彼地も鶴岡と号す、其𦾔地なれば今に祠ありて鶴岡八幡社職の持とす 事は鶴岡八幡宮の條に詳載す
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(山之内庄 鶴岡)鶴岡八幡宮
康平六年(1063年)八月、伊豫守源頼義、石清水の神を勧請して、瑞籬を当郡由比の郷に建 【東鑑】治承四年(1180年)十月十二日條曰、本社者、後冷泉院御宇、伊豫守源朝臣頼義、奉勅定征伐安倍貞任之時、有丹新之旨、康平六年(1063年)秋八月、潜勧請石清水建瑞籬於当国由比郷、原注に今号之下若宮とあり、按ずるに由比宮の𦾔地は、由比濱大鳥居の東にあり、今に小社を存し社外の末社に属す 永保元年(1081年)二月、陸奥守源義家修理を加ふ 治承四年(1180年)十月、右大将源頼朝鎌倉に到り、由比の宮を遥拝し 七日條曰、先奉遙拝鶴岡八幡宮給 同月、此地を點じて假に宮廟を構へ、由比の宮を遷せり 今の下宮是なり 建久二年(1191年)三月四日神殿以下、悉く回禄に罹る、四月頼朝、下宮後背の山上に、新に寶殿を営作す、是別に八幡宮を、勧請せしが為なり 今の上宮是なり、十一月上下両宮及末社等に至まで、造営成就して、遷宮の儀を行はる、是より両宮となれり
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(山之内庄 鶴岡 五)下ノ宮
若宮と称す
社僧云、若宮とは本社より別ちて、他所に勧請せし宮を号す。蓋頼義、由井(ママ)郷に祀りしは、石清水八幡宮なれど、【東鏡】に載する如く、私に勧請する所なれば、則別宮の義に取り、若宮と称せり、又頼朝上宮を勧請せしは、勅許を得たる事なれば、直に八幡宮と号す、故に此時下宮の神躰を、上宮に遷し、下宮は空殿となりしかば、後世若宮の唱へに因て、仁徳帝を勧請せしなりと、按ずるに、【東鏡】に建久二年(1191年)三月若宮以下火災に罹りし時、新に上宮を造立し、若宮及末社等、悉く再建ありて、十月上下両宮共に、遷宮ありしと見ゆ、然れば下宮、空殿となりしと伝は謬なり、旦頼義の勧請する所、石清水の本宮たらば、若宮の称呼ありとも、頼朝祖先の祀る所を廃して、更に勧請すべき謂なし、社僧の説信じ難し(中略)
治承四年(1180年)十月、源頼朝由比郷より移して建立ありし社なり
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(山之内庄 鶴岡 五)由比若宮
由比ノ濱大鳥居の東、辻町(大町村属)にあり、下宮の原社なり、康平六年(1063年)八月頼義の勧請せしより治承四年(1180年)十月、頼朝下宮の地に移せし事は社の総説に見えたり 【東鑑】仁治二年(1241年)四月由比大鳥居邊の拝殿、逆浪の為に流失せし由載せたるは 即当社の拝殿なるべし 我覺院管す
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
治承四年(1180年)十月七日、源頼朝は鎌倉に入り先ず由比郷に鎮座していた鶴岡八幡宮を遙拝してから鎌倉の経営に着手したようである。
十一日に(伊豆山)走湯山の専光坊良暹が鎌倉に到着すると、十二日には小林郷の北山に建てた宮廟にこの鶴岡八幡宮を遷し、同時に良暹を当座の別当とし大庭景義に宮寺のことを執行わせた。
これが現在の若宮の始まりで、その位置も大体今と同じと考えてよかろう。
そして、頼朝は同社を鶴岡八幡新宮若宮と称している。
鶴岡八幡新宮若宮の称は寿永二年(1183年)の頼朝の寄進状に見える。新宮は本宮に対する分社をいうのであるが、若宮も同じ意に用いられることがある。
由比郷に勧請されていた石清水八幡宮の分社のまた分社として鶴岡八幡新宮若宮と称したのであろう。
遡って由比郷にあった鶴岡八幡宮というのは、源頼義が勅定を奉じて陸奥の安倍貞任を征伐のとき、石清水八幡宮に祈願をこめたが、その効験あって征討の目的を果たすことが出来たので、康平六年(1063年)八月、潜かにかの石清水八幡宮を勧請することとし、由比郷に瑞籬を営んだことに始まる。それから十八年を経た永保元年(1081年)二月に、頼義の子義家がこれに修復を加えたと伝えており、その位置は大町字西町にある由比若宮の地であるといわれている。
建久二年(1191年)三月四日、鎌倉は大火となり、社域にも延焼しすべてが灰燼と化してしまった。
八日には頼朝監臨のもとに、若宮仮殿の造営が始められたが(中略)これを機会に頼朝は改めて石清水八幡宮を勧請しようとして、鶴岡若宮の上の地に社殿の営作を始めたが(中略)これが現在の本宮の起りで大体現在の位置であろう。
十一月二十一日になると本宮に石清水八幡宮の神体が勧請され、若宮及び末社等の遷宮が行われたのである。
これよりのち本宮を鶴岡八幡宮或は鶴岡八幡宮寺などと称し、更にこれを上宮と呼び、鶴岡若宮の社殿は若宮或は下宮と称せられるようになった。
ここに新に石清水八幡宮の神体を勧請したのは、鶴岡を石清水に模するためであったようである。そのため鶴岡若宮の社殿には八幡宮の摂社としての若宮(仁徳天皇以下祭神四座)の神体が勧請されたものと考えられる。
この結果、八幡宮の分社としての鶴岡若宮が、摂社としての若宮の性格を帯びることとなった。
■ 現地掲示(由比若宮 御由緒)
鶴岡八幡宮境内末社。
前九年の役で奥州を鎮定した源頼義が、康平六(1063)年、報賽の意を込め、源氏の守り神である石清水八幡宮を由比郷に潜かに勧請したことに始まる。
鶴岡八幡宮の元となったことから元八幡とも称される。
祭神 応神天皇
例祭日 四月二日 毎月三日
由比若宮創建以前、鎌倉は郡衙が置かれるなど古代東国の要地で、源頼義以来、源家相伝の地としてあった。
源頼義は勅諚により奥州安倍貞任を征伐した時、丹祈の心あって潜かに康平六(1063)年秋に石清水八幡宮を勧請し、瑞籬をを営み、永保元(1081)年には源義家が修復を加えた。
その後治承四(1180)年十月、源頼朝公が鎌倉に入ると、この社を遙拝し、神意を伺って、現在の鶴岡八幡宮の場所である小林郷北山に遷した。
社頭には義家旗立松があり、近くには石清水の井がある。
■ 現地掲示(鶴岡八幡宮境内、抜粋)
御祭神 応神天皇 比売神 神功皇后
当宮は源頼義公が前九年の役平定後、康平六年(1063)報賽のため由比郷鶴岡の地に八幡大神を勧請したのに始まる。
治承四年(1180)源頼朝公は源氏再興の旗を挙げ、父祖由縁の地鎌倉に入ると、まず由比郷の鶴岡八幡宮を遙拝し「祖宗を崇めんが為」小林郷北山(現在地)に奉遷し、京に於ける内裏に相当する位置に据えて諸整備に努めた。
■ 国土交通省資料(PDF)
由比若宮
由比若宮は鎌倉の八幡信仰の発祥の地です。
「元八幡」とも呼ばれるこの宮は、京の帝に武将として仕えた源頼義 (988–1075) が1063 年に創建しました。
1051 年、頼義は侍の謀反を制圧するため東北地方へと送られます。京を発つ際、頼義は源氏の守護神で祖先でもある八幡大神に必勝を祈願しました。
12 年におよぶ戦いを制した頼義は京へ帰る途中鎌倉に立ち寄り、そのとき八幡大神への感謝のしるしとして祀ったのが由比若宮です。
その1世紀以上のちの1180年、頼義の子孫である源頼朝 (1147–1199) が新たに打ち立てた幕府の拠点を鎌倉に置きました。頼朝は町を広げ、その信仰の中心として鶴岡八幡宮を創建しました。
こうして信仰の中心地は鶴岡八幡宮へと移り、頼義が祀った簡素な神社は創建当時と同じ場所に残されました。
■ 観光庁Web資料
由比若宮
由比若宮は鎌倉の八幡信仰の発祥の地です。
京の帝に武将として仕えた源頼義 (988–1075) が1063年に創建しました。1051年、頼義は侍の謀反を制圧するため東北地方へと送られます。京を発つ際、頼義は源氏の守護神で祖先でもある八幡大神に必勝を祈願しました。12年におよぶ戦いを制した頼義は京へ帰る途中鎌倉に立ち寄り、そのとき八幡大神への感謝のしるしとして祀ったのが由比若宮です。
その1世紀以上のちの1180年、頼義の子孫である源頼朝 (1147–1199) が鎌倉に拠点を置き、町を切り開いてその中心に鶴岡八幡宮を建てました。
引き続き八幡大神を源氏の守護神として崇めた頼朝は、京の朝廷を支配していた敵の平氏に対抗すべく兵力を集めます。頼朝は5年にわたった源平合戦に勝利して、日本で初めての武士による政権を鎌倉に打ち立てました。
由比若宮は今も、鶴岡八幡宮参道の東側、海に近い材木座地区の創建当時と同じ場所に建っています。
「元八幡」とも呼ばれるこの宮は、鎌倉の歴史の中で源氏が果たした大きな役割を今に伝える遺産となっています。
■ 石川県神社庁Web(抜粋)
若宮八幡宮
御祭神
応神天皇(境内社より合祀 綿津見神 大山祇神 日本武尊 豊受比売神 大田神)
鎮座地
白山市若宮1丁目100
由緒
康平6年(1063)鎮守府将軍 源頼義の建立と言われる。
源頼義が奥州を平定し、石清水八幡宮を相州鎌倉郡由比郷鶴岡の地に勧請し、次いでこの加賀松任の地に国守富樫介に造営を命じ富樫介の臣であった山上新保介はその命をかしこみ、誠をもって社殿の建立の事にあたると共に新たに武内社守六社の境内社を勧請しました。
-------------------------
小町大路が横須賀線を渡る踏切のすぐ南側の路地を西側に入ったところです。
あたりは住宅地で、鶴岡八幡宮の元宮がこのような目立たない住宅地の一画に御鎮座とはある意味おどろきです。
むろん、神社が先にあったわけですが。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道入口の社号標


【写真 上(左)】 全景
【写真 下(右)】 境内入口
参道入口には社号標、境内入口にも社号標があります。
住宅地のなかにまとまった社叢を配して神さびた空気感。


【写真 上(左)】 境内入口の社号標
【写真 下(右)】 境内


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 参道
朱塗りの一の鳥居抜けると参道左手に「源義家公旗立の松」で、その先に朱塗りの二の鳥居。
すみません。源義家が源氏の白旗を立てて武運長久を願ったとされる「源義家公旗立の松」のUP写真がなぜかありません。
二基の鳥居はいずれも亀腹、転び、貫、額束、島木、笠木、反増を備える明神鳥居系ですが、楔はありません。


【写真 上(左)】 拝殿前
【写真 下(右)】 拝殿
拝殿前に石灯籠一対。
階段をのぼると拝殿です。
拝殿は銅板葺の一間社流造と思われ、身舎、向拝とも朱塗りで華やいだイメージの社殿です。
賽銭箱に刻まれた紋は「鶴の丸(つるのまる)紋」で、鶴岡八幡宮の神紋です。
朱塗りの木柵に囲まれた拝殿前は荘厳な空気が流れ、さすがに鶴岡八幡宮の元宮です。
御朱印は、たまたまご縁があって拝受できましたが、ご不在も多そうです。
境内に書置ありとのWeb情報もありますが、筆者は未確認です。
〔 由比若宮の御首題 〕
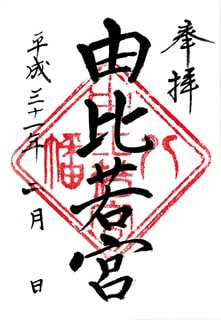
→ ■ 鎌倉市の御朱印-17 (B.名越口-12)へつづく。
【 BGM 】
■ True To Life - Roxy Music (1982)
■ A Clue - Boz Scaggs (1977)
■ After All This Time - Think Out Loud (1988)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)
■ 同-15 (B.名越口-10)から。
47.法華山 本興寺(ほんこうじ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市大町2-5-32
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
司元別当:
札所:
本興寺は、大町二丁目の歴史ある日蓮宗寺院です。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
本興寺は、延元元年(1336年)「九老僧」の一人天目上人が開基建立し、日蓮聖人が辻説法の途中に休息された地に因んで「休息山本興寺」を号しました。
永徳二年(1382年)、2世日什上人が法華山と改め、開山は日什上人とされています。
日蓮聖人の鎌倉辻説法の由緒地・大町にあるため「辻の本興寺」とも呼ばれます。
当山は宗派的に複雑な変遷をたどっています。
開山・美濃阿闍梨天目上人(1256-1337年)は、日蓮六老僧・日朗上人の弟子「九老僧」の一人で日盛、上法房とも称します。
法華山 本興寺(横浜市泉区)公式Webには
「天目上人は、法華経二十八品のうち、前半十四品の迹門と後半十四品の本門では説相が異なると「迹門不読説」を主張しており、天目上人の弟子達も同じ主張をしておりましたが、日什門流の開祖である日什大正師の教化にふれ改派に至りました。」とあります。
この記述は「本迹勝劣」の概念がわからないと理解できません。
ただし、「本迹勝劣」は法華宗の本義にかかわる重要なことがらなので、Wikipediaの内容に従って概略のみまとめてみます。
・所依の法華経を構成する二十八品(28章)は前半の「迹門」、後半の「本門」に二分される。
・二十八品全体を一体のものとして扱うべきとするのが一致派。(釈尊を本仏とする)
・「本門」に法華経の極意があるとするのが勝劣派。
・勝劣派は「釈尊を本仏とする勝劣派」と「日蓮聖人を本仏とする勝劣派」に分かれる。
・「勝劣五派」とは、日興門流(富士門流、興門派)、日什門流(妙満寺派)、日陣門流(本成寺派)、日隆門流(八品派)、日真門流(本隆寺派)をさす。
天目上人は「迹門不読説」を唱えられ、当山2世の日什上人は「釈尊を本仏とする勝劣派」の日什門流の流祖です。
日什上人(1314年-1392年)について、京都妙満寺公式Webには以下のとおりあります。
---------------------------------
19歳で比叡山に登られ「玄妙」と号され、38歳の時には三千人の学僧の学頭となり、「玄妙能化」と称されました。
故郷の会津に戻られた日什上人は66歳のとき、日蓮聖人の御書『開目抄』『如説修行鈔』に触れられ、直ちに日蓮聖人を師と仰ぎ、名を「日什」と改められました。
下総中山の法華経寺にこもられ、不惜身命の布教を誓われた日什上人は、永徳元年(1381)京に上られ関白・二条良基卿と対面し、「洛中弘法の綸旨」と「二位僧都」の官位を賜わりました。
関東でも、関東管領・足利義満公などに諌暁を繰り返され、宗旨と修行の方軌を示されて日什門流を開かれました。
---------------------------------
日什門流は顕本法華宗(総本山・妙満寺)につながり、顕本法華宗の宗祖は日什上人です。
「鎌倉市史 社寺編」によると、天正十九年(1591年)、徳川家康公は当山に寺領五百五十文を寄進しています。
文明十三年(1481年)、当山16世日泰上人は大旦那酒井清伝によって堂を建立とありますが、「千葉市Web資料」によると酒井清伝は上総国土気の武将です。
Wikipediaには「上総酒井氏の祖は酒井清伝と称される人物で、この人物については、16世紀の東金城主酒井胤敏および土気城主酒井胤治が揃って酒井氏の祖として清伝の名前を挙げている。」とあるので、上総酒井氏の祖(酒井定隆?)とみられます。
酒井清伝(定隆)は法華宗(妙満寺派)の日泰上人に帰依した熱心な法華宗信者で、上総北部の平定後数年で領内のほとんどの寺院を法華宗へと改宗させた(上総七里法華)とする伝説があります。
「上総七里法華」は、江戸時代初期に不受不施を唱えた寺院があるといいます。
永禄二年(1559年)、清伝の子酒井胤治とその子政茂も当山を修造、その費用寄進者には生実御所・足利高基の室もいて、造営のため奥州や越中からも僧が鎌倉に来たとあるので、「上総七里法華」が主体となって大々的に改修が行われたのでは。
『鎌倉市史 社寺編』はまた、当山27世から妙満寺27世となった(Wikipedia)日経上人は、慶長の初年(1596年-)に倒壊した堂を慶長四年(1599年)再興したと記しています。
しかし慶長十三年(1608年)、日経上人は「不受不施」を説いたため、江戸幕府より弾圧を受けました。(慶長の法難)
不受不施派は以降も幕府の厳しい詮議を受けたため、万治三年(1660年)当山30世日顕上人により鎌倉郡飯田村に寺基を移したのが、現在の横浜市泉区上飯田町の本興寺といいます。
寛文十年(1670年)、比企谷妙本寺照幡院日逞上人が宗祖辻説法旧地の衰退を嘆き、徳川家より寺領の寄付を受けて、鎌倉の辻の旧地に本興寺を再興したといいます。
日什門流は「釈尊を本仏とする勝劣派」、妙本寺は日朗門流(比企谷門流)で「釈尊を本仏とする一致派」とされますから、複雑な門流を経由していることがわかります。
なお、日什門流の名刹・飯田本興寺は顕本法華宗本山でしたが、明治政府の宗教政策により日蓮宗と合同し、現在も日蓮宗本山(由緒寺院)の寺格を誇っています。
寛文十年(1670年)といえば将軍家綱公の治世。
名刹妙本寺の末寺で家綱公のお墨付きを得たとなれば、江戸時代の寺院経営は安定していたとみられ、明治の神仏分離も乗り切って、「辻の本興寺」の名跡をいまに伝えています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(大町村)本興寺
辻町にあり、法華山と号す 本寺前に同じ(妙本寺末)、古は京妙満寺の末なりしが、中興の後今の末となると云ふ
本尊三寶祖師を安ぜり、開山を日什(明徳三年(1392年)二月廿八日寂す)中興を日逞と云ふ(延寶三年(1675年)五月十七日寂す)天正十九年(1591年)十一月寺領五百五十文の御朱印を賜へり
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
法華山本興寺と号する。日蓮宗。もと妙本寺末。
開山、日什。中興開山、日逞
本尊、三宝祖師
境内地523.82坪。本堂・庫裏・太子堂・渡廊下・山門あり。
もと京都の妙満寺末。日什は明徳三年(1392年)二月廿八日寂、日逞は延寶三年(1675年)五月十七日寂。
天正十九年(1591年)十一月、徳川家康は寺領五百五十文を寄進した。
文明十三年(1481年)六月、当寺十六世日泰は大旦那酒井清伝によって、堂を建立した。(中略)
清伝の子酒井胤治とその子政茂が、永禄二年(1559年)修造した。この時の住持は日芸である。
修理の費用は胤治をはじめその一族がだしたが、その中には生実御所足利高基の室もいて(中略)造営のためには奥州や越中からも僧が鎌倉に来ている。
慶長の初年(1596年-)に再び倒壊した堂を復興するため、日経が僧俗にすすめて(中略)慶長四年(1599年)再興した。
■ 山内掲示(縁起碑)
本興寺略縁起 日蓮大聖人 辻説法之𦾔地
日蓮大聖人鎌倉御弘通の当時 此の地点は若宮小路に至る辻なるにより 今猶辻の本興寺と称す 御弟子天目上人聖躅を継いで又此地に折伏説法あり 實に当山の開基なり 後年日什上人(顕本法華宗開祖)留錫せられ 寺観大いに面目を改む 常楽院日経上人も亦 当寺の第廿七世なり
■ 法華山 本興寺(横浜市泉区)公式Webより
本興寺は、日蓮大聖人の直弟子である天目上人が鎌倉に開創したお寺です。
大聖人が辻説法の途中、休息された地として、『休息山本興寺』と称していました。
天目上人は、法華経二十八品のうち、前半十四品の迹門と後半十四品の本門では説相が異なると「迹門不読説」を主張しており、天目上人の弟子達も同じ主張をしておりましたが、日什門流の開祖である日什大正師の教化にふれ改派に至りました。
その後、弘和2年(1382年)に『法華山 本興寺』と改称しました。
以後、日什大正師を当山の事実上の開祖としております。
また、現在本興寺のある飯田は、弘安5年(1282年)に日蓮大聖人が池上でご入滅後、ご遺骨を身延に奉じる途次、10月20日頃にご一泊された地と伝えられています。
(中略)
万治3年(1660年)に現在の地(泉区上飯田町)にお寺の一切を移されたとされています。
-------------------------
小町大路が横須賀線を渡る踏切のすぐ北側に参道があり、山内北側は旧車小路に面しています。
参道入口には「日蓮大聖人辻説法之𦾔地」の石碑(縁起碑)が建っています。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 縁起碑


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 山門
山門手前左手にお題目が刻まれた寺号標。
山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、門柱は朱塗りの丸柱です。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 飾り瓦
山内正面が入母屋造桟瓦葺流れ向拝の整った意匠の本堂。
軒上の飾り瓦の獅子の表情がいい味を出しています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 鎮守?
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股を置いています。
向拝正面は端正な唐桟戸。
山内に御鎮座の朱塗りの一間社流造のお社と石祠は当山鎮守でしょうか。
御首題は、参拝時本堂前におられたご住職からこころよく授与いただけましたが、こちらやこちらの記事によるとご不在が多そうです。
〔 本興寺の御首題 〕

48.由比若宮(鶴岡八幡宮元宮・元鶴岡八幡宮)(ゆいのわかみや)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市材木座1-7
御祭神:応神天皇
※■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1でも触れています。
由比若宮は鶴岡八幡宮の元宮で、頼朝公や鎌倉幕府にとってすこぶる重要な神社です。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
康平六年(1063年)源頼義公が、奥州安倍氏征伐(前九年の役)にあたり、京の石清水八幡宮に戦捷を祈願されました。
征伐が成り京に帰る帰途、鎌倉に立ち寄られ由比郷鶴岡に源氏の守り神である石清水八幡宮の御祭神を勧請されて創祀といいます。
永保元年(1081年)には、頼義公の子八幡太郎義家公が修復したとも伝わります。
治承四年(1180年)10月7日(11日とも)、鎌倉に入られた源頼朝公は、まず由比郷の鶴岡八幡宮を遙拝され、そののちに鎌倉の経営に着手したといいます。
同月11日、(伊豆山)走湯山の専光坊良暹が鎌倉に到着すると、12日には小林郷北山に建てた宮廟に(由比郷の)鶴岡八幡宮を遷し、同時に良暹を当座の別当としました。
これが現在の若宮(下宮)の始まりで、頼朝公は同社を「鶴岡八幡新宮若宮」と称されました。
つまり、康平六年(1063年)源頼義公創祀の(由比郷)鶴岡八幡宮を、治承四年(1180年)10月に源頼朝公が現在の若宮(下宮)に御遷座ということになります。
【 由比元宮と鶴岡八幡宮の関係 】
両社の関係については、史料によりニュアンスが異なりますが、だいたいつぎのとおりです。
・康平六年(1063年)源頼義公が(由比郷)鶴岡八幡宮を創祀。
・治承四年(1180年)鎌倉に入られた頼朝公が(由比郷)鶴岡八幡宮を今の若宮(下宮)の地に御遷座。
・(由比郷)鶴岡に御鎮座だったが、小林郷北山(現社地)に遷したのちも「鶴岡」を号した。
・建久二年(1191年)11月、若宮(下宮)の上方の地に建てた本宮社殿に石清水八幡宮の御神体を勧請。若宮及び末社等の遷宮も行われた。
『新編相模國風土記稿』の「(山之内庄 鶴岡 五)下ノ宮」の條に意味深な記述があります。
それは「社僧が語った」という内容で、頼義公が由比郷に祀った鶴岡八幡宮は石清水八幡宮からの勧請ながら、私の勧請だったので「別宮」の意味で「若宮」と称している。
これに対して(鶴岡八幡宮)上宮は、頼朝公が勅許を得て(公式に)勧請されたので直に「八幡宮」と称しているというのです。
また、下宮の神躰を上宮に遷して下宮は空殿となったところ、後世「若宮」の称に因んで(応神帝/誉田別命)の御子の仁徳帝(大鷦鷯命)を勧請せしめたとも。
これに対して『新編相模國風土記稿』の著者は、【東鏡】によると建久二年3月に若宮以下火災に罹りしとき、新たに上宮を造立、若宮および末社等もことごとく再建されて10月には上下両宮ともに(石清水八幡宮)から遷宮ありとあるので、「下宮は空殿となった」というのは誤謬であると断じています。
しかし、康平六年(1063年)源頼義公の勧請を多くの史料・資料が「潜かに(ひそかに)」と記しているのは、上記の社僧の「私の勧請」という説明とニュアンスが重なります。
由比元宮と鶴岡八幡宮の関係がわかりにくくなっているのは、「別宮」「新宮」「若宮」の意味が錯綜しているためと思われます。
たとえば「別宮」・「若宮」は、「本宮」(石清水八幡宮)から私に勧請した宮の意で使われています。
「新宮」は「本宮」からの分社で「若宮」も同じ意味に用いられることがあるといいます。
また、八幡社では「本宮」の御祭神・誉田別命(応神帝)に対し「若宮」では御子の仁徳帝(大鷦鷯命)を祀る例が多くみられます。
頼朝公が由比郷から小林郷に遷座された八幡宮を「鶴岡八幡新宮若宮」と称したことが混乱のもととも思えますが、『鎌倉市史 社寺編』に記されている「由比郷に勧請されていた石清水八幡宮の分社のまた分社として鶴岡八幡新宮若宮と称したのであろう。」という見解がわかりやすいように思えます。
この考えをとると、由比郷鶴岡の八幡宮は「鶴岡八幡本宮若宮」になるかとも思いますが、これを記した史料は存在しない模様です。
【 由比若宮の御祭神 】
由比若宮の御祭神を記した史料や公的資料はほとんどありませんが、境内縁起書には「祭神 応神天皇」とあります。
しかし、Web記事ではつぎのふたつの記載がみられます。
1.応神天皇
2.応神天皇、比売神、神功皇后
康平六年(1063年)、源頼義公が由比郷鶴岡に勧請されたのは石清水八幡宮です。
このとき勧請された御祭神は、つぎの2パターンが考えられるので、ここから↑の2説が出てきているかと思います。
1.石清水八幡宮の中御前御祭神:誉田別命(応神天皇)
2.石清水八幡宮の八幡三所大神
(中御前:誉田別命(応神天皇)、西御前:比咩大神(比売神)、東御前:息長帯姫命(神功皇后))
いずれにしても主祭神は応神天皇ですから、この時点では「若宮」は称せず、由比郷鶴岡に御鎮座の八幡宮ということで「鶴岡八幡宮」を称したのではないかと思いました。
しかし、そうではないかもしれません。
石川県白山市若宮に源頼義公建立と伝わる若宮八幡宮があります。
石川県神社庁のWeb資料によると、こちらの御祭神は応神天皇で、由緒に「康平6年(1063)鎮守府将軍 源頼義の建立と言われる。源頼義が奥州を平定し、石清水八幡宮を相州鎌倉郡由比郷鶴岡の地に勧請し、次いでこの加賀松任の地に国守富樫介に造営を命じ」とあります。
由比若宮と同年に源頼義公が建立し、おそらく石清水八幡宮からの勧請で御祭神は応神天皇。そして社号は「若宮八幡宮」です。
こちらの「若宮」の社号は「本宮(石清水八幡宮)から勧請した『若宮』」から来ているとも思われます。
となると、あるいは由比若宮も当初から「若宮」を称していたのかもしれません。
---------------------------------
ここからはほとんど筆者の推測です。
・治承四年(1180年)頼朝公が小林郷に造営し(由比郷)鶴岡八幡宮から御遷座のお社は、石清水八幡宮から勧請したため「若宮」を称した。
・頼朝公が石清水八幡宮からの勧請社を「若宮」を称した以上、由比郷の八幡宮も「(由比)若宮」と称した。(あるいは当初から「若宮」を称していた。)
・康平六年(1063年)頼朝公が造営した「本社」(上社)には、改めて石清水八幡宮から八幡三所大神(中御前:誉田別命(応神天皇)、西御前:比咩大神(比売神)、東御前:息長帯姫命(神功皇后))を勧請。このとき、旧「若宮」の御祭神が合祀?されたかは不明。
・新しい「若宮」(下宮)には石清水八幡宮から仁徳天皇、履中天皇・仲媛命・磐之媛命の四柱を勧請し、ここに(若宮=仁徳天皇)が成立。
となると、気になるのは小林郷北山に御遷座されたのちの由比の鶴岡八幡宮です。
『新編相模國風土記稿』に「旦頼義の勧請する所、石清水の本宮たらば、若宮の称呼ありとも、頼朝祖先の祀る所を廃して、更に勧請すべき謂なし」とあり、頼朝公が祖先の祀る所(頼義公勧請の由比若宮)を廃するいわれはないと断じています。
『新編相模國風土記稿』には「其𦾔地なれば今に祠ありて鶴岡八幡社職の持とす」「由比宮の𦾔地は、由比濱大鳥居の東にあり、今に小社を存し社外の末社に属す」とあり、由比若宮の祠は鶴岡八幡宮の社外末社で鶴岡八幡社職が奉仕していたことを伝えます。
鶴岡八幡宮境内には由比若宮遥拝所があることから、昔もいまも元宮たる神社として尊崇されているものとみられます。


【写真 上(左)】 由比若宮遙拝所(鶴岡八幡宮境内)
【写真 下(右)】 同
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新刊吾妻鏡 巻1』(国立国会図書館)
治承四年(1180年)十月十一日庚寅
卯尅御臺所入御鎌倉 景義奉迎之 去夜自伊豆國阿岐戸郷 雖令到着給 依日次不宜 止宿稻瀬河邊民居給云々 又走湯山住侶專光房良暹 依兼日御契約参着 是武衛年來御師檀也
治承四年(1180年)十月十二日辛卯
快晴 寅尅 為崇祖宗 點小林郷之北山搆宮廟 被奉遷鶴岳(岡)宮於此所 以專光房暫為別當職 令景義執行宮寺事 武衛此間潔齋給 當宮御在所 本新両所用捨 賢慮猶危給之間 任神鑒 於寳前自令取鬮給 治定當砌訖 然而未及花搆之餝 先作茅茨之営 本社者 後冷泉院御宇 伊豫守源朝臣頼義奉勅定 征伐安倍貞任之時 有丹祈之旨 康平六年秋八月 潜勧請石淸水 建瑞籬於當國由比郷 今号之下若宮 永保元年二月 陸奥守同朝臣義家加修復 今又奉遷小林郷 致●繁礼奠云々
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
下宮𦾔地
下宮𦾔地は、由比濱大鳥居の東にあり、【東鏡】に、頼朝卿、鎌倉に入給ふ時、先遙に鶴岡の八幡宮を拝み奉るとあるは、此所に有し時也。此所に有し社を、今の若宮の地に遷し奉らん為に、本・新両所の用捨を、賽前にて籤を取、今の若宮の地に治定し給ふ。本と有は此所の事、新とあるは今の若宮の事なり。爰を鶴岡と云ゆへに、小林へ遷して後も、鶴岡の若宮と云なり。鶴岡の條下と照し見るべし。
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
鶴岡八幡宮
鶴岡八幡宮は、【東鏡】に、本社は、伊豫守源頼義、勅を奉て、安倍貞任征伐の時、丹新の旨有て、康平六年(1063年)秋八月、潜に石清水を勧請し、瑞籬を当國由比郷に建。今此を下宮の𦾔跡と云也。永保元年(1081年)二月、陸奥守源義家、修復を加ふ。其後治承四年(1180年)十月十二日、源頼朝、祖宗を崇めんがために、小林郷の北の山を點じて宮廟を構へ、鶴岡由比の宮を此所に遷し奉る。(中略)
由比濱下の宮の𦾔地を、昔しは鶴が岡と云なり。【東鏡】に、治承四年(1180年)十月七日、頼朝先遙に鶴岡の八幡宮ををがみ奉るとあるは、由比濱の宮なり。小林郷に遷して後も、又鶴岡の八幡宮と云傳へたり。
■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
若宮𦾔地
由比濱大鳥居の東の方にあり、此邊を往昔は鶴岡と号しける𦾔地なり。右大将家、治承四年(1180年)十月鎌倉に入給ふ最初、まづ遙に八幡宮を拝み奉るとあるは、爰に鎮座の宮殿をいふ。是則天喜年中(1053-1058年)、源頼義朝臣当所へ初て勧請の社頭なり。頼朝卿、今の地へ移し給はんとせらるゝ砌、本新両所決しかたく、神前にて籤を取給ふとあるも此地にて、本といふは爰の𦾔地をさし、新とは今の社地をさす。神監に任て、今の地に治定せしと云云。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(大町村)下若宮
辻町の西にあり、往昔当所を鶴岡と号す 今𦾔号を失ふ
康平六年(1063年)八月、頼義潜に石清水の神官を模して此所に勧請ありしを治承四年(1180年)頼朝鎌倉に入て当所の宮を小林松ヶ岡に遷し、夫より彼地も鶴岡と号す、其𦾔地なれば今に祠ありて鶴岡八幡社職の持とす 事は鶴岡八幡宮の條に詳載す
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(山之内庄 鶴岡)鶴岡八幡宮
康平六年(1063年)八月、伊豫守源頼義、石清水の神を勧請して、瑞籬を当郡由比の郷に建 【東鑑】治承四年(1180年)十月十二日條曰、本社者、後冷泉院御宇、伊豫守源朝臣頼義、奉勅定征伐安倍貞任之時、有丹新之旨、康平六年(1063年)秋八月、潜勧請石清水建瑞籬於当国由比郷、原注に今号之下若宮とあり、按ずるに由比宮の𦾔地は、由比濱大鳥居の東にあり、今に小社を存し社外の末社に属す 永保元年(1081年)二月、陸奥守源義家修理を加ふ 治承四年(1180年)十月、右大将源頼朝鎌倉に到り、由比の宮を遥拝し 七日條曰、先奉遙拝鶴岡八幡宮給 同月、此地を點じて假に宮廟を構へ、由比の宮を遷せり 今の下宮是なり 建久二年(1191年)三月四日神殿以下、悉く回禄に罹る、四月頼朝、下宮後背の山上に、新に寶殿を営作す、是別に八幡宮を、勧請せしが為なり 今の上宮是なり、十一月上下両宮及末社等に至まで、造営成就して、遷宮の儀を行はる、是より両宮となれり
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(山之内庄 鶴岡 五)下ノ宮
若宮と称す
社僧云、若宮とは本社より別ちて、他所に勧請せし宮を号す。蓋頼義、由井(ママ)郷に祀りしは、石清水八幡宮なれど、【東鏡】に載する如く、私に勧請する所なれば、則別宮の義に取り、若宮と称せり、又頼朝上宮を勧請せしは、勅許を得たる事なれば、直に八幡宮と号す、故に此時下宮の神躰を、上宮に遷し、下宮は空殿となりしかば、後世若宮の唱へに因て、仁徳帝を勧請せしなりと、按ずるに、【東鏡】に建久二年(1191年)三月若宮以下火災に罹りし時、新に上宮を造立し、若宮及末社等、悉く再建ありて、十月上下両宮共に、遷宮ありしと見ゆ、然れば下宮、空殿となりしと伝は謬なり、旦頼義の勧請する所、石清水の本宮たらば、若宮の称呼ありとも、頼朝祖先の祀る所を廃して、更に勧請すべき謂なし、社僧の説信じ難し(中略)
治承四年(1180年)十月、源頼朝由比郷より移して建立ありし社なり
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(山之内庄 鶴岡 五)由比若宮
由比ノ濱大鳥居の東、辻町(大町村属)にあり、下宮の原社なり、康平六年(1063年)八月頼義の勧請せしより治承四年(1180年)十月、頼朝下宮の地に移せし事は社の総説に見えたり 【東鑑】仁治二年(1241年)四月由比大鳥居邊の拝殿、逆浪の為に流失せし由載せたるは 即当社の拝殿なるべし 我覺院管す
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
治承四年(1180年)十月七日、源頼朝は鎌倉に入り先ず由比郷に鎮座していた鶴岡八幡宮を遙拝してから鎌倉の経営に着手したようである。
十一日に(伊豆山)走湯山の専光坊良暹が鎌倉に到着すると、十二日には小林郷の北山に建てた宮廟にこの鶴岡八幡宮を遷し、同時に良暹を当座の別当とし大庭景義に宮寺のことを執行わせた。
これが現在の若宮の始まりで、その位置も大体今と同じと考えてよかろう。
そして、頼朝は同社を鶴岡八幡新宮若宮と称している。
鶴岡八幡新宮若宮の称は寿永二年(1183年)の頼朝の寄進状に見える。新宮は本宮に対する分社をいうのであるが、若宮も同じ意に用いられることがある。
由比郷に勧請されていた石清水八幡宮の分社のまた分社として鶴岡八幡新宮若宮と称したのであろう。
遡って由比郷にあった鶴岡八幡宮というのは、源頼義が勅定を奉じて陸奥の安倍貞任を征伐のとき、石清水八幡宮に祈願をこめたが、その効験あって征討の目的を果たすことが出来たので、康平六年(1063年)八月、潜かにかの石清水八幡宮を勧請することとし、由比郷に瑞籬を営んだことに始まる。それから十八年を経た永保元年(1081年)二月に、頼義の子義家がこれに修復を加えたと伝えており、その位置は大町字西町にある由比若宮の地であるといわれている。
建久二年(1191年)三月四日、鎌倉は大火となり、社域にも延焼しすべてが灰燼と化してしまった。
八日には頼朝監臨のもとに、若宮仮殿の造営が始められたが(中略)これを機会に頼朝は改めて石清水八幡宮を勧請しようとして、鶴岡若宮の上の地に社殿の営作を始めたが(中略)これが現在の本宮の起りで大体現在の位置であろう。
十一月二十一日になると本宮に石清水八幡宮の神体が勧請され、若宮及び末社等の遷宮が行われたのである。
これよりのち本宮を鶴岡八幡宮或は鶴岡八幡宮寺などと称し、更にこれを上宮と呼び、鶴岡若宮の社殿は若宮或は下宮と称せられるようになった。
ここに新に石清水八幡宮の神体を勧請したのは、鶴岡を石清水に模するためであったようである。そのため鶴岡若宮の社殿には八幡宮の摂社としての若宮(仁徳天皇以下祭神四座)の神体が勧請されたものと考えられる。
この結果、八幡宮の分社としての鶴岡若宮が、摂社としての若宮の性格を帯びることとなった。
■ 現地掲示(由比若宮 御由緒)
鶴岡八幡宮境内末社。
前九年の役で奥州を鎮定した源頼義が、康平六(1063)年、報賽の意を込め、源氏の守り神である石清水八幡宮を由比郷に潜かに勧請したことに始まる。
鶴岡八幡宮の元となったことから元八幡とも称される。
祭神 応神天皇
例祭日 四月二日 毎月三日
由比若宮創建以前、鎌倉は郡衙が置かれるなど古代東国の要地で、源頼義以来、源家相伝の地としてあった。
源頼義は勅諚により奥州安倍貞任を征伐した時、丹祈の心あって潜かに康平六(1063)年秋に石清水八幡宮を勧請し、瑞籬をを営み、永保元(1081)年には源義家が修復を加えた。
その後治承四(1180)年十月、源頼朝公が鎌倉に入ると、この社を遙拝し、神意を伺って、現在の鶴岡八幡宮の場所である小林郷北山に遷した。
社頭には義家旗立松があり、近くには石清水の井がある。
■ 現地掲示(鶴岡八幡宮境内、抜粋)
御祭神 応神天皇 比売神 神功皇后
当宮は源頼義公が前九年の役平定後、康平六年(1063)報賽のため由比郷鶴岡の地に八幡大神を勧請したのに始まる。
治承四年(1180)源頼朝公は源氏再興の旗を挙げ、父祖由縁の地鎌倉に入ると、まず由比郷の鶴岡八幡宮を遙拝し「祖宗を崇めんが為」小林郷北山(現在地)に奉遷し、京に於ける内裏に相当する位置に据えて諸整備に努めた。
■ 国土交通省資料(PDF)
由比若宮
由比若宮は鎌倉の八幡信仰の発祥の地です。
「元八幡」とも呼ばれるこの宮は、京の帝に武将として仕えた源頼義 (988–1075) が1063 年に創建しました。
1051 年、頼義は侍の謀反を制圧するため東北地方へと送られます。京を発つ際、頼義は源氏の守護神で祖先でもある八幡大神に必勝を祈願しました。
12 年におよぶ戦いを制した頼義は京へ帰る途中鎌倉に立ち寄り、そのとき八幡大神への感謝のしるしとして祀ったのが由比若宮です。
その1世紀以上のちの1180年、頼義の子孫である源頼朝 (1147–1199) が新たに打ち立てた幕府の拠点を鎌倉に置きました。頼朝は町を広げ、その信仰の中心として鶴岡八幡宮を創建しました。
こうして信仰の中心地は鶴岡八幡宮へと移り、頼義が祀った簡素な神社は創建当時と同じ場所に残されました。
■ 観光庁Web資料
由比若宮
由比若宮は鎌倉の八幡信仰の発祥の地です。
京の帝に武将として仕えた源頼義 (988–1075) が1063年に創建しました。1051年、頼義は侍の謀反を制圧するため東北地方へと送られます。京を発つ際、頼義は源氏の守護神で祖先でもある八幡大神に必勝を祈願しました。12年におよぶ戦いを制した頼義は京へ帰る途中鎌倉に立ち寄り、そのとき八幡大神への感謝のしるしとして祀ったのが由比若宮です。
その1世紀以上のちの1180年、頼義の子孫である源頼朝 (1147–1199) が鎌倉に拠点を置き、町を切り開いてその中心に鶴岡八幡宮を建てました。
引き続き八幡大神を源氏の守護神として崇めた頼朝は、京の朝廷を支配していた敵の平氏に対抗すべく兵力を集めます。頼朝は5年にわたった源平合戦に勝利して、日本で初めての武士による政権を鎌倉に打ち立てました。
由比若宮は今も、鶴岡八幡宮参道の東側、海に近い材木座地区の創建当時と同じ場所に建っています。
「元八幡」とも呼ばれるこの宮は、鎌倉の歴史の中で源氏が果たした大きな役割を今に伝える遺産となっています。
■ 石川県神社庁Web(抜粋)
若宮八幡宮
御祭神
応神天皇(境内社より合祀 綿津見神 大山祇神 日本武尊 豊受比売神 大田神)
鎮座地
白山市若宮1丁目100
由緒
康平6年(1063)鎮守府将軍 源頼義の建立と言われる。
源頼義が奥州を平定し、石清水八幡宮を相州鎌倉郡由比郷鶴岡の地に勧請し、次いでこの加賀松任の地に国守富樫介に造営を命じ富樫介の臣であった山上新保介はその命をかしこみ、誠をもって社殿の建立の事にあたると共に新たに武内社守六社の境内社を勧請しました。
-------------------------
小町大路が横須賀線を渡る踏切のすぐ南側の路地を西側に入ったところです。
あたりは住宅地で、鶴岡八幡宮の元宮がこのような目立たない住宅地の一画に御鎮座とはある意味おどろきです。
むろん、神社が先にあったわけですが。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 参道入口の社号標


【写真 上(左)】 全景
【写真 下(右)】 境内入口
参道入口には社号標、境内入口にも社号標があります。
住宅地のなかにまとまった社叢を配して神さびた空気感。


【写真 上(左)】 境内入口の社号標
【写真 下(右)】 境内


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 参道
朱塗りの一の鳥居抜けると参道左手に「源義家公旗立の松」で、その先に朱塗りの二の鳥居。
すみません。源義家が源氏の白旗を立てて武運長久を願ったとされる「源義家公旗立の松」のUP写真がなぜかありません。
二基の鳥居はいずれも亀腹、転び、貫、額束、島木、笠木、反増を備える明神鳥居系ですが、楔はありません。


【写真 上(左)】 拝殿前
【写真 下(右)】 拝殿
拝殿前に石灯籠一対。
階段をのぼると拝殿です。
拝殿は銅板葺の一間社流造と思われ、身舎、向拝とも朱塗りで華やいだイメージの社殿です。
賽銭箱に刻まれた紋は「鶴の丸(つるのまる)紋」で、鶴岡八幡宮の神紋です。
朱塗りの木柵に囲まれた拝殿前は荘厳な空気が流れ、さすがに鶴岡八幡宮の元宮です。
御朱印は、たまたまご縁があって拝受できましたが、ご不在も多そうです。
境内に書置ありとのWeb情報もありますが、筆者は未確認です。
〔 由比若宮の御首題 〕
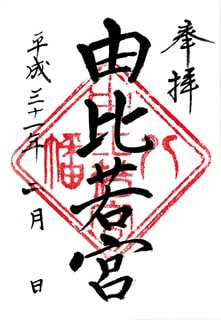
→ ■ 鎌倉市の御朱印-17 (B.名越口-12)へつづく。
【 BGM 】
■ True To Life - Roxy Music (1982)
■ A Clue - Boz Scaggs (1977)
■ After All This Time - Think Out Loud (1988)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 長瀞秋の七草寺巡り&埼玉県長瀞町の札所と御朱印
長瀞秋の七草寺巡りは、境内に「秋の七草」が一種類づつ植えられている長瀞町内の七つのお寺を巡る札所巡りです。
ウォーキングブーム、花の写真ブーム、そして御朱印ブームが重なって、人気を集めているようです。
今回は、あわせて長瀞町内でいただいた御朱印をすべてご紹介します。
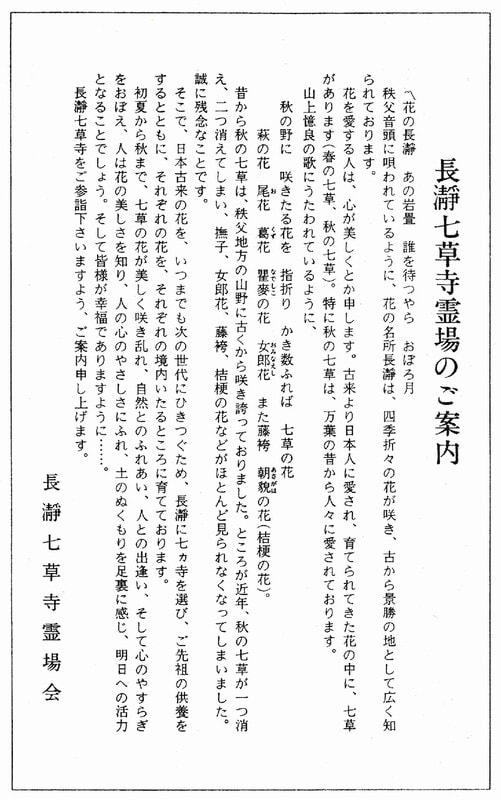
長瀞七草寺霊場のご案内(専用納経帳)
→ 秩父観光協会Web
→ 長瀞町観光協会
→ 同 パンフ(PDF)
→ 秩父鉄道
→ 地図(東武鉄道、PDF)
■ ご朱印ラリー
8/24(木)~9/30(土) 受付時間 9:00~17:00
各七草寺を巡り、七ヶ寺すべてのご朱印(有料)を集めます。
七ヶ寺すべてのご朱印を集めた方には、最終のお寺にて記念品を差し上げます。
8年ぶりに専用御朱印帳で回ってみました。
前回(2016年9月)に比べるとだいぶん人は少なめで、御朱印ブームの落ち着きを感じますが、その分ゆったりと参拝や撮影ができると思います。
綺麗な花のイラスト入りの専用台紙もありますので、これもスタンプをいただいてきました。
朱印が御寶印や三寶印でなく、花の印なので厳密には御朱印とはいえないかもしれませんが、こちらもご紹介します。

台紙にスタンプ捺印
「ご朱印ラリー」は9月末日までです。
今年は猛暑で開花が遅れているせいか、9月中旬でもほとんど満開でした。
なお、専用御朱印帳は1,700円、御朱印(揮毫)は各500円。印判捺印は各200円です。
満願の記念品は2016年は手ぬぐい、2024年は一筆箋でした。
2016年は御朱印(揮毫)、2024年は専用御朱印帳(捺印)での結願だったので、それぞれれ記念品が違うのかもしれません。(未確認)

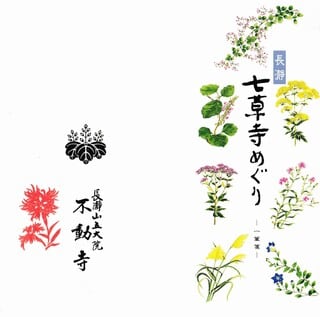
【写真 上(左)】 結願でいただけた手拭い(2016年)
【写真 下(右)】 結願でいただけた一筆箋(2021年)
駐車場は全寺院ありますが、狭い路地やアプローチ道が荒れ気味のところもあるので要注意。
御朱印対応は17:00までです。
筆者は12時少し前から車で回り始めましたが、楽勝で結願&寶登山神社の参拝ができました。(ただし昼からだと奥宮はきびしいかも。)




---------------------------------
2016-09-11 UP
■長瀞秋の七草寺巡り
・秩父鉄道サイト
・長瀞町観光協会サイト
境内に「秋の七草」が一種類づつ植えられている長瀞町内の七つのお寺を巡る札所巡り。
ウォーキングブーム、花の写真ブーム、そして御朱印ブームが重なって、近年とみに活況を呈しているようです。
各鉄道会社が力を入れているので、電車で行き徒歩・レンタサイクルや巡回バスなどで楽しむのも手かと思いますが、今回は車で行きました。
札所間の距離はさしてないので、早めに現地に入れば徒歩でも1日で結願できるかと思います。
花の盛りはややタイムラグがあって、くず、ききょう、なでしこが早めです。
秩父鉄道のチラシでもこの3ヶ寺を先に巡る2日間分割プランが紹介されていました。
また、この霊場は他札所の重複札所が1ヶ寺しかないので、御朱印収集的にも貴重なものだと思います。
●秋の七草
山上憶良が詠んだ以下の二首の歌がその由来とされ、滋養などのために”七草がゆ”を楽しむ「春の七草」とちがって、花の美しさを愛でるものとされているようです。
秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花
〔万葉集・巻八 1537〕
萩の花 尾花 葛花 瞿麦(なでしこ)の花 姫部志(をみなへし) また藤袴 朝貌の花
〔万葉集・巻八 1538〕
尾花はすすき、をみなへしは女郎花とも。「朝貌の花」は桔梗とするのが定説のようで、やはり桔梗が植えられていました。
春の七草は調子のよい「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」の順で定着していますが、秋の七草の順序は諸説あります。
山上憶良の歌に因むと、「はぎ、おばな、くず、なでしこ、おみなえし、ふじばかま、ききょう」となります。
五・七・五の調子でいくなら「はぎ、ききょう、くず、ふじばかま、おみなえし、おばな、なでしこ、(秋の七草)」となります。
語呂で知られているのは「おすきなふく(服)は」で、「お:おみなえし、す:すすき、き:ききょう、な:なでしこ、ふ:ふじばかま、く:くず、は:はぎ」となります。
べつに「おおきなはかま(袴)は(穿)く」=「お:おみなえし、お:おばな、き:ききょう、な:なでしこ、はかま:ふじばかま、は:はぎ、く:くず」というのもあります。
秩父鉄道、町観光協会のチラシともに並び順は↑のいずれともことなるランダムですが、末尾のおみなえしとなでしこだけは一致しています。(長瀞駅周辺での結願を意図したものだと思う。)
筆者はふだんは順打ち、逆打ちにはさほどこだわらないのですが、今回は一日結願なので御朱印の構成(順序)にこだわってみました(笑)
やはり、由来とされる山上憶良の歌に因む、「はぎ、おばな、くず、なでしこ、おみなえし、ふじばかま、ききょう」の順にしました。
寄居方面から入りこの順番で順打ちすると、おばなとなでしこで道順の重複が出るので、効率的に回るために頁を決めて揮毫いただくという、綴じ式納経帳的な方法をとりました。
長瀞七草寺で花をテーマにしたブログ記事はたくさんみつかるので、今回はほとけさまに焦点をあててまとめてみたいと思います。
1.不動山 白山寺 洞昌院 【萩】
埼玉県長瀞町野上下郷2868
真言宗智山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:同上
他札所:関東三十六不動尊霊場第29番
花期:7月中旬~9月下旬


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 萩-1
【写真 下(右)】 萩-2


【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)


【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン
七草寺で唯一、他霊場の札所(関東三十六不動尊霊場)を兼ねるお寺です。
私は関東三十六不動、連れは七草寺の御朱印をいただきましたが、単に「御朱印をお願いします」というと、どちらの御朱印か尋ねられるかもしれません。(2016年)
御本尊は弘法大師のお作とも伝わる不動明王です。
奥の院は「苔不動」の聖地とされていますが、今回は遙拝のみでした。
本堂左手には虚空蔵菩薩のお堂があり、向拝から扉越しに端正なお姿が拝観できます。
萩は参道から本堂前、そして裏山とたくさん植えられています。
2.吉祥山 道光寺 【尾花(すすき)】
埼玉県長瀞町岩田735
臨済宗妙心寺派
御本尊:釈迦如来
御朱印尊格:同上
花期:7月中旬~9月下旬


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 尾花-1
【写真 下(右)】 尾花-2


【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)


【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン
寄居方面から入ると最初のお寺で、秩父鉄道「樋口」駅からも近いのでここから打ち始める人も多いかもしれません。県道に面して広いPがあります。
開けた感じの明るい寺で、あちこちで尾花が穂を上げています。
色味に微妙なコントラストがあり、陽光を受けてとても綺麗でした。
山門右手の六地蔵もすすきを背景になかなか画になります。
納経所には地元の方?が何人か詰められてご開帳札所のようです。
御本尊は釈迦如来で、普賢、文殊の両菩薩とともに釈迦三尊形式となっており、御朱印の尊格も”南無釈迦三尊”となっています。
3.野上山 金剛院 遍照寺 【くず】
埼玉県長瀞町野上下郷2322
真言宗智山派
御本尊:神変大菩薩(役行者)
御朱印尊格:同上
花期:8月上旬~9月中旬(葛の花のトンネル)


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 くず-1
【写真 下(右)】 くず-2

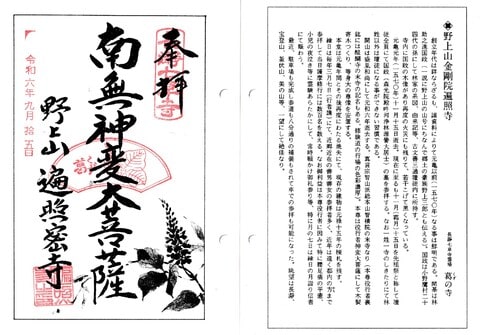
【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)
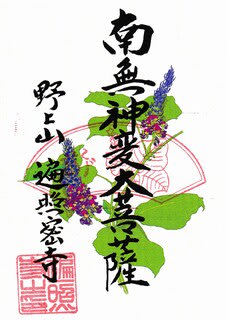

【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン


【写真 上(左)】 役行者のおすがた
【写真 下(右)】 遍照寺
すこし山手に入ったところにあります。徒歩アプローチと車アプローチは別で、車アプローチは距離は短いですが一部未舗装で荒れ気味です。
Pからは山道をトラバース気味に少し下って葛棚をくぐっての風情あるアプローチ。
高台で見晴らしもよい好ロケーションのお寺です。
御本尊は、御本尊としてはめずらしい役行者(神変大菩薩)で、等身大で迫力があります。
脇本尊として不動明王もおわしますが、こちらも古色を帯びられて風格あるお姿でした。
御本尊が役行者ということもあってか、山岳修験的な雰囲気を感じます。由緒書きによると醍醐寺とのつながりを示すものもあるそうです。
御朱印の尊格は”神変大菩薩”。役行者の御朱印はなかなかいただけないのでこれは希少です。
4.長瀞山 五大院 不動寺 【撫子】
埼玉県長瀞町長瀞1753-1
真言宗醍醐派
御本尊:不動明王・五大明王
御朱印尊格:同上
花期:7月下旬~10月上旬(河原撫子約5,000本)


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 撫子-1
【写真 下(右)】 撫子-2


【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)


【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン
宝登山ロープウェイの乗場のそばにあるお寺で、宝登山ロープウェイ駐車場の奥にPがあります。じっさいにはここが最後(結願)のお寺となりました。
なお、ETCによっては全然違う場所をナビされるので、国道から寶登山神社の鳥居をくぐり、左手のロープウェイ乗場の方へ坂を登り、参道をすこし進むと階段手前に駐車スペースがあります。
寶登山は山岳信仰の歴史も古く、寶登山神社・玉泉寺から不動寺にかけてはやはり山岳修験的な雰囲気を感じます。
開山は品川寺三十一世・仲田順和和上(境内縁起書より)で、いまなお真言宗醍醐派別格本山である品川寺との関係が深そうです。
また、「火生三昧・火渡り荒行」が年々厳修されているようです。
本堂はこぢんまりとしていますが、御内陣須弥壇には御本尊不動明王とその脇侍である矜羯羅童子と制多迦童子、そして、東に降三世明王、南に軍荼利明王、西に大威徳明王、北に金剛夜叉明王がおわされる壮麗な五大明王の様式となっています。
筆者参拝時は堂内にあげていただけたので、まぢかで拝することができました。
ふつう不動明王を御本尊とする寺院では、御真言として中咒(慈救咒)が掲げられていることが多いですが、ここでは、大咒(火界咒)、中咒(慈救咒)、小咒(一字咒)と掲げられていて、護摩修行の場としての臨場感があります。(2016年)
御朱印の尊格は”五大力尊”で、これも関東では例のすくないものです。
参道まわりや本堂前に植えられているなでしこは、近年害虫に蕾を食べられてしまうとのことで、かろうじて数輪のみ咲いていました。(2024年)
5.東谷山 真性寺 【女郎花(おみなえし)】
埼玉県長瀞町本野上436
真言宗智山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:同上
花期:7月中旬~9月下旬


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 おみなえし-1
【写真 下(右)】 おみなえし-2
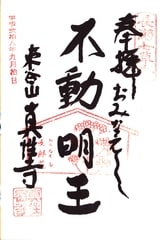

【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)
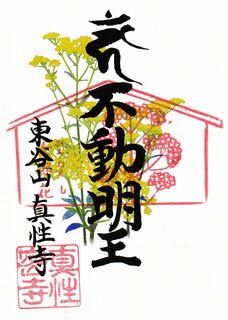

【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン
アプローチは狭いですが、本堂手前に駐車できるスペースがあります。
規模は大きくないですが、なんとなくほのぼのとした感じのするお寺です。
おみなえしは本堂を囲むようにたくさん植えられていて満開でした。
本堂前には立派な修行大師像が御座されます。
弘法大師御作と伝わる薬師如来像も護持されています。
「幸せを運ぶ青い蜂」ともいわれる”オオセイボウ”が来ていて、写真も撮れました。


【写真 上(左)】 オオセイボウ
【写真 下(右)】 オオセイボウの説明書
6.金嶽山 法善寺 【藤袴(ふじばかま)】
埼玉県長瀞町井戸4176
臨済宗妙心寺派
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:同上
花期:9月上旬~10月上旬


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 ふじばかま-1
【写真 下(右)】 ふじばかま-2

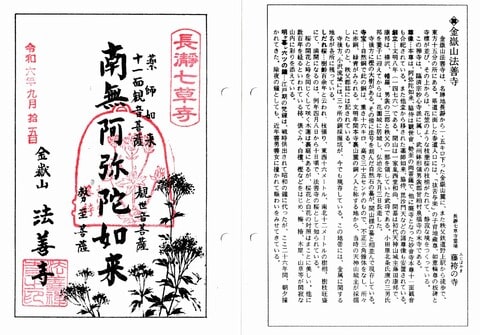
【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)


【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン
道沿いに広いP。風格ある山門、楚々とした境内は禅寺の趣。
文明八年(1476年)、初代天神山城主藤田康邦と伝わる古刹です。
境内のあちこちで咲いていたふじばかまは繊細な花姿で、うす紫と白の二種類あります。
すっきりとした御内陣。竜虎の欄間彫刻が見事でした。
御朱印はご住職とおぼしきご高齢の方に揮毫いただけました。味わいのあるすばらしい筆致です。(2016年)
7.金玉山 多宝寺 【桔梗(ききょう)】
埼玉県長瀞町本野上40-1
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
御朱印尊格:同上
花期:7月下旬~9月下旬


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 桔梗-1
【写真 下(右)】 桔梗-2
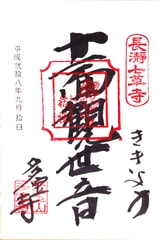
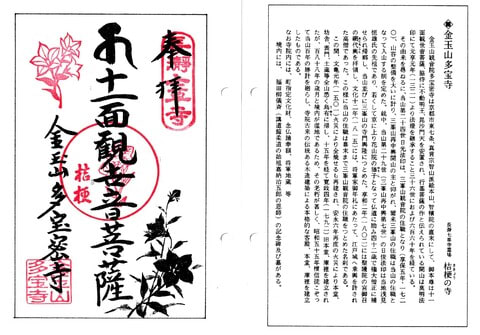
【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)


【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン
道沿いに大きなスペースがありますが、Pはさらに奥です。
参道まわりには、如意輪観世音菩薩や馬頭観世音菩薩も御座します。
ちょうど巡礼バスが発車するところで、20人以上も乗っていたと思います。このバスの到着とかちあうと御朱印拝受は時間がかかるのでは?(2016年)
なお、今回御朱印所は最大でも3人待ち、ほとんどは待ちなしでいただけました。御朱印を受けない参拝客もけっこういたので、ウォーキングメインの人も多いのでは。
ききょうは参道まわりや本堂前に植えられています。
御本尊はこの霊場唯一の観音様で行基菩薩御作と伝わります。
十一面観世音菩薩は人々の十一品類の無明煩悩を断ち切る功徳を施すとされ、数々の大寺の御本尊とされる力感のある観音様です。
脇侍は不動明王、毘沙門天の三尊様式です。
---------------------------------
長瀞七草寺の御朱印の特徴は、中央の御宝印・三宝印のかわりに花の印判が捺されているところです。
イメージ的にはやさしい感じがありますが、不動明王、釈迦三尊、神変大菩薩、五大力尊、不動明王、阿弥陀如来、十一面観世音菩薩と力感ある尊格が並びます。


【写真 上(左)】 七草寺の御朱印
【写真 下(右)】 不動寺の御朱印所看板


【写真 上(左)】 洞昌院の七草寺霊場の御朱印
【写真 下(右)】 洞昌院の関東三十六不動霊場の御朱印
------------------------------------------------
(2016年)
結願後、かなり時間があったので、寶登山神社や秩父十三佛、秩父七福神の札所巡りにモードチェンジ。(御朱印三昧 ^^; )
寶登山神社はさすがですね。空気がちがいます。本殿から藤谷淵神社、日本武尊社、天満天神社、宝玉稲荷神社と回っていくと、なぜかいつの間にか玉泉寺の境内にいるという・・・。
神仏習合、そして特殊な分離の歴史があるそう。(玉泉寺の御朱印は授与されていないようです。)
あと、藤谷淵神社の御祭神にはおどろきました。

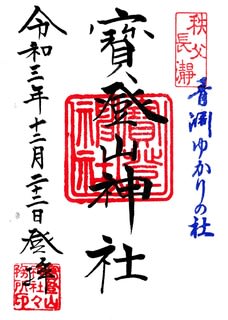
【写真 上(左)】 寶登山神社
【写真 下(右)】 寶登山神社の御朱印(2021年)


【写真 上(左)】 寶登山神社の御朱印(2024年)
【写真 下(右)】 寶登山神社の御朱印帳


【写真 上(左)】 玉泉寺山門
【写真 下(右)】 みごとなタマゴタケが生えていました
寶登山神社奥宮はロープウェイを使ってのアプローチ。
降り場からもそれなりに歩きますので、余裕をもった参拝をおすすめします。


【写真 上(左)】 寶登山神社奥宮
【写真 下(右)】 寶登山奥宮の御朱印
寶登山神社は人気のパワスポらしく、若いカップルや女性グループが目立ちました。人気のかき氷も行列店がいくつかありました。
---------------------------------
長瀞町では、上記のほかつぎの御朱印がいただけます。
普光山 総持寺
埼玉県長瀞町本野上924
臨済宗南禅寺派
御本尊:文殊菩薩
札所:秩父七福神(福禄寿)


※御本尊の御朱印は不授与です。
【秩父満願の湯】


【写真 上(左)】 満願の湯
【写真 下(右)】 秩父鹿の味噌焼丼
参拝を終えて、ひさびさに秩父満願の湯に立ち寄りました。
入浴前に「秩父鹿の味噌焼丼」があったので食べてみました。味噌だけでシンプルに仕上げられ鹿肉の滋味が引き立ってなかなか美味でした。こういうのはあまり手を加えずにシンプルに調理した方がいいですね。
連れが注文した”黄金めし(セット)”もなかなか美味でした。(セットでついていた蕎麦のレベルも想定外に高かった。)
脱衣所、露天まわりなどリニューアルされて綺麗になっていました。依然はやや雑多な感じのあった脱衣所&浴場がシックな感じに一新され、これはリニューアルの成功例では。
露天から望む奥長瀞渓谷の佇まいはやはりいいですね。日帰り温泉では関東でも屈指の沢沿い露天ではないでしょうか。
土曜の夜だったのでファミリー客が目立ちました。客回転を速めるためか湯温が高めに設定されていて、子供さんがゆっくり入れる浴槽があまりなくちょっと気の毒でした。
全体にお湯のコンディションは悪くないです。
とくに水風呂は源泉のかけ流しに近い湯づかいで、しっかりイオウ臭が香ります。高アルカリのイオウ重曹泉系の威力発揮でお肌つるつる。
このところ秩父では新木鉱泉ばかり入っていたのですが、新木の”甘イオウ臭たまご水”とはちょっとちがったニュアンスを感じました。
以前のレポはこちら(当サイトでのレポは近日UPの予定。)
【 BGM 】
■ Best Part Of My Life - Marc Jordan
■ You Stand Out - The Manhattans
■ Umoya - Miriam Stockley
ウォーキングブーム、花の写真ブーム、そして御朱印ブームが重なって、人気を集めているようです。
今回は、あわせて長瀞町内でいただいた御朱印をすべてご紹介します。
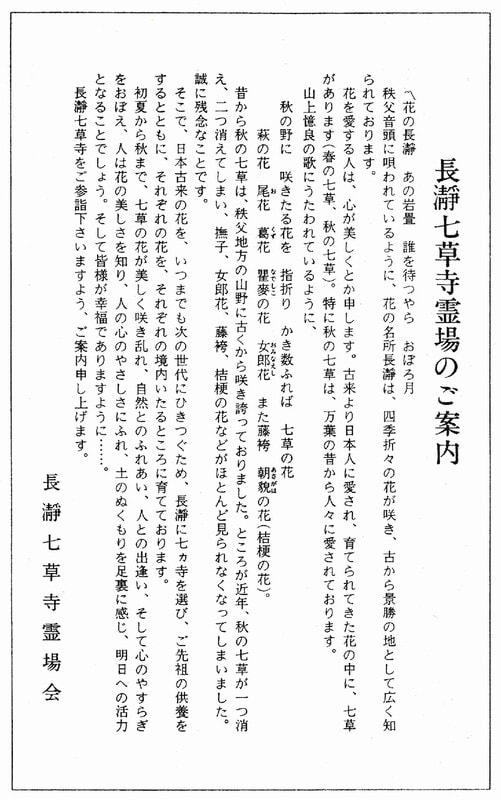
長瀞七草寺霊場のご案内(専用納経帳)
→ 秩父観光協会Web
→ 長瀞町観光協会
→ 同 パンフ(PDF)
→ 秩父鉄道
→ 地図(東武鉄道、PDF)
■ ご朱印ラリー
8/24(木)~9/30(土) 受付時間 9:00~17:00
各七草寺を巡り、七ヶ寺すべてのご朱印(有料)を集めます。
七ヶ寺すべてのご朱印を集めた方には、最終のお寺にて記念品を差し上げます。
8年ぶりに専用御朱印帳で回ってみました。
前回(2016年9月)に比べるとだいぶん人は少なめで、御朱印ブームの落ち着きを感じますが、その分ゆったりと参拝や撮影ができると思います。
綺麗な花のイラスト入りの専用台紙もありますので、これもスタンプをいただいてきました。
朱印が御寶印や三寶印でなく、花の印なので厳密には御朱印とはいえないかもしれませんが、こちらもご紹介します。

台紙にスタンプ捺印
「ご朱印ラリー」は9月末日までです。
今年は猛暑で開花が遅れているせいか、9月中旬でもほとんど満開でした。
なお、専用御朱印帳は1,700円、御朱印(揮毫)は各500円。印判捺印は各200円です。
満願の記念品は2016年は手ぬぐい、2024年は一筆箋でした。
2016年は御朱印(揮毫)、2024年は専用御朱印帳(捺印)での結願だったので、それぞれれ記念品が違うのかもしれません。(未確認)

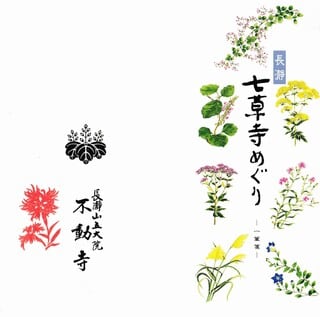
【写真 上(左)】 結願でいただけた手拭い(2016年)
【写真 下(右)】 結願でいただけた一筆箋(2021年)
駐車場は全寺院ありますが、狭い路地やアプローチ道が荒れ気味のところもあるので要注意。
御朱印対応は17:00までです。
筆者は12時少し前から車で回り始めましたが、楽勝で結願&寶登山神社の参拝ができました。(ただし昼からだと奥宮はきびしいかも。)




---------------------------------
2016-09-11 UP
■長瀞秋の七草寺巡り
・秩父鉄道サイト
・長瀞町観光協会サイト
境内に「秋の七草」が一種類づつ植えられている長瀞町内の七つのお寺を巡る札所巡り。
ウォーキングブーム、花の写真ブーム、そして御朱印ブームが重なって、近年とみに活況を呈しているようです。
各鉄道会社が力を入れているので、電車で行き徒歩・レンタサイクルや巡回バスなどで楽しむのも手かと思いますが、今回は車で行きました。
札所間の距離はさしてないので、早めに現地に入れば徒歩でも1日で結願できるかと思います。
花の盛りはややタイムラグがあって、くず、ききょう、なでしこが早めです。
秩父鉄道のチラシでもこの3ヶ寺を先に巡る2日間分割プランが紹介されていました。
また、この霊場は他札所の重複札所が1ヶ寺しかないので、御朱印収集的にも貴重なものだと思います。
●秋の七草
山上憶良が詠んだ以下の二首の歌がその由来とされ、滋養などのために”七草がゆ”を楽しむ「春の七草」とちがって、花の美しさを愛でるものとされているようです。
秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花
〔万葉集・巻八 1537〕
萩の花 尾花 葛花 瞿麦(なでしこ)の花 姫部志(をみなへし) また藤袴 朝貌の花
〔万葉集・巻八 1538〕
尾花はすすき、をみなへしは女郎花とも。「朝貌の花」は桔梗とするのが定説のようで、やはり桔梗が植えられていました。
春の七草は調子のよい「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」の順で定着していますが、秋の七草の順序は諸説あります。
山上憶良の歌に因むと、「はぎ、おばな、くず、なでしこ、おみなえし、ふじばかま、ききょう」となります。
五・七・五の調子でいくなら「はぎ、ききょう、くず、ふじばかま、おみなえし、おばな、なでしこ、(秋の七草)」となります。
語呂で知られているのは「おすきなふく(服)は」で、「お:おみなえし、す:すすき、き:ききょう、な:なでしこ、ふ:ふじばかま、く:くず、は:はぎ」となります。
べつに「おおきなはかま(袴)は(穿)く」=「お:おみなえし、お:おばな、き:ききょう、な:なでしこ、はかま:ふじばかま、は:はぎ、く:くず」というのもあります。
秩父鉄道、町観光協会のチラシともに並び順は↑のいずれともことなるランダムですが、末尾のおみなえしとなでしこだけは一致しています。(長瀞駅周辺での結願を意図したものだと思う。)
筆者はふだんは順打ち、逆打ちにはさほどこだわらないのですが、今回は一日結願なので御朱印の構成(順序)にこだわってみました(笑)
やはり、由来とされる山上憶良の歌に因む、「はぎ、おばな、くず、なでしこ、おみなえし、ふじばかま、ききょう」の順にしました。
寄居方面から入りこの順番で順打ちすると、おばなとなでしこで道順の重複が出るので、効率的に回るために頁を決めて揮毫いただくという、綴じ式納経帳的な方法をとりました。
長瀞七草寺で花をテーマにしたブログ記事はたくさんみつかるので、今回はほとけさまに焦点をあててまとめてみたいと思います。
1.不動山 白山寺 洞昌院 【萩】
埼玉県長瀞町野上下郷2868
真言宗智山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:同上
他札所:関東三十六不動尊霊場第29番
花期:7月中旬~9月下旬


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 萩-1
【写真 下(右)】 萩-2


【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)


【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン
七草寺で唯一、他霊場の札所(関東三十六不動尊霊場)を兼ねるお寺です。
私は関東三十六不動、連れは七草寺の御朱印をいただきましたが、単に「御朱印をお願いします」というと、どちらの御朱印か尋ねられるかもしれません。(2016年)
御本尊は弘法大師のお作とも伝わる不動明王です。
奥の院は「苔不動」の聖地とされていますが、今回は遙拝のみでした。
本堂左手には虚空蔵菩薩のお堂があり、向拝から扉越しに端正なお姿が拝観できます。
萩は参道から本堂前、そして裏山とたくさん植えられています。
2.吉祥山 道光寺 【尾花(すすき)】
埼玉県長瀞町岩田735
臨済宗妙心寺派
御本尊:釈迦如来
御朱印尊格:同上
花期:7月中旬~9月下旬


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 尾花-1
【写真 下(右)】 尾花-2


【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)


【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン
寄居方面から入ると最初のお寺で、秩父鉄道「樋口」駅からも近いのでここから打ち始める人も多いかもしれません。県道に面して広いPがあります。
開けた感じの明るい寺で、あちこちで尾花が穂を上げています。
色味に微妙なコントラストがあり、陽光を受けてとても綺麗でした。
山門右手の六地蔵もすすきを背景になかなか画になります。
納経所には地元の方?が何人か詰められてご開帳札所のようです。
御本尊は釈迦如来で、普賢、文殊の両菩薩とともに釈迦三尊形式となっており、御朱印の尊格も”南無釈迦三尊”となっています。
3.野上山 金剛院 遍照寺 【くず】
埼玉県長瀞町野上下郷2322
真言宗智山派
御本尊:神変大菩薩(役行者)
御朱印尊格:同上
花期:8月上旬~9月中旬(葛の花のトンネル)


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 くず-1
【写真 下(右)】 くず-2

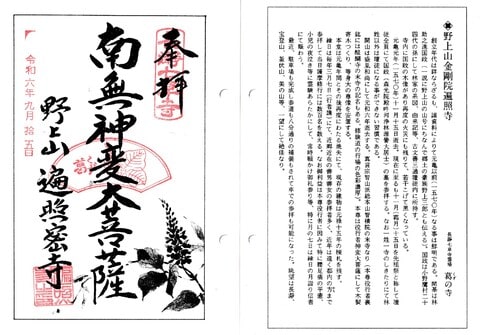
【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)
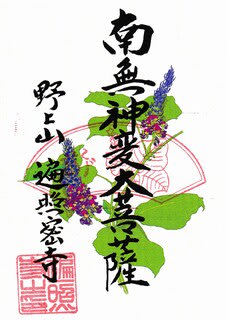

【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン


【写真 上(左)】 役行者のおすがた
【写真 下(右)】 遍照寺
すこし山手に入ったところにあります。徒歩アプローチと車アプローチは別で、車アプローチは距離は短いですが一部未舗装で荒れ気味です。
Pからは山道をトラバース気味に少し下って葛棚をくぐっての風情あるアプローチ。
高台で見晴らしもよい好ロケーションのお寺です。
御本尊は、御本尊としてはめずらしい役行者(神変大菩薩)で、等身大で迫力があります。
脇本尊として不動明王もおわしますが、こちらも古色を帯びられて風格あるお姿でした。
御本尊が役行者ということもあってか、山岳修験的な雰囲気を感じます。由緒書きによると醍醐寺とのつながりを示すものもあるそうです。
御朱印の尊格は”神変大菩薩”。役行者の御朱印はなかなかいただけないのでこれは希少です。
4.長瀞山 五大院 不動寺 【撫子】
埼玉県長瀞町長瀞1753-1
真言宗醍醐派
御本尊:不動明王・五大明王
御朱印尊格:同上
花期:7月下旬~10月上旬(河原撫子約5,000本)


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 撫子-1
【写真 下(右)】 撫子-2


【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)


【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン
宝登山ロープウェイの乗場のそばにあるお寺で、宝登山ロープウェイ駐車場の奥にPがあります。じっさいにはここが最後(結願)のお寺となりました。
なお、ETCによっては全然違う場所をナビされるので、国道から寶登山神社の鳥居をくぐり、左手のロープウェイ乗場の方へ坂を登り、参道をすこし進むと階段手前に駐車スペースがあります。
寶登山は山岳信仰の歴史も古く、寶登山神社・玉泉寺から不動寺にかけてはやはり山岳修験的な雰囲気を感じます。
開山は品川寺三十一世・仲田順和和上(境内縁起書より)で、いまなお真言宗醍醐派別格本山である品川寺との関係が深そうです。
また、「火生三昧・火渡り荒行」が年々厳修されているようです。
本堂はこぢんまりとしていますが、御内陣須弥壇には御本尊不動明王とその脇侍である矜羯羅童子と制多迦童子、そして、東に降三世明王、南に軍荼利明王、西に大威徳明王、北に金剛夜叉明王がおわされる壮麗な五大明王の様式となっています。
筆者参拝時は堂内にあげていただけたので、まぢかで拝することができました。
ふつう不動明王を御本尊とする寺院では、御真言として中咒(慈救咒)が掲げられていることが多いですが、ここでは、大咒(火界咒)、中咒(慈救咒)、小咒(一字咒)と掲げられていて、護摩修行の場としての臨場感があります。(2016年)
御朱印の尊格は”五大力尊”で、これも関東では例のすくないものです。
参道まわりや本堂前に植えられているなでしこは、近年害虫に蕾を食べられてしまうとのことで、かろうじて数輪のみ咲いていました。(2024年)
5.東谷山 真性寺 【女郎花(おみなえし)】
埼玉県長瀞町本野上436
真言宗智山派
御本尊:不動明王
御朱印尊格:同上
花期:7月中旬~9月下旬


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 おみなえし-1
【写真 下(右)】 おみなえし-2
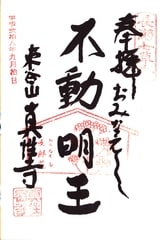

【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)
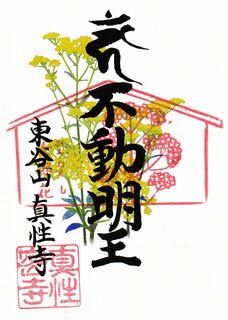

【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン
アプローチは狭いですが、本堂手前に駐車できるスペースがあります。
規模は大きくないですが、なんとなくほのぼのとした感じのするお寺です。
おみなえしは本堂を囲むようにたくさん植えられていて満開でした。
本堂前には立派な修行大師像が御座されます。
弘法大師御作と伝わる薬師如来像も護持されています。
「幸せを運ぶ青い蜂」ともいわれる”オオセイボウ”が来ていて、写真も撮れました。


【写真 上(左)】 オオセイボウ
【写真 下(右)】 オオセイボウの説明書
6.金嶽山 法善寺 【藤袴(ふじばかま)】
埼玉県長瀞町井戸4176
臨済宗妙心寺派
御本尊:阿弥陀如来
御朱印尊格:同上
花期:9月上旬~10月上旬


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 ふじばかま-1
【写真 下(右)】 ふじばかま-2

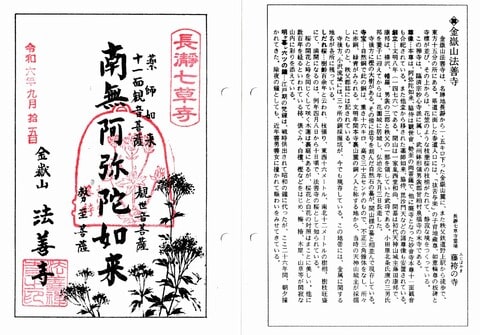
【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)


【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン
道沿いに広いP。風格ある山門、楚々とした境内は禅寺の趣。
文明八年(1476年)、初代天神山城主藤田康邦と伝わる古刹です。
境内のあちこちで咲いていたふじばかまは繊細な花姿で、うす紫と白の二種類あります。
すっきりとした御内陣。竜虎の欄間彫刻が見事でした。
御朱印はご住職とおぼしきご高齢の方に揮毫いただけました。味わいのあるすばらしい筆致です。(2016年)
7.金玉山 多宝寺 【桔梗(ききょう)】
埼玉県長瀞町本野上40-1
真言宗智山派
御本尊:十一面観世音菩薩
御朱印尊格:同上
花期:7月下旬~9月下旬


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 扁額


【写真 上(左)】 桔梗-1
【写真 下(右)】 桔梗-2
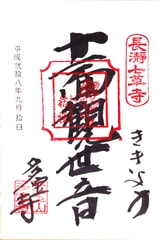
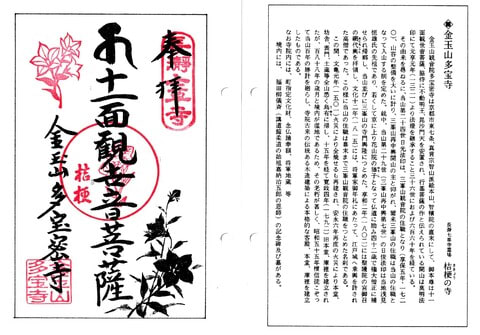
【写真 上(左)】 御朱印(揮毫)
【写真 下(右)】 御朱印(専用御朱印帳)


【写真 上(左)】 台紙スタンプ
【写真 下(右)】 案内サイン
道沿いに大きなスペースがありますが、Pはさらに奥です。
参道まわりには、如意輪観世音菩薩や馬頭観世音菩薩も御座します。
ちょうど巡礼バスが発車するところで、20人以上も乗っていたと思います。このバスの到着とかちあうと御朱印拝受は時間がかかるのでは?(2016年)
なお、今回御朱印所は最大でも3人待ち、ほとんどは待ちなしでいただけました。御朱印を受けない参拝客もけっこういたので、ウォーキングメインの人も多いのでは。
ききょうは参道まわりや本堂前に植えられています。
御本尊はこの霊場唯一の観音様で行基菩薩御作と伝わります。
十一面観世音菩薩は人々の十一品類の無明煩悩を断ち切る功徳を施すとされ、数々の大寺の御本尊とされる力感のある観音様です。
脇侍は不動明王、毘沙門天の三尊様式です。
---------------------------------
長瀞七草寺の御朱印の特徴は、中央の御宝印・三宝印のかわりに花の印判が捺されているところです。
イメージ的にはやさしい感じがありますが、不動明王、釈迦三尊、神変大菩薩、五大力尊、不動明王、阿弥陀如来、十一面観世音菩薩と力感ある尊格が並びます。


【写真 上(左)】 七草寺の御朱印
【写真 下(右)】 不動寺の御朱印所看板


【写真 上(左)】 洞昌院の七草寺霊場の御朱印
【写真 下(右)】 洞昌院の関東三十六不動霊場の御朱印
------------------------------------------------
(2016年)
結願後、かなり時間があったので、寶登山神社や秩父十三佛、秩父七福神の札所巡りにモードチェンジ。(御朱印三昧 ^^; )
寶登山神社はさすがですね。空気がちがいます。本殿から藤谷淵神社、日本武尊社、天満天神社、宝玉稲荷神社と回っていくと、なぜかいつの間にか玉泉寺の境内にいるという・・・。
神仏習合、そして特殊な分離の歴史があるそう。(玉泉寺の御朱印は授与されていないようです。)
あと、藤谷淵神社の御祭神にはおどろきました。

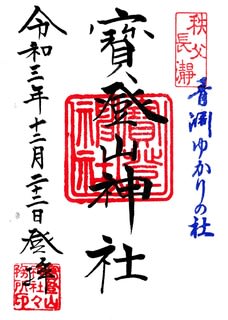
【写真 上(左)】 寶登山神社
【写真 下(右)】 寶登山神社の御朱印(2021年)


【写真 上(左)】 寶登山神社の御朱印(2024年)
【写真 下(右)】 寶登山神社の御朱印帳


【写真 上(左)】 玉泉寺山門
【写真 下(右)】 みごとなタマゴタケが生えていました
寶登山神社奥宮はロープウェイを使ってのアプローチ。
降り場からもそれなりに歩きますので、余裕をもった参拝をおすすめします。


【写真 上(左)】 寶登山神社奥宮
【写真 下(右)】 寶登山奥宮の御朱印
寶登山神社は人気のパワスポらしく、若いカップルや女性グループが目立ちました。人気のかき氷も行列店がいくつかありました。
---------------------------------
長瀞町では、上記のほかつぎの御朱印がいただけます。
普光山 総持寺
埼玉県長瀞町本野上924
臨済宗南禅寺派
御本尊:文殊菩薩
札所:秩父七福神(福禄寿)


※御本尊の御朱印は不授与です。
【秩父満願の湯】


【写真 上(左)】 満願の湯
【写真 下(右)】 秩父鹿の味噌焼丼
参拝を終えて、ひさびさに秩父満願の湯に立ち寄りました。
入浴前に「秩父鹿の味噌焼丼」があったので食べてみました。味噌だけでシンプルに仕上げられ鹿肉の滋味が引き立ってなかなか美味でした。こういうのはあまり手を加えずにシンプルに調理した方がいいですね。
連れが注文した”黄金めし(セット)”もなかなか美味でした。(セットでついていた蕎麦のレベルも想定外に高かった。)
脱衣所、露天まわりなどリニューアルされて綺麗になっていました。依然はやや雑多な感じのあった脱衣所&浴場がシックな感じに一新され、これはリニューアルの成功例では。
露天から望む奥長瀞渓谷の佇まいはやはりいいですね。日帰り温泉では関東でも屈指の沢沿い露天ではないでしょうか。
土曜の夜だったのでファミリー客が目立ちました。客回転を速めるためか湯温が高めに設定されていて、子供さんがゆっくり入れる浴槽があまりなくちょっと気の毒でした。
全体にお湯のコンディションは悪くないです。
とくに水風呂は源泉のかけ流しに近い湯づかいで、しっかりイオウ臭が香ります。高アルカリのイオウ重曹泉系の威力発揮でお肌つるつる。
このところ秩父では新木鉱泉ばかり入っていたのですが、新木の”甘イオウ臭たまご水”とはちょっとちがったニュアンスを感じました。
以前のレポはこちら(当サイトでのレポは近日UPの予定。)
【 BGM 】
■ Best Part Of My Life - Marc Jordan
■ You Stand Out - The Manhattans
■ Umoya - Miriam Stockley
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-15 (B.名越口-10)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)から。
※字数制限の関係上、44.円龍山 向福寺の記事は後ほどUPします。
45.内裏山 霊獄院 九品寺(くほんじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座5-13-14
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:(乱橋材木座)三島明神
札所:鎌倉三十三観音霊場第16番、相州二十一ヶ所霊場第9番、小田急沿線花の寺四季めぐり第18番
九品寺は、新田義貞公開基と伝わる浄土宗の古刹です。
鎌倉市観光協会Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
元弘三年(1333年)新田義貞公の鎌倉攻めの際、本陣をかまえたという場所で、義貞公が京から招いた風航順西和尚を開山に、北条方の戦死者の霊を弔うため創建と伝わります。
創建年は建武三年/延元元年(1336年)と建武四年/延元二年(1337年)の2説あります。
こちら(「鎌倉史跡・寺社データベース」様)には、「もともとは別の場所にあり、かつて乱橋材木座にあった三島明神の別当であったが、荒廃し、後に現在地に移ったという。」とあり、草創が1336年、当地での開山が1337年かもしれません。
(ただし、わずか1年で「荒廃」は解せませんが。)
当山は鎌倉では数少ない新田義貞公ゆかりの寺院です。
義貞公は『太平記』前半の主役といってもいいほど登場回数が多いですが、『太平記』のみ記載の事跡も多く、史実が辿りにくい人物です。
Wikipediaなどから義貞公の略歴を追ってみます。
新田氏の開祖は、八幡太郎源義家公の三男(諸説あり)源義国公です。
義国公は下野国足利荘(栃木県足利市)を本拠とし、足利荘は次子・義康公が継いで足利氏を名乗り、異母兄の義重公は上野国八幡荘を継承し、新田荘を立荘して新田氏を称しました。
新田義貞公(1301-1338年)は、新田朝氏公(新田氏宗家7代当主)の嫡男として 正安三年(1301年)頃に生まれました。(里見氏からの養子説あり)
新田荘がある大間々扇状地は、ふるくは「笠懸野」(かさかけの)と呼ばれたとおり、広大な平地が広がり馬掛けに適した土地柄で、義貞公とその郎党はこの「笠懸野」で弓馬の術を磨きました。
新田氏は河内源氏の名族で鎌倉御家人でしたが、頼朝公の親族として優遇され北条氏とも婚姻関係にあった足利氏にくらべ、幕府内の地位や家格は高いものではありませんでした。
新田宗家4代当主政義公の妻は足利宗家3代当主義氏公の息女で、その子政氏公が新田家嫡流を継ぎ、以降足利氏は新田氏の代々の烏帽子親であったという説があります。
実際、義貞公の烏帽子親は足利氏嫡流で早世した足利高義公で、義貞の「義」は高義の「義」の偏諱とするとされ、鎌倉末期の両氏は対立関係にはなかったとみられています。
文保二年(1318年)、義貞公は新田氏宗家の家督を継承、8代当主となりました。
しかし、その頃の義貞公は無位無官だったとみられ、とくに北条得宗家との関係が悪く鎌倉幕府から冷遇されていたとも。
世良田氏や大舘氏など新田一門も、幕府内で高い地位を得たという記録はありません。
義貞公は得宗被官の安東聖秀の姪を妻として迎えたとされ、北条得宗家への接近もみられますが、鎌倉幕府内で重きをなすことはありませんでした。
一方、足利尊氏公は得宗・北条高時公の偏諱を受けて「高氏」を名乗り、わずか15歳にして官位は従五位下治部大輔でした。
Wikipediaには「15歳での叙爵は北条氏であれば得宗家・赤橋家に次ぎ、大仏家・金沢家と同格の待遇であり、北条氏以外の御家人に比べれば圧倒的に優遇されていた」とあり、幕府内で格別の地位にあったことがわかります。
元弘元年(1331年)8月、倒幕をめざす後醍醐帝と幕府・北条得宗家の間で、いわゆる「元弘の乱」が起こりました。
後醍醐帝は笠置山の戦いで幕府方の大軍に破れ逃亡しました。
幕府は帝が京から逃れるとただちに廃位し、光厳帝を即位させ、捕虜とした後醍醐帝を隠岐に流しました。
元弘二年(1332年)大番役として在京していた義貞公は、幕府の動員令に応じて他の御家人らと後醍醐帝方の楠木正成討伐に向かい 千早城の戦いに参加しています。
元弘三年(1333年)3月、義貞公は病気を理由に河内を退去し新田荘に帰参しました。
『太平記』には元弘の乱の出兵中、義貞公が護良親王と接触して北条氏打倒の綸旨を受けたとありますが、真偽について諸説あるようです。
義貞公の新田荘帰還後、幕府は軍資金として新田氏に膨大な額の納税(有徳銭)を命じ、徴税人(金沢出雲介親連と黒沼彦四郎)を差し向けました。
法外な金額と強引な徴税に憤激した義貞公は、金沢を幽閉し黒沼を斬殺しました。
これを咎めた幕府が新田討伐の軍勢を差し向けるという情報が入り、同年5月、ついに義貞公は倒幕の兵を挙げました。
生品明神社(生品神社)での義貞公決起の名場面は、『太平記』でよく知られています。
この時点の新田軍主力は、義貞公に弟の脇屋義助、大舘宗氏とその一族、堀口貞満、江田行義、岩松経家、里見義胤、桃井尚義などとみられています。

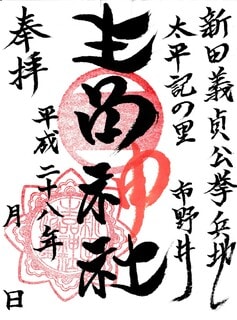
【写真 上(左)】 生品明神社(生品神社)
【写真 下(右)】 生品明神社(生品神社)の御朱印
新田勢は新田を発して上野国八幡荘に入り、越後勢、甲斐源氏、信濃源氏の一派と合流して9,000余の軍勢に膨れ上がったといいます。
5月9日、新田勢は武蔵国に向けて出撃、足利尊氏公(1305-1358年、当初は「高氏」ですが「尊氏」で統一します)の嫡男・千寿王(後の足利義詮公)と久米川付近で合流しました。
これを受けてさらに兵士が集まり、『太平記』では20万7,000騎と記しています。
千寿王の参陣は政治的に大きく、鎌倉攻めの軍勢には義貞公と千寿王の二人の大将がいたとする説があり、千寿王挙兵に義貞公が参陣という説さえあります。
義貞公挙兵の報を受けた幕府方は、桜田貞国を総大将、長崎高重、長崎孫四郎左衛門、加治二郎左衛門を副将とする幕府軍約5万で入間川へと向かい、別働隊として金沢貞将を大将とする上総・下総勢2万が下総の下河辺郷に集結しました。
新田勢は鎌倉街道を南下し、5月11日に小手指原(所沢市小手指)で幕府軍と衝突しました。(小手指原の戦い)
翌12日、義貞公の奇襲により幕府方の長崎・加治軍は撃破され、南方の分倍河原まで退却しました。(久米川の戦い)
分倍河原の幕府軍に北条泰家(得宗北条高時公の弟)を大将とする援軍が加わり15万にもなったといい、幕府方の士気は上がりました。
5月15日、義貞公はこの援軍を知らずに1万の軍で急襲したところ、反撃を受けかろうじて北方の堀兼(所沢市堀兼)まで退却したといいます。(分倍河原の戦い)
しかし、三浦氏一族の大多和義勝、河村・土肥・渋谷・本間らの相模の軍勢8000騎が駆けつけ義貞公に加勢。
勢いをとりもどした義貞勢は5月16日分倍河原に押し出し、北条泰家以下幕府軍は敗走しました。
新田勢の勢いはとまらず、多摩川を渡り霞ノ関(多摩市関戸)で幕府軍に総攻撃をかけ、幕府方は新田勢の猛攻に耐えきれず総崩れとなって鎌倉に潰走しました。(関戸の戦い)
ここに常陸、下野、上総の豪族たちが続々と新田勢に合流、その勢いを駆って一気に鎌倉まで攻め上がりました。
対する幕府方は各切通しと市街要所に軍勢をおき、鎌倉の防備を固めました。
義貞公は軍勢を三手に分け、義貞本隊が金沢貞将守る化粧坂、大舘宗氏・江田行義が大仏貞直守る極楽寺坂、堀口貞満・大島守之が北条守時守る巨福呂坂を攻撃することとしました。
5月18日、新田勢は三方から鎌倉に攻め入りましたが、守りに強い鎌倉ゆえ三方とも攻略はならず、極楽寺坂口の大舘宗氏は討ち死にしました。
義貞公は化粧坂攻撃の指揮を脇屋義助に託し、大舘宗氏を失った極楽寺坂の援軍に向かいました。
5月20日夜半、義貞公は極楽寺坂の海側にあたる稲村ヶ崎へ駆け付けました。
稲村ヶ崎は海が迫る難所ですが、ここを突破されると一気に鎌倉市街まで侵入されます。
稲村ヶ崎進撃を予想していた幕府方は、稲村ヶ崎の断崖下に逆茂木をたて、海には軍船を浮かべて義貞勢の来襲に備えていました。
5月21未明、義貞公率いる軍勢は潮が沖に引いた隙を狙って、稲村ヶ崎の突破に見事成功しました。
この稲村ヶ崎の突破は『太平記』をはじめとする物語や絵画などによって広く知られています。
稲村ヶ崎突破については、干潮を利用したという説が有力ですが、『太平記』では義貞公が黄金作りの太刀を海に投じたところ、龍神が呼応して潮を引かせたというドラマティックな展開が描かれています。
ともあれ難所・稲村ヶ崎を突破した新田勢は由比ヶ浜で幕府軍を撃破し、一気に鎌倉市内に攻め入りました。
このとき新田勢が本陣をおいたのが、現在の九品寺の場所ともいいます。
5月22日、小町葛西谷の北条一族菩提寺・東勝寺で、長崎思元、大仏貞直、金沢貞将らの奮戦むなしく、北条得宗家当主・北条高時公らは自害し鎌倉幕府はここに滅亡しました。(東勝寺合戦)
義貞公の生品明神挙兵からわずか半月という怒濤の進撃でした。
鎌倉を陥落させた義貞公は雪ノ下の勝長寿院に本陣を敷き、足利千寿王は二階堂永福寺に布陣しました。
元弘三年/正慶二年(1333年)、後醍醐帝は隠岐から脱出、伯耆船上山で挙兵されました。帝追討のため幕府から派遣された尊氏公は上洛の途中幕府謀反を決意、船上山の後醍醐帝より討幕の密勅を受け取り、すぐさま六波羅探題を攻めて京を制圧しました。
尊氏公はこの密勅を根拠に、諸国の武将に向けて軍勢催促状を発しました。
新田勢に実子の千寿王を加勢させたことといい、将来への布石を着々と置いていることがわかります。
幕府滅亡後、後醍醐帝は建武の新政を開始
尊氏公は後醍醐帝から「勲功第一」と賞され鎮守府将軍となり、8月5日には従三位に昇叙、武蔵守を兼ねて尊氏と改名しています。
この時点で、後醍醐帝が鎌倉陥落の功労者、義貞公よりも尊氏公を優遇していたことがわかります。
義貞公に付き従っていた武将達は論功行賞のためつぎつぎと上洛し、鎌倉に残った武将たちも尊氏公の子千寿王のもとに集ったといいます。
そのなかで義貞公は千寿王補佐役の細川三兄弟(和氏、頼春、師氏)と諍いを起こし、6月に鎌倉を去って上洛したといい、以降の鎌倉は足利氏が統治したともいいます。
8月5日、義貞公は従四位上に叙され、左馬助に任ぜらて上野守、越後守となり、武者所の長である頭人となりました。
弟の脇屋義助は駿河守、長男の義顕も越後守に任ぜられ、尊氏公には及ばないものの恩賞を手にしました。
後醍醐帝の建武政権では尊氏公と護良親王の争いが起こり、護良親王は失脚しました。
この頃新田一族の昇進が目立ちますが、これは尊氏公の台頭を牽制するために、後醍醐帝が義貞公を対抗馬として取り立てたという見方があります。
建武二年(1335年)7月、信濃国で北条高時公の遺児・時行公を擁立し鎌倉を占領する事件(中先代の乱)が起こりました。
尊氏公は勅許を得ずに鎌倉に下り乱を鎮圧すると、新田一族の所領を他氏に分与し「義貞と公家達が自分を讒訴している」と主張して鎌倉に居座り、10月には細川和氏を使者に立てて後醍醐帝に義貞誅伐の奏状を提出しました。
おそらく、後醍醐帝が自身の対抗馬として義貞公を取り立てた時点で、義貞公と袂を分かったものとみられます。
これに対して義貞公はすぐさま反論の奏状を提出し、尊氏・直義兄弟の誅伐許可を求めたといいます。
義貞奏状で訴えられた足利直義による護良親王殺害が改めて問題となり、11月8日帝は義貞公に尊氏・直義追討の宣旨を発しました。
義貞公は政争に拙いという見方がありますが、このあたりの迅速な対応と要所を衝いた指摘は優れた政治力を感じさせます。
---------------------------------
ここからの義貞公の事跡戦歴は変転をきわめるので、略しつついきます。
官軍(足利討伐軍)の大将となった義貞公は尊良親王を奉じ、大軍を率いて東海道・東山道の二手から鎌倉に進軍、奥州の北畠顕家公も鎌倉へと進軍を開始しました。
官軍は三河国矢作、箱根・竹下で足利勢と戦い軍を進めましたが、鎌倉の手前で尊氏公指揮する足利勢に敗れて西へと逃れ京に戻りました。
尊氏公は躁鬱の気があったとされ、鬱のときはまったく弱気になるものの、躁に転じたときは俄然覇気にあふれて、これに従わない武将はなかったといいます。
今回の鎌倉防衛でも尊氏公が躁をあらわし、一気に劣勢を覆したと伝えます。
その後京に攻め上った足利勢は淀川で官軍を破り、後醍醐帝は西に遷幸、義貞公もこれに供奉しました。
京は尊氏勢に一旦占拠されたものの、奥州から北畠顕家軍、鎌倉から尊良親王軍が京に迫ると形勢は逆転。
義貞公は北畠軍、楠木正成、名和長年、千種忠顕らとともに京に総攻撃を仕掛け、尊氏公を九州へと追い落としました。
建武三年(1336年)2月、義貞公は足利勢を破った功績により正四位下に昇叙。左近衛中将に遷任し播磨守を兼任しました。
しかし義貞勢が尊氏方の播磨の赤松則村(円心)を攻めあぐねているうちに、尊氏勢は九州で勢力を盛り返し、再び東に攻め上ってきました。
尊氏公は、光厳院から得た義貞討伐の院宣をかざしていたともいいます。
5月25日、楠木正成と合流した義貞勢は摂津国湊川で尊氏勢と激突しました。(湊川の戦い)
尊氏勢の猛攻に新田、楠木両軍は分断され、楠木正成は奮戦むなしく湊川で自害しました。
義貞公も奮闘しましたが次第に劣勢となり、近江東坂本まで引きました。
6月14日尊氏公は光厳院を奉じて京に入り、光厳院の院宣を仰いで光明帝を即位させました。
比叡山から吉野に入られた後醍醐帝は自らの退位を否認され、光明帝の即位も認めなかったため、京(北朝)と吉野(南朝)に二帝並立する南北朝体制となりました。
諸戦で多くの配下を失い、楠木正成はすでに亡く、名和長年、千種忠顕らの友将も戦死して、もはや義貞公に以前の勢いはありませんでした。
加えて後醍醐帝と尊氏公で和平交渉が進み、義貞公は後醍醐帝の後ろ盾も失うこととなりました。
和平交渉を知り比叡山に駆け上がった義貞公が、涙ながらに後醍醐帝の変心を責める場面は、多くの物語で語られています。
義貞公は妥協策として恒良親王、尊良親王を推戴のうえ北国への下向を望むと、後醍醐帝はこれを許したといいます。
10月13日、義貞公は両親王を奉戴して越前敦賀の金ヶ崎城に入りました。
両親王は各地の武士へ尊氏討伐の綸旨を送り兵を募ったものの応じる武将は少なく、まもなく足利軍の攻撃を受けました。
義貞勢は奮戦し一度は足利軍を迎撃したものの、建武四年(1337年)1月足利軍の総攻撃を受けて籠城戦となり、兵糧尽きて3月6日ついに金ヶ崎城は陥落しました。
落城にあたり義貞公は越前・杣山城に遁れたとされますが、この時点で義貞公はすでに杣山城に移っていたという説もあります。
8月になると奥州の北畠顕家公が義良親王を奉じて鎌倉攻略の途につき、義貞公の次男新田義興公と、南朝に帰参した北条時行公が合流して12月には鎌倉を落としました。
---------------------------------
九品寺は、建武四年(1337年)に義貞公が北条方の戦死者の霊を慰めるため京より招いた風航順西和尚を開山として創建と伝わります。
しかし、この年義貞公は越前の金ヶ崎城ないし杣山城で足利勢を相手に戦闘・雌伏中で、とても「北条方の戦死者の霊を慰めるため鎌倉に寺院を建立」できる状況ではなかったように思われます。
もし北条氏菩提の目的で寺院を建立するとしたら、元弘三年(1333年)5月22日の北条氏滅亡後が考えられますが、義貞公は同年6月に上洛して以降、戦つづきでそのような余裕はないようにも思えます。
そもそも義貞公はほとんど鎌倉に腰を落ち着けたことはなく、「京より風航順西を招いて開山とし、寺院を創建する」という時間的余裕はないように思われます。
それに元弘三年(1333年)時点では義貞公はまだ上洛も果たしておらず、京・東山の風航順西和尚に知己を得て帰依とは考えにくいです。
などと考えつつ開山の風航順西(暦応四年(1341年)寂)をWeb検索したら、思いがけない記事がヒットしました。(→ 「鎌倉シニア通信」様「九品寺の縁起」)
無断転載不可につき、要旨のみ引用させていただきます。
-------------------(引用はじめ)
建武三年(1337年)に至り新田家戦死の霊魂を吊らはしか為、京都東山に「風航順西和尚」という浄家の僧、義貞公帰依により命じて共に下向し霊魂の得脱回向を懇望し則ちこの地に一宇を創建あり、内裏山霊嶽院九品寺と号す。
千時延文三丙申歳三月 為後代記置之
当寺三世 順妙
-------------------(引用おわり)
ここには当山創建は、(北条一族ではなく)新田家戦死者菩提の為とあります。
そうなると、義貞公が京・東山で浄土宗の風航順西和尚に帰依し、戦で失った新田一族の武将の菩提を懇請したということになるのかもしれません。
『太平記』は、京を舞台に義貞公と勾当内侍(こうとうのないし)との恋物語を伝えます。
であれば、東山の僧に帰依して一族の菩提を依頼するくらいの余裕はあったやもしれません。
ただし上記の「(建武三年(1337年))共に(鎌倉に?)下向し この地に一宇を創建」という記述は、同年の義貞公の事跡と符合しません。
もしも金ヶ崎城の戦いに破れ、落魄の義貞公がいっとき越前杣山城を離れ、鎌倉に入って寺院(九品寺)を建立したとしたら、歴史の一大スクープになるかと思いますが、これを伝える史料類は他に見当たりません。
---------------------------------
建武五年(1338年)1月北畠軍は上洛の途につき、後醍醐帝も各地の南朝勢力に対し顕家公への加勢を促しました。
越前鯖江(もしくは美濃大垣)まできた北畠勢は、しかし杣山城の義貞勢と合流することなく伊勢から奈良へと向かいました。
このとき北畠勢と義貞勢が合流しなかった理由については諸説ありますが、以前から北畠勢と義貞勢の連携はうまくいっていたとはいえず、顕家公と義貞公の間になんらかの確執があったのかもしれません。
その後の北畠勢は苦戦つづきで、5月22日和泉堺浦・石津で足利軍に敗北し顕家公は戦死しました。
建武五年(1338年)閏7月、義貞公は越前国藤島(福井市)の灯明寺畏畷で斯波高経が送った細川出羽守、鹿草公相の軍勢と交戦中に戦死しました。
享年38と伝わります。
義貞公は南朝復権のため再度の上洛を企図して藤島の戦いに臨んだといい、『太平記』には義貞公の凄絶な戦いぶりが描かれています。
義貞公の死は南朝方に大きな痛手となりましたが、年月日不明ながら義貞公は南朝側から正二位を贈位され、大納言の贈官を受けたという記録が残ります。
義貞公の墓所は「牛久沼ドットコム」様によると、当初称念寺(福井県坂井市)にあり、文明年間(1469-1486年)、義貞公の三男・新田義宗の子とされる横瀬貞氏(上州太田金山城主・岩松家純の重臣)が、義貞公の遺骨を称念寺から城内に移して墓を建てました。
この「城内の墓」は金山山麓の金龍寺(金山城主横瀬氏の菩提寺)ともみられ、金龍寺には義貞公の供養塔があります。
戦国中期、横瀬氏6代目の横瀬泰繁の代に横瀬氏は由良氏と名乗り、泰繁の子由良成繁は小田原北条軍に金山城を攻められ降服、嫡男国繁は小田原城に人質となり、由良一族は金山城を明け渡して桐生城へ移り、金龍寺も桐生へと移りました。
天正十八年(1590年)秀吉軍が小田原城を攻撃したとき、由良成繁の未亡人・赤井氏(妙尼印)は城主のごとく活躍したといいます。
北条氏滅亡後、秀吉は妙尼印の器量を称えて赤井氏に常陸国牛久の地と牛久城を与え、妙尼印は領地を子の国繁に相伝、前城主の菩提寺・東林寺に桐生の金龍寺を移して号を改めたといいます。
国繁没後、理由は不明ですが領地は没収となりますが、牛久の金龍寺と義貞公の墓は、幕府の庇護を受けて、寛文六年(1666年)牛久沼の対岸、龍ケ崎若柴の古寺を改修してここに移されたといい、以降、義貞公の墓所は龍ケ崎若柴の金龍寺とされているようです。


【写真 上(左)】 太田金山金龍寺の御朱印
【写真 下(右)】 龍ケ崎若柴金龍寺の御朱印
↑に「幕府の庇護を受けて」とありますが、この根拠とみられるのは神君・徳川家康公の出自です。
家康公は、新田氏の祖・新田義重公の四男得川義季(世良田義季)の末裔を称しました。
(→ 太田市観光物産協会Web)
足利氏の室町幕府で、草創時に敵対した新田一族は冷遇されました。
しかし、家康公が新田一門を公称したことからも、源氏名流たる新田氏の譽れは戦国末期に至ってなお健在だったとみられます。
征夷大将軍の座は源氏の統領のみに許されるという慣例に則り、源姓新田氏流の統領・家康公は征夷大将軍の座につき徳川幕府を開きました。
征夷大将軍の座は、公的には足利氏から新田氏(徳川氏)に移ったことになります。
徳川将軍家は新田氏(得川氏/世良田氏)ゆかりの上州世良田の地に東照宮を勧請して別格扱いとし、租税を軽くするなど住民までも優遇したと伝わります。
---------------------------------
義貞公の死から500年以上のちの明治の世に、義貞公は朝廷に尽しつづけた「忠臣」として顕彰され、明治15年には正一位を贈位されています。
数々の書物で義貞公の義勇忠節ぶりが描かれ、義貞公の「忠臣」としての評価は定まりました。
明治6年発行の国立銀行紙幣二円券の表面には、稲村ヶ崎で太刀を海中に投じる義貞公の姿が描かれています。
九品寺の義貞公ゆかりの事物として、山門の「内裏山」、本堂の「九品寺」の扁額の文字は、義貞公の揮毫を写したものと伝わります。
当山の御本尊は阿弥陀三尊。
寺号の「九品」とは九パターンの極楽往生のあり様をいい、上品、中品、下品それぞれに上生、中生、下生があり、合わせて九品(九軆)の阿弥陀仏がおわし、救われないものはないといいます。
義貞公が人々の菩提を祈り創ったとされる九品寺。
衆生を極楽往生に導く九品(阿弥陀仏)の寺号は、ふさわしいものといえましょうか。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(亂橋村)九品寺
内裏山靈嶽院と号す、浄土宗 材木座村、光明寺末、三尊の彌陀を本尊とす、中興を卓辨と云へり
■ 山内掲示(鎌倉市)
九品(くほん)とは、九種類の往生のありさまのことをいいます。極楽往生を願う人々の生前の行いによって定められます。上品、中品、下品のそれぞれに、上生、中生、下生があり、合わせて九品とされます。
鎌倉攻めの総大将であった新田義貞が、鎌倉幕府滅亡後に敵方であった北条氏の戦死者を供養するために、材木座に建立しました。
山門の「内裏山」、本堂の「九品寺」の文字は、新田義貞の筆を写したものといわれます。
本尊は阿弥陀三尊です。
■ 『鎌倉市史 社寺編』(鎌倉市)(抜粋)
内裏山靈嶽院九品寺と号する。浄土宗、もと光明寺末、新田義貞の草創で、風航順西を開山と伝える。中興開山は二十一世鏡誉岌故、二十五世台誉卓弁、三十二世楽誉浄阿良澄の三人。
本尊、阿弥陀三尊。
境内地311.95坪。本堂・庫裏・山門あり。
神奈川県重要文化財、石造薬師如来坐像。
寺の『過去帳』によれば、風航順西は暦応四年(1341年)十月十八日に寂している。
岌故は慶安二年(1649年)二月十五日、本尊の御身を再興した。願主は戸塚の吉田四良兵衛とみえている。良澄は弘化二年(1846年)二月、本堂及び三尊像を再興した。(略)
関東大震災にて全潰した。
-------------------------
小町大路に面してあり、光明寺とならんで材木座海岸にもっとも近い寺院です。
鎌倉のメイン通り、若宮大路の材木座口にもほど近く、稲村ヶ崎から侵入し由比ヶ浜で北条勢を破った義貞公が一旦軍勢を落ち着かせ、本陣をおいたという縁起にふさわしい立地です。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 お地蔵さまと寺号標
小町大路に面して参道入口。
手前に地蔵尊立像をおいた寺号標。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
正面は脇塀付き切妻屋根桟瓦葺四脚の山門。
向拝見上げに掲げられている山号扁額は、義貞公の揮毫を移したものと伝わります。


【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場札所標
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場札所標
山門手前に鎌倉三十三観音霊場と相州二十一ヶ所霊場の札所標が置かれています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 六地蔵と不動尊
緑ゆたかな山内で、参道沿いには古色を帯びた一体型の六地蔵と不動尊立像が御座します。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 扁額と龍の彫刻
参道正面が本堂。
本堂は入母屋造銅本棒葺流れ向拝。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。
御本尊の阿弥陀如来立像は、玉眼を填め込んだ宗元風彫刻として鎌倉市の文化財に指定されています。
本堂のほかに堂宇は見当たらないので、鎌倉三十三観音霊場札所本尊・聖観世音菩薩像、相州二十一ヶ所霊場札所本尊・弘法大師尊像、鎌倉時代作とされ県指定重要文化財の石造薬師如来像はいずれも本堂内に奉安とみられます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 天水鉢
向拝見上げに掲げられている寺号扁額は、義貞公の揮毫を移したものと伝わります。
堂前の天水鉢にはしっかり新田氏の家紋、「新田一つ引き紋」が描かれていました。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
御本尊、鎌倉三十三観音霊場、相州二十一ヶ所霊場の御朱印を授与されています。
〔 九品寺の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御本尊・阿弥陀如来の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

相州二十一ヶ所霊場の御朱印
46.海潮山 妙長寺(みょうちょうじ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市材木座2-7-41
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
司元別当:
札所:
妙長寺は、材木座にある日蓮聖人・伊豆法難ゆかりの日蓮宗寺院です。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料、山内縁起碑等から縁起沿革を追ってみます。
妙長寺は、正安元年(1299年)に、伊豆で日蓮聖人の命を救った漁師の子、日実(日實)上人が開山したのがはじまりといわれています。
もともとは由比ヶ浜の字沼ヶ浦というところにあり、延享(1744-1748年)以後に現在地に移転とみられています。
日蓮宗神奈川県第二部布教センターのWebには「妙長寺 日蓮聖人伊豆流罪の際(伊豆法難)、日蓮聖人の命を救った漁師「舟守弥三郎」の子「日実」が開山。伊豆流罪の霊跡の一。」とあります。
「Wikipedia」伊豆法難(いずほうなん)とは、弘長元年(1261年)5月12日に日蓮聖人が捕らえられ、伊豆へ流罪となった事件で「日蓮聖人四大法難」の一つです。
日蓮宗Web、久城寺(秋田県秋田市)の公式Web、および伊豆蓮慶寺の現地掲示等によると、日蓮聖人は文応元年(1260年)に世の中の乱れを嘆き『立正安国論』を執筆されましたが、幕府の反感を買って弘長元年(1261年)5月に伊豆流罪となりました。
日蓮聖人は由比ヶ浜の沼ヶ浦というところから伊豆に向けて船出したといいますが、当山の旧地は「由比ヶ濱沼ヶ浦」なので、船出の地のそばに開創とみられます。


【写真 上(左)】 日蓮崎と俎岩
【写真 下(右)】 俎岩
幕府の役人は船を伊東の湊に着けず、なんと烏崎(日蓮崎)の沖にある「俎岩(まないたいわ)」の上に置き去りにしました。
波浪に晒される岩上に置き去りにされた日蓮聖人は、しかしいささかも動じることなくお題目を唱えられていました。
そばで漁をしていた地元の漁師・舩守弥三郎はお題目をきくと、俎岩に船を漕ぎ寄せて日蓮聖人を救出、川奈港奥の御岩屋祖師堂にかくまったといいます。


【写真 上(左)】 連着寺・奥の院の奉納額
【写真 下(右)】 日蓮聖人「袈裟掛の松」
弥三郎夫妻の住居跡に伊東庄の代官今村若狭守が祖師堂(のちの蓮慶寺)を建て、蓮慶寺本堂には日蓮聖人とともに夫妻の像が祀られています。


【写真 上(左)】 連着寺の寺号標
【写真 下(右)】 連着寺


【写真 上(左)】 連着寺の本堂扁額
【写真 下(右)】 連着寺・奥の院

連着寺の御首題
日蓮聖人は伊豆で3年を過ごされ、伊東の佛現寺、佛光寺などゆかりの寺院を残された後、弘長三年(1263年)に赦免され、鎌倉に帰って伝道活動を再開されました。
弥三郎夫妻の子はのちに日蓮聖人の弟子(ないし孫弟子)となり、日実(日實)と号して日蓮聖人船出の地に妙長寺を開創したと伝わります。
天和元年(1681年)の大津波で堂宇が流されたため、第二十一世常徳院日慶上人が廃寺となっていた乱橋村畠中の天目山圓成寺の旧地に妙長寺を移したといいます。
山内縁起碑では移転の年を「同年(天和元年)」とし、『鎌倉市史 社寺編』では「延享三年(1746年)八月の『小鐘銘』には、相州鎌倉沼浦、海潮山妙長寺とあるから、延享(1744-1748年)以後の移転であろう。」としています。
山内縁起碑には天目山圓成寺は「寛文(1661-1673年)ノ頃 不受不施義ヲ唱ヘタルニヨリ廃絶セルカ」とあります。
徳川幕府が不受不施派を禁じ、他派への転派を命じたのは元禄四年(1691年)とされるので、山内縁起碑の圓成寺廃絶はそれより早く、禁令より早く廃されたのかもしれません。
(寛文九年(1669年)、幕府は不受不施派に対して寺請を禁じたという記録があるようです。)
『鎌倉市史 社寺編』の説をとれば、
天和元年(1681年) 大津波で堂宇流失
元禄四年(1691年)以降 天目山圓成寺廃絶
延享三年(1746年)以後 妙長寺、圓成寺跡地に移転
となり時系列は整います。
しかし、この説だと天和元年(1681年)の堂宇流失から延享三年(1746年)以後の移転まで、短くとも65年の空白が開きます。
ただ、山内縁起碑には「祖師堂ノミ難ヲ免レタリ」とあるので、その期間は祖師堂のみで寺を存続したのかもしれず、詳細はわかりません。
山内には「伊豆法難」ゆかりの伊豆法難記念相輪塔があります。
明治時代には小説家の泉鏡花が明治24年の夏に滞在し、このときの経験を題材にした「星あかり」という作品が残されています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(乱橋村)妙長寺
海潮山と号す 日蓮宗 比企谷妙本寺末
開山は日實と云ふ 元弘元年十月廿三日寂
本尊釋迦を安ず、小名沼浦に当寺の舊地あり、今も除地なりと云ふ、何の頃此に移りしにや
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
海潮山妙長寺と号する。日蓮宗。もと妙本寺末。
開山は日実と云える。
本尊、三宝祖師。
境内地308.7坪 本堂・庫裏・上行堂・門あり。
材木座小字沼浦から移ったという(『風土記稿』)。
延享三年(1746年)八月の『小鐘銘』には、相州鎌倉沼浦、海潮山妙長寺とあるから、延享(1744-1748年)以後の移転であろう。
■ 山内掲示(縁起、不明瞭箇所あり抜粋転記)
海潮山妙長寺縁起
当山ハモト由比ヶ濱沼ヶ浦ニ在リ 弘長元年(1261年)五月十二日宗祖日蓮大聖人伊豆ニ配流セラルヤ沼ヶ浦ヨリ乗船シ給フ ●子大國阿闍梨日朗上●ニ縋リテ随行ヲモヒシニ 幕吏櫂ヲ揮ツテ日朗上人ノ右臂ヲ打(?)ク 宗祖船上ヨリ●●護持ノ文ヲ唱ヘ給フ ●音海浪ニ遮ラレテ 長短●シカラス所 ●●●●●ココニ起ル 川奈ノ漁師舟守彌三郎 宗祖ヲ俎岩ニ救ヒ奉リ ●●奥に供養ノ●ヲ画シ 一子ヲ宗祖ニ●ス(不明)日實上人是レナリ 弘長三年(1263年)二月二十八日宗祖赦サレテ海路鎌倉ニ●リ●●沼ヶ浦ニ着船ス
宗祖入滅後第十八年正安元年(1299年)日實上人沼ヶ浦二一宇ヲ建立シ海潮山妙長寺ト号シ 父母(不明)発祥ノ地ニ拠リテ 梵音海潮音ノ妙●ヲ長ヘニ使ヘンカタ●ナリ 然ルニ天和元年(1681年)●●ニヨリ堂宇悉ク流失セシカ 但タ祖師堂ノミ難ヲ免レタリ ●ノ中棄マテ(不明)堂實成庵ト称セリ
堂宇流失ノ年第二十一世常徳院日慶上人(不明)ヒテ寺●ヲ亂橋村畠中天目山圓成寺ノ𦾔址ニ移ス 是レ現在ノ地ナリ
圓成寺ハ美濃阿闍梨天目上人ノ開創ニ係ル 寛文(1661-1673年)ノ頃 不受不施義ヲ唱ヘタルニヨリ廃絶セルカ 創建巳来星霜茲ニ六百七十年史實ノ漸ク(不明)トスルヲ●ヘ 本年開●六百五十年遠忌ニ際シ碑ヲ建テ 實ノ●シテ後ニ傳フト云爾
昭和四十四年五月十二日
海潮山四十二世慈徳(?)院日秀謹●
■ 山内掲示(鎌倉市、抜粋)
泉鏡花は明治24年に鎌倉に来て、この妙長寺に七・八月の二か月滞在した。
その後、十月に思い切って(尾崎)紅葉を訪ね、入門を許された。以後創作に励み、小説家として認められ、数々の名作を残した。
この妙長寺滞在の経験をもとにして、明治31年に小説「みだれ橋」を発表し、後に「星あかり」と改題した。
星あかり(山内説明板より)
もとより何故といふ理はないので、墓石の倒れたのを引摺寄せて、二ツばかり重ねて臺にした。其の上に乗って、雨戸の引合せの上の方を、ガタゝ動かして見たが、開きさうにもない。雨戸の中は、相州西鎌倉亂橋の妙長寺といふ、法華宗の寺の、本堂に隣つた八畳の、横に長い置床の附いた座敷で、向つて左手(ゆんで)に、葛籠、革鞄などを置いた際に、山科といふ醫學生が、四六の借蚊帳を釣つて寝て居るのである。
-------------------------
小町大路「水道橋」交差点から南に少し行った道沿いにあります。
小町大路から間口と奥行きのある参道を置き、入口には日蓮聖人の尊像が奉安されています。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 日蓮上人像


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
山門は脇塀付きの切妻屋根銅板葺の四脚門で、正面に本堂が見えます。
石敷きで開けたイメージの山内です。
浄行菩薩堂には丁寧な浄行菩薩の説明書があり、堂上部奥には大曼荼羅も掛けられていました。


【写真 上(左)】 浄行菩薩堂
【写真 下(右)】 本堂
本堂は寄棟造銅板で向拝柱はなく、向拝見上げに寺号扁額を掲げています。
明るくすっきりとしたきもちのよい向拝です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
山内には「日蓮上人伊豆法難記念」と刻まれた高さ約十メートルの相輪塔があります。
この相輪塔は昭和8年5月に建てられました。
中央の石柱は関東大震災のときくずれた鶴岡八幡宮の二の鳥居の一部を用い、寛文八年(1668年)8月の銘があるそうです。


【写真 上(左)】 縁起碑
【写真 下(右)】 相輪塔と鱗供養塔
他にも立派な寺号標(お題目碑)があり「鱗供養塔」もあります。
「鱗供養塔」は当山で執り行なわれる、材木座海岸沖の放生会にちなむものです。
御首題・御朱印は山内庫裏にて拝受しました。
御首題・御朱印とも、伊豆法難船出の地にかかる揮毫があります。
〔 妙長寺の御首題・御朱印 〕


【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 日蓮大菩薩の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-16 (B.名越口-11)へつづく。
【 BGM 】
■ Angel - Change
■ Hero - David Crosby & Phil Collins
■ Don't Call My Name - King of Hearts -
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)
■ 同-14 (B.名越口-9)から。
※字数制限の関係上、44.円龍山 向福寺の記事は後ほどUPします。
45.内裏山 霊獄院 九品寺(くほんじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座5-13-14
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:(乱橋材木座)三島明神
札所:鎌倉三十三観音霊場第16番、相州二十一ヶ所霊場第9番、小田急沿線花の寺四季めぐり第18番
九品寺は、新田義貞公開基と伝わる浄土宗の古刹です。
鎌倉市観光協会Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
元弘三年(1333年)新田義貞公の鎌倉攻めの際、本陣をかまえたという場所で、義貞公が京から招いた風航順西和尚を開山に、北条方の戦死者の霊を弔うため創建と伝わります。
創建年は建武三年/延元元年(1336年)と建武四年/延元二年(1337年)の2説あります。
こちら(「鎌倉史跡・寺社データベース」様)には、「もともとは別の場所にあり、かつて乱橋材木座にあった三島明神の別当であったが、荒廃し、後に現在地に移ったという。」とあり、草創が1336年、当地での開山が1337年かもしれません。
(ただし、わずか1年で「荒廃」は解せませんが。)
当山は鎌倉では数少ない新田義貞公ゆかりの寺院です。
義貞公は『太平記』前半の主役といってもいいほど登場回数が多いですが、『太平記』のみ記載の事跡も多く、史実が辿りにくい人物です。
Wikipediaなどから義貞公の略歴を追ってみます。
新田氏の開祖は、八幡太郎源義家公の三男(諸説あり)源義国公です。
義国公は下野国足利荘(栃木県足利市)を本拠とし、足利荘は次子・義康公が継いで足利氏を名乗り、異母兄の義重公は上野国八幡荘を継承し、新田荘を立荘して新田氏を称しました。
新田義貞公(1301-1338年)は、新田朝氏公(新田氏宗家7代当主)の嫡男として 正安三年(1301年)頃に生まれました。(里見氏からの養子説あり)
新田荘がある大間々扇状地は、ふるくは「笠懸野」(かさかけの)と呼ばれたとおり、広大な平地が広がり馬掛けに適した土地柄で、義貞公とその郎党はこの「笠懸野」で弓馬の術を磨きました。
新田氏は河内源氏の名族で鎌倉御家人でしたが、頼朝公の親族として優遇され北条氏とも婚姻関係にあった足利氏にくらべ、幕府内の地位や家格は高いものではありませんでした。
新田宗家4代当主政義公の妻は足利宗家3代当主義氏公の息女で、その子政氏公が新田家嫡流を継ぎ、以降足利氏は新田氏の代々の烏帽子親であったという説があります。
実際、義貞公の烏帽子親は足利氏嫡流で早世した足利高義公で、義貞の「義」は高義の「義」の偏諱とするとされ、鎌倉末期の両氏は対立関係にはなかったとみられています。
文保二年(1318年)、義貞公は新田氏宗家の家督を継承、8代当主となりました。
しかし、その頃の義貞公は無位無官だったとみられ、とくに北条得宗家との関係が悪く鎌倉幕府から冷遇されていたとも。
世良田氏や大舘氏など新田一門も、幕府内で高い地位を得たという記録はありません。
義貞公は得宗被官の安東聖秀の姪を妻として迎えたとされ、北条得宗家への接近もみられますが、鎌倉幕府内で重きをなすことはありませんでした。
一方、足利尊氏公は得宗・北条高時公の偏諱を受けて「高氏」を名乗り、わずか15歳にして官位は従五位下治部大輔でした。
Wikipediaには「15歳での叙爵は北条氏であれば得宗家・赤橋家に次ぎ、大仏家・金沢家と同格の待遇であり、北条氏以外の御家人に比べれば圧倒的に優遇されていた」とあり、幕府内で格別の地位にあったことがわかります。
元弘元年(1331年)8月、倒幕をめざす後醍醐帝と幕府・北条得宗家の間で、いわゆる「元弘の乱」が起こりました。
後醍醐帝は笠置山の戦いで幕府方の大軍に破れ逃亡しました。
幕府は帝が京から逃れるとただちに廃位し、光厳帝を即位させ、捕虜とした後醍醐帝を隠岐に流しました。
元弘二年(1332年)大番役として在京していた義貞公は、幕府の動員令に応じて他の御家人らと後醍醐帝方の楠木正成討伐に向かい 千早城の戦いに参加しています。
元弘三年(1333年)3月、義貞公は病気を理由に河内を退去し新田荘に帰参しました。
『太平記』には元弘の乱の出兵中、義貞公が護良親王と接触して北条氏打倒の綸旨を受けたとありますが、真偽について諸説あるようです。
義貞公の新田荘帰還後、幕府は軍資金として新田氏に膨大な額の納税(有徳銭)を命じ、徴税人(金沢出雲介親連と黒沼彦四郎)を差し向けました。
法外な金額と強引な徴税に憤激した義貞公は、金沢を幽閉し黒沼を斬殺しました。
これを咎めた幕府が新田討伐の軍勢を差し向けるという情報が入り、同年5月、ついに義貞公は倒幕の兵を挙げました。
生品明神社(生品神社)での義貞公決起の名場面は、『太平記』でよく知られています。
この時点の新田軍主力は、義貞公に弟の脇屋義助、大舘宗氏とその一族、堀口貞満、江田行義、岩松経家、里見義胤、桃井尚義などとみられています。

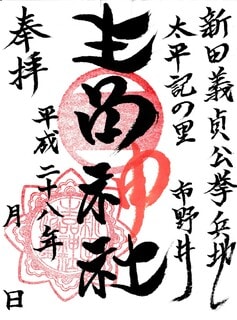
【写真 上(左)】 生品明神社(生品神社)
【写真 下(右)】 生品明神社(生品神社)の御朱印
新田勢は新田を発して上野国八幡荘に入り、越後勢、甲斐源氏、信濃源氏の一派と合流して9,000余の軍勢に膨れ上がったといいます。
5月9日、新田勢は武蔵国に向けて出撃、足利尊氏公(1305-1358年、当初は「高氏」ですが「尊氏」で統一します)の嫡男・千寿王(後の足利義詮公)と久米川付近で合流しました。
これを受けてさらに兵士が集まり、『太平記』では20万7,000騎と記しています。
千寿王の参陣は政治的に大きく、鎌倉攻めの軍勢には義貞公と千寿王の二人の大将がいたとする説があり、千寿王挙兵に義貞公が参陣という説さえあります。
義貞公挙兵の報を受けた幕府方は、桜田貞国を総大将、長崎高重、長崎孫四郎左衛門、加治二郎左衛門を副将とする幕府軍約5万で入間川へと向かい、別働隊として金沢貞将を大将とする上総・下総勢2万が下総の下河辺郷に集結しました。
新田勢は鎌倉街道を南下し、5月11日に小手指原(所沢市小手指)で幕府軍と衝突しました。(小手指原の戦い)
翌12日、義貞公の奇襲により幕府方の長崎・加治軍は撃破され、南方の分倍河原まで退却しました。(久米川の戦い)
分倍河原の幕府軍に北条泰家(得宗北条高時公の弟)を大将とする援軍が加わり15万にもなったといい、幕府方の士気は上がりました。
5月15日、義貞公はこの援軍を知らずに1万の軍で急襲したところ、反撃を受けかろうじて北方の堀兼(所沢市堀兼)まで退却したといいます。(分倍河原の戦い)
しかし、三浦氏一族の大多和義勝、河村・土肥・渋谷・本間らの相模の軍勢8000騎が駆けつけ義貞公に加勢。
勢いをとりもどした義貞勢は5月16日分倍河原に押し出し、北条泰家以下幕府軍は敗走しました。
新田勢の勢いはとまらず、多摩川を渡り霞ノ関(多摩市関戸)で幕府軍に総攻撃をかけ、幕府方は新田勢の猛攻に耐えきれず総崩れとなって鎌倉に潰走しました。(関戸の戦い)
ここに常陸、下野、上総の豪族たちが続々と新田勢に合流、その勢いを駆って一気に鎌倉まで攻め上がりました。
対する幕府方は各切通しと市街要所に軍勢をおき、鎌倉の防備を固めました。
義貞公は軍勢を三手に分け、義貞本隊が金沢貞将守る化粧坂、大舘宗氏・江田行義が大仏貞直守る極楽寺坂、堀口貞満・大島守之が北条守時守る巨福呂坂を攻撃することとしました。
5月18日、新田勢は三方から鎌倉に攻め入りましたが、守りに強い鎌倉ゆえ三方とも攻略はならず、極楽寺坂口の大舘宗氏は討ち死にしました。
義貞公は化粧坂攻撃の指揮を脇屋義助に託し、大舘宗氏を失った極楽寺坂の援軍に向かいました。
5月20日夜半、義貞公は極楽寺坂の海側にあたる稲村ヶ崎へ駆け付けました。
稲村ヶ崎は海が迫る難所ですが、ここを突破されると一気に鎌倉市街まで侵入されます。
稲村ヶ崎進撃を予想していた幕府方は、稲村ヶ崎の断崖下に逆茂木をたて、海には軍船を浮かべて義貞勢の来襲に備えていました。
5月21未明、義貞公率いる軍勢は潮が沖に引いた隙を狙って、稲村ヶ崎の突破に見事成功しました。
この稲村ヶ崎の突破は『太平記』をはじめとする物語や絵画などによって広く知られています。
稲村ヶ崎突破については、干潮を利用したという説が有力ですが、『太平記』では義貞公が黄金作りの太刀を海に投じたところ、龍神が呼応して潮を引かせたというドラマティックな展開が描かれています。
ともあれ難所・稲村ヶ崎を突破した新田勢は由比ヶ浜で幕府軍を撃破し、一気に鎌倉市内に攻め入りました。
このとき新田勢が本陣をおいたのが、現在の九品寺の場所ともいいます。
5月22日、小町葛西谷の北条一族菩提寺・東勝寺で、長崎思元、大仏貞直、金沢貞将らの奮戦むなしく、北条得宗家当主・北条高時公らは自害し鎌倉幕府はここに滅亡しました。(東勝寺合戦)
義貞公の生品明神挙兵からわずか半月という怒濤の進撃でした。
鎌倉を陥落させた義貞公は雪ノ下の勝長寿院に本陣を敷き、足利千寿王は二階堂永福寺に布陣しました。
元弘三年/正慶二年(1333年)、後醍醐帝は隠岐から脱出、伯耆船上山で挙兵されました。帝追討のため幕府から派遣された尊氏公は上洛の途中幕府謀反を決意、船上山の後醍醐帝より討幕の密勅を受け取り、すぐさま六波羅探題を攻めて京を制圧しました。
尊氏公はこの密勅を根拠に、諸国の武将に向けて軍勢催促状を発しました。
新田勢に実子の千寿王を加勢させたことといい、将来への布石を着々と置いていることがわかります。
幕府滅亡後、後醍醐帝は建武の新政を開始
尊氏公は後醍醐帝から「勲功第一」と賞され鎮守府将軍となり、8月5日には従三位に昇叙、武蔵守を兼ねて尊氏と改名しています。
この時点で、後醍醐帝が鎌倉陥落の功労者、義貞公よりも尊氏公を優遇していたことがわかります。
義貞公に付き従っていた武将達は論功行賞のためつぎつぎと上洛し、鎌倉に残った武将たちも尊氏公の子千寿王のもとに集ったといいます。
そのなかで義貞公は千寿王補佐役の細川三兄弟(和氏、頼春、師氏)と諍いを起こし、6月に鎌倉を去って上洛したといい、以降の鎌倉は足利氏が統治したともいいます。
8月5日、義貞公は従四位上に叙され、左馬助に任ぜらて上野守、越後守となり、武者所の長である頭人となりました。
弟の脇屋義助は駿河守、長男の義顕も越後守に任ぜられ、尊氏公には及ばないものの恩賞を手にしました。
後醍醐帝の建武政権では尊氏公と護良親王の争いが起こり、護良親王は失脚しました。
この頃新田一族の昇進が目立ちますが、これは尊氏公の台頭を牽制するために、後醍醐帝が義貞公を対抗馬として取り立てたという見方があります。
建武二年(1335年)7月、信濃国で北条高時公の遺児・時行公を擁立し鎌倉を占領する事件(中先代の乱)が起こりました。
尊氏公は勅許を得ずに鎌倉に下り乱を鎮圧すると、新田一族の所領を他氏に分与し「義貞と公家達が自分を讒訴している」と主張して鎌倉に居座り、10月には細川和氏を使者に立てて後醍醐帝に義貞誅伐の奏状を提出しました。
おそらく、後醍醐帝が自身の対抗馬として義貞公を取り立てた時点で、義貞公と袂を分かったものとみられます。
これに対して義貞公はすぐさま反論の奏状を提出し、尊氏・直義兄弟の誅伐許可を求めたといいます。
義貞奏状で訴えられた足利直義による護良親王殺害が改めて問題となり、11月8日帝は義貞公に尊氏・直義追討の宣旨を発しました。
義貞公は政争に拙いという見方がありますが、このあたりの迅速な対応と要所を衝いた指摘は優れた政治力を感じさせます。
---------------------------------
ここからの義貞公の事跡戦歴は変転をきわめるので、略しつついきます。
官軍(足利討伐軍)の大将となった義貞公は尊良親王を奉じ、大軍を率いて東海道・東山道の二手から鎌倉に進軍、奥州の北畠顕家公も鎌倉へと進軍を開始しました。
官軍は三河国矢作、箱根・竹下で足利勢と戦い軍を進めましたが、鎌倉の手前で尊氏公指揮する足利勢に敗れて西へと逃れ京に戻りました。
尊氏公は躁鬱の気があったとされ、鬱のときはまったく弱気になるものの、躁に転じたときは俄然覇気にあふれて、これに従わない武将はなかったといいます。
今回の鎌倉防衛でも尊氏公が躁をあらわし、一気に劣勢を覆したと伝えます。
その後京に攻め上った足利勢は淀川で官軍を破り、後醍醐帝は西に遷幸、義貞公もこれに供奉しました。
京は尊氏勢に一旦占拠されたものの、奥州から北畠顕家軍、鎌倉から尊良親王軍が京に迫ると形勢は逆転。
義貞公は北畠軍、楠木正成、名和長年、千種忠顕らとともに京に総攻撃を仕掛け、尊氏公を九州へと追い落としました。
建武三年(1336年)2月、義貞公は足利勢を破った功績により正四位下に昇叙。左近衛中将に遷任し播磨守を兼任しました。
しかし義貞勢が尊氏方の播磨の赤松則村(円心)を攻めあぐねているうちに、尊氏勢は九州で勢力を盛り返し、再び東に攻め上ってきました。
尊氏公は、光厳院から得た義貞討伐の院宣をかざしていたともいいます。
5月25日、楠木正成と合流した義貞勢は摂津国湊川で尊氏勢と激突しました。(湊川の戦い)
尊氏勢の猛攻に新田、楠木両軍は分断され、楠木正成は奮戦むなしく湊川で自害しました。
義貞公も奮闘しましたが次第に劣勢となり、近江東坂本まで引きました。
6月14日尊氏公は光厳院を奉じて京に入り、光厳院の院宣を仰いで光明帝を即位させました。
比叡山から吉野に入られた後醍醐帝は自らの退位を否認され、光明帝の即位も認めなかったため、京(北朝)と吉野(南朝)に二帝並立する南北朝体制となりました。
諸戦で多くの配下を失い、楠木正成はすでに亡く、名和長年、千種忠顕らの友将も戦死して、もはや義貞公に以前の勢いはありませんでした。
加えて後醍醐帝と尊氏公で和平交渉が進み、義貞公は後醍醐帝の後ろ盾も失うこととなりました。
和平交渉を知り比叡山に駆け上がった義貞公が、涙ながらに後醍醐帝の変心を責める場面は、多くの物語で語られています。
義貞公は妥協策として恒良親王、尊良親王を推戴のうえ北国への下向を望むと、後醍醐帝はこれを許したといいます。
10月13日、義貞公は両親王を奉戴して越前敦賀の金ヶ崎城に入りました。
両親王は各地の武士へ尊氏討伐の綸旨を送り兵を募ったものの応じる武将は少なく、まもなく足利軍の攻撃を受けました。
義貞勢は奮戦し一度は足利軍を迎撃したものの、建武四年(1337年)1月足利軍の総攻撃を受けて籠城戦となり、兵糧尽きて3月6日ついに金ヶ崎城は陥落しました。
落城にあたり義貞公は越前・杣山城に遁れたとされますが、この時点で義貞公はすでに杣山城に移っていたという説もあります。
8月になると奥州の北畠顕家公が義良親王を奉じて鎌倉攻略の途につき、義貞公の次男新田義興公と、南朝に帰参した北条時行公が合流して12月には鎌倉を落としました。
---------------------------------
九品寺は、建武四年(1337年)に義貞公が北条方の戦死者の霊を慰めるため京より招いた風航順西和尚を開山として創建と伝わります。
しかし、この年義貞公は越前の金ヶ崎城ないし杣山城で足利勢を相手に戦闘・雌伏中で、とても「北条方の戦死者の霊を慰めるため鎌倉に寺院を建立」できる状況ではなかったように思われます。
もし北条氏菩提の目的で寺院を建立するとしたら、元弘三年(1333年)5月22日の北条氏滅亡後が考えられますが、義貞公は同年6月に上洛して以降、戦つづきでそのような余裕はないようにも思えます。
そもそも義貞公はほとんど鎌倉に腰を落ち着けたことはなく、「京より風航順西を招いて開山とし、寺院を創建する」という時間的余裕はないように思われます。
それに元弘三年(1333年)時点では義貞公はまだ上洛も果たしておらず、京・東山の風航順西和尚に知己を得て帰依とは考えにくいです。
などと考えつつ開山の風航順西(暦応四年(1341年)寂)をWeb検索したら、思いがけない記事がヒットしました。(→ 「鎌倉シニア通信」様「九品寺の縁起」)
無断転載不可につき、要旨のみ引用させていただきます。
-------------------(引用はじめ)
建武三年(1337年)に至り新田家戦死の霊魂を吊らはしか為、京都東山に「風航順西和尚」という浄家の僧、義貞公帰依により命じて共に下向し霊魂の得脱回向を懇望し則ちこの地に一宇を創建あり、内裏山霊嶽院九品寺と号す。
千時延文三丙申歳三月 為後代記置之
当寺三世 順妙
-------------------(引用おわり)
ここには当山創建は、(北条一族ではなく)新田家戦死者菩提の為とあります。
そうなると、義貞公が京・東山で浄土宗の風航順西和尚に帰依し、戦で失った新田一族の武将の菩提を懇請したということになるのかもしれません。
『太平記』は、京を舞台に義貞公と勾当内侍(こうとうのないし)との恋物語を伝えます。
であれば、東山の僧に帰依して一族の菩提を依頼するくらいの余裕はあったやもしれません。
ただし上記の「(建武三年(1337年))共に(鎌倉に?)下向し この地に一宇を創建」という記述は、同年の義貞公の事跡と符合しません。
もしも金ヶ崎城の戦いに破れ、落魄の義貞公がいっとき越前杣山城を離れ、鎌倉に入って寺院(九品寺)を建立したとしたら、歴史の一大スクープになるかと思いますが、これを伝える史料類は他に見当たりません。
---------------------------------
建武五年(1338年)1月北畠軍は上洛の途につき、後醍醐帝も各地の南朝勢力に対し顕家公への加勢を促しました。
越前鯖江(もしくは美濃大垣)まできた北畠勢は、しかし杣山城の義貞勢と合流することなく伊勢から奈良へと向かいました。
このとき北畠勢と義貞勢が合流しなかった理由については諸説ありますが、以前から北畠勢と義貞勢の連携はうまくいっていたとはいえず、顕家公と義貞公の間になんらかの確執があったのかもしれません。
その後の北畠勢は苦戦つづきで、5月22日和泉堺浦・石津で足利軍に敗北し顕家公は戦死しました。
建武五年(1338年)閏7月、義貞公は越前国藤島(福井市)の灯明寺畏畷で斯波高経が送った細川出羽守、鹿草公相の軍勢と交戦中に戦死しました。
享年38と伝わります。
義貞公は南朝復権のため再度の上洛を企図して藤島の戦いに臨んだといい、『太平記』には義貞公の凄絶な戦いぶりが描かれています。
義貞公の死は南朝方に大きな痛手となりましたが、年月日不明ながら義貞公は南朝側から正二位を贈位され、大納言の贈官を受けたという記録が残ります。
義貞公の墓所は「牛久沼ドットコム」様によると、当初称念寺(福井県坂井市)にあり、文明年間(1469-1486年)、義貞公の三男・新田義宗の子とされる横瀬貞氏(上州太田金山城主・岩松家純の重臣)が、義貞公の遺骨を称念寺から城内に移して墓を建てました。
この「城内の墓」は金山山麓の金龍寺(金山城主横瀬氏の菩提寺)ともみられ、金龍寺には義貞公の供養塔があります。
戦国中期、横瀬氏6代目の横瀬泰繁の代に横瀬氏は由良氏と名乗り、泰繁の子由良成繁は小田原北条軍に金山城を攻められ降服、嫡男国繁は小田原城に人質となり、由良一族は金山城を明け渡して桐生城へ移り、金龍寺も桐生へと移りました。
天正十八年(1590年)秀吉軍が小田原城を攻撃したとき、由良成繁の未亡人・赤井氏(妙尼印)は城主のごとく活躍したといいます。
北条氏滅亡後、秀吉は妙尼印の器量を称えて赤井氏に常陸国牛久の地と牛久城を与え、妙尼印は領地を子の国繁に相伝、前城主の菩提寺・東林寺に桐生の金龍寺を移して号を改めたといいます。
国繁没後、理由は不明ですが領地は没収となりますが、牛久の金龍寺と義貞公の墓は、幕府の庇護を受けて、寛文六年(1666年)牛久沼の対岸、龍ケ崎若柴の古寺を改修してここに移されたといい、以降、義貞公の墓所は龍ケ崎若柴の金龍寺とされているようです。


【写真 上(左)】 太田金山金龍寺の御朱印
【写真 下(右)】 龍ケ崎若柴金龍寺の御朱印
↑に「幕府の庇護を受けて」とありますが、この根拠とみられるのは神君・徳川家康公の出自です。
家康公は、新田氏の祖・新田義重公の四男得川義季(世良田義季)の末裔を称しました。
(→ 太田市観光物産協会Web)
足利氏の室町幕府で、草創時に敵対した新田一族は冷遇されました。
しかし、家康公が新田一門を公称したことからも、源氏名流たる新田氏の譽れは戦国末期に至ってなお健在だったとみられます。
征夷大将軍の座は源氏の統領のみに許されるという慣例に則り、源姓新田氏流の統領・家康公は征夷大将軍の座につき徳川幕府を開きました。
征夷大将軍の座は、公的には足利氏から新田氏(徳川氏)に移ったことになります。
徳川将軍家は新田氏(得川氏/世良田氏)ゆかりの上州世良田の地に東照宮を勧請して別格扱いとし、租税を軽くするなど住民までも優遇したと伝わります。
---------------------------------
義貞公の死から500年以上のちの明治の世に、義貞公は朝廷に尽しつづけた「忠臣」として顕彰され、明治15年には正一位を贈位されています。
数々の書物で義貞公の義勇忠節ぶりが描かれ、義貞公の「忠臣」としての評価は定まりました。
明治6年発行の国立銀行紙幣二円券の表面には、稲村ヶ崎で太刀を海中に投じる義貞公の姿が描かれています。
九品寺の義貞公ゆかりの事物として、山門の「内裏山」、本堂の「九品寺」の扁額の文字は、義貞公の揮毫を写したものと伝わります。
当山の御本尊は阿弥陀三尊。
寺号の「九品」とは九パターンの極楽往生のあり様をいい、上品、中品、下品それぞれに上生、中生、下生があり、合わせて九品(九軆)の阿弥陀仏がおわし、救われないものはないといいます。
義貞公が人々の菩提を祈り創ったとされる九品寺。
衆生を極楽往生に導く九品(阿弥陀仏)の寺号は、ふさわしいものといえましょうか。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(亂橋村)九品寺
内裏山靈嶽院と号す、浄土宗 材木座村、光明寺末、三尊の彌陀を本尊とす、中興を卓辨と云へり
■ 山内掲示(鎌倉市)
九品(くほん)とは、九種類の往生のありさまのことをいいます。極楽往生を願う人々の生前の行いによって定められます。上品、中品、下品のそれぞれに、上生、中生、下生があり、合わせて九品とされます。
鎌倉攻めの総大将であった新田義貞が、鎌倉幕府滅亡後に敵方であった北条氏の戦死者を供養するために、材木座に建立しました。
山門の「内裏山」、本堂の「九品寺」の文字は、新田義貞の筆を写したものといわれます。
本尊は阿弥陀三尊です。
■ 『鎌倉市史 社寺編』(鎌倉市)(抜粋)
内裏山靈嶽院九品寺と号する。浄土宗、もと光明寺末、新田義貞の草創で、風航順西を開山と伝える。中興開山は二十一世鏡誉岌故、二十五世台誉卓弁、三十二世楽誉浄阿良澄の三人。
本尊、阿弥陀三尊。
境内地311.95坪。本堂・庫裏・山門あり。
神奈川県重要文化財、石造薬師如来坐像。
寺の『過去帳』によれば、風航順西は暦応四年(1341年)十月十八日に寂している。
岌故は慶安二年(1649年)二月十五日、本尊の御身を再興した。願主は戸塚の吉田四良兵衛とみえている。良澄は弘化二年(1846年)二月、本堂及び三尊像を再興した。(略)
関東大震災にて全潰した。
-------------------------
小町大路に面してあり、光明寺とならんで材木座海岸にもっとも近い寺院です。
鎌倉のメイン通り、若宮大路の材木座口にもほど近く、稲村ヶ崎から侵入し由比ヶ浜で北条勢を破った義貞公が一旦軍勢を落ち着かせ、本陣をおいたという縁起にふさわしい立地です。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 お地蔵さまと寺号標
小町大路に面して参道入口。
手前に地蔵尊立像をおいた寺号標。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
正面は脇塀付き切妻屋根桟瓦葺四脚の山門。
向拝見上げに掲げられている山号扁額は、義貞公の揮毫を移したものと伝わります。


【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場札所標
【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場札所標
山門手前に鎌倉三十三観音霊場と相州二十一ヶ所霊場の札所標が置かれています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 六地蔵と不動尊
緑ゆたかな山内で、参道沿いには古色を帯びた一体型の六地蔵と不動尊立像が御座します。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 扁額と龍の彫刻
参道正面が本堂。
本堂は入母屋造銅本棒葺流れ向拝。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置いています。
御本尊の阿弥陀如来立像は、玉眼を填め込んだ宗元風彫刻として鎌倉市の文化財に指定されています。
本堂のほかに堂宇は見当たらないので、鎌倉三十三観音霊場札所本尊・聖観世音菩薩像、相州二十一ヶ所霊場札所本尊・弘法大師尊像、鎌倉時代作とされ県指定重要文化財の石造薬師如来像はいずれも本堂内に奉安とみられます。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 天水鉢
向拝見上げに掲げられている寺号扁額は、義貞公の揮毫を移したものと伝わります。
堂前の天水鉢にはしっかり新田氏の家紋、「新田一つ引き紋」が描かれていました。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
御本尊、鎌倉三十三観音霊場、相州二十一ヶ所霊場の御朱印を授与されています。
〔 九品寺の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御本尊・阿弥陀如来の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

相州二十一ヶ所霊場の御朱印
46.海潮山 妙長寺(みょうちょうじ)
鎌倉公式観光ガイドWeb
鎌倉市材木座2-7-41
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
司元別当:
札所:
妙長寺は、材木座にある日蓮聖人・伊豆法難ゆかりの日蓮宗寺院です。
鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料、山内縁起碑等から縁起沿革を追ってみます。
妙長寺は、正安元年(1299年)に、伊豆で日蓮聖人の命を救った漁師の子、日実(日實)上人が開山したのがはじまりといわれています。
もともとは由比ヶ浜の字沼ヶ浦というところにあり、延享(1744-1748年)以後に現在地に移転とみられています。
日蓮宗神奈川県第二部布教センターのWebには「妙長寺 日蓮聖人伊豆流罪の際(伊豆法難)、日蓮聖人の命を救った漁師「舟守弥三郎」の子「日実」が開山。伊豆流罪の霊跡の一。」とあります。
「Wikipedia」伊豆法難(いずほうなん)とは、弘長元年(1261年)5月12日に日蓮聖人が捕らえられ、伊豆へ流罪となった事件で「日蓮聖人四大法難」の一つです。
日蓮宗Web、久城寺(秋田県秋田市)の公式Web、および伊豆蓮慶寺の現地掲示等によると、日蓮聖人は文応元年(1260年)に世の中の乱れを嘆き『立正安国論』を執筆されましたが、幕府の反感を買って弘長元年(1261年)5月に伊豆流罪となりました。
日蓮聖人は由比ヶ浜の沼ヶ浦というところから伊豆に向けて船出したといいますが、当山の旧地は「由比ヶ濱沼ヶ浦」なので、船出の地のそばに開創とみられます。


【写真 上(左)】 日蓮崎と俎岩
【写真 下(右)】 俎岩
幕府の役人は船を伊東の湊に着けず、なんと烏崎(日蓮崎)の沖にある「俎岩(まないたいわ)」の上に置き去りにしました。
波浪に晒される岩上に置き去りにされた日蓮聖人は、しかしいささかも動じることなくお題目を唱えられていました。
そばで漁をしていた地元の漁師・舩守弥三郎はお題目をきくと、俎岩に船を漕ぎ寄せて日蓮聖人を救出、川奈港奥の御岩屋祖師堂にかくまったといいます。


【写真 上(左)】 連着寺・奥の院の奉納額
【写真 下(右)】 日蓮聖人「袈裟掛の松」
弥三郎夫妻の住居跡に伊東庄の代官今村若狭守が祖師堂(のちの蓮慶寺)を建て、蓮慶寺本堂には日蓮聖人とともに夫妻の像が祀られています。


【写真 上(左)】 連着寺の寺号標
【写真 下(右)】 連着寺


【写真 上(左)】 連着寺の本堂扁額
【写真 下(右)】 連着寺・奥の院

連着寺の御首題
日蓮聖人は伊豆で3年を過ごされ、伊東の佛現寺、佛光寺などゆかりの寺院を残された後、弘長三年(1263年)に赦免され、鎌倉に帰って伝道活動を再開されました。
弥三郎夫妻の子はのちに日蓮聖人の弟子(ないし孫弟子)となり、日実(日實)と号して日蓮聖人船出の地に妙長寺を開創したと伝わります。
天和元年(1681年)の大津波で堂宇が流されたため、第二十一世常徳院日慶上人が廃寺となっていた乱橋村畠中の天目山圓成寺の旧地に妙長寺を移したといいます。
山内縁起碑では移転の年を「同年(天和元年)」とし、『鎌倉市史 社寺編』では「延享三年(1746年)八月の『小鐘銘』には、相州鎌倉沼浦、海潮山妙長寺とあるから、延享(1744-1748年)以後の移転であろう。」としています。
山内縁起碑には天目山圓成寺は「寛文(1661-1673年)ノ頃 不受不施義ヲ唱ヘタルニヨリ廃絶セルカ」とあります。
徳川幕府が不受不施派を禁じ、他派への転派を命じたのは元禄四年(1691年)とされるので、山内縁起碑の圓成寺廃絶はそれより早く、禁令より早く廃されたのかもしれません。
(寛文九年(1669年)、幕府は不受不施派に対して寺請を禁じたという記録があるようです。)
『鎌倉市史 社寺編』の説をとれば、
天和元年(1681年) 大津波で堂宇流失
元禄四年(1691年)以降 天目山圓成寺廃絶
延享三年(1746年)以後 妙長寺、圓成寺跡地に移転
となり時系列は整います。
しかし、この説だと天和元年(1681年)の堂宇流失から延享三年(1746年)以後の移転まで、短くとも65年の空白が開きます。
ただ、山内縁起碑には「祖師堂ノミ難ヲ免レタリ」とあるので、その期間は祖師堂のみで寺を存続したのかもしれず、詳細はわかりません。
山内には「伊豆法難」ゆかりの伊豆法難記念相輪塔があります。
明治時代には小説家の泉鏡花が明治24年の夏に滞在し、このときの経験を題材にした「星あかり」という作品が残されています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
(乱橋村)妙長寺
海潮山と号す 日蓮宗 比企谷妙本寺末
開山は日實と云ふ 元弘元年十月廿三日寂
本尊釋迦を安ず、小名沼浦に当寺の舊地あり、今も除地なりと云ふ、何の頃此に移りしにや
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
海潮山妙長寺と号する。日蓮宗。もと妙本寺末。
開山は日実と云える。
本尊、三宝祖師。
境内地308.7坪 本堂・庫裏・上行堂・門あり。
材木座小字沼浦から移ったという(『風土記稿』)。
延享三年(1746年)八月の『小鐘銘』には、相州鎌倉沼浦、海潮山妙長寺とあるから、延享(1744-1748年)以後の移転であろう。
■ 山内掲示(縁起、不明瞭箇所あり抜粋転記)
海潮山妙長寺縁起
当山ハモト由比ヶ濱沼ヶ浦ニ在リ 弘長元年(1261年)五月十二日宗祖日蓮大聖人伊豆ニ配流セラルヤ沼ヶ浦ヨリ乗船シ給フ ●子大國阿闍梨日朗上●ニ縋リテ随行ヲモヒシニ 幕吏櫂ヲ揮ツテ日朗上人ノ右臂ヲ打(?)ク 宗祖船上ヨリ●●護持ノ文ヲ唱ヘ給フ ●音海浪ニ遮ラレテ 長短●シカラス所 ●●●●●ココニ起ル 川奈ノ漁師舟守彌三郎 宗祖ヲ俎岩ニ救ヒ奉リ ●●奥に供養ノ●ヲ画シ 一子ヲ宗祖ニ●ス(不明)日實上人是レナリ 弘長三年(1263年)二月二十八日宗祖赦サレテ海路鎌倉ニ●リ●●沼ヶ浦ニ着船ス
宗祖入滅後第十八年正安元年(1299年)日實上人沼ヶ浦二一宇ヲ建立シ海潮山妙長寺ト号シ 父母(不明)発祥ノ地ニ拠リテ 梵音海潮音ノ妙●ヲ長ヘニ使ヘンカタ●ナリ 然ルニ天和元年(1681年)●●ニヨリ堂宇悉ク流失セシカ 但タ祖師堂ノミ難ヲ免レタリ ●ノ中棄マテ(不明)堂實成庵ト称セリ
堂宇流失ノ年第二十一世常徳院日慶上人(不明)ヒテ寺●ヲ亂橋村畠中天目山圓成寺ノ𦾔址ニ移ス 是レ現在ノ地ナリ
圓成寺ハ美濃阿闍梨天目上人ノ開創ニ係ル 寛文(1661-1673年)ノ頃 不受不施義ヲ唱ヘタルニヨリ廃絶セルカ 創建巳来星霜茲ニ六百七十年史實ノ漸ク(不明)トスルヲ●ヘ 本年開●六百五十年遠忌ニ際シ碑ヲ建テ 實ノ●シテ後ニ傳フト云爾
昭和四十四年五月十二日
海潮山四十二世慈徳(?)院日秀謹●
■ 山内掲示(鎌倉市、抜粋)
泉鏡花は明治24年に鎌倉に来て、この妙長寺に七・八月の二か月滞在した。
その後、十月に思い切って(尾崎)紅葉を訪ね、入門を許された。以後創作に励み、小説家として認められ、数々の名作を残した。
この妙長寺滞在の経験をもとにして、明治31年に小説「みだれ橋」を発表し、後に「星あかり」と改題した。
星あかり(山内説明板より)
もとより何故といふ理はないので、墓石の倒れたのを引摺寄せて、二ツばかり重ねて臺にした。其の上に乗って、雨戸の引合せの上の方を、ガタゝ動かして見たが、開きさうにもない。雨戸の中は、相州西鎌倉亂橋の妙長寺といふ、法華宗の寺の、本堂に隣つた八畳の、横に長い置床の附いた座敷で、向つて左手(ゆんで)に、葛籠、革鞄などを置いた際に、山科といふ醫學生が、四六の借蚊帳を釣つて寝て居るのである。
-------------------------
小町大路「水道橋」交差点から南に少し行った道沿いにあります。
小町大路から間口と奥行きのある参道を置き、入口には日蓮聖人の尊像が奉安されています。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 日蓮上人像


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
山門は脇塀付きの切妻屋根銅板葺の四脚門で、正面に本堂が見えます。
石敷きで開けたイメージの山内です。
浄行菩薩堂には丁寧な浄行菩薩の説明書があり、堂上部奥には大曼荼羅も掛けられていました。


【写真 上(左)】 浄行菩薩堂
【写真 下(右)】 本堂
本堂は寄棟造銅板で向拝柱はなく、向拝見上げに寺号扁額を掲げています。
明るくすっきりとしたきもちのよい向拝です。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
山内には「日蓮上人伊豆法難記念」と刻まれた高さ約十メートルの相輪塔があります。
この相輪塔は昭和8年5月に建てられました。
中央の石柱は関東大震災のときくずれた鶴岡八幡宮の二の鳥居の一部を用い、寛文八年(1668年)8月の銘があるそうです。


【写真 上(左)】 縁起碑
【写真 下(右)】 相輪塔と鱗供養塔
他にも立派な寺号標(お題目碑)があり「鱗供養塔」もあります。
「鱗供養塔」は当山で執り行なわれる、材木座海岸沖の放生会にちなむものです。
御首題・御朱印は山内庫裏にて拝受しました。
御首題・御朱印とも、伊豆法難船出の地にかかる揮毫があります。
〔 妙長寺の御首題・御朱印 〕


【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 日蓮大菩薩の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-16 (B.名越口-11)へつづく。
【 BGM 】
■ Angel - Change
■ Hero - David Crosby & Phil Collins
■ Don't Call My Name - King of Hearts -
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-14 (B.名越口-9)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)から。
43.南向山 帰命院 補陀落寺(ふだらくじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-7-31
真言宗大覚寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
司元別当:(材木座)諏訪神社(鎌倉市材木座)
札所:鎌倉三十三観音霊場第17番、相州二十一ヶ所霊場第10番、新四国東国八十八ヶ所霊場第81番
補陀落寺は源頼朝公開基、文覚上人開山とも伝わる古義真言宗の古刹です。
鎌倉市観光協会Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
補陀落寺は養和元年(1181年)源頼朝公が文覚上人を開山として建立、源頼朝公の御祈願所であったとも伝わる名刹です。
中興は、鶴岡八幡宮の供僧佛乗房浄國院賴基大夫法印(文和四年(1355年)寂)と伝わります。
もと京都仁和寺の直末で、その後鎌倉手広の青蓮寺の末寺となりましたが、後に京都大覚寺の直末となったようです。
補陀洛寺は別名を「竜巻寺」ともいい、幾度も竜巻や火災に遭っているようで寺伝類の多くは失われたといいますが、それでもいくつかの寺宝が伝わります。
「平家の赤旗」は、平家の総大将平宗盛が最後まで持っていたものとされ、頼朝公による奉納と伝わります。
平家の赤旗は春の「鎌倉まつり」期間中、公開されている模様です。
御本尊の十一面観世音菩薩立像は伝・平安時代作、薬師如来および両脇侍像(中尊は行基、脇侍は運慶作との伝あり)、伝・文覚上人裸形像などの尊像が伝わり、明治元年の火災でも仏像類がすべて無事であったといいます。
御本尊の十一面観世音菩薩は鎌倉三十三観音霊場第17番札所本尊、木造弘法大師坐像(秘鍵大師)は南北朝時代の作と伝わり相州二十一ヶ所霊場第10番の札所本尊です。
また、奉安の千手観世音菩薩は新四国東国八十八ヶ所霊場第81番の札所本尊です。
鎌倉三十三観音霊場の巡拝者はそれなりにいると思いますが、相州二十一ヶ所霊場、新四国東国八十八ヶ所霊場はどちらかというと「知る人ぞ知る」霊場で巡拝者は多くないと思います。
新四国東国八十八ヶ所霊場は川崎から横浜、そして逗子、鎌倉、藤沢と巡拝する神奈川県の弘法大師霊場(八十八ヶ所)です。
初番・発願は川崎大師(平間寺)、第88番の結願は鎌倉・手広の青蓮寺。
番外や掛所はなく、八十八の札所はすべて真言宗寺院です。
札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様)
新四国東国霊場はすこぶる情報が少なく、ガイドブックはおろかリーフレットさえみたことがありません。
そのわりにしっかりとした札所標が設置されていたりして、どうもナゾの多い霊場です。
新四国東国霊場で面白いのは、ふつう弘法大師霊場では御本尊ないし弘法大師が札所本尊となりますが、新四国東国霊場では別尊や境内仏が札所本尊となる例がみられることです。
当山でも新四国東国霊場の札所本尊は、寺院御本尊(十一面観世音菩薩)ではなく千手観世音菩薩となっています。
新四国東国霊場の鎌倉市内の札所はつぎの7箇寺で、宗派は真言宗大覚寺派、真言宗泉涌寺派、高野山真言宗と古義真言宗系です。
観光寺院はほとんどなく、この点からも新四国東国霊場が「知られざる霊場」であることがわかります。
第81番 南向山 帰命院 補陀洛寺 鎌倉市材木座6
第82番 泉谷山 浄光明寺 鎌倉市扇ヶ谷2
第83番 普明山 法立寺 成就院 鎌倉市極楽寺1
第84番 龍護山 満福寺 鎌倉市腰越2
第85番 小動山 松岩院 浄泉寺 鎌倉市腰越2
第86番 加持山 宝善院 鎌倉市腰越5
第88番 飯盛山 仁王院 青蓮寺 鎌倉市手広
詳細は■ 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印-1をご覧くださいませ。
---------------------------------
「希代の怪僧」ともいわれる文覚上人の開山とあっては、触れないわけにはいきません。
長くなりますが文覚上人の事績を追ってみます
【神護寺】
文覚上人を語るとき、神護寺は外すことができません。まずはここから始めます。
和気清麻呂は、天応元年(781年)頃、国家安泰を祈願して河内に神願寺、山城に和気氏の私寺として高雄山寺を建立しました。
和気氏は仏教への帰依篤く、伝教大師最澄、弘法大師空海を相次いで自らの高雄山寺に招きました。
その縁もあってか弘法大師は唐から帰国の三年後、大同四年(809年)に京入りを果たされ、高雄山寺に入られました。
弘仁三年(812年)、弘法大師は高雄山寺で有名な金剛界結縁灌頂、胎蔵灌頂を開壇されるなど、弘法大師と高雄山寺は深い所縁があります。
天長元年(824年)和気氏は神願寺と高雄山寺を合併し、寺号を神護国祚真言寺(略して神護寺)と改め、弘法大師の保護もあって真言宗の名刹として寺勢を強めました。
しかし正暦五年(994年)と久安五年(1149年)の二度の火災で寺勢衰微し、文覚上人の頃には、わずかに御本尊の薬師如来を風雨に晒しながら残すのみであったといいます。
【文覚上人】 (以下「文覚」と記します。)
文覚の生没年は不詳ですが、源頼朝公(1147-1199年)と同時代の人です。
父は左近将監(遠藤)茂遠、俗名を遠藤盛遠といい、出自は摂津源氏傘下の渡辺党とみられています。
北面の武士として鳥羽天皇の皇女統子内親王(上西門院)に仕えていましたが、19歳で出家したといいます。
出家の理由として、同僚の源渡の妻・袈裟御前に恋慕し、誤って彼女を殺したのが動機といいますが、史実として疑う説もあるようです。
文覚は弘法大師を深く崇敬したといい、出家ののち諸国の霊場を遍歴・修行しました。
その修行は苛烈をきわめ「文覚の荒行」「荒法師文覚」として世に知られていたようです。
安達太良山や那智滝などに文覚荒行伝説が残ります。
仁安三年(1168年)、文覚は30歳のころ弘法大師所縁の神護寺の荒廃を嘆き、再興を決意して神護寺に入り、草庵を結び、薬師堂を建てて御本尊を安置し、弘法大師住坊跡である納凉殿、不動堂等を再建したといいます。
しかし、復興が意のままに進まなかったため、承安三年(1173年)文覚は意を決して後白河法皇の法住寺殿におもむき、荘園の寄進を強訴しました。
この強訴は法皇の逆鱗にふれ、文覚は伊豆に流されました。
ところで、どうして文覚の配所が伊豆だったのでしょうか。
この件についてはこちらの記事で興味ある説を展開されていますので、こちらも参考にしつつ考えてみます。
文覚が後白河法皇の逆鱗にふれて捕縛され、預けられたのは源仲綱ともいいます。
源仲綱は源三位源頼政を父とする摂津源氏で、文覚が出たという渡辺党の主家筋です。
源三位頼政は後白河天皇の皇子・以仁王と結んで平家打倒の兵を挙げたものの戦いに敗れ、宇治平等院で自害しました。
しかし、諸国の源氏に平家打倒の令旨を伝えたのは頼政で、平家打倒・源氏挙兵に大きな道筋を拓きました。
【文覚と源頼朝公】
折しも伊豆には平治の乱で清盛の義母池禅尼の助命により辛うじて斬罪を免れた源頼朝公が隠栖され、源仲綱はその頃伊豆守となっていました。
文覚はこの様な背景から伊豆に配流されたという見方があります。
つまり、後白河法皇-以仁王-源三位頼政-源仲綱という平家打倒・源氏挙兵をもくろむラインがあって、このラインの総意により文覚は伊豆の源頼朝公のもとに送り込まれたという説です。
そうでもなければ、河内(清和)源氏とさほど近しくもない文覚が、頼朝公に熱心に源家再興を説いた動機がわかりません。
文覚は近藤四郎国高に預かりとなって、韮山東部の「奈古屋寺」に籠居しました。
ここは現在の天長山 国清寺の山手で、いまでも「文覚上人流寓之跡」として石碑が残されています。
このそばには頼朝公が文覚に建てさせたという毘沙門堂(安養浄土院/瑞龍寺授福寺)があり、いまは「国清寺の毘沙門堂」といわれています。
また、国清寺の御本尊・聖観世音菩薩は、奈古屋寺の御本尊であったとも伝わります。

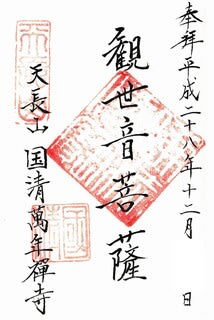
【写真 上(左)】 国清寺
【写真 下(右)】 国清寺の御朱印
奈古屋寺と頼朝公の配所・蛭ヶ小島はほど近く、文覚が足繁く頼朝公を訪れたという逸話もうなづけます。
ともかくも頼朝公と文覚は親交を深め、文覚は頼朝公に源家再興を強く促したといいます。また、頼朝公は源家再興の暁には神護寺復興を約したとも。
治承二年(1178年)、中宮徳子の皇子出産による恩赦で文覚は赦免されました。
その後の数年間の消息が明らかでなく、いくつかの逸話が遺る由縁となっています。
すぐさま帰京し、後白河法皇の許しを得て治承四年(1180年)平氏追討の院宣を介して頼朝公に挙兵を促したという説もあります。
この類似パターンとして、『愚管抄』は治承四年(1180年)当時福原京にいた藤原光能を文覚が訪れ、頼朝公の上奏を後白河法皇に取りつぎ清盛公追討の院宣を出させるように迫ったとの伝聞を記していますが、『愚管抄』の筆者(慈圓僧正)はこれを否定しています。
一度は逆鱗にふれ伊豆に流された文覚ですが、後白河法皇に敬愛の念をいだいていた節があり、治承二年(1179年)平清盛公が法皇を幽閉したのを憤り、(院宣の有無はさておき)頼朝公に平家打倒を督促したという見方もあるようです。
寿永元年(1182年)後白河法皇の蓮華王院御幸の折、文覚は推参して直訴し、ついに正式に法皇の御裁許を得ました。
法皇は翌年、荘園を寄進せられ、寿永三年(1184年)には頼朝公も丹波国宇都荘ほかを寄進、文覚の神護寺再興はここに成ったともいいます。
『吾妻鏡』には、寿永元年(1182年)頼朝公の命により文覚が江ノ島の岩屋に弁財天を勧請とあるので、頼朝公の支援を得て東国でもいくつかの寺院を開創している可能性があります。
元暦二年(1185年)、今後の神護寺のあり方を定めた『(文覚)四十五箇條起請文』を起草して法王に上奏しました。
その内容は強訴を是認する内容を含むものでしたが、法王はこれを咎めることはなかったともいわれ、文治六年(1190年)には高雄山寺に法皇の御幸がありました。
文覚は神護寺復興と並行して東寺の復興、高野山大塔の復興にも関わったとされています。
建久三年(1192年)後白河法皇が崩御され、正治元年(1199年)に頼朝公が没すると文覚はその後ろ盾を失いました。
建久九年(1198年)、権大納言源(土御門)通親は文覚が東寺講堂の諸仏を勝手に動かしたとして咎め、佐渡に流しました。
この流罪はいわゆる「三左衛門事件」に絡むものとみられています。
この事件は正治元年(1199年)頼朝公逝去の直後、遺臣・一条能保・高能父子が源通親の襲撃を企てたとして逮捕された事件です。
外孫・土御門天皇を擁立して権勢を手にした源通親は、頼朝公の嫡子・頼家公の左中将昇進の手続きを強引に進めたところ騒動となり、後藤基清・中原政経・小野義成が頼家公の雑色に捕らえられ、文覚も検非違使に身柄を引き渡され、佐渡へ配流となりました。
しかし、「三左衛門事件」の連座で佐渡配流はいささか罪科が重すぎる感じがあります。
それに文覚佐渡配流は建久九年(1198年)、「三左衛門事件」は正治元年(1199年)とされるので、文覚の佐渡配流は「三左衛門事件」より前で、別の理由も考えられます。
Wikipediaには「『延慶本平家物語』には文覚が守貞親王擁立を企て、頼朝に働きかけたが実現しなかったという記述がある。(中略)通親に対する守貞親王派の不満が噴出したもので、頼朝死後の幕府首脳部は後鳥羽上皇との関係改善のために、守貞親王派の持明院家、一条家、文覚を切り捨てたのではないかと推測」「文覚の勧進事業で寄進されていた神護寺領が事件後に後鳥羽上皇に没収され、承久の乱で後鳥羽上皇が配流されると、今度は鎌倉幕府を介してその所領を与えられた後高倉院(守貞親王)が直ちに上覚(文覚の弟子で師の没後に神護寺再建の中心人物となった)へ返還されていることから、文覚を首謀者とする守貞擁立構想は実際に存在したとする見解も」などの記述があります。
文覚が守貞親王擁立を企て失敗して佐渡へ配流という説もあるようで、この説の方が遠流という重罪に見合っている感もありますが、真相は闇のなかです。
頼朝公は建久六年(1195年)あたりから息女・大姫の入内(後鳥羽天皇への輿入れ)を源通親と丹後局(後白河帝の側室)に画策しましたが、 建久八年(1197年)夏の大姫逝去によりその企ては潰えました。
このあたりの機微にも文覚が絡んでいたのかもしれません。
また、源通親は後白河天皇の第六皇女・宣陽門院の領する広大な長講堂領を実質的に管理していたとみられ、長講堂領を巡るさまざまな駆け引きに文覚が一枚噛んでいたのかも。
佐渡配流3年後の建仁元年(1202年)源通親が没すると、文覚は許されて京に帰りましたが、その間に文覚が保護していた平高清公(六代御前)が処刑されたため、文覚佐渡配流と六代御前処刑の因果関係を示唆する説もあります。
【文覚と平高清公(六代御前)】
寿永二年(1183年)、源義仲の攻勢を受けて平氏が都落ちをしたとき、平維盛公は妻子を都に残して西走しました。
維盛公の嫡子・高清公(六代御前、平正盛公から直系六代目で清盛公の曾孫)は母(藤原成親の息女、新大納言局)とともに京の大覚寺北に潜伏していましたが、平氏滅亡後の文治元年(1185年)に北条時政の捜索で捕らえられました。
平家の嫡流ゆえ、鎌倉に送られて斬首となるところ、文覚の助命嘆願が功を奏して処刑を免れ、身柄は文覚に預けられたといいます。
文治五年(1189年)六代御前は剃髪して妙覚と号し、建久五年(1194年)には文覚の使者として鎌倉を訪れ、大江広元を通じて鎌倉府に対して異心ないことを伝えました。
頼朝公は平治の乱後、六代御前の祖父・平重盛公が自身の助命に尽力してくれた恩として、六代御前をしかるべき寺の別当に任命しようと申し出たと伝わります。
(文覚は、六代御前を神護寺に保護したという説あり。)
六代御前は頼朝公-文覚上人の保護下にありましたが、正治元年(1199年)頼朝公逝去からほどなく処刑されたことになります。
なお、逗子市桜山8丁目に六代御前の墓と伝えられる塚があり、逗子市史跡指定地となっています。
【文覚と頼朝公の関係】
頼朝公は大江広元・中原親能はもとより、九条兼実、源通親ら有力公卿との関係も築き、朝廷ないし後白河法皇とのとりもち役として文覚を頼ったとは考えにくいです。
頼朝公は尊大な人物やアクの強い武将をしばしば粛清しており、この流れからすると個性が強すぎる文覚はすぐにも逆鱗にふれそうです。
また、文覚が保護した六代御前は平家嫡流の遺児ですから、猜疑心の強い頼朝公であれば平家再興の芽を摘むために真っ先に抹殺しているはずです。
ところが文覚も六代御前も頼朝公存命中は咎を受けず、むしろ頼朝公が保護していた感があります。
となると、頼朝公が損得勘定を度外視して文覚に惹かれるなにか、たとえば人間的な魅力とか、卓越した験力とか、そういうものが文覚には備わっていたのかもしれません。
【文覚と後鳥羽上皇】
建仁二年(1202年)「三左衛門事件」に連座して佐渡に配流されたという文覚を赦免し、召還したのは後鳥羽上皇とも目されます。
文覚は後鳥羽院政下で一時はポジションを得たともみられますが、建仁三年(1203年)後鳥羽上皇によって対馬国へ流され、途中、鎮西で客死したとも伝わります。
文覚対馬配流の理由については「文覚が上皇に暴言を吐き怒りを買った」「上皇より謀叛の疑いをかけられた」「文覚が後鳥羽上皇の政を批判した」などいろいろな説が見られますが定説はないようです。
後鳥羽天皇はすこぶる多才で果断な人物と伝わり、同様の個性をもつ文覚とはどうしても感情的に相容れなかったのかもしれません。
文覚の墓所とされる場所は神護寺裏山山頂のほか、隠岐や信州高遠など全国各地にあり、怪僧文覚の神出鬼没ぶりがうかがわれます。
晩年の文覚の活動はさながら「政僧」の趣で、その活動と人脈はあまりに複雑で整理がつかなくなるのですが、後ろ盾だった後白河法皇が没し、正治元年(1199年)に頼朝公が没するとその立場はきわどいものとなったことは容易に想像がつきます。
そして後鳥羽院政下で、その力を失ったことになります。
後白河法皇、後鳥羽上皇、源頼朝公、そして平家嫡流六代御前・・・。
動乱の時代をきらびやかな人脈のなかで生きた文覚は、『平家物語』の数々の名場面でも描かれ、その強烈な個性もあいまっていまも歴史のなかで光芒を放っています。
ながながと辿ってきましたが、源頼朝公開基、文覚上人開山とも伝わる補陀落寺は源平騒乱の歴史に彩られています。
『吾妻鏡』には、寿永元年(1182年)頼朝公の命により文覚が江ノ島の岩屋に辨財天を勧請とあるので、養和元年(1181年)創建の補陀落寺は江ノ島に先立つ開山とみられます。
養和元年(1181年)は、前年の富士川の戦いで平家軍と干戈を交え、これから平家軍との本格的な戦いがはじまるというタイミングです。
この時点での頼朝公の「祈願」が平家調伏、源氏戦捷であったことは容易に想像できるところで、これは『新編相模国風土記稿』の補陀落寺の項に「本尊不動(長三尺智證作、平家調伏の像と云ふ)」「卓圍(祭壇布)一張 頼朝の寄附にて、平家調伏の打敷(仏壇の荘厳具)と云ふ」とあることからも裏付けられます。
江の島岩屋の辨財天も、養和二年(1182年)頼朝公の奥州藤原氏征伐祈願のために文覚が勧請という縁起が伝わり、文覚による祈祷はいずれも験を顕したことになります。
このような文覚の験力も、頼朝公の信任を高めたとみられます。
補陀落寺の梵鐘(観応元年(1350年)鋳造)は、いまは松岡(北鎌倉)の東慶寺にあり、これは農民が当地の土中から掘り出したものといいます。
また、東慶寺の旧梵鐘は、韮山の日蓮宗本立寺にあるといいます。
材木座の補陀落寺の梵鐘が、かなり離れた松岡(北鎌倉)の土中から掘り出されるとは不思議なはなしですが、とにかくそういうことになっています。

東慶寺の梵鐘
また、当山の鎮守・寶満菩薩像(見目明神)は、五社神社と所縁をもつともいわれています。
いまは住宅地のなかにひっそりと佇む補陀落寺ですが、文覚を巡る物語や鎌倉幕府草創の歴史に思いを馳せ、巡ってみるのもまた一興ではないでしょうか。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
補陀落寺は南向山帰命院と号す 材木座の東、民家の間にあり。
古義の真言宗にて、仁和寺の末寺なり。開山は、文覺上人なり。
勧進帳の切たるあり。首尾破れて、作者も年号も不知。其中に文覺、鎌倉へ下向の時、頼朝卿、比来の恩を報ぜんとて、此寺を立られしとあり。
其後頽廃せしを、鶴岡の供僧頼基中略せしとなり。(中略)
本尊薬師・十二神、運慶作也。文覺上人の位牌あり。開山権僧正法眼文覺尊儀とあり。頼朝の木像あり。鏡の御影と云ふ。白旗明神と同じ體なり。同位牌あり。征夷大将軍二品幕下頼朝神儀とあり。
寺寶
八幡画像壱幅 束帯にて袈裟をかけ、数珠を持つしむ。冠より一寸ばかり上に日輪をゑかく。
寶満菩薩像一軀 八幡の姨なり。鶴岡にもあり。社家にては見目明神(ミルメ)と云ふ。
平家調伏の打敷壱張
平家赤旗壱流 幅二布、長三尺五分あり。九萬八千軍神と、書付てあり。(中略)
鐘楼跡
今跡のみ有て鐘もなし。当寺の鐘は、松岡東慶寺にあり。農民、松岡の地にて掘出したりと云ふ。銘を見れば、当寺の鐘なり。兵乱の時、紛散したるなるべし。
●東慶寺(松岡)
鐘楼
山門外、右にあり。此寺の鐘は、小田原陣の時失して、今有鐘は、松岡の領地にて、農民ほり出したりと云う。銘を見るに補陀落寺の鐘なり。故に此鐘の銘は補陀落寺の條下に記す。
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(材木座村)補陀落寺
南向山帰命院と号す 古義真言宗 往昔京都仁和寺に属せしが、今は手廣村青蓮寺末たり 開山は文覺にて養和元年(1181年)頼朝祈願所として創建あり
按ずるに、当寺に勧進帳の切あり、首尾破れて詳ならず、其中に文覺鎌倉へ下向の時、頼朝比来の恩を報ぜんとて、此寺を建られしとあり、思ふに此勧進帳の文は、中興の僧、頼基の作なるべし
其後頽廃せしを鶴岡の供僧頼基(鶴岡供僧次第に、佛乗房浄國院頼基大夫法印、文和四年(1355年)二月二日寂す、千田大僧都と号すとあり)中興せり(中略)
本尊不動(長三尺智證作、平家調伏の像と云ふ、按ずるに、【鎌倉志】には、本尊薬師とあり)及び薬師(長三尺七寸行基作)日光・月光・十二神(長各二尺八寸、共に運慶作)十一面観音(長三尺八寸許行基作、往昔の本尊なりと云ふ)地蔵二軀(一は鐡佛、長一尺許、門前の井中より出現せしと云ふ、一は弘法作、長一尺七寸)大黒(長尺許傳作)大日(長八寸許)賓頭盧(長三尺已上弘法作)等の像を置く、又頼朝の木像あり(長八寸許四十二歳の自作と云ふ)鏡の御影と称せり、同位牌あり 征夷将軍二品幕下神儀とあり文覺の書と云ふ)開山文覺の牌もあり(開山権僧正法眼文覺尊儀とあり)
【寺寶】
八幡画像一幅 束帶にて袈裟をかけ、數珠を持しむ、冠より一寸ばかり上に、日輪を畫
寶満菩薩像一幅 應神帝の姨にて、見目明神と称すとなり
卓圍(祭壇布)一張 頼朝の寄附にて、平家調伏の打敷(仏壇の荘厳具)と云ふ、孔雀鳳凰の繍文あり
旗一流 平家赤旗と称し、文字は相國清盛の筆と傳ふ(中略)
牛頭天王見目明神合社 大道寺源六周勝社領二貫三百文及び寺内修補の料を寄附せし事所蔵文書に見えたり
住吉社
鐘楼蹟
𦾔観應年間の古鐘あり。兵乱の為に亡失せしを後松岡ヶの農民地中より掘出し同所東慶寺に収むと云ふ。今尚あり。
■ 『鎌倉市史 社寺編』(鎌倉市)(抜粋)
南向山帰命院補陀落寺と号する。古義真言宗。もと京都仁和寺末。のち青蓮寺末。現在京都大覚寺末。開山は文覚上人、開基は源頼朝と伝える。後、鶴岡八幡宮供僧頼基が中興した。
本尊、十一面観音。もとの本尊は薬師如来。日光・月光、ほかに不動明王あり。
境内地163坪。本堂・門・庫裏あり。(中略)
開基は仏乗坊の八代及び十代で、建武三年六月に還補されているから、この寺の鐘ができた観応元年(1350年)には供僧であったこととなる。(中略)
『新編鎌倉志』は鐘銘及び寺号によって、本尊は観音であったはずであるといっている。
従うべきであろう。(中略)
当寺が頼朝と関係があることは前述の勧進帳に見えるのを初見とするが(中略)頼朝の供養をここですることになっていたらしい。(中略)
明治初年の火災で殆ど烏有に帰したが、その時誰も出した覚えがないのに、仏像類は全部無事であったという。大正十二年震災で全壊し、現在の本堂は大正十三年の建立である。
-------------------------
材木座の巨刹、光明寺にもほど近い住宅街にあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 石碑
山内入口に門柱で、その手前に「源頼朝公御祈願所●●補陀落寺」と彫られた石碑があります。


【写真 上(左)】 門柱
【写真 下(右)】 山内
山内は広くはないですが閑雅な落ち着きがあり、「荒法師開山」のイメージはあまりありません。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 寺号板
本堂はおそらく切妻造桟瓦葺平入りで、右手に寄せて流れ向拝を置いています。
向拝の柱や虹梁はシンプルですが、向拝柱に寺号標を掲げています。


【写真 上(左)】 庫裏への道
【写真 下(右)】 同 紫陽花
御朱印は庫裏にて拝受しました。
鎌倉三十三観音霊場、相州二十一ヶ所霊場、新四国東国八十八ヶ所霊場いずれの御朱印も拝受していますが、現況の授与状況は不明です。
〔 補陀落寺の御朱印 〕


【写真 上(左)】 弘法大師の御朱印(ご縁日)
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

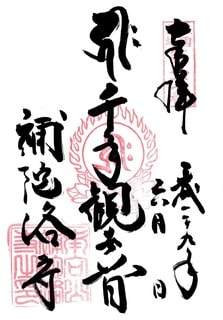
【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印
44.円龍山 向福寺(こうふくじ)
公式Web
鎌倉市材木座3-15-13
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
司元別当:
札所:鎌倉三十三観音霊場第15番
向福寺は一向俊聖上人開山と伝わる時宗寺院です。
公式Web、下記史料・資料、現地掲示から縁起沿革を追ってみます。
向福寺は弘安五年(1282年)、開山を一向俊聖上人として創建されました。
一向俊聖上人(1239年?-1287年?)は、鎌倉時代の名僧で時宗一向派の祖です。
儀空菩薩とも呼ばれます。
「新纂 浄土宗大辞典」および「Wikipedia」を参考にその足跡を追ってみます。
伝承によれば、筑後国竹野荘西好田(福岡県久留米市)の御家人草野永泰の次男として生まれたといいます。
永泰の兄草野永平は浄土宗鎮西派の聖光上人(弁長)に帰依し、建久三年(1192年)に久留米善導寺を建立した大檀越でした。
寛元三年(1245年)、播磨国書写山圓教寺に入寺して天台教学を志し、建長五年(1253年)に剃髪受戒して名を俊聖としました。
翌年夏に書写山を下り、奈良興福寺などで修行されるも悟りを得られず、鎌倉蓮華寺(光明寺)の然阿良忠上人の門弟となりました。
一向専念の文より号を一向と改め、文永十年(1273年)から各地を念仏聖として遊行回国し、踊り念仏(踊躍念佛)、天道念仏(天童念佛)を修して道場を設けました。
後年は遊行と踊り念仏で民衆を教化し、弘安一〇年(1287年)11月、近江国番場蓮華寺(滋賀県米原市)で立ち往生したと伝わります。
俊聖上人の教えは時宗一向派(天童派)として各地に広く伝わったため伝承も多く、ナゾの多い僧ともいわれます。
実在していないという説さえありましたが、近年山形県天童市の高野坊遺跡より出土した墨書の礫石経により、その実在が立証されています。
ただし、法統については諸説あり、浄土宗鎮西義の然阿良忠上人のほか、浄土宗西山深草派西山三派の祖・証空門下の顕性に師事したという説もあります。
一向俊聖上人を祖とする(時宗)一向派は時宗十二派の一つで、番場時衆、時宗番場派とも呼ばれ、本山は番場蓮華寺(滋賀県米原市)です。
「一向派」の呼称は、元禄一〇年(1697年)成立の時宗触頭・浅草日輪寺吞上人著の『時宗要略譜』が初見とされます。
『一向上人血脈譜』によると、上人には「十五戒弟」と称する弟子があり、東北、関東、甲信越を中心に布教をすすめて全盛期には末寺一七四箇寺を数えたといいます。
とくに山形県天童市の仏向寺は一向俊聖上人開山で、番場蓮華寺とならぶ中心寺院となっています。
江戸幕府の宗教政策により時宗遊行派の傘下に編入され、派内の本末論争などもあって衰勢となりました。
当初「一向宗」とし、江戸時代に「時宗」に吸収されたとする資料もみられます。
「新纂 浄土宗大辞典」には、明治36年時宗内で一向派の立場を認める『時宗宗憲宗規』が制定されましたが、昭和16年の一宗一管長制により、翌17年には一向派97箇寺中57箇寺が時宗より浄土宗に転宗、残る41箇寺は時宗にとどまったとあります。
向福寺は、おそらく時宗一向派(あるいは一向宗)から時宗となった寺院のひとつとみられます。
公益財団法人住友財団の公式Webによると、御本尊の阿弥陀三尊木像は中世(現地掲示資料では南北朝時代)作。檜材、割矧ぎ造ないし寄木造りで玉眼を嵌入しています。
脇侍の観世音菩薩、勢至菩薩とともに鎌倉市指定文化財に指定されています。
また、『鎌倉札所巡り』(メイツ出版)・現地掲示によると、当山本堂南側の部屋は、『丹下左膳』で知られる作家・林不忘(長谷川海太郎、1900年-1935年)が関東大震災前に新婚生活を送ったところです。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(乱橋村)向福寺
圓龍山と号す 本寺前に同じ(藤澤清浄光寺末) 本尊三尊彌陀を安ず 各立像、安阿彌作
■ 山内掲示(鎌倉市)
公式Webと重複するため略。
■ 『鎌倉市史 社寺編』(鎌倉市)(抜粋)
円龍山向福寺と号する。時宗。藤沢清浄光寺末。
開山、一向。
本尊、阿弥陀如来。
境内地229.7坪。本堂兼庫裏あり
『大正三年明細書』によれば文政九年に再建した本堂・表門があったが、大正大震災で全潰した。今の本堂は昭和五年の再建である。
-------------------------
小町大路「水道路」交差点から少し南下した右手の路地沿いにあり、あまり目立ちません。
門柱に「時宗 向福寺」となければ、ほとんど民家にしか見えません。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 門柱の寺号標
山内は緑が多く、植木鉢もきれいに並べられています。
参道正面の本堂は入母屋造銅板で身舎右手に向拝を附設しています。
本堂は庫裏とつながり、一見寺院建築のイメージはあまりありません。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
向拝は水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板本蟇股を置いています。
ここまでくるとさすがに寺院本堂の存在感があります。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 観音霊場の札所板
ガラス格子の扉のうえに鎌倉三十三観音霊場の札所板を掲げています。
文政九年(1826年)再建の本堂は大正の関東大震災で全潰し、いまの本堂は昭和五年の再建とのことですが、そこまで古びた感じはないので手を入れられているかもしれません。
観音堂はなく、本堂向拝に札所板が掲げられているので、鎌倉三十三観音霊場第15番の札所本尊・聖観世音菩薩立像は、御本尊の阿弥陀三尊とともに本堂内に奉安とみられます。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
御本尊と鎌倉三十三観音霊場の御朱印を授与されています。
〔 向福寺の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御本尊・阿弥陀如来の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-15 (B.名越口-10)へつづく。
【 BGM 】
■ Hearts - Marty Balin
■ If I Belive - Patti Austin
■ Late At Night - George Benson Ft. Vickie Randle
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)
■ 同-13 (B.名越口-8)から。
43.南向山 帰命院 補陀落寺(ふだらくじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-7-31
真言宗大覚寺派
御本尊:十一面観世音菩薩
司元別当:(材木座)諏訪神社(鎌倉市材木座)
札所:鎌倉三十三観音霊場第17番、相州二十一ヶ所霊場第10番、新四国東国八十八ヶ所霊場第81番
補陀落寺は源頼朝公開基、文覚上人開山とも伝わる古義真言宗の古刹です。
鎌倉市観光協会Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
補陀落寺は養和元年(1181年)源頼朝公が文覚上人を開山として建立、源頼朝公の御祈願所であったとも伝わる名刹です。
中興は、鶴岡八幡宮の供僧佛乗房浄國院賴基大夫法印(文和四年(1355年)寂)と伝わります。
もと京都仁和寺の直末で、その後鎌倉手広の青蓮寺の末寺となりましたが、後に京都大覚寺の直末となったようです。
補陀洛寺は別名を「竜巻寺」ともいい、幾度も竜巻や火災に遭っているようで寺伝類の多くは失われたといいますが、それでもいくつかの寺宝が伝わります。
「平家の赤旗」は、平家の総大将平宗盛が最後まで持っていたものとされ、頼朝公による奉納と伝わります。
平家の赤旗は春の「鎌倉まつり」期間中、公開されている模様です。
御本尊の十一面観世音菩薩立像は伝・平安時代作、薬師如来および両脇侍像(中尊は行基、脇侍は運慶作との伝あり)、伝・文覚上人裸形像などの尊像が伝わり、明治元年の火災でも仏像類がすべて無事であったといいます。
御本尊の十一面観世音菩薩は鎌倉三十三観音霊場第17番札所本尊、木造弘法大師坐像(秘鍵大師)は南北朝時代の作と伝わり相州二十一ヶ所霊場第10番の札所本尊です。
また、奉安の千手観世音菩薩は新四国東国八十八ヶ所霊場第81番の札所本尊です。
鎌倉三十三観音霊場の巡拝者はそれなりにいると思いますが、相州二十一ヶ所霊場、新四国東国八十八ヶ所霊場はどちらかというと「知る人ぞ知る」霊場で巡拝者は多くないと思います。
新四国東国八十八ヶ所霊場は川崎から横浜、そして逗子、鎌倉、藤沢と巡拝する神奈川県の弘法大師霊場(八十八ヶ所)です。
初番・発願は川崎大師(平間寺)、第88番の結願は鎌倉・手広の青蓮寺。
番外や掛所はなく、八十八の札所はすべて真言宗寺院です。
札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様)
新四国東国霊場はすこぶる情報が少なく、ガイドブックはおろかリーフレットさえみたことがありません。
そのわりにしっかりとした札所標が設置されていたりして、どうもナゾの多い霊場です。
新四国東国霊場で面白いのは、ふつう弘法大師霊場では御本尊ないし弘法大師が札所本尊となりますが、新四国東国霊場では別尊や境内仏が札所本尊となる例がみられることです。
当山でも新四国東国霊場の札所本尊は、寺院御本尊(十一面観世音菩薩)ではなく千手観世音菩薩となっています。
新四国東国霊場の鎌倉市内の札所はつぎの7箇寺で、宗派は真言宗大覚寺派、真言宗泉涌寺派、高野山真言宗と古義真言宗系です。
観光寺院はほとんどなく、この点からも新四国東国霊場が「知られざる霊場」であることがわかります。
第81番 南向山 帰命院 補陀洛寺 鎌倉市材木座6
第82番 泉谷山 浄光明寺 鎌倉市扇ヶ谷2
第83番 普明山 法立寺 成就院 鎌倉市極楽寺1
第84番 龍護山 満福寺 鎌倉市腰越2
第85番 小動山 松岩院 浄泉寺 鎌倉市腰越2
第86番 加持山 宝善院 鎌倉市腰越5
第88番 飯盛山 仁王院 青蓮寺 鎌倉市手広
詳細は■ 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印-1をご覧くださいませ。
---------------------------------
「希代の怪僧」ともいわれる文覚上人の開山とあっては、触れないわけにはいきません。
長くなりますが文覚上人の事績を追ってみます
【神護寺】
文覚上人を語るとき、神護寺は外すことができません。まずはここから始めます。
和気清麻呂は、天応元年(781年)頃、国家安泰を祈願して河内に神願寺、山城に和気氏の私寺として高雄山寺を建立しました。
和気氏は仏教への帰依篤く、伝教大師最澄、弘法大師空海を相次いで自らの高雄山寺に招きました。
その縁もあってか弘法大師は唐から帰国の三年後、大同四年(809年)に京入りを果たされ、高雄山寺に入られました。
弘仁三年(812年)、弘法大師は高雄山寺で有名な金剛界結縁灌頂、胎蔵灌頂を開壇されるなど、弘法大師と高雄山寺は深い所縁があります。
天長元年(824年)和気氏は神願寺と高雄山寺を合併し、寺号を神護国祚真言寺(略して神護寺)と改め、弘法大師の保護もあって真言宗の名刹として寺勢を強めました。
しかし正暦五年(994年)と久安五年(1149年)の二度の火災で寺勢衰微し、文覚上人の頃には、わずかに御本尊の薬師如来を風雨に晒しながら残すのみであったといいます。
【文覚上人】 (以下「文覚」と記します。)
文覚の生没年は不詳ですが、源頼朝公(1147-1199年)と同時代の人です。
父は左近将監(遠藤)茂遠、俗名を遠藤盛遠といい、出自は摂津源氏傘下の渡辺党とみられています。
北面の武士として鳥羽天皇の皇女統子内親王(上西門院)に仕えていましたが、19歳で出家したといいます。
出家の理由として、同僚の源渡の妻・袈裟御前に恋慕し、誤って彼女を殺したのが動機といいますが、史実として疑う説もあるようです。
文覚は弘法大師を深く崇敬したといい、出家ののち諸国の霊場を遍歴・修行しました。
その修行は苛烈をきわめ「文覚の荒行」「荒法師文覚」として世に知られていたようです。
安達太良山や那智滝などに文覚荒行伝説が残ります。
仁安三年(1168年)、文覚は30歳のころ弘法大師所縁の神護寺の荒廃を嘆き、再興を決意して神護寺に入り、草庵を結び、薬師堂を建てて御本尊を安置し、弘法大師住坊跡である納凉殿、不動堂等を再建したといいます。
しかし、復興が意のままに進まなかったため、承安三年(1173年)文覚は意を決して後白河法皇の法住寺殿におもむき、荘園の寄進を強訴しました。
この強訴は法皇の逆鱗にふれ、文覚は伊豆に流されました。
ところで、どうして文覚の配所が伊豆だったのでしょうか。
この件についてはこちらの記事で興味ある説を展開されていますので、こちらも参考にしつつ考えてみます。
文覚が後白河法皇の逆鱗にふれて捕縛され、預けられたのは源仲綱ともいいます。
源仲綱は源三位源頼政を父とする摂津源氏で、文覚が出たという渡辺党の主家筋です。
源三位頼政は後白河天皇の皇子・以仁王と結んで平家打倒の兵を挙げたものの戦いに敗れ、宇治平等院で自害しました。
しかし、諸国の源氏に平家打倒の令旨を伝えたのは頼政で、平家打倒・源氏挙兵に大きな道筋を拓きました。
【文覚と源頼朝公】
折しも伊豆には平治の乱で清盛の義母池禅尼の助命により辛うじて斬罪を免れた源頼朝公が隠栖され、源仲綱はその頃伊豆守となっていました。
文覚はこの様な背景から伊豆に配流されたという見方があります。
つまり、後白河法皇-以仁王-源三位頼政-源仲綱という平家打倒・源氏挙兵をもくろむラインがあって、このラインの総意により文覚は伊豆の源頼朝公のもとに送り込まれたという説です。
そうでもなければ、河内(清和)源氏とさほど近しくもない文覚が、頼朝公に熱心に源家再興を説いた動機がわかりません。
文覚は近藤四郎国高に預かりとなって、韮山東部の「奈古屋寺」に籠居しました。
ここは現在の天長山 国清寺の山手で、いまでも「文覚上人流寓之跡」として石碑が残されています。
このそばには頼朝公が文覚に建てさせたという毘沙門堂(安養浄土院/瑞龍寺授福寺)があり、いまは「国清寺の毘沙門堂」といわれています。
また、国清寺の御本尊・聖観世音菩薩は、奈古屋寺の御本尊であったとも伝わります。

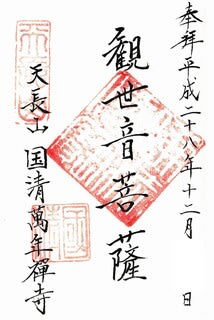
【写真 上(左)】 国清寺
【写真 下(右)】 国清寺の御朱印
奈古屋寺と頼朝公の配所・蛭ヶ小島はほど近く、文覚が足繁く頼朝公を訪れたという逸話もうなづけます。
ともかくも頼朝公と文覚は親交を深め、文覚は頼朝公に源家再興を強く促したといいます。また、頼朝公は源家再興の暁には神護寺復興を約したとも。
治承二年(1178年)、中宮徳子の皇子出産による恩赦で文覚は赦免されました。
その後の数年間の消息が明らかでなく、いくつかの逸話が遺る由縁となっています。
すぐさま帰京し、後白河法皇の許しを得て治承四年(1180年)平氏追討の院宣を介して頼朝公に挙兵を促したという説もあります。
この類似パターンとして、『愚管抄』は治承四年(1180年)当時福原京にいた藤原光能を文覚が訪れ、頼朝公の上奏を後白河法皇に取りつぎ清盛公追討の院宣を出させるように迫ったとの伝聞を記していますが、『愚管抄』の筆者(慈圓僧正)はこれを否定しています。
一度は逆鱗にふれ伊豆に流された文覚ですが、後白河法皇に敬愛の念をいだいていた節があり、治承二年(1179年)平清盛公が法皇を幽閉したのを憤り、(院宣の有無はさておき)頼朝公に平家打倒を督促したという見方もあるようです。
寿永元年(1182年)後白河法皇の蓮華王院御幸の折、文覚は推参して直訴し、ついに正式に法皇の御裁許を得ました。
法皇は翌年、荘園を寄進せられ、寿永三年(1184年)には頼朝公も丹波国宇都荘ほかを寄進、文覚の神護寺再興はここに成ったともいいます。
『吾妻鏡』には、寿永元年(1182年)頼朝公の命により文覚が江ノ島の岩屋に弁財天を勧請とあるので、頼朝公の支援を得て東国でもいくつかの寺院を開創している可能性があります。
元暦二年(1185年)、今後の神護寺のあり方を定めた『(文覚)四十五箇條起請文』を起草して法王に上奏しました。
その内容は強訴を是認する内容を含むものでしたが、法王はこれを咎めることはなかったともいわれ、文治六年(1190年)には高雄山寺に法皇の御幸がありました。
文覚は神護寺復興と並行して東寺の復興、高野山大塔の復興にも関わったとされています。
建久三年(1192年)後白河法皇が崩御され、正治元年(1199年)に頼朝公が没すると文覚はその後ろ盾を失いました。
建久九年(1198年)、権大納言源(土御門)通親は文覚が東寺講堂の諸仏を勝手に動かしたとして咎め、佐渡に流しました。
この流罪はいわゆる「三左衛門事件」に絡むものとみられています。
この事件は正治元年(1199年)頼朝公逝去の直後、遺臣・一条能保・高能父子が源通親の襲撃を企てたとして逮捕された事件です。
外孫・土御門天皇を擁立して権勢を手にした源通親は、頼朝公の嫡子・頼家公の左中将昇進の手続きを強引に進めたところ騒動となり、後藤基清・中原政経・小野義成が頼家公の雑色に捕らえられ、文覚も検非違使に身柄を引き渡され、佐渡へ配流となりました。
しかし、「三左衛門事件」の連座で佐渡配流はいささか罪科が重すぎる感じがあります。
それに文覚佐渡配流は建久九年(1198年)、「三左衛門事件」は正治元年(1199年)とされるので、文覚の佐渡配流は「三左衛門事件」より前で、別の理由も考えられます。
Wikipediaには「『延慶本平家物語』には文覚が守貞親王擁立を企て、頼朝に働きかけたが実現しなかったという記述がある。(中略)通親に対する守貞親王派の不満が噴出したもので、頼朝死後の幕府首脳部は後鳥羽上皇との関係改善のために、守貞親王派の持明院家、一条家、文覚を切り捨てたのではないかと推測」「文覚の勧進事業で寄進されていた神護寺領が事件後に後鳥羽上皇に没収され、承久の乱で後鳥羽上皇が配流されると、今度は鎌倉幕府を介してその所領を与えられた後高倉院(守貞親王)が直ちに上覚(文覚の弟子で師の没後に神護寺再建の中心人物となった)へ返還されていることから、文覚を首謀者とする守貞擁立構想は実際に存在したとする見解も」などの記述があります。
文覚が守貞親王擁立を企て失敗して佐渡へ配流という説もあるようで、この説の方が遠流という重罪に見合っている感もありますが、真相は闇のなかです。
頼朝公は建久六年(1195年)あたりから息女・大姫の入内(後鳥羽天皇への輿入れ)を源通親と丹後局(後白河帝の側室)に画策しましたが、 建久八年(1197年)夏の大姫逝去によりその企ては潰えました。
このあたりの機微にも文覚が絡んでいたのかもしれません。
また、源通親は後白河天皇の第六皇女・宣陽門院の領する広大な長講堂領を実質的に管理していたとみられ、長講堂領を巡るさまざまな駆け引きに文覚が一枚噛んでいたのかも。
佐渡配流3年後の建仁元年(1202年)源通親が没すると、文覚は許されて京に帰りましたが、その間に文覚が保護していた平高清公(六代御前)が処刑されたため、文覚佐渡配流と六代御前処刑の因果関係を示唆する説もあります。
【文覚と平高清公(六代御前)】
寿永二年(1183年)、源義仲の攻勢を受けて平氏が都落ちをしたとき、平維盛公は妻子を都に残して西走しました。
維盛公の嫡子・高清公(六代御前、平正盛公から直系六代目で清盛公の曾孫)は母(藤原成親の息女、新大納言局)とともに京の大覚寺北に潜伏していましたが、平氏滅亡後の文治元年(1185年)に北条時政の捜索で捕らえられました。
平家の嫡流ゆえ、鎌倉に送られて斬首となるところ、文覚の助命嘆願が功を奏して処刑を免れ、身柄は文覚に預けられたといいます。
文治五年(1189年)六代御前は剃髪して妙覚と号し、建久五年(1194年)には文覚の使者として鎌倉を訪れ、大江広元を通じて鎌倉府に対して異心ないことを伝えました。
頼朝公は平治の乱後、六代御前の祖父・平重盛公が自身の助命に尽力してくれた恩として、六代御前をしかるべき寺の別当に任命しようと申し出たと伝わります。
(文覚は、六代御前を神護寺に保護したという説あり。)
六代御前は頼朝公-文覚上人の保護下にありましたが、正治元年(1199年)頼朝公逝去からほどなく処刑されたことになります。
なお、逗子市桜山8丁目に六代御前の墓と伝えられる塚があり、逗子市史跡指定地となっています。
【文覚と頼朝公の関係】
頼朝公は大江広元・中原親能はもとより、九条兼実、源通親ら有力公卿との関係も築き、朝廷ないし後白河法皇とのとりもち役として文覚を頼ったとは考えにくいです。
頼朝公は尊大な人物やアクの強い武将をしばしば粛清しており、この流れからすると個性が強すぎる文覚はすぐにも逆鱗にふれそうです。
また、文覚が保護した六代御前は平家嫡流の遺児ですから、猜疑心の強い頼朝公であれば平家再興の芽を摘むために真っ先に抹殺しているはずです。
ところが文覚も六代御前も頼朝公存命中は咎を受けず、むしろ頼朝公が保護していた感があります。
となると、頼朝公が損得勘定を度外視して文覚に惹かれるなにか、たとえば人間的な魅力とか、卓越した験力とか、そういうものが文覚には備わっていたのかもしれません。
【文覚と後鳥羽上皇】
建仁二年(1202年)「三左衛門事件」に連座して佐渡に配流されたという文覚を赦免し、召還したのは後鳥羽上皇とも目されます。
文覚は後鳥羽院政下で一時はポジションを得たともみられますが、建仁三年(1203年)後鳥羽上皇によって対馬国へ流され、途中、鎮西で客死したとも伝わります。
文覚対馬配流の理由については「文覚が上皇に暴言を吐き怒りを買った」「上皇より謀叛の疑いをかけられた」「文覚が後鳥羽上皇の政を批判した」などいろいろな説が見られますが定説はないようです。
後鳥羽天皇はすこぶる多才で果断な人物と伝わり、同様の個性をもつ文覚とはどうしても感情的に相容れなかったのかもしれません。
文覚の墓所とされる場所は神護寺裏山山頂のほか、隠岐や信州高遠など全国各地にあり、怪僧文覚の神出鬼没ぶりがうかがわれます。
晩年の文覚の活動はさながら「政僧」の趣で、その活動と人脈はあまりに複雑で整理がつかなくなるのですが、後ろ盾だった後白河法皇が没し、正治元年(1199年)に頼朝公が没するとその立場はきわどいものとなったことは容易に想像がつきます。
そして後鳥羽院政下で、その力を失ったことになります。
後白河法皇、後鳥羽上皇、源頼朝公、そして平家嫡流六代御前・・・。
動乱の時代をきらびやかな人脈のなかで生きた文覚は、『平家物語』の数々の名場面でも描かれ、その強烈な個性もあいまっていまも歴史のなかで光芒を放っています。
ながながと辿ってきましたが、源頼朝公開基、文覚上人開山とも伝わる補陀落寺は源平騒乱の歴史に彩られています。
『吾妻鏡』には、寿永元年(1182年)頼朝公の命により文覚が江ノ島の岩屋に辨財天を勧請とあるので、養和元年(1181年)創建の補陀落寺は江ノ島に先立つ開山とみられます。
養和元年(1181年)は、前年の富士川の戦いで平家軍と干戈を交え、これから平家軍との本格的な戦いがはじまるというタイミングです。
この時点での頼朝公の「祈願」が平家調伏、源氏戦捷であったことは容易に想像できるところで、これは『新編相模国風土記稿』の補陀落寺の項に「本尊不動(長三尺智證作、平家調伏の像と云ふ)」「卓圍(祭壇布)一張 頼朝の寄附にて、平家調伏の打敷(仏壇の荘厳具)と云ふ」とあることからも裏付けられます。
江の島岩屋の辨財天も、養和二年(1182年)頼朝公の奥州藤原氏征伐祈願のために文覚が勧請という縁起が伝わり、文覚による祈祷はいずれも験を顕したことになります。
このような文覚の験力も、頼朝公の信任を高めたとみられます。
補陀落寺の梵鐘(観応元年(1350年)鋳造)は、いまは松岡(北鎌倉)の東慶寺にあり、これは農民が当地の土中から掘り出したものといいます。
また、東慶寺の旧梵鐘は、韮山の日蓮宗本立寺にあるといいます。
材木座の補陀落寺の梵鐘が、かなり離れた松岡(北鎌倉)の土中から掘り出されるとは不思議なはなしですが、とにかくそういうことになっています。

東慶寺の梵鐘
また、当山の鎮守・寶満菩薩像(見目明神)は、五社神社と所縁をもつともいわれています。
いまは住宅地のなかにひっそりと佇む補陀落寺ですが、文覚を巡る物語や鎌倉幕府草創の歴史に思いを馳せ、巡ってみるのもまた一興ではないでしょうか。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
補陀落寺は南向山帰命院と号す 材木座の東、民家の間にあり。
古義の真言宗にて、仁和寺の末寺なり。開山は、文覺上人なり。
勧進帳の切たるあり。首尾破れて、作者も年号も不知。其中に文覺、鎌倉へ下向の時、頼朝卿、比来の恩を報ぜんとて、此寺を立られしとあり。
其後頽廃せしを、鶴岡の供僧頼基中略せしとなり。(中略)
本尊薬師・十二神、運慶作也。文覺上人の位牌あり。開山権僧正法眼文覺尊儀とあり。頼朝の木像あり。鏡の御影と云ふ。白旗明神と同じ體なり。同位牌あり。征夷大将軍二品幕下頼朝神儀とあり。
寺寶
八幡画像壱幅 束帯にて袈裟をかけ、数珠を持つしむ。冠より一寸ばかり上に日輪をゑかく。
寶満菩薩像一軀 八幡の姨なり。鶴岡にもあり。社家にては見目明神(ミルメ)と云ふ。
平家調伏の打敷壱張
平家赤旗壱流 幅二布、長三尺五分あり。九萬八千軍神と、書付てあり。(中略)
鐘楼跡
今跡のみ有て鐘もなし。当寺の鐘は、松岡東慶寺にあり。農民、松岡の地にて掘出したりと云ふ。銘を見れば、当寺の鐘なり。兵乱の時、紛散したるなるべし。
●東慶寺(松岡)
鐘楼
山門外、右にあり。此寺の鐘は、小田原陣の時失して、今有鐘は、松岡の領地にて、農民ほり出したりと云う。銘を見るに補陀落寺の鐘なり。故に此鐘の銘は補陀落寺の條下に記す。
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(材木座村)補陀落寺
南向山帰命院と号す 古義真言宗 往昔京都仁和寺に属せしが、今は手廣村青蓮寺末たり 開山は文覺にて養和元年(1181年)頼朝祈願所として創建あり
按ずるに、当寺に勧進帳の切あり、首尾破れて詳ならず、其中に文覺鎌倉へ下向の時、頼朝比来の恩を報ぜんとて、此寺を建られしとあり、思ふに此勧進帳の文は、中興の僧、頼基の作なるべし
其後頽廃せしを鶴岡の供僧頼基(鶴岡供僧次第に、佛乗房浄國院頼基大夫法印、文和四年(1355年)二月二日寂す、千田大僧都と号すとあり)中興せり(中略)
本尊不動(長三尺智證作、平家調伏の像と云ふ、按ずるに、【鎌倉志】には、本尊薬師とあり)及び薬師(長三尺七寸行基作)日光・月光・十二神(長各二尺八寸、共に運慶作)十一面観音(長三尺八寸許行基作、往昔の本尊なりと云ふ)地蔵二軀(一は鐡佛、長一尺許、門前の井中より出現せしと云ふ、一は弘法作、長一尺七寸)大黒(長尺許傳作)大日(長八寸許)賓頭盧(長三尺已上弘法作)等の像を置く、又頼朝の木像あり(長八寸許四十二歳の自作と云ふ)鏡の御影と称せり、同位牌あり 征夷将軍二品幕下神儀とあり文覺の書と云ふ)開山文覺の牌もあり(開山権僧正法眼文覺尊儀とあり)
【寺寶】
八幡画像一幅 束帶にて袈裟をかけ、數珠を持しむ、冠より一寸ばかり上に、日輪を畫
寶満菩薩像一幅 應神帝の姨にて、見目明神と称すとなり
卓圍(祭壇布)一張 頼朝の寄附にて、平家調伏の打敷(仏壇の荘厳具)と云ふ、孔雀鳳凰の繍文あり
旗一流 平家赤旗と称し、文字は相國清盛の筆と傳ふ(中略)
牛頭天王見目明神合社 大道寺源六周勝社領二貫三百文及び寺内修補の料を寄附せし事所蔵文書に見えたり
住吉社
鐘楼蹟
𦾔観應年間の古鐘あり。兵乱の為に亡失せしを後松岡ヶの農民地中より掘出し同所東慶寺に収むと云ふ。今尚あり。
■ 『鎌倉市史 社寺編』(鎌倉市)(抜粋)
南向山帰命院補陀落寺と号する。古義真言宗。もと京都仁和寺末。のち青蓮寺末。現在京都大覚寺末。開山は文覚上人、開基は源頼朝と伝える。後、鶴岡八幡宮供僧頼基が中興した。
本尊、十一面観音。もとの本尊は薬師如来。日光・月光、ほかに不動明王あり。
境内地163坪。本堂・門・庫裏あり。(中略)
開基は仏乗坊の八代及び十代で、建武三年六月に還補されているから、この寺の鐘ができた観応元年(1350年)には供僧であったこととなる。(中略)
『新編鎌倉志』は鐘銘及び寺号によって、本尊は観音であったはずであるといっている。
従うべきであろう。(中略)
当寺が頼朝と関係があることは前述の勧進帳に見えるのを初見とするが(中略)頼朝の供養をここですることになっていたらしい。(中略)
明治初年の火災で殆ど烏有に帰したが、その時誰も出した覚えがないのに、仏像類は全部無事であったという。大正十二年震災で全壊し、現在の本堂は大正十三年の建立である。
-------------------------
材木座の巨刹、光明寺にもほど近い住宅街にあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 石碑
山内入口に門柱で、その手前に「源頼朝公御祈願所●●補陀落寺」と彫られた石碑があります。


【写真 上(左)】 門柱
【写真 下(右)】 山内
山内は広くはないですが閑雅な落ち着きがあり、「荒法師開山」のイメージはあまりありません。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 寺号板
本堂はおそらく切妻造桟瓦葺平入りで、右手に寄せて流れ向拝を置いています。
向拝の柱や虹梁はシンプルですが、向拝柱に寺号標を掲げています。


【写真 上(左)】 庫裏への道
【写真 下(右)】 同 紫陽花
御朱印は庫裏にて拝受しました。
鎌倉三十三観音霊場、相州二十一ヶ所霊場、新四国東国八十八ヶ所霊場いずれの御朱印も拝受していますが、現況の授与状況は不明です。
〔 補陀落寺の御朱印 〕


【写真 上(左)】 弘法大師の御朱印(ご縁日)
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

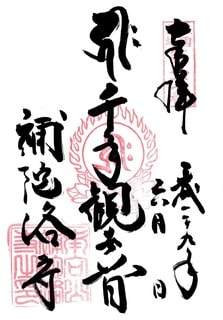
【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印
【写真 下(右)】 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印
44.円龍山 向福寺(こうふくじ)
公式Web
鎌倉市材木座3-15-13
時宗
御本尊:阿弥陀三尊
司元別当:
札所:鎌倉三十三観音霊場第15番
向福寺は一向俊聖上人開山と伝わる時宗寺院です。
公式Web、下記史料・資料、現地掲示から縁起沿革を追ってみます。
向福寺は弘安五年(1282年)、開山を一向俊聖上人として創建されました。
一向俊聖上人(1239年?-1287年?)は、鎌倉時代の名僧で時宗一向派の祖です。
儀空菩薩とも呼ばれます。
「新纂 浄土宗大辞典」および「Wikipedia」を参考にその足跡を追ってみます。
伝承によれば、筑後国竹野荘西好田(福岡県久留米市)の御家人草野永泰の次男として生まれたといいます。
永泰の兄草野永平は浄土宗鎮西派の聖光上人(弁長)に帰依し、建久三年(1192年)に久留米善導寺を建立した大檀越でした。
寛元三年(1245年)、播磨国書写山圓教寺に入寺して天台教学を志し、建長五年(1253年)に剃髪受戒して名を俊聖としました。
翌年夏に書写山を下り、奈良興福寺などで修行されるも悟りを得られず、鎌倉蓮華寺(光明寺)の然阿良忠上人の門弟となりました。
一向専念の文より号を一向と改め、文永十年(1273年)から各地を念仏聖として遊行回国し、踊り念仏(踊躍念佛)、天道念仏(天童念佛)を修して道場を設けました。
後年は遊行と踊り念仏で民衆を教化し、弘安一〇年(1287年)11月、近江国番場蓮華寺(滋賀県米原市)で立ち往生したと伝わります。
俊聖上人の教えは時宗一向派(天童派)として各地に広く伝わったため伝承も多く、ナゾの多い僧ともいわれます。
実在していないという説さえありましたが、近年山形県天童市の高野坊遺跡より出土した墨書の礫石経により、その実在が立証されています。
ただし、法統については諸説あり、浄土宗鎮西義の然阿良忠上人のほか、浄土宗西山深草派西山三派の祖・証空門下の顕性に師事したという説もあります。
一向俊聖上人を祖とする(時宗)一向派は時宗十二派の一つで、番場時衆、時宗番場派とも呼ばれ、本山は番場蓮華寺(滋賀県米原市)です。
「一向派」の呼称は、元禄一〇年(1697年)成立の時宗触頭・浅草日輪寺吞上人著の『時宗要略譜』が初見とされます。
『一向上人血脈譜』によると、上人には「十五戒弟」と称する弟子があり、東北、関東、甲信越を中心に布教をすすめて全盛期には末寺一七四箇寺を数えたといいます。
とくに山形県天童市の仏向寺は一向俊聖上人開山で、番場蓮華寺とならぶ中心寺院となっています。
江戸幕府の宗教政策により時宗遊行派の傘下に編入され、派内の本末論争などもあって衰勢となりました。
当初「一向宗」とし、江戸時代に「時宗」に吸収されたとする資料もみられます。
「新纂 浄土宗大辞典」には、明治36年時宗内で一向派の立場を認める『時宗宗憲宗規』が制定されましたが、昭和16年の一宗一管長制により、翌17年には一向派97箇寺中57箇寺が時宗より浄土宗に転宗、残る41箇寺は時宗にとどまったとあります。
向福寺は、おそらく時宗一向派(あるいは一向宗)から時宗となった寺院のひとつとみられます。
公益財団法人住友財団の公式Webによると、御本尊の阿弥陀三尊木像は中世(現地掲示資料では南北朝時代)作。檜材、割矧ぎ造ないし寄木造りで玉眼を嵌入しています。
脇侍の観世音菩薩、勢至菩薩とともに鎌倉市指定文化財に指定されています。
また、『鎌倉札所巡り』(メイツ出版)・現地掲示によると、当山本堂南側の部屋は、『丹下左膳』で知られる作家・林不忘(長谷川海太郎、1900年-1935年)が関東大震災前に新婚生活を送ったところです。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(乱橋村)向福寺
圓龍山と号す 本寺前に同じ(藤澤清浄光寺末) 本尊三尊彌陀を安ず 各立像、安阿彌作
■ 山内掲示(鎌倉市)
公式Webと重複するため略。
■ 『鎌倉市史 社寺編』(鎌倉市)(抜粋)
円龍山向福寺と号する。時宗。藤沢清浄光寺末。
開山、一向。
本尊、阿弥陀如来。
境内地229.7坪。本堂兼庫裏あり
『大正三年明細書』によれば文政九年に再建した本堂・表門があったが、大正大震災で全潰した。今の本堂は昭和五年の再建である。
-------------------------
小町大路「水道路」交差点から少し南下した右手の路地沿いにあり、あまり目立ちません。
門柱に「時宗 向福寺」となければ、ほとんど民家にしか見えません。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 門柱の寺号標
山内は緑が多く、植木鉢もきれいに並べられています。
参道正面の本堂は入母屋造銅板で身舎右手に向拝を附設しています。
本堂は庫裏とつながり、一見寺院建築のイメージはあまりありません。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 本堂
向拝は水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板本蟇股を置いています。
ここまでくるとさすがに寺院本堂の存在感があります。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 観音霊場の札所板
ガラス格子の扉のうえに鎌倉三十三観音霊場の札所板を掲げています。
文政九年(1826年)再建の本堂は大正の関東大震災で全潰し、いまの本堂は昭和五年の再建とのことですが、そこまで古びた感じはないので手を入れられているかもしれません。
観音堂はなく、本堂向拝に札所板が掲げられているので、鎌倉三十三観音霊場第15番の札所本尊・聖観世音菩薩立像は、御本尊の阿弥陀三尊とともに本堂内に奉安とみられます。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
御本尊と鎌倉三十三観音霊場の御朱印を授与されています。
〔 向福寺の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御本尊・阿弥陀如来の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-15 (B.名越口-10)へつづく。
【 BGM 】
■ Hearts - Marty Balin
■ If I Belive - Patti Austin
■ Late At Night - George Benson Ft. Vickie Randle
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-13 (B.名越口-8)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)から。
40.隨我山 来迎寺(らいこうじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-9-5
時宗
御本尊:阿弥陀如来(弥陀三尊)
司元別当:
札所:鎌倉三十三観音霊場第14番
鎌倉には来迎寺を号する時宗の寺院がふたつあります。
ふつう満光山 来迎寺を「西御門来迎寺」、隨我山 来迎寺を「材木座来迎寺」と呼んで区別しているようです。
来迎寺は材木座の氏神とされる五所神社の並びにある時宗寺院です。
公式Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
来迎寺は建久五年(1194年)、源頼朝公が鎌倉幕府開創の礎石となった三浦大介義明の冥福を祈るため、真言宗能蔵寺を建立したのが創始とされますが、草創時の開山は不明です。
頼朝公亡きあと、音阿上人が開山となり時宗に改宗して来迎寺と号を改めました。
境内には三浦義明の木造と、義明および多々良重春(一説には義明夫婦)の二基一組の五輪塔墓があり、本堂裏手には三浦一族の墓とされる百基あまりの五輪塔や寶篋印塔が並びます。
多々良重春は石橋山の戦いで戦死した武将で、三浦義明の孫ともいいます。
御本尊は阿弥陀如来(弥陀三尊)で、三浦義明の守護佛と伝わります。
鎌倉三十三所観音霊場第14番札所としても知られ、札所本尊は「子育て観音」。
この観音様に念ずれば、必ず智恵福徳円満な子供を授かるとして、古来から尊崇を集めました。
以前は当山本堂裏側の山頂に観音堂がありましたが、昭和十一年、軍事的な理由から国の指令により取り壊されたといいます。
従前の観音堂は鎌倉市街を隔て、長谷観音と相対していたといいます。
当山は明治五年十二月の材木座発火の類焼に遭い寺宝はことごとく消失したといいます。
よって『新編相模国風土記稿』にある「宗祖一遍上人像、三浦義明の像」は現存しません。
三浦氏については「鎌倉殿の13人」と御朱印-6/37.岩浦山 福寿寺にまとめているので転記します。
三浦氏は桓武平氏良文流(ないし良兼流)で、神奈川県資料『三浦一族関連略系図』によると、高望王の子孫・為通が村岡姓を三浦姓に改め、為継、義継、義明と嗣いでいます。
三浦大介義明は三浦郡衣笠城に拠った武将で三浦荘の在庁官人。
”三浦介”を称して三浦半島一円に勢力を張りました。
三浦氏は、千葉氏・上総氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏とともに「坂東八平氏」に数えられる名族です。
義明の娘は源義朝公の側室に入ったとされ、義朝の子・義平が叔父の義賢と戦った「大蔵合戦」でも義朝・義平側に与しました。
(義平公の母が義明の娘という説もあり)
このような背景もあってか、治承四年(1180年)の頼朝公旗揚げ時には当初から一貫して頼朝公側につき、次男の義澄率いる三浦一族は加勢のため伊豆に向けて出撃するも、大雨で酒匂川を渡れず石橋山の戦いには参戦していません。
衣笠城への帰途、三浦軍は由比ヶ浜~小坪辺で畠山軍と遭遇し、畠山を撃退しました。
しかし、衣笠城に帰参してほどない治承四年(1180年)8月26日、畠山重忠・河越重頼・江戸重長らの秩父一族に攻められ、子の義澄以下一族を安房に逃した後、義明は奮戦むなしく討ち死にしました。(衣笠城合戦)
『吾妻鏡』によると、義明は「我は源氏累代の家人として、老齢にしてその貴種再興に巡りあうことができた。今は老いた命を武衛(頼朝公)に捧げ、子孫の手柄としたい。」と言い遺し、従容として世を去ったといいます。ときに齢89歳。
三浦義明の娘は畠山重能の正室といいますが、子に恵まれず江戸重継の娘を側室として重忠ら兄弟を生み、嫡男の重忠は義明の娘の養子となったという説があります。
(論拠は『源平盛衰記』が三浦義明が重忠を「継子孫」と呼んでいること。)
一方、三浦義明は実孫の畠山重忠に討たれたという説もあり、このあたりははっきりしません。
頼朝公は、老躯をおして秩父一族に対抗し討ち死にした三浦義明の功績を高く評価し、義明を称えたといいます。
頼朝公が衣笠の満昌寺で義明の十七回忌法要を催した際、「義明はまだ存命し加護してくれているのだ」と宣ったといい、戦死したときの89歳に回忌17年を加えた106から、義明は後に「三浦大介百六ツ」と呼ばれることとなります。
義明の犠牲により落ち延びた三浦一族は安房国で頼朝勢に合流、千葉常胤・上総介広常などの加勢を得て頼朝公は再挙し、10月に武蔵国へ入ると、畠山重忠・河越重頼・江戸重長ら秩父一族は隅田川の長井の渡で頼朝公に帰伏しました。
『吾妻鏡』には、三浦氏総領・義明のかたきである秩父一族の帰順に強く抵抗する三浦一族を、頼朝公みずからが説得したという記述があります。
三浦義明の長男・杉本義宗の子は和田義盛で侍所別当。
次男・三浦義澄は三浦氏を嗣ぎ、他の子息も大多和氏、佐原氏、長井氏、森戸氏などを興し、また重鎮・岡崎義実は義明の弟で、三浦党は一大勢力となりました。
三浦義澄は源平合戦でも武功を重ね、建久元年(1190年)頼朝公上洛の右近衛大将拝賀の際に布衣侍7人に選ばれて参院供奉、頼朝公逝去後には「十三人の合議制」の一人となり幕政でも重きをなしました。
義澄の子の義村は希代の策士ともいわれ、鎌倉幕府内で重要なポジションを占めましたが、このあたりの経緯については、「鎌倉殿の13人」と御朱印-6/37.岩浦山 福寿寺をご覧くださいませ。
しかし北条氏の専制強化には地位も実力もある三浦氏の存在は邪魔だったとみられるわけで、じっさい義村亡きあとの宝治元年(1247年)6月5日の「宝治合戦」で、三浦一族は北条氏と外戚安達氏らによって滅ぼされています。
三浦一族の流れとしては、三浦義明の七男・佐原義連から蘆名(芦名)氏が出て会津で勢力を張り、戦国期に伊達氏と奥州の覇を競いました。
来迎寺は、鎌倉幕府創建の大功労者ともいえる三浦大介義明の偉業を伝える貴重な寺院といえましょう。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(亂橋村)来迎寺
随我山と號す、時宗 藤澤清浄光寺末、開山一向 建治元年寂すと云ふ
本尊三尊彌陀を安ず 中尊、長二尺左右各長一尺五寸、共に運慶作、三浦大介義明の守護佛と云ふ、宗祖一遍の像あり、又三浦義明の木像を置く
三浦義明墓 五輪塔なり、義明は庄司義繼が長子なり、治承四年八月衣笠に於て自盡す、今三浦郡大矢部村(衣笠庄に属す)即義明自盡の所と伝ふ
建久年中義明が追福の為頼朝其地に一寺を創立して満昌寺と号せり、其域内に義明が廟あり尚彼寺の條に詳なり、此に義明の墳墓ある其縁故を知らざれど思ふに冥福を修せんが為寺僧の造立せしならん
■ 山内掲示(当山)
時宗来迎寺縁起
時宗来迎寺の開基は、建久五年(一一九四年)源頼朝が己の鎌倉幕府の基礎となった三浦大介義明の霊を弔う為、真言宗能蔵寺を建立したときに始まる。(能蔵寺の名は、この付近の地名として使われていた) 尚、開山上人は明らかでない。
おそらく頼朝が亡くなった後、現在の「時宗」に改宗したと思われるが改宗年代は不詳である。山院寺号を随我山来迎寺と号し、音阿上人(当時過去帳記載)が入山以降法燈を継承している。能蔵寺から起算すると実に八百余年の歴史がある。
時宗の総本山は神奈川県藤沢市西富、藤沢山清浄光寺、通称遊行寺と呼ばれている。開祖は一遍上人、今から七百年余り前文久十一年(一二七四年)熊野権現澄誠殿に参籠、熊野権現から夢想の口伝を感得し、「信不信浄不浄を選ばず、その札を配るべし」の口伝を拠り處に、神勅の札を携え西は薩摩から東は奥羽に至るまで、日本全国津々浦々へ、念仏賦算の旅を続けられること凡そ十六年。その間寺に住されることなく亡くなるまで遊行聖に徹した。
教法の要旨は『今日の行生座臥擧足下足平生の上を即ち臨終とこれを心得称名念仏する宗門の肝要となすなり』とある「念仏によって心の苦しみや悩みは、南無阿弥陀仏の力で救ってくださる」という教えである。
当寺の本尊阿弥陀如来(弥陀三尊)は三浦義明の守護佛と伝えられる。(中略)
鎌倉三十三観音札所十四番で子育て観音をおまつりしてある。
この観音様に念ずれば、必ず智恵福徳円満な子供を授かるとして、昔から多くの信者に信仰されている。以前、当寺の山頂(本堂裏側の山頂)にこの観音堂があったが昭和十一年、国の指令により「敵機の目標になるから」という理由で、取り壊された。鎌倉旧市街および海が一望でき、長谷観音と相対していた。
当山は明治五年十二月二十一日夜、材木座発火の類焼に遭い寺寶はことごとく消失してしまった。「相模風土記」によると「宗祖一遍上人像、三浦義明の像有り」とあるが現存しない。(中略)
当山四十五代照雄和尚の徳により三浦義明の像並びにこれ御安置する御堂を建立、昭和三十五年五月、義明七百八十年忌にあたり一族と共に供養した。(この義明像は三浦一族に由縁のある彫刻家鈴木国策氏の献身的な奉仕によって見事制作されたものである)
しかし、この御堂も諸般の事情により取り壊した。将来境内整備が終わりしだい再建する予定である。
境内には義明公および多々良三郎重春公の五輪塔(高さ二米)一説には義明公夫婦ともいわれている。また応永、正長年銘などの寶篋印塔(数基鎌倉国宝館に貸し出し展示中)ありこの数七百余基を数える。
「相模風土記」によれば、「三浦義明の墓は五輪塔なり、ここに義明の墳墓あるはその縁故知らざれど、思うに冥福を修せんがために寺僧が造立せしならん」とある。
義明は庄司義継の長男で平家の出で、平家の横暴腐敗した政治を正すため、源氏に仕え、時の世人挙げて平家に従ったが、ただ一人敢然として頼朝に尽力した。
治承四年(一一八〇年)頼朝の召に応じて子義澄を遣わしたが、石橋山の敗戦で帰郷の途次、畠山重忠の軍を破った為、重忠らに三浦の居城衣笠城を包囲された。
防守の望みを失ったので、義澄らの一族を脱出させて頼朝のもとに赴かせひとり城に留まって善戦したが、ついに陥落して悲壮な最期を遂げ、源氏のために忠を尽くした。
一方石橋山の戦いで平家に敗れた頼朝は、海路安房に渡って再挙を図り、関東各地の源氏家人の加勢を得、義澄と共に鎌倉に拠って策源地と定めた。
後、征夷大将軍となり鎌倉幕府を創建したのである。
この国家大業の成就の陰には義明の先見の叡智と偉大な人徳によるところただい(多大?)である。義明あって鎌倉幕府の成否は義明によって決したと断ずるも過言でない。
後に頼朝が義明あるいは一族に対する報謝の意が実に数々の温情の行業に伺われる。
義明が後に「三浦大介百六ツ」と呼ばれる由来は頼朝が衣笠の満昌寺において、義明の十七回忌法要を供養したとき、義明がまだ存命して加護していてくれるのだ。という心からの事で自刃したときの八拾九歳と十七年を加えた数と思われる。
私たちは、このような幾多の先祖の偉業、遺徳を懇ろに偲び、人生の心の糧として、何時までもこの行跡をたたえ続けて行きたいものである。
■ 『鎌倉市史 社寺編』(鎌倉市)(抜粋)
隨我山来迎寺と号する。時宗。藤沢清浄光寺末。
開山、音阿 本尊、阿弥陀三尊
境内地258.55坪。
本堂兼庫裏、来迎寺幼稚園あり
ここはもと真言宗能蔵寺の旧蹟と伝える。
本尊は三浦大介義明の守本尊であるといい、境内に義明及び多々良三郎重春の分骨を葬ってあるという。
-------------------------
鎌倉駅構内の観光客の動線をみると、多くの客は東口に出て小町通りを北上し、鶴岡八幡宮方面か、扇ヶ谷 or 源氏山方面へ向かいます。
東口から南方向の本覚寺、妙本寺、八雲神社、安養院、妙法寺、安国論寺方面へ向かう人はどちらかというと中~上級者(?)で数は多くなく、さらに横須賀線を渡って材木座方面まで足を伸ばす人はかなり少なくなります。
しかし、材木座界隈には寺社が多くほとんどが御朱印、御首題を授与されているので、隠れた御朱印エリアとなっています。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 札所標と墓碑
来迎寺もそんな材木座の一画にあります。
周囲は真新しい住宅街ですが、山内に足を踏み入れると俄然しっとりとした鎌倉寺院の趣が出てくるという、面白いロケーションです。
参道入口に観音霊場札所標と三浦義明の墓碑。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 寺号標
参道途中から石畳となり、寺号標が建っています。
参道正面が本堂、左手が庫裏、右手に回り込むと三浦義明の墓所(五輪塔墓)です。


【写真 上(左)】 墓所への案内
【写真 下(右)】 五輪塔墓


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂と庫裏
本堂はおそらく宝形造で桟瓦葺流れ向拝です。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股を置き、身舎左右には大ぶりの花頭窓。
水引虹梁は朱を散りばめた、変化のある意匠です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 札所板
向拝見上には鎌倉観音霊場の札所板が掲げられています。

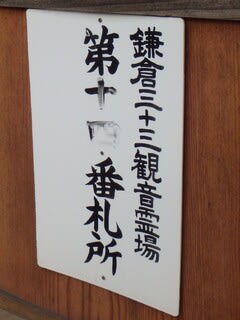
【写真 上(左)】 観音像
【写真 下(右)】 札所案内
堂前向かって右手前にある胸像は、すみませんよくわかりません。
山内には白衣でおだやかな面差しの観音立像も安置されていました。
御朱印は庫裏にて拝受しましたが、ご不在の場合もあるようです。
〔 来迎寺の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
41.五所神社(ごしょじんじゃ)
公式Web
神奈川県神社庁Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-9-1
御祭神:大山祇命、天照大御神、素盞嗚命、建御名方命、崇徳院霊
旧社格:村社、材木座の氏神
元別当:南向山 補陀落寺(鎌倉市材木座) 旧・諏訪神社の別当
五所神社は「材木座の氏神」と親しまれる、地域を代表する神社です。
公式Web 、下記史料・資料、境内掲示などから縁起沿革を追ってみます。
もともとこの地は材木座村でしたが、乱橋(みだればし)村と材木座(ざいもくざ)村に分村しました。
明治22年、両村が合併して西鎌倉郡乱橋材木座(鎌倉郡西鎌倉村ないし東鎌倉村の一部とも)となりました。
境内掲示によると、合併以前から両村には下記の神社が鎮座されていました。
・三島神社 御祭神 大山祇命
現社地、乱橋村の鎮守社、旧村社
・八雲神社
現・材木座4-4-26公会堂内、乱橋村龍蔵寺(能巌寺)部落、三島神社の相殿?
・金比羅宮(金刀比羅社) 御祭神 金山彦命
現・材木座4-7-2竹内宅裏山「普賢象山」、乱橋村
・諏訪神社 御祭神 建御名方命
現・材木座5-13-8山ノ上方、材木座の鎮守、補陀落寺持
・視女八坂社(見目明神・見目天王、牛頭天王、見目明神社合社)
現・材木座6-7-35、材木座村仲島部落、補陀洛寺の鎮守?
『新編相模国風土記稿』には「(亂橋村)三島社 村持」「(材木座村)諏訪社 補陀落寺持」の記載がみえます。
見目明神は、三島大社の摂社として知られています。→ 三島市Web資料
御祭神は三嶋大社の御祭神・事代主神のお妃六柱です。
こちらの視女八坂社(見目明神)も、乱橋村鎮守の三島神社となんらかの関係があるのかもしれません。
『鎌倉市史 社寺編』では、五社神社に合祀の見目明神は『補陀洛寺文書』に見目天王分としてみえることから、古くから補陀洛寺の鎮守であったとみています。
また、『新編鎌倉志』の補陀落寺の項には「寺寶 寶満菩薩像 壹軀 八幡の姨なり。鶴岡にもあり。社家にては見目明神(ミルメ)と云ふ。」とあり、見目明神の本地が寶満菩薩であることを示しています。
寶満(宝満)菩薩は、太宰府の宝満山が有名です。
「文化遺産オンライン」には「(宝満山)は八幡信仰と融合し、宮寺として社寺一体となり」「中世には宝満山とも呼ばれ、宝満大菩薩という仏神となり、英彦山修験道と結合して英彦山の胎蔵界に対し、金剛界の行場として、修験の山となった。」とあり、寶満(宝満)菩薩と八幡神、修験道との関係を示しています。
また、境内の「板碑(石造板塔婆)」は廃寺となった乱橋村の感應寺から遷されたとの説明があります。
由比山寶幢院感應寺は、真言宗京都三寶院末でした。
三寶院は真言宗系修験道「当山派」の本寺ですから、旧・感應寺から当山修験の流れが五社神社に引き継がれたのかもしれません。
明治41年、三島神社に四社を合祀して五所神社と改称しました。
合祀時に旧・諏訪神社の社殿を移築した本殿は、関東大震災の土砂災害で倒壊したため昭和6年に新築されました。
五所神社はいまも材木座の氏神として尊崇され、三基の神輿が渡る例祭は鎌倉の風物詩として広く知られています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
補陀落寺 寺寶 寶満菩薩像 壹軀
八幡の姨なり。鶴岡にもあり。社家にては見目明神(ミルメ)と云ふ。
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(亂橋村)
三島社 村持
(材木座村)
諏訪社 補陀落寺持
(亂橋村)
感應寺
由比山寶幢院と号す、真言宗京都三寶院末 不動を本尊とし、神変菩薩理源大師の像あり、中興を養源と云ふ 境内に倶利迦羅竜王の古碑あり
■ 神奈川県神社庁Web資料
五所神社
当社鎮座地は、古くは乱橋村と材木座村とに分かれていた。乱橋村には三島神社、八雲神社、金刀比羅社の3社が鎮座し、材木座村には諏訪社と視女八坂社の2社が鎮座していた。明治初年に村が合併し、乱橋材木座村となった。相模風土記稿に「三島社村持」とある如く、村の中心的社であったので明治6年、村社に列格された。
明治41年に他の四社が合祀され、五所神社と改称された。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
五社神社
祭神、大山祇命、天照大御神、素盞嗚命、建御名方命、崇徳院霊。
例祭七月七日。元指定村社。乱橋材木座の鎮守。境内地163.09坪。
覆殿、社殿、神輿庫あり。現在の社殿は昭和六年七月の新築。
現在の神社は明治四十一年七月、乱橋村と材木座村が合して、東鎌倉村大字乱橋材木座となったとき、乱橋村の鎮守三島神社の地に材木座村の鎮守諏訪神社・乱橋村能蔵寺部落の八雲神社・金比羅宮・材木座村中島部落の見目明神の四社を合わせ、同年十一月、五所神社と改称したものである。もとの五社はいずれも勧請年月不明。
このうち、見目明神は補陀洛寺文書に見目天王分として二貫三百文の地を北条氏康が同寺に寄進しているから、古くから同寺の鎮守であったと思われる。
『新編鎌倉誌』には見目明神とよんだ宝満宮菩薩像があったことがみえ、『風土記稿』には牛頭天王、見目明神社合社とある。
三島神社は、乱橋村持(『風土記稿』)で八雲社を相殿とし、この相殿天王の神輿棟札によれば、寛永十九年(1642年)修造以後、延宝九年(1681年)元禄十一年(1698年)元文二年(1737年)宝暦十三年(1763年)に修理を加え、万延元年(1860年)に再建している。(中略)
境内に昭和十六年重要美術品に認定された板碑がある。
境内坪数二八0坪で、もとの本殿は明治十六年七月建立の諏訪神社本殿を合併後移築したものであったが、震災の時山崩れのため社殿埋没全壊した。
■ 境内掲示
五所神社
祭神 天照大御神、素盞嗚命、大山祇命、建御名方命、崇徳院命
明治二十二年(一八八八)乱橋村と材木座村が合併して西鎌倉村大字乱橋材木座となった後明治四十一年(一九〇八)七月に、もとの乱橋村の鎮守”三島神社”(現在の地)の地に材木座の鎮守、諏訪神社(現材木座五-十三-八 山ノ上方)乱橋村龍蔵寺部落の八雲神社(現材木座四-四-二六 公会堂内)、金比羅宮(材木座四-七-二 竹内宅裏山「普賢象山」中腹)、材木座村仲島部落の見目明神 材木座六-七-三五)の四社を合併して五所神社として改名したものである。
もとの五所はいずれも勧請年月不詳このうち見目明神は補陀洛寺文書に見目天王文と二貫三百文の地を北条氏康が同時に寄進しているから古くから同寺の鎮守であったと思われる。
「新編鎌倉誌」には、見目明神とよんだ宝満宮菩薩像があったとみえ「風土記稿」には牛頭天王、見目明神社合社とある。
三島神社は、乱橋村持「風土記稿」で八雲社を相殿とし、この相殿天王みこし棟札によれば、寛永十九年(一六四二)修造以後、延宝九年(一六八一)元禄十一年(一六九八)元文二年(一七三七)宝暦十三年(一七六三)に修理を加え、万延元年(一八六〇)に再建している。
諏訪社は補陀洛寺であった「風土記稿」明治八年(一八七五)公達に基づいての皇国地誌調査さんによると次の通り記載されている。
三島社
式外村社々地東西四間南北六間三尺面積二六坪の東方にアリ大山祇命ヲマツル。
勧譜年暦詳ナラス 例祭四月 十一月ノ酉ノ日ヲ用ウ
見目社
同社東西九間南北八間四尺八寸面積七九坪村ノ東西間ニアリ祭神及ビ創造勧譜年暦詳ナラス 例祭二月二七日 六月七日両回トス
諏訪社
同社東西八間一尺二寸南北一間六寸面九坪村のノ南方ニアリ祭神建御名方命勧譜年暦詳ナラス 例祭六月七日 七月二七日ノ二回トス
金比羅社
同社東西十間南北七間面七十坪村ノ辰ノ方ニアリ祭神金山彦命勧譜年暦詳ナラス 例祭十月十日
現在の社殿は昭和六年(一九三一)七月に新築されたものである。
もとの本殿は明治一六年(一八八三)七月諏訪神社の本殿を合併後、移建したものであったが大正十二年(一九二三)九月一日震災のとき山崩れのため社殿埋没全潰した。
お神輿三基
一号 諏訪神社 二号 三合(ママ) 見目明神の持ち物であった。
祭礼、潮祭り 一月十一日 春季小祭 四月十五日 秋季小祭 十一月二十四日
例大祭 七月七日から十四日
現在の祭礼(抜粋)
例大祭 六月第二日曜日 三ツ目神楽 例大祭三日目(火曜日)
-------------------------
名越・朝比奈方面からつづく鎌倉東部の山地は、材木座・光明寺の裏手から大町、小町と北にかけて連なり、西向きの山裾を大蔵あたりまで落としています。
この山裾は鎌倉有数の寺社の集積エリアで、五社神社もこの山裾に当たります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 参道-1
来迎寺と実相寺の中間くらいに路地に面して社頭があります。
参道右手に社号標、その先に藁座を置いた神明鳥居?。
鳥居は本殿手前の石段前に置かれていましたが、関東大震災で倒壊破損したため昭和9年に社頭に移設されたものです。
参道は鳥居から真っ直ぐに伸びていますが、かなり奥行きがありここから拝殿は見えません。


【写真 上(左)】 狛犬-1
【写真 下(右)】 狛犬-2
すぐ先に石灯籠一対と真新しい狛犬一対。
さらに進んだ古い狛犬一対は、大正5年に材木座三丁目の地主ら十三名が寄進したものとのこと。


【写真 上(左)】 参道-2
【写真 下(右)】 参道-3
さらに行くと数段の石段で、ここまでくると参道階段の上に社殿が見えてきます。
社殿下の階段左脇に社務所があり、御朱印はこちらで授与されています。
あたりはうっそうとした木々に囲まれ、山里の神社のようです。
参道階段をのぼった正面、切妻造の建物は神輿庫(天王堂)で、庫内にはきらびやかな三基の神輿が安置されています。


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 神輿庫(天王堂)
公式Webには「向かって右手より一番様(旧諏訪神社 江戸末期建造・鎌倉市指定有形民俗文化財)、二番様(旧牛頭天王社 弘化四年(1847)建造)、三番様(旧見目明神社 弘化四年(1847)建造)」とあります。
三基の神輿のお渡りをはじめ、数々の見どころがある五社神社の祭礼は、鎌倉の風物詩としてよく知られています。


【写真 上(左)】 神輿
【写真 下(右)】 拝殿
神輿庫(天王堂)前を左に直角に曲がった正面が拝殿です。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、軒唐破風を張り出し、妻側千鳥破風に経の巻獅子口を置き、寺院建築のイメージ。


【写真 上(左)】 拝殿妻側
【写真 下(右)】 拝殿向拝-1


【写真 上(左)】 拝殿向拝-2
【写真 下(右)】 中備の彫刻
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻、その上に兎の毛通しと、こちらにも経の巻獅子口を置いています。
彫刻類はいずれも重厚感を備えたすばらしい出来です。
向拝見上の扁額には「国家興隆」とあり、鎌倉宮ゆかりのもののようです。
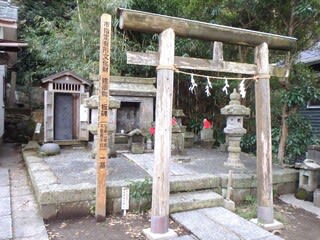

【写真 上(左)】 三光尊石上稲荷と板碑(石造板塔婆)
【写真 下(右)】 板碑
神輿庫右手の木の鳥居のおく、正面が三光尊石上稲荷、向かって左手が板碑(石造板塔婆)の覆屋です。
三光尊石上稲荷は、ふるくは豆腐川の河口に御鎮座といいます。
豆腐川は、材木座海岸に注ぐ短い川です。
お祀りされている石は「石上さま」といわれ、漁師の網を切ったり、船を転覆させたりと、いたずらをする石であったそうです。
陸に引き揚げられ、昭和9年、補陀洛寺第33世光照上人より名を授かり、昭和12年に石祠を建立、海上安全の守護神としてお祀りされています。
左手の板碑(石造板塔婆)は弘長二年(1262年)の銘。
倶利迦羅剣になぞらえた不動明王のお種子「カン/カーン」を蓮華座のうえに置く見事な板碑で、上部には天蓋も彫られています。
板碑の多くは秩父片岩ですが、この板碑は雲母片岩を用いて特徴的とのことで、市指定有形民俗資料に指定されています。
板碑の説明板に「昔は感應寺『修験真言宗、京都三宝院末」(材木座公会堂のある附近一帯)の境内に建っていたが、同寺が廃寺となったため五所神社創建の際ここに移されたのである。」とあります。
『新編相模国風土記稿』には「(亂橋村)感應寺 由比山寶幢院と号す、真言宗京都三寶院末 不動を本尊とし、神変菩薩理源大師の像あり、中興を養源と云ふ 境内に倶利迦羅竜王の古碑」とあり、もしかしてこの「倶利迦羅竜王の古碑」が五所神社の「板碑(石造板塔婆)」なのかもしれません。
鳥居の右よこには旧諏訪神社の古祠と、そのよこに大阪株式取引所(現・大阪取引所)の第二代頭取・吉田千足書の石碑があります。



【写真 上(左)】 旧諏訪神社の古祠
【写真 下(右)】 庚申塔
その右手には十数基の庚申塔と石佛。
庚申塔は乱橋村・材木座村両村の道端や辻にあったものを明治9年境内に集めてお祀りしたものとの由。
馬頭観音像のよこには、背後に十字架が置かれた「お春像」が安置されています。
公式Webには「『天和四』と掘られていることから一六八四年(徳川幕府五代将軍綱吉の初期の時代)一月から二月に造られたであろう石像と思われますが、その目的は未詳。その様子から隠れキリシタン殉教の像と伝えられています。」とあります。
神社の境内に十字架とは、かなりインパクトがありますが、このような歴史を伝える尊像です。


【写真 上(左)】 お春像
【写真 下(右)】 摩利支天像
さらにその右には大正2年奉納の「摩利支天像」。
摩利支天はもとは天竺(インド)の神格でしたが、仏教にとり入れられて守護神となりました。
三面六臂の丸彫りで椎型兜をかぶり、槍先が三つに割れた矛を握られたこのお姿の摩利支天像は、公式Webによると日本で十二体しか存在していないそうです。
境内には手玉石(かめ石)や疱瘡ばあさんの石、山岳信仰道場などもあります。
西向きの明るい境内ですが、どこかパワスポ的な陰りを感じるのは、修験や神仏混淆の歴史がもたらすものかもしれません。
御朱印は参道階段左手の社務所にて拝受しました。
〔 五所神社の御朱印 〕


42.弘延山 實相寺(じっそうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座4-3-13
日蓮宗:
司元別当:
札所:札所:
實相寺は宗祖嫡弟六老僧日昭尊者潜居の地とも伝わる日蓮宗の名刹です。
鎌倉市観光協会Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
實相寺は、日蓮宗六老僧の辨阿闍梨日昭(元享三年(1323年寂))が創建とされます。
日蓮聖人が佐渡へ流罪となった後も当地で布教を続け、伊豆の名刹・玉澤妙法華寺が移転する前の旧地といいます。


【写真 上(左)】 玉澤妙法華寺
【写真 下(右)】 同 御首題
またこの地は、鎌倉時代の武将・工藤祐経の屋敷跡で、日昭上人はその息女の子とも伝わります。
日昭上人が屋敷跡に法華堂を建てたのが創始といいます。
法華堂は法華寺と号して三島・玉澤に移り、元和七年(1621年)に日潤上人が再建とされます。
日昭上人はWikipediaによると俗姓を印東氏といい、晩年の日蓮聖人を池上に迎え、池上本門寺の基礎をつくった日蓮宗の有力檀越・池上宗仲と親戚関係にあったとも。
玉澤法華経寺公式Webによると、宗祖日蓮聖人の比叡山遊学中の学友ともいい、聖人に共鳴し、宗祖が鎌倉で法華経弘通を始められとすぐ最初の弟子となったとの由。
日蓮六老僧の一人に数えられ、日昭門流(濱門流・玉澤門流)の祖です。
現在の日昭門流の本山は、妙法華寺(三島市玉澤)と村田妙法寺(新潟県長岡市)で、その妙法華寺の旧地とあっては宗門上、重要な寺院とみられます。
工藤氏については■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2/14.稲荷山 東林寺でとりあげているので再掲します。
藤原南家の流れとされる工藤氏は、平安時代から鎌倉時代にかけて東伊豆で勢力を張り、当初は久須見氏(大見・宇佐見・伊東などからなる久須見荘の領主)を称したともいいますが、のちに伊東氏、河津氏、狩野氏など地名を苗字とするようになりました。
東伊豆における工藤(久須見)氏の流れは諸説あるようです。
いささか長くなりますが整理してみます。
工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の(滝口)祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)
他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)
伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。
(河津祐親→伊東祐親)
一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。
工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。
娘の八重姫が頼朝と通じ、子・千鶴丸をもうけたことを知った祐親は激怒し千鶴丸を殺害、さらに頼朝公の殺害をも図ったとされます。
このとき、頼朝公の乳母・比企尼と、その三女を妻としていた次男の祐清が危機を頼朝公に知らせ、頼朝公は伊豆山神社に逃げ込んで事なきを得たといいます。
なお、北条時政の正室は伊東祐親の娘で、鎌倉幕府第二代執権・北条義時は祐親の孫にあたるので、鎌倉幕府における伊東祐親の存在はすこぶる大きなものがあったとみられます。
工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すも効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。
安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。
祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。
伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東市の東林寺に入って出家しました。
治承四年(1180年)頼朝公が挙兵すると、伊東祐親は大庭景親らと協力して石橋山の戦いでこれを撃破しました。
しかし頼朝公が坂東を制圧したのちは追われる身となり、富士川の戦いの後に捕らえられ、娘婿の三浦義澄に預けられ、義澄の助命嘆願により命を赦されたものの、祐親はこれを潔しとせず「以前の行いを恥じる」といい、養和二年(1182年)2月、自害して果てたとされます。
河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。
建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。
工藤祐経の子・祐時は伊東氏を称し、日向国の伊東氏はその子孫とされています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(亂橋村)實相寺
弘延山と号す 豆州玉澤妙法華寺末 開山日昭 元享三年(1323年)三月廿六日寂す
本尊三寶を安ず
■ 山門掲示
當山ハ宗祖嫡弟六老僧第一辨大成辨阿闍梨日昭尊者潜居の地 宗祖佐渡流竄後門下僧俗を統率したる濱土法華堂(祖滅後法華寺と称す)乃霊跡にて玉澤妙法華寺の旧地也 傳フ工藤祐経邸趾と云ふ
日昭尊者濱土法華堂霊跡
御廟 裏山の麓にあり往古ハ峯の岩屋ニ有しを元禄三年現所ニ移せり
■ 玉澤妙法華寺公式Web
妙法華寺は、日蓮聖人の本弟子で六老僧第一の弁阿閣梨日昭上人が開創された寺である。
もと鎌倉の浜にあった法華寺がその前身であり、宗祖が日頃、日昭上人を浜殿と呼んでいたのは、この浜の地名によるものである。宗門としては最も初期の寺に属する。
当山の古記録によると、身延を除けば妙本寺第叫、法華寺第二と誌されている。この古い歴史と霊宝の聖人ご真筆、『宗祖説法御影』、調度品等が聖人の息吹を今に伝えている。
縁起
弘安7年(1284)12月、越後の風間信昭により、鎌倉の浜にあった日昭上人の庵室を寺としたのが起源である。
日昭上人は、宗祖の比叡山遊学中の学友であったが、聖人に共鳴し、宗祖が鎌倉で法華経弘通を始めるとすぐ最初の弟子となった。
鎌倉の浜土に草庵を構え、宗祖や他の門弟と共に教化活動を行い、その後、宗祖が身延に人山すると、日朗上人とともに鎌倉の日蓮教団の中心的役割を果たした。一門を日昭門流とか浜土門流と称し、近代は玉沢門流と呼んだ。(以下略)
■ 『鎌倉市史 社寺編』(鎌倉市)(抜粋)
弘延山 實相寺と号する。日蓮宗。伊豆玉澤妙法華寺の旧地。
開山、日昭。
本尊、一尊四士。
境内地405坪。
本堂・庫裏・山門あり。
日昭は元亨三年(1323年)三月廿六日寂。日昭は工藤祐経の女の生んだ子。この地は祐経の旧邸址と伝える。当寺の十一代日弘・十二代日南は関東管領扇ガ谷上杉氏の一族であるという。明治初年の大火で焼失した。
-------------------------
鎌倉材木座・五所神社の並びにあります。
由緒ある名刹ですが、やはり立地的に観光客の拝観は多くないと思われます。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 斜めからの山門
路地に面する山門は、門前にゆったりと空間をおき、二基のお題目塔(寺号標)を拝して落ち着いた名刹の風情。


【写真 上(左)】 寺号標-1
【写真 下(右)】 寺号標-2
山門は脇塀を巡らした切妻屋根桟瓦葺の薬医門かと思われますが、水引虹梁に四連の斗栱を拝して風格があります。
山門柱には「日昭尊者濱土法華堂霊跡」の表札で、由緒が記されています。


【写真 上(左)】 霊跡の札板
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 お題目塔
【写真 下(右)】 本堂
山内は数基のお題目塔はありますがすっきりシンプルで、参道正面が本堂です。
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、なだらかに照りを帯びる屋根の勾配が優美です。


【写真 上(左)】 向拝-1
【写真 下(右)】 向拝-2
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を置いています。
向拝・身舎ともに格子と桟をおき、端正なイメージの堂宇です。
御首題・御朱印は庫裏にて拝受しました。
〔 實相寺の御首題・御朱印 〕


【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-14 (B.名越口-9)へつづく。
【 BGM 】
■ Rina Aiuchi(愛内里菜) - Magic
■ 森高千里 - 渡良瀬橋
■ 今井美樹 - Goodbye Yesterday
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)
■ 同-12 (B.名越口-7)から。
40.隨我山 来迎寺(らいこうじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-9-5
時宗
御本尊:阿弥陀如来(弥陀三尊)
司元別当:
札所:鎌倉三十三観音霊場第14番
鎌倉には来迎寺を号する時宗の寺院がふたつあります。
ふつう満光山 来迎寺を「西御門来迎寺」、隨我山 来迎寺を「材木座来迎寺」と呼んで区別しているようです。
来迎寺は材木座の氏神とされる五所神社の並びにある時宗寺院です。
公式Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
来迎寺は建久五年(1194年)、源頼朝公が鎌倉幕府開創の礎石となった三浦大介義明の冥福を祈るため、真言宗能蔵寺を建立したのが創始とされますが、草創時の開山は不明です。
頼朝公亡きあと、音阿上人が開山となり時宗に改宗して来迎寺と号を改めました。
境内には三浦義明の木造と、義明および多々良重春(一説には義明夫婦)の二基一組の五輪塔墓があり、本堂裏手には三浦一族の墓とされる百基あまりの五輪塔や寶篋印塔が並びます。
多々良重春は石橋山の戦いで戦死した武将で、三浦義明の孫ともいいます。
御本尊は阿弥陀如来(弥陀三尊)で、三浦義明の守護佛と伝わります。
鎌倉三十三所観音霊場第14番札所としても知られ、札所本尊は「子育て観音」。
この観音様に念ずれば、必ず智恵福徳円満な子供を授かるとして、古来から尊崇を集めました。
以前は当山本堂裏側の山頂に観音堂がありましたが、昭和十一年、軍事的な理由から国の指令により取り壊されたといいます。
従前の観音堂は鎌倉市街を隔て、長谷観音と相対していたといいます。
当山は明治五年十二月の材木座発火の類焼に遭い寺宝はことごとく消失したといいます。
よって『新編相模国風土記稿』にある「宗祖一遍上人像、三浦義明の像」は現存しません。
三浦氏については「鎌倉殿の13人」と御朱印-6/37.岩浦山 福寿寺にまとめているので転記します。
三浦氏は桓武平氏良文流(ないし良兼流)で、神奈川県資料『三浦一族関連略系図』によると、高望王の子孫・為通が村岡姓を三浦姓に改め、為継、義継、義明と嗣いでいます。
三浦大介義明は三浦郡衣笠城に拠った武将で三浦荘の在庁官人。
”三浦介”を称して三浦半島一円に勢力を張りました。
三浦氏は、千葉氏・上総氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏とともに「坂東八平氏」に数えられる名族です。
義明の娘は源義朝公の側室に入ったとされ、義朝の子・義平が叔父の義賢と戦った「大蔵合戦」でも義朝・義平側に与しました。
(義平公の母が義明の娘という説もあり)
このような背景もあってか、治承四年(1180年)の頼朝公旗揚げ時には当初から一貫して頼朝公側につき、次男の義澄率いる三浦一族は加勢のため伊豆に向けて出撃するも、大雨で酒匂川を渡れず石橋山の戦いには参戦していません。
衣笠城への帰途、三浦軍は由比ヶ浜~小坪辺で畠山軍と遭遇し、畠山を撃退しました。
しかし、衣笠城に帰参してほどない治承四年(1180年)8月26日、畠山重忠・河越重頼・江戸重長らの秩父一族に攻められ、子の義澄以下一族を安房に逃した後、義明は奮戦むなしく討ち死にしました。(衣笠城合戦)
『吾妻鏡』によると、義明は「我は源氏累代の家人として、老齢にしてその貴種再興に巡りあうことができた。今は老いた命を武衛(頼朝公)に捧げ、子孫の手柄としたい。」と言い遺し、従容として世を去ったといいます。ときに齢89歳。
三浦義明の娘は畠山重能の正室といいますが、子に恵まれず江戸重継の娘を側室として重忠ら兄弟を生み、嫡男の重忠は義明の娘の養子となったという説があります。
(論拠は『源平盛衰記』が三浦義明が重忠を「継子孫」と呼んでいること。)
一方、三浦義明は実孫の畠山重忠に討たれたという説もあり、このあたりははっきりしません。
頼朝公は、老躯をおして秩父一族に対抗し討ち死にした三浦義明の功績を高く評価し、義明を称えたといいます。
頼朝公が衣笠の満昌寺で義明の十七回忌法要を催した際、「義明はまだ存命し加護してくれているのだ」と宣ったといい、戦死したときの89歳に回忌17年を加えた106から、義明は後に「三浦大介百六ツ」と呼ばれることとなります。
義明の犠牲により落ち延びた三浦一族は安房国で頼朝勢に合流、千葉常胤・上総介広常などの加勢を得て頼朝公は再挙し、10月に武蔵国へ入ると、畠山重忠・河越重頼・江戸重長ら秩父一族は隅田川の長井の渡で頼朝公に帰伏しました。
『吾妻鏡』には、三浦氏総領・義明のかたきである秩父一族の帰順に強く抵抗する三浦一族を、頼朝公みずからが説得したという記述があります。
三浦義明の長男・杉本義宗の子は和田義盛で侍所別当。
次男・三浦義澄は三浦氏を嗣ぎ、他の子息も大多和氏、佐原氏、長井氏、森戸氏などを興し、また重鎮・岡崎義実は義明の弟で、三浦党は一大勢力となりました。
三浦義澄は源平合戦でも武功を重ね、建久元年(1190年)頼朝公上洛の右近衛大将拝賀の際に布衣侍7人に選ばれて参院供奉、頼朝公逝去後には「十三人の合議制」の一人となり幕政でも重きをなしました。
義澄の子の義村は希代の策士ともいわれ、鎌倉幕府内で重要なポジションを占めましたが、このあたりの経緯については、「鎌倉殿の13人」と御朱印-6/37.岩浦山 福寿寺をご覧くださいませ。
しかし北条氏の専制強化には地位も実力もある三浦氏の存在は邪魔だったとみられるわけで、じっさい義村亡きあとの宝治元年(1247年)6月5日の「宝治合戦」で、三浦一族は北条氏と外戚安達氏らによって滅ぼされています。
三浦一族の流れとしては、三浦義明の七男・佐原義連から蘆名(芦名)氏が出て会津で勢力を張り、戦国期に伊達氏と奥州の覇を競いました。
来迎寺は、鎌倉幕府創建の大功労者ともいえる三浦大介義明の偉業を伝える貴重な寺院といえましょう。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(亂橋村)来迎寺
随我山と號す、時宗 藤澤清浄光寺末、開山一向 建治元年寂すと云ふ
本尊三尊彌陀を安ず 中尊、長二尺左右各長一尺五寸、共に運慶作、三浦大介義明の守護佛と云ふ、宗祖一遍の像あり、又三浦義明の木像を置く
三浦義明墓 五輪塔なり、義明は庄司義繼が長子なり、治承四年八月衣笠に於て自盡す、今三浦郡大矢部村(衣笠庄に属す)即義明自盡の所と伝ふ
建久年中義明が追福の為頼朝其地に一寺を創立して満昌寺と号せり、其域内に義明が廟あり尚彼寺の條に詳なり、此に義明の墳墓ある其縁故を知らざれど思ふに冥福を修せんが為寺僧の造立せしならん
■ 山内掲示(当山)
時宗来迎寺縁起
時宗来迎寺の開基は、建久五年(一一九四年)源頼朝が己の鎌倉幕府の基礎となった三浦大介義明の霊を弔う為、真言宗能蔵寺を建立したときに始まる。(能蔵寺の名は、この付近の地名として使われていた) 尚、開山上人は明らかでない。
おそらく頼朝が亡くなった後、現在の「時宗」に改宗したと思われるが改宗年代は不詳である。山院寺号を随我山来迎寺と号し、音阿上人(当時過去帳記載)が入山以降法燈を継承している。能蔵寺から起算すると実に八百余年の歴史がある。
時宗の総本山は神奈川県藤沢市西富、藤沢山清浄光寺、通称遊行寺と呼ばれている。開祖は一遍上人、今から七百年余り前文久十一年(一二七四年)熊野権現澄誠殿に参籠、熊野権現から夢想の口伝を感得し、「信不信浄不浄を選ばず、その札を配るべし」の口伝を拠り處に、神勅の札を携え西は薩摩から東は奥羽に至るまで、日本全国津々浦々へ、念仏賦算の旅を続けられること凡そ十六年。その間寺に住されることなく亡くなるまで遊行聖に徹した。
教法の要旨は『今日の行生座臥擧足下足平生の上を即ち臨終とこれを心得称名念仏する宗門の肝要となすなり』とある「念仏によって心の苦しみや悩みは、南無阿弥陀仏の力で救ってくださる」という教えである。
当寺の本尊阿弥陀如来(弥陀三尊)は三浦義明の守護佛と伝えられる。(中略)
鎌倉三十三観音札所十四番で子育て観音をおまつりしてある。
この観音様に念ずれば、必ず智恵福徳円満な子供を授かるとして、昔から多くの信者に信仰されている。以前、当寺の山頂(本堂裏側の山頂)にこの観音堂があったが昭和十一年、国の指令により「敵機の目標になるから」という理由で、取り壊された。鎌倉旧市街および海が一望でき、長谷観音と相対していた。
当山は明治五年十二月二十一日夜、材木座発火の類焼に遭い寺寶はことごとく消失してしまった。「相模風土記」によると「宗祖一遍上人像、三浦義明の像有り」とあるが現存しない。(中略)
当山四十五代照雄和尚の徳により三浦義明の像並びにこれ御安置する御堂を建立、昭和三十五年五月、義明七百八十年忌にあたり一族と共に供養した。(この義明像は三浦一族に由縁のある彫刻家鈴木国策氏の献身的な奉仕によって見事制作されたものである)
しかし、この御堂も諸般の事情により取り壊した。将来境内整備が終わりしだい再建する予定である。
境内には義明公および多々良三郎重春公の五輪塔(高さ二米)一説には義明公夫婦ともいわれている。また応永、正長年銘などの寶篋印塔(数基鎌倉国宝館に貸し出し展示中)ありこの数七百余基を数える。
「相模風土記」によれば、「三浦義明の墓は五輪塔なり、ここに義明の墳墓あるはその縁故知らざれど、思うに冥福を修せんがために寺僧が造立せしならん」とある。
義明は庄司義継の長男で平家の出で、平家の横暴腐敗した政治を正すため、源氏に仕え、時の世人挙げて平家に従ったが、ただ一人敢然として頼朝に尽力した。
治承四年(一一八〇年)頼朝の召に応じて子義澄を遣わしたが、石橋山の敗戦で帰郷の途次、畠山重忠の軍を破った為、重忠らに三浦の居城衣笠城を包囲された。
防守の望みを失ったので、義澄らの一族を脱出させて頼朝のもとに赴かせひとり城に留まって善戦したが、ついに陥落して悲壮な最期を遂げ、源氏のために忠を尽くした。
一方石橋山の戦いで平家に敗れた頼朝は、海路安房に渡って再挙を図り、関東各地の源氏家人の加勢を得、義澄と共に鎌倉に拠って策源地と定めた。
後、征夷大将軍となり鎌倉幕府を創建したのである。
この国家大業の成就の陰には義明の先見の叡智と偉大な人徳によるところただい(多大?)である。義明あって鎌倉幕府の成否は義明によって決したと断ずるも過言でない。
後に頼朝が義明あるいは一族に対する報謝の意が実に数々の温情の行業に伺われる。
義明が後に「三浦大介百六ツ」と呼ばれる由来は頼朝が衣笠の満昌寺において、義明の十七回忌法要を供養したとき、義明がまだ存命して加護していてくれるのだ。という心からの事で自刃したときの八拾九歳と十七年を加えた数と思われる。
私たちは、このような幾多の先祖の偉業、遺徳を懇ろに偲び、人生の心の糧として、何時までもこの行跡をたたえ続けて行きたいものである。
■ 『鎌倉市史 社寺編』(鎌倉市)(抜粋)
隨我山来迎寺と号する。時宗。藤沢清浄光寺末。
開山、音阿 本尊、阿弥陀三尊
境内地258.55坪。
本堂兼庫裏、来迎寺幼稚園あり
ここはもと真言宗能蔵寺の旧蹟と伝える。
本尊は三浦大介義明の守本尊であるといい、境内に義明及び多々良三郎重春の分骨を葬ってあるという。
-------------------------
鎌倉駅構内の観光客の動線をみると、多くの客は東口に出て小町通りを北上し、鶴岡八幡宮方面か、扇ヶ谷 or 源氏山方面へ向かいます。
東口から南方向の本覚寺、妙本寺、八雲神社、安養院、妙法寺、安国論寺方面へ向かう人はどちらかというと中~上級者(?)で数は多くなく、さらに横須賀線を渡って材木座方面まで足を伸ばす人はかなり少なくなります。
しかし、材木座界隈には寺社が多くほとんどが御朱印、御首題を授与されているので、隠れた御朱印エリアとなっています。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 札所標と墓碑
来迎寺もそんな材木座の一画にあります。
周囲は真新しい住宅街ですが、山内に足を踏み入れると俄然しっとりとした鎌倉寺院の趣が出てくるという、面白いロケーションです。
参道入口に観音霊場札所標と三浦義明の墓碑。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 寺号標
参道途中から石畳となり、寺号標が建っています。
参道正面が本堂、左手が庫裏、右手に回り込むと三浦義明の墓所(五輪塔墓)です。


【写真 上(左)】 墓所への案内
【写真 下(右)】 五輪塔墓


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂と庫裏
本堂はおそらく宝形造で桟瓦葺流れ向拝です。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股を置き、身舎左右には大ぶりの花頭窓。
水引虹梁は朱を散りばめた、変化のある意匠です。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝


【写真 上(左)】 斜めからの向拝
【写真 下(右)】 札所板
向拝見上には鎌倉観音霊場の札所板が掲げられています。

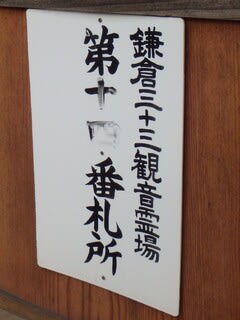
【写真 上(左)】 観音像
【写真 下(右)】 札所案内
堂前向かって右手前にある胸像は、すみませんよくわかりません。
山内には白衣でおだやかな面差しの観音立像も安置されていました。
御朱印は庫裏にて拝受しましたが、ご不在の場合もあるようです。
〔 来迎寺の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
41.五所神社(ごしょじんじゃ)
公式Web
神奈川県神社庁Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-9-1
御祭神:大山祇命、天照大御神、素盞嗚命、建御名方命、崇徳院霊
旧社格:村社、材木座の氏神
元別当:南向山 補陀落寺(鎌倉市材木座) 旧・諏訪神社の別当
五所神社は「材木座の氏神」と親しまれる、地域を代表する神社です。
公式Web 、下記史料・資料、境内掲示などから縁起沿革を追ってみます。
もともとこの地は材木座村でしたが、乱橋(みだればし)村と材木座(ざいもくざ)村に分村しました。
明治22年、両村が合併して西鎌倉郡乱橋材木座(鎌倉郡西鎌倉村ないし東鎌倉村の一部とも)となりました。
境内掲示によると、合併以前から両村には下記の神社が鎮座されていました。
・三島神社 御祭神 大山祇命
現社地、乱橋村の鎮守社、旧村社
・八雲神社
現・材木座4-4-26公会堂内、乱橋村龍蔵寺(能巌寺)部落、三島神社の相殿?
・金比羅宮(金刀比羅社) 御祭神 金山彦命
現・材木座4-7-2竹内宅裏山「普賢象山」、乱橋村
・諏訪神社 御祭神 建御名方命
現・材木座5-13-8山ノ上方、材木座の鎮守、補陀落寺持
・視女八坂社(見目明神・見目天王、牛頭天王、見目明神社合社)
現・材木座6-7-35、材木座村仲島部落、補陀洛寺の鎮守?
『新編相模国風土記稿』には「(亂橋村)三島社 村持」「(材木座村)諏訪社 補陀落寺持」の記載がみえます。
見目明神は、三島大社の摂社として知られています。→ 三島市Web資料
御祭神は三嶋大社の御祭神・事代主神のお妃六柱です。
こちらの視女八坂社(見目明神)も、乱橋村鎮守の三島神社となんらかの関係があるのかもしれません。
『鎌倉市史 社寺編』では、五社神社に合祀の見目明神は『補陀洛寺文書』に見目天王分としてみえることから、古くから補陀洛寺の鎮守であったとみています。
また、『新編鎌倉志』の補陀落寺の項には「寺寶 寶満菩薩像 壹軀 八幡の姨なり。鶴岡にもあり。社家にては見目明神(ミルメ)と云ふ。」とあり、見目明神の本地が寶満菩薩であることを示しています。
寶満(宝満)菩薩は、太宰府の宝満山が有名です。
「文化遺産オンライン」には「(宝満山)は八幡信仰と融合し、宮寺として社寺一体となり」「中世には宝満山とも呼ばれ、宝満大菩薩という仏神となり、英彦山修験道と結合して英彦山の胎蔵界に対し、金剛界の行場として、修験の山となった。」とあり、寶満(宝満)菩薩と八幡神、修験道との関係を示しています。
また、境内の「板碑(石造板塔婆)」は廃寺となった乱橋村の感應寺から遷されたとの説明があります。
由比山寶幢院感應寺は、真言宗京都三寶院末でした。
三寶院は真言宗系修験道「当山派」の本寺ですから、旧・感應寺から当山修験の流れが五社神社に引き継がれたのかもしれません。
明治41年、三島神社に四社を合祀して五所神社と改称しました。
合祀時に旧・諏訪神社の社殿を移築した本殿は、関東大震災の土砂災害で倒壊したため昭和6年に新築されました。
五所神社はいまも材木座の氏神として尊崇され、三基の神輿が渡る例祭は鎌倉の風物詩として広く知られています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
補陀落寺 寺寶 寶満菩薩像 壹軀
八幡の姨なり。鶴岡にもあり。社家にては見目明神(ミルメ)と云ふ。
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(亂橋村)
三島社 村持
(材木座村)
諏訪社 補陀落寺持
(亂橋村)
感應寺
由比山寶幢院と号す、真言宗京都三寶院末 不動を本尊とし、神変菩薩理源大師の像あり、中興を養源と云ふ 境内に倶利迦羅竜王の古碑あり
■ 神奈川県神社庁Web資料
五所神社
当社鎮座地は、古くは乱橋村と材木座村とに分かれていた。乱橋村には三島神社、八雲神社、金刀比羅社の3社が鎮座し、材木座村には諏訪社と視女八坂社の2社が鎮座していた。明治初年に村が合併し、乱橋材木座村となった。相模風土記稿に「三島社村持」とある如く、村の中心的社であったので明治6年、村社に列格された。
明治41年に他の四社が合祀され、五所神社と改称された。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
五社神社
祭神、大山祇命、天照大御神、素盞嗚命、建御名方命、崇徳院霊。
例祭七月七日。元指定村社。乱橋材木座の鎮守。境内地163.09坪。
覆殿、社殿、神輿庫あり。現在の社殿は昭和六年七月の新築。
現在の神社は明治四十一年七月、乱橋村と材木座村が合して、東鎌倉村大字乱橋材木座となったとき、乱橋村の鎮守三島神社の地に材木座村の鎮守諏訪神社・乱橋村能蔵寺部落の八雲神社・金比羅宮・材木座村中島部落の見目明神の四社を合わせ、同年十一月、五所神社と改称したものである。もとの五社はいずれも勧請年月不明。
このうち、見目明神は補陀洛寺文書に見目天王分として二貫三百文の地を北条氏康が同寺に寄進しているから、古くから同寺の鎮守であったと思われる。
『新編鎌倉誌』には見目明神とよんだ宝満宮菩薩像があったことがみえ、『風土記稿』には牛頭天王、見目明神社合社とある。
三島神社は、乱橋村持(『風土記稿』)で八雲社を相殿とし、この相殿天王の神輿棟札によれば、寛永十九年(1642年)修造以後、延宝九年(1681年)元禄十一年(1698年)元文二年(1737年)宝暦十三年(1763年)に修理を加え、万延元年(1860年)に再建している。(中略)
境内に昭和十六年重要美術品に認定された板碑がある。
境内坪数二八0坪で、もとの本殿は明治十六年七月建立の諏訪神社本殿を合併後移築したものであったが、震災の時山崩れのため社殿埋没全壊した。
■ 境内掲示
五所神社
祭神 天照大御神、素盞嗚命、大山祇命、建御名方命、崇徳院命
明治二十二年(一八八八)乱橋村と材木座村が合併して西鎌倉村大字乱橋材木座となった後明治四十一年(一九〇八)七月に、もとの乱橋村の鎮守”三島神社”(現在の地)の地に材木座の鎮守、諏訪神社(現材木座五-十三-八 山ノ上方)乱橋村龍蔵寺部落の八雲神社(現材木座四-四-二六 公会堂内)、金比羅宮(材木座四-七-二 竹内宅裏山「普賢象山」中腹)、材木座村仲島部落の見目明神 材木座六-七-三五)の四社を合併して五所神社として改名したものである。
もとの五所はいずれも勧請年月不詳このうち見目明神は補陀洛寺文書に見目天王文と二貫三百文の地を北条氏康が同時に寄進しているから古くから同寺の鎮守であったと思われる。
「新編鎌倉誌」には、見目明神とよんだ宝満宮菩薩像があったとみえ「風土記稿」には牛頭天王、見目明神社合社とある。
三島神社は、乱橋村持「風土記稿」で八雲社を相殿とし、この相殿天王みこし棟札によれば、寛永十九年(一六四二)修造以後、延宝九年(一六八一)元禄十一年(一六九八)元文二年(一七三七)宝暦十三年(一七六三)に修理を加え、万延元年(一八六〇)に再建している。
諏訪社は補陀洛寺であった「風土記稿」明治八年(一八七五)公達に基づいての皇国地誌調査さんによると次の通り記載されている。
三島社
式外村社々地東西四間南北六間三尺面積二六坪の東方にアリ大山祇命ヲマツル。
勧譜年暦詳ナラス 例祭四月 十一月ノ酉ノ日ヲ用ウ
見目社
同社東西九間南北八間四尺八寸面積七九坪村ノ東西間ニアリ祭神及ビ創造勧譜年暦詳ナラス 例祭二月二七日 六月七日両回トス
諏訪社
同社東西八間一尺二寸南北一間六寸面九坪村のノ南方ニアリ祭神建御名方命勧譜年暦詳ナラス 例祭六月七日 七月二七日ノ二回トス
金比羅社
同社東西十間南北七間面七十坪村ノ辰ノ方ニアリ祭神金山彦命勧譜年暦詳ナラス 例祭十月十日
現在の社殿は昭和六年(一九三一)七月に新築されたものである。
もとの本殿は明治一六年(一八八三)七月諏訪神社の本殿を合併後、移建したものであったが大正十二年(一九二三)九月一日震災のとき山崩れのため社殿埋没全潰した。
お神輿三基
一号 諏訪神社 二号 三合(ママ) 見目明神の持ち物であった。
祭礼、潮祭り 一月十一日 春季小祭 四月十五日 秋季小祭 十一月二十四日
例大祭 七月七日から十四日
現在の祭礼(抜粋)
例大祭 六月第二日曜日 三ツ目神楽 例大祭三日目(火曜日)
-------------------------
名越・朝比奈方面からつづく鎌倉東部の山地は、材木座・光明寺の裏手から大町、小町と北にかけて連なり、西向きの山裾を大蔵あたりまで落としています。
この山裾は鎌倉有数の寺社の集積エリアで、五社神社もこの山裾に当たります。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 参道-1
来迎寺と実相寺の中間くらいに路地に面して社頭があります。
参道右手に社号標、その先に藁座を置いた神明鳥居?。
鳥居は本殿手前の石段前に置かれていましたが、関東大震災で倒壊破損したため昭和9年に社頭に移設されたものです。
参道は鳥居から真っ直ぐに伸びていますが、かなり奥行きがありここから拝殿は見えません。


【写真 上(左)】 狛犬-1
【写真 下(右)】 狛犬-2
すぐ先に石灯籠一対と真新しい狛犬一対。
さらに進んだ古い狛犬一対は、大正5年に材木座三丁目の地主ら十三名が寄進したものとのこと。


【写真 上(左)】 参道-2
【写真 下(右)】 参道-3
さらに行くと数段の石段で、ここまでくると参道階段の上に社殿が見えてきます。
社殿下の階段左脇に社務所があり、御朱印はこちらで授与されています。
あたりはうっそうとした木々に囲まれ、山里の神社のようです。
参道階段をのぼった正面、切妻造の建物は神輿庫(天王堂)で、庫内にはきらびやかな三基の神輿が安置されています。


【写真 上(左)】 境内
【写真 下(右)】 神輿庫(天王堂)
公式Webには「向かって右手より一番様(旧諏訪神社 江戸末期建造・鎌倉市指定有形民俗文化財)、二番様(旧牛頭天王社 弘化四年(1847)建造)、三番様(旧見目明神社 弘化四年(1847)建造)」とあります。
三基の神輿のお渡りをはじめ、数々の見どころがある五社神社の祭礼は、鎌倉の風物詩としてよく知られています。


【写真 上(左)】 神輿
【写真 下(右)】 拝殿
神輿庫(天王堂)前を左に直角に曲がった正面が拝殿です。
入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、軒唐破風を張り出し、妻側千鳥破風に経の巻獅子口を置き、寺院建築のイメージ。


【写真 上(左)】 拝殿妻側
【写真 下(右)】 拝殿向拝-1


【写真 上(左)】 拝殿向拝-2
【写真 下(右)】 中備の彫刻
水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻、その上に兎の毛通しと、こちらにも経の巻獅子口を置いています。
彫刻類はいずれも重厚感を備えたすばらしい出来です。
向拝見上の扁額には「国家興隆」とあり、鎌倉宮ゆかりのもののようです。
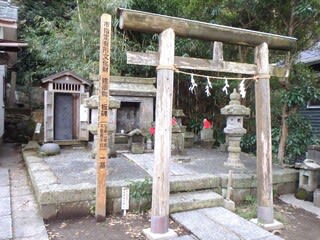

【写真 上(左)】 三光尊石上稲荷と板碑(石造板塔婆)
【写真 下(右)】 板碑
神輿庫右手の木の鳥居のおく、正面が三光尊石上稲荷、向かって左手が板碑(石造板塔婆)の覆屋です。
三光尊石上稲荷は、ふるくは豆腐川の河口に御鎮座といいます。
豆腐川は、材木座海岸に注ぐ短い川です。
お祀りされている石は「石上さま」といわれ、漁師の網を切ったり、船を転覆させたりと、いたずらをする石であったそうです。
陸に引き揚げられ、昭和9年、補陀洛寺第33世光照上人より名を授かり、昭和12年に石祠を建立、海上安全の守護神としてお祀りされています。
左手の板碑(石造板塔婆)は弘長二年(1262年)の銘。
倶利迦羅剣になぞらえた不動明王のお種子「カン/カーン」を蓮華座のうえに置く見事な板碑で、上部には天蓋も彫られています。
板碑の多くは秩父片岩ですが、この板碑は雲母片岩を用いて特徴的とのことで、市指定有形民俗資料に指定されています。
板碑の説明板に「昔は感應寺『修験真言宗、京都三宝院末」(材木座公会堂のある附近一帯)の境内に建っていたが、同寺が廃寺となったため五所神社創建の際ここに移されたのである。」とあります。
『新編相模国風土記稿』には「(亂橋村)感應寺 由比山寶幢院と号す、真言宗京都三寶院末 不動を本尊とし、神変菩薩理源大師の像あり、中興を養源と云ふ 境内に倶利迦羅竜王の古碑」とあり、もしかしてこの「倶利迦羅竜王の古碑」が五所神社の「板碑(石造板塔婆)」なのかもしれません。
鳥居の右よこには旧諏訪神社の古祠と、そのよこに大阪株式取引所(現・大阪取引所)の第二代頭取・吉田千足書の石碑があります。



【写真 上(左)】 旧諏訪神社の古祠
【写真 下(右)】 庚申塔
その右手には十数基の庚申塔と石佛。
庚申塔は乱橋村・材木座村両村の道端や辻にあったものを明治9年境内に集めてお祀りしたものとの由。
馬頭観音像のよこには、背後に十字架が置かれた「お春像」が安置されています。
公式Webには「『天和四』と掘られていることから一六八四年(徳川幕府五代将軍綱吉の初期の時代)一月から二月に造られたであろう石像と思われますが、その目的は未詳。その様子から隠れキリシタン殉教の像と伝えられています。」とあります。
神社の境内に十字架とは、かなりインパクトがありますが、このような歴史を伝える尊像です。


【写真 上(左)】 お春像
【写真 下(右)】 摩利支天像
さらにその右には大正2年奉納の「摩利支天像」。
摩利支天はもとは天竺(インド)の神格でしたが、仏教にとり入れられて守護神となりました。
三面六臂の丸彫りで椎型兜をかぶり、槍先が三つに割れた矛を握られたこのお姿の摩利支天像は、公式Webによると日本で十二体しか存在していないそうです。
境内には手玉石(かめ石)や疱瘡ばあさんの石、山岳信仰道場などもあります。
西向きの明るい境内ですが、どこかパワスポ的な陰りを感じるのは、修験や神仏混淆の歴史がもたらすものかもしれません。
御朱印は参道階段左手の社務所にて拝受しました。
〔 五所神社の御朱印 〕


42.弘延山 實相寺(じっそうじ)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座4-3-13
日蓮宗:
司元別当:
札所:札所:
實相寺は宗祖嫡弟六老僧日昭尊者潜居の地とも伝わる日蓮宗の名刹です。
鎌倉市観光協会Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
實相寺は、日蓮宗六老僧の辨阿闍梨日昭(元享三年(1323年寂))が創建とされます。
日蓮聖人が佐渡へ流罪となった後も当地で布教を続け、伊豆の名刹・玉澤妙法華寺が移転する前の旧地といいます。


【写真 上(左)】 玉澤妙法華寺
【写真 下(右)】 同 御首題
またこの地は、鎌倉時代の武将・工藤祐経の屋敷跡で、日昭上人はその息女の子とも伝わります。
日昭上人が屋敷跡に法華堂を建てたのが創始といいます。
法華堂は法華寺と号して三島・玉澤に移り、元和七年(1621年)に日潤上人が再建とされます。
日昭上人はWikipediaによると俗姓を印東氏といい、晩年の日蓮聖人を池上に迎え、池上本門寺の基礎をつくった日蓮宗の有力檀越・池上宗仲と親戚関係にあったとも。
玉澤法華経寺公式Webによると、宗祖日蓮聖人の比叡山遊学中の学友ともいい、聖人に共鳴し、宗祖が鎌倉で法華経弘通を始められとすぐ最初の弟子となったとの由。
日蓮六老僧の一人に数えられ、日昭門流(濱門流・玉澤門流)の祖です。
現在の日昭門流の本山は、妙法華寺(三島市玉澤)と村田妙法寺(新潟県長岡市)で、その妙法華寺の旧地とあっては宗門上、重要な寺院とみられます。
工藤氏については■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2/14.稲荷山 東林寺でとりあげているので再掲します。
藤原南家の流れとされる工藤氏は、平安時代から鎌倉時代にかけて東伊豆で勢力を張り、当初は久須見氏(大見・宇佐見・伊東などからなる久須見荘の領主)を称したともいいますが、のちに伊東氏、河津氏、狩野氏など地名を苗字とするようになりました。
東伊豆における工藤(久須見)氏の流れは諸説あるようです。
いささか長くなりますが整理してみます。
工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の(滝口)祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)
他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)
伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。
(河津祐親→伊東祐親)
一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。
工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。
娘の八重姫が頼朝と通じ、子・千鶴丸をもうけたことを知った祐親は激怒し千鶴丸を殺害、さらに頼朝公の殺害をも図ったとされます。
このとき、頼朝公の乳母・比企尼と、その三女を妻としていた次男の祐清が危機を頼朝公に知らせ、頼朝公は伊豆山神社に逃げ込んで事なきを得たといいます。
なお、北条時政の正室は伊東祐親の娘で、鎌倉幕府第二代執権・北条義時は祐親の孫にあたるので、鎌倉幕府における伊東祐親の存在はすこぶる大きなものがあったとみられます。
工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すも効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。
安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。
祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。
伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東市の東林寺に入って出家しました。
治承四年(1180年)頼朝公が挙兵すると、伊東祐親は大庭景親らと協力して石橋山の戦いでこれを撃破しました。
しかし頼朝公が坂東を制圧したのちは追われる身となり、富士川の戦いの後に捕らえられ、娘婿の三浦義澄に預けられ、義澄の助命嘆願により命を赦されたものの、祐親はこれを潔しとせず「以前の行いを恥じる」といい、養和二年(1182年)2月、自害して果てたとされます。
河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。
建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。
工藤祐経の子・祐時は伊東氏を称し、日向国の伊東氏はその子孫とされています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(亂橋村)實相寺
弘延山と号す 豆州玉澤妙法華寺末 開山日昭 元享三年(1323年)三月廿六日寂す
本尊三寶を安ず
■ 山門掲示
當山ハ宗祖嫡弟六老僧第一辨大成辨阿闍梨日昭尊者潜居の地 宗祖佐渡流竄後門下僧俗を統率したる濱土法華堂(祖滅後法華寺と称す)乃霊跡にて玉澤妙法華寺の旧地也 傳フ工藤祐経邸趾と云ふ
日昭尊者濱土法華堂霊跡
御廟 裏山の麓にあり往古ハ峯の岩屋ニ有しを元禄三年現所ニ移せり
■ 玉澤妙法華寺公式Web
妙法華寺は、日蓮聖人の本弟子で六老僧第一の弁阿閣梨日昭上人が開創された寺である。
もと鎌倉の浜にあった法華寺がその前身であり、宗祖が日頃、日昭上人を浜殿と呼んでいたのは、この浜の地名によるものである。宗門としては最も初期の寺に属する。
当山の古記録によると、身延を除けば妙本寺第叫、法華寺第二と誌されている。この古い歴史と霊宝の聖人ご真筆、『宗祖説法御影』、調度品等が聖人の息吹を今に伝えている。
縁起
弘安7年(1284)12月、越後の風間信昭により、鎌倉の浜にあった日昭上人の庵室を寺としたのが起源である。
日昭上人は、宗祖の比叡山遊学中の学友であったが、聖人に共鳴し、宗祖が鎌倉で法華経弘通を始めるとすぐ最初の弟子となった。
鎌倉の浜土に草庵を構え、宗祖や他の門弟と共に教化活動を行い、その後、宗祖が身延に人山すると、日朗上人とともに鎌倉の日蓮教団の中心的役割を果たした。一門を日昭門流とか浜土門流と称し、近代は玉沢門流と呼んだ。(以下略)
■ 『鎌倉市史 社寺編』(鎌倉市)(抜粋)
弘延山 實相寺と号する。日蓮宗。伊豆玉澤妙法華寺の旧地。
開山、日昭。
本尊、一尊四士。
境内地405坪。
本堂・庫裏・山門あり。
日昭は元亨三年(1323年)三月廿六日寂。日昭は工藤祐経の女の生んだ子。この地は祐経の旧邸址と伝える。当寺の十一代日弘・十二代日南は関東管領扇ガ谷上杉氏の一族であるという。明治初年の大火で焼失した。
-------------------------
鎌倉材木座・五所神社の並びにあります。
由緒ある名刹ですが、やはり立地的に観光客の拝観は多くないと思われます。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 斜めからの山門
路地に面する山門は、門前にゆったりと空間をおき、二基のお題目塔(寺号標)を拝して落ち着いた名刹の風情。


【写真 上(左)】 寺号標-1
【写真 下(右)】 寺号標-2
山門は脇塀を巡らした切妻屋根桟瓦葺の薬医門かと思われますが、水引虹梁に四連の斗栱を拝して風格があります。
山門柱には「日昭尊者濱土法華堂霊跡」の表札で、由緒が記されています。


【写真 上(左)】 霊跡の札板
【写真 下(右)】 山内


【写真 上(左)】 お題目塔
【写真 下(右)】 本堂
山内は数基のお題目塔はありますがすっきりシンプルで、参道正面が本堂です。
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、なだらかに照りを帯びる屋根の勾配が優美です。


【写真 上(左)】 向拝-1
【写真 下(右)】 向拝-2
水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を置いています。
向拝・身舎ともに格子と桟をおき、端正なイメージの堂宇です。
御首題・御朱印は庫裏にて拝受しました。
〔 實相寺の御首題・御朱印 〕


【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-14 (B.名越口-9)へつづく。
【 BGM 】
■ Rina Aiuchi(愛内里菜) - Magic
■ 森高千里 - 渡良瀬橋
■ 今井美樹 - Goodbye Yesterday
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-12 (B.名越口-7)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)から。
37.天照山 蓮乗院(れんじょういん)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-16-15
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:
札所:鎌倉三十三観音霊場第19番、相州二十一ヶ所霊場第11番
蓮乗院は材木座・光明寺の参道右手にある塔頭寺院です。
鎌倉市観光協会Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
蓮乗院の創立年代・開山は不詳ですが、光明寺開山(寛元元年(1243年))より早い時期からこの地にあり、当初は蓮乗寺と号す真言密寺だったと伝わります。
佐介谷の悟真寺(蓮華寺)がこの地に移転の際(寛元三年(1247年))、良忠上人は伽藍落成まで蓮乗院に入られて建築を督励されたといいます。
光明寺(改号後)の子院となり、浄土宗の蓮乗院と改めたと伝わります。
この沿革にもとづき、光明寺の新住職はまず蓮乗院に入ってから光明寺の本山方丈に入るならわしだったといいます。
蓮乗院が塔頭や僧坊ではなく、「子院」と呼ばれることがあるのもこのような格式によるものかも。
本堂に御座す十一面観世音菩薩は鎌倉三十三観音霊場第19番、弘法大師像は相州二十一ヶ所霊場第11番の札所本尊となっています。
『鎌倉市史 寺社編』には「弘法大師の霊場として大正三年東京東山講(魚河岸の人達)が大師像を作って納め、当二十一ヶ所の十一番とした。」とあり、大正三年に相州二十一ヶ所霊場第11番の札所となったことがわかります。
なお、相州二十一ヶ所霊場については、こちらの「31.金龍山 釈満院 宝戒寺」をご覧くださいませ。
『新編鎌倉志』『新編相模国風土記稿』ともに、蓮乗院の御本尊・阿弥陀如来木像は伝・運慶作で、千葉介常胤の守護佛と伝えます。
千葉介常胤および千葉氏については「鎌倉殿の13人」と御朱印-3/22.阿毘盧山 密乗院 大日寺にまとめていますが転記します。
千葉氏は桓武平氏良文流、坂東八平氏(千葉氏・上総氏・三浦氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏)を代表する名族として知られています。
律令制のもとの親王任国(親王が国守に任じられた国。常陸国、上総国、上野国の3国ですべて「大国」)の国守(太守)は親王で、次官として「介」(すけ)がおかれ、実質的な国の長官は「介」ないし「権介」であったとされます。
常陸国の「介」には平家盛、頼盛、経盛、教盛など伊勢平氏(いわゆる「平家」)が任ぜられました。上総国の「介」は早くから坂東に下向した桓武平氏良文流の上総氏、下総国は親王任国ではありませんが、こちらも実質的な長官は「介」ないし「権介」で、良文流の千葉氏が占めて”千葉介”を称し、有力在庁官人としてともに勢力を張りました。
もうひとつの親王任国、上野国(現・群馬県)には、平良文公や千葉氏の嫡流・平(千葉)常将公にまつわる伝承が多く残ります。
(ご参考→『榛名山南東麓の千葉氏伝承』)
千葉氏の妙見信仰にもかかわる逸話が伝わるので、少しく寄り道してみます。
千葉氏の妙見信仰のはじまりについては諸説がありますが、千葉市史のなかに、上野国の妙見菩薩にちなむとする記載がありました。(『千葉市史 第1巻 原始古代中世編』(千葉市地域情報デジタルアーカイブ))
これによると、桓武天皇四世、平高望公の子・平良文公は武蔵国大里郡を本拠とし、良文公と平将門公が結んで上野国に攻め入り、上野国府中花園の村の染谷川で平国香公の大軍と戦った際に示現された妙見菩薩(花園妙見・羊妙見)が、その信仰のはじまりだというのです。
「染谷川の戦い」は、伊勢平氏の祖・国香公と良文流の祖・良文公、そして関東の覇者・将門公という超大物が相戦うスケール感あふれる戦いですが、複数の伝承があるようで、国香公と将門公の対峙は明らかですが、良文公がどちらについたかが定かでありません。(そもそも史実かどうかも不明)
しかし、この戦いで花園妙見の加護を得た将門公と良文公が実質的な勝利を得、国香公は撤収したとされています。
これに類する逸話は『源平闘諍録』にも記されており、千葉市史はこれにもとづいて構成されたのかもしれません。
また、良文公の嫡流、平(千葉)常将公も、上野国の榛名山麓に多くの逸話を残しています。
上野国に大きな所領を得たわけでもない良文公や常将公の足跡が上野国にのこるのは、やはり房総平氏の妙見信仰が上野国所縁であることを示すものかもしれません。
※関連記事 → ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)の6.三鈷山 吉祥院 妙見寺
房総半島に依った桓武平氏は「房総平氏」とも呼ばれ、平忠常公がその始祖とされます。
「房総平氏」の代表格は上総介と千葉介で、鎌倉幕府草創期の当主は上総介広常と千葉介常胤でした。(→千葉氏系図)(千葉一族の歴史と史跡)
石橋山の戦いで敗れ房総で再挙を図った頼朝公ですが、大きな武力をもつ「房総平氏」の上総介と千葉介の協力なくして鎌倉入りは果たせなかったとみられています。
上総介広常は頼朝公に粛清されましたが、頼朝公のサポート役に徹した千葉介常胤はその地位を能く保ちました。
常胤は千葉氏の祖ともされる平常重の嫡男で、保元元年(1156年)の保元の乱では源義朝公の指揮下で戦いました。
治承四年(1180年)、石橋山の戦いで敗れた頼朝公が安房に逃れると、頼朝公は安達盛長を使者として千葉庄(現在の千葉市付近)の常胤に送り、常胤は盛長を迎え入れ、頼朝公に源氏ゆかりの鎌倉に入ることを勧めたとされます。(『吾妻鑑』治承4年9月9日条)
『吾妻鏡』には、同年9月17日に常胤が下総国府に赴き頼朝公に参陣とあります。
この時期、頼朝公が千葉妙見宮を参詣、以降も尊崇篤かったと伝えられ、頼朝公は房総における妙見信仰の大切さを熟知していたのかもしれません。
これに関連して『千葉市における源頼朝の伝説と地域文化の創出に向けて』(丸井敬司氏)には興味ぶかい説が記されています。
頼朝公は鎌倉に入るやいなや鶴岡若宮(現・元八幡宮)を北に遷座(現・鶴岡八幡宮)していますが、同書では「(鶴岡若宮の北遷は)八幡神を道教における四神の玄武と見做したことを意味する。こうした既存の八幡社に妙見の神格を加えるような事例は房総半島には多く確認される。」とし、守谷の妙見八幡、竜(龍)ヶ崎の妙見八幡を例にひいています。
また、「尊光院(現・千葉神社)のように妙見の別当寺を町の北側に建立することで、事実上、八幡社を妙見社とする例もある(こうした八幡に妙見の神格を加えたものを「千葉型の八幡信仰」という)。こうした事例から考えると筆者は、鶴岡若宮は典型的な「千葉型の八幡信仰」の寺院であったと考えている。」とし、鶴岡八幡宮の御遷座に千葉氏の関与ないしは献策があったことを示唆しています。
源平合戦では範頼公に属して一ノ谷の戦いに参加、豊後国で軍功をあげ、奥州討伐では東海道方面の大将に任じられて活躍、鎌倉幕府でも重きをなしたとされています。
頼朝公も常胤を深く信頼し、「(常胤を)以て父となす」という言葉が伝わります。
千葉氏における常胤の存在の大きさは、常胤以降、嫡流は諱に「胤」の一字を受け継ぐことが通例となったことからもうかがわれます。
また、千葉市Webや千葉市立郷土博物館Webでも、千葉氏が大きくとりあげられ、この地における千葉氏の存在の大きさが感じられます。
これは千葉氏が単なる豪族にとどまらず、房総に広がる妙見信仰と深くかかわっていることもあると思われ、実際、千葉市公式Webには「千葉氏と北辰(妙見)信仰」というコンテンツが掲載されています。
常胤の6人の息子の子孫は分家を繰り返しながら全国に広がり、のちに「千葉六党(ちばりくとう)」(千葉氏、相馬氏、武石氏、大須賀氏、国分氏、東氏)と呼ばれる同族勢力を形成しています。
千葉介常胤は真言宗ともゆかりがふかく、あるいは真言密寺の旧・蓮乗寺は千葉介常胤とゆかりがあり、旧・蓮乗寺の御本尊が蓮乗院の御本尊に奉安されたのかもしれませんが、史料類は詳細を伝えていません。
千葉介常胤絡みで当山を訪れる人は多くはないと思いますが、ふたつの霊場の札所なので、こちらの巡拝者の参拝は多いと思われます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志 鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
蓮乗院
総門を入右にあり。光明寺草創以前に、真言宗の寺あり。蓮乗寺と云ふ。今の蓮乗院是なり。開山此寺に居て、光明寺を建立す。故に今に住持入院の時は、先づ此院に入て後方丈に入。古例なりと云ふ。当院の本尊阿彌陀木像、腹内に書付あり。貞治二年(1363年)三月十五日、修復之とあり。伝へ云、運慶が作にて、千葉介常胤が守本尊なりと。
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(材木座村)塔頭 蓮乗院
総門を入て右にあり、当院は本坊草創已前密刹にて蓮乗寺と号せり、開山良忠此寺に居て光明寺を建立す 故に今に住持入院の時は先此院に入て後方丈に入る古例なりと云ふ、
本尊は彌陀の雕像にて肚裏に紙片あり貞治二年(1363年)三月十五日修復之の十二字を記す、是運慶が作にて千葉介常胤が守護佛なりと伝ふ
-------------------------
光明寺の参道・山門の左手にあります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
山門は脇塀付き切妻屋根桟瓦葺のおそらく薬医門かと思います。
見上げに院号扁額。
山内は広くはないものの、しっとりと落ち着きがあります。
相州二十一ヶ所霊場第11番の札所標もありました。


【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場札所標
【写真 下(右)】 (光明寺の?)鐘楼堂
墓域の方に見える斗栱をダイナミックに組み上げた鐘楼堂は、光明寺のものでしょうか。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。
向拝の張り出しが大きく、なんとなく入母屋造的イメージもありますが、寄棟造平入りかと思います。
シンプルな屋根構成ながら軒上にはしっかり飾り瓦を置いています。


【写真 上(左)】 飾り瓦
【写真 下(右)】 向拝
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に卍紋付きの板蟇股を置いています。
繋ぎ虹梁はないものの、向拝まわりは朱塗りで華やかなイメージのある本堂です。
本堂の扉はわずかに開くので、堂内を拝することができます。
阿弥陀如来、釈迦如来、十一面観世音菩薩、善導大師像、法然上人像、弘法大師像などが安置され、うち十一面観世音菩薩は鎌倉三十三観音霊場第19番、弘法大師像は相州二十一ヶ所霊場第11番の札所本尊となっています。


【写真 上(左)】 観音霊場札所板
【写真 下(右)】 天水鉢
鎌倉三十三観音霊場の札所標も置かれていました。
板ふすま絵や絢爛たる天井絵は逸品とされます。
堂前の天水鉢には月星紋が置かれています。
月星紋は千葉氏の家紋のひとつとされるので、当山と千葉氏のゆかりを示すものかもしれません。
御朱印は本堂右手庫裏にて拝受しました。
〔 蓮乗院の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

相州二十一ヶ所霊場の御朱印
38.天照山 千手院(せんじゅいん)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-12-8
浄土宗
御本尊:確認中
司元別当:
札所:札所:鎌倉三十三観音霊場第20番
千手院は光明寺の参道・山門の左手にある光明寺の塔頭寺院です。
鎌倉市観光協会Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
開山・縁起等は不明です。
材木座への光明寺移転は寛元三年(1247年)とされるので、寺僧寮である千手院の創立もそれ以降とみられますが、史料類は明示していません。
『新編相模国風土記稿』には「按ずるに、【鎌倉志】専修院に作る、当時しか書記せしにや、詳ならず」とあり、『新編鎌倉志』記載の専修院を千手院とみていますが、「詳ならず」と付記しています。
奉安する千手観世音菩薩は、鎌倉三十三観音霊場第20番の札所本尊です。
「Wikipedia」によると千手観世音菩薩像は、天文元年(1532年)恢誉上人により奉安と伝わるとのこと。
なお、『鎌倉市史 社寺編』には「本尊、千手観音」とあり、拝受した御朱印には「本尊 阿弥陀如来」とあったので、御本尊については不明です。
当初は各地から集まった学僧の修行道場ないし寮でしたが、江戸期には学僧の数も減ったため、近所の子供たちに読み書きなどを教える寺子屋としての役割も果たしたといいます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志 鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
専修院
総門を入左にあり。此二箇院(蓮乗院・専修院)、共に光明寺の寺僧寮なり。
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(材木座村)千手院
僧門を入て、左にあり(按ずるに、【鎌倉志】専修院に作る、当時しか書記せしにや、詳ならず、)千手観音を本尊とす
■ 山内掲示
千手院は浄土宗で、天照山千手院と号し、光明寺の塔頭の一つであり、もとは光明寺の寺僧寮であったと伝えられる。
本尊は千手観音、江戸時代から寺子屋のあった所で、境内には梅の古木があった。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
天照山千手院と号する。
『新編鎌倉志』には専修院とあり、『光明寺志』には千手院とある。浄土宗。
もと光明寺の寺僧寮という。開山不詳。本尊、千手観音。
-------------------------
光明寺の参道・山門の左手にあります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 院号板
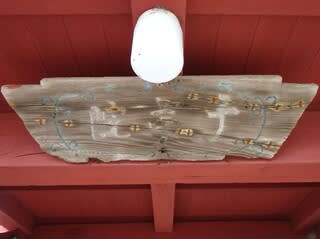

【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 観音霊場札所標
山門は脇塀付き切妻屋根桟瓦葺のおそらく四脚門かと思われます。
「赤門寺」と呼ばれそうな鮮やかな朱色の山門です。
門柱に院号板、見上げに院号扁額を掲げ、門前には鎌倉三十三観音霊場第20番の札所標を置いています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 参道
山内はかなりの奥行きがあり、緑が多く落ち着いたたたずまい。
参道は本堂前で左手に曲がり、その前の覆屋内には子恵地蔵尊が御座します。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂の様式は不詳ですが、宝形造桟瓦葺の流れ向拝かと思います。
水引虹梁は軒下に連接し両端に角形の木鼻、身舎側に繋ぎ虹梁を伸ばしています。
全体にシンプルでスクエアなイメージがあります。
見上げには鎌倉三十三観音霊場の札所板が掲げられていました。
鎌倉三十三観音霊場の第19番蓮乗院・第20番千手院は光明寺の子院・塔頭、第27番妙高院・第29番龍嶺院は建長寺の塔所、結願第33番佛日庵は円覚寺の塔頭で、とくに妙高院・龍嶺院は一般拝観不可で、原則観音霊場巡拝者のみ山内立ち入り・参拝が許されています。
大寺も多くメジャー霊場のイメージがありますが、意外にマニアックな霊場かもしれません。
(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))


【写真 上(左)】 観音霊場札所板
【写真 下(右)】 芭蕉句碑
境内には、当院の定賢和尚(明治25年寂)の教え子の田中氏が建立したという松尾芭蕉の句碑があります。
春もやヽ 気しきとヽのふ月と梅
かつてあったという梅の古木にちなんで選句したともみられています。
御朱印は山内右手の庫裏にて拝受しました。
比較的メジャーな鎌倉三十三観音霊場の札所なので、ご対応は手慣れておられます。
〔 千手院の御朱印 〕


【写真 上(左)】 阿弥陀如来の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
39.石井山 長勝寺(ちょうしょうじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-12-17
日蓮宗
司元別当:
札所:札所:
長勝寺は日蓮聖人開山とも伝わる日蓮宗の名刹です。
鎌倉市観光協会Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
開山・縁起等については諸説ある模様です。
長勝寺は、妙法寺・安国論寺とともに日蓮聖人が鎌倉に入られ最初に営まれた小庵(松葉ヶ谷御小庵の法華堂)の旧地ともみられています。
石井藤五郎長勝が日蓮聖人に帰依し、邸宅を寄進して一寺にしたという伝もあります。
Wikipediaには、石井氏は鎌倉の有力御家人三浦氏(佐原流)の流れといい、石井藤五郎長勝は文応(1260-1261年)の頃、鎌倉松葉ヶ谷付近の地頭職をつとめていたとあります。
また、宝治合戦(1247年)で三浦一族が滅亡の後、出家して日隆と号したとも。
一方、Wikipediaの「大隅石井氏」の項には、大隅石井氏の略系図として「(三浦)義明 - 義澄 - 義村 - 朝村 - 員村 - 盛明 - 義継(石井太郎) - 重義(大隅国に下向)」とあります。
これによると、盛明は宝治合戦(1247年)には誕生しているので、その子石井義継(石井氏初代)は宝治合戦の数十年後には誕生していたことになります。
義継の子石井重義が大隅国(鹿児島県東部)に下向したのは元徳二年(1330年)頃とされるので、石井義継と石井藤五郎長勝は同族関係にあったのかもしれません。
この系譜を信じると、石井藤五郎長勝は佐原流ではなく、三浦義明 - 義澄 - 義村とつながる三浦氏嫡流筋ということになります。
なお、日蓮聖人が名越松葉ヶ谷に草庵を構え布教を開始されたのは建長五年(1253年)といいますから、戦いに敗れ落魄の身にあった長勝が日蓮聖人の教えにふれて出家し、日隆と号したという説は時系列的に符合します。
ただし、戦いに敗れ、出家した三浦一族の身ではおそらく地頭職には就けないので、「文応(1260-1261年)の頃、鎌倉松葉ヶ谷付近の地頭職」というのは、もう少し前のような気がしますが、宝治合戦ののちでも三浦氏傍系の佐原流・三浦盛時(相模三浦氏)は御家人として命脈を保っているので、あるいはその流れで文応の頃でも地頭職を担えたのかもしれません。
この地は、京都・本圀寺の跡地ともいわれます。
Wikipediaには、本国寺(現・本圀寺)が鎌倉から京都へ移ったのは貞和元年(1345年)、四祖日静上人の時とあります。
京都の本圀寺は日蓮宗の大本山(霊跡寺院)で、日蓮宗公式Webには「(本圀寺は)建長5(1253)年、高祖日蓮大聖人が鎌倉松葉ヶ谷に構え22ヵ年住まわれた御小庵の法華堂を前身とします。」とあるので、本国寺が鎌倉から京都に移ったのは確実です。
ただし、鎌倉から移ったのは「松葉ヶ谷の法華堂」(御小庵の法華堂)なので、この法華堂の旧地が問題となります。(諸説あります。)
「御小庵の法華堂」がいまの長勝寺にあったとした場合に、「長勝寺=本圀寺の跡地」説が成り立つことになります。
『新編相模国風土記稿』には「サレド当所ヲ京都本國寺ノ舊蹟ト云ハ疑ベシ。」とあり、『鎌倉市史 社寺編』でも「草創について寺伝は石井長勝が日蓮に帰依して長勝寺をつくるといい、『新編鎌倉志』及び『(新編相模国)風土記稿』もいろいろ書いているが明らかでない。」と、やや突き放した書きぶりです。
『鎌倉市史 社寺編』は、各寺社の縁起や沿革をすこぶる精緻に考証しており、このような書きぶりはめずらしいもの。
とはいえ、同書は「京都に移った本国寺の旧跡に、貞和元年(1345年)日静が寺を再興し石井山長勝寺と名づけた。(『由緒書』)」と、(当山?)由緒書を引用するかたちで「本国寺旧跡」説を紹介しています。
さらに「延徳五年四月二十日付、結城政朝堵状によれば、正行院が、松葉谷法花堂屋地を本国寺の屋地として充行われている。この正行院が長勝寺の塔頭であるとすると、本国寺跡の問題に一つの手がかりとなるであろう。」とし、「御小庵の法華堂」の旧地については名言を避けているようにもみえます。
『新編鎌倉志』と『新編相模国風土記稿』でもややニュアンスが異なり、『新編鎌倉志』では妙法寺や啓運寺まで出てくるので、やはり長勝寺の縁起は一筋縄ではいかないようです。
筆者にはとても「本国寺跡の問題」を整理する力はないので、下記「史料」の原文をご覧ください。(と逃げる。)
なお、山内掲示(鎌倉市)には、「創建:弘長三年(1263年)」とあり、「京都本圀寺の前身と伝えられており、日静の代、貞和元年(1345年)に寺号が京都に移った後、石井山長勝寺と号し今日に至ります。」と記されています。
『新編鎌倉志』『新編相模国風土記稿』ともに「日朗・日印・日靜と次第して居す。日靜は、源(足利)尊氏の叔父なるゆへに、此寺を京都に移し本國寺と号す。」と記しています。
貞和元年(1345年)、日静上人(日隆上人とも)が復興し、石井長勝の名にちなんで長勝寺と名付けたといいます。
本圀寺は「六条門流」の中心寺院です。
六条門流は釈尊を本仏とする一致派の一派とされ、日静門流とも呼ばれます。
日静上人(1298-1369年)は、Wikipediaに「父は藤原北家の末裔上杉頼重、母は足利氏の娘と言われ、姉の上杉清子が征夷大将軍足利尊氏の生母であるため尊氏の叔父とされる。字は豊龍。号は妙龍院。出身は駿河国(現在の静岡県)。六条門流の祖。」とあり、史料類の「日靜は源尊氏の叔父」という記述と一致します。
貞和元年(1345年)3月、本国寺を鎌倉から京都へ移した日静上人は、みずから住していた鎌倉の本国寺旧地を寺院として残したのでは。
ここから、日静上人復興説が出ているのだと思います。
『新編鎌倉志』に中興開山は日際とありますが、詳細は不明です。
天正十九年(1590年)、関東を平定した豊臣秀吉公より寺領四貫三百文の御朱印を賜わったといい、この寺領は江戸時代も承継されたようです。
現在は、2月11日の建国記念日に、市川市中山の法華経寺で百日間堂に籠もり荒行を遂げた僧たちが、寒水を浴びて世界平和と諸人開運を祈祷する「大国祷会成満祭」のお寺として知られています。
また、鎌倉厄除開運帝釋天のお寺としても有名ですが、これは日蓮聖人が松葉ヶ谷法難の際、帝釋天のお使いである白猿に助けられたことを由縁とされているようです。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志 鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
長勝寺 附石井
長勝寺は、石井山と号す。名越坂へ通る道の南の谷にあり。寺内に岩を切抜たる井あり。鎌倉十井の一なり。
故に俗に石井の長勝寺と云ふ。法華宗也。
当寺は、洛陽本國寺の舊蹟なり。今は却て末寺となる。寺僧語て曰く、此地に昔日蓮、菴室を卜て居せり。後日朗・日印・日靜と次第して居す。
日靜は、源尊氏の叔父なるゆへに、此寺を京都に移し本國寺と号す。跡の長勝寺を弟子日叡に相続して住せしむ。日叡寺号を妙法寺と改む。本日叡を妙法坊と云しを以てなり。
其後大倉塔辻へ移し。又其後辻町へ移す。寺僧云、今の辻町の啓運寺なり。近来妙法寺と啓運寺の寺号を●たり。辻町の啓運寺は、元妙法寺なるを、今は啓運寺と云ひ、名越の妙法寺は、元啓運寺なるを、今妙法寺と云ふ。其謂を不知。
今の長勝寺は、荒地なりしを、中比日際法師と云僧、舊地を慕ひ一寺を立、又寺号を長勝寺と号す。故に日際を中興開山と云也。
日際は、房州小湊の人なりと云ふ。其再興の年月、幷に日際の死期も不知。
寺領四貫三百文あり。豊臣秀吉公幷に御当家、代々の御朱印あり。
本尊は釋迦なり。
鐘楼 堂の東にあり。銘あり。
日蓮乞水
名越切通の坂より、鎌倉の方一里半許前、道の南にある小井を云なり。
日蓮、安房國より鎌倉に出給ふ時、此坂にて水を求められしに、此水俄に涌出けると也。
水斗升に過ぎざれども、大旱
にも涸ずと云ふ。甚冷水也。土人云。鎌倉に五名水あり。曰く金龍水、不老水、銭洗水、日蓮乞水、梶原太刀洗水なりと。
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(大町村)長勝寺
松葉谷ノ南方ニアリ。石井山ト号ス。日蓮宗。京都本國寺末。寺伝ニ当所ハ。日蓮菴室ノ地ナリ。其後一寺トナシ。日朗。日印。日靜次第シテ住ス。
靜ハ将軍尊氏ノ叔父ニテ。当寺ヲ京都ニ移ス。今ノ本國寺是ナリ。故ニ当寺ヲ本國寺舊蹟ト称ス。後僧日際(平安元年九月晦日寂ス。)其舊蹟タルヲ追慕シ。更ニ一寺ヲ●建セリ。
際ハ俗稱石井藤五郎長勝ト云ヘリ。故ニ寺ヲ長勝寺ト名ヅク。因テ際ヲ中興開山ト称セリト云フ。サレド当所ヲ京都本國寺ノ舊蹟ト云ハ疑ベシ。
寺寶宗祖ノ筆蹟二幅アリテ。一ハ建長六年。石井藤五郎長勝ヘ授與ノ物。一ハ文應元年九月。松葉谷石井長勝屋鋪、法華堂ニテ書セシ物ト云ヘバ。当所長勝ガ宅地ニテ。日蓮此邊小菴ニ在リシ頃。長勝帰依シテ。爰ニ堂舎ヲ営ミ。其後一寺トナシ。長勝寺ト号セシナラン。
日靜カ本國寺ヲ京都ニ移セシハ。貞和元年ナレバ。夫より四十六年已前。正安元年ニ寂セシ日際。当時本國寺舊蹟ニ一寺ヲ建ト云フモノ。年代事暦合期シ難ク。其訛論スベカラズ。
鎌倉志ニ。長勝寺ハ荒地ナリシヲ。中頃僧日際舊地ヲ慕ヒ一寺ヲ立。又寺号トヲ長勝寺ト號ス。故ニ日際ヲ中興開山ト云フナリ。
際ハは、房州小湊ノ人ト云フ。再興ノ年代。際カ死期モシレズ云々。トアルニ據レバ。当時長勝入道日際。当寺ヲ開基セシガ。本國寺京都に移転ノ後。当寺モ一旦廃寺トナリシヲ。其後日隆再建エリシヨリ。妙法寺ト同ジク。本國寺舊蹟ノ訛傳ハ起リシナルベシ。
天正十八年。小田原陣ノ時。豊臣太閤制札ヲ出セリ。寺領四貫三百文ハ同十九年十一月。御朱印ヲ賜ヘリ。
本尊釋迦ヲ安ス。本堂ハ小田原北條氏ノ臣。遠山因幡守宗爲ガ建立ト云フ。
寺寶
日蓮書二幅 一ハ建長六年正月元日。石井藤五郎長勝授與之トアリ。一ハ文應元年九月三日。松葉谷石井長勝屋鋪法華堂ニテ。御認ナリト書記セリ。
鬼子母神像一軀 長一尺五寸。立像。傳教作。
釋迦像一軀 唐木。長九寸二分。座像運慶作。
大黒像一軀 長一尺四分。日蓮作。
寶陀觀音像一軀 長一尺七寸五分。座像。道潤作。新羅三郎義光。守本尊ト云フ。
山王像一軀 立像。長八寸二分。菅家作ト云フ。
八幡像一軀 金體立像。長一寸八分。将軍賴朝判アリ。
日蓮眞骨塔一基 同歯骨塔一基 古文書二通
釋迦堂 本尊ハ立像ナリ。長一尺九寸。
祖師堂 中央に日蓮。左右に日朗日印ノ像ヲを安ス。
鐘樓 鐘ニ寛永元年鑄造ノ序銘ヲ彫ス。
銚子井 東方ニアリ。日蓮ノ供水ト云フ。寺伝ニハ。日蓮乞水ト唱フトイヘド。是ハ近キアタリ。同名ノ小井アルヲ。混ジ訛レルラン。鎌倉志ニハ。当寺境内ニ。岩ヲ穿チシ井アリ。石井ト号ス。鎌倉十井ノ一ナリト記ス。此井の事歟。今詳ナラズ。
表門 妙法華庵ノ額ヲ扁ス。
駒留木
■ 山内掲示(鎌倉市)
宗派 日蓮宗
山号寺号 石井山長勝寺
創建 弘長3年(1263)
開山 日蓮大聖人
開基 石井長勝
伊豆に配流されてたいた日蓮が鎌倉に戻り、この地にあった石井長勝の邸内に庵を結んだことが当寺の発祥です。
京都本圀寺の前身と伝えられており、日静の代、貞和元年(1345年)に寺号が京都に移った後、石井山長勝寺と号し今日に至ります。
境内の建物と、法華堂は県指定重要文化財。室町時代末期の造営と推定されています。
また、日蓮大聖人の銅像は、鎌倉辻説法を写しています。
毎年二月十一日には、國祷会といわれる厳しい寒さの中で冷水を浴びる荒行が行われます。
■ 『鎌倉市史 社寺編』(鎌倉市)(抜粋)
石井山長勝寺と号する。日蓮宗。京都本国寺の旧地。
開山、日蓮聖人 本尊、日蓮聖人
境内地1017.69坪。
祖師堂、帝釈堂、客殿、尊神堂、龍神堂、石井稲荷社、鐘楼、山門あり。
この寺は本国寺の旧跡と称する。
草創について寺伝は石井長勝が日蓮に帰依して長勝寺をつくるといい、『新編鎌倉志』及び『(新編相模国)風土記稿』もいろいろ書いているが明らかでない。
京都に移った本国寺の旧跡に、貞和元年(1345年)日静が寺を再興し石井山長勝寺と名づけた。(『由緒書』)
天正十八年、秀吉の小田原征伐にあたり、北条氏が当寺の鐘を徴発したため、寛永にいたって、鐘を住持寿仙院日桑が新鋳したという(『新編鎌倉志』)。(中略)
本堂は小田原北条氏の臣遠山因幡守宗為の建立という。
昭和三十三年十月、山門の位置を変更して現在のところに改めた。
延徳五年四月二十日付、結城政朝堵状によれば、正行院が、松葉谷法花堂屋地を本国寺の屋地として充行われている。この正行院が長勝寺の塔頭であるとすると、本国寺跡の問題に一つの手がかりとなるであろう。
-------------------------
鎌倉大町のはずれ、名越切通への登り口辺にあります。
住所は材木座ですが、材木座海岸からは一山越えたところにあるので、大町に近いです。
大町市街から横須賀線を挟んだ山際にあり、奥まった感じの場所ですが、安国論寺や妙法寺にもほど近いところです。
大町方面から横須賀線の名越踏切りを渡り、道を一本横切るとその先が長勝寺の山内です。
山内入口に真新しい寺号標が建っています。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 山門
参道が直角に曲がったところに山門。
脇塀付き切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、水引虹梁両端に獅子漠の木鼻、その上にボリューム感ある四連の斗栱を置く堂々たるつくりです。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 お題目塔
ここから正面の本堂(帝釋堂)に向けて、真っ直ぐに参道が伸びています。
参道途中のお題目塔には「松葉谷」「宗門根本法華堂本圀寺𦾔地」とあります。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 本堂前
本堂前に日蓮聖人像、その尊像を取り囲むように持国天(東方)、増長天(南方),広目天(西方)、多聞天(北方)の四天王立像が御座します。
いずれも精緻なブロンズ像で迫力があります。
5像すべてかはわかりませんが、少なくとも日蓮聖人像は上野の西郷隆盛像造立で有名な彫刻家・高村光雲(1852-1934年)の作といいます。


【写真 上(左)】 水行の場
【写真 下(右)】 水行肝文
持国天の奥手に水行の場があり、こちらで「大国祷会成満祭」の水行が行われます。
覆屋には「水行肝文」が掲げられていました。
その奥には、「久遠」の扁額が掛かる六角堂。


【写真 上(左)】 六角堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂は屋根頂部の基盤に宝珠を置き、宝形造銅板葺とも思われますが、堂宇の規模が大きく確定できません。
三連の扉を置いた向拝の見上げに「帝釋尊天」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 法華堂参道
本堂向かって左手の高みには重要な堂宇が並びます。
山門寄り階段を上った先に法華堂(祖師堂)。
小田原の後北条氏の家臣・遠山因幡守宗為による室町時代末の建立とみられ、県唯一の中世五間堂として神奈川県指定重要文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 法華堂
【写真 下(右)】 法華堂向拝
桁行五間梁間六間寄棟造銅板葺で、向拝には端正な禅宗様の桟唐戸が並び、質素ながら落ち着きのある意匠です。
向拝見上げに「法華堂」の扁額。


【写真 上(左)】 法華堂扁額
【写真 下(右)】 本師堂
その本堂寄りには鐘楼と本師堂。
本師堂は銅板葺、頂部に立派な火焔宝珠を置く八角堂で、向拝には「本師堂」の扁額が掲げられています。
御本尊は釈迦尊像のようです。


【写真 上(左)】 本師堂向拝
【写真 下(右)】 本師堂扁額
その上手には伝説の映画俳優・赤木圭一郎(1939-1961年)の胸像があります。
赤木の記念碑が当山・材木座霊園にあるため、これにちなみ「赤木圭一郎を偲ぶ会」が造立したとのことです。
御首題・御朱印は本堂向かって左手の庫裏にて拝受しました。
御首題と大帝釋天の御朱印を授与されています。
〔 長勝寺の御首題・御朱印 〕

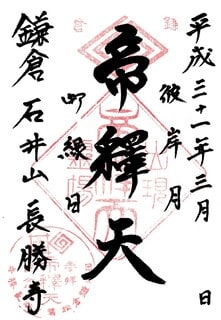
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-13 (B.名越口-8)へつづく。
【 BGM 】
■ David Foster and Olivia Newton-John - The Best Of Me (Official Music Video)
■ Natalie Cole - Split Decision
■ Jon and Vangelis - BESIDE
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)
■ 同-11 (B.名越口-6)から。
37.天照山 蓮乗院(れんじょういん)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-16-15
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:
札所:鎌倉三十三観音霊場第19番、相州二十一ヶ所霊場第11番
蓮乗院は材木座・光明寺の参道右手にある塔頭寺院です。
鎌倉市観光協会Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
蓮乗院の創立年代・開山は不詳ですが、光明寺開山(寛元元年(1243年))より早い時期からこの地にあり、当初は蓮乗寺と号す真言密寺だったと伝わります。
佐介谷の悟真寺(蓮華寺)がこの地に移転の際(寛元三年(1247年))、良忠上人は伽藍落成まで蓮乗院に入られて建築を督励されたといいます。
光明寺(改号後)の子院となり、浄土宗の蓮乗院と改めたと伝わります。
この沿革にもとづき、光明寺の新住職はまず蓮乗院に入ってから光明寺の本山方丈に入るならわしだったといいます。
蓮乗院が塔頭や僧坊ではなく、「子院」と呼ばれることがあるのもこのような格式によるものかも。
本堂に御座す十一面観世音菩薩は鎌倉三十三観音霊場第19番、弘法大師像は相州二十一ヶ所霊場第11番の札所本尊となっています。
『鎌倉市史 寺社編』には「弘法大師の霊場として大正三年東京東山講(魚河岸の人達)が大師像を作って納め、当二十一ヶ所の十一番とした。」とあり、大正三年に相州二十一ヶ所霊場第11番の札所となったことがわかります。
なお、相州二十一ヶ所霊場については、こちらの「31.金龍山 釈満院 宝戒寺」をご覧くださいませ。
『新編鎌倉志』『新編相模国風土記稿』ともに、蓮乗院の御本尊・阿弥陀如来木像は伝・運慶作で、千葉介常胤の守護佛と伝えます。
千葉介常胤および千葉氏については「鎌倉殿の13人」と御朱印-3/22.阿毘盧山 密乗院 大日寺にまとめていますが転記します。
千葉氏は桓武平氏良文流、坂東八平氏(千葉氏・上総氏・三浦氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏)を代表する名族として知られています。
律令制のもとの親王任国(親王が国守に任じられた国。常陸国、上総国、上野国の3国ですべて「大国」)の国守(太守)は親王で、次官として「介」(すけ)がおかれ、実質的な国の長官は「介」ないし「権介」であったとされます。
常陸国の「介」には平家盛、頼盛、経盛、教盛など伊勢平氏(いわゆる「平家」)が任ぜられました。上総国の「介」は早くから坂東に下向した桓武平氏良文流の上総氏、下総国は親王任国ではありませんが、こちらも実質的な長官は「介」ないし「権介」で、良文流の千葉氏が占めて”千葉介”を称し、有力在庁官人としてともに勢力を張りました。
もうひとつの親王任国、上野国(現・群馬県)には、平良文公や千葉氏の嫡流・平(千葉)常将公にまつわる伝承が多く残ります。
(ご参考→『榛名山南東麓の千葉氏伝承』)
千葉氏の妙見信仰にもかかわる逸話が伝わるので、少しく寄り道してみます。
千葉氏の妙見信仰のはじまりについては諸説がありますが、千葉市史のなかに、上野国の妙見菩薩にちなむとする記載がありました。(『千葉市史 第1巻 原始古代中世編』(千葉市地域情報デジタルアーカイブ))
これによると、桓武天皇四世、平高望公の子・平良文公は武蔵国大里郡を本拠とし、良文公と平将門公が結んで上野国に攻め入り、上野国府中花園の村の染谷川で平国香公の大軍と戦った際に示現された妙見菩薩(花園妙見・羊妙見)が、その信仰のはじまりだというのです。
「染谷川の戦い」は、伊勢平氏の祖・国香公と良文流の祖・良文公、そして関東の覇者・将門公という超大物が相戦うスケール感あふれる戦いですが、複数の伝承があるようで、国香公と将門公の対峙は明らかですが、良文公がどちらについたかが定かでありません。(そもそも史実かどうかも不明)
しかし、この戦いで花園妙見の加護を得た将門公と良文公が実質的な勝利を得、国香公は撤収したとされています。
これに類する逸話は『源平闘諍録』にも記されており、千葉市史はこれにもとづいて構成されたのかもしれません。
また、良文公の嫡流、平(千葉)常将公も、上野国の榛名山麓に多くの逸話を残しています。
上野国に大きな所領を得たわけでもない良文公や常将公の足跡が上野国にのこるのは、やはり房総平氏の妙見信仰が上野国所縁であることを示すものかもしれません。
※関連記事 → ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)の6.三鈷山 吉祥院 妙見寺
房総半島に依った桓武平氏は「房総平氏」とも呼ばれ、平忠常公がその始祖とされます。
「房総平氏」の代表格は上総介と千葉介で、鎌倉幕府草創期の当主は上総介広常と千葉介常胤でした。(→千葉氏系図)(千葉一族の歴史と史跡)
石橋山の戦いで敗れ房総で再挙を図った頼朝公ですが、大きな武力をもつ「房総平氏」の上総介と千葉介の協力なくして鎌倉入りは果たせなかったとみられています。
上総介広常は頼朝公に粛清されましたが、頼朝公のサポート役に徹した千葉介常胤はその地位を能く保ちました。
常胤は千葉氏の祖ともされる平常重の嫡男で、保元元年(1156年)の保元の乱では源義朝公の指揮下で戦いました。
治承四年(1180年)、石橋山の戦いで敗れた頼朝公が安房に逃れると、頼朝公は安達盛長を使者として千葉庄(現在の千葉市付近)の常胤に送り、常胤は盛長を迎え入れ、頼朝公に源氏ゆかりの鎌倉に入ることを勧めたとされます。(『吾妻鑑』治承4年9月9日条)
『吾妻鏡』には、同年9月17日に常胤が下総国府に赴き頼朝公に参陣とあります。
この時期、頼朝公が千葉妙見宮を参詣、以降も尊崇篤かったと伝えられ、頼朝公は房総における妙見信仰の大切さを熟知していたのかもしれません。
これに関連して『千葉市における源頼朝の伝説と地域文化の創出に向けて』(丸井敬司氏)には興味ぶかい説が記されています。
頼朝公は鎌倉に入るやいなや鶴岡若宮(現・元八幡宮)を北に遷座(現・鶴岡八幡宮)していますが、同書では「(鶴岡若宮の北遷は)八幡神を道教における四神の玄武と見做したことを意味する。こうした既存の八幡社に妙見の神格を加えるような事例は房総半島には多く確認される。」とし、守谷の妙見八幡、竜(龍)ヶ崎の妙見八幡を例にひいています。
また、「尊光院(現・千葉神社)のように妙見の別当寺を町の北側に建立することで、事実上、八幡社を妙見社とする例もある(こうした八幡に妙見の神格を加えたものを「千葉型の八幡信仰」という)。こうした事例から考えると筆者は、鶴岡若宮は典型的な「千葉型の八幡信仰」の寺院であったと考えている。」とし、鶴岡八幡宮の御遷座に千葉氏の関与ないしは献策があったことを示唆しています。
源平合戦では範頼公に属して一ノ谷の戦いに参加、豊後国で軍功をあげ、奥州討伐では東海道方面の大将に任じられて活躍、鎌倉幕府でも重きをなしたとされています。
頼朝公も常胤を深く信頼し、「(常胤を)以て父となす」という言葉が伝わります。
千葉氏における常胤の存在の大きさは、常胤以降、嫡流は諱に「胤」の一字を受け継ぐことが通例となったことからもうかがわれます。
また、千葉市Webや千葉市立郷土博物館Webでも、千葉氏が大きくとりあげられ、この地における千葉氏の存在の大きさが感じられます。
これは千葉氏が単なる豪族にとどまらず、房総に広がる妙見信仰と深くかかわっていることもあると思われ、実際、千葉市公式Webには「千葉氏と北辰(妙見)信仰」というコンテンツが掲載されています。
常胤の6人の息子の子孫は分家を繰り返しながら全国に広がり、のちに「千葉六党(ちばりくとう)」(千葉氏、相馬氏、武石氏、大須賀氏、国分氏、東氏)と呼ばれる同族勢力を形成しています。
千葉介常胤は真言宗ともゆかりがふかく、あるいは真言密寺の旧・蓮乗寺は千葉介常胤とゆかりがあり、旧・蓮乗寺の御本尊が蓮乗院の御本尊に奉安されたのかもしれませんが、史料類は詳細を伝えていません。
千葉介常胤絡みで当山を訪れる人は多くはないと思いますが、ふたつの霊場の札所なので、こちらの巡拝者の参拝は多いと思われます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志 鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
蓮乗院
総門を入右にあり。光明寺草創以前に、真言宗の寺あり。蓮乗寺と云ふ。今の蓮乗院是なり。開山此寺に居て、光明寺を建立す。故に今に住持入院の時は、先づ此院に入て後方丈に入。古例なりと云ふ。当院の本尊阿彌陀木像、腹内に書付あり。貞治二年(1363年)三月十五日、修復之とあり。伝へ云、運慶が作にて、千葉介常胤が守本尊なりと。
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(材木座村)塔頭 蓮乗院
総門を入て右にあり、当院は本坊草創已前密刹にて蓮乗寺と号せり、開山良忠此寺に居て光明寺を建立す 故に今に住持入院の時は先此院に入て後方丈に入る古例なりと云ふ、
本尊は彌陀の雕像にて肚裏に紙片あり貞治二年(1363年)三月十五日修復之の十二字を記す、是運慶が作にて千葉介常胤が守護佛なりと伝ふ
-------------------------
光明寺の参道・山門の左手にあります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
山門は脇塀付き切妻屋根桟瓦葺のおそらく薬医門かと思います。
見上げに院号扁額。
山内は広くはないものの、しっとりと落ち着きがあります。
相州二十一ヶ所霊場第11番の札所標もありました。


【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場札所標
【写真 下(右)】 (光明寺の?)鐘楼堂
墓域の方に見える斗栱をダイナミックに組み上げた鐘楼堂は、光明寺のものでしょうか。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂
本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。
向拝の張り出しが大きく、なんとなく入母屋造的イメージもありますが、寄棟造平入りかと思います。
シンプルな屋根構成ながら軒上にはしっかり飾り瓦を置いています。


【写真 上(左)】 飾り瓦
【写真 下(右)】 向拝
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に卍紋付きの板蟇股を置いています。
繋ぎ虹梁はないものの、向拝まわりは朱塗りで華やかなイメージのある本堂です。
本堂の扉はわずかに開くので、堂内を拝することができます。
阿弥陀如来、釈迦如来、十一面観世音菩薩、善導大師像、法然上人像、弘法大師像などが安置され、うち十一面観世音菩薩は鎌倉三十三観音霊場第19番、弘法大師像は相州二十一ヶ所霊場第11番の札所本尊となっています。


【写真 上(左)】 観音霊場札所板
【写真 下(右)】 天水鉢
鎌倉三十三観音霊場の札所標も置かれていました。
板ふすま絵や絢爛たる天井絵は逸品とされます。
堂前の天水鉢には月星紋が置かれています。
月星紋は千葉氏の家紋のひとつとされるので、当山と千葉氏のゆかりを示すものかもしれません。
御朱印は本堂右手庫裏にて拝受しました。
〔 蓮乗院の御朱印 〕


【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印

相州二十一ヶ所霊場の御朱印
38.天照山 千手院(せんじゅいん)
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座6-12-8
浄土宗
御本尊:確認中
司元別当:
札所:札所:鎌倉三十三観音霊場第20番
千手院は光明寺の参道・山門の左手にある光明寺の塔頭寺院です。
鎌倉市観光協会Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
開山・縁起等は不明です。
材木座への光明寺移転は寛元三年(1247年)とされるので、寺僧寮である千手院の創立もそれ以降とみられますが、史料類は明示していません。
『新編相模国風土記稿』には「按ずるに、【鎌倉志】専修院に作る、当時しか書記せしにや、詳ならず」とあり、『新編鎌倉志』記載の専修院を千手院とみていますが、「詳ならず」と付記しています。
奉安する千手観世音菩薩は、鎌倉三十三観音霊場第20番の札所本尊です。
「Wikipedia」によると千手観世音菩薩像は、天文元年(1532年)恢誉上人により奉安と伝わるとのこと。
なお、『鎌倉市史 社寺編』には「本尊、千手観音」とあり、拝受した御朱印には「本尊 阿弥陀如来」とあったので、御本尊については不明です。
当初は各地から集まった学僧の修行道場ないし寮でしたが、江戸期には学僧の数も減ったため、近所の子供たちに読み書きなどを教える寺子屋としての役割も果たしたといいます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志 鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
専修院
総門を入左にあり。此二箇院(蓮乗院・専修院)、共に光明寺の寺僧寮なり。
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(材木座村)千手院
僧門を入て、左にあり(按ずるに、【鎌倉志】専修院に作る、当時しか書記せしにや、詳ならず、)千手観音を本尊とす
■ 山内掲示
千手院は浄土宗で、天照山千手院と号し、光明寺の塔頭の一つであり、もとは光明寺の寺僧寮であったと伝えられる。
本尊は千手観音、江戸時代から寺子屋のあった所で、境内には梅の古木があった。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
天照山千手院と号する。
『新編鎌倉志』には専修院とあり、『光明寺志』には千手院とある。浄土宗。
もと光明寺の寺僧寮という。開山不詳。本尊、千手観音。
-------------------------
光明寺の参道・山門の左手にあります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 院号板
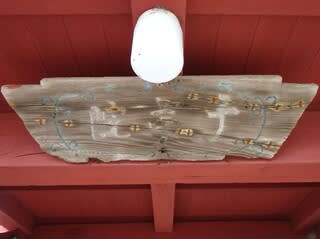

【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 観音霊場札所標
山門は脇塀付き切妻屋根桟瓦葺のおそらく四脚門かと思われます。
「赤門寺」と呼ばれそうな鮮やかな朱色の山門です。
門柱に院号板、見上げに院号扁額を掲げ、門前には鎌倉三十三観音霊場第20番の札所標を置いています。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 参道
山内はかなりの奥行きがあり、緑が多く落ち着いたたたずまい。
参道は本堂前で左手に曲がり、その前の覆屋内には子恵地蔵尊が御座します。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂の様式は不詳ですが、宝形造桟瓦葺の流れ向拝かと思います。
水引虹梁は軒下に連接し両端に角形の木鼻、身舎側に繋ぎ虹梁を伸ばしています。
全体にシンプルでスクエアなイメージがあります。
見上げには鎌倉三十三観音霊場の札所板が掲げられていました。
鎌倉三十三観音霊場の第19番蓮乗院・第20番千手院は光明寺の子院・塔頭、第27番妙高院・第29番龍嶺院は建長寺の塔所、結願第33番佛日庵は円覚寺の塔頭で、とくに妙高院・龍嶺院は一般拝観不可で、原則観音霊場巡拝者のみ山内立ち入り・参拝が許されています。
大寺も多くメジャー霊場のイメージがありますが、意外にマニアックな霊場かもしれません。
(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))


【写真 上(左)】 観音霊場札所板
【写真 下(右)】 芭蕉句碑
境内には、当院の定賢和尚(明治25年寂)の教え子の田中氏が建立したという松尾芭蕉の句碑があります。
春もやヽ 気しきとヽのふ月と梅
かつてあったという梅の古木にちなんで選句したともみられています。
御朱印は山内右手の庫裏にて拝受しました。
比較的メジャーな鎌倉三十三観音霊場の札所なので、ご対応は手慣れておられます。
〔 千手院の御朱印 〕


【写真 上(左)】 阿弥陀如来の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
39.石井山 長勝寺(ちょうしょうじ)
公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市材木座2-12-17
日蓮宗
司元別当:
札所:札所:
長勝寺は日蓮聖人開山とも伝わる日蓮宗の名刹です。
鎌倉市観光協会Web、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
開山・縁起等については諸説ある模様です。
長勝寺は、妙法寺・安国論寺とともに日蓮聖人が鎌倉に入られ最初に営まれた小庵(松葉ヶ谷御小庵の法華堂)の旧地ともみられています。
石井藤五郎長勝が日蓮聖人に帰依し、邸宅を寄進して一寺にしたという伝もあります。
Wikipediaには、石井氏は鎌倉の有力御家人三浦氏(佐原流)の流れといい、石井藤五郎長勝は文応(1260-1261年)の頃、鎌倉松葉ヶ谷付近の地頭職をつとめていたとあります。
また、宝治合戦(1247年)で三浦一族が滅亡の後、出家して日隆と号したとも。
一方、Wikipediaの「大隅石井氏」の項には、大隅石井氏の略系図として「(三浦)義明 - 義澄 - 義村 - 朝村 - 員村 - 盛明 - 義継(石井太郎) - 重義(大隅国に下向)」とあります。
これによると、盛明は宝治合戦(1247年)には誕生しているので、その子石井義継(石井氏初代)は宝治合戦の数十年後には誕生していたことになります。
義継の子石井重義が大隅国(鹿児島県東部)に下向したのは元徳二年(1330年)頃とされるので、石井義継と石井藤五郎長勝は同族関係にあったのかもしれません。
この系譜を信じると、石井藤五郎長勝は佐原流ではなく、三浦義明 - 義澄 - 義村とつながる三浦氏嫡流筋ということになります。
なお、日蓮聖人が名越松葉ヶ谷に草庵を構え布教を開始されたのは建長五年(1253年)といいますから、戦いに敗れ落魄の身にあった長勝が日蓮聖人の教えにふれて出家し、日隆と号したという説は時系列的に符合します。
ただし、戦いに敗れ、出家した三浦一族の身ではおそらく地頭職には就けないので、「文応(1260-1261年)の頃、鎌倉松葉ヶ谷付近の地頭職」というのは、もう少し前のような気がしますが、宝治合戦ののちでも三浦氏傍系の佐原流・三浦盛時(相模三浦氏)は御家人として命脈を保っているので、あるいはその流れで文応の頃でも地頭職を担えたのかもしれません。
この地は、京都・本圀寺の跡地ともいわれます。
Wikipediaには、本国寺(現・本圀寺)が鎌倉から京都へ移ったのは貞和元年(1345年)、四祖日静上人の時とあります。
京都の本圀寺は日蓮宗の大本山(霊跡寺院)で、日蓮宗公式Webには「(本圀寺は)建長5(1253)年、高祖日蓮大聖人が鎌倉松葉ヶ谷に構え22ヵ年住まわれた御小庵の法華堂を前身とします。」とあるので、本国寺が鎌倉から京都に移ったのは確実です。
ただし、鎌倉から移ったのは「松葉ヶ谷の法華堂」(御小庵の法華堂)なので、この法華堂の旧地が問題となります。(諸説あります。)
「御小庵の法華堂」がいまの長勝寺にあったとした場合に、「長勝寺=本圀寺の跡地」説が成り立つことになります。
『新編相模国風土記稿』には「サレド当所ヲ京都本國寺ノ舊蹟ト云ハ疑ベシ。」とあり、『鎌倉市史 社寺編』でも「草創について寺伝は石井長勝が日蓮に帰依して長勝寺をつくるといい、『新編鎌倉志』及び『(新編相模国)風土記稿』もいろいろ書いているが明らかでない。」と、やや突き放した書きぶりです。
『鎌倉市史 社寺編』は、各寺社の縁起や沿革をすこぶる精緻に考証しており、このような書きぶりはめずらしいもの。
とはいえ、同書は「京都に移った本国寺の旧跡に、貞和元年(1345年)日静が寺を再興し石井山長勝寺と名づけた。(『由緒書』)」と、(当山?)由緒書を引用するかたちで「本国寺旧跡」説を紹介しています。
さらに「延徳五年四月二十日付、結城政朝堵状によれば、正行院が、松葉谷法花堂屋地を本国寺の屋地として充行われている。この正行院が長勝寺の塔頭であるとすると、本国寺跡の問題に一つの手がかりとなるであろう。」とし、「御小庵の法華堂」の旧地については名言を避けているようにもみえます。
『新編鎌倉志』と『新編相模国風土記稿』でもややニュアンスが異なり、『新編鎌倉志』では妙法寺や啓運寺まで出てくるので、やはり長勝寺の縁起は一筋縄ではいかないようです。
筆者にはとても「本国寺跡の問題」を整理する力はないので、下記「史料」の原文をご覧ください。(と逃げる。)
なお、山内掲示(鎌倉市)には、「創建:弘長三年(1263年)」とあり、「京都本圀寺の前身と伝えられており、日静の代、貞和元年(1345年)に寺号が京都に移った後、石井山長勝寺と号し今日に至ります。」と記されています。
『新編鎌倉志』『新編相模国風土記稿』ともに「日朗・日印・日靜と次第して居す。日靜は、源(足利)尊氏の叔父なるゆへに、此寺を京都に移し本國寺と号す。」と記しています。
貞和元年(1345年)、日静上人(日隆上人とも)が復興し、石井長勝の名にちなんで長勝寺と名付けたといいます。
本圀寺は「六条門流」の中心寺院です。
六条門流は釈尊を本仏とする一致派の一派とされ、日静門流とも呼ばれます。
日静上人(1298-1369年)は、Wikipediaに「父は藤原北家の末裔上杉頼重、母は足利氏の娘と言われ、姉の上杉清子が征夷大将軍足利尊氏の生母であるため尊氏の叔父とされる。字は豊龍。号は妙龍院。出身は駿河国(現在の静岡県)。六条門流の祖。」とあり、史料類の「日靜は源尊氏の叔父」という記述と一致します。
貞和元年(1345年)3月、本国寺を鎌倉から京都へ移した日静上人は、みずから住していた鎌倉の本国寺旧地を寺院として残したのでは。
ここから、日静上人復興説が出ているのだと思います。
『新編鎌倉志』に中興開山は日際とありますが、詳細は不明です。
天正十九年(1590年)、関東を平定した豊臣秀吉公より寺領四貫三百文の御朱印を賜わったといい、この寺領は江戸時代も承継されたようです。
現在は、2月11日の建国記念日に、市川市中山の法華経寺で百日間堂に籠もり荒行を遂げた僧たちが、寒水を浴びて世界平和と諸人開運を祈祷する「大国祷会成満祭」のお寺として知られています。
また、鎌倉厄除開運帝釋天のお寺としても有名ですが、これは日蓮聖人が松葉ヶ谷法難の際、帝釋天のお使いである白猿に助けられたことを由縁とされているようです。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志 鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
長勝寺 附石井
長勝寺は、石井山と号す。名越坂へ通る道の南の谷にあり。寺内に岩を切抜たる井あり。鎌倉十井の一なり。
故に俗に石井の長勝寺と云ふ。法華宗也。
当寺は、洛陽本國寺の舊蹟なり。今は却て末寺となる。寺僧語て曰く、此地に昔日蓮、菴室を卜て居せり。後日朗・日印・日靜と次第して居す。
日靜は、源尊氏の叔父なるゆへに、此寺を京都に移し本國寺と号す。跡の長勝寺を弟子日叡に相続して住せしむ。日叡寺号を妙法寺と改む。本日叡を妙法坊と云しを以てなり。
其後大倉塔辻へ移し。又其後辻町へ移す。寺僧云、今の辻町の啓運寺なり。近来妙法寺と啓運寺の寺号を●たり。辻町の啓運寺は、元妙法寺なるを、今は啓運寺と云ひ、名越の妙法寺は、元啓運寺なるを、今妙法寺と云ふ。其謂を不知。
今の長勝寺は、荒地なりしを、中比日際法師と云僧、舊地を慕ひ一寺を立、又寺号を長勝寺と号す。故に日際を中興開山と云也。
日際は、房州小湊の人なりと云ふ。其再興の年月、幷に日際の死期も不知。
寺領四貫三百文あり。豊臣秀吉公幷に御当家、代々の御朱印あり。
本尊は釋迦なり。
鐘楼 堂の東にあり。銘あり。
日蓮乞水
名越切通の坂より、鎌倉の方一里半許前、道の南にある小井を云なり。
日蓮、安房國より鎌倉に出給ふ時、此坂にて水を求められしに、此水俄に涌出けると也。
水斗升に過ぎざれども、大旱
にも涸ずと云ふ。甚冷水也。土人云。鎌倉に五名水あり。曰く金龍水、不老水、銭洗水、日蓮乞水、梶原太刀洗水なりと。
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(大町村)長勝寺
松葉谷ノ南方ニアリ。石井山ト号ス。日蓮宗。京都本國寺末。寺伝ニ当所ハ。日蓮菴室ノ地ナリ。其後一寺トナシ。日朗。日印。日靜次第シテ住ス。
靜ハ将軍尊氏ノ叔父ニテ。当寺ヲ京都ニ移ス。今ノ本國寺是ナリ。故ニ当寺ヲ本國寺舊蹟ト称ス。後僧日際(平安元年九月晦日寂ス。)其舊蹟タルヲ追慕シ。更ニ一寺ヲ●建セリ。
際ハ俗稱石井藤五郎長勝ト云ヘリ。故ニ寺ヲ長勝寺ト名ヅク。因テ際ヲ中興開山ト称セリト云フ。サレド当所ヲ京都本國寺ノ舊蹟ト云ハ疑ベシ。
寺寶宗祖ノ筆蹟二幅アリテ。一ハ建長六年。石井藤五郎長勝ヘ授與ノ物。一ハ文應元年九月。松葉谷石井長勝屋鋪、法華堂ニテ書セシ物ト云ヘバ。当所長勝ガ宅地ニテ。日蓮此邊小菴ニ在リシ頃。長勝帰依シテ。爰ニ堂舎ヲ営ミ。其後一寺トナシ。長勝寺ト号セシナラン。
日靜カ本國寺ヲ京都ニ移セシハ。貞和元年ナレバ。夫より四十六年已前。正安元年ニ寂セシ日際。当時本國寺舊蹟ニ一寺ヲ建ト云フモノ。年代事暦合期シ難ク。其訛論スベカラズ。
鎌倉志ニ。長勝寺ハ荒地ナリシヲ。中頃僧日際舊地ヲ慕ヒ一寺ヲ立。又寺号トヲ長勝寺ト號ス。故ニ日際ヲ中興開山ト云フナリ。
際ハは、房州小湊ノ人ト云フ。再興ノ年代。際カ死期モシレズ云々。トアルニ據レバ。当時長勝入道日際。当寺ヲ開基セシガ。本國寺京都に移転ノ後。当寺モ一旦廃寺トナリシヲ。其後日隆再建エリシヨリ。妙法寺ト同ジク。本國寺舊蹟ノ訛傳ハ起リシナルベシ。
天正十八年。小田原陣ノ時。豊臣太閤制札ヲ出セリ。寺領四貫三百文ハ同十九年十一月。御朱印ヲ賜ヘリ。
本尊釋迦ヲ安ス。本堂ハ小田原北條氏ノ臣。遠山因幡守宗爲ガ建立ト云フ。
寺寶
日蓮書二幅 一ハ建長六年正月元日。石井藤五郎長勝授與之トアリ。一ハ文應元年九月三日。松葉谷石井長勝屋鋪法華堂ニテ。御認ナリト書記セリ。
鬼子母神像一軀 長一尺五寸。立像。傳教作。
釋迦像一軀 唐木。長九寸二分。座像運慶作。
大黒像一軀 長一尺四分。日蓮作。
寶陀觀音像一軀 長一尺七寸五分。座像。道潤作。新羅三郎義光。守本尊ト云フ。
山王像一軀 立像。長八寸二分。菅家作ト云フ。
八幡像一軀 金體立像。長一寸八分。将軍賴朝判アリ。
日蓮眞骨塔一基 同歯骨塔一基 古文書二通
釋迦堂 本尊ハ立像ナリ。長一尺九寸。
祖師堂 中央に日蓮。左右に日朗日印ノ像ヲを安ス。
鐘樓 鐘ニ寛永元年鑄造ノ序銘ヲ彫ス。
銚子井 東方ニアリ。日蓮ノ供水ト云フ。寺伝ニハ。日蓮乞水ト唱フトイヘド。是ハ近キアタリ。同名ノ小井アルヲ。混ジ訛レルラン。鎌倉志ニハ。当寺境内ニ。岩ヲ穿チシ井アリ。石井ト号ス。鎌倉十井ノ一ナリト記ス。此井の事歟。今詳ナラズ。
表門 妙法華庵ノ額ヲ扁ス。
駒留木
■ 山内掲示(鎌倉市)
宗派 日蓮宗
山号寺号 石井山長勝寺
創建 弘長3年(1263)
開山 日蓮大聖人
開基 石井長勝
伊豆に配流されてたいた日蓮が鎌倉に戻り、この地にあった石井長勝の邸内に庵を結んだことが当寺の発祥です。
京都本圀寺の前身と伝えられており、日静の代、貞和元年(1345年)に寺号が京都に移った後、石井山長勝寺と号し今日に至ります。
境内の建物と、法華堂は県指定重要文化財。室町時代末期の造営と推定されています。
また、日蓮大聖人の銅像は、鎌倉辻説法を写しています。
毎年二月十一日には、國祷会といわれる厳しい寒さの中で冷水を浴びる荒行が行われます。
■ 『鎌倉市史 社寺編』(鎌倉市)(抜粋)
石井山長勝寺と号する。日蓮宗。京都本国寺の旧地。
開山、日蓮聖人 本尊、日蓮聖人
境内地1017.69坪。
祖師堂、帝釈堂、客殿、尊神堂、龍神堂、石井稲荷社、鐘楼、山門あり。
この寺は本国寺の旧跡と称する。
草創について寺伝は石井長勝が日蓮に帰依して長勝寺をつくるといい、『新編鎌倉志』及び『(新編相模国)風土記稿』もいろいろ書いているが明らかでない。
京都に移った本国寺の旧跡に、貞和元年(1345年)日静が寺を再興し石井山長勝寺と名づけた。(『由緒書』)
天正十八年、秀吉の小田原征伐にあたり、北条氏が当寺の鐘を徴発したため、寛永にいたって、鐘を住持寿仙院日桑が新鋳したという(『新編鎌倉志』)。(中略)
本堂は小田原北条氏の臣遠山因幡守宗為の建立という。
昭和三十三年十月、山門の位置を変更して現在のところに改めた。
延徳五年四月二十日付、結城政朝堵状によれば、正行院が、松葉谷法花堂屋地を本国寺の屋地として充行われている。この正行院が長勝寺の塔頭であるとすると、本国寺跡の問題に一つの手がかりとなるであろう。
-------------------------
鎌倉大町のはずれ、名越切通への登り口辺にあります。
住所は材木座ですが、材木座海岸からは一山越えたところにあるので、大町に近いです。
大町市街から横須賀線を挟んだ山際にあり、奥まった感じの場所ですが、安国論寺や妙法寺にもほど近いところです。
大町方面から横須賀線の名越踏切りを渡り、道を一本横切るとその先が長勝寺の山内です。
山内入口に真新しい寺号標が建っています。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 山門
参道が直角に曲がったところに山門。
脇塀付き切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、水引虹梁両端に獅子漠の木鼻、その上にボリューム感ある四連の斗栱を置く堂々たるつくりです。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 お題目塔
ここから正面の本堂(帝釋堂)に向けて、真っ直ぐに参道が伸びています。
参道途中のお題目塔には「松葉谷」「宗門根本法華堂本圀寺𦾔地」とあります。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 本堂前
本堂前に日蓮聖人像、その尊像を取り囲むように持国天(東方)、増長天(南方),広目天(西方)、多聞天(北方)の四天王立像が御座します。
いずれも精緻なブロンズ像で迫力があります。
5像すべてかはわかりませんが、少なくとも日蓮聖人像は上野の西郷隆盛像造立で有名な彫刻家・高村光雲(1852-1934年)の作といいます。


【写真 上(左)】 水行の場
【写真 下(右)】 水行肝文
持国天の奥手に水行の場があり、こちらで「大国祷会成満祭」の水行が行われます。
覆屋には「水行肝文」が掲げられていました。
その奥には、「久遠」の扁額が掛かる六角堂。


【写真 上(左)】 六角堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝
本堂は屋根頂部の基盤に宝珠を置き、宝形造銅板葺とも思われますが、堂宇の規模が大きく確定できません。
三連の扉を置いた向拝の見上げに「帝釋尊天」の扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 法華堂参道
本堂向かって左手の高みには重要な堂宇が並びます。
山門寄り階段を上った先に法華堂(祖師堂)。
小田原の後北条氏の家臣・遠山因幡守宗為による室町時代末の建立とみられ、県唯一の中世五間堂として神奈川県指定重要文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 法華堂
【写真 下(右)】 法華堂向拝
桁行五間梁間六間寄棟造銅板葺で、向拝には端正な禅宗様の桟唐戸が並び、質素ながら落ち着きのある意匠です。
向拝見上げに「法華堂」の扁額。


【写真 上(左)】 法華堂扁額
【写真 下(右)】 本師堂
その本堂寄りには鐘楼と本師堂。
本師堂は銅板葺、頂部に立派な火焔宝珠を置く八角堂で、向拝には「本師堂」の扁額が掲げられています。
御本尊は釈迦尊像のようです。


【写真 上(左)】 本師堂向拝
【写真 下(右)】 本師堂扁額
その上手には伝説の映画俳優・赤木圭一郎(1939-1961年)の胸像があります。
赤木の記念碑が当山・材木座霊園にあるため、これにちなみ「赤木圭一郎を偲ぶ会」が造立したとのことです。
御首題・御朱印は本堂向かって左手の庫裏にて拝受しました。
御首題と大帝釋天の御朱印を授与されています。
〔 長勝寺の御首題・御朱印 〕

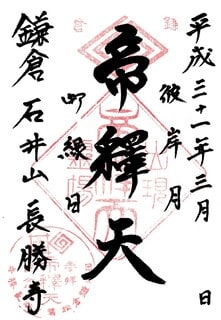
【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-13 (B.名越口-8)へつづく。
【 BGM 】
■ David Foster and Olivia Newton-John - The Best Of Me (Official Music Video)
■ Natalie Cole - Split Decision
■ Jon and Vangelis - BESIDE
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-11 (B.名越口-6)
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)から。
ここから材木座エリアに入ります。
36.天照山 蓮華院 光明寺(こうみょうじ)
公式Web
「新纂 浄土宗大辞典/光明寺」
鎌倉市材木座6-17-19
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:
札所:関東十八檀林10、鎌倉六阿弥陀霊場第3番、鎌倉三十三観音霊場第18番、鎌倉二十四地蔵霊場第22番、三浦半島四十八阿弥陀霊場第48番、東国花の寺百ヶ寺霊場鎌倉第2番、七観音霊場第3番、小田急沿線花の寺四季めぐり第25番
光明寺は材木座にある浄土宗の大本山です。
公式Web、「新纂 浄土宗大辞典/光明寺」、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
光明寺の創立は寛元元年(1243年)、開山は浄土宗三祖然阿良忠上人(1199-1287年・記主禅師)といいます。
良忠上人は正治元年(1199年)石見国三隅庄に生まれ、38歳で聖光上人のお弟子となり、学究ののち法然上人の教えを受け継がれて浄土宗の三祖になられました。
浄土宗の宗祖は法然上人で、二祖は久留米善導寺を開かれた聖光上人(弁長)です。
法然上人の寂後、浄土教学は大きく以下の4流(浄土四流)に分かれました。
・三鈷寺証空の西山義(西山派)
・善導寺弁長の鎮西義(鎮西派)
・長楽寺隆寛の長楽寺義
・九品寺長西の九品寺義
うち、浄土宗主流は弁長(聖光上人)の鎮西義(鎮西派)となり、良忠上人はこの鎮西義(鎮西派)を継がれました。
---------------------------------
建暦元年(1211年)良忠上人は13歳のとき、出雲国の天台宗寺門派鰐淵寺の月珠房信暹門弟となり、16歳で出家受戒。
鰐淵寺では天台寺門派、同山門派等の天台密教を相承したといいます。
嘉禎二年(1236年)九州に下向、筑後国上妻の天福寺で浄土宗二祖の聖光上人に面謁、数々の教えを相伝。宗論を撰述し、聖光上人の印可を受けました。
暦仁元年(1238年)から約10年間石見国~安芸国を教化。
高野山明王院学頭の源朝阿闍梨が安芸国に左遷された折、良忠上人は源朝阿闍梨に師事して真言密教を学んだともいいます。
建長元年(1249年)頃、信濃善光寺を経て下総に向われ千葉氏一族の外護を受け、常陸、上総、下総三国の教化活動と浄土宗典の講述をなされました。
正元元年(1259年)頃鎌倉に移住。
ただし、仁治元年(1240年)鎌倉入り説もあります。
浄土宗の立教開宗の書ともされる『選択本願念仏集』(選択集/せんちゃくしゅう)、浄土三部経(『無量寿経』『観無量寿経(観経)』『阿弥陀経』)、『観経疏』(『観経』の注釈書)などの講述を究められたといいます。
東密(真言密教)、台密(天台密教)と幅広く学ばれた良忠上人は、浄土宗論の撰述・講述でも卓越した才をあらわされたのではないでしょうか。
鎌倉では幕府の評定衆・大仏(北条)朝直の帰依を得て佐介ヶ谷に悟真寺を創建。
朝直は北条時政の子息・北条時房(鎌倉幕府初代連署)の子につき相応の権力を有していたとみられ、バックアップは安定していたのでは。
良忠上人は朝直の子時遠からも帰依を受け、専修念仏の指導的な立場を担われたといいます。
なお、寺伝では当山開基は鎌倉幕府第四代執権・北条経時公とされています。
悟真寺については後述しますが、悟真寺(蓮華寺)を光明寺の前身寺院とすることについては年代的な不整合もみられ、異説もあるようです。
文永八年(1271年)、良忠上人は極楽寺の良観・理智光寺の道教・浄光明寺の行敏らとともに日蓮宗に対抗するとともに、比叡山修学中の良暁を鎌倉に呼び寄せ浄土の奥義を授けたといいます。
当時の鎌倉では法然門流のうち、長楽寺義の南無房智慶・願行円満、西山義西谷流の観智・行観、諸行本願義の念空道教・性仙道空らがそれぞれの浄土教を布教・展開していました。
したがって良忠上人は、独自の教学を強く打ち出す必要がありました。
建治二年(1276年)良忠上人は上洛され、宗祖法然上人の遺弟を尋ねて法然上人の遺文の収集に努めたといいます。
また、良忠上人の教学は、浄土教学(法然門流)の長楽寺義・九品寺義・西山義(東山義・深草義)との討論(教学論争)によって研ぎ澄まされたとみられています。
そして各種の教学講述や法然上人の遺文類をもとに、『決疑鈔』(五巻本)を完成されました。
良忠上人は弘安九年(1286年)の秋、鎌倉に再度下向されました。
その直後、弟子の良暁に授与された付法状で、法然—聖光—良忠の「三代相伝」をいい、「三代之義勢」を表明されたといいます。
弘安十年(1287年)89歳をもって入寂。
生前の功績が認められ、伏見天皇より「記主禅師」の謚号を賜りました。
良忠上人の寂後、その門流は以下の6派に分かれました。
・白旗派(良暁)
・藤田派(性心)
・名越派(尊観)
・三条派(道光)
・一条派(然空)
・木幡派(慈心)
うち白旗派が浄土宗(鎮西義)の主流となり、現在に至っています。
光明寺は白旗派を代表する名刹です。
名越派は尊観が鎌倉名越谷善導寺で布教したため善導寺義ともいい、善導寺は大町の安養院(浄土宗)の前身のため、大町~材木座にかけては良忠上人の影響がとりわけ強いエリアです。
※ 善導寺および名越谷善導寺については、■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)の24.安養院を参照願います。
【 悟真寺・蓮華寺 】(ごしんじ・れんげじ)
正嘉元年(1257年)頃(仁治元年(1240年)説あり)、下総から鎌倉入りした良忠上人は、はじめ慈恩坊を頼って大仏勧進聖の浄光を尋ね、浄光は大仏谷に一宇を建てて良忠上人はここに住されたと伝えます。
間もなく大仏(北条)朝直の支援を得て、佐介ヶ谷に悟真寺を創建といいます。
寺号については、浄土第三祖・善導大師入山の終南山悟真寺由来との説があります。
のちに蓮華寺と改名され、材木座へ移転して浄土宗大本山光明寺となったため、光明寺の前身寺院とされます。
悟真寺から蓮華寺への改号の理由ははっきりせず、蓮華寺から光明寺への改号は北条経時の霊夢によるという伝承もありますが、こちらもはっきりしません。
また、佐介谷から材木座への移転の理由も時期も、多くの史料類は明示していません。
悟真寺については後述しますが、悟真寺・蓮華寺を光明寺の前身寺院とすることについては史料により年代的な不整合もみられ、異説もあるようです。
今回、史料・資料類を当たってみると2つの時系列説があることがわかります。
ひとつは『新纂 浄土宗大辞典』系のもの、もうひとつは『新編鎌倉志』系のものです。
【A.『新纂 浄土宗大辞典』系説】
正元元年(1259年)頃
良忠上人 下総から鎌倉に移住
佐介ヶ谷に建立された悟真寺に入る
建治二年(1276年)
良忠上人 鎌倉から上洛
弘安九年(1286年)
良忠上人 京から鎌倉へ下向
弘安十年(1287年)
良忠上人 鎌倉にて八九歳で入寂
後継者の良暁上人は悟真寺を中心に教線の拡張を計る
正中二年(1325年)頃
良暁上人は悟真寺から蓮華寺と寺名を改めた
九世祐崇上人(1426-1509)のとき
佐介ヶ谷の蓮華寺を材木座の現在地に移し、光明寺と改称したともいわれる
明応四年(1495年)
祐崇上人は後土御門天皇の勅命により浄土教を講説
光明寺は勅願寺と関東総本山となる
【B.『新編鎌倉志』系説】
仁治元年(1240年)
良忠上人鎌倉に入られる
寛元元年(1243年)
北条経時、佐介谷に悟真寺を良忠上人を開山として開基
寛元三年(1247年)以前
良忠上人、材木座の蓮乗院に入られ光明寺建立の準備をされる
寛元三年(1247年)
悟真寺(蓮華寺)が材木座に移り光明寺と改号
弘安十年(1287年)
良忠上人 鎌倉にて八九歳で入寂
※ただし、蓮華寺跡(佐介谷)の項に「光明寺、本此地にあって、蓮華寺と号す。後に光明寺と改む。『鎌倉大日記』に、建長三年(1251年)、経時が為に、佐介に於て蓮華寺建立、住持良忠とあり。良忠此谷に居住ありしゆへに、佐介の上人と云ふなり。」との記事があり、上記と整合しません。
A.『新纂 浄土宗大辞典』系説では、弘安十年(1287年)良忠上人が八九歳で入寂されたときには佐介谷悟真寺が存在し、光明寺(1426年以降の移転・改称)はまだありません。
B.『新編鎌倉志』系説では、良忠上人が材木座の蓮乗院に入ってみずから光明寺建立の準備をされ、寛元三年(1247年)悟真寺(蓮華寺)が材木座に移り光明寺に改号という流れです。
以上、A説とB説では年代的に隔たりがあるので、この二説が混在すると時系列が不整合となります。
光明寺の前身寺院の沿革に諸説あるのは、このような背景があるためと思われます。
なお、光明寺公式Webや現地案内板では光明寺の創立を寛元元年(1243年)としているので、B.『新編鎌倉志』系説が定説として流布している模様です。
関連して、『新編鎌倉志』『新編相模国風土記稿』の「光明寺・善導堂」の項には気になる記述があります。
善導堂はもと光明寺の海側の総門内松葉林中にあったといいます。
御本尊の善導大師(613-681年)は、唐時代の中国の僧で「浄土五祖」の第三祖とされ、その教えは法然上人・親鸞上人に大きな影響を与えました。
---------------------------------
【善導堂縁起】
善導大師の霊像が唐船で筑紫に渡来したとき、鎮西善導寺の開山・聖光上人の夢に善導大師があらわれて「われ筥崎にあり、来り迎へよ」とお告げがありました。
聖光上人が筥崎に来てみると果して善導大師の霊像がみつかり、一宇を建立して霊像を安置し、その後善導寺に遷しました。
聖光上人はこの霊像を良忠上人に託しましたが、良忠上人が関東巡錫に出立される際、この霊像に向かい「わたしはこれから関東教化のため出立します。どうぞ願わくば教化有縁の地を示し給え」と念じて、尊像を筑紫の海中に投じたといいます。
良忠上人は鎌倉の佐介谷に住しましたが、あるとき由比の浜辺に光明が満ちて、かの霊像が忽然とお姿をあらわしました。
良忠上人は霊像漂着の地が浄土教学有縁の地と確信され、一宇を建立して霊像を安じました。
これが光明寺といいます。
---------------------------------
上の善導堂縁起によると、良忠上人は佐介谷の悟真寺(ないし蓮華寺)に住されていましたが、善導大師の霊像の霊験を目の当たりにして材木座の海岸に一宇を建立、これが光明寺(の前身)ということになります。
つまり、佐介谷に悟真寺(蓮華寺)が存在した時点で、すでに材木座の海岸にも一宇(善導堂)があったという見方です。
佐介谷の悟真寺(蓮華寺)が材木座に移り光明寺と改めたのは良忠上人寂後としても、上人が材木座に建立された善導堂の地に移ったという流れなのかもしれません。
寺号については史料に「光明赫奕して霊像が忽然と由比濱に着岸」とあるので、あるいはこの縁起から由来という想像も浮かびます。
なお、悟真寺→蓮華寺→光明寺の改号については、以前別記事(■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-8/蓮花寺)にてとり上げています。興味のある方はご参照くださいませ。
光明寺は、その後も第五代執権・北条時頼公をはじめ歴代執権の帰依を受けました。
関東における念仏道場の中心となり、七堂伽藍を整え、後土御門天皇より「関東総本山」の称号を賜り勅願寺とされ、「関東総本山」ともされました。
後土御門天皇の帰依を受け、紫衣を許された八世観誉祐崇上人は中興開山とされています。
上記のA説によれば佐介谷の蓮華寺を現在地(材木座)に移し、光明寺と改めたのは祐崇上人ですから、この業績も認められてのことかもしれません。
徳川家康公は当山を「関東十八檀林」の筆頭に位置づけ、念仏信仰、仏教研鑽の根本道場の地位を固めました。(※檀林とは徳川幕府が定めた学問所です。)
同じ大本山の芝・増上寺は徳川家菩提寺で、当山とは役割を分けていたようです。
浄土宗公式Webによると、現在の主要寺院の格式は以下のとおりです。
総本山
・知恩院(京都市東山区)
大本山(7寺院)
・増上寺(港区芝公園)
・金戒光明寺(京都市左京区)
・百萬遍知恩寺(京都市左京区)
・清浄華院(京都市上京区)
・善導寺(福岡県久留米市)
・光明寺(神奈川県鎌倉市)
・善光寺大本願(長野県長野市)
光明寺は関東にふたつしかない浄土宗大本山で、たいへん高い寺格をもちます。
筆者は光明寺の御朱印帳をもって関東の浄土宗寺院を回ったことがあるのですが、いくつかの寺院で「光明寺様の御朱印帳に書き入れるのは畏れ多い。」とのご住職のお言葉をいただきました。
それだけ高い格式・権威をもたれているということかと。
当山は譜代大名・内藤家の菩提所です。
内藤氏はふるくから松平氏(徳川氏)に仕えた譜代の家臣の家柄で、上総佐貫藩主を経て陸奥磐城平藩主から日向延岡藩7万石の藩主に転じました。
磐城平藩第3代藩主・内藤義概(1619-1685年)の代まで、内藤家菩提寺は江戸霊厳寺でしたが、義概は位牌堂と石塔を光明寺に移し、寺領百五十石を寄進して光明寺の大旦那となりました。
別に新庄家などの墓所もあり、こうした武家の旦那衆が江戸期の当山の経営を支えたともみられています。
当山は「お十夜」発祥の寺でもあります。
お十夜法要は、第九世観譽祐崇上人の代(明応四年(1495年))に始まりました。
後土御門天皇の勅許を受け、引声阿弥陀経と引声念仏による十夜法要を勤めるようになり、いまも毎年十月の四日間盛大に法要が勤められています。
関東大震災で大きな被害を被りましたが復興し、いまも浄土宗大本山、鎌倉を代表する名刹としての存在感を放っています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志 鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
光明寺
光明寺は、本は佐介谷に在しを、後に此地に移す。当寺開山の伝に、寛元元年(1243年)五月三日、前武州太守平経時、佐介谷に於て浄刹を建立し、蓮華寺と号し、良忠を導師として、供養をのべらる。後に経時、霊夢有て光明寺と改む。方丈を蓮華院と名くとあり。(中略)
開山は記主禅師、諱は良忠、然阿と号す。石州三隅荘人なり。父は宰相藤原頼定、母は伴氏、正治元年(1199年)七月二十七日に生る。弘安十年(1287年)七月六日に示寂。年八十九。聖光上人の弟子なり。聖光は法然上人の弟子なり。
良忠弟子六人有て、今に六派相分る。
所謂六派は、京都の三箇は、一條ノ禮阿、三條ノ道光、小幡ノ慈心なり。
関東の三箇は、白旗ノ寂慧(光明寺二世)、名越尊観(大澤流義の祖)、藤田ノ持阿(藤田流義の祖)、是を六派と云ふ。
当寺は六派の本寺なり。六派の内、白旗・大澤の両派のみ今尚盛なり。四派は断絶す。
十七箇寺の檀林は白旗なり。(中略)
外門 昔佐介谷に有し時、平経時の弟時頼外門に額を掛て、佐介浄刹と号すと。今は額なし。
山門 額、天照山とあり。後花園帝の宸筆なり。
開山堂 開山木像を安ず。自作なり。勅諡記主禅師とある額を此堂に掛しとなり。
客殿 三尊を安ず。阿彌陀の像は運慶作。観音勢至像、作者不知。
方丈 蓮華院と号す。阿彌陀の像を安ず、此像も運慶が作にて肚裏に運慶が骨を収むと云ふ。
祈祷堂 今は念佛堂と云ふ。本尊は阿彌陀、慧心の作と云ふ。左方に辯才天の像あり。昔江島辯才天の像、或時暴風吹来て、此寺前海濱に寄泊る。里民相議して彼島帰す。其後又来る。如此する事三度なり。因て寺僧御●を取に、永く此寺に止まるべき由なり。故に爰に安ずと云。右の方に善導像あり。自作と云。
寺寶
勅額 二枚
一枚は、後宇多帝の宸筆、勅諡記主禅師とあり。
一枚は、後土御門帝の宸筆、祈禱の二字なり。
善導塚 ※由緒は『新編相模国風土記稿』にほぼ同じにつき略。
蓮華寺跡(佐介谷)(同上資料)
今俗に光明寺畠と云ふ。光明寺、本此地にあって、蓮華寺と号す。後に光明寺と改む。
『鎌倉大日記』に、建長三年(1251年)、経時が為に、佐介に於て蓮華寺建立、住持良忠とあり。良忠此谷に居住ありしゆへに、佐介の上人と云ふなり。光明寺の條下及ひ『記主上人傳』に詳也。
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(材木座村)光明寺
天照山蓮華院と号す、浄土宗、関東総本山と称し十八檀林の第一位にして六派の本寺なり、仁治元年(1240年)北條武蔵守経時佐介谷に於て浄刹を創立し蓮華寺と名つく時に僧良忠悟眞寺に在り経時延て開山初祖とし、武州足立郡箕田の地を寄附して寺領とす
寛元元年(1243年)今の地に移転して堂宇を修復す斯て経時夢兆に感じて光明寺と改む(中略)寶治二年(1248年)良忠洛の尼院にあり、後嵯峨上皇の戒師となり、香衣幷に上人号を賜ふ
建長元年(1249年)鎌倉に帰る、時頼由良の地を割て寄附せり、良忠弘安十年(1287年)七月六日寂す 永仁元年(1293年)勅謚ありて記主禅師と号す
建武二年九月當寺造營の爲修理田一町を寄附あり(注釈)
貞治二年二月足利基氏上總國湯井號觀應三年の例に任せ、寄附ある旨證状を授與す(注釈)
其後祐崇永正六年(1509年)寂す、当寺の住職たり、是を中興の祖とす
本堂 開山の像を置く
客殿 三尊の彌陀を安ず 中尊は運慶作余は作人知れず
方丈 彌陀を安ず 運慶作にて肚裏に運慶が骨を収むと云ふ
【寺寶】(中略)
紫石硯一面 唐玄宗の松蔭の硯と称す、相伝て平重衡受戒の時、法然に与ふ、法然是を聖光に譲り、聖光又記主に譲ると云へど、背に永享(1429年)の年号あり、是法然記主の時代にあらず、是非詳ならず
二尊堂 善導大師 自作、衣に金泥にて、彌陀經を書たり
辨財天 江島奥院の分身と云ふ、昔江島辨財天の像、或時暴風吹来て、此の如する事三度なり、因て寺僧御●を取に、当寺に止まるべき由なり、故に爰に安ずといへり、及び聖徳太子の像を置く
善導堂 総門内松葉林中にあり、金銅の像を安ず【鎌倉志】には是を善導塚と挙げ、古伝を引て昔善導の像僧と化し唐船に乗て筑紫に渡来す、時に鎮西善導寺の開山聖光夢に善導来朝して筥崎にあり、来り迎へよと告ると見しかば頓て彼地に至る果して像あり、其地に一宇を建立す、其落善導寺に移す、後良忠鎮西にて(聖?)光より其像を附屬せらる(良?)忠霊像に向て吾是より関東の諸國に化を施さんと思ふ、其間何國にても有縁の地に蹟を留め給へと云て海中に投ず、其後(良?)忠鎌倉に至り佐介谷に居す、由比の澳に光明赫奕たり、漁父奇とする処霊像忽然として由比濱に着岸す、(良?)忠因て一宇を建立して彼像を安ず、光明寺是なり、漂泊の地を善導塚と名づくと載せたれど此霊像の為に(良?)忠当寺を創建せしと云ふは寺伝と齟齬せり、さて舶来せしは今二尊堂に安ずる像にて是なるは其模像なりとぞ
神明宮 八幡春日を合祀す、域内鎮護の祠なり
秋葉社、九頭權現社、蔵王窟 後阜にあり、開山塔。山上にあり
内藤家祠堂。阿彌陀 定朝作 如意輪等の像を安じ、内藤備後守、同氏播磨守先世代々の霊牌を置く
鐘樓 正保四年鑄造の鐘を掛く 按ずるに当寺に、竹園山法泉寺の鐘ありしが、今は失へりと云ふ
記主水 寺の山麓にあり 開山の加持水なりと云ふ
総門 昔佐介谷に在し時は、経時の弟時頼、浄刹の額を掲げしと云ふ 今其額を伝へず
山門 天照山の額を扁す 後花園帝の宸筆なり
■ 山内掲示
・光明寺(鎌倉市)
宗派 浄土宗
山号寺号 天照山蓮華院光明寺
創建 寛元元年(1243)
開基 北条経時
材木座に所在する光明寺は、江戸時代には浄土宗関東十八檀林の第一位として格付けされた格式の高い寺院です。
開山は記主禅師然阿良忠、開基は鎌倉幕府の第四代執権北条経時で仁治元年(一二四0)鎌倉に入った良忠のために、経時が佐助ガ谷に寺を建てて蓮華寺と名づけ、それが寛元三年(一二四三)に現在地に移り光明寺と改められたと伝えます。
元禄十一年(一六九八)建立の本堂は、国指定重要文化財。また、弘化四年(一八四七)建立の山門は、県指定重要文化財。ことに本堂は、鎌倉で現存する近世仏堂のうちでも最大規模を誇ります。当寺は今なお、建長寺、円覚寺と並ぶ壮大な伽藍を構成しています。
十月十二日から十五日の間に行われる「十夜法要」の行事は今でも、夜市が立ち大勢の人で賑わいます。
・御案内
この寺は天照山蓮華院光明寺と称し、浄土宗の大本山で「お十夜さんの寺」として、多くの方々に親しまれております。
その十夜法要は明応四年(一四九五年)当山第九代観誉祐崇上人が後土御門天皇の勅許によりつとめられたのを始めといたします。
創立 鎌倉時代・寛元元年(一二四三年)
開基 鎌倉幕府 執権第四代 北条経時公
法号は蓮華寺殿安樂大禅定門
開山 浄土宗第三祖然阿良忠記主禅師大和尚
御入滅 弘安十年(一二八七年)七月六日 八十九歳
御本尊 阿弥陀如来「伝 鎌倉中期作」(大殿中央)
札所 鎌倉三十三観音霊場第十八番如意輪観音(大殿右手)
鎌倉二十四地蔵霊場第二十二番延命地蔵(境内右手)
鎮守 天照皇大神(天照山中腹)
秋葉大権現(天照山山頂)
繁栄稲荷大明神(境内右手)
建物 総門 承応四年(一六五五年)
山門 弘化四年(一八四七年)
大殿 元禄十一年(一六九八年)
開山堂 元禄十一年(一六九八年)
大聖閣 平成二十一年再建
施設 小堀遠州作「記主庭園」
昭和の名庭「三尊五祖の石庭」
・山門
弘化四年(一八四七)に再建された鎌倉に現存する最大の山門です。
建築は和様と唐様の折衷様式で、江戸時代後期の重厚な風格を備えています。
「天照山」の扁額は永享八年(一四三六)の裏書のある後花園天皇の御宸筆です。
楼上には次の諸尊が安置されています。
釈迦三尊
四天王像
十六羅漢像
(いずれも江戸時代後期作のすぐれたお像です。)
・大殿
本尊阿弥陀如来、観音・勢至両菩薩を安置する当山の中心の御堂です。
元禄十一年(一六九八)、当山第五十一世洞譽上人の代に建立されたものです。
十四間四方の大建築で現存する木造の古建築では鎌倉一の大堂です。
建物は数度の改修で一部建立当初の形を変えていますが、内部の円柱、格天井、欄間の彫刻など建立当初の荘厳さを今に伝えています。
大殿の左側には小堀遠州の流れをくむ蓮池として有名な記主庭園、右側は三尊五祖の石庭が配してあります。
大殿内の主な尊像
本尊阿弥陀三尊像 善導大師像 宗祖法然上人像
如意輪観音像 和賀江島弁財天僧
・開山堂
当寺開山良忠上人(記主禅師)の尊像および歴代の法主(住職)を祀る御堂です。
開山の良忠上人は、浄土宗の第三祖(宗祖法然上人から三代目)として関東にお念仏の教えを弘められました。
上人は島根県那賀郡に生まれ各地で修業と修学を積み正嘉二年(一二五八)の頃鎌倉に入り、幕府第四代執権北条経時公の帰依を受けて、この寺を開かれました。学徳を備えた高僧で、すぐれた僧侶を育てました。
また多くの書物を著し、今日の浄土宗の基盤を為るという大きな働きをされ、この功績を称えて、没後、伏見天皇から記主禅師の謚号を贈られました。
毎年七月六日のご命日には開山忌法要を勤めています。
・善導大師像
中国唐時代に活躍された浄土教の高僧で、宗祖法然上人はこの善導大師の教えに導かれて浄土宗を開かれました。
浄土宗では大師を高祖と崇拝しています。
当寺の御開山良忠上人も厚く大師を敬い鎌倉時代から深く心の結びつきを持たれていました。
良忠上人はこの地に光明寺を開かれて善導像を作り、大師を顕彰されました。
この銅像は寛文(一六六三年)当時第四十一代玄譽知鑑上人の建立です。
・繁栄稲荷大明神
当寺開山良忠上人は、この地に当寺を開くまでしばらく佐介ヶ谷に住まわれていました。
この時上人は子狐を助けたことがありました。すると夢に親狐が現れ、お礼とともに薬種袋を残していったということです。
鎌倉に悪病が流行した折、上人はこの時の夢のお告げに従って、薬種を蒔くと、三日の内に成長し、この薬草を服すると薬効顕れ、病魔はたちまちに退散したということです。
のちに稲荷大明神として当寺に勧請し病魔退散、豊漁満般、家業繁栄を祈念しています。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
浄土宗大本山 もと関東総本山と称し、良忠門下六派の総本山、十八檀林の第一位であった。
開山 然阿良忠
中興開山 八世観誉祐崇、三十一世深誉伝察
開基は北条経時と伝える。
本尊 阿弥陀三尊
従来光明寺について多くのものは『鎌倉佐介浄刹光明寺開山御伝』により、然阿良忠が仁治元年(1241年)二月、鎌倉に入り、住吉谷悟真寺に住して浄土宗を弘めていた、時の執権経時は良忠を尊崇し、佐介谷に蓮華寺を建立して開山とし、ついで光明寺とその名を改め、前の名蓮華の二字を残して方丈を蓮華院となづけた。寛元元年(1243年)五月三日、吉日を卜して良忠を導師として供養した。といい、『風土記稿』所引の寺伝では、この時に、現在地材木座に移転したようにいっている。
しかし、経時(1246年没)の法名は蓮花寺殿安楽大禅定門とあるから、光明寺と改名するのは、どうも後世のように思われる。
『良暁述聞制文』には、「佐介谷悟真寺今号蓮華寺」とあり、正中二年(1325年)三月十五日にはまだ光明寺という名がでてこない。(中略)
『開山御伝』に建長頃(1249-1256年)、北条時頼が寺領を加へ、外門の額字を、佐介浄刹としたという話も、佐介谷にあればこそのことではないかと思う。(中略)
現在のところ(材木座)に移転した期日及び名を光明寺と改めた時期はなお研究を要する問題である。
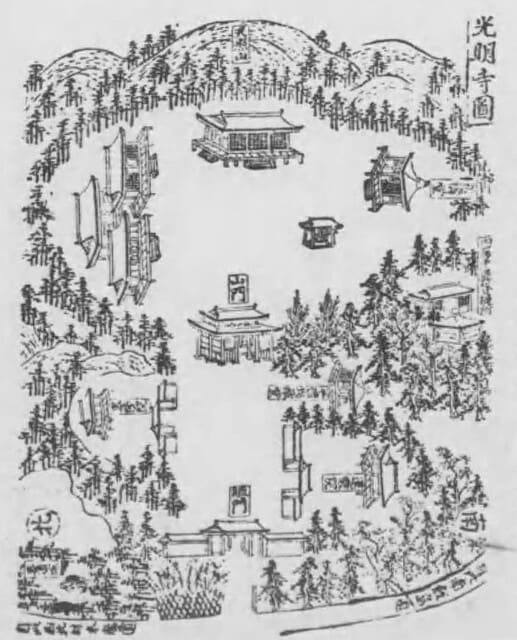
原典:河井恒久 等著 ほか『新編鎌倉志,鎌倉攬勝考』,大日本地誌大系刊行会,大正4.国立国会図書館DC(保護期間満了)
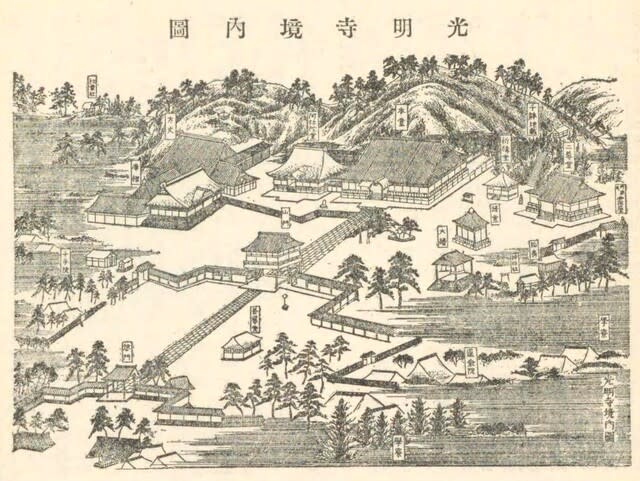
原典:雄山閣編輯局 編『大日本地誌大系』第40巻/ 第40巻 新編相模国風土記稿. 第1至5,雄山閣,昭7-8.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
光明寺は材木座海岸にほとんど面してあります。
車の場合、海沿いの国道134号からは直接アプローチできず、小坪海岸トンネルか小町大路経由となるので要注意です。
材木座海岸には鎌倉時代に北条泰時公(1183-1242年)の命で築かれた「和賀江嶋」(わかえのしま)の遺蹟があります。
和賀江嶋は遠浅の相模湾で港の機能を強化するために築かれたもので、鎌倉時代から江戸時代まで使われたといいます。
南宋などから船が来港していた可能性もあり、光明寺は鎌倉の海の玄関口に位置していたことになります。
海岸から100mも離れず参道が始まります。
関東でも海に近い神社はけっこうありますが、海に至近の名刹はめずらしく、当山と安房鴨川の誕生寺くらいしか思いつきません。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 総本山の石標
入口に「関東総本山」の立派な石標。参道の幅員も広くさすがに名刹の風格。
正面が総門、右手が支院の蓮乗院、左手も旧僧坊の千手院です。
イメージ的には材木座海岸が南ですが、じつはほぼ西向きで、夕刻まで日が差す明るい山内。
関東では稀少な「ウェスト・コーストのお寺」です。


【写真 上(左)】 総門(開門時)
【写真 下(右)】 総門(閉門時)


【写真 上(左)】 総門前寺号標
【写真 下(右)】 総門の寺号板


【写真 上(左)】 総門の扁額と彫刻
【写真 下(右)】 総門門扉の紋
総門は鎌倉市指定文化財。
切妻屋根本瓦葺の四脚門で、柱に「大本山光明寺」、見上げに精緻な彫刻を置き中央に扁額を掲げています。
建立は明応四年(1495年)で寛永年間(1624-1628年)に再興。
以前はもっと大きな門だったといいますが、上部には桃山時代の様式をいまも残すとされます。
門扉は格子、桟と菱格子を併用した意匠性の高いもので、五七桐紋と菊花紋を組み合わせた紋を置いています。
この格調高い御紋は、後土御門帝勅願所の格式をいまに伝えるものでは。
総門前には「浄土宗第三祖 記主禅師遺蹟 大本山光明寺」の石標。
総門をくぐると広大な駐車場。この広さは鎌倉屈指です。


【写真 上(左)】 六字御名号
【写真 下(右)】 山内案内図


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 斜めからの山門
その先に弘化四年(1847年)再建の山門(県重要文化財)が聳え建ちます。
間口約16m、奥行約7m、高さ約20mで、鎌倉に現存する最大の山門です。
桟瓦葺、間数のある堂々たる二重門で、上下層軒下の複雑な斗栱組手が圧巻です。


【写真 上(左)】 山門の斗栱と扁額
【写真 下(右)】 山門扁額
和様唐様折衷様式で、江戸時代後期の重厚な風格を備えるとされます。
折衷様式の代表例は、一層軒の平行繁垂木(和様)、二層軒の扇垂木(唐様/禅宗様)にも見られるといいます。
二層中央の「天照山」の扁額は、永享八年(1436年)の裏書のある後花園天皇の御宸筆です。
楼上には釈迦三尊像、四天王像、十六羅漢像(いずれも江戸時代後期作)が安置されています。


【写真 上(左)】 山門から山内
【写真 下(右)】 参道から本堂
山門をくぐると参道正面が大殿(本堂)。
右手手前から合祀墓、鐘楼堂、繁栄稲荷大明神、延命地蔵尊、本堂右手奥に三尊五祖之石庭。
当山大旦那・内藤家墓所は右手墓域内にあり、宝筐印塔を中心に100以上の石塔を連ねています。
左手は手前から庫裏・本坊、書院、開山堂、本堂左手奥に記主庭園、大聖閣という構成です。
順にみていきます。
【鐘楼堂】
総欅瓦葺きの鐘楼堂は弘化四年(1847年)建立。
現梵鐘は昭和36年、法然上人七百五十年遠忌に鋳造された重量三百貫の巨鐘です。


【写真 上(左)】 鐘楼堂-1
【写真 下(右)】 鐘楼堂-2
【繁栄稲荷大明神】
良忠上人は佐介ヶ谷で子狐を助けたことがありました。すると夢に親狐があらわれ、お礼とともに薬種袋を残していきました。
鎌倉で悪病が流行した折、上人はこの薬種を蒔くと三日の内に成長し、この薬草を服したものは薬効顕れ、病魔はたちまち退散したといいます。
のちに繁栄稲荷大明神として当山に勧請され、病魔退散、豊漁満般、家業繁栄に霊験あらたかといいます。


【写真 上(左)】 繁栄稲荷大明神
【写真 下(右)】 山内の石碑群
【延命地蔵尊】
稲荷大明神の本堂寄りに地蔵堂があります。
『鎌倉札所めぐり』(メイツ出版)等によると、こちらには正中二年(1325年)作銘のある石佛坐像・綱引延命地蔵尊が安置されています。
かつて以前光明寺裏山の小坪切通しの鎌倉側の入口のやぐらにあった御像を遷したものです。
こちらは鎌倉二十四地蔵霊場第22番札所(綱引延命地蔵尊)となっています。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 綱引延命地蔵尊
【三尊五祖之石庭】(本堂改修中は拝観不可)
本堂右手奥側にあります。
「三尊」とは、阿弥陀仏とその脇士観音・勢至の二菩薩。
「五祖」とは浄土教を説法流布された釈尊、善導大師、法然上人(浄土宗開祖)、鎮西上人(浄土第宗二祖・聖光)、記主禅師(良忠上人)の五大祖師を示します。
この三尊五祖が庭園中の石により表現され、庭園構図は此岸と彼岸をあらわしています。

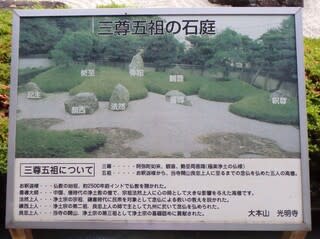
【写真 上(左)】 三尊五祖之石庭
【写真 下(右)】 同 説明板
【庫裏・本坊】
前面の附属棟が授与所となっています。
【開山堂】
開山良忠上人(記主禅師)の尊像、および歴代法主(住職)を祀る御堂です。
令和2年春からの「大殿・令和の大改修」にともない、現在・大殿(本堂)にお祀りする阿弥陀如来および諸尊像は開山堂に遷られ、仮本堂となっています。
かつては現・本堂(大殿)を祖師堂と称していました。
関東大震災で倒潰した旧・阿弥陀堂の御本尊を旧・開山堂へ遷座して本堂とし、開山堂は大正13年新たに建てられ、平成14年老朽化のため再建されました。
入母屋造銅板葺流れ向拝の平入りですが、向拝上部に大がかりな千鳥破風を起こしているので、一見妻入りに見えます。
三間の向拝で、水引虹梁両端に獅子漠の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に三連の蟇股を置いています。
向拝見上げに「開山堂」、堂内に「勅諡記主禅師」の二重扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 開山堂
【写真 下(右)】 開山堂扁額-1


【写真 上(左)】 開山堂扁額-2
【写真 下(右)】 開山堂堂内
本堂と開山堂のあいだには回廊が渡され、背後の庭園とあいまって見どころとなっています。
回廊前には善導大師像が安置されています。


【写真 上(左)】 庭園方向
【写真 下(右)】 善導大師像
【本堂(大殿)】
元禄十一年(1698年)建立の十四間四面の大堂で、現存する木造の古建築では鎌倉一の規模とされ「百本柱のお堂」として知られています。国指定の重要文化財です。
かつては開山良忠上人像を安置して「祖師堂」と称していましたが、祖師堂を中心伽藍に置く様式は、知恩院をはじめとする京都の浄土宗本山の通例とされます。


【写真 上(左)】 本堂(改修前)
【写真 下(右)】 本堂(改修中)
入母屋造銅本棒葺流れ向拝で軒唐破風。大棟には菊花紋と五七桐紋を交互に置いています。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 向拝(閉扉時)
【写真 下(右)】 向拝(開扉時)
向拝は三間で水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に蟇股を置いています。
向拝柱には「専修念佛根本道場」、見上げに寺号扁額、堂内にも扁額を置く二重扁額です。


【写真 上(左)】 「専修念佛根本道場」
【写真 下(右)】 向拝扁額


【写真 上(左)】 二重扁額
【写真 下(右)】 本堂内-1


【写真 上(左)】 本堂内-2
【写真 下(右)】 御本尊
浄土宗では本堂を開放する寺院が多いですが、こちらも通常開扉され堂内拝観できます。
華やかな欄間彫刻、精緻な天井絵、金色に輝く天蓋や瓔珞など、さすがに名刹にふさわしい空間です。
中央の御本尊阿弥陀三尊像は、伝・鎌倉中期作といいます。
右檀には善導大師等身大立像と弁財天像が安置されています。
善導大師立像は、かつて二尊堂にあって良忠上人が聖光上人より拝受の像といい、由比ヶ浜漂着の縁起が伝わります。
弁財天像は、江ノ島辯才天ゆかりの縁起が伝わります。
左檀上には、如意輪観世音菩薩像(鎌倉三十三観音霊場第18番・七観音霊場札所本尊)と宗祖法然上人像が安置されています。

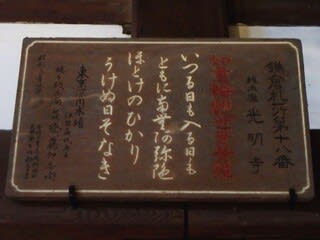
【写真 上(左)】 如意輪観世音菩薩像
【写真 下(右)】 観音霊場札所板


【写真 上(左)】 法然上人像
【写真 下(右)】 天井絵
令和2年春から10 年計画で保存修理工事が始まり、御本尊阿弥陀如来および諸尊像は開山堂に遷られています。
■ 大殿 令和の大改修【令和5年度ダイジェスト】―重要文化財光明寺本堂修理工事―
【記主庭園・大聖閣】
背後に小山をおく風雅な浄土宗庭園で、小堀遠州作と伝わります。
蓮池の蓮は夏に色とりどりに開花します。
大聖閣は宗祖法然上人800年大御忌を期して建立。二層には阿弥陀三尊が安置されています。


【写真 上(左)】 記主庭園
【写真 下(右)】 大聖閣
本堂背後の天照山は、良忠上人が天照大神の尊像を感得せられたことからの命名といいます。
中腹に良忠上人をはじめ歴代の墓所と開基である北条経時公(法名:蓮華寺殿安楽大禅定門)の墓所があります。
鎮守社・神明社、秋葉大権現も天照山に祀られています。
【神明社】
天照・春日・八幡の三神を合祀しています。
『新編相模国風土記稿』には、「神明宮 八幡春日を合祀す、域内鎮護の祠なり」とあります。
【秋葉社】
『新編相模国風土記稿』には、「秋葉社、九頭權現社、蔵王窟 後阜にあり」とあります。
寺伝には、当山三十三世深譽伝察上人が身を天狗に現じて当山を守護されたとあります。
御朱印は山内左手の庫裏・本坊附属棟にて拝受しました。
複数の御朱印を授与されていますが、↓ の注意書きがあります。
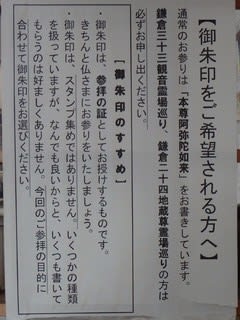
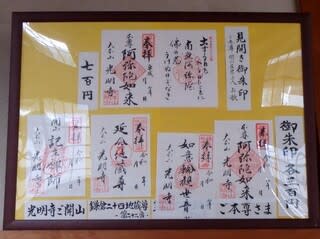
【写真 上(左)】 注意書き
【写真 下(右)】 御朱印見本(金額は変更の可能性あり。)
〔 光明寺の御朱印 〕
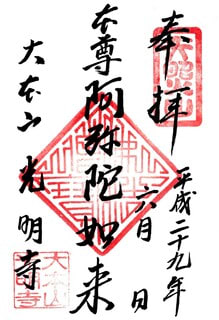
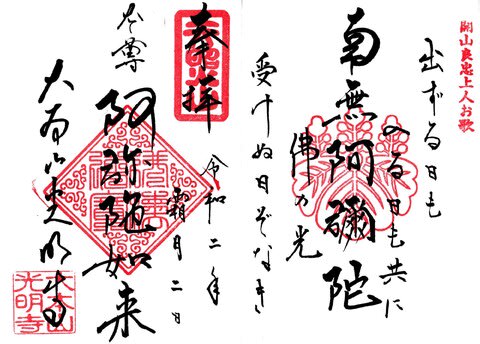
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 御名号の御朱印

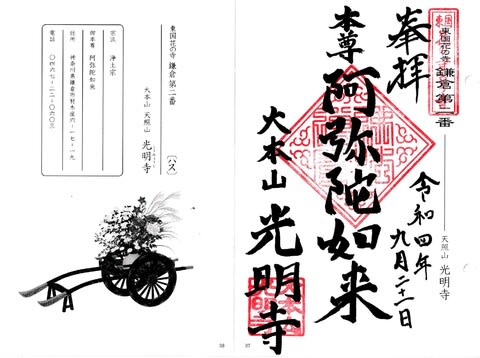
【写真 上(左)】 開山 記主禅師の御朱印
【写真 下(右)】 東国花の寺霊場の御朱印

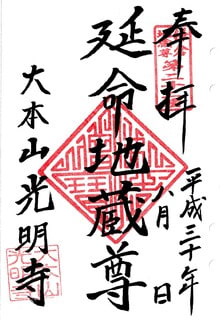
【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印
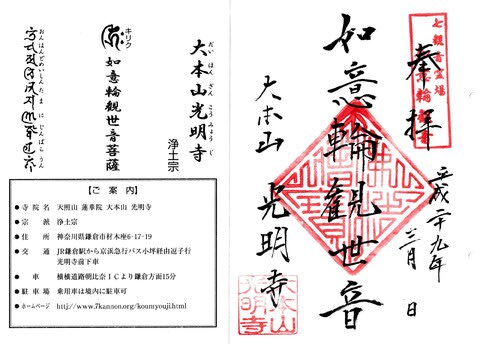
七観音霊場の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-12 (B.名越口-6)へつづく。
【 BGM 】
■ David Benoit - The Key To You
■ King of Hearts - Don't Call My Name
■ Bryan Ferry & Roxy Music - Avalon
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)
■ 同-10 (B.名越口-5)から。
ここから材木座エリアに入ります。
36.天照山 蓮華院 光明寺(こうみょうじ)
公式Web
「新纂 浄土宗大辞典/光明寺」
鎌倉市材木座6-17-19
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
司元別当:
札所:関東十八檀林10、鎌倉六阿弥陀霊場第3番、鎌倉三十三観音霊場第18番、鎌倉二十四地蔵霊場第22番、三浦半島四十八阿弥陀霊場第48番、東国花の寺百ヶ寺霊場鎌倉第2番、七観音霊場第3番、小田急沿線花の寺四季めぐり第25番
光明寺は材木座にある浄土宗の大本山です。
公式Web、「新纂 浄土宗大辞典/光明寺」、下記史料・資料から縁起沿革を追ってみます。
光明寺の創立は寛元元年(1243年)、開山は浄土宗三祖然阿良忠上人(1199-1287年・記主禅師)といいます。
良忠上人は正治元年(1199年)石見国三隅庄に生まれ、38歳で聖光上人のお弟子となり、学究ののち法然上人の教えを受け継がれて浄土宗の三祖になられました。
浄土宗の宗祖は法然上人で、二祖は久留米善導寺を開かれた聖光上人(弁長)です。
法然上人の寂後、浄土教学は大きく以下の4流(浄土四流)に分かれました。
・三鈷寺証空の西山義(西山派)
・善導寺弁長の鎮西義(鎮西派)
・長楽寺隆寛の長楽寺義
・九品寺長西の九品寺義
うち、浄土宗主流は弁長(聖光上人)の鎮西義(鎮西派)となり、良忠上人はこの鎮西義(鎮西派)を継がれました。
---------------------------------
建暦元年(1211年)良忠上人は13歳のとき、出雲国の天台宗寺門派鰐淵寺の月珠房信暹門弟となり、16歳で出家受戒。
鰐淵寺では天台寺門派、同山門派等の天台密教を相承したといいます。
嘉禎二年(1236年)九州に下向、筑後国上妻の天福寺で浄土宗二祖の聖光上人に面謁、数々の教えを相伝。宗論を撰述し、聖光上人の印可を受けました。
暦仁元年(1238年)から約10年間石見国~安芸国を教化。
高野山明王院学頭の源朝阿闍梨が安芸国に左遷された折、良忠上人は源朝阿闍梨に師事して真言密教を学んだともいいます。
建長元年(1249年)頃、信濃善光寺を経て下総に向われ千葉氏一族の外護を受け、常陸、上総、下総三国の教化活動と浄土宗典の講述をなされました。
正元元年(1259年)頃鎌倉に移住。
ただし、仁治元年(1240年)鎌倉入り説もあります。
浄土宗の立教開宗の書ともされる『選択本願念仏集』(選択集/せんちゃくしゅう)、浄土三部経(『無量寿経』『観無量寿経(観経)』『阿弥陀経』)、『観経疏』(『観経』の注釈書)などの講述を究められたといいます。
東密(真言密教)、台密(天台密教)と幅広く学ばれた良忠上人は、浄土宗論の撰述・講述でも卓越した才をあらわされたのではないでしょうか。
鎌倉では幕府の評定衆・大仏(北条)朝直の帰依を得て佐介ヶ谷に悟真寺を創建。
朝直は北条時政の子息・北条時房(鎌倉幕府初代連署)の子につき相応の権力を有していたとみられ、バックアップは安定していたのでは。
良忠上人は朝直の子時遠からも帰依を受け、専修念仏の指導的な立場を担われたといいます。
なお、寺伝では当山開基は鎌倉幕府第四代執権・北条経時公とされています。
悟真寺については後述しますが、悟真寺(蓮華寺)を光明寺の前身寺院とすることについては年代的な不整合もみられ、異説もあるようです。
文永八年(1271年)、良忠上人は極楽寺の良観・理智光寺の道教・浄光明寺の行敏らとともに日蓮宗に対抗するとともに、比叡山修学中の良暁を鎌倉に呼び寄せ浄土の奥義を授けたといいます。
当時の鎌倉では法然門流のうち、長楽寺義の南無房智慶・願行円満、西山義西谷流の観智・行観、諸行本願義の念空道教・性仙道空らがそれぞれの浄土教を布教・展開していました。
したがって良忠上人は、独自の教学を強く打ち出す必要がありました。
建治二年(1276年)良忠上人は上洛され、宗祖法然上人の遺弟を尋ねて法然上人の遺文の収集に努めたといいます。
また、良忠上人の教学は、浄土教学(法然門流)の長楽寺義・九品寺義・西山義(東山義・深草義)との討論(教学論争)によって研ぎ澄まされたとみられています。
そして各種の教学講述や法然上人の遺文類をもとに、『決疑鈔』(五巻本)を完成されました。
良忠上人は弘安九年(1286年)の秋、鎌倉に再度下向されました。
その直後、弟子の良暁に授与された付法状で、法然—聖光—良忠の「三代相伝」をいい、「三代之義勢」を表明されたといいます。
弘安十年(1287年)89歳をもって入寂。
生前の功績が認められ、伏見天皇より「記主禅師」の謚号を賜りました。
良忠上人の寂後、その門流は以下の6派に分かれました。
・白旗派(良暁)
・藤田派(性心)
・名越派(尊観)
・三条派(道光)
・一条派(然空)
・木幡派(慈心)
うち白旗派が浄土宗(鎮西義)の主流となり、現在に至っています。
光明寺は白旗派を代表する名刹です。
名越派は尊観が鎌倉名越谷善導寺で布教したため善導寺義ともいい、善導寺は大町の安養院(浄土宗)の前身のため、大町~材木座にかけては良忠上人の影響がとりわけ強いエリアです。
※ 善導寺および名越谷善導寺については、■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)の24.安養院を参照願います。
【 悟真寺・蓮華寺 】(ごしんじ・れんげじ)
正嘉元年(1257年)頃(仁治元年(1240年)説あり)、下総から鎌倉入りした良忠上人は、はじめ慈恩坊を頼って大仏勧進聖の浄光を尋ね、浄光は大仏谷に一宇を建てて良忠上人はここに住されたと伝えます。
間もなく大仏(北条)朝直の支援を得て、佐介ヶ谷に悟真寺を創建といいます。
寺号については、浄土第三祖・善導大師入山の終南山悟真寺由来との説があります。
のちに蓮華寺と改名され、材木座へ移転して浄土宗大本山光明寺となったため、光明寺の前身寺院とされます。
悟真寺から蓮華寺への改号の理由ははっきりせず、蓮華寺から光明寺への改号は北条経時の霊夢によるという伝承もありますが、こちらもはっきりしません。
また、佐介谷から材木座への移転の理由も時期も、多くの史料類は明示していません。
悟真寺については後述しますが、悟真寺・蓮華寺を光明寺の前身寺院とすることについては史料により年代的な不整合もみられ、異説もあるようです。
今回、史料・資料類を当たってみると2つの時系列説があることがわかります。
ひとつは『新纂 浄土宗大辞典』系のもの、もうひとつは『新編鎌倉志』系のものです。
【A.『新纂 浄土宗大辞典』系説】
正元元年(1259年)頃
良忠上人 下総から鎌倉に移住
佐介ヶ谷に建立された悟真寺に入る
建治二年(1276年)
良忠上人 鎌倉から上洛
弘安九年(1286年)
良忠上人 京から鎌倉へ下向
弘安十年(1287年)
良忠上人 鎌倉にて八九歳で入寂
後継者の良暁上人は悟真寺を中心に教線の拡張を計る
正中二年(1325年)頃
良暁上人は悟真寺から蓮華寺と寺名を改めた
九世祐崇上人(1426-1509)のとき
佐介ヶ谷の蓮華寺を材木座の現在地に移し、光明寺と改称したともいわれる
明応四年(1495年)
祐崇上人は後土御門天皇の勅命により浄土教を講説
光明寺は勅願寺と関東総本山となる
【B.『新編鎌倉志』系説】
仁治元年(1240年)
良忠上人鎌倉に入られる
寛元元年(1243年)
北条経時、佐介谷に悟真寺を良忠上人を開山として開基
寛元三年(1247年)以前
良忠上人、材木座の蓮乗院に入られ光明寺建立の準備をされる
寛元三年(1247年)
悟真寺(蓮華寺)が材木座に移り光明寺と改号
弘安十年(1287年)
良忠上人 鎌倉にて八九歳で入寂
※ただし、蓮華寺跡(佐介谷)の項に「光明寺、本此地にあって、蓮華寺と号す。後に光明寺と改む。『鎌倉大日記』に、建長三年(1251年)、経時が為に、佐介に於て蓮華寺建立、住持良忠とあり。良忠此谷に居住ありしゆへに、佐介の上人と云ふなり。」との記事があり、上記と整合しません。
A.『新纂 浄土宗大辞典』系説では、弘安十年(1287年)良忠上人が八九歳で入寂されたときには佐介谷悟真寺が存在し、光明寺(1426年以降の移転・改称)はまだありません。
B.『新編鎌倉志』系説では、良忠上人が材木座の蓮乗院に入ってみずから光明寺建立の準備をされ、寛元三年(1247年)悟真寺(蓮華寺)が材木座に移り光明寺に改号という流れです。
以上、A説とB説では年代的に隔たりがあるので、この二説が混在すると時系列が不整合となります。
光明寺の前身寺院の沿革に諸説あるのは、このような背景があるためと思われます。
なお、光明寺公式Webや現地案内板では光明寺の創立を寛元元年(1243年)としているので、B.『新編鎌倉志』系説が定説として流布している模様です。
関連して、『新編鎌倉志』『新編相模国風土記稿』の「光明寺・善導堂」の項には気になる記述があります。
善導堂はもと光明寺の海側の総門内松葉林中にあったといいます。
御本尊の善導大師(613-681年)は、唐時代の中国の僧で「浄土五祖」の第三祖とされ、その教えは法然上人・親鸞上人に大きな影響を与えました。
---------------------------------
【善導堂縁起】
善導大師の霊像が唐船で筑紫に渡来したとき、鎮西善導寺の開山・聖光上人の夢に善導大師があらわれて「われ筥崎にあり、来り迎へよ」とお告げがありました。
聖光上人が筥崎に来てみると果して善導大師の霊像がみつかり、一宇を建立して霊像を安置し、その後善導寺に遷しました。
聖光上人はこの霊像を良忠上人に託しましたが、良忠上人が関東巡錫に出立される際、この霊像に向かい「わたしはこれから関東教化のため出立します。どうぞ願わくば教化有縁の地を示し給え」と念じて、尊像を筑紫の海中に投じたといいます。
良忠上人は鎌倉の佐介谷に住しましたが、あるとき由比の浜辺に光明が満ちて、かの霊像が忽然とお姿をあらわしました。
良忠上人は霊像漂着の地が浄土教学有縁の地と確信され、一宇を建立して霊像を安じました。
これが光明寺といいます。
---------------------------------
上の善導堂縁起によると、良忠上人は佐介谷の悟真寺(ないし蓮華寺)に住されていましたが、善導大師の霊像の霊験を目の当たりにして材木座の海岸に一宇を建立、これが光明寺(の前身)ということになります。
つまり、佐介谷に悟真寺(蓮華寺)が存在した時点で、すでに材木座の海岸にも一宇(善導堂)があったという見方です。
佐介谷の悟真寺(蓮華寺)が材木座に移り光明寺と改めたのは良忠上人寂後としても、上人が材木座に建立された善導堂の地に移ったという流れなのかもしれません。
寺号については史料に「光明赫奕して霊像が忽然と由比濱に着岸」とあるので、あるいはこの縁起から由来という想像も浮かびます。
なお、悟真寺→蓮華寺→光明寺の改号については、以前別記事(■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-8/蓮花寺)にてとり上げています。興味のある方はご参照くださいませ。
光明寺は、その後も第五代執権・北条時頼公をはじめ歴代執権の帰依を受けました。
関東における念仏道場の中心となり、七堂伽藍を整え、後土御門天皇より「関東総本山」の称号を賜り勅願寺とされ、「関東総本山」ともされました。
後土御門天皇の帰依を受け、紫衣を許された八世観誉祐崇上人は中興開山とされています。
上記のA説によれば佐介谷の蓮華寺を現在地(材木座)に移し、光明寺と改めたのは祐崇上人ですから、この業績も認められてのことかもしれません。
徳川家康公は当山を「関東十八檀林」の筆頭に位置づけ、念仏信仰、仏教研鑽の根本道場の地位を固めました。(※檀林とは徳川幕府が定めた学問所です。)
同じ大本山の芝・増上寺は徳川家菩提寺で、当山とは役割を分けていたようです。
浄土宗公式Webによると、現在の主要寺院の格式は以下のとおりです。
総本山
・知恩院(京都市東山区)
大本山(7寺院)
・増上寺(港区芝公園)
・金戒光明寺(京都市左京区)
・百萬遍知恩寺(京都市左京区)
・清浄華院(京都市上京区)
・善導寺(福岡県久留米市)
・光明寺(神奈川県鎌倉市)
・善光寺大本願(長野県長野市)
光明寺は関東にふたつしかない浄土宗大本山で、たいへん高い寺格をもちます。
筆者は光明寺の御朱印帳をもって関東の浄土宗寺院を回ったことがあるのですが、いくつかの寺院で「光明寺様の御朱印帳に書き入れるのは畏れ多い。」とのご住職のお言葉をいただきました。
それだけ高い格式・権威をもたれているということかと。
当山は譜代大名・内藤家の菩提所です。
内藤氏はふるくから松平氏(徳川氏)に仕えた譜代の家臣の家柄で、上総佐貫藩主を経て陸奥磐城平藩主から日向延岡藩7万石の藩主に転じました。
磐城平藩第3代藩主・内藤義概(1619-1685年)の代まで、内藤家菩提寺は江戸霊厳寺でしたが、義概は位牌堂と石塔を光明寺に移し、寺領百五十石を寄進して光明寺の大旦那となりました。
別に新庄家などの墓所もあり、こうした武家の旦那衆が江戸期の当山の経営を支えたともみられています。
当山は「お十夜」発祥の寺でもあります。
お十夜法要は、第九世観譽祐崇上人の代(明応四年(1495年))に始まりました。
後土御門天皇の勅許を受け、引声阿弥陀経と引声念仏による十夜法要を勤めるようになり、いまも毎年十月の四日間盛大に法要が勤められています。
関東大震災で大きな被害を被りましたが復興し、いまも浄土宗大本山、鎌倉を代表する名刹としての存在感を放っています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志 鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
光明寺
光明寺は、本は佐介谷に在しを、後に此地に移す。当寺開山の伝に、寛元元年(1243年)五月三日、前武州太守平経時、佐介谷に於て浄刹を建立し、蓮華寺と号し、良忠を導師として、供養をのべらる。後に経時、霊夢有て光明寺と改む。方丈を蓮華院と名くとあり。(中略)
開山は記主禅師、諱は良忠、然阿と号す。石州三隅荘人なり。父は宰相藤原頼定、母は伴氏、正治元年(1199年)七月二十七日に生る。弘安十年(1287年)七月六日に示寂。年八十九。聖光上人の弟子なり。聖光は法然上人の弟子なり。
良忠弟子六人有て、今に六派相分る。
所謂六派は、京都の三箇は、一條ノ禮阿、三條ノ道光、小幡ノ慈心なり。
関東の三箇は、白旗ノ寂慧(光明寺二世)、名越尊観(大澤流義の祖)、藤田ノ持阿(藤田流義の祖)、是を六派と云ふ。
当寺は六派の本寺なり。六派の内、白旗・大澤の両派のみ今尚盛なり。四派は断絶す。
十七箇寺の檀林は白旗なり。(中略)
外門 昔佐介谷に有し時、平経時の弟時頼外門に額を掛て、佐介浄刹と号すと。今は額なし。
山門 額、天照山とあり。後花園帝の宸筆なり。
開山堂 開山木像を安ず。自作なり。勅諡記主禅師とある額を此堂に掛しとなり。
客殿 三尊を安ず。阿彌陀の像は運慶作。観音勢至像、作者不知。
方丈 蓮華院と号す。阿彌陀の像を安ず、此像も運慶が作にて肚裏に運慶が骨を収むと云ふ。
祈祷堂 今は念佛堂と云ふ。本尊は阿彌陀、慧心の作と云ふ。左方に辯才天の像あり。昔江島辯才天の像、或時暴風吹来て、此寺前海濱に寄泊る。里民相議して彼島帰す。其後又来る。如此する事三度なり。因て寺僧御●を取に、永く此寺に止まるべき由なり。故に爰に安ずと云。右の方に善導像あり。自作と云。
寺寶
勅額 二枚
一枚は、後宇多帝の宸筆、勅諡記主禅師とあり。
一枚は、後土御門帝の宸筆、祈禱の二字なり。
善導塚 ※由緒は『新編相模国風土記稿』にほぼ同じにつき略。
蓮華寺跡(佐介谷)(同上資料)
今俗に光明寺畠と云ふ。光明寺、本此地にあって、蓮華寺と号す。後に光明寺と改む。
『鎌倉大日記』に、建長三年(1251年)、経時が為に、佐介に於て蓮華寺建立、住持良忠とあり。良忠此谷に居住ありしゆへに、佐介の上人と云ふなり。光明寺の條下及ひ『記主上人傳』に詳也。
■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館)
(材木座村)光明寺
天照山蓮華院と号す、浄土宗、関東総本山と称し十八檀林の第一位にして六派の本寺なり、仁治元年(1240年)北條武蔵守経時佐介谷に於て浄刹を創立し蓮華寺と名つく時に僧良忠悟眞寺に在り経時延て開山初祖とし、武州足立郡箕田の地を寄附して寺領とす
寛元元年(1243年)今の地に移転して堂宇を修復す斯て経時夢兆に感じて光明寺と改む(中略)寶治二年(1248年)良忠洛の尼院にあり、後嵯峨上皇の戒師となり、香衣幷に上人号を賜ふ
建長元年(1249年)鎌倉に帰る、時頼由良の地を割て寄附せり、良忠弘安十年(1287年)七月六日寂す 永仁元年(1293年)勅謚ありて記主禅師と号す
建武二年九月當寺造營の爲修理田一町を寄附あり(注釈)
貞治二年二月足利基氏上總國湯井號觀應三年の例に任せ、寄附ある旨證状を授與す(注釈)
其後祐崇永正六年(1509年)寂す、当寺の住職たり、是を中興の祖とす
本堂 開山の像を置く
客殿 三尊の彌陀を安ず 中尊は運慶作余は作人知れず
方丈 彌陀を安ず 運慶作にて肚裏に運慶が骨を収むと云ふ
【寺寶】(中略)
紫石硯一面 唐玄宗の松蔭の硯と称す、相伝て平重衡受戒の時、法然に与ふ、法然是を聖光に譲り、聖光又記主に譲ると云へど、背に永享(1429年)の年号あり、是法然記主の時代にあらず、是非詳ならず
二尊堂 善導大師 自作、衣に金泥にて、彌陀經を書たり
辨財天 江島奥院の分身と云ふ、昔江島辨財天の像、或時暴風吹来て、此の如する事三度なり、因て寺僧御●を取に、当寺に止まるべき由なり、故に爰に安ずといへり、及び聖徳太子の像を置く
善導堂 総門内松葉林中にあり、金銅の像を安ず【鎌倉志】には是を善導塚と挙げ、古伝を引て昔善導の像僧と化し唐船に乗て筑紫に渡来す、時に鎮西善導寺の開山聖光夢に善導来朝して筥崎にあり、来り迎へよと告ると見しかば頓て彼地に至る果して像あり、其地に一宇を建立す、其落善導寺に移す、後良忠鎮西にて(聖?)光より其像を附屬せらる(良?)忠霊像に向て吾是より関東の諸國に化を施さんと思ふ、其間何國にても有縁の地に蹟を留め給へと云て海中に投ず、其後(良?)忠鎌倉に至り佐介谷に居す、由比の澳に光明赫奕たり、漁父奇とする処霊像忽然として由比濱に着岸す、(良?)忠因て一宇を建立して彼像を安ず、光明寺是なり、漂泊の地を善導塚と名づくと載せたれど此霊像の為に(良?)忠当寺を創建せしと云ふは寺伝と齟齬せり、さて舶来せしは今二尊堂に安ずる像にて是なるは其模像なりとぞ
神明宮 八幡春日を合祀す、域内鎮護の祠なり
秋葉社、九頭權現社、蔵王窟 後阜にあり、開山塔。山上にあり
内藤家祠堂。阿彌陀 定朝作 如意輪等の像を安じ、内藤備後守、同氏播磨守先世代々の霊牌を置く
鐘樓 正保四年鑄造の鐘を掛く 按ずるに当寺に、竹園山法泉寺の鐘ありしが、今は失へりと云ふ
記主水 寺の山麓にあり 開山の加持水なりと云ふ
総門 昔佐介谷に在し時は、経時の弟時頼、浄刹の額を掲げしと云ふ 今其額を伝へず
山門 天照山の額を扁す 後花園帝の宸筆なり
■ 山内掲示
・光明寺(鎌倉市)
宗派 浄土宗
山号寺号 天照山蓮華院光明寺
創建 寛元元年(1243)
開基 北条経時
材木座に所在する光明寺は、江戸時代には浄土宗関東十八檀林の第一位として格付けされた格式の高い寺院です。
開山は記主禅師然阿良忠、開基は鎌倉幕府の第四代執権北条経時で仁治元年(一二四0)鎌倉に入った良忠のために、経時が佐助ガ谷に寺を建てて蓮華寺と名づけ、それが寛元三年(一二四三)に現在地に移り光明寺と改められたと伝えます。
元禄十一年(一六九八)建立の本堂は、国指定重要文化財。また、弘化四年(一八四七)建立の山門は、県指定重要文化財。ことに本堂は、鎌倉で現存する近世仏堂のうちでも最大規模を誇ります。当寺は今なお、建長寺、円覚寺と並ぶ壮大な伽藍を構成しています。
十月十二日から十五日の間に行われる「十夜法要」の行事は今でも、夜市が立ち大勢の人で賑わいます。
・御案内
この寺は天照山蓮華院光明寺と称し、浄土宗の大本山で「お十夜さんの寺」として、多くの方々に親しまれております。
その十夜法要は明応四年(一四九五年)当山第九代観誉祐崇上人が後土御門天皇の勅許によりつとめられたのを始めといたします。
創立 鎌倉時代・寛元元年(一二四三年)
開基 鎌倉幕府 執権第四代 北条経時公
法号は蓮華寺殿安樂大禅定門
開山 浄土宗第三祖然阿良忠記主禅師大和尚
御入滅 弘安十年(一二八七年)七月六日 八十九歳
御本尊 阿弥陀如来「伝 鎌倉中期作」(大殿中央)
札所 鎌倉三十三観音霊場第十八番如意輪観音(大殿右手)
鎌倉二十四地蔵霊場第二十二番延命地蔵(境内右手)
鎮守 天照皇大神(天照山中腹)
秋葉大権現(天照山山頂)
繁栄稲荷大明神(境内右手)
建物 総門 承応四年(一六五五年)
山門 弘化四年(一八四七年)
大殿 元禄十一年(一六九八年)
開山堂 元禄十一年(一六九八年)
大聖閣 平成二十一年再建
施設 小堀遠州作「記主庭園」
昭和の名庭「三尊五祖の石庭」
・山門
弘化四年(一八四七)に再建された鎌倉に現存する最大の山門です。
建築は和様と唐様の折衷様式で、江戸時代後期の重厚な風格を備えています。
「天照山」の扁額は永享八年(一四三六)の裏書のある後花園天皇の御宸筆です。
楼上には次の諸尊が安置されています。
釈迦三尊
四天王像
十六羅漢像
(いずれも江戸時代後期作のすぐれたお像です。)
・大殿
本尊阿弥陀如来、観音・勢至両菩薩を安置する当山の中心の御堂です。
元禄十一年(一六九八)、当山第五十一世洞譽上人の代に建立されたものです。
十四間四方の大建築で現存する木造の古建築では鎌倉一の大堂です。
建物は数度の改修で一部建立当初の形を変えていますが、内部の円柱、格天井、欄間の彫刻など建立当初の荘厳さを今に伝えています。
大殿の左側には小堀遠州の流れをくむ蓮池として有名な記主庭園、右側は三尊五祖の石庭が配してあります。
大殿内の主な尊像
本尊阿弥陀三尊像 善導大師像 宗祖法然上人像
如意輪観音像 和賀江島弁財天僧
・開山堂
当寺開山良忠上人(記主禅師)の尊像および歴代の法主(住職)を祀る御堂です。
開山の良忠上人は、浄土宗の第三祖(宗祖法然上人から三代目)として関東にお念仏の教えを弘められました。
上人は島根県那賀郡に生まれ各地で修業と修学を積み正嘉二年(一二五八)の頃鎌倉に入り、幕府第四代執権北条経時公の帰依を受けて、この寺を開かれました。学徳を備えた高僧で、すぐれた僧侶を育てました。
また多くの書物を著し、今日の浄土宗の基盤を為るという大きな働きをされ、この功績を称えて、没後、伏見天皇から記主禅師の謚号を贈られました。
毎年七月六日のご命日には開山忌法要を勤めています。
・善導大師像
中国唐時代に活躍された浄土教の高僧で、宗祖法然上人はこの善導大師の教えに導かれて浄土宗を開かれました。
浄土宗では大師を高祖と崇拝しています。
当寺の御開山良忠上人も厚く大師を敬い鎌倉時代から深く心の結びつきを持たれていました。
良忠上人はこの地に光明寺を開かれて善導像を作り、大師を顕彰されました。
この銅像は寛文(一六六三年)当時第四十一代玄譽知鑑上人の建立です。
・繁栄稲荷大明神
当寺開山良忠上人は、この地に当寺を開くまでしばらく佐介ヶ谷に住まわれていました。
この時上人は子狐を助けたことがありました。すると夢に親狐が現れ、お礼とともに薬種袋を残していったということです。
鎌倉に悪病が流行した折、上人はこの時の夢のお告げに従って、薬種を蒔くと、三日の内に成長し、この薬草を服すると薬効顕れ、病魔はたちまちに退散したということです。
のちに稲荷大明神として当寺に勧請し病魔退散、豊漁満般、家業繁栄を祈念しています。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
浄土宗大本山 もと関東総本山と称し、良忠門下六派の総本山、十八檀林の第一位であった。
開山 然阿良忠
中興開山 八世観誉祐崇、三十一世深誉伝察
開基は北条経時と伝える。
本尊 阿弥陀三尊
従来光明寺について多くのものは『鎌倉佐介浄刹光明寺開山御伝』により、然阿良忠が仁治元年(1241年)二月、鎌倉に入り、住吉谷悟真寺に住して浄土宗を弘めていた、時の執権経時は良忠を尊崇し、佐介谷に蓮華寺を建立して開山とし、ついで光明寺とその名を改め、前の名蓮華の二字を残して方丈を蓮華院となづけた。寛元元年(1243年)五月三日、吉日を卜して良忠を導師として供養した。といい、『風土記稿』所引の寺伝では、この時に、現在地材木座に移転したようにいっている。
しかし、経時(1246年没)の法名は蓮花寺殿安楽大禅定門とあるから、光明寺と改名するのは、どうも後世のように思われる。
『良暁述聞制文』には、「佐介谷悟真寺今号蓮華寺」とあり、正中二年(1325年)三月十五日にはまだ光明寺という名がでてこない。(中略)
『開山御伝』に建長頃(1249-1256年)、北条時頼が寺領を加へ、外門の額字を、佐介浄刹としたという話も、佐介谷にあればこそのことではないかと思う。(中略)
現在のところ(材木座)に移転した期日及び名を光明寺と改めた時期はなお研究を要する問題である。
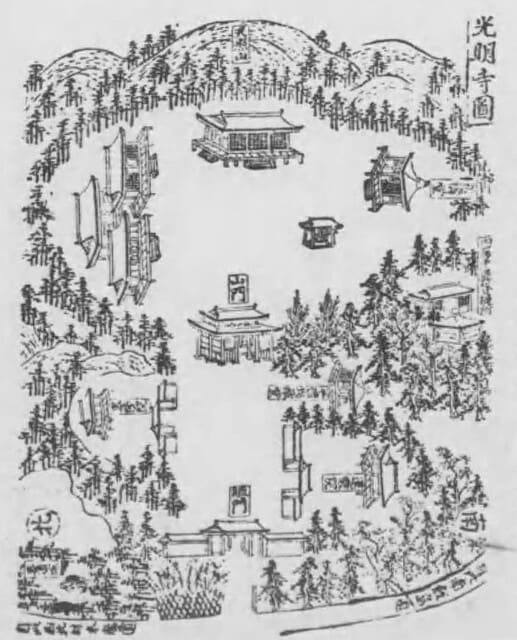
原典:河井恒久 等著 ほか『新編鎌倉志,鎌倉攬勝考』,大日本地誌大系刊行会,大正4.国立国会図書館DC(保護期間満了)
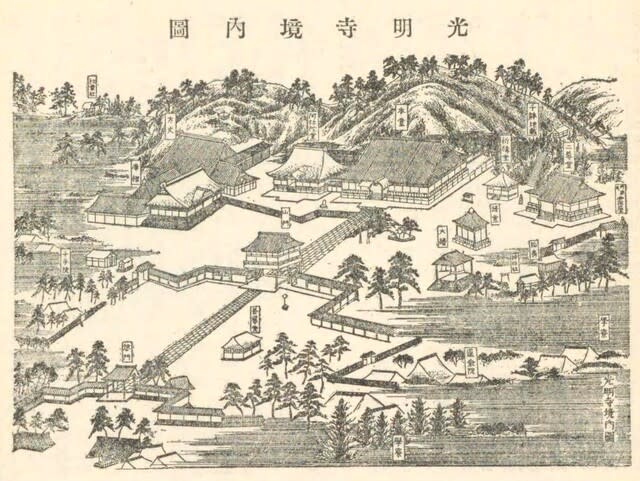
原典:雄山閣編輯局 編『大日本地誌大系』第40巻/ 第40巻 新編相模国風土記稿. 第1至5,雄山閣,昭7-8.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
光明寺は材木座海岸にほとんど面してあります。
車の場合、海沿いの国道134号からは直接アプローチできず、小坪海岸トンネルか小町大路経由となるので要注意です。
材木座海岸には鎌倉時代に北条泰時公(1183-1242年)の命で築かれた「和賀江嶋」(わかえのしま)の遺蹟があります。
和賀江嶋は遠浅の相模湾で港の機能を強化するために築かれたもので、鎌倉時代から江戸時代まで使われたといいます。
南宋などから船が来港していた可能性もあり、光明寺は鎌倉の海の玄関口に位置していたことになります。
海岸から100mも離れず参道が始まります。
関東でも海に近い神社はけっこうありますが、海に至近の名刹はめずらしく、当山と安房鴨川の誕生寺くらいしか思いつきません。


【写真 上(左)】 参道入口
【写真 下(右)】 総本山の石標
入口に「関東総本山」の立派な石標。参道の幅員も広くさすがに名刹の風格。
正面が総門、右手が支院の蓮乗院、左手も旧僧坊の千手院です。
イメージ的には材木座海岸が南ですが、じつはほぼ西向きで、夕刻まで日が差す明るい山内。
関東では稀少な「ウェスト・コーストのお寺」です。


【写真 上(左)】 総門(開門時)
【写真 下(右)】 総門(閉門時)


【写真 上(左)】 総門前寺号標
【写真 下(右)】 総門の寺号板


【写真 上(左)】 総門の扁額と彫刻
【写真 下(右)】 総門門扉の紋
総門は鎌倉市指定文化財。
切妻屋根本瓦葺の四脚門で、柱に「大本山光明寺」、見上げに精緻な彫刻を置き中央に扁額を掲げています。
建立は明応四年(1495年)で寛永年間(1624-1628年)に再興。
以前はもっと大きな門だったといいますが、上部には桃山時代の様式をいまも残すとされます。
門扉は格子、桟と菱格子を併用した意匠性の高いもので、五七桐紋と菊花紋を組み合わせた紋を置いています。
この格調高い御紋は、後土御門帝勅願所の格式をいまに伝えるものでは。
総門前には「浄土宗第三祖 記主禅師遺蹟 大本山光明寺」の石標。
総門をくぐると広大な駐車場。この広さは鎌倉屈指です。


【写真 上(左)】 六字御名号
【写真 下(右)】 山内案内図


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 斜めからの山門
その先に弘化四年(1847年)再建の山門(県重要文化財)が聳え建ちます。
間口約16m、奥行約7m、高さ約20mで、鎌倉に現存する最大の山門です。
桟瓦葺、間数のある堂々たる二重門で、上下層軒下の複雑な斗栱組手が圧巻です。


【写真 上(左)】 山門の斗栱と扁額
【写真 下(右)】 山門扁額
和様唐様折衷様式で、江戸時代後期の重厚な風格を備えるとされます。
折衷様式の代表例は、一層軒の平行繁垂木(和様)、二層軒の扇垂木(唐様/禅宗様)にも見られるといいます。
二層中央の「天照山」の扁額は、永享八年(1436年)の裏書のある後花園天皇の御宸筆です。
楼上には釈迦三尊像、四天王像、十六羅漢像(いずれも江戸時代後期作)が安置されています。


【写真 上(左)】 山門から山内
【写真 下(右)】 参道から本堂
山門をくぐると参道正面が大殿(本堂)。
右手手前から合祀墓、鐘楼堂、繁栄稲荷大明神、延命地蔵尊、本堂右手奥に三尊五祖之石庭。
当山大旦那・内藤家墓所は右手墓域内にあり、宝筐印塔を中心に100以上の石塔を連ねています。
左手は手前から庫裏・本坊、書院、開山堂、本堂左手奥に記主庭園、大聖閣という構成です。
順にみていきます。
【鐘楼堂】
総欅瓦葺きの鐘楼堂は弘化四年(1847年)建立。
現梵鐘は昭和36年、法然上人七百五十年遠忌に鋳造された重量三百貫の巨鐘です。


【写真 上(左)】 鐘楼堂-1
【写真 下(右)】 鐘楼堂-2
【繁栄稲荷大明神】
良忠上人は佐介ヶ谷で子狐を助けたことがありました。すると夢に親狐があらわれ、お礼とともに薬種袋を残していきました。
鎌倉で悪病が流行した折、上人はこの薬種を蒔くと三日の内に成長し、この薬草を服したものは薬効顕れ、病魔はたちまち退散したといいます。
のちに繁栄稲荷大明神として当山に勧請され、病魔退散、豊漁満般、家業繁栄に霊験あらたかといいます。


【写真 上(左)】 繁栄稲荷大明神
【写真 下(右)】 山内の石碑群
【延命地蔵尊】
稲荷大明神の本堂寄りに地蔵堂があります。
『鎌倉札所めぐり』(メイツ出版)等によると、こちらには正中二年(1325年)作銘のある石佛坐像・綱引延命地蔵尊が安置されています。
かつて以前光明寺裏山の小坪切通しの鎌倉側の入口のやぐらにあった御像を遷したものです。
こちらは鎌倉二十四地蔵霊場第22番札所(綱引延命地蔵尊)となっています。


【写真 上(左)】 地蔵堂
【写真 下(右)】 綱引延命地蔵尊
【三尊五祖之石庭】(本堂改修中は拝観不可)
本堂右手奥側にあります。
「三尊」とは、阿弥陀仏とその脇士観音・勢至の二菩薩。
「五祖」とは浄土教を説法流布された釈尊、善導大師、法然上人(浄土宗開祖)、鎮西上人(浄土第宗二祖・聖光)、記主禅師(良忠上人)の五大祖師を示します。
この三尊五祖が庭園中の石により表現され、庭園構図は此岸と彼岸をあらわしています。

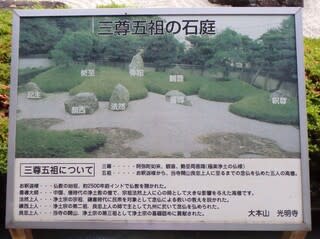
【写真 上(左)】 三尊五祖之石庭
【写真 下(右)】 同 説明板
【庫裏・本坊】
前面の附属棟が授与所となっています。
【開山堂】
開山良忠上人(記主禅師)の尊像、および歴代法主(住職)を祀る御堂です。
令和2年春からの「大殿・令和の大改修」にともない、現在・大殿(本堂)にお祀りする阿弥陀如来および諸尊像は開山堂に遷られ、仮本堂となっています。
かつては現・本堂(大殿)を祖師堂と称していました。
関東大震災で倒潰した旧・阿弥陀堂の御本尊を旧・開山堂へ遷座して本堂とし、開山堂は大正13年新たに建てられ、平成14年老朽化のため再建されました。
入母屋造銅板葺流れ向拝の平入りですが、向拝上部に大がかりな千鳥破風を起こしているので、一見妻入りに見えます。
三間の向拝で、水引虹梁両端に獅子漠の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に三連の蟇股を置いています。
向拝見上げに「開山堂」、堂内に「勅諡記主禅師」の二重扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 開山堂
【写真 下(右)】 開山堂扁額-1


【写真 上(左)】 開山堂扁額-2
【写真 下(右)】 開山堂堂内
本堂と開山堂のあいだには回廊が渡され、背後の庭園とあいまって見どころとなっています。
回廊前には善導大師像が安置されています。


【写真 上(左)】 庭園方向
【写真 下(右)】 善導大師像
【本堂(大殿)】
元禄十一年(1698年)建立の十四間四面の大堂で、現存する木造の古建築では鎌倉一の規模とされ「百本柱のお堂」として知られています。国指定の重要文化財です。
かつては開山良忠上人像を安置して「祖師堂」と称していましたが、祖師堂を中心伽藍に置く様式は、知恩院をはじめとする京都の浄土宗本山の通例とされます。


【写真 上(左)】 本堂(改修前)
【写真 下(右)】 本堂(改修中)
入母屋造銅本棒葺流れ向拝で軒唐破風。大棟には菊花紋と五七桐紋を交互に置いています。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂向拝


【写真 上(左)】 向拝(閉扉時)
【写真 下(右)】 向拝(開扉時)
向拝は三間で水引虹梁両端に木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に蟇股を置いています。
向拝柱には「専修念佛根本道場」、見上げに寺号扁額、堂内にも扁額を置く二重扁額です。


【写真 上(左)】 「専修念佛根本道場」
【写真 下(右)】 向拝扁額


【写真 上(左)】 二重扁額
【写真 下(右)】 本堂内-1


【写真 上(左)】 本堂内-2
【写真 下(右)】 御本尊
浄土宗では本堂を開放する寺院が多いですが、こちらも通常開扉され堂内拝観できます。
華やかな欄間彫刻、精緻な天井絵、金色に輝く天蓋や瓔珞など、さすがに名刹にふさわしい空間です。
中央の御本尊阿弥陀三尊像は、伝・鎌倉中期作といいます。
右檀には善導大師等身大立像と弁財天像が安置されています。
善導大師立像は、かつて二尊堂にあって良忠上人が聖光上人より拝受の像といい、由比ヶ浜漂着の縁起が伝わります。
弁財天像は、江ノ島辯才天ゆかりの縁起が伝わります。
左檀上には、如意輪観世音菩薩像(鎌倉三十三観音霊場第18番・七観音霊場札所本尊)と宗祖法然上人像が安置されています。

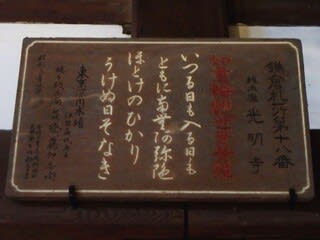
【写真 上(左)】 如意輪観世音菩薩像
【写真 下(右)】 観音霊場札所板


【写真 上(左)】 法然上人像
【写真 下(右)】 天井絵
令和2年春から10 年計画で保存修理工事が始まり、御本尊阿弥陀如来および諸尊像は開山堂に遷られています。
■ 大殿 令和の大改修【令和5年度ダイジェスト】―重要文化財光明寺本堂修理工事―
【記主庭園・大聖閣】
背後に小山をおく風雅な浄土宗庭園で、小堀遠州作と伝わります。
蓮池の蓮は夏に色とりどりに開花します。
大聖閣は宗祖法然上人800年大御忌を期して建立。二層には阿弥陀三尊が安置されています。


【写真 上(左)】 記主庭園
【写真 下(右)】 大聖閣
本堂背後の天照山は、良忠上人が天照大神の尊像を感得せられたことからの命名といいます。
中腹に良忠上人をはじめ歴代の墓所と開基である北条経時公(法名:蓮華寺殿安楽大禅定門)の墓所があります。
鎮守社・神明社、秋葉大権現も天照山に祀られています。
【神明社】
天照・春日・八幡の三神を合祀しています。
『新編相模国風土記稿』には、「神明宮 八幡春日を合祀す、域内鎮護の祠なり」とあります。
【秋葉社】
『新編相模国風土記稿』には、「秋葉社、九頭權現社、蔵王窟 後阜にあり」とあります。
寺伝には、当山三十三世深譽伝察上人が身を天狗に現じて当山を守護されたとあります。
御朱印は山内左手の庫裏・本坊附属棟にて拝受しました。
複数の御朱印を授与されていますが、↓ の注意書きがあります。
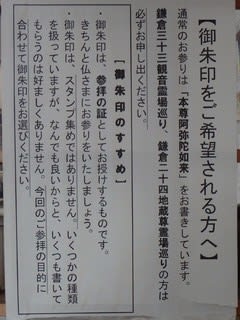
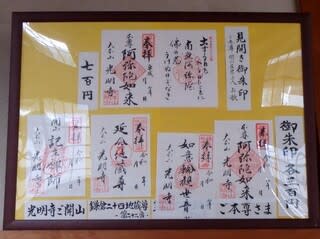
【写真 上(左)】 注意書き
【写真 下(右)】 御朱印見本(金額は変更の可能性あり。)
〔 光明寺の御朱印 〕
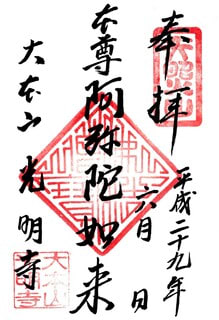
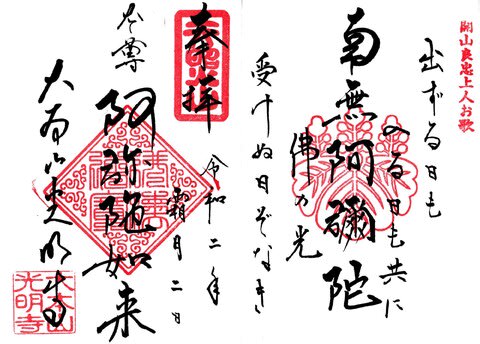
【写真 上(左)】 御本尊の御朱印
【写真 下(右)】 御名号の御朱印

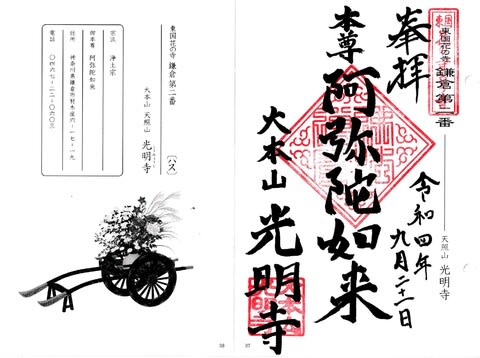
【写真 上(左)】 開山 記主禅師の御朱印
【写真 下(右)】 東国花の寺霊場の御朱印

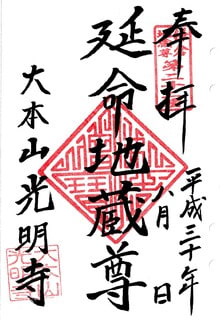
【写真 上(左)】 鎌倉三十三観音霊場の御朱印
【写真 下(右)】 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印
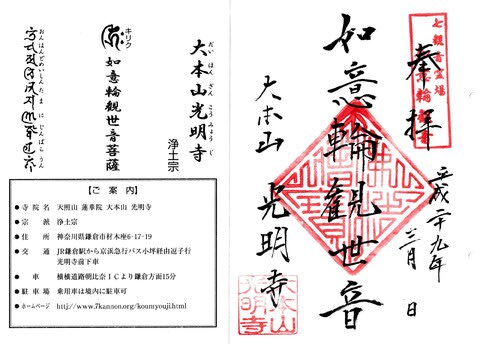
七観音霊場の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-12 (B.名越口-6)へつづく。
【 BGM 】
■ David Benoit - The Key To You
■ King of Hearts - Don't Call My Name
■ Bryan Ferry & Roxy Music - Avalon
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 鎌倉市の御朱印-10 (B.名越口-5)
書きかけの「鎌倉市の御朱印」に戻ります。
しばらくつづけます。
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)から。
33.蛭子神社(ひるこじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市小町2-23-3
御祭神:大己貴命
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、小町一帯の産土神
元別当:妙厳山 本覚寺(鎌倉市小町)
蛭子神社は小町大路に面する小町地区の鎮守社です。
蛭子神社の縁起沿革はすこぶる複雑で、本覚寺内の夷三郎社、宝戒寺内の山王大権現、現在地に御鎮座の七面大明神の合祀といいます。
各社の縁起沿革を順に追ってみます。
【 夷三郎社(夷堂) 】
滑川は鎌倉十二所、二階堂方面から鶴岡八幡宮東脇~若宮大路に沿って流れ、由比ヶ浜に注ぐ鎌倉随一の河川です。
源頼朝公は鎌倉幕府の裏鬼門除けのために小町大路が滑川を渡る橋のたもとに「夷三郎社」(夷堂)を祀ったといい、この橋を「夷堂橋」といいます。
当所は小町と大町の境。
夷堂橋の上に立って左右を眺めると西は本覚寺山門、東は妙本寺参道で、信仰的にも重要な場であることがわかります。


【写真 上(左)】 夷堂橋の石碑
【写真 下(右)】 夷堂橋から本覚寺
「本覚寺公式Web」「鎌倉公式観光ガイド(鎌倉市観光協会)」等によると、夷堂はもともと天台宗系でしたが、文永十一年(1274年)流罪の地・佐渡から鎌倉に戻られた日蓮聖人が約40日間滞在されたお堂といい、鎌倉幕府に対して三度目の諫暁をされ、受け入れられなかったために身延への隠棲を決められたと伝わります。
鎌倉幕府滅亡(正慶二年(1333年))の際に焼失したともいいますが、永享八年(1436年)この地にあった天台宗夷堂を、一乗房日出上人が日蓮宗に改め開創したのが本覚寺と伝わります。
Wikipediaには、「永享法難」をめぐる一乗房日出上人と本覚寺創建の由来が記されています。抜粋引用します。
---------(抜粋引用はじめ)
永享八年(1436年)、気鋭の布教伝道で名高い一乗房日出が常在山本覺寺(静岡県三島市)から鎌倉へ転出するも、足利持氏は弾圧処分を試みた。これに反発する信徒衆が荒居閻魔堂(現・新居山圓應寺)に集結し一触即発の状態になった。持氏はこの騒動が“鎌倉府討伐の口実”となる事を憂慮し処分を撤回。更に日出に対して日蓮の国家諌暁ゆかりの夷堂とその社領12000坪を寄進して法華寺院の建立を認めた。これが本覺寺創建の由来と伝えられている。
---------(抜粋引用おわり)
夷三郎社(夷堂)は旧地の橋のたもとから本覚寺山内に遷され、ひきつづき夷三郎社と称して山内の鎮守と仰がれましたが、明治初期の神仏分離により同山の管理を離れ、現社地に御鎮座の小町下町の鎮守・七面大明神に合祀されたといいます。
【 宝戒寺内の山王大権現 】
『新編鎌倉志』には「(宝戒寺)山門を入て右にあり。」とあり、小町上町の鎮守といいます。
『鎌倉市史』には「山王権現は応永二年(1395年)二月に宝戒寺住持興顗が山王七社と大行事早尾の御正躰一面を造立している。御神体はもとからあったというから、山王社は恐らく草創と共に勧請されていたのであろう。」とあり、宝戒寺草創当初(観応三年(1352年)頃造営)から山内に御鎮座とみられます。
『山門秘書記』翻刻版(小峯和明氏/PDF)、Wikipediaの「山王権現」によると、山王七社とは日吉大社の本社・摂社・末社二十一社を上・中・下に七社ずつ分けていう呼び名のうち、とくに上の七社をさすといい、大宮(大比叡)・二宮(小比叡)・聖真子・八王子・客人・十禅師・三宮の七所です。
大行事権現は中七社の一社で本地を毘沙門天といい、天台宗寺院の地主神として本堂の裏手等に祀られる例があります。
早尾権現も中七社の一社で本地を不動明王といいます。
上記の山王七社と大行事権現、早尾権現を併せて(宝戒寺の)山王大権現と称していた可能性があります。
明治維新後の神仏分離令により宝戒寺から分離され、現社地に御鎮座の七面大明神に合祀されたといいます。
【 小町下町の鎮守・七面大明神 】
小町下町の鎮守・七面大明神についての縁起沿革は見つかりませんでしたが、神号からおそらく日蓮宗系の尊格と思われます。
以上のとおり、もともと現在地に御鎮座の小町下町の鎮守・七面大明神、本覚寺山内の夷三郎社、宝戒寺山内に御鎮座で小町上町の鎮守・山王大権現の3社を合祀して、明治7年8月蛭子神社を号したとみられます。
明治6年の村社列格を記念して、明治7年社殿を新築。
本殿は、そのときに鶴岡八幡宮末社今宮の社殿を譲り受け移築したものといいます。
昭和15年神饌幣帛料供進神社に指定。
『鎌倉市史』には、旧社殿は関東大震災で大破し、昭和8年改築とあります。
3社合祀の沿革で御祭神が気になるところですが、神奈川県神社庁資料には大己貴命(おおなむちのみこと)と記されています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
夷堂橋
夷堂橋は、小町と大町との境にあり。座禅川の下流なり。昔は此邊に夷三郎社ありしとなり。今はなし。
寶戒寺(山王権現社)
門を入て右にあり。
■ 神奈川県神社庁Web資料
蛭子神社
新編相模風土記稿に「夷堂橋は 此辺に夷三郎社ありしとなり」とある如く、産土神であったが、其所に本覚寺が創建され、地主神として山門の鎮守として奉斎されていたが、神仏分離令により寺内より離れ、小町村の鎮守として明治6年村社に列格された、付近の山王権現、七面大明神などを合祀に明治7年8月、蛭子神社と称した。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
蛭子神社
ヒルコと読む。祭神、大己貴命。例祭九月十五日。元指定村社。境内地八二.六二坪。拝殿・本殿・社務所あり。本殿は明治七年八月、鶴岡八幡宮の末社今宮の社殿を譲りうけて建立したものである。
小町の鎮守。この所にはもと小町下町の鎮守七面大明神が祀られていたが、神仏分離により本覚寺の鎮守であった夷三郎社をここに移し、かつ上町下町が一村に合され一村に鎮守は一社しかおかぬという達しによって、小町上町の宝戒寺鎮守山王大権現も合祀したという。
夷三郎社は『風土記稿』本覚寺境内図に見えている。いま本覚寺山門前の橋を夷堂橋というのはこの社によってつけられた名といわれている。
宝戒寺の山王も『風土記稿』同寺の項に見えている。現在の社殿は大正十二年関東大震災で大破したが、昭和八年九月改築したもの。
宝戒寺(山王権現の項)
寛永十二年、弁盛が宝戒寺造営のことについて目安を江戸幕府に上った。それによると、境内には本堂・僧堂・鎮守(山王権現)があり、山王権現は応永二年二月に宝戒寺住持興顗が山王七社と大行事早尾の御正躰一面を造立している。
御神体はもとからあったというから、山王社は恐らく草創と共に勧請されていたのであろ
う。
■ 境内掲示(鎌倉市)(「猫のあしあと」様より/抜粋)
鎮守蛭子神社は出雲大社に鎮ります大国主神を御祭神として(里俗夷尊神)と称され、往古永享年間(凡五百余年前)日蓮宗本覚寺前夷堂端の傍に夷堂あり夷三郎社とも称され、同寺の守護神として、又付近住民の氏神様として崇敬されたが、明治維新に神仏分離によりこの地に鎮座し、同時に宝戒寺門前地区の氏神として、同寺境内に祀られし北条一門の守護神山王大権現をも之に合祀し、蛭子神社と称するに至った。
爾来百余年えびす様の愛称で福の神・むすびの神として信仰され遠近より善男善女の参詣多く神賑を極め今日に至った。
■ 鎌倉公式観光ガイド(鎌倉市観光協会)
鎌倉十橋(かまくらじっきょう)/夷堂橋
夷堂橋は、本覚寺門前を流れる滑川に架かる橋で、その名は本覚寺の仁王門前あたりにあったとされる夷堂に由来します。夷堂は源頼朝が御所の裏鬼門に夷神をまつった夷三郎社が始まりで、滑川もこのあたりでは夷堂川とも呼ばれていました。現在夷堂は本覚寺の境内にあります。
夷堂橋(えびすどうばし)
設置場所:小町1-12-12
本覚寺前。鎌倉十橋の一つ。かって、この橋のたもとに源頼朝が幕府の鬼門除けのために創建した「夷三郎社」(夷堂)があったことからこの名前になったと言われています。
本覚寺
小町大路が滑川を渡るところに、源頼朝が幕府の守り神として創建した夷堂がありました。
今も夷堂橋があります。
日蓮が滞在していたお堂で、その後ここから身延山へ旅立ちました。
夷堂は鎌倉幕府滅亡のときに焼け、その跡につくられたのが本覚寺です。
1436(永享8)年、もとこの地にあった天台宗夷堂を日出上人が日蓮宗に改めたのがはじまりと伝えます。
■ 本覺寺公式Web(日蓮宗)
本覺寺の創立は永享8年(1436)ですが、夷堂の歴史はさらに古く、鎌倉時代の初期頃と伝わります。そしてこの夷堂は日蓮聖人とも縁が深く、流罪の地・佐渡から鎌倉に戻られた日蓮聖人が、40数日滞在されたといわれています。その間に、日蓮聖人は鎌倉幕府へ3度目の諫暁をされ、受け入れられなかったために身延への隠棲を決められるなど、後の布教のあり方などを大きく変えられました。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
本覚寺
寺ではこの地は『吾妻鏡』にみえる夷堂の地であるという。そして日蓮は佐渡から帰ってここに留錫し、この地から身延に移った。夷堂はもと天台宗の寺であったといい、その本尊と伝える釈迦・文殊・普賢の像がある。日出が改宗して創建した。
『風土記稿』所蔵の絵図には、夷三郎社・番神堂・祖師分骨堂などもみえる。
-------------------------
鎌倉駅にもほど近い小町大路に面して御鎮座、「日蓮上人辻説法跡」にも至近です。
小町大路に面する社頭・参道の間口は広くなく、あまり目立たないので観光客の参拝はさほど多くはないのでは。
御朱印が授与されていることも、あまり知られていないかと思います。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 社号標
社頭に社号標と亀腹を置く明神鳥居で、社号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 鳥居扁額
【写真 下(右)】 参道
しかしながら小町の鎮守であり、鎌倉有数の名刹、本覚寺、宝戒寺と古いゆかりをもつこともあってか、参道を進むにしたがい神さびた空気感に包まれます。
桟瓦葺で木鼻獅子や蟇股を備えた立派な手水舎。
手水鉢には「魚がし」の刻字。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 斜めからの拝殿
拝殿は南面し、向かってすぐ右手(東側)は滑川です。


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 拝殿扁額
拝殿は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、向拝上に唐破風を置いています。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に精緻な彫刻を置いています。
唐破風の鬼板や兎の毛通しも見事な出来映えで見応えがあります。
向拝正面桟唐戸の上部に、端正な字体の社号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 天水鉢
向拝桟唐戸と殿前の天水鉢とに同じ紋を置いています。
梶の葉紋系統にも思えますが、諏訪系の梶の葉紋とは趣を異にしていて、他の神紋を当たってみましたが該当する紋がみつからず、よくわかりません。
御朱印は大町の八雲神社にて拝受しました。
〔 蛭子神社の御朱印 〕
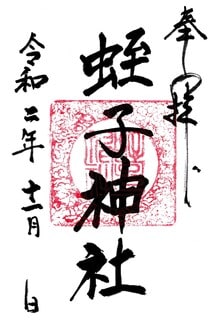
34.長慶山 正覺院 大巧寺(だいぎょうじ)
公式Web
鎌倉市小町2-17-20
単立(日蓮宗系)
御本尊:産女霊神(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
大巧寺は小町にある日蓮宗系単立寺院で、「おんめさま」の愛称で親しまれています。
当初は十二所の梶原屋敷内にあったといい、長慶山正覺院大行寺と号す真言宗寺院でした。
大行寺は頼朝公の祈願所で、この寺で軍評定した戦に勝利したため大巧寺と改めたといいます。
後に小町の現在地に移転。
日蓮聖人が妙本寺御在時の折、住僧が聖人に帰依して日蓮宗に改宗。
開山は九老僧の日澄上人とも日證上人とも伝わります。
「(朗門の)九老僧(朗門九鳳)」とは、日蓮六老僧の一人・筑後房日朗上人の9人の高弟を指します。
日澄上人 (大乗坊、1239-1326年?)は、比企谷門流の僧で九老僧(朗門九鳳)のひとりです。
『新編相模國風土記稿』には、小田原の妙珍山圓成院蓮昌寺の項で当山開山が九老ノ一、形善院日澄上人(文保元年(1317年)卒)であること。開基は小田原の濱名豊後守時成(永仁六年(1298年)卒)であること。時成は日蓮上人の投宿に随喜して出家し、妙音院日行を号したこと。時成の子は祖母妙珍尼に養われ、七歳で出家し日澄と号したこと。北條氏政の家臣・濱名時成は鎌倉小町大巧寺の檀那で、天正三年(1575年)大巧寺に寺領を寄附したこと。法名を妙法といい大巧寺に墓があり、子の蓮真と母妙節等の碑があることなどが記されています。
神奈川県平塚市の松雲山 要法寺の公式Webには、歴代上人として「二祖 九老僧 形善院日澄上人」「喜暦元(丙寅)年(1326年)八月1日化 池上大坊開山 本要阿闍梨小田原浜名豊後守時成長男」とあります。
また、池上大坊 本行寺の公式Webにも、「3祖大乗阿闍梨 形善院 日澄(嘉歴1(1326)没)」と明記されています。
上記から、大巧寺は小田原で日蓮上人に宿を提供した濱名豊後守時成(永仁六年(1298年)卒)の子で、九老僧のひとり形善院日澄上人(嘉歴元年(1326年)寂)の開山ともみられます。
しかし、天正三年(1575年)大巧寺に寺領を寄附した檀那・濱名時成は北條氏政(1538-1590年)の家臣で、鎌倉時代と戦国時代にそれぞれ2人の濱名時成が大巧寺とゆかりをもったことになりますが、詳細は不明です。
なお、濱名氏は源三位頼政の子孫といわれ、「鵺退治」で有名な頼政が恩賞に賜った遠江国堀之内郷を領したことから「鵺代」とも称しました。
濱名詮政は足利将軍義満公の信任厚かった記録があり、著名な歌人を輩出したことでも知られていますが、濱名氏の本拠は遠江で戦国期は今川氏との関係が深く、小田原や鎌倉に拠点をもった濱名時成がこの系統かどうかは不明です。
大巧寺は妙本寺の院家寺院でしたが、現在は単立寺院となっています。
大巧寺は安産祈願で有名で、「安産腹帯守」を求めて多くの参詣者があります。
安産祈願は『産女霊神縁起』にもとづくものです。
詳細は公式Web(PDF)で紹介されていますが、概要は以下のとおりです。
当山第五世日棟上人は毎夜妙本寺の祖師堂に詣でていましたが、天文元年(1532年)4月のある夜、夷堂橋の脇で産女の霊と遭遇しました。
やつれた様子の産女の霊は、日棟上人に自分は大倉に住む秋山勘解由の妻で難産によりこの世を去ったが、死出の旅路に迷って成仏できない。
どうぞよしなに回向をいただき成仏に導いていただきたいと訴えました。
哀れに思った日棟上人は法華経を読経して回向すると、女はいつのまにか姿を消していました。
数日後、日棟上人の前にみちがえったように美しい件の産女が現れ、上人の回向により成仏できたことを謝し、布に包んだ金銭を奉じたうえで、夫の秋山勘解由にこの経緯を伝え、宝塔を建立し供養して欲しいと訴えました。
そして、宝塔を供養してくれればその恩返しとして、今後、この塔に妊婦が参詣すれば安産となるよう尽力することを伝えました。
上人はこの願いに報いることを約すと、すぐに大倉の秋山勘解由を訪れました。
勘解由はこの話におどろきましたが、妻が日頃からこつこつとお金を蓄えていたこと、上人に奉じた金銭を包んでいた布は、妻が残した小袖の片袖であったことがわかりました。
勘解由は妻の回向を上人に深く謝し、自らも上人と師壇の契りを結んで宝塔建立への協力を申し出ました。
上人は「産女霊神」と号して産女の霊を祀り、宝塔を建立して手厚く供養しました。
この縁起を聞いて妊婦が参詣すると、みな安産となったので、当山は安産祈願で有名となったといいます。
この縁起を読んだとき、疑問に感じたことがあります。
・秋山勘解由について
鎌倉に秋山姓は少ないですが、あえて「大倉に住む秋山勘解由」と明記していること。
・上人への宝塔建立のお布施
諸史料は秋山勘解由の財産ではなく、産女の私財と強調していること。
・天文元年(1532年)という年号
Web検索していくと、「おんめさま 産女(うぶめ)伝説 (私説)」という記事がみつかりました。
秋山姓は甲斐発祥の甲斐源氏で、のちに武田二十四将の秋山伯耆守虎繁(信友)を生んでいます。
そして、天文三年(1534年)には武田信玄の正室・上杉の方(上杉朝興の息女)が難産で逝去しています。
上の記事では、私説として「おんめさま」と上杉の方との関係を示唆しています。
そこで筆者の想像も含めて整理してみます。
秋山氏は甲斐源氏・加賀美遠光の嫡男・光朝を祖とし、巨摩郡秋山を領しました。
秋山光朝は上京して平重盛に仕え、重盛の息女(六女・茂子)を室としたといいます。
平家滅亡後に甲斐に戻りますが、一時平家に使えていたことで頼朝公にうとまれ、居城雨鳴城を攻められ自害、あるいは鎌倉で暗殺されたともいいます。
しかし子孫は存続し、同族の甲斐武田氏に属しました。
武田家の重臣であった秋山伯耆守虎繁は大永七年(1527年)の生まれですから、上杉朝興の息女が武田晴信(信玄公)に嫁いだ天文二年(1533年)には一族の誰かが上杉の方の甲斐での後見役ないし世話役に任ぜられた可能性もあるのでは。
話が飛びますが戦国末期、穴山信君は甲斐源氏で武田家臣の秋山越前守虎康の息女を養女とし、この養女は天正十年(1582年)、信君が織田・徳川氏に臣従した際に徳川家康公の側室となりました。(下山殿/お都摩の方)
下山殿は天正十一年(1583年)、家康公の五男・万千代君(武田信吉公)を出産。
信吉公は下総小金城3万石~下総佐倉城10万石と移り、佐竹氏に替わって水戸25万石の太守となり、旧武田遺臣を付けられて武田氏を再興するやにみえましたが、慶長八年(1603年)21歳で死去し武田氏再興はなりませんでした。
下山殿は天正十九年(1591年)下総国小金にて早逝。平賀の日蓮宗の名刹・長谷山 本土寺に葬られました。
また、下山殿の実父(武田信吉公の実祖父)・秋山虎康は松戸市大橋の地に止住し、慶長元年(1596年)に了修山 本源寺を開山しているのでおそらく日蓮宗信徒です。
下山殿の「下山」は身延町下山から称したといいます。
『穴山氏とその支配構造』/町田是正氏(PDF)には「(秋山氏の祖)秋山太郎光朝の末の下山氏の住する処で(中略)『日蓮聖人遺文』にも下山氏の存在が記される所」とあり、下山殿の実家の秋山氏は、京よりはやくに讃岐に日蓮宗を伝えた(→ビジネス香川)ともいいますから、そんなこともあって日蓮宗寺院と秋山氏は結びつきやすかったのかもしれません。
さすがに話が飛びすぎました。
---------------------------------
信玄公の正室を三条の方(左大臣・三条公頼の次女)とする資料もありますが、正式には継室で、正室は上杉の方です。
上杉の方が嫁いだとき信玄公はわずか13歳で、上杉の方も同年代といいます。
天文三年(1534年)に出産の折、年若い上杉の方は難産であえなく逝去されました。
その頃、上杉の方の父・上杉朝興は扇谷上杉家の家督を嫡男・朝定に譲ったものの川越城に依り、相模国に盛んに兵を出しています。
年若くして難産で世を去った息女の供養は、父親としてごく自然な感情です。
しかし、当時の扇谷上杉家は古河公方、関東管領(山内上杉家)、武田家、後北条家、越後長尾家などとすこぶるデリケートな関係にあり、政略結婚で命を落とした娘の供養を、(娘に仕えていた)秋山勘解由の妻に託したという想像もあるいは許されるかもしれません。
また、秋山勘解由の在所は大倉(大蔵)で旧・大蔵幕府の跡、かつては幕政の中心地で官吏なども住んでいたと思われます。
上杉朝興は扇谷上杉家で関東管領ではないですが、関東管領(山内上杉家)に比肩する勢力をもち、その家人や与力衆はこの辺に住んでいたかもしれません。
勘解由の名も官吏・文官的な性格をイメージさせます。
このような背景から「おんめさま 産女(うぶめ)伝説 (私説)」は、「彼女(上杉の方)に仕えていた秋山勘解由の妻は、葬儀を終えて鎌倉の大倉に帰って来た。彼女の死後1年を過ぎて、自宅近くの寺に彼女を弔った。傷心の上杉朝興(46歳)は、彼女を通じて寺に寄進をし、娘の菩提を弔う秋山勘解由の心遣いを喜んだ。」という私説を展開されているのでは。
なお、大巧寺と上杉の方・上杉朝興の関係を示唆する史料は見当たらないので、上の内容はあくまでも想像で、お寺の紹介としてはいささか飛躍が過ぎたかもしれません。
いずれにしても、大巧寺は寺院が集まる鎌倉市内でも「安産祈願」という格別のご利益をもって広く信仰を集めていることは間違いありません。
寺宝で、産女霊神神骨を収めるという宝塔(水晶五輪塔)は、旧本山の妙本寺に預けられていましたが、平成23年に返却されて以降、当山にて格護されています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
大巧寺
大巧寺は、小町の西頰にあり。相伝、昔は長慶山正覺院大行寺と号し、真言宗にて、梶原屋敷の内にあり。後に大巧寺と改め、此地に移すとなり。梶原屋敷の條下に詳なり。昔し日蓮、妙本寺在世の時、此寺法華宗となり、九老僧日澄上人を開山とし、妙本寺の院家になれり。(略)
産女寶塔
堂の内に、一間四面の二重の塔あり。是を産女寶塔と云事は、相伝ふ、当寺第五世日棟と云僧、道念至誠にして、毎夜妙本寺の祖師堂に詣す。或夜、夷堂橋の脇より、産女の幽魂出て、日棟に逢、廻向に預て苦患を免れ度由を云。日棟これが為に廻向す。産女、䞋金一包を捧て謝す。日棟これを受て其為に造立すと云ふ。寺の前に産女幽魂の出たる池、橋柱の跡と云て今尚存す。夷堂橋の小北なり。
寺宝
曼荼羅 三幅 共に日蓮の筆。
無邊行菩薩名号 日蓮筆。
日蓮消息 壱幅
曼荼羅 壱幅 日朗筆。
舎利塔 壱基 五重の玉塔なり。
濱名石塔 北條氏政の家臣、濱名豊後守時成、法名妙法、子息蓮眞、母儀妙節、三人の石塔なり。
番神堂 濱名時成建立すと云。
梶原屋敷 附大巧寺𦾔跡
梶原屋敷は五大堂の北方山際にあり。梶原平三景時が𦾔跡なり。『東鑑』に、景時は正治二年(1200年)十二月十八日に、鎌倉を追出され、相模国一宮へ下る。彼家屋を破却して、永福寺の僧坊に寄附せらるとあり。頼家の時也。今此所に、大なる佛像の首ばかり、草庵に安置す。按ずるに『東鑑脱漏』に、安貞元年(1227年)四月二日、大慈寺の郭内に於て、二位家平政子第三年忌の為に。武州泰時、丈六堂を建らるとあり。此所大慈寺へ近ければ、疑らくは其丈六佛の首ならんか。又里老云、昔大行寺と云真言寺此所にあり。頼朝の祈願所にて、或は此寺にて、軍の評議して勝利を得られたり。故に大巧寺と改む。後に小町へ移し、日蓮宗となる。今の小町の長慶山大巧寺なりと、しかれども、『東鑑』等の記録に不見。按ずるに、五大堂を大行寺と号すれば、昔の大行寺の跡は、五大堂を云ならんか。不分明也。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
大巧寺
長慶山正覺院ト号ス。法華宗 古大行寺ト号シ。真言宗ニテ。今唱フル。梶原屋敷ノ内ニアリ。頼朝ノ祈願所タリ。或時此寺ニテ。軍評定妙本寺大町村ニ在シ時。当寺住僧帰依シテ改宗シ。日證ヲ開山トシ。妙本寺ノ院家ニ属セリ。(略)
天正三年(1575年)二月。濱名豊後守時成。鎌倉能成分。六貫文ノ地ヲ寄附ス。(略)
本尊ハ三寶諸尊ヲ安ス。(以下略)
■ 『新編相模國風土記稿12』(国立公文書館デジタルアーカイブ)
蓮昌寺(小田原筋違橋町)
日蓮宗。鎌倉比企谷妙本寺末。妙珍山圓成院ト号ス。開山日澄。形善院ト號ス。九老ノ一、文保元年八月十日卒。傳云。文永十一年(1274年)五月。日蓮身延ヘ入山ノ時。憩ヒシ旧蹟ニテ。後ニ一寺トナル。開基濱名豊後守時成。寺傳云。宗祖身延入山ノ時。当所豊後守時成ノ館ニ投宿セリ。其時時成随喜シテ出家シ。妙音院日行ト号ス。永仁六年(1298年)二月五日。尾州熱田ニテ卒ス。一子アリ。祖母妙珍尼ニ養レ七歳にて出家ス。日澄ト号ス。即当寺開山ナリ。日澄其祖父蓮昌。祖母妙珍菩提ノ為。当寺ヲ開キ。即祖父母ノ法号ニヨリテ。寺山号ニ名けケシト云。今按スルニ豊後守時成ハ。北條氏政ニ仕ヘシ人ニテ。鎌倉小町大巧寺ノ檀那ナリ。天正三年(1575年)二月。大巧寺ニ時成寺領を寄附セシ券状。今ニ彼寺ニ傳フ。又同寺ニ墳アリ。法名妙法ト云。其子蓮真母妙節等ノ碑モアリ。然ルヲ時成日蓮ノ弟子トナリ。日澄ヲ其子トナスノ類。(以下略)
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
大巧寺
長慶山正覺院大巧寺と号する。日蓮宗系 単立宗教法人。もと妙本寺の院家。
開山、日澄。本尊、産女霊神。本堂・庫裏・山門・門あり。
産女宝塔は妙本寺に預けてある。
寺伝によると、大巧寺はもと大行寺と号した。真言宗の寺で十二所にあり、頼朝が軍の評議をしたところであるという。また日蓮が妙本寺にいたとき、時の住持が帰依して文永十一年(1274年)に改宗したという。(略)
産女様
当寺は俗におうめさまといい、安産のお守りを出す。これは五世日棟が産女の幽魂を鎮めたところから起こったといわれている。
■ 山内掲示(鎌倉市)
宗派 日蓮宗系単立寺院
山号寺号 長慶山大巧寺
開山 日澄上人
初め「大行寺」という名でしたが、源頼朝がこの寺で行った軍評定(作戦会議)で大勝したので、「大巧寺」に改めるようになったと伝えられています。
室町時代の終わり頃、この寺の住職の日棟上人が、難産で死んだ秋山勘解由の妻を供養して成仏させました。その後、お産で苦しむ女性を守護するために、「産女霊神(うぶすめれいじん)」を本尊としてお祀りしました。
今も安産祈願の寺として、「おんめさま」の愛称で呼ばれ、多くの方が参詣されています。
-------------------------
若宮大路と小町大路双方に接し、鎌倉駅からもっとも近い寺社のひとつです。
たいていの鎌倉ガイドに載っているので、観光客の参詣も多いとみられます。


【写真 上(左)】 若宮大路口
【写真 下(右)】 寺号標
若宮大路に面して整った石積みの参道とその奥に山門。
参道入口の「安産子育 産女霊神 長慶山大巧寺」の標石、そして参道の正中に据えられた石が目立ちます。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 参道
山門は脇塀付切妻屋根銅板葺のおそらく四脚門で、渋い朱塗りが趣を添えています。
石畳の参道は、右手のビルの存在感はあるものの緑豊かで四季折々の花が咲くようです。


【写真 上(左)】 小町大路口
【写真 下(右)】 小町大路口のお題目塔
小町大路側からも参道が伸び、入口には寺号を配したお題目塔とその奥には門柱を置いています。
こちらからは本堂が正面で、本来の参道はこちら側かもしれません。
こちらの参道も緑豊かで、雑踏の鎌倉駅至近とは思えない落ち着いた空間です。


【写真 上(左)】 小町大路側の門柱
【写真 下(右)】 手水舎
山内に産女霊神、福子霊神の石の墓碑がありますが、写真は撮っておりません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝上部
本堂は入母屋造銅板棒葺流れ向拝で、向拝上に整った唐破風を置いています。
水引虹梁両端に獅子・獏(象かも)の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に二本の大瓶束と、その間に風格ある龍の彫刻を置いています。
彫刻の上段には笈形(おいがた)付大瓶束(たいへいづか)で、兎の毛通し&鬼板も配して見応えがあります。
向拝は桟の上に白壁(?)を置いた個性的な扉で、見上げの本蟇股とその上の三連の斗栱も存在感があります。


【写真 上(左)】 向拝中備
【写真 下(右)】 授与所
御首題・御朱印は本堂よこの授与所で拝受しましたが。Web情報によるとタイミングにより授与を休止されることもあるようです。
こちらの授与所では安産腹帯守が授与されています。
戌の日および大安の休日にはたいへん混雑するようです。
〔 大巧寺の御首題・御朱印 〕
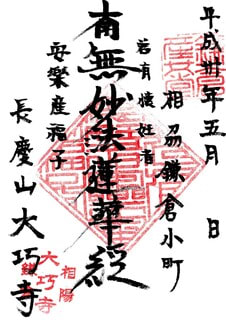

【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
35.妙厳山 本覺寺(ほんがくじ)
日蓮宗公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町1-12-12
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:鎌倉十三仏霊場第3番、鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)
司元別当:蛭子神社(鎌倉市小町)
本覺寺は小町にある日蓮宗の本山(由緒寺院)です。
身延山久遠寺の日蓮聖人の遺骨を分骨したため「東身延」とも呼ばれます。
鎌倉時代の初期、本覺寺の山門前の滑川にかかる端のたもとには「夷堂」と呼ばれる堂宇がありました。
鎌倉幕府の裏鬼門にあたり、源頼朝公が幕府守護のために夷堂を創建したといいます。
もとは天台宗系でしたが、文永十一年(1274年)に佐渡配流から戻られた日蓮聖人が約40日間にわたって夷堂に滞在され、鎌倉幕府に対し三度目の諫暁をされたものの、受け入れられなかったためついに身延への隠棲を決められたと伝わります。
(この「夷堂」の詳細については、33.蛭子神社を参照願います。)
夷堂は、鎌倉幕府滅亡(正慶二年(1333年))の際に焼失したともいいますが、永享八年(1436年)この地にあった天台宗夷堂を、一乗房日出上人が日蓮宗に改め開創したのが本覺寺と伝わります。
鎌倉公方・足利持氏開基説もみられます。
永享八年(1436年)、日蓮宗の布教伝道で名高い一乗房日出上人が常在山本覺寺(静岡県三島市)から鎌倉へ入られ、天台宗宝戒寺の僧・心海和尚と問答を繰り広げ(永享問答)、これをきっかけに騒動が起こったといいます。(永享法難)
Wikipediaには、「永享法難」をめぐる一乗房日出上人と本覺寺創建の由来が記されています。抜粋引用します。
---------(抜粋引用はじめ)
永享八年(1436年)、気鋭の布教伝道で名高い一乗房日出が常在山本覺寺(静岡県三島市)から鎌倉へ転出するも、足利持氏は弾圧処分を試みた。これに反発する信徒衆が荒居閻魔堂(現・新居山圓應寺)に集結し一触即発の状態になった。持氏はこの騒動が“鎌倉府討伐の口実”となる事を憂慮し処分を撤回。更に日出に対して日蓮の国家諌暁ゆかりの夷堂とその社領12000坪を寄進して法華寺院の建立を認めた。これが本覺寺創建の由来と伝えられている。
---------(抜粋引用おわり)
文安三年(1446年)に日出上人の弟子・行学院日朝上人が第2世として在寺され、15年ののちに身延山久遠寺第11世として入られ、身延山の再興を図られたといいます。
日朝上人は身延山への参詣が難しい老人や女性のために、身延山から日蓮聖人の遺骨を分骨して本覺寺に納めたため、以降当山は「東身延」とも称されました。
また、日朝上人は眼病救護の誓願を立てられたことから、当山は「日朝さま」とも呼ばれ鎌倉の庶民に親しまれました。
日蓮聖人の分骨の権威と、日朝上人の名声により、当山は鎌倉における日蓮宗の名刹の地位を確立し、後北条氏、豊臣氏、徳川氏から代々寺領を安堵され、塔頭末寺併せて10箇寺をもつ中本寺の格式を保ちました。
『新編鎌倉志』には「東三十三箇國、別して関八州の僧録」とあります。
僧録とは、僧侶の登録・住持の任免などの人事を統括した役職をいい、当山が大きな権威をもっていたことがうかがえます。
『鎌倉市史 社寺編』には「嘉永三年(1850年)の境内及び寺領の絵図があり、いまの市役所、市民座、駅前等を含む広い境内であったことがわかる。」とあるので、幕末の当山はすこぶる広大な寺領を有していたことがわかります。
開山七百年の節目にあたる昭和49年には日蓮宗本山(由緒寺院)に昇格し、いまも隆盛を保っています。
日蓮聖人ゆかりの夷堂は、山内鎮守の夷三郎社として祀られたといいますが、明治の神仏分離の際に蛭子神社に合祀されたといいます。
現在の八角形の夷堂は、昭和56年に建立されたものです。
名刹だけに文化財も豊富で、本堂安置の木造釈迦如来 、文殊菩薩、普賢菩薩の三尊像は
南北朝時代の作で宋風のすぐれた作風を伝えるとされ、鎌倉市指定の文化財です。
墓域には、鎌倉の住人で名刀工の正宗の墓があります。
正月三が日の「初えびす」、正月10日の「本えびす」には商売繁盛を願う参詣者たちで賑わい、10月の人形供養も古都・鎌倉の風物詩とされます。
鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)、鎌倉十三仏霊場第3番(文殊菩薩)の札所で、巡拝客や観光客も多く訪れる鎌倉の名所です。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
本覺寺
妙厳山と号す。身延山の末寺なり。開山日出上人。永享年中(1429-1441年)に草創すと云伝。此寺は東國法華宗の小本寺也。当寺三世日燿へ、日朝より書を遺して曰、総じて東三十三箇國、別して関八州の僧録に任じ置事に候へば、萬端制法肝要に候と云云。
う々、とありし由鎌倉志に見えたり、今此文書傳はらず。日朝上人は、日出上人の弟子、当寺第二世なり。廿歳にして身延山に住す。身延山第十一祖なり。在住四十年。身延山の諸法式も此代に定む。此書も身延山より遺はすと云ふ。本尊は釋迦・文殊・普賢なり。(以下略)
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
本覺寺
妙厳山ト号ス。法華宗身延山久遠寺末。永享年中(1429-1441年)ノ草創ニシテ開山ヲ日出(武州ノ人ナリ。始ハ是性坊ト号シ。天台宗ナリシカ。身延山日延ニ帰依シテ改宗シ。一乗坊ト称ス。)ト云フ。
当寺ハ東國法華宗ノ小本寺ナリ。日朝(当寺二世。本寺十一世ナリ。)身延山ニ在シ時。当寺三世日燿ヘ贈リシ書ニ。総して東三十三箇國。別シテ関八州ノ僧録ニ。任シ置事ニ候ヘハ。萬端制法。肝要ニ候云々。トアリシ由。鎌倉志ニ見エタリ。今此文書伝ハラス。(略)
本尊三寶ヲ安ス。又釋迦文殊普賢ノ像アリ。元ノ本尊ト云。
寺寶
曼陀羅一幅。日蓮筆。
日蓮消息十通。
記録一巻。日出天台宗ト問答ノ時。執権某是非ヲ糾シ。又修法ノ怪異ニ驚キ。褒賞シテ。田園ヲ寄附スルノ由。日出ノ書ナリ。巻尾ニ永享八年(1436年)五月晦日トアリ。
古文書十通。其文前ニ註記ス。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
本覚寺
妙厳山と号する。日蓮宗。もと身延山久遠寺末中本寺。開山、一乗日出。永享八年(1436年)の創建と伝える。
本尊、三宝祖師。境内地二六一四坪。本堂・祖師分骨堂・客殿・庫裏・鐘楼・二王門・横門棟あり。
寺ではこの地は『吾妻鏡』にみえる夷堂の地であるという。そして日蓮は佐渡から帰ってここに留錫し、この地から身延に移った。夷堂はもと天台宗の寺であったといい、その本尊と伝える釈迦・文殊・普賢の像がある。日出が改宗して創建した。
二世日朝の書状に本覚寺大浄坊を関八州の僧録となすことがみえ東身延と称している。
俗に日朝様とよぶ。串川光明寺にある善宝寺寺池の図にみえる法華堂はここのことであろう。(略)
嘉永三年(1850年)の境内及び寺領の絵図があり、いまの市役所、市民座、駅前等を含む広い境内であったことがわかる。
『風土記稿』所蔵の絵図には、夷三郎社・番神堂・祖師分骨堂などもみえる。
なお境内の墓地には正宗の墓と伝えるものがある。
■ 山内掲示(鎌倉市)
宗派 日蓮宗
山号寺号 妙厳山本覚寺
建立 永享8年(1436)
開山 日出
本覚寺のあるこの場所は幕府の裏鬼門にあたり、源頼朝が鎮守として夷堂を建てた所といわれています。
この夷堂を、日蓮が佐渡配流を許されて鎌倉に戻り、布教を再開した際に住まいにしたと伝えられます。その後、鎌倉公方・足利持氏がこの地に寺を建て、日出に寄進したのが本覚寺であるといい、二代目住職の日朝が、身延山から日蓮の骨を分けたので「東身延」と呼ばれています。
日朝は「眼を治す仏」といわれ、本覚寺は眼病に効く寺「日朝さま」の愛称で知られています。
十月は「人形供養」、正月は福娘がお神酒を振舞う「初えびす」でにぎわいます。
鎌倉の住人、名刀工・正宗の墓が境内にあります。
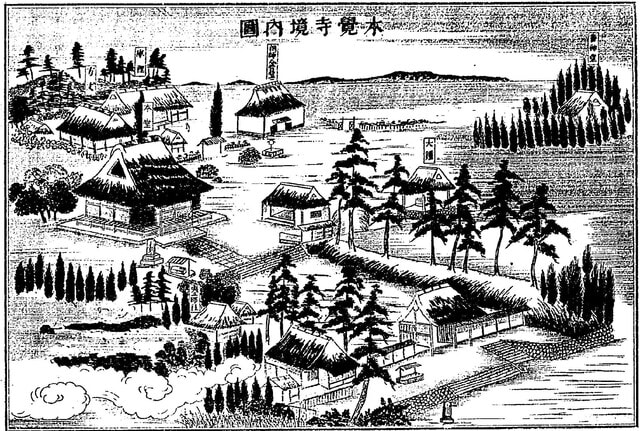
原典:間宮士信 等編『新編相模国風土記稿』第4輯 鎌倉郡,鳥跡蟹行社,明17-21.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
小町大路に接し、鎌倉駅からもっとも近い寺社のひとつです。
鎌倉市内の名所の位置づけで、観光客の参詣も多いとみられます。
「日蓮上人辻説法跡」にもほどちかいところです。


【写真 上(左)】 日蓮上人辻説法跡
【写真 下(右)】 夷堂橋から山門


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 斜めからの山門
小町大路が滑川を渡る夷堂橋のたもとに山門(二王門)があります。
桟瓦葺の楼門。両脇間に二王尊を安する三間一戸の八脚門で、大寺の風格があります。
手前には台座に「東身延」とある大きなお題目塔。


【写真 上(左)】 山門前のお題目塔
【写真 下(右)】 夷堂
山門をくぐって右側に鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)である夷堂。
銅板葺の屋根上に相輪を置き、急傾斜でむくり気味の屋根の角部が向拝になっている変わった意匠で、宝形造とも思いますがよくわかりません。
向拝には「夷尊堂」の扁額を掲げています。
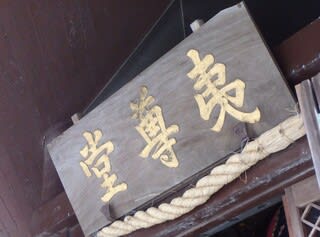

【写真 上(左)】 夷堂の扁額
【写真 下(右)】 授与所と参道


【写真 上(左)】 客殿?
【写真 下(右)】 手水舎
参道を進むと左手が授与所と、その奥は庫裏と客殿でしょうか。
さらに行くと右手に虹梁、木鼻、斗栱、中備を備えた立派な手水舎。
手水鉢では剣に二軆の龍が巻き付いた、倶利迦羅剣のような吐水口から水が注がれています。
その奥手に均整のとれた鐘楼。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 本堂前
【写真 下(右)】 本堂
正面本堂の堂前に香炉、金灯籠、石灯籠と天水鉢。
本堂は基壇上に入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、向拝上に軒唐破風をおこしています。


【写真 上(左)】 向拝-1
【写真 下(右)】 向拝-2
向拝は三間で水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に三連の蟇股を置いています。
各所に菱格子、格子を配して引き締まったイメージの意匠です。
向拝見上げに各号扁額を掲げていますが、達筆すぎて読解できず。(常拝閣か/?)


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 しあわせ地蔵尊


【写真 上(左)】 日蓮上人分骨堂
【写真 下(右)】 斜めからの分骨堂
本堂向かって右手奥にまわると、濡佛のしあわせ地蔵尊。
その奥には堂前に宝塔、香炉、石灯籠を配した日蓮上人分骨堂。
当山が「東身延」と呼ばれる由縁の重要な堂宇です。
桟瓦葺、二層の楼閣で、二層屋根の基盤上に宝珠。
堂回りに瑞垣をまわし、堂前は日蓮宗の宗紋「井桁橘」が刻まれた石扉で閉ざされています。
向拝の桟唐戸と両脇の花頭窓が、シンプルながら風格を感じさせます。
大寺ながら堂宇や山内佛がすくなく、明るくすっきりとして公園のような印象です。


【写真 上(左)】 路地からの脇門
【写真 下(右)】 脇門
若宮大路から小町大路に抜ける路地側にも山門があります。
脇塀付き切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、脇門ながら風格があります。
門前にお題目塔と「一天四海皆妙法」の石碑。


【写真 上(左)】 脇門前のお題目
【写真 下(右)】 脇門前の石碑
御首題・御朱印は参道左手の授与所で拝受しました。
札所でもあるので、複数の御朱印を授与されています。
〔 本覺寺の御首題・御朱印 〕
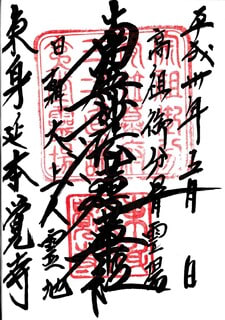

【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 日朝大上人の御朱印

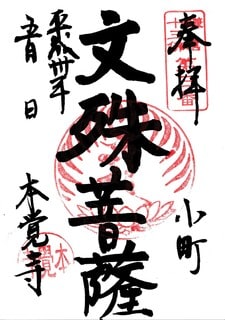
【写真 上(左)】 夷神(鎌倉・江ノ島七福神)の御朱印
【写真 下(右)】 文殊菩薩(鎌倉十三仏霊場)の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-11 (B.名越口-5)へつづく。
【 BGM 】
■ 私にはできない - Eiーvy
■ Re:Call - 霜月はるか
■ あなたの夜が明けるまで - Covered by 春吹そらの
しばらくつづけます。
■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)
■ 同-2 (A.朝夷奈口)
■ 同-3 (A.朝夷奈口)
■ 同-4 (A.朝夷奈口)
■ 同-5 (A.朝夷奈口)
■ 同-6 (B.名越口-1)
■ 同-7 (B.名越口-2)
■ 同-8 (B.名越口-3)
■ 同-9 (B.名越口-4)から。
33.蛭子神社(ひるこじんじゃ)
神奈川県神社庁Web
鎌倉市小町2-23-3
御祭神:大己貴命
旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、小町一帯の産土神
元別当:妙厳山 本覚寺(鎌倉市小町)
蛭子神社は小町大路に面する小町地区の鎮守社です。
蛭子神社の縁起沿革はすこぶる複雑で、本覚寺内の夷三郎社、宝戒寺内の山王大権現、現在地に御鎮座の七面大明神の合祀といいます。
各社の縁起沿革を順に追ってみます。
【 夷三郎社(夷堂) 】
滑川は鎌倉十二所、二階堂方面から鶴岡八幡宮東脇~若宮大路に沿って流れ、由比ヶ浜に注ぐ鎌倉随一の河川です。
源頼朝公は鎌倉幕府の裏鬼門除けのために小町大路が滑川を渡る橋のたもとに「夷三郎社」(夷堂)を祀ったといい、この橋を「夷堂橋」といいます。
当所は小町と大町の境。
夷堂橋の上に立って左右を眺めると西は本覚寺山門、東は妙本寺参道で、信仰的にも重要な場であることがわかります。


【写真 上(左)】 夷堂橋の石碑
【写真 下(右)】 夷堂橋から本覚寺
「本覚寺公式Web」「鎌倉公式観光ガイド(鎌倉市観光協会)」等によると、夷堂はもともと天台宗系でしたが、文永十一年(1274年)流罪の地・佐渡から鎌倉に戻られた日蓮聖人が約40日間滞在されたお堂といい、鎌倉幕府に対して三度目の諫暁をされ、受け入れられなかったために身延への隠棲を決められたと伝わります。
鎌倉幕府滅亡(正慶二年(1333年))の際に焼失したともいいますが、永享八年(1436年)この地にあった天台宗夷堂を、一乗房日出上人が日蓮宗に改め開創したのが本覚寺と伝わります。
Wikipediaには、「永享法難」をめぐる一乗房日出上人と本覚寺創建の由来が記されています。抜粋引用します。
---------(抜粋引用はじめ)
永享八年(1436年)、気鋭の布教伝道で名高い一乗房日出が常在山本覺寺(静岡県三島市)から鎌倉へ転出するも、足利持氏は弾圧処分を試みた。これに反発する信徒衆が荒居閻魔堂(現・新居山圓應寺)に集結し一触即発の状態になった。持氏はこの騒動が“鎌倉府討伐の口実”となる事を憂慮し処分を撤回。更に日出に対して日蓮の国家諌暁ゆかりの夷堂とその社領12000坪を寄進して法華寺院の建立を認めた。これが本覺寺創建の由来と伝えられている。
---------(抜粋引用おわり)
夷三郎社(夷堂)は旧地の橋のたもとから本覚寺山内に遷され、ひきつづき夷三郎社と称して山内の鎮守と仰がれましたが、明治初期の神仏分離により同山の管理を離れ、現社地に御鎮座の小町下町の鎮守・七面大明神に合祀されたといいます。
【 宝戒寺内の山王大権現 】
『新編鎌倉志』には「(宝戒寺)山門を入て右にあり。」とあり、小町上町の鎮守といいます。
『鎌倉市史』には「山王権現は応永二年(1395年)二月に宝戒寺住持興顗が山王七社と大行事早尾の御正躰一面を造立している。御神体はもとからあったというから、山王社は恐らく草創と共に勧請されていたのであろう。」とあり、宝戒寺草創当初(観応三年(1352年)頃造営)から山内に御鎮座とみられます。
『山門秘書記』翻刻版(小峯和明氏/PDF)、Wikipediaの「山王権現」によると、山王七社とは日吉大社の本社・摂社・末社二十一社を上・中・下に七社ずつ分けていう呼び名のうち、とくに上の七社をさすといい、大宮(大比叡)・二宮(小比叡)・聖真子・八王子・客人・十禅師・三宮の七所です。
大行事権現は中七社の一社で本地を毘沙門天といい、天台宗寺院の地主神として本堂の裏手等に祀られる例があります。
早尾権現も中七社の一社で本地を不動明王といいます。
上記の山王七社と大行事権現、早尾権現を併せて(宝戒寺の)山王大権現と称していた可能性があります。
明治維新後の神仏分離令により宝戒寺から分離され、現社地に御鎮座の七面大明神に合祀されたといいます。
【 小町下町の鎮守・七面大明神 】
小町下町の鎮守・七面大明神についての縁起沿革は見つかりませんでしたが、神号からおそらく日蓮宗系の尊格と思われます。
以上のとおり、もともと現在地に御鎮座の小町下町の鎮守・七面大明神、本覚寺山内の夷三郎社、宝戒寺山内に御鎮座で小町上町の鎮守・山王大権現の3社を合祀して、明治7年8月蛭子神社を号したとみられます。
明治6年の村社列格を記念して、明治7年社殿を新築。
本殿は、そのときに鶴岡八幡宮末社今宮の社殿を譲り受け移築したものといいます。
昭和15年神饌幣帛料供進神社に指定。
『鎌倉市史』には、旧社殿は関東大震災で大破し、昭和8年改築とあります。
3社合祀の沿革で御祭神が気になるところですが、神奈川県神社庁資料には大己貴命(おおなむちのみこと)と記されています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
夷堂橋
夷堂橋は、小町と大町との境にあり。座禅川の下流なり。昔は此邊に夷三郎社ありしとなり。今はなし。
寶戒寺(山王権現社)
門を入て右にあり。
■ 神奈川県神社庁Web資料
蛭子神社
新編相模風土記稿に「夷堂橋は 此辺に夷三郎社ありしとなり」とある如く、産土神であったが、其所に本覚寺が創建され、地主神として山門の鎮守として奉斎されていたが、神仏分離令により寺内より離れ、小町村の鎮守として明治6年村社に列格された、付近の山王権現、七面大明神などを合祀に明治7年8月、蛭子神社と称した。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
蛭子神社
ヒルコと読む。祭神、大己貴命。例祭九月十五日。元指定村社。境内地八二.六二坪。拝殿・本殿・社務所あり。本殿は明治七年八月、鶴岡八幡宮の末社今宮の社殿を譲りうけて建立したものである。
小町の鎮守。この所にはもと小町下町の鎮守七面大明神が祀られていたが、神仏分離により本覚寺の鎮守であった夷三郎社をここに移し、かつ上町下町が一村に合され一村に鎮守は一社しかおかぬという達しによって、小町上町の宝戒寺鎮守山王大権現も合祀したという。
夷三郎社は『風土記稿』本覚寺境内図に見えている。いま本覚寺山門前の橋を夷堂橋というのはこの社によってつけられた名といわれている。
宝戒寺の山王も『風土記稿』同寺の項に見えている。現在の社殿は大正十二年関東大震災で大破したが、昭和八年九月改築したもの。
宝戒寺(山王権現の項)
寛永十二年、弁盛が宝戒寺造営のことについて目安を江戸幕府に上った。それによると、境内には本堂・僧堂・鎮守(山王権現)があり、山王権現は応永二年二月に宝戒寺住持興顗が山王七社と大行事早尾の御正躰一面を造立している。
御神体はもとからあったというから、山王社は恐らく草創と共に勧請されていたのであろ
う。
■ 境内掲示(鎌倉市)(「猫のあしあと」様より/抜粋)
鎮守蛭子神社は出雲大社に鎮ります大国主神を御祭神として(里俗夷尊神)と称され、往古永享年間(凡五百余年前)日蓮宗本覚寺前夷堂端の傍に夷堂あり夷三郎社とも称され、同寺の守護神として、又付近住民の氏神様として崇敬されたが、明治維新に神仏分離によりこの地に鎮座し、同時に宝戒寺門前地区の氏神として、同寺境内に祀られし北条一門の守護神山王大権現をも之に合祀し、蛭子神社と称するに至った。
爾来百余年えびす様の愛称で福の神・むすびの神として信仰され遠近より善男善女の参詣多く神賑を極め今日に至った。
■ 鎌倉公式観光ガイド(鎌倉市観光協会)
鎌倉十橋(かまくらじっきょう)/夷堂橋
夷堂橋は、本覚寺門前を流れる滑川に架かる橋で、その名は本覚寺の仁王門前あたりにあったとされる夷堂に由来します。夷堂は源頼朝が御所の裏鬼門に夷神をまつった夷三郎社が始まりで、滑川もこのあたりでは夷堂川とも呼ばれていました。現在夷堂は本覚寺の境内にあります。
夷堂橋(えびすどうばし)
設置場所:小町1-12-12
本覚寺前。鎌倉十橋の一つ。かって、この橋のたもとに源頼朝が幕府の鬼門除けのために創建した「夷三郎社」(夷堂)があったことからこの名前になったと言われています。
本覚寺
小町大路が滑川を渡るところに、源頼朝が幕府の守り神として創建した夷堂がありました。
今も夷堂橋があります。
日蓮が滞在していたお堂で、その後ここから身延山へ旅立ちました。
夷堂は鎌倉幕府滅亡のときに焼け、その跡につくられたのが本覚寺です。
1436(永享8)年、もとこの地にあった天台宗夷堂を日出上人が日蓮宗に改めたのがはじまりと伝えます。
■ 本覺寺公式Web(日蓮宗)
本覺寺の創立は永享8年(1436)ですが、夷堂の歴史はさらに古く、鎌倉時代の初期頃と伝わります。そしてこの夷堂は日蓮聖人とも縁が深く、流罪の地・佐渡から鎌倉に戻られた日蓮聖人が、40数日滞在されたといわれています。その間に、日蓮聖人は鎌倉幕府へ3度目の諫暁をされ、受け入れられなかったために身延への隠棲を決められるなど、後の布教のあり方などを大きく変えられました。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
本覚寺
寺ではこの地は『吾妻鏡』にみえる夷堂の地であるという。そして日蓮は佐渡から帰ってここに留錫し、この地から身延に移った。夷堂はもと天台宗の寺であったといい、その本尊と伝える釈迦・文殊・普賢の像がある。日出が改宗して創建した。
『風土記稿』所蔵の絵図には、夷三郎社・番神堂・祖師分骨堂などもみえる。
-------------------------
鎌倉駅にもほど近い小町大路に面して御鎮座、「日蓮上人辻説法跡」にも至近です。
小町大路に面する社頭・参道の間口は広くなく、あまり目立たないので観光客の参拝はさほど多くはないのでは。
御朱印が授与されていることも、あまり知られていないかと思います。


【写真 上(左)】 社頭
【写真 下(右)】 社号標
社頭に社号標と亀腹を置く明神鳥居で、社号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 鳥居扁額
【写真 下(右)】 参道
しかしながら小町の鎮守であり、鎌倉有数の名刹、本覚寺、宝戒寺と古いゆかりをもつこともあってか、参道を進むにしたがい神さびた空気感に包まれます。
桟瓦葺で木鼻獅子や蟇股を備えた立派な手水舎。
手水鉢には「魚がし」の刻字。


【写真 上(左)】 手水舎
【写真 下(右)】 斜めからの拝殿
拝殿は南面し、向かってすぐ右手(東側)は滑川です。


【写真 上(左)】 拝殿
【写真 下(右)】 拝殿扁額
拝殿は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、向拝上に唐破風を置いています。
水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に精緻な彫刻を置いています。
唐破風の鬼板や兎の毛通しも見事な出来映えで見応えがあります。
向拝正面桟唐戸の上部に、端正な字体の社号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 天水鉢
向拝桟唐戸と殿前の天水鉢とに同じ紋を置いています。
梶の葉紋系統にも思えますが、諏訪系の梶の葉紋とは趣を異にしていて、他の神紋を当たってみましたが該当する紋がみつからず、よくわかりません。
御朱印は大町の八雲神社にて拝受しました。
〔 蛭子神社の御朱印 〕
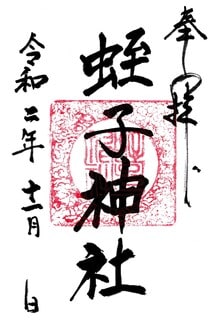
34.長慶山 正覺院 大巧寺(だいぎょうじ)
公式Web
鎌倉市小町2-17-20
単立(日蓮宗系)
御本尊:産女霊神(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:-
大巧寺は小町にある日蓮宗系単立寺院で、「おんめさま」の愛称で親しまれています。
当初は十二所の梶原屋敷内にあったといい、長慶山正覺院大行寺と号す真言宗寺院でした。
大行寺は頼朝公の祈願所で、この寺で軍評定した戦に勝利したため大巧寺と改めたといいます。
後に小町の現在地に移転。
日蓮聖人が妙本寺御在時の折、住僧が聖人に帰依して日蓮宗に改宗。
開山は九老僧の日澄上人とも日證上人とも伝わります。
「(朗門の)九老僧(朗門九鳳)」とは、日蓮六老僧の一人・筑後房日朗上人の9人の高弟を指します。
日澄上人 (大乗坊、1239-1326年?)は、比企谷門流の僧で九老僧(朗門九鳳)のひとりです。
『新編相模國風土記稿』には、小田原の妙珍山圓成院蓮昌寺の項で当山開山が九老ノ一、形善院日澄上人(文保元年(1317年)卒)であること。開基は小田原の濱名豊後守時成(永仁六年(1298年)卒)であること。時成は日蓮上人の投宿に随喜して出家し、妙音院日行を号したこと。時成の子は祖母妙珍尼に養われ、七歳で出家し日澄と号したこと。北條氏政の家臣・濱名時成は鎌倉小町大巧寺の檀那で、天正三年(1575年)大巧寺に寺領を寄附したこと。法名を妙法といい大巧寺に墓があり、子の蓮真と母妙節等の碑があることなどが記されています。
神奈川県平塚市の松雲山 要法寺の公式Webには、歴代上人として「二祖 九老僧 形善院日澄上人」「喜暦元(丙寅)年(1326年)八月1日化 池上大坊開山 本要阿闍梨小田原浜名豊後守時成長男」とあります。
また、池上大坊 本行寺の公式Webにも、「3祖大乗阿闍梨 形善院 日澄(嘉歴1(1326)没)」と明記されています。
上記から、大巧寺は小田原で日蓮上人に宿を提供した濱名豊後守時成(永仁六年(1298年)卒)の子で、九老僧のひとり形善院日澄上人(嘉歴元年(1326年)寂)の開山ともみられます。
しかし、天正三年(1575年)大巧寺に寺領を寄附した檀那・濱名時成は北條氏政(1538-1590年)の家臣で、鎌倉時代と戦国時代にそれぞれ2人の濱名時成が大巧寺とゆかりをもったことになりますが、詳細は不明です。
なお、濱名氏は源三位頼政の子孫といわれ、「鵺退治」で有名な頼政が恩賞に賜った遠江国堀之内郷を領したことから「鵺代」とも称しました。
濱名詮政は足利将軍義満公の信任厚かった記録があり、著名な歌人を輩出したことでも知られていますが、濱名氏の本拠は遠江で戦国期は今川氏との関係が深く、小田原や鎌倉に拠点をもった濱名時成がこの系統かどうかは不明です。
大巧寺は妙本寺の院家寺院でしたが、現在は単立寺院となっています。
大巧寺は安産祈願で有名で、「安産腹帯守」を求めて多くの参詣者があります。
安産祈願は『産女霊神縁起』にもとづくものです。
詳細は公式Web(PDF)で紹介されていますが、概要は以下のとおりです。
当山第五世日棟上人は毎夜妙本寺の祖師堂に詣でていましたが、天文元年(1532年)4月のある夜、夷堂橋の脇で産女の霊と遭遇しました。
やつれた様子の産女の霊は、日棟上人に自分は大倉に住む秋山勘解由の妻で難産によりこの世を去ったが、死出の旅路に迷って成仏できない。
どうぞよしなに回向をいただき成仏に導いていただきたいと訴えました。
哀れに思った日棟上人は法華経を読経して回向すると、女はいつのまにか姿を消していました。
数日後、日棟上人の前にみちがえったように美しい件の産女が現れ、上人の回向により成仏できたことを謝し、布に包んだ金銭を奉じたうえで、夫の秋山勘解由にこの経緯を伝え、宝塔を建立し供養して欲しいと訴えました。
そして、宝塔を供養してくれればその恩返しとして、今後、この塔に妊婦が参詣すれば安産となるよう尽力することを伝えました。
上人はこの願いに報いることを約すと、すぐに大倉の秋山勘解由を訪れました。
勘解由はこの話におどろきましたが、妻が日頃からこつこつとお金を蓄えていたこと、上人に奉じた金銭を包んでいた布は、妻が残した小袖の片袖であったことがわかりました。
勘解由は妻の回向を上人に深く謝し、自らも上人と師壇の契りを結んで宝塔建立への協力を申し出ました。
上人は「産女霊神」と号して産女の霊を祀り、宝塔を建立して手厚く供養しました。
この縁起を聞いて妊婦が参詣すると、みな安産となったので、当山は安産祈願で有名となったといいます。
この縁起を読んだとき、疑問に感じたことがあります。
・秋山勘解由について
鎌倉に秋山姓は少ないですが、あえて「大倉に住む秋山勘解由」と明記していること。
・上人への宝塔建立のお布施
諸史料は秋山勘解由の財産ではなく、産女の私財と強調していること。
・天文元年(1532年)という年号
Web検索していくと、「おんめさま 産女(うぶめ)伝説 (私説)」という記事がみつかりました。
秋山姓は甲斐発祥の甲斐源氏で、のちに武田二十四将の秋山伯耆守虎繁(信友)を生んでいます。
そして、天文三年(1534年)には武田信玄の正室・上杉の方(上杉朝興の息女)が難産で逝去しています。
上の記事では、私説として「おんめさま」と上杉の方との関係を示唆しています。
そこで筆者の想像も含めて整理してみます。
秋山氏は甲斐源氏・加賀美遠光の嫡男・光朝を祖とし、巨摩郡秋山を領しました。
秋山光朝は上京して平重盛に仕え、重盛の息女(六女・茂子)を室としたといいます。
平家滅亡後に甲斐に戻りますが、一時平家に使えていたことで頼朝公にうとまれ、居城雨鳴城を攻められ自害、あるいは鎌倉で暗殺されたともいいます。
しかし子孫は存続し、同族の甲斐武田氏に属しました。
武田家の重臣であった秋山伯耆守虎繁は大永七年(1527年)の生まれですから、上杉朝興の息女が武田晴信(信玄公)に嫁いだ天文二年(1533年)には一族の誰かが上杉の方の甲斐での後見役ないし世話役に任ぜられた可能性もあるのでは。
話が飛びますが戦国末期、穴山信君は甲斐源氏で武田家臣の秋山越前守虎康の息女を養女とし、この養女は天正十年(1582年)、信君が織田・徳川氏に臣従した際に徳川家康公の側室となりました。(下山殿/お都摩の方)
下山殿は天正十一年(1583年)、家康公の五男・万千代君(武田信吉公)を出産。
信吉公は下総小金城3万石~下総佐倉城10万石と移り、佐竹氏に替わって水戸25万石の太守となり、旧武田遺臣を付けられて武田氏を再興するやにみえましたが、慶長八年(1603年)21歳で死去し武田氏再興はなりませんでした。
下山殿は天正十九年(1591年)下総国小金にて早逝。平賀の日蓮宗の名刹・長谷山 本土寺に葬られました。
また、下山殿の実父(武田信吉公の実祖父)・秋山虎康は松戸市大橋の地に止住し、慶長元年(1596年)に了修山 本源寺を開山しているのでおそらく日蓮宗信徒です。
下山殿の「下山」は身延町下山から称したといいます。
『穴山氏とその支配構造』/町田是正氏(PDF)には「(秋山氏の祖)秋山太郎光朝の末の下山氏の住する処で(中略)『日蓮聖人遺文』にも下山氏の存在が記される所」とあり、下山殿の実家の秋山氏は、京よりはやくに讃岐に日蓮宗を伝えた(→ビジネス香川)ともいいますから、そんなこともあって日蓮宗寺院と秋山氏は結びつきやすかったのかもしれません。
さすがに話が飛びすぎました。
---------------------------------
信玄公の正室を三条の方(左大臣・三条公頼の次女)とする資料もありますが、正式には継室で、正室は上杉の方です。
上杉の方が嫁いだとき信玄公はわずか13歳で、上杉の方も同年代といいます。
天文三年(1534年)に出産の折、年若い上杉の方は難産であえなく逝去されました。
その頃、上杉の方の父・上杉朝興は扇谷上杉家の家督を嫡男・朝定に譲ったものの川越城に依り、相模国に盛んに兵を出しています。
年若くして難産で世を去った息女の供養は、父親としてごく自然な感情です。
しかし、当時の扇谷上杉家は古河公方、関東管領(山内上杉家)、武田家、後北条家、越後長尾家などとすこぶるデリケートな関係にあり、政略結婚で命を落とした娘の供養を、(娘に仕えていた)秋山勘解由の妻に託したという想像もあるいは許されるかもしれません。
また、秋山勘解由の在所は大倉(大蔵)で旧・大蔵幕府の跡、かつては幕政の中心地で官吏なども住んでいたと思われます。
上杉朝興は扇谷上杉家で関東管領ではないですが、関東管領(山内上杉家)に比肩する勢力をもち、その家人や与力衆はこの辺に住んでいたかもしれません。
勘解由の名も官吏・文官的な性格をイメージさせます。
このような背景から「おんめさま 産女(うぶめ)伝説 (私説)」は、「彼女(上杉の方)に仕えていた秋山勘解由の妻は、葬儀を終えて鎌倉の大倉に帰って来た。彼女の死後1年を過ぎて、自宅近くの寺に彼女を弔った。傷心の上杉朝興(46歳)は、彼女を通じて寺に寄進をし、娘の菩提を弔う秋山勘解由の心遣いを喜んだ。」という私説を展開されているのでは。
なお、大巧寺と上杉の方・上杉朝興の関係を示唆する史料は見当たらないので、上の内容はあくまでも想像で、お寺の紹介としてはいささか飛躍が過ぎたかもしれません。
いずれにしても、大巧寺は寺院が集まる鎌倉市内でも「安産祈願」という格別のご利益をもって広く信仰を集めていることは間違いありません。
寺宝で、産女霊神神骨を収めるという宝塔(水晶五輪塔)は、旧本山の妙本寺に預けられていましたが、平成23年に返却されて以降、当山にて格護されています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
大巧寺
大巧寺は、小町の西頰にあり。相伝、昔は長慶山正覺院大行寺と号し、真言宗にて、梶原屋敷の内にあり。後に大巧寺と改め、此地に移すとなり。梶原屋敷の條下に詳なり。昔し日蓮、妙本寺在世の時、此寺法華宗となり、九老僧日澄上人を開山とし、妙本寺の院家になれり。(略)
産女寶塔
堂の内に、一間四面の二重の塔あり。是を産女寶塔と云事は、相伝ふ、当寺第五世日棟と云僧、道念至誠にして、毎夜妙本寺の祖師堂に詣す。或夜、夷堂橋の脇より、産女の幽魂出て、日棟に逢、廻向に預て苦患を免れ度由を云。日棟これが為に廻向す。産女、䞋金一包を捧て謝す。日棟これを受て其為に造立すと云ふ。寺の前に産女幽魂の出たる池、橋柱の跡と云て今尚存す。夷堂橋の小北なり。
寺宝
曼荼羅 三幅 共に日蓮の筆。
無邊行菩薩名号 日蓮筆。
日蓮消息 壱幅
曼荼羅 壱幅 日朗筆。
舎利塔 壱基 五重の玉塔なり。
濱名石塔 北條氏政の家臣、濱名豊後守時成、法名妙法、子息蓮眞、母儀妙節、三人の石塔なり。
番神堂 濱名時成建立すと云。
梶原屋敷 附大巧寺𦾔跡
梶原屋敷は五大堂の北方山際にあり。梶原平三景時が𦾔跡なり。『東鑑』に、景時は正治二年(1200年)十二月十八日に、鎌倉を追出され、相模国一宮へ下る。彼家屋を破却して、永福寺の僧坊に寄附せらるとあり。頼家の時也。今此所に、大なる佛像の首ばかり、草庵に安置す。按ずるに『東鑑脱漏』に、安貞元年(1227年)四月二日、大慈寺の郭内に於て、二位家平政子第三年忌の為に。武州泰時、丈六堂を建らるとあり。此所大慈寺へ近ければ、疑らくは其丈六佛の首ならんか。又里老云、昔大行寺と云真言寺此所にあり。頼朝の祈願所にて、或は此寺にて、軍の評議して勝利を得られたり。故に大巧寺と改む。後に小町へ移し、日蓮宗となる。今の小町の長慶山大巧寺なりと、しかれども、『東鑑』等の記録に不見。按ずるに、五大堂を大行寺と号すれば、昔の大行寺の跡は、五大堂を云ならんか。不分明也。
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
大巧寺
長慶山正覺院ト号ス。法華宗 古大行寺ト号シ。真言宗ニテ。今唱フル。梶原屋敷ノ内ニアリ。頼朝ノ祈願所タリ。或時此寺ニテ。軍評定妙本寺大町村ニ在シ時。当寺住僧帰依シテ改宗シ。日證ヲ開山トシ。妙本寺ノ院家ニ属セリ。(略)
天正三年(1575年)二月。濱名豊後守時成。鎌倉能成分。六貫文ノ地ヲ寄附ス。(略)
本尊ハ三寶諸尊ヲ安ス。(以下略)
■ 『新編相模國風土記稿12』(国立公文書館デジタルアーカイブ)
蓮昌寺(小田原筋違橋町)
日蓮宗。鎌倉比企谷妙本寺末。妙珍山圓成院ト号ス。開山日澄。形善院ト號ス。九老ノ一、文保元年八月十日卒。傳云。文永十一年(1274年)五月。日蓮身延ヘ入山ノ時。憩ヒシ旧蹟ニテ。後ニ一寺トナル。開基濱名豊後守時成。寺傳云。宗祖身延入山ノ時。当所豊後守時成ノ館ニ投宿セリ。其時時成随喜シテ出家シ。妙音院日行ト号ス。永仁六年(1298年)二月五日。尾州熱田ニテ卒ス。一子アリ。祖母妙珍尼ニ養レ七歳にて出家ス。日澄ト号ス。即当寺開山ナリ。日澄其祖父蓮昌。祖母妙珍菩提ノ為。当寺ヲ開キ。即祖父母ノ法号ニヨリテ。寺山号ニ名けケシト云。今按スルニ豊後守時成ハ。北條氏政ニ仕ヘシ人ニテ。鎌倉小町大巧寺ノ檀那ナリ。天正三年(1575年)二月。大巧寺ニ時成寺領を寄附セシ券状。今ニ彼寺ニ傳フ。又同寺ニ墳アリ。法名妙法ト云。其子蓮真母妙節等ノ碑モアリ。然ルヲ時成日蓮ノ弟子トナリ。日澄ヲ其子トナスノ類。(以下略)
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
大巧寺
長慶山正覺院大巧寺と号する。日蓮宗系 単立宗教法人。もと妙本寺の院家。
開山、日澄。本尊、産女霊神。本堂・庫裏・山門・門あり。
産女宝塔は妙本寺に預けてある。
寺伝によると、大巧寺はもと大行寺と号した。真言宗の寺で十二所にあり、頼朝が軍の評議をしたところであるという。また日蓮が妙本寺にいたとき、時の住持が帰依して文永十一年(1274年)に改宗したという。(略)
産女様
当寺は俗におうめさまといい、安産のお守りを出す。これは五世日棟が産女の幽魂を鎮めたところから起こったといわれている。
■ 山内掲示(鎌倉市)
宗派 日蓮宗系単立寺院
山号寺号 長慶山大巧寺
開山 日澄上人
初め「大行寺」という名でしたが、源頼朝がこの寺で行った軍評定(作戦会議)で大勝したので、「大巧寺」に改めるようになったと伝えられています。
室町時代の終わり頃、この寺の住職の日棟上人が、難産で死んだ秋山勘解由の妻を供養して成仏させました。その後、お産で苦しむ女性を守護するために、「産女霊神(うぶすめれいじん)」を本尊としてお祀りしました。
今も安産祈願の寺として、「おんめさま」の愛称で呼ばれ、多くの方が参詣されています。
-------------------------
若宮大路と小町大路双方に接し、鎌倉駅からもっとも近い寺社のひとつです。
たいていの鎌倉ガイドに載っているので、観光客の参詣も多いとみられます。


【写真 上(左)】 若宮大路口
【写真 下(右)】 寺号標
若宮大路に面して整った石積みの参道とその奥に山門。
参道入口の「安産子育 産女霊神 長慶山大巧寺」の標石、そして参道の正中に据えられた石が目立ちます。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 参道
山門は脇塀付切妻屋根銅板葺のおそらく四脚門で、渋い朱塗りが趣を添えています。
石畳の参道は、右手のビルの存在感はあるものの緑豊かで四季折々の花が咲くようです。


【写真 上(左)】 小町大路口
【写真 下(右)】 小町大路口のお題目塔
小町大路側からも参道が伸び、入口には寺号を配したお題目塔とその奥には門柱を置いています。
こちらからは本堂が正面で、本来の参道はこちら側かもしれません。
こちらの参道も緑豊かで、雑踏の鎌倉駅至近とは思えない落ち着いた空間です。


【写真 上(左)】 小町大路側の門柱
【写真 下(右)】 手水舎
山内に産女霊神、福子霊神の石の墓碑がありますが、写真は撮っておりません。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 向拝上部
本堂は入母屋造銅板棒葺流れ向拝で、向拝上に整った唐破風を置いています。
水引虹梁両端に獅子・獏(象かも)の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に二本の大瓶束と、その間に風格ある龍の彫刻を置いています。
彫刻の上段には笈形(おいがた)付大瓶束(たいへいづか)で、兎の毛通し&鬼板も配して見応えがあります。
向拝は桟の上に白壁(?)を置いた個性的な扉で、見上げの本蟇股とその上の三連の斗栱も存在感があります。


【写真 上(左)】 向拝中備
【写真 下(右)】 授与所
御首題・御朱印は本堂よこの授与所で拝受しましたが。Web情報によるとタイミングにより授与を休止されることもあるようです。
こちらの授与所では安産腹帯守が授与されています。
戌の日および大安の休日にはたいへん混雑するようです。
〔 大巧寺の御首題・御朱印 〕
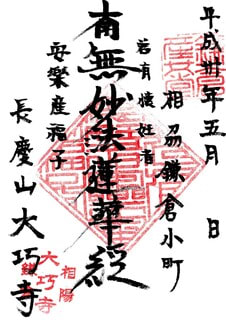

【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 御朱印
35.妙厳山 本覺寺(ほんがくじ)
日蓮宗公式Web
鎌倉市観光協会Web
鎌倉市小町1-12-12
日蓮宗
御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)
札所:鎌倉十三仏霊場第3番、鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)
司元別当:蛭子神社(鎌倉市小町)
本覺寺は小町にある日蓮宗の本山(由緒寺院)です。
身延山久遠寺の日蓮聖人の遺骨を分骨したため「東身延」とも呼ばれます。
鎌倉時代の初期、本覺寺の山門前の滑川にかかる端のたもとには「夷堂」と呼ばれる堂宇がありました。
鎌倉幕府の裏鬼門にあたり、源頼朝公が幕府守護のために夷堂を創建したといいます。
もとは天台宗系でしたが、文永十一年(1274年)に佐渡配流から戻られた日蓮聖人が約40日間にわたって夷堂に滞在され、鎌倉幕府に対し三度目の諫暁をされたものの、受け入れられなかったためついに身延への隠棲を決められたと伝わります。
(この「夷堂」の詳細については、33.蛭子神社を参照願います。)
夷堂は、鎌倉幕府滅亡(正慶二年(1333年))の際に焼失したともいいますが、永享八年(1436年)この地にあった天台宗夷堂を、一乗房日出上人が日蓮宗に改め開創したのが本覺寺と伝わります。
鎌倉公方・足利持氏開基説もみられます。
永享八年(1436年)、日蓮宗の布教伝道で名高い一乗房日出上人が常在山本覺寺(静岡県三島市)から鎌倉へ入られ、天台宗宝戒寺の僧・心海和尚と問答を繰り広げ(永享問答)、これをきっかけに騒動が起こったといいます。(永享法難)
Wikipediaには、「永享法難」をめぐる一乗房日出上人と本覺寺創建の由来が記されています。抜粋引用します。
---------(抜粋引用はじめ)
永享八年(1436年)、気鋭の布教伝道で名高い一乗房日出が常在山本覺寺(静岡県三島市)から鎌倉へ転出するも、足利持氏は弾圧処分を試みた。これに反発する信徒衆が荒居閻魔堂(現・新居山圓應寺)に集結し一触即発の状態になった。持氏はこの騒動が“鎌倉府討伐の口実”となる事を憂慮し処分を撤回。更に日出に対して日蓮の国家諌暁ゆかりの夷堂とその社領12000坪を寄進して法華寺院の建立を認めた。これが本覺寺創建の由来と伝えられている。
---------(抜粋引用おわり)
文安三年(1446年)に日出上人の弟子・行学院日朝上人が第2世として在寺され、15年ののちに身延山久遠寺第11世として入られ、身延山の再興を図られたといいます。
日朝上人は身延山への参詣が難しい老人や女性のために、身延山から日蓮聖人の遺骨を分骨して本覺寺に納めたため、以降当山は「東身延」とも称されました。
また、日朝上人は眼病救護の誓願を立てられたことから、当山は「日朝さま」とも呼ばれ鎌倉の庶民に親しまれました。
日蓮聖人の分骨の権威と、日朝上人の名声により、当山は鎌倉における日蓮宗の名刹の地位を確立し、後北条氏、豊臣氏、徳川氏から代々寺領を安堵され、塔頭末寺併せて10箇寺をもつ中本寺の格式を保ちました。
『新編鎌倉志』には「東三十三箇國、別して関八州の僧録」とあります。
僧録とは、僧侶の登録・住持の任免などの人事を統括した役職をいい、当山が大きな権威をもっていたことがうかがえます。
『鎌倉市史 社寺編』には「嘉永三年(1850年)の境内及び寺領の絵図があり、いまの市役所、市民座、駅前等を含む広い境内であったことがわかる。」とあるので、幕末の当山はすこぶる広大な寺領を有していたことがわかります。
開山七百年の節目にあたる昭和49年には日蓮宗本山(由緒寺院)に昇格し、いまも隆盛を保っています。
日蓮聖人ゆかりの夷堂は、山内鎮守の夷三郎社として祀られたといいますが、明治の神仏分離の際に蛭子神社に合祀されたといいます。
現在の八角形の夷堂は、昭和56年に建立されたものです。
名刹だけに文化財も豊富で、本堂安置の木造釈迦如来 、文殊菩薩、普賢菩薩の三尊像は
南北朝時代の作で宋風のすぐれた作風を伝えるとされ、鎌倉市指定の文化財です。
墓域には、鎌倉の住人で名刀工の正宗の墓があります。
正月三が日の「初えびす」、正月10日の「本えびす」には商売繁盛を願う参詣者たちで賑わい、10月の人形供養も古都・鎌倉の風物詩とされます。
鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)、鎌倉十三仏霊場第3番(文殊菩薩)の札所で、巡拝客や観光客も多く訪れる鎌倉の名所です。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)
本覺寺
妙厳山と号す。身延山の末寺なり。開山日出上人。永享年中(1429-1441年)に草創すと云伝。此寺は東國法華宗の小本寺也。当寺三世日燿へ、日朝より書を遺して曰、総じて東三十三箇國、別して関八州の僧録に任じ置事に候へば、萬端制法肝要に候と云云。
う々、とありし由鎌倉志に見えたり、今此文書傳はらず。日朝上人は、日出上人の弟子、当寺第二世なり。廿歳にして身延山に住す。身延山第十一祖なり。在住四十年。身延山の諸法式も此代に定む。此書も身延山より遺はすと云ふ。本尊は釋迦・文殊・普賢なり。(以下略)
■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)
本覺寺
妙厳山ト号ス。法華宗身延山久遠寺末。永享年中(1429-1441年)ノ草創ニシテ開山ヲ日出(武州ノ人ナリ。始ハ是性坊ト号シ。天台宗ナリシカ。身延山日延ニ帰依シテ改宗シ。一乗坊ト称ス。)ト云フ。
当寺ハ東國法華宗ノ小本寺ナリ。日朝(当寺二世。本寺十一世ナリ。)身延山ニ在シ時。当寺三世日燿ヘ贈リシ書ニ。総して東三十三箇國。別シテ関八州ノ僧録ニ。任シ置事ニ候ヘハ。萬端制法。肝要ニ候云々。トアリシ由。鎌倉志ニ見エタリ。今此文書伝ハラス。(略)
本尊三寶ヲ安ス。又釋迦文殊普賢ノ像アリ。元ノ本尊ト云。
寺寶
曼陀羅一幅。日蓮筆。
日蓮消息十通。
記録一巻。日出天台宗ト問答ノ時。執権某是非ヲ糾シ。又修法ノ怪異ニ驚キ。褒賞シテ。田園ヲ寄附スルノ由。日出ノ書ナリ。巻尾ニ永享八年(1436年)五月晦日トアリ。
古文書十通。其文前ニ註記ス。
■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)
本覚寺
妙厳山と号する。日蓮宗。もと身延山久遠寺末中本寺。開山、一乗日出。永享八年(1436年)の創建と伝える。
本尊、三宝祖師。境内地二六一四坪。本堂・祖師分骨堂・客殿・庫裏・鐘楼・二王門・横門棟あり。
寺ではこの地は『吾妻鏡』にみえる夷堂の地であるという。そして日蓮は佐渡から帰ってここに留錫し、この地から身延に移った。夷堂はもと天台宗の寺であったといい、その本尊と伝える釈迦・文殊・普賢の像がある。日出が改宗して創建した。
二世日朝の書状に本覚寺大浄坊を関八州の僧録となすことがみえ東身延と称している。
俗に日朝様とよぶ。串川光明寺にある善宝寺寺池の図にみえる法華堂はここのことであろう。(略)
嘉永三年(1850年)の境内及び寺領の絵図があり、いまの市役所、市民座、駅前等を含む広い境内であったことがわかる。
『風土記稿』所蔵の絵図には、夷三郎社・番神堂・祖師分骨堂などもみえる。
なお境内の墓地には正宗の墓と伝えるものがある。
■ 山内掲示(鎌倉市)
宗派 日蓮宗
山号寺号 妙厳山本覚寺
建立 永享8年(1436)
開山 日出
本覚寺のあるこの場所は幕府の裏鬼門にあたり、源頼朝が鎮守として夷堂を建てた所といわれています。
この夷堂を、日蓮が佐渡配流を許されて鎌倉に戻り、布教を再開した際に住まいにしたと伝えられます。その後、鎌倉公方・足利持氏がこの地に寺を建て、日出に寄進したのが本覚寺であるといい、二代目住職の日朝が、身延山から日蓮の骨を分けたので「東身延」と呼ばれています。
日朝は「眼を治す仏」といわれ、本覚寺は眼病に効く寺「日朝さま」の愛称で知られています。
十月は「人形供養」、正月は福娘がお神酒を振舞う「初えびす」でにぎわいます。
鎌倉の住人、名刀工・正宗の墓が境内にあります。
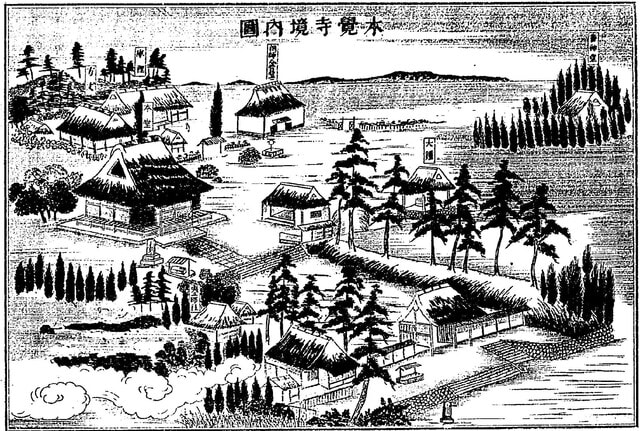
原典:間宮士信 等編『新編相模国風土記稿』第4輯 鎌倉郡,鳥跡蟹行社,明17-21.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
小町大路に接し、鎌倉駅からもっとも近い寺社のひとつです。
鎌倉市内の名所の位置づけで、観光客の参詣も多いとみられます。
「日蓮上人辻説法跡」にもほどちかいところです。


【写真 上(左)】 日蓮上人辻説法跡
【写真 下(右)】 夷堂橋から山門


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 斜めからの山門
小町大路が滑川を渡る夷堂橋のたもとに山門(二王門)があります。
桟瓦葺の楼門。両脇間に二王尊を安する三間一戸の八脚門で、大寺の風格があります。
手前には台座に「東身延」とある大きなお題目塔。


【写真 上(左)】 山門前のお題目塔
【写真 下(右)】 夷堂
山門をくぐって右側に鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)である夷堂。
銅板葺の屋根上に相輪を置き、急傾斜でむくり気味の屋根の角部が向拝になっている変わった意匠で、宝形造とも思いますがよくわかりません。
向拝には「夷尊堂」の扁額を掲げています。
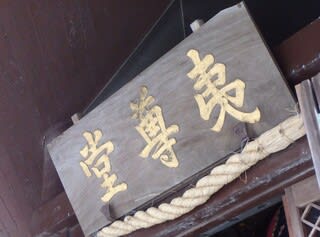

【写真 上(左)】 夷堂の扁額
【写真 下(右)】 授与所と参道


【写真 上(左)】 客殿?
【写真 下(右)】 手水舎
参道を進むと左手が授与所と、その奥は庫裏と客殿でしょうか。
さらに行くと右手に虹梁、木鼻、斗栱、中備を備えた立派な手水舎。
手水鉢では剣に二軆の龍が巻き付いた、倶利迦羅剣のような吐水口から水が注がれています。
その奥手に均整のとれた鐘楼。


【写真 上(左)】 鐘楼
【写真 下(右)】 参道


【写真 上(左)】 本堂前
【写真 下(右)】 本堂
正面本堂の堂前に香炉、金灯籠、石灯籠と天水鉢。
本堂は基壇上に入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、向拝上に軒唐破風をおこしています。


【写真 上(左)】 向拝-1
【写真 下(右)】 向拝-2
向拝は三間で水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に三連の蟇股を置いています。
各所に菱格子、格子を配して引き締まったイメージの意匠です。
向拝見上げに各号扁額を掲げていますが、達筆すぎて読解できず。(常拝閣か/?)


【写真 上(左)】 本堂扁額
【写真 下(右)】 しあわせ地蔵尊


【写真 上(左)】 日蓮上人分骨堂
【写真 下(右)】 斜めからの分骨堂
本堂向かって右手奥にまわると、濡佛のしあわせ地蔵尊。
その奥には堂前に宝塔、香炉、石灯籠を配した日蓮上人分骨堂。
当山が「東身延」と呼ばれる由縁の重要な堂宇です。
桟瓦葺、二層の楼閣で、二層屋根の基盤上に宝珠。
堂回りに瑞垣をまわし、堂前は日蓮宗の宗紋「井桁橘」が刻まれた石扉で閉ざされています。
向拝の桟唐戸と両脇の花頭窓が、シンプルながら風格を感じさせます。
大寺ながら堂宇や山内佛がすくなく、明るくすっきりとして公園のような印象です。


【写真 上(左)】 路地からの脇門
【写真 下(右)】 脇門
若宮大路から小町大路に抜ける路地側にも山門があります。
脇塀付き切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、脇門ながら風格があります。
門前にお題目塔と「一天四海皆妙法」の石碑。


【写真 上(左)】 脇門前のお題目
【写真 下(右)】 脇門前の石碑
御首題・御朱印は参道左手の授与所で拝受しました。
札所でもあるので、複数の御朱印を授与されています。
〔 本覺寺の御首題・御朱印 〕
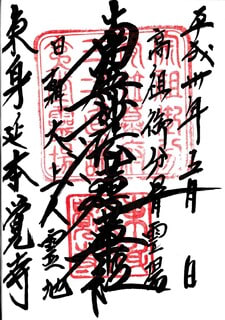

【写真 上(左)】 御首題
【写真 下(右)】 日朝大上人の御朱印

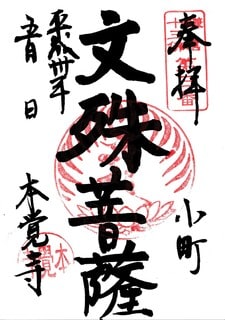
【写真 上(左)】 夷神(鎌倉・江ノ島七福神)の御朱印
【写真 下(右)】 文殊菩薩(鎌倉十三仏霊場)の御朱印
→ ■ 鎌倉市の御朱印-11 (B.名越口-5)へつづく。
【 BGM 】
■ 私にはできない - Eiーvy
■ Re:Call - 霜月はるか
■ あなたの夜が明けるまで - Covered by 春吹そらの
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-8
■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-7からのつづきです。
※札所および記事リストは→ こちら。
『荒川辺八十八ヵ所と隅田川二十一ヵ所霊場案内』(新田昭江氏著/1991年)を『ガイド』と略記し、適宜引用させていただきます。
■ 第21番 清瀧山 観音院 蓮花寺
(れんげじ)
墨田区観光協会公式Web
墨田区東向島3-23-17
真言宗智山派
御本尊:弘法大師
札所本尊:
司元別当:(寺島村)総鎮守・白鬚神社(墨田区東向島)
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第72番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第84番、新葛西三十三観音霊場第19番、墨田区お寺めぐり第11番
第21番は墨田区東向島の蓮花寺。
東向島の旧町名「寺島」の地名のいわれとなったとされる中本寺格の真言密寺です。
墨田区観光協会公式Web、下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
蓮花寺はすこぶる複雑な縁起をもたれます。
一説には寛元四年(1246年)、鎌倉幕府第5代執権、最明寺入道北条時頼の開基で、時頼の兄の北条武蔵守経時追福のため鎌倉佐介谷(現・鎌倉市佐助)に創建された蓮華寺が創始といいます。
頼朝公の外伯父、深井法眼範智の孫・良弁法印審範を開祖として聖徳太子の御像を安置といい、後に京の禁裏から弘法大師空海御自筆の「女人済度厄除弘法大師」を招来し奉安したといいます。
経時の死後、子の頼助は諸般の事情から執権職を叔父の時頼に譲り、自らは剃髪入道して諸国を廻ったといいます。
廻国ののち寺島の地に一寺を建て、弘安三年(1280年)鎌倉の蓮華寺の名跡を遷し、「女人済度厄除弘法大師」を御本尊とし、堂宇を建てて聖徳太子の御像を納め、佐々目大僧正頼助と号して自ら開山となったといいます。
(『ガイド』によると蓮花寺の『日過去帳』には、「大僧正頼助永仁四年(1296年)二月八日蓮華寺開山」とある由。)
以上の縁起は、江戸期には人口に膾炙していたようですが、『新編武蔵風土記稿』『江戸名所図会』『葛西志』などは、こぞってこの縁起に疑義を呈しています。
その疑義とはおおよそ以下のとおりです。
*******
1.『鎌倉大日記』に、建長三年(1251年)経時のために佐介谷に蓮華寺を建立した住持は良忠(記主禅師)と記されていること。
2.『鎌倉志』に、佐介谷の蓮華寺は寛元元年(1243年)平(北条)経時の建立にて、時の導師は記主禅師(良忠)とあること。
3.上の二書ともに蓮華寺建立の導師は記主禅師(良忠)とあるからには、その宗門はもとより浄家(浄土宗)であることは明らかである。
4.『鎌倉志』には蓮華寺創立の後、経時の霊夢により光明寺と改めたとあり、光明寺でもこのように伝わる(ので蓮華寺が光明寺の前身であることは明らか)。
5.以上より、佐介谷の蓮華寺は光明寺となったことは明らかであり、あるいは寺島の地は頼助の領地だったため、(佐介谷の蓮華寺)遙拝のために同名の寺を起立したのではないか。
佐介谷の蓮華寺が(光明寺)に改号した(材木座に移転して佐介谷の蓮華寺がなくなった)ため、後の人々が(佐介谷の)蓮華寺が(寺島の)蓮華寺に移ったという説を打ちたてたのではないか。
*******
鎌倉材木座の光明寺といえば浄土宗の大本山であり、光明寺公式Webには「良忠上人は鎌倉幕府第四代の執権、北条経時公の帰依を受けてこの光明寺を開かれたといわれています。」と記されています。
その光明寺の前身が佐介谷の蓮華寺であることは諸史料に明らかで、記主禅師良忠上人ゆかりの佐介谷の蓮華寺が、江戸墨東・寺島の地に、しかも真言密寺として移転というのはどうみても不自然です。
また、諸史料からすると、京の禁裏から弘法大師空海御自筆の「女人済度厄除弘法大師」を招来し安置したのは佐介谷の蓮華寺とみられますが、禁裏に奉安の弘法大師御自筆の「女人済度厄除弘法大師」といえば真言宗の至宝であり、その至宝を浄土宗の蓮華寺に相伝するというのもいささか解せない流れです。
さらにWikipediaで頼助 (北条氏)を当たってみると、
---------------------------------
・頼助(1244-1296年)は真言僧で、父・北条経時の菩提所である鎌倉佐々目の遺身院を拠点とし、佐々目頼助とも呼ばれた。
・弘長二年(1262年)以前には出家している。
・三宝院・安祥寺・仁和寺各流を受法し、仁和寺流・法助の弟子となって文永六年(1269年)に頼守から頼助に改名した。
・修行を積んで鎌倉に戻り、弘安四年(1281年)の元寇の際には異国降伏祈祷を行い、弘安六年(1283年)には鶴岡八幡宮の10代別当となる。
・円教寺、遍照寺、左女牛若宮等の別当、東寺長者などを歴任し、正応五年(1292年)、大僧正・東大寺別当に就任。
---------------------------------
とあり、真言僧として錚錚たる地位を歴任しています。
なお、佐々目(谷)は佐助と長谷の間の谷で、『吾妻鏡』寛元四年(1246年)閏4月2日條には、北条経時が佐々目山麓に葬られたと記されています。
佐々目の遺身院および頼助については、以前こちらの記事(鎌倉市の御朱印-7の24.安養院)でもふれています。
『鎌倉下向僧の研究 - 願行房憲静の事跡 -』(高橋秀栄氏/PDF)には「勝賢開山の佐々目西方寺にはじまり、関東の三宝院流はここに発祥し、大門寺、遺身院その他の寺院群が佐々目の地にあった模様である。」とあります。
以上から考えると、頼助は真言密各派の教義を修めたばりばりの真言僧で、自身の領地(寺島)に鎌倉から寺院を遷すとすれば、拠点としていた佐々目の真言密寺・遺身院を遷すのではないかとも思えます。
鎌倉の拠点として遺身院を残しておきたいのであれば、寺島には分院を置いてもいいですし、佐々目にいくつかあった真言密寺を遷してもいい筈です。
少なくとも他宗派の重要寺院・蓮華寺を遷すという発想には至らないのでは。
このような疑義もあってか、当山の縁起については「はっきりしない」とか「諸説あり」と記される例が多くなっているのだと思います。
どうにもすっきりしないので、さらに『鎌倉市史 寺社編』を当たってみました。
同書P.429~に気になる記述があります。
「従来光明寺について多くのものは『鎌倉佐介浄刹光明寺開山御伝』により、然阿良忠か仁治元年(1241年)二月、鎌倉に入り、住吉谷悟真寺に住して浄土宗を弘めていた、時の執権経時は良忠を尊崇し、佐介谷に蓮華寺を建立して開山とし、ついで光明寺とその名を改め、前の名蓮華の二字を残して方丈を蓮華院となづけた。寛元元年(1243年)五月三日、吉日を卜して良忠を導師として供養した。といい、『風土記稿』所引の寺伝では、この時に、現在地材木座に移転したようにいっている。しかし、経時(1246年没)の法名は蓮花寺殿安楽大禅定門とあるから、光明寺と改名するのは、どうも後世のように思われる。『良暁述聞制文』には、「佐介谷悟真寺今号蓮華寺」とあり、正中二年(1325年)三月十五日にはまだ光明寺という名がでてこない。(中略)『開山御伝』に建長頃(1249-1256年)、北条時頼が寺領を加へ、外門の額字を、佐介浄刹としたという話も、佐介谷にあればこそのことではないかと思う。(中略)『資料編』三の四七六及び四七八はいづれも江戸時代に納められたもので、内容から考えてどうも密教系の寺のものでここのものではないらしい。光明寺の肩の文字を抹消していることも、疑問がのこるところである。(中略)現在のところ(材木座)に移転した期日及び名を光明寺と改めた時期はなお研究を要する問題である。」
『資料編』三の四七六及び四七八が手元にないのでなんともいえませんが、「密教系の寺」が寺島の蓮花寺だとすると、光明寺の縁起を辿るときに寺島蓮花寺関連の文書が入り、錯綜している様子がうかがえます。
こんなこともあって、寺島の蓮花寺の縁起は現代に至ってなお「諸説あり」とされるのかもしれません。
なお、上記の『鎌倉市史 寺社編』によると、正中二年(1325年)の時点ではまだ光明寺の名は出てこず(=蓮華寺が存在していた)、弘安三年(1280年)に頼助が鎌倉から蓮華寺を遷したという当山縁起(説)の内容と時系列的には符合しますが、そうなると弘安三年(1280年)以降は(寺島に移転したため)鎌倉に蓮華寺は存在しないことになり、光明寺まで系譜がつながらなくなってしまいます。
---------------------------------
以上のように縁起沿革こそ不明瞭さは残るものの、禁裏から相伝の弘法大師御自筆の「女人済度厄除弘法大師」を奉安は、江戸庶民にとって圧倒的なインパクトであり、当山は「厄除け寺島大師」と尊称され、川崎大師平間寺、西新井大師総持寺とともに「江戸三大師」に数えられて参詣者を集めました。
一説に鎌倉幕府第5代執権、北条時頼公の開基、大僧正・東大寺別当の(北条)頼助の開山ということもあり、自ずから寺格は高く京都智積院直末の中本寺格寺院でした。
墨東の弘法大師霊場・隅田川二十一ヶ所霊場の結願寺として、まことにふさわしい名刹といえましょう。
北条家滅亡の後も足利将軍、管領等の崇敬は篤かったものの、文明年間(1469-1487年)の下総千葉家内の騒乱によって当山は荒廃したといいます。
天文年間(1532-1555年)、この地が小田原北條家の領地となった頃、遠山丹波守が奉行として寺領等を寄附して寺勢を復しましたが、その後ふたたび戦乱で荒廃。
しかし家康公の治世に当山由緒の御尋ねあって、御朱印を賜い堂舎を造立、「江戸三大師」にも数えられて寺勢を保ちいまに至るといいます。
女人救済の霊場としては「江戸六阿弥陀」(→ 関連記事)が知られていますが、「女人済度厄除弘法大師」は江戸近辺ではあまり例がないとみられ、多くの女性の参詣を集めたことは想像に難くありません。
なお、当山は江戸期には東向島(寺島村)総鎮守・白鬚神社の別当でした。


【写真 上(左)】 白髭神社
【写真 下(右)】 白髭神社の御朱印
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻二』(国立国会図書館)
(寺島村)蓮華寺
新義真言宗山城國醍醐三寶院末 清瀧山観音院ト号セリ
本尊弘法大師自書ノ像ヲ安ス(中略)縁起云 当寺ハ最明寺平時頼ノ舎兄武蔵守経時朝臣ノ菩提寺ナリ
初ハ相州鎌倉郡佐介谷ニ創立アリテ 其経時寛元四年(1246年)逝去ノ後時頼一寺ヲ建立シ 蓮華寺殿前武州安楽大禅定門ト謚ス 時ノ開山ハ辨法印審範ナリ 審範ハ則頼朝卿ノ外伯父 深井法眼範智ノ孫ナリ 其後経時ノ子佐々目大僧正頼助此寺嶋ヲ知行アリシ時 鎌倉ノ蓮華寺ヲ此所ニ移シ 弘安三年(1280年)八月建立シテ頼助自カラ中興ノ開山トナレリ云々
按ニ此寺伝甚疑フヘシ イカニト云ニ 鎌倉大日記ニ建長三年(1251年)経時ガ為ニ佐介ニ於テ蓮華寺建立住持ハ良忠ト記シ 又鎌倉志ニ佐介谷ノ蓮華寺は寛元元年(1243年)五月三日平経時ノ建立ニテ 時ノ導師ハ記主禅師トアリ 此二書ニ載ル処年代等ハ異同アレト 導師ハ共ニ記主ナレハ宗門元ヨリ浄家ニシテ審範ニアラサルコト明ケシ シカノミナラス鎌倉志ニハ蓮華寺創立ノ後経時霊夢アリテ光時(明?)寺ト改ム由ヲ記シ今モ光明寺ニテモシカ伝フレハ 当寺の伝記正シトハオモハレス モシクハ当所頼助カ領知ナレハ 遙拝ノ為別ニ同名ノ寺ヲ起立アリシヲ タマタマ佐介谷ノ蓮華寺改号セル故 後人妄ニ彼寺ヲ引キ来リシナト云コセシニアラスヤ
鐘楼 宝暦八年ノ鐘ナリ
愛染堂 興教大師ノ書ケル像ヲ安ス
権現堂 清瀧権現ト号ス
■ 『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館)
清瀧山蓮華寺
寺嶋村にあり 寺記に云く昔此地ハ海原なり 後世ようやく干潟となりし頃当寺を創建ありし故に寺嶋の称ありといへり 小田原北条家の所領役帳に行方与●島葛西寺寺嶋の地を領すとあり
当寺ハ真言宗にして醍醐の三宝院末に属す 本尊阿弥陀如来如来の像ハ恵心僧都の作といふ
太子堂 本堂の右にあり本尊聖徳太子の像ハ十六歳の真影にして太子自彫造ありしと云
北条経時の念持佛にて往古ハ相州鎌倉佐々目にありしを 弘安三年(1280年)の秋北条頼助寺院●●●に本尊共に此地へ引移し同年八月二日入佛供養を営し故(中略)
寛文二年(1662年)の夏國中大に疫病流行し人民死する者少からしを 経時頗●是を嘆き本尊に告て諸人の病苦を消除せんとて懇に祈願すと 或夜経時に霊示ありて秘符を賜ふ 即此秘符によりて其頃病を退け命を全うする者●●(少な?)からすとなり
相伝ふ 寛元四年(1246年)三月北条経時病に臨む其時 舎弟時頼を側へ招き示して云く我疾難治なり 死後に至らハ一宇の梵刹を創建し年頃念ね処の聖徳太子の像を安置すへしといひ●て同四月朔日享年三十八歳にして逝去あり
依時頼遺命を奉じて鎌倉佐介谷に一宇を闢き蓮華寺と号く 経時の法号を蓮華寺殿前武州安楽大禅定門と号す 即辨法印審範を以て開山とす
寺記に審範は頼朝の伯父深井法眼範智の孫なりと云されと 鎌倉大日記にハ開山良忠とありて一なら●●次に詳ん
又其後経時の子頼助此寺嶋を領せし● 出離の志頗にして忽に剃髪し弘安三年(1280年)の秋鎌倉の蓮華寺●寺嶋に移し自開山たり
佐々目大僧正頼助と号せり按に先に審範を開山とすとあるハ鎌倉にありての寺をいふなるへし 此寺移るに至りてハ頼助開山たりしなるへし 諸家係累に経時の子に顕助といふ号を載て●傍に依て木像と注せり
疑ふらくハ佐々目といふ●●●を誤●るなるへしにて頼助ハ顕助のことをいふならん(以下不明)
北條家滅亡の後もなを尊氏将軍及ひ管領基氏等崇敬厚く(中略)文明(1469-1487年)の頃下総の千葉両家と別●て時 たがひに争戦止時なく兵火の災●にして当寺も大に荒廃せり 然に天文年間(1532-1555年)小田原北條家の領地となりし頃 遠山丹波守奉行として寺領等を寄附せし(以下略)
按に鎌倉光明寺の開山記主禅師伝に云く 寛元元年(1243年)五月三日前武州太守平経時鎌倉の佐介谷にをひて浄刹を建立し蓮華寺と号け良忠を導師として供養を●らる後に経時霊夢を感するところありて 光明寺とあらたむると云々
又鎌倉大日記に云く建長三年(1251年)経時の為に佐介にをひて蓮華寺建立住持良忠とあり されと寛元(1243-1247年)に建立せし蓮華寺ハ経時の生前なり 又建長(1249-1256年)に建立ありし蓮華寺ハ経時の没後にして其間七年を隔てり 依て考ふるに其号によるときハ一寺の如なれども自ら別なるへし 然る時ハ鎌倉光明寺の開山伝に載て寛元元年(1243年)経時生前に建立すとある●のハ 後に光明寺 とあらしめ鎌倉の内の材木座へうつしたる是なり 又鎌倉鎌倉大日記に●●●る経時卒去の後菩提の為に建立とある●ノハ即当寺の権よなるへし

■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
(寺島村)蓮華寺
新義真言宗、山城國醍醐三寶院末なり。清瀧山観音院と号す。
縁起云、最明寺平時頼の舎兄、武蔵守経時朝臣の菩提寺なり。
初めは相州鎌倉郡佐介谷に創立あり、かの経時は、寛元四年(1246年)逝去なり。
執権の職を、舎弟最明寺殿(時頼)にゆべり、その後一寺~建立し、法号を蓮華寺殿前武州安楽大禅定門と号す。
その時の開山は辨法印審範なり。審範は、則頼朝卿の外伯父、深井法眼範智の孫なり。
初は天台宗長瞬法眼の門弟なりしが、後に真言となり、道禅僧正に受法す。
又公縁僧正灌頂の弟子となり、弘長元年(1261年)入滅す。
其後経時の御ご子息、佐々目大僧正頼助、此寺嶋を知行ありしとき、鎌倉の蓮華寺を此所に移転し、弘安三年(1280年)八月当寺を建立して、則頼助開山となれり。
按に此縁起の説、未他の所見なし、鎌倉志に、佐介谷の蓮華寺は、寛元元年(1243年)五月三日平経時の建立にして、時の導師は記主禅師なりとあり、又鎌倉大日記に、建長三年(1251年)経時が為に、佐介谷に於て蓮華寺建立、住持は良忠(記主禅師の名なり、とあり(略)導師は共に記主禅師なるよしいへば、今ここに開山を審範なりといふ事最疑ふべし、又鎌倉蓮華寺創立の後、経時霊夢有て、光明寺と改むとあり、是によればかの佐介谷の蓮華寺は、全く今の光明寺の古号にして、当所のは自ら別寺なりしを、たまたま同名なるゆへ附会せしものか、ここに当所は頼助が、領知なりしといへば父の菩提の為に建立ありて蓮華寺と称せしも、又しるべからず とにかく鎌倉より移転せしと云はおぼつかなし。
その後此僧正鎌倉八幡宮の別当に補任なり、在鎌倉十四年京六條の若宮の別当も、兼帯なり、此僧正は、守海法印入室の弟子、三寶院良入前僧正灌頂安祥寺 奉遇仁和寺御室開田准后灌頂(中略)
文明(1469-1487年)の比に至りて、下総の千葉両家相分かれて、合戦やむ時なし、千葉自胤、同實胤は、葛西郡及び武州石濱まで出張して、総州勢とかけ合たれば、当所はたまたま合戦のただ中となり、兵火の為に焼るゝ事度々なり、よりて代々の寄附状、或は古佛に至るまで、みな何地へか分散して、僅にのこれるものは、本堂と本尊のなり、かゝりける程に、天文年中(1532-1555年当所の地頭、遠山丹波守某が推挙に依て、小田原北條家より虎印の願書と、寺領を附せられて、再建なり
北條家の運尽て、天正十八年(1590年)、終に落城に及びしかば、朱印はむなしく伝へたれども、領地はいづくへか奪はれしを悉くも、神君関東後打入の後、当寺の由緒を御尋有て、先規のごとく若干の寺地をゆるされ、御朱印をも賜ひしかば、再び堂舎を造立して、今に至ると云。
客殿 本尊阿彌陀如来を安置す 作しれず。
清瀧権現堂 祭神詳ならず。
鐘楼 鐘は宝暦八年の鋳造(以下略)
■ 『墨田区史 本編』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
蓮花寺(清滝山観音院)
山城三宝院末で真言宗に属し本尊の宗祖の像は弘法大師の自画像と伝えられ、「厄除女人済度弘法大師」の称がある。
伝えられる創建の由来によれば、同寺は初めは相模の国の鎌倉郡佐介谷にあり、最明寺入道北条時頼が寛元四年(1246年)に死去した兄の武蔵守経時の追福のために建立、辨法印審範を開山としたもので、経時の子佐々目大僧正頼助が葛西寺島の地を知行していた関係で鎌倉から寺島に移し、弘安三年(1280年)八月に則頼みずから中興助開山となったのである。
しかし蓮花寺移転のことについては「夢跡集」門柱「蓮花寺は佐介ヶ谷より武蔵国葛西の地へうつり、其寺院の跡に光明寺を建立せし事ならん。」と述べているものの、「新編武蔵風土記稿」の記すところによれば鎌倉の蓮花寺は浄土宗の寺院であり、経時追福のために良忠が建長三年(1251年)に創建したといい、あるいは経時自身によって寛元元年(1243年)五月三日に建立されたともいわれ、のちに霊夢によって寺号を光明寺と改称したのであると伝えられている。
これによれば蓮花寺は鎌倉の蓮華寺(のちに光明寺)とは別の同名の寺院であるが、寺号改称のことは光明寺の寺伝にも明らかに記されているとのことであるから、寺島の蓮花寺はおそらく「武蔵通志」が述べているように、経時の子で僧籍にはいった頼助によってその所領地の寺島に弘安三年(1280年)八月に建立されたものであろう。
蓮花寺創建によって土地の名称を寺島というようになったとの説がある。(以下略)
■ 『すみだの史跡文化財散歩 P.21』(墨田区資料/PDF)
蓮花寺(東向島3-23-17)
清滝山蓮花寺は、京都智積院末で真言宗智山派に属し、本尊は空海自筆の弘法大師画像と伝えられています。この寺の開山については諸説があります。
■ 『新編鎌倉志 鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
光明寺
光明寺は、本は佐介谷に在しを、後に此地に移す。当寺開山の伝に、寛元元年(1243年)五月三日、前武州太守平経時、佐介谷に於て浄刹を建立し、蓮華寺と号し、良忠を導師として、供養をのべらる。後に経時、霊夢有て光明寺と改む。方丈を蓮華院と名くとあり。
蓮華寺跡(佐介谷)(同上資料)
今俗に光明寺畠と云ふ。光明寺、本此地にあって、蓮華寺と号す。後に光明寺と改む。
『鎌倉大日記』に、建長三年(1251年)、経時が為に、佐介に於て蓮華寺建立、住持良忠とあり。良忠此谷に居住ありしゆへに、佐介の上人と云ふなり。光明寺の條下及ひ『記主上人傳』に詳也。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』隅田川向島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは東武スカイツリーライン「東向島」駅で徒歩約10分。
下町らしからぬ整備された街区にあり、門前、山内ともに広々として名刹の風格があります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 女人済度弘法大師碑
参道入口向かって右手に「女人済度 御自筆 弘法大師」の道標石碑(文化十五年(1818年)建立)、左手には「厄除弘法大師」の道標石碑(文政五年(1822年)建立)があり、いずれも隅田区登録文化財です。


【写真 上(左)】 厄除弘法大師碑
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
その先に立派な寺号標と山門。
山門は築地塀を附設した切妻屋根本瓦葺の四脚門で、見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 石碑群
山内も十分な奥行きがあり、山門くぐって右手には石碑群が整然と並び、山内には多くの石碑が点在します。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 地蔵堂
参道右手墓域入口には六地蔵と地蔵堂、墓域内には弘法大師千百五十年御遠忌記念の大きな仏塔と舎利塔があります。


【写真 上(左)】 弘法大師千百五十年御遠忌記念塔と舎利塔
【写真 下(右)】 太子堂
樹木が少なく明るく開けた山内を進みます。
参道右手の宝形造の堂宇は太子堂で、開祖と伝わる良弁法印審範奉安の聖徳太子像ゆかりとみられます。
その先に切妻屋根桟瓦葺一間妻入りの大師堂。
堂内に御座すお大師さまの台座には「第八十四番」とあるので、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第84番の札所とみられますが、荒川辺霊場、隅田川霊場の拝所でもあると思われます。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 佐助稲荷大明神
さらにその先には佐助稲荷大明神が御鎮座です。
当山が鎌倉・佐助谷の蓮華寺ゆかりという縁起に因んでの勧請かもしれません。

【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝。桟瓦葺のコンクリ身舎ながら名刹にふさわしい風格があります。
本堂の扉は開きました。
大規模な天蓋、幢幡を拝した絢爛たる堂内の御内陣正面に、牀座に結跏される真如親王様の弘法大師像が御座されます。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 堂内


【写真 上(左)】 天水鉢
【写真 下(右)】 庫裏
堂前天水鉢の三つ鱗紋は、開山の(北条)佐々目大僧正頼助にちなむものでしょうか。
御朱印は本堂左手奥の庫裏にて拝受しました。
〔 蓮花寺の御朱印 〕

中央に「女人済度 厄除弘法大師」の揮毫と、弘法大師のお種子「ユ」の印判と寺院印。
左には寺号の印判が捺されています。

■ 墨田区お寺めぐり第11番のスタンプ
---------------------------------
これにて隅田川二十一ヶ所霊場のご紹介は完結です。
いまはほとんど知られていない存在となっていますが、下町の歴史ある寺院を順にまわれる面白い霊場かと思います。
興味のある方はぜひぜひどうぞ。
※札所および記事リストは→ こちら。
【 BGM 】
■ Waiting For Love feat.Noa - 中村舞子
■ ガラスの林檎 - 松田聖子
踊りはおろか、振りさえつけていない。
それでいてこの存在感。天性のシンガーだと思う。
■ 瞳がほほえむから - 今井美樹
※札所および記事リストは→ こちら。
『荒川辺八十八ヵ所と隅田川二十一ヵ所霊場案内』(新田昭江氏著/1991年)を『ガイド』と略記し、適宜引用させていただきます。
■ 第21番 清瀧山 観音院 蓮花寺
(れんげじ)
墨田区観光協会公式Web
墨田区東向島3-23-17
真言宗智山派
御本尊:弘法大師
札所本尊:
司元別当:(寺島村)総鎮守・白鬚神社(墨田区東向島)
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第72番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第84番、新葛西三十三観音霊場第19番、墨田区お寺めぐり第11番
第21番は墨田区東向島の蓮花寺。
東向島の旧町名「寺島」の地名のいわれとなったとされる中本寺格の真言密寺です。
墨田区観光協会公式Web、下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
蓮花寺はすこぶる複雑な縁起をもたれます。
一説には寛元四年(1246年)、鎌倉幕府第5代執権、最明寺入道北条時頼の開基で、時頼の兄の北条武蔵守経時追福のため鎌倉佐介谷(現・鎌倉市佐助)に創建された蓮華寺が創始といいます。
頼朝公の外伯父、深井法眼範智の孫・良弁法印審範を開祖として聖徳太子の御像を安置といい、後に京の禁裏から弘法大師空海御自筆の「女人済度厄除弘法大師」を招来し奉安したといいます。
経時の死後、子の頼助は諸般の事情から執権職を叔父の時頼に譲り、自らは剃髪入道して諸国を廻ったといいます。
廻国ののち寺島の地に一寺を建て、弘安三年(1280年)鎌倉の蓮華寺の名跡を遷し、「女人済度厄除弘法大師」を御本尊とし、堂宇を建てて聖徳太子の御像を納め、佐々目大僧正頼助と号して自ら開山となったといいます。
(『ガイド』によると蓮花寺の『日過去帳』には、「大僧正頼助永仁四年(1296年)二月八日蓮華寺開山」とある由。)
以上の縁起は、江戸期には人口に膾炙していたようですが、『新編武蔵風土記稿』『江戸名所図会』『葛西志』などは、こぞってこの縁起に疑義を呈しています。
その疑義とはおおよそ以下のとおりです。
*******
1.『鎌倉大日記』に、建長三年(1251年)経時のために佐介谷に蓮華寺を建立した住持は良忠(記主禅師)と記されていること。
2.『鎌倉志』に、佐介谷の蓮華寺は寛元元年(1243年)平(北条)経時の建立にて、時の導師は記主禅師(良忠)とあること。
3.上の二書ともに蓮華寺建立の導師は記主禅師(良忠)とあるからには、その宗門はもとより浄家(浄土宗)であることは明らかである。
4.『鎌倉志』には蓮華寺創立の後、経時の霊夢により光明寺と改めたとあり、光明寺でもこのように伝わる(ので蓮華寺が光明寺の前身であることは明らか)。
5.以上より、佐介谷の蓮華寺は光明寺となったことは明らかであり、あるいは寺島の地は頼助の領地だったため、(佐介谷の蓮華寺)遙拝のために同名の寺を起立したのではないか。
佐介谷の蓮華寺が(光明寺)に改号した(材木座に移転して佐介谷の蓮華寺がなくなった)ため、後の人々が(佐介谷の)蓮華寺が(寺島の)蓮華寺に移ったという説を打ちたてたのではないか。
*******
鎌倉材木座の光明寺といえば浄土宗の大本山であり、光明寺公式Webには「良忠上人は鎌倉幕府第四代の執権、北条経時公の帰依を受けてこの光明寺を開かれたといわれています。」と記されています。
その光明寺の前身が佐介谷の蓮華寺であることは諸史料に明らかで、記主禅師良忠上人ゆかりの佐介谷の蓮華寺が、江戸墨東・寺島の地に、しかも真言密寺として移転というのはどうみても不自然です。
また、諸史料からすると、京の禁裏から弘法大師空海御自筆の「女人済度厄除弘法大師」を招来し安置したのは佐介谷の蓮華寺とみられますが、禁裏に奉安の弘法大師御自筆の「女人済度厄除弘法大師」といえば真言宗の至宝であり、その至宝を浄土宗の蓮華寺に相伝するというのもいささか解せない流れです。
さらにWikipediaで頼助 (北条氏)を当たってみると、
---------------------------------
・頼助(1244-1296年)は真言僧で、父・北条経時の菩提所である鎌倉佐々目の遺身院を拠点とし、佐々目頼助とも呼ばれた。
・弘長二年(1262年)以前には出家している。
・三宝院・安祥寺・仁和寺各流を受法し、仁和寺流・法助の弟子となって文永六年(1269年)に頼守から頼助に改名した。
・修行を積んで鎌倉に戻り、弘安四年(1281年)の元寇の際には異国降伏祈祷を行い、弘安六年(1283年)には鶴岡八幡宮の10代別当となる。
・円教寺、遍照寺、左女牛若宮等の別当、東寺長者などを歴任し、正応五年(1292年)、大僧正・東大寺別当に就任。
---------------------------------
とあり、真言僧として錚錚たる地位を歴任しています。
なお、佐々目(谷)は佐助と長谷の間の谷で、『吾妻鏡』寛元四年(1246年)閏4月2日條には、北条経時が佐々目山麓に葬られたと記されています。
佐々目の遺身院および頼助については、以前こちらの記事(鎌倉市の御朱印-7の24.安養院)でもふれています。
『鎌倉下向僧の研究 - 願行房憲静の事跡 -』(高橋秀栄氏/PDF)には「勝賢開山の佐々目西方寺にはじまり、関東の三宝院流はここに発祥し、大門寺、遺身院その他の寺院群が佐々目の地にあった模様である。」とあります。
以上から考えると、頼助は真言密各派の教義を修めたばりばりの真言僧で、自身の領地(寺島)に鎌倉から寺院を遷すとすれば、拠点としていた佐々目の真言密寺・遺身院を遷すのではないかとも思えます。
鎌倉の拠点として遺身院を残しておきたいのであれば、寺島には分院を置いてもいいですし、佐々目にいくつかあった真言密寺を遷してもいい筈です。
少なくとも他宗派の重要寺院・蓮華寺を遷すという発想には至らないのでは。
このような疑義もあってか、当山の縁起については「はっきりしない」とか「諸説あり」と記される例が多くなっているのだと思います。
どうにもすっきりしないので、さらに『鎌倉市史 寺社編』を当たってみました。
同書P.429~に気になる記述があります。
「従来光明寺について多くのものは『鎌倉佐介浄刹光明寺開山御伝』により、然阿良忠か仁治元年(1241年)二月、鎌倉に入り、住吉谷悟真寺に住して浄土宗を弘めていた、時の執権経時は良忠を尊崇し、佐介谷に蓮華寺を建立して開山とし、ついで光明寺とその名を改め、前の名蓮華の二字を残して方丈を蓮華院となづけた。寛元元年(1243年)五月三日、吉日を卜して良忠を導師として供養した。といい、『風土記稿』所引の寺伝では、この時に、現在地材木座に移転したようにいっている。しかし、経時(1246年没)の法名は蓮花寺殿安楽大禅定門とあるから、光明寺と改名するのは、どうも後世のように思われる。『良暁述聞制文』には、「佐介谷悟真寺今号蓮華寺」とあり、正中二年(1325年)三月十五日にはまだ光明寺という名がでてこない。(中略)『開山御伝』に建長頃(1249-1256年)、北条時頼が寺領を加へ、外門の額字を、佐介浄刹としたという話も、佐介谷にあればこそのことではないかと思う。(中略)『資料編』三の四七六及び四七八はいづれも江戸時代に納められたもので、内容から考えてどうも密教系の寺のものでここのものではないらしい。光明寺の肩の文字を抹消していることも、疑問がのこるところである。(中略)現在のところ(材木座)に移転した期日及び名を光明寺と改めた時期はなお研究を要する問題である。」
『資料編』三の四七六及び四七八が手元にないのでなんともいえませんが、「密教系の寺」が寺島の蓮花寺だとすると、光明寺の縁起を辿るときに寺島蓮花寺関連の文書が入り、錯綜している様子がうかがえます。
こんなこともあって、寺島の蓮花寺の縁起は現代に至ってなお「諸説あり」とされるのかもしれません。
なお、上記の『鎌倉市史 寺社編』によると、正中二年(1325年)の時点ではまだ光明寺の名は出てこず(=蓮華寺が存在していた)、弘安三年(1280年)に頼助が鎌倉から蓮華寺を遷したという当山縁起(説)の内容と時系列的には符合しますが、そうなると弘安三年(1280年)以降は(寺島に移転したため)鎌倉に蓮華寺は存在しないことになり、光明寺まで系譜がつながらなくなってしまいます。
---------------------------------
以上のように縁起沿革こそ不明瞭さは残るものの、禁裏から相伝の弘法大師御自筆の「女人済度厄除弘法大師」を奉安は、江戸庶民にとって圧倒的なインパクトであり、当山は「厄除け寺島大師」と尊称され、川崎大師平間寺、西新井大師総持寺とともに「江戸三大師」に数えられて参詣者を集めました。
一説に鎌倉幕府第5代執権、北条時頼公の開基、大僧正・東大寺別当の(北条)頼助の開山ということもあり、自ずから寺格は高く京都智積院直末の中本寺格寺院でした。
墨東の弘法大師霊場・隅田川二十一ヶ所霊場の結願寺として、まことにふさわしい名刹といえましょう。
北条家滅亡の後も足利将軍、管領等の崇敬は篤かったものの、文明年間(1469-1487年)の下総千葉家内の騒乱によって当山は荒廃したといいます。
天文年間(1532-1555年)、この地が小田原北條家の領地となった頃、遠山丹波守が奉行として寺領等を寄附して寺勢を復しましたが、その後ふたたび戦乱で荒廃。
しかし家康公の治世に当山由緒の御尋ねあって、御朱印を賜い堂舎を造立、「江戸三大師」にも数えられて寺勢を保ちいまに至るといいます。
女人救済の霊場としては「江戸六阿弥陀」(→ 関連記事)が知られていますが、「女人済度厄除弘法大師」は江戸近辺ではあまり例がないとみられ、多くの女性の参詣を集めたことは想像に難くありません。
なお、当山は江戸期には東向島(寺島村)総鎮守・白鬚神社の別当でした。


【写真 上(左)】 白髭神社
【写真 下(右)】 白髭神社の御朱印
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻二』(国立国会図書館)
(寺島村)蓮華寺
新義真言宗山城國醍醐三寶院末 清瀧山観音院ト号セリ
本尊弘法大師自書ノ像ヲ安ス(中略)縁起云 当寺ハ最明寺平時頼ノ舎兄武蔵守経時朝臣ノ菩提寺ナリ
初ハ相州鎌倉郡佐介谷ニ創立アリテ 其経時寛元四年(1246年)逝去ノ後時頼一寺ヲ建立シ 蓮華寺殿前武州安楽大禅定門ト謚ス 時ノ開山ハ辨法印審範ナリ 審範ハ則頼朝卿ノ外伯父 深井法眼範智ノ孫ナリ 其後経時ノ子佐々目大僧正頼助此寺嶋ヲ知行アリシ時 鎌倉ノ蓮華寺ヲ此所ニ移シ 弘安三年(1280年)八月建立シテ頼助自カラ中興ノ開山トナレリ云々
按ニ此寺伝甚疑フヘシ イカニト云ニ 鎌倉大日記ニ建長三年(1251年)経時ガ為ニ佐介ニ於テ蓮華寺建立住持ハ良忠ト記シ 又鎌倉志ニ佐介谷ノ蓮華寺は寛元元年(1243年)五月三日平経時ノ建立ニテ 時ノ導師ハ記主禅師トアリ 此二書ニ載ル処年代等ハ異同アレト 導師ハ共ニ記主ナレハ宗門元ヨリ浄家ニシテ審範ニアラサルコト明ケシ シカノミナラス鎌倉志ニハ蓮華寺創立ノ後経時霊夢アリテ光時(明?)寺ト改ム由ヲ記シ今モ光明寺ニテモシカ伝フレハ 当寺の伝記正シトハオモハレス モシクハ当所頼助カ領知ナレハ 遙拝ノ為別ニ同名ノ寺ヲ起立アリシヲ タマタマ佐介谷ノ蓮華寺改号セル故 後人妄ニ彼寺ヲ引キ来リシナト云コセシニアラスヤ
鐘楼 宝暦八年ノ鐘ナリ
愛染堂 興教大師ノ書ケル像ヲ安ス
権現堂 清瀧権現ト号ス
■ 『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館)
清瀧山蓮華寺
寺嶋村にあり 寺記に云く昔此地ハ海原なり 後世ようやく干潟となりし頃当寺を創建ありし故に寺嶋の称ありといへり 小田原北条家の所領役帳に行方与●島葛西寺寺嶋の地を領すとあり
当寺ハ真言宗にして醍醐の三宝院末に属す 本尊阿弥陀如来如来の像ハ恵心僧都の作といふ
太子堂 本堂の右にあり本尊聖徳太子の像ハ十六歳の真影にして太子自彫造ありしと云
北条経時の念持佛にて往古ハ相州鎌倉佐々目にありしを 弘安三年(1280年)の秋北条頼助寺院●●●に本尊共に此地へ引移し同年八月二日入佛供養を営し故(中略)
寛文二年(1662年)の夏國中大に疫病流行し人民死する者少からしを 経時頗●是を嘆き本尊に告て諸人の病苦を消除せんとて懇に祈願すと 或夜経時に霊示ありて秘符を賜ふ 即此秘符によりて其頃病を退け命を全うする者●●(少な?)からすとなり
相伝ふ 寛元四年(1246年)三月北条経時病に臨む其時 舎弟時頼を側へ招き示して云く我疾難治なり 死後に至らハ一宇の梵刹を創建し年頃念ね処の聖徳太子の像を安置すへしといひ●て同四月朔日享年三十八歳にして逝去あり
依時頼遺命を奉じて鎌倉佐介谷に一宇を闢き蓮華寺と号く 経時の法号を蓮華寺殿前武州安楽大禅定門と号す 即辨法印審範を以て開山とす
寺記に審範は頼朝の伯父深井法眼範智の孫なりと云されと 鎌倉大日記にハ開山良忠とありて一なら●●次に詳ん
又其後経時の子頼助此寺嶋を領せし● 出離の志頗にして忽に剃髪し弘安三年(1280年)の秋鎌倉の蓮華寺●寺嶋に移し自開山たり
佐々目大僧正頼助と号せり按に先に審範を開山とすとあるハ鎌倉にありての寺をいふなるへし 此寺移るに至りてハ頼助開山たりしなるへし 諸家係累に経時の子に顕助といふ号を載て●傍に依て木像と注せり
疑ふらくハ佐々目といふ●●●を誤●るなるへしにて頼助ハ顕助のことをいふならん(以下不明)
北條家滅亡の後もなを尊氏将軍及ひ管領基氏等崇敬厚く(中略)文明(1469-1487年)の頃下総の千葉両家と別●て時 たがひに争戦止時なく兵火の災●にして当寺も大に荒廃せり 然に天文年間(1532-1555年)小田原北條家の領地となりし頃 遠山丹波守奉行として寺領等を寄附せし(以下略)
按に鎌倉光明寺の開山記主禅師伝に云く 寛元元年(1243年)五月三日前武州太守平経時鎌倉の佐介谷にをひて浄刹を建立し蓮華寺と号け良忠を導師として供養を●らる後に経時霊夢を感するところありて 光明寺とあらたむると云々
又鎌倉大日記に云く建長三年(1251年)経時の為に佐介にをひて蓮華寺建立住持良忠とあり されと寛元(1243-1247年)に建立せし蓮華寺ハ経時の生前なり 又建長(1249-1256年)に建立ありし蓮華寺ハ経時の没後にして其間七年を隔てり 依て考ふるに其号によるときハ一寺の如なれども自ら別なるへし 然る時ハ鎌倉光明寺の開山伝に載て寛元元年(1243年)経時生前に建立すとある●のハ 後に光明寺 とあらしめ鎌倉の内の材木座へうつしたる是なり 又鎌倉鎌倉大日記に●●●る経時卒去の後菩提の為に建立とある●ノハ即当寺の権よなるへし

■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
(寺島村)蓮華寺
新義真言宗、山城國醍醐三寶院末なり。清瀧山観音院と号す。
縁起云、最明寺平時頼の舎兄、武蔵守経時朝臣の菩提寺なり。
初めは相州鎌倉郡佐介谷に創立あり、かの経時は、寛元四年(1246年)逝去なり。
執権の職を、舎弟最明寺殿(時頼)にゆべり、その後一寺~建立し、法号を蓮華寺殿前武州安楽大禅定門と号す。
その時の開山は辨法印審範なり。審範は、則頼朝卿の外伯父、深井法眼範智の孫なり。
初は天台宗長瞬法眼の門弟なりしが、後に真言となり、道禅僧正に受法す。
又公縁僧正灌頂の弟子となり、弘長元年(1261年)入滅す。
其後経時の御ご子息、佐々目大僧正頼助、此寺嶋を知行ありしとき、鎌倉の蓮華寺を此所に移転し、弘安三年(1280年)八月当寺を建立して、則頼助開山となれり。
按に此縁起の説、未他の所見なし、鎌倉志に、佐介谷の蓮華寺は、寛元元年(1243年)五月三日平経時の建立にして、時の導師は記主禅師なりとあり、又鎌倉大日記に、建長三年(1251年)経時が為に、佐介谷に於て蓮華寺建立、住持は良忠(記主禅師の名なり、とあり(略)導師は共に記主禅師なるよしいへば、今ここに開山を審範なりといふ事最疑ふべし、又鎌倉蓮華寺創立の後、経時霊夢有て、光明寺と改むとあり、是によればかの佐介谷の蓮華寺は、全く今の光明寺の古号にして、当所のは自ら別寺なりしを、たまたま同名なるゆへ附会せしものか、ここに当所は頼助が、領知なりしといへば父の菩提の為に建立ありて蓮華寺と称せしも、又しるべからず とにかく鎌倉より移転せしと云はおぼつかなし。
その後此僧正鎌倉八幡宮の別当に補任なり、在鎌倉十四年京六條の若宮の別当も、兼帯なり、此僧正は、守海法印入室の弟子、三寶院良入前僧正灌頂安祥寺 奉遇仁和寺御室開田准后灌頂(中略)
文明(1469-1487年)の比に至りて、下総の千葉両家相分かれて、合戦やむ時なし、千葉自胤、同實胤は、葛西郡及び武州石濱まで出張して、総州勢とかけ合たれば、当所はたまたま合戦のただ中となり、兵火の為に焼るゝ事度々なり、よりて代々の寄附状、或は古佛に至るまで、みな何地へか分散して、僅にのこれるものは、本堂と本尊のなり、かゝりける程に、天文年中(1532-1555年当所の地頭、遠山丹波守某が推挙に依て、小田原北條家より虎印の願書と、寺領を附せられて、再建なり
北條家の運尽て、天正十八年(1590年)、終に落城に及びしかば、朱印はむなしく伝へたれども、領地はいづくへか奪はれしを悉くも、神君関東後打入の後、当寺の由緒を御尋有て、先規のごとく若干の寺地をゆるされ、御朱印をも賜ひしかば、再び堂舎を造立して、今に至ると云。
客殿 本尊阿彌陀如来を安置す 作しれず。
清瀧権現堂 祭神詳ならず。
鐘楼 鐘は宝暦八年の鋳造(以下略)
■ 『墨田区史 本編』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
蓮花寺(清滝山観音院)
山城三宝院末で真言宗に属し本尊の宗祖の像は弘法大師の自画像と伝えられ、「厄除女人済度弘法大師」の称がある。
伝えられる創建の由来によれば、同寺は初めは相模の国の鎌倉郡佐介谷にあり、最明寺入道北条時頼が寛元四年(1246年)に死去した兄の武蔵守経時の追福のために建立、辨法印審範を開山としたもので、経時の子佐々目大僧正頼助が葛西寺島の地を知行していた関係で鎌倉から寺島に移し、弘安三年(1280年)八月に則頼みずから中興助開山となったのである。
しかし蓮花寺移転のことについては「夢跡集」門柱「蓮花寺は佐介ヶ谷より武蔵国葛西の地へうつり、其寺院の跡に光明寺を建立せし事ならん。」と述べているものの、「新編武蔵風土記稿」の記すところによれば鎌倉の蓮花寺は浄土宗の寺院であり、経時追福のために良忠が建長三年(1251年)に創建したといい、あるいは経時自身によって寛元元年(1243年)五月三日に建立されたともいわれ、のちに霊夢によって寺号を光明寺と改称したのであると伝えられている。
これによれば蓮花寺は鎌倉の蓮華寺(のちに光明寺)とは別の同名の寺院であるが、寺号改称のことは光明寺の寺伝にも明らかに記されているとのことであるから、寺島の蓮花寺はおそらく「武蔵通志」が述べているように、経時の子で僧籍にはいった頼助によってその所領地の寺島に弘安三年(1280年)八月に建立されたものであろう。
蓮花寺創建によって土地の名称を寺島というようになったとの説がある。(以下略)
■ 『すみだの史跡文化財散歩 P.21』(墨田区資料/PDF)
蓮花寺(東向島3-23-17)
清滝山蓮花寺は、京都智積院末で真言宗智山派に属し、本尊は空海自筆の弘法大師画像と伝えられています。この寺の開山については諸説があります。
■ 『新編鎌倉志 鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)
光明寺
光明寺は、本は佐介谷に在しを、後に此地に移す。当寺開山の伝に、寛元元年(1243年)五月三日、前武州太守平経時、佐介谷に於て浄刹を建立し、蓮華寺と号し、良忠を導師として、供養をのべらる。後に経時、霊夢有て光明寺と改む。方丈を蓮華院と名くとあり。
蓮華寺跡(佐介谷)(同上資料)
今俗に光明寺畠と云ふ。光明寺、本此地にあって、蓮華寺と号す。後に光明寺と改む。
『鎌倉大日記』に、建長三年(1251年)、経時が為に、佐介に於て蓮華寺建立、住持良忠とあり。良忠此谷に居住ありしゆへに、佐介の上人と云ふなり。光明寺の條下及ひ『記主上人傳』に詳也。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』隅田川向島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは東武スカイツリーライン「東向島」駅で徒歩約10分。
下町らしからぬ整備された街区にあり、門前、山内ともに広々として名刹の風格があります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 女人済度弘法大師碑
参道入口向かって右手に「女人済度 御自筆 弘法大師」の道標石碑(文化十五年(1818年)建立)、左手には「厄除弘法大師」の道標石碑(文政五年(1822年)建立)があり、いずれも隅田区登録文化財です。


【写真 上(左)】 厄除弘法大師碑
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 山門扁額
その先に立派な寺号標と山門。
山門は築地塀を附設した切妻屋根本瓦葺の四脚門で、見上げに山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 石碑群
山内も十分な奥行きがあり、山門くぐって右手には石碑群が整然と並び、山内には多くの石碑が点在します。


【写真 上(左)】 六地蔵
【写真 下(右)】 地蔵堂
参道右手墓域入口には六地蔵と地蔵堂、墓域内には弘法大師千百五十年御遠忌記念の大きな仏塔と舎利塔があります。


【写真 上(左)】 弘法大師千百五十年御遠忌記念塔と舎利塔
【写真 下(右)】 太子堂
樹木が少なく明るく開けた山内を進みます。
参道右手の宝形造の堂宇は太子堂で、開祖と伝わる良弁法印審範奉安の聖徳太子像ゆかりとみられます。
その先に切妻屋根桟瓦葺一間妻入りの大師堂。
堂内に御座すお大師さまの台座には「第八十四番」とあるので、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第84番の札所とみられますが、荒川辺霊場、隅田川霊場の拝所でもあると思われます。


【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 佐助稲荷大明神
さらにその先には佐助稲荷大明神が御鎮座です。
当山が鎌倉・佐助谷の蓮華寺ゆかりという縁起に因んでの勧請かもしれません。

【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂
本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝。桟瓦葺のコンクリ身舎ながら名刹にふさわしい風格があります。
本堂の扉は開きました。
大規模な天蓋、幢幡を拝した絢爛たる堂内の御内陣正面に、牀座に結跏される真如親王様の弘法大師像が御座されます。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 堂内


【写真 上(左)】 天水鉢
【写真 下(右)】 庫裏
堂前天水鉢の三つ鱗紋は、開山の(北条)佐々目大僧正頼助にちなむものでしょうか。
御朱印は本堂左手奥の庫裏にて拝受しました。
〔 蓮花寺の御朱印 〕

中央に「女人済度 厄除弘法大師」の揮毫と、弘法大師のお種子「ユ」の印判と寺院印。
左には寺号の印判が捺されています。

■ 墨田区お寺めぐり第11番のスタンプ
---------------------------------
これにて隅田川二十一ヶ所霊場のご紹介は完結です。
いまはほとんど知られていない存在となっていますが、下町の歴史ある寺院を順にまわれる面白い霊場かと思います。
興味のある方はぜひぜひどうぞ。
※札所および記事リストは→ こちら。
【 BGM 】
■ Waiting For Love feat.Noa - 中村舞子
■ ガラスの林檎 - 松田聖子
踊りはおろか、振りさえつけていない。
それでいてこの存在感。天性のシンガーだと思う。
■ 瞳がほほえむから - 今井美樹
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-7
■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-6からのつづきです。
※札所および記事リストは→ こちら。
『荒川辺八十八ヵ所と隅田川二十一ヵ所霊場案内』(新田昭江氏著/1991年)を『ガイド』と略記し、適宜引用させていただきます。
■ 第18番 宝寿山 遍照院 長命寺
(ちょうめいじ)
公式Web
天台宗東京教区公式Web
墨田区向島5-4-4
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:
司元別当:
他札所:隅田川七福神(弁財天)、東京三十三所観世音霊場第32番、弁財天百社参り番外22、墨田区お寺めぐり第15番
第18番は墨田区向島の長命寺、比叡山延暦寺直末とみられる名刹です。
公式Web、天台宗東京教区公式Web、下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
長命寺の創建年代等は詳らかでないですが、寺伝には「元和元年(1615年)頃の中田某の檀那寺」とあり、「長命水石文」によると古くは寶寿山常泉寺と号した天台宗寺院でした。
一説には慶長年間(1596-1615年)に孝徳または宗泉によって創立ともあります。
中興開山は誓院権僧正玄照和尚(寶暦十三年(1763年)寂)。
御本尊は『新編武蔵風土記稿』『墨田区史』には阿弥陀如来、『江戸名所図会』には釋迦如来と記され、公式Web、天台宗東京教区公式Webでは阿弥陀如来となっています。
寛永年間(1624-1643年)のある日、三代将軍家光公(大猶院殿)がこの地に鷹狩に訪れた際、にわかに腹痛をおこして当寺で休憩、住職・孝徳(専海とも)和尚が傳教大師御作と伝わる当山の辨財天に加持した庭の井水・般若水を捧げ、この水で薬を服用したところ痛みはたちまち収まったので、家光公はこの水に「長命水」の名を賜い、これより寺号を長命寺と改めたといいます。
山内には長命水がいまもその姿を残しています。
(なお、『紫の一本』『墨水消夏録』は、これを徳川家康公の事跡としています。)
山内の精大明神社は「蹴鞠ノ神」と言い伝えられましたが、祭神等は定かではないようです。
般若堂と不動堂は相殿で、安する不動尊像は智證大師の御作といいます。
『新編武蔵風土記稿』によると、傳教大師御作の辨財天と元三大師降魔像も相殿だったようです。
地蔵堂は『葛西志』に「西國二十二番観音の寫を相殿とす」とあるので西國写観音霊場第22番札所であった模様ですが、この観音霊場については不明です。
当山は関東大震災の慰霊のため開創という東京三十三ヶ所観音霊場第32番の札所ですが、前身としてこの観音霊場の存在があったのかもしれません。
(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
こちらの辨天様は有名で、隅田川七福神の一尊であっただけでなく、弁財天百社参り番外22の札所本尊にもなっています。

『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館より、筆者にて加筆加工)
古くは山内に弁天堂や芭蕉堂がありました。
芭蕉堂は宝暦年間(1751-1764年)に俳人衹徳が建てた自在庵を創始とし、後に能阿により再興、芭蕉の木像を安置して芭蕉堂と称されていました。
『本所区史』には、芭蕉像を安したのは芭蕉の門人・青流(稲津祇空/1663-1733年)の門人で浅草蔵前の札差であった自在庵祇徳で、享保年間(1716-1736年)のこととあります。
しかし、『江戸名所図会』には「自在庵𦾔址 堂の右竹藪の中にあり 誹諧師水國ここに庵室をむすひて住たりしといへり」とあり、現地掲示にも芭蕉庵を建てたのは俳人雲津水国(1682-1734年)とあります。
山内に建つ、松尾芭蕉の「いざさらばの句碑」(区登録文化財)。
「いさゝらは 雪見にころふ 所まて」
これは芭蕉が熱田神宮参詣の際に『笈の小文』に詠んだ句ですが、長命寺が墨堤の雪景色の名所として知られていたため、山内に句碑が置かれたとされています。
現地掲示には「いざさらばの句碑」を建てたのは三代仲祇徳で、安政五年(1858年)とあります。
よって、芭蕉堂は俳人雲津水国(1682-1734年)が建て、「いざさらばの句碑」を建てたのは三代仲祇徳ということになります。
ただし、仲祇徳は少なくとも三代(三人)はいるようなので、このあたりの時系列はよくわかりません。
筆者は俳諧の道にはまったくうとく、下手に書き込むとたちまち馬脚を露わすので(笑)、このくらいにしておきます。
なお、『江戸名所図会』で長命寺のすぐ横に「本社」と描かれているお社はおそらく牛御前社(現・牛嶋神社)と思われます。
いかにも本社と別当を示す位置関係ですが、牛御前社の別当は東駒形の第7番札所の牛宝山 最勝寺で、最勝寺は大正2年江戸川区平井に移転しています。
本堂は安政二年(1855年)の大地震で焼失、麻布の武家屋敷を移築して本堂とし明治に及んだといいます。
関東大震災で本堂、芭蕉堂など多くの伽藍を失いましたが、御本尊は難を遁れていまも本堂に御座します。
長命寺は雪景色の美しさでも知られ、『江戸名所花暦』にも「長命寺隅田川の堤曲行の角にあり。境内に芭蕉の碑あり。この辺に佇みて左右をかへり見れば、雪の景色いはんかたなし。」と記されています。
もとより向島は風流の地として知られ、雪景色や芭蕉堂の存在もあって、長命寺には多くの文人墨客が訪れたとみられます。
寺内には芭蕉句碑をはじめ、東京都指定の橘守部(江戸時代の国学者)の墓、義太夫節の名家鶴沢清六の塚、太田蜀山人の歌碑、成島柳北(明治時代のジャーナリスト)の碑などがあり、いまもエリア屈指の文化財のお寺として知られています。
※山内の文化財については→ 公式Webをご覧ください。
【長命寺桜もち】
「桜餅 食ふてぬけけり 長命寺」 (虚子)
長命寺桜もちはこの向島屈指の銘菓です。
享保二年(1717年)、創業者山本新六が墨堤土手の桜の葉を樽の中に塩漬けにした「桜もち」を考案して長命寺門前で売り始め、参詣客や桜の名所・隅堤の花見客のあいだで評判となりました。
桜葉の香り高い美味しさもさることながら代々の店主の看板娘の接待が評判で、なかでも三代目の長女「お豊さん」は美貌で名を馳せ、猿若町で芝居にも上演されたといいます。
明治の「お陸さん」という娘も美人の誉れ高く、正岡子規が当家の二階に下宿し、子規とお陸さんとの恋物語もあったとか。
「鐘の音に夢さめはてて浅草や 朝の別れのつらくもあるかな」 (子規)
『江戸切絵図』では長命寺の山内に「名物サクラモチ」とあり、よほど人気があったと思われます。
「長命寺桜もち」はなんと長命寺の公式Webでも紹介され、両社の密接な関係を物語っています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻二』(国立国会図書館)
(須崎村)長命寺
天台宗東叡山末 寶寿山扁(ママ)照院ト号ス 本尊阿彌陀脇士ニ観音勢至ヲ置 過去帳ニ住僧宗泉慶安二年(1649年)十一月七日示寂トアリ 境内辨天ノ縁起ニ 寛永(1624-1644年)ノ末大猶院殿御放鷹ノ時 俄ニ御異例ニテ当寺ニ入御アリケルニ 住僧専海辨才天ニ祈願ヲコメ則御手洗ノ般若水ヲ汲ミテ御供ノ士中根壱岐守ヲ以テ捧ケ奉リシニ 御心地サハヤカニナラセタマヒケレハ 御快気ノ程ヲ祝セラレ 寶樹山常泉寺ノ𦾔号ヲ改テ今ノ寺山号ヲ賜ヒシト云 是ニヨレハ専海ハ寛永ノ頃ノ住僧ニシテ宗泉ヨリ先代ナルヘシ
精大明神社
神体金幣ニテ光成卿ノ霊ヲ祭ル 蹴鞠ノ神ナリトノミ云傳フ 光成卿トイヘルハイカナル人ニヤ 蹴鞠ノ宗匠難波飛鳥井両家ニハ聞エサル人ナリ 按ニ諸神記ニ中御門西洞院東頬滋野井小社三座是蹴鞠神也 此地大納言成通卿旧跡トアリ 成通卿ハ蹴鞠ノ名人ニテ凡人ノシワサニアラサル由『著聞集』等ニモ記シタリハ モシクハ是ヲ誤テ光成卿ナト云傳ヘシニヤ 又近江國志賀郡松本ト云地ニ精大明神社アリ 祭礼猿田彦命ニテ蹴鞠ノ神ナリト云 当社ハ恐クハ是ヲウツセシモノニテ光成卿ヲ配祀セルナラン
稲荷社
般若堂 文殊普賢ノ外十六善神ヲ置 又不動及二童子アリ 不動ハ智證大師ノ作又傳教大師ノツクレル辨天元三大師降魔ノ像アリ
地蔵堂
長命水趾 此井ノ水ヲ般若水ト呼フ則前ニ云ル御手洗ノ跡也
奈岐木 菓子所大久保主水カ植シモノナリ 高二丈程周四尺モアルヘシ 樹根ニ此木ヲ植ル顛末ヲ鋳セル碑ヲ立
■ 『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館)
寶寿山長命寺
遍照院と号す 天台宗東叡山に属せり 本尊ハ等身の釋迦如来 脇士ハ文殊普賢 般若十六善神等の像を安す
牛嶋辨財天 同じ堂内に安す 傳教大師の作なり
長命水 同じ堂の後の方にあり 一に般若水と云
自在庵𦾔址 堂の右竹藪の中にあり 誹諧師水國ここに庵室をむすひて住たりしといへり 今其地に芭蕉翁の句を彫たる碑を建てあり
殊更当寺ハ雪の名所にて前に隅田川の流れをうけて風色たらすといふをなし
■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
長命寺
牛御前社の北に隣りて、門は西向きなり、天台宗東叡山末、寶寿山遍照院と号す、寺伝云、当寺古は寶樹山常泉寺と唱へしに、寛永年中(1624-1644年)、大猶院殿此邊御鷹狩に成らせ給ひて、御不例おはしませし時、中根壱岐守当寺の井水を汲て、後手水に奉りしかば、御なやみ頓に御本復あり、よりて寺山号を、今のごとくに改められしと、又紫一本には、これを、東照宮の御事績となし、寺もその比なでは寺号もなく、ただ草庵なりしなど、いとうきなる伝へなれど、何れゆへある寺号とはみヘたり、開山起立の年代詳ならず、中興を弘誓院権僧正玄照和尚と云、寶暦十三年(1763年)四月廿二日寂を示せり、本尊釋迦如来を安置す。
辨天不動相殿 門を入て正面にあり
精大明神社 門を入て右の方にあり、祭神詳ならず。
長命水 辨天堂の側にあり、則前にしるせる、大猶院殿御手水に用ひ給ひしと云井なり。
地蔵堂 門を入て右の方にあり、西國二十二番観音の寫を相殿とす。
■ 『東京名所図会 [第14] (本所区之部)(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
長命寺
長命寺は。向島須崎町八十八番地即ち牛島神社の北隣に在り。寶寿山と号し。遍照院と称す。天台宗にして。延暦寺の末なり。当寺初は常泉寺といひしが。寛永年間(1624-1644年)将軍家家光公放鷹の途次。微恙ありて寺に憩ひ。住持孝徳をして境内の盤石水を加め。服薬して頓に快癒せしを以て。長命水の名を賜ふ。因て是より長命寺と改む。
長命水今尚現存し。洗心養神と刻したる石標の傍に屋代弘賢のしるしたる碑を建たり。(中略)本堂は二十九年焼失後の新築にて。別に盤若堂と芭蕉堂あり。芭蕉堂殊に雅なり。
■ 『本所区史』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
長命寺
長命寺は向島須崎町八十八番地即ち牛島神社の北隣に在り寶壽山と号遍照院と称した。
天台宗にして延暦寺の末である。当寺初は常泉寺といったが寛永年間(1624-1644年)将軍家家光公放鷹の途次微恙の為めに寺に憩ひ、住持孝徳の差出した境内の般若水を以て服薬した処頓に快癒したので長命水の名を賜はった。因て是より長命寺と改めたのである。
長命水は今尚現存し洗心養神と刻した石標の傍に屋代弘賢のしるした碑を建てたとある。
り。(中略)本堂は二十九年焼失後の新築にて。別に盤若堂と芭蕉堂あり。芭蕉堂殊に雅なり。
元禄の昔、芭蕉松尾桃青は西行宗祇の遺風を慕ひ、未だ五七五の野風を楽しとして生涯を過ごしたが、即ち彼芭蕉は誹諧道中興開山といふべきであらう。
芭蕉の門人に青流といふ人が居り、或時宗祇法師の墓参をなしその墓前に於て、既に祇空しとて名を祇空と更め、向島の地に草庵をむすんで居たが、ふと雲水の心動き剃髪して諸国を遊歴し、享保十八年(1733年)四月廿三日享年六十八にして箱根湯本に没し、早雲寺に葬られた。
祇空の門人に自在庵祇徳といふ人があった。この人は浅草蔵前の札差であったが隠遁の志深く、享保年間(1716-1736年)に祇空の庵址近き長命寺中に草庵をしつらへ、庵室に芭蕉翁の像を安置し、三昧の外に他事なかった。これ即ち長命寺芭蕉堂の起原である。
■ 『墨田区史 本編』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
長命寺
天台宗延暦寺の末寺で古くは宝樹山常泉寺と号していたというが、開基者・開山者および創建の年などは明らかではなく、一説には慶長年間(1596-1615年)に孝徳または宗泉によって創立されたとする。
中興開山は誓院権僧正玄照和尚で、本尊は阿弥陀如来を安置する。
長命寺の寺号については、寛永(1624-1644年)のころ三代将軍家光が墨東の地に鷹狩を行った時、急病となってこの寺に立ち寄り寺内の井戸の水で薬を服用してたちまちに快癒したので、寺号常泉寺を改めて長命寺としたと伝えられており、また「紫の一本」や「墨水消夏録」はこれを徳川家康の事跡とし、当寺は名もない小庵であったので長命寺の寺号を与えたのであると述べている。
寺内には長命水が今もその姿を残していて、これが家光の用いた名水とされているが、このほか古くは弁天堂や芭蕉堂もあった。
芭蕉堂は宝暦年中(1751-1764年)に俳人祇徳が建てた自在庵という庵で、のちに能阿によって再興され長命寺芭蕉堂と通称されていたものである。
長命寺はまた雪景色の美しさで江戸名所のひとつに数えられていた。(中略)『江戸名所花暦』にも「長命寺隅田川の堤曲行の角にあり。境内に芭蕉の碑あり。この辺に佇みて左右をかへり見れば、雪の景色いはんかたなし。」と述べられている。
寺内には東京都指定の橘守部の墓、成島柳北の碑があり、また弁財天は隅田川七福神のひとつである。
■ 『すみだの史跡文化財散歩 P.35』(墨田区資料/PDF)
長命寺(向島5-4-4)
天台宗延暦寺末で、古くは宝寿山常泉寺と号していたそうですが、創建年等は不明です。寛永のころ3代将軍家光がこの辺りに臆狩りに来た時、急に腹痛をおこしましたが、住職
が加持した庭の井の水で薬を服用したところ痛みが治まったので、長命寺の寺号を与えたといいます。
■ 松尾芭蕉「いざさらば」の句碑 <区登録文化財>
「いさゝらは 雪見にころふ所まて」
碑陰には、3世自在庵祇徳の文で、芭蕉や祇空、祇徳の略伝等が述べられています。
■ 「長命水石文」の碑
この寺が長命の寺号を賜った経緯と井戸が長命水と名付けられたことを、時の住職最空が記しています。書は国学者の屋代弘賢で、天保3年(1832)の建碑です。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』隅田川向島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営地下鉄浅草線・メトロ半蔵門線「押上駅」駅で徒歩約15分。
隅田川にかかる「桜橋」経由で今戸方面からも歩けます。


【写真 上(左)】 桜橋
【写真 下(右)】 桜橋からの隅田川
第13番弘福寺のすぐお隣りにあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 門扉の三諦星紋
【写真 下(右)】 山内幼稚園ゾーン
山内門寄りは言問幼稚園で、山内入口の門柱と寺号標、そして門扉に輝く天台宗の宗紋・三諦星(さんたいせい)がなければほとんど寺院とわかりません。
平日昼間は園児の声で賑やかで主門は閉められていますが、通用門からお参りはできるようです。
圓舎の並びには「よいこのおじぞうさま」も御座されます。


【写真 上(左)】 よいこのおじぞうさま
【写真 下(右)】 本堂ゾーン
園庭を抜けると本堂前、俄然名刹の趣がでてきます。
本堂向かって右手が庫裏で、その前に傳教大師童像と辨財天碑が置かれています。


【写真 上(左)】 傳教大師童像
【写真 下(右)】 辨財天碑


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝。
コンクリ身舎ながら整った寺院建築で、向拝にはしっかり水引虹梁、雲形の木鼻、繋ぎ虹梁、蟇股を備え、向拝見上げには寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 横からの向拝


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 辨財天のお姿
本堂は通常は閉扉のようですが、お正月期間の七福神ご開扉期間は開扉されます。
辨財天は八臂坐像のお姿です。


【写真 上(左)】 長命水
【写真 下(右)】 長命水石文
本堂向かって左手の隅田川寄りの一角が文化財の宝庫。
本堂すぐよこには長命水と長命水石文。
芭蕉の「いざさらば」句碑、橘守部の墓、太田蜀山人の歌碑、鶴沢清六の塚と成島柳北の碑などがこのエリアに点在します。

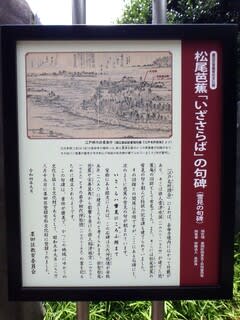
【写真 上(左)】 芭蕉の「いざさらば」句碑
【写真 下(右)】 同 説明板


【写真 上(左)】 橘守部の墓
【写真 下(右)】 太田蜀山人の歌碑


【写真 上(左)】 鶴沢清六の塚と成島柳北の碑
【写真 下(右)】 庚申地蔵尊
万治二年(1659年)造立の庚申地蔵尊石像も御座し、「出羽三山の碑」は墨田区登録文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 出羽三山の碑
【写真 下(右)】 隅田川側からの入口
御朱印は庫裏にて拝受しました。
複数の御朱印を快く授与いただけました。
〔 長命寺の御朱印 〕

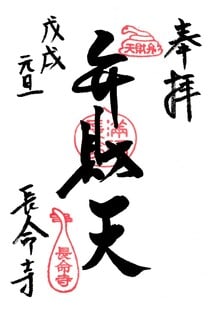
【写真 上(左)】 御本尊・阿弥陀如来の御朱印
【写真 下(右)】 辨財天の御朱印
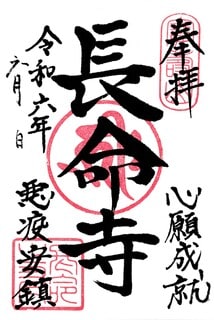
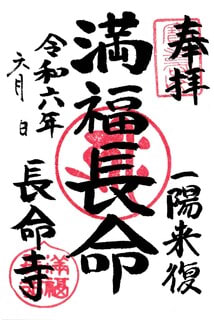
【写真 上(左)】 寺号の御朱印
【写真 下(右)】 同
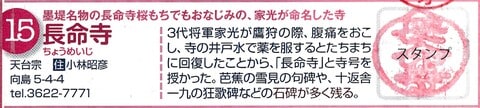
■ 墨田区お寺めぐり第15番のスタンプ
■ 第19番 清滝山 金長院 正王寺
(しょうおうじ)
葛飾区堀切5-29-14
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:
司元別当:(下千葉村)八王子権現社(現・葛飾氷川神社の境内社)/(下千葉村)氷川社(現・葛飾氷川神社)
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第59番、荒綾八十八ヶ所霊場第15番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第59番、(京成)東三十三観音霊場)第3番
第19番は葛飾区堀切の正王寺で、朱塗りの山門から「赤門寺」とも呼ばれています。
下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
正王寺は治承二年(1178年)、(下千葉村)八王子権現社(現・葛飾氷川神社の境内社)の別当として法印侔義(正治元年(1199年)寂)が創建という古刹です。
青戸村寶持院末の新義真言宗寺院で、御本尊は阿弥陀如来です。
『葛飾区寺院調査報告』記載の『清滝山正王寺八王子宮神縁起』によると、源頼朝公は山王廿一社のうち八王子権現を深く尊信し、関西よりこの地に勧請、御鎮座といいます。
天文七年(1538年)、国府台合戦(後北条氏と里見氏など房総諸将との戦い)の戦火を受け荒廃しましたが、慶長年間(1596-1615年)に山城国の法印源榮(承応元年(1652年)寂)が中興して開山と伝わります。
慶安年間(1648-1652年)、徳川3代将軍家光公が鷹狩の際に八王子権現社を拝せられ、当社の由緒を尋ねられたところ源頼朝公の勧請であることを知り、大いに尊崇されて荘園を寄附したといいます。
家光公の来山(1648-1652年)と法印源榮(承応元年(1652年)寂)の年代が重なるので、おそらく家光公から荘園を賜ったのが法印源榮で、その功績により中興開山になったとみられます。
また、当山の住僧は、徳川四天王のひとり本多忠勝ゆかりの家系ともいいます。
八王子権現社は徳川家綱公の代、慶安二年(1649年)にも御朱印をくだされています。
数度にわたる水禍で古記録を失い由緒は不詳ですが、『葛飾区寺院調査報告』には本堂、山門、客殿、庫裏を備え、御本尊に室町時代の作とみられる阿弥陀如来立像、不動明王立像、聖観世音菩薩立像、弘法興教両大師像、弘法大師坐像などの寺宝を安するとあります。
うち、聖観世音菩薩立像は(京成)東三十三観音霊場)第3番の札所本尊と思われます。
なお、正王寺は(下千葉村)氷川社(現・葛飾氷川神社)の別当も務めていました。
葛飾氷川神社境内縁起書によると、氷川社は正治元年(1199年)武蔵国一の宮氷川神社を勧請、下千葉村の鎮守として奉斎とのことです。

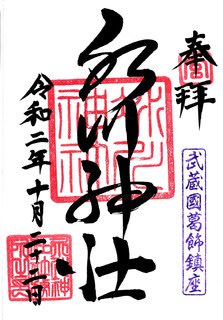
【写真 上(左)】 葛飾氷川神社
【写真 下(右)】 葛飾氷川神社の御朱印
八王子神社は現在、葛飾氷川神社の境内末社ですが(大正年間氷川神社へ勧請)、頼朝公ゆかりの由緒もあってか末社らしからぬ存在感を放たれ、御朱印も授与されています。

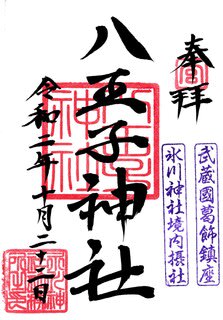
【写真 上(左)】 八王子神社
【写真 下(右)】 八王子神社の御朱印
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻三』(国立国会図書館)
(下千葉村)八王子社 別当正王寺
新義真言宗 青戸村寶持院末 清龍山金長院ト号ス
開山俊義正治元年三月十四日寂ス 中興源榮承応元年九月十六日寂セリ 本尊彌陀
■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
(千葉村)八王子権現社 別当正王寺
八王子権現社
下千葉の内、西南の方にあり、勧請の年歴詳ならず。
別当正王寺
清龍山金長院と号す。新義真言宗、青戸村寶持院の末なり。
開基は俊義法印にて、此人正治元年三月十四日寂すといへば、古き草創なる事知らる。
中興を源榮法印と云、承応元年九月十六日化す、客殿八間に六間、本尊阿彌陀如来を安置す。
氷川社
同じ邊にあり、正王寺持。
■ 『葛飾区寺院調査報告 上』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
正王寺
治承二年(1178年)五月、法印俊義の開山と伝えられる。
天文七年(1538年)国府台の合戦による兵火に焼失して荒廃したが、慶長年間(1596-1614年)山城国の人法印源栄が再興し、中興開基となった。
その後数回にわたる水禍のため古記録を失い、由緒は明らかでないが、当寺がもと別当職を勤めた八王子社(隣接する現氷川神社)の縁起には、次のように記されている。
清滝山正王寺八王子宮神縁起
武蔵国葛飾郡下千葉村清滝山正王寺は、治承二年(1178年)の創建(中略)人皇八十二代後鳥羽院の御宇、右大将頼朝卿、山王廿一社の内なる八王子権現を深く尊信なし給ひ、坂西より此地に移し、当寺に鎮座し奉り(中略)慶安年間(1648-1652年)、三代将軍家光公御鷹狩の刻、境内を通らせられ、八王子の宮を拝せられ、神録を御訊問ありしに、征夷大将軍の始祖たる源右幕下の勧請たりし事を聞召され、恭も五石の荘園を寄附し給ふ。
当寺の住僧は、山城国の産にして、将軍の親臣本多図書忠勝候の紙支層なり。
なお当寺の山門は朱色のため、一般に赤門寺と呼んでいる。
本堂 山門 客殿・庫裏
寺宝
阿彌陀如来立像(本尊) 寄木造 蓮華座 室町時代の作か
不動明王立像 寄木造 両童子 江戸時代の作
聖観世音菩薩立像 寄木造 江戸時代の作
弘法興教両大師像 寄木造 椅子に座し 江戸時代の作
天部坐像 江戸時代の作
弘法大師坐像 椅子に座す 江戸時代の作であろう
紙本着色弥勒菩薩造 江戸時代の作
正岡子規遺墨二点
-------------------------
最寄りは京成本線「堀切菖蒲園」駅で徒歩約5分。
下町らしい住宅密集地に、切妻屋根桟瓦葺の朱塗りの四脚門で山号扁額を掲げ、門前には寺号標を置いています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標

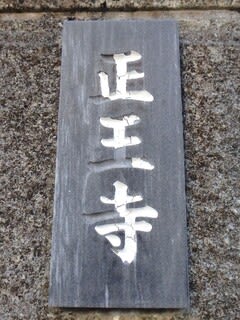
【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 寺号表札
門前からすでに古刹らしい落ち着きをみせていますが、山内もよく整備されきもちのよい参拝ができます。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂
階段上の本堂は、入母屋造桟瓦葺流れ向拝の堂々たる構え。
堂前の十三重石塔がいいアクセントとなっています。
天水鉢には家光公とのゆかりを示すがごとく、葵紋が刻まれています。


【写真 上(左)】 天水鉢
【写真 下(右)】 向拝
コンクリ身舎の近代建築ですが、水引虹梁、雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に虹梁、中備に蟇股と寺社建築に則った意匠で、向拝見上には寺号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 庭園
山内に大師堂があります。
切妻造桟瓦葺妻入りで、柱には「弘法大師堂」の堂号と「南無大師遍照金剛」の御寶号が掲げられています。

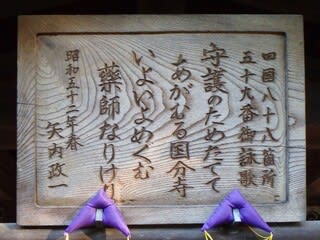
【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂札所板
見上げに掲げられた札所板には「四国八十八箇所五十九番」の御詠歌が掲げられており、荒川辺八十八ヶ所霊場第59番あるいは南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第59番の札所ですが、荒綾八十八ヶ所霊場第15番の札所も兼ねているかと思われます。
薬師如来を称える御詠歌で、本四国八十八ヶ所霊場第59番札所の金光山 国分寺(札所本尊:薬師如来)を示す内容かと思います。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
〔 天王寺の御朱印 〕
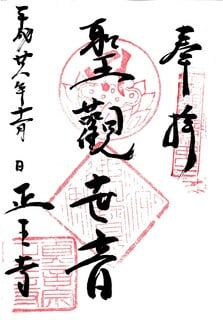
中央に「聖観世音」の揮毫と、聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右の札所印は不明瞭ですが「東観音第三番」とも読めるので、(京成)東三十三観音霊場第3番の札所印かもしれません。
左には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第20番 榎木山 善福院
(ぜんぷくいん)
葛飾区四つ木3-4-29
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:
司元別当:(若宮村)若宮八幡社(現・若宮八幡宮)(葛飾区四つ木)
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第67番、荒綾八十八ヶ所霊場第25番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第43番、葛西三十三観音霊場第15番、新葛西三十三観音霊場第15番
第20番は墨田区四つ木の善福院です。
下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
善福院は、(若宮村)若宮八幡社の別当で新義真言宗、寺嶋村蓮花寺の末でした。
善福院じたいは永正十六年(1519年)祐誉法印が東照宮若王寺と号して創建とも伝わりますが、若宮八幡社の社歴はそれよりも古いので、こちらから追ってみます。
文治五年(1189年)7月源頼朝公は奥州征伐を決意、伊豆山走湯権現の僧侶で頼朝公の師僧ともいわれる専光坊良暹を伊豆山から呼び戻し、留守中の安寧維持と戦勝祈願を託しました。
自身も奥州発向の折、若宮八幡社に参詣し源家の武運長久を祈りました。
その際、手みずから榎の枝根を逆に地に挿して宣うに、この度の戦に利あればこの榎は根付いて繁るべしと。
奥州を収めて凱陣なったとき、この榎は見事に根付いて盛んに繁っていたため、頼朝公は改めて鶴岡八幡宮を勧請し、この地の領主・葛西三郎清重に命じて社容を整えたといいます。
『新編武蔵風土記稿』には「ヨリテ別当寺ヲ榎木山ト号スト云(中略)年歴テ再建修理等中絶シ空ク狐狸ノ住家トナリシヲ 御入國ノ後伊奈備前守中興スト云」とあるので、流れからすると、善福院は源頼朝公の治世にすでに若宮八幡社の別当として存在し、永正十六年(1519年)祐誉法印が東照宮若王寺と号して創建(中興)したとみられます。
天正十八年(1590年)、家康公関東入国後の関東郡代伊奈備前守による若宮八幡社中興の際に、別当の当山も整備されたとみられます。
元和二年(1616年)4月、家康公は薨去し、同年12月に久能山に東照社(現・久能山東照宮)が創建されました。
当時、「東照宮若王寺」を号していた当山は、東照宮の神号をはばかり善福院と改め寺号は唱えなくなったといいます。
御本尊は『新編武蔵風土記稿』で薬師如来、『葛西志』で大日如来、『葛飾区寺院調査報告』で聖観世音菩薩とありますが、拝受した御朱印の尊格は十一面観世音菩薩でした。
また、『新編武蔵風土記稿』には「観音堂 正観音ヲ安ス 葛西三十三番札所第十五番ナリ」とあり、こちらは葛西三十三観音霊場第15番であったことがわかります。
(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
なお、現在も再編された新葛西三十三観音霊場の第15番札所です。
末社として稲荷社が御鎮座と伝わります。
若宮八幡宮は若宮村の鎮守で、別当であった当山は明治初期の神仏分離を乗り越え存続しました。
しかし大正元年、荒川放水路の開削により現在地に移転しています。
関東大震災や幾度の水難を経て、現本堂は昭和44年の落慶です。
比較的情報の少ない寺院ですが、『ガイド』には寺嶋村蓮花寺末から京都智積院末に変更とあるので、相応の寺格を有するとみられ、当地のおもだった霊場の札所を兼務しています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻二』(国立国会図書館)
(若宮村)若宮八幡社 別当善福院
新義真言宗寺嶋村蓮花寺末 榎木山ト号ス
昔ハ東照院若王寺ト称セシヲ 御神号ヲ避テ今ノ如ク善福院ト改メ寺号ハ唱ヘズ云
本尊薬師
観音堂 正観音ヲ安ス 葛西三十三番札所第十五番ナリ
(若宮村)若宮八幡社
村ノ鎮守ナリ
相伝フ当社ハ右大将頼朝文治五年泰衡征伐トシテ奥州ニ発向ノ時 軍功アランコトヲ祈願シ手ツカラ榎ノ策ヲサカシマニ挿 此行利アランニハ此木必生ヒ榮フヘシト誓ヒシニ 果シテ勝利ノ後枝葉盛ニ生ヒ茂リ今ノ世マテモ社頭ニ残レリ ヨリテ別当寺ヲ榎木山ト号スト云(中略)年歴テ再建修理等中絶シ空ク狐狸ノ住家トナリシヲ 御入國ノ後伊奈備前守中興スト云(中略)
末社稲荷社
■ 『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館)
若宮八幡宮
若宮村にあり 別当ハ真言宗にして善福寺と号す
社伝云往古文治五年七月右大将源頼朝卿 奥州泰衡征伐として発向あるにより同十八日伊豆國より専光坊の阿闍梨を召て潜に泰衡征伐の立願の旨を告らす(中略)当社に参詣ありて源家繁盛武運長久の祈念あり
又手自榎の策を逆に地に指誓て云く 此度の軍利あらハ枝根を生して栄ゆへしと●
竟に奥州ををさめて凱陣あら●●ハ 其後鶴岡八幡宮を勧請し此地ハ葛西三郎清重乃領地たるにより清重に命じて社頭を経営せしめ(以下略)
■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
(若宮村)若宮八幡社 別当 善福院
(若宮八幡社)の側に住居す。新義真言宗、寺島村蓮華寺末 榎木山若王寺と号す。
古は東照院号せしが、後に東照宮の御神号を避て、今の寺山号に改められしと云。
本尊大日如来を安置す。
■ 『葛飾区寺院調査報告 上』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
善福院
真言宗智山派。榎木山と号し、古くは寺島村蓮華寺の末、後には京都智積院の末であった。
永正十六年(1519年)祐誉法印の創立。はじめ東照宮若王寺と号したが、徳川家康公の神号をはばかり、善福院と改めたという。明治維新前までは付近の若宮村若宮八幡宮の別当職を勤めた。大正元年、荒川放水路開削工事のため、現在地に移転した。大正十二年九月の関東大震災で本堂が大破し、昭和九年、火災に焼失し、同十二年再建、さらに同二十二年九月の水害で破損し、同四十四年四月、現在の本堂が新築された。
本堂 客殿・庫裏 大師堂
寺宝
聖観世音菩薩立像(本尊) 寄木造蓮華座 江戸時代の作
弘法大師立像 寄木造 江戸時代の作か
興教大師坐像 寄木造 近時の補修か
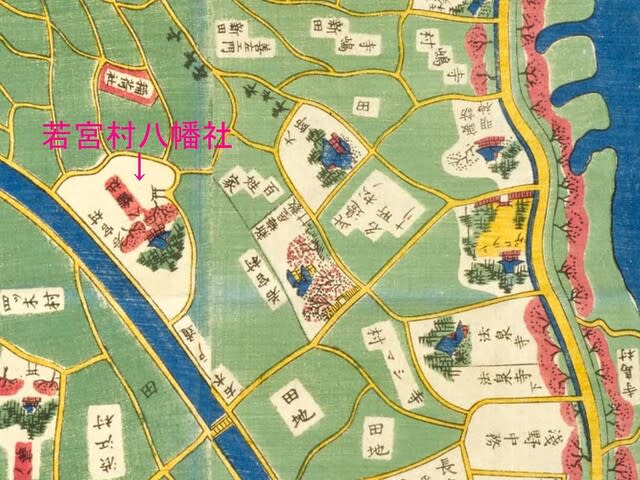
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』隅田川向島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは京成押上線「四ツ木」駅で徒歩約11分。
隅田川河畔の四つ木三丁目の住宅密集地にあります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 院号標
築地塀の中央に切妻屋根桟瓦葺の山門、様式はおそらく薬医門かと思いますが写真が少なく確定できません。
門柱に院号標。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 天水鉢
山内は広くはないものの、手前右に大師堂、正面おくに本堂を配して、立体感ある伽藍構成です。
本堂前の天水鉢には真言宗智山派の宗紋・桔梗紋。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造でおそらく銅本棒葺と思われ流れ向拝。
大棟、降り棟、隅棟、掛瓦も整って端正な印象。
身舎に設えられた縦長の花頭窓がいいアクセントになっています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股を置き、向拝見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 大師堂
大師堂は銅板葺の宝形造で基盤上に宝珠を置いています。
こちらも格子文様が効果的につかわれてきっちり端正なイメージ。
向拝見上げに「大師堂」濃醇扁額、向拝扉には真如親王様のお大師さまが描かれた立派な千社札が打たれています。


【写真 上(左)】 大師堂の千社札
【写真 下(右)】 大師堂の扁額
当山は荒川辺、荒綾、南葛(いろは大師)、隅田川の4つの弘法大師霊場の札所で、おそらくこちらの大師堂が霊場拝所とみられます。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
〔 善福院の御朱印 〕
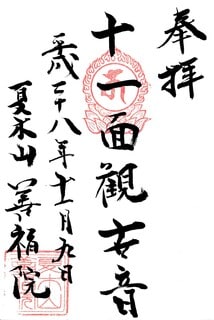
中央に「十一面観世音」の揮毫と、十一面観世音菩薩のお種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左には山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
→ ■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-8へつづきます。
※札所および記事リストは→ こちら。
【 BGM 】
■ 言い出しかねて -TRY TO SAY- 当山ひとみ
■ By the side of love - 今井優子
■ ebb and flow - LaLa(歌ってみた)
※札所および記事リストは→ こちら。
『荒川辺八十八ヵ所と隅田川二十一ヵ所霊場案内』(新田昭江氏著/1991年)を『ガイド』と略記し、適宜引用させていただきます。
■ 第18番 宝寿山 遍照院 長命寺
(ちょうめいじ)
公式Web
天台宗東京教区公式Web
墨田区向島5-4-4
天台宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:
司元別当:
他札所:隅田川七福神(弁財天)、東京三十三所観世音霊場第32番、弁財天百社参り番外22、墨田区お寺めぐり第15番
第18番は墨田区向島の長命寺、比叡山延暦寺直末とみられる名刹です。
公式Web、天台宗東京教区公式Web、下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
長命寺の創建年代等は詳らかでないですが、寺伝には「元和元年(1615年)頃の中田某の檀那寺」とあり、「長命水石文」によると古くは寶寿山常泉寺と号した天台宗寺院でした。
一説には慶長年間(1596-1615年)に孝徳または宗泉によって創立ともあります。
中興開山は誓院権僧正玄照和尚(寶暦十三年(1763年)寂)。
御本尊は『新編武蔵風土記稿』『墨田区史』には阿弥陀如来、『江戸名所図会』には釋迦如来と記され、公式Web、天台宗東京教区公式Webでは阿弥陀如来となっています。
寛永年間(1624-1643年)のある日、三代将軍家光公(大猶院殿)がこの地に鷹狩に訪れた際、にわかに腹痛をおこして当寺で休憩、住職・孝徳(専海とも)和尚が傳教大師御作と伝わる当山の辨財天に加持した庭の井水・般若水を捧げ、この水で薬を服用したところ痛みはたちまち収まったので、家光公はこの水に「長命水」の名を賜い、これより寺号を長命寺と改めたといいます。
山内には長命水がいまもその姿を残しています。
(なお、『紫の一本』『墨水消夏録』は、これを徳川家康公の事跡としています。)
山内の精大明神社は「蹴鞠ノ神」と言い伝えられましたが、祭神等は定かではないようです。
般若堂と不動堂は相殿で、安する不動尊像は智證大師の御作といいます。
『新編武蔵風土記稿』によると、傳教大師御作の辨財天と元三大師降魔像も相殿だったようです。
地蔵堂は『葛西志』に「西國二十二番観音の寫を相殿とす」とあるので西國写観音霊場第22番札所であった模様ですが、この観音霊場については不明です。
当山は関東大震災の慰霊のため開創という東京三十三ヶ所観音霊場第32番の札所ですが、前身としてこの観音霊場の存在があったのかもしれません。
(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
こちらの辨天様は有名で、隅田川七福神の一尊であっただけでなく、弁財天百社参り番外22の札所本尊にもなっています。

『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館より、筆者にて加筆加工)
古くは山内に弁天堂や芭蕉堂がありました。
芭蕉堂は宝暦年間(1751-1764年)に俳人衹徳が建てた自在庵を創始とし、後に能阿により再興、芭蕉の木像を安置して芭蕉堂と称されていました。
『本所区史』には、芭蕉像を安したのは芭蕉の門人・青流(稲津祇空/1663-1733年)の門人で浅草蔵前の札差であった自在庵祇徳で、享保年間(1716-1736年)のこととあります。
しかし、『江戸名所図会』には「自在庵𦾔址 堂の右竹藪の中にあり 誹諧師水國ここに庵室をむすひて住たりしといへり」とあり、現地掲示にも芭蕉庵を建てたのは俳人雲津水国(1682-1734年)とあります。
山内に建つ、松尾芭蕉の「いざさらばの句碑」(区登録文化財)。
「いさゝらは 雪見にころふ 所まて」
これは芭蕉が熱田神宮参詣の際に『笈の小文』に詠んだ句ですが、長命寺が墨堤の雪景色の名所として知られていたため、山内に句碑が置かれたとされています。
現地掲示には「いざさらばの句碑」を建てたのは三代仲祇徳で、安政五年(1858年)とあります。
よって、芭蕉堂は俳人雲津水国(1682-1734年)が建て、「いざさらばの句碑」を建てたのは三代仲祇徳ということになります。
ただし、仲祇徳は少なくとも三代(三人)はいるようなので、このあたりの時系列はよくわかりません。
筆者は俳諧の道にはまったくうとく、下手に書き込むとたちまち馬脚を露わすので(笑)、このくらいにしておきます。
なお、『江戸名所図会』で長命寺のすぐ横に「本社」と描かれているお社はおそらく牛御前社(現・牛嶋神社)と思われます。
いかにも本社と別当を示す位置関係ですが、牛御前社の別当は東駒形の第7番札所の牛宝山 最勝寺で、最勝寺は大正2年江戸川区平井に移転しています。
本堂は安政二年(1855年)の大地震で焼失、麻布の武家屋敷を移築して本堂とし明治に及んだといいます。
関東大震災で本堂、芭蕉堂など多くの伽藍を失いましたが、御本尊は難を遁れていまも本堂に御座します。
長命寺は雪景色の美しさでも知られ、『江戸名所花暦』にも「長命寺隅田川の堤曲行の角にあり。境内に芭蕉の碑あり。この辺に佇みて左右をかへり見れば、雪の景色いはんかたなし。」と記されています。
もとより向島は風流の地として知られ、雪景色や芭蕉堂の存在もあって、長命寺には多くの文人墨客が訪れたとみられます。
寺内には芭蕉句碑をはじめ、東京都指定の橘守部(江戸時代の国学者)の墓、義太夫節の名家鶴沢清六の塚、太田蜀山人の歌碑、成島柳北(明治時代のジャーナリスト)の碑などがあり、いまもエリア屈指の文化財のお寺として知られています。
※山内の文化財については→ 公式Webをご覧ください。
【長命寺桜もち】
「桜餅 食ふてぬけけり 長命寺」 (虚子)
長命寺桜もちはこの向島屈指の銘菓です。
享保二年(1717年)、創業者山本新六が墨堤土手の桜の葉を樽の中に塩漬けにした「桜もち」を考案して長命寺門前で売り始め、参詣客や桜の名所・隅堤の花見客のあいだで評判となりました。
桜葉の香り高い美味しさもさることながら代々の店主の看板娘の接待が評判で、なかでも三代目の長女「お豊さん」は美貌で名を馳せ、猿若町で芝居にも上演されたといいます。
明治の「お陸さん」という娘も美人の誉れ高く、正岡子規が当家の二階に下宿し、子規とお陸さんとの恋物語もあったとか。
「鐘の音に夢さめはてて浅草や 朝の別れのつらくもあるかな」 (子規)
『江戸切絵図』では長命寺の山内に「名物サクラモチ」とあり、よほど人気があったと思われます。
「長命寺桜もち」はなんと長命寺の公式Webでも紹介され、両社の密接な関係を物語っています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻二』(国立国会図書館)
(須崎村)長命寺
天台宗東叡山末 寶寿山扁(ママ)照院ト号ス 本尊阿彌陀脇士ニ観音勢至ヲ置 過去帳ニ住僧宗泉慶安二年(1649年)十一月七日示寂トアリ 境内辨天ノ縁起ニ 寛永(1624-1644年)ノ末大猶院殿御放鷹ノ時 俄ニ御異例ニテ当寺ニ入御アリケルニ 住僧専海辨才天ニ祈願ヲコメ則御手洗ノ般若水ヲ汲ミテ御供ノ士中根壱岐守ヲ以テ捧ケ奉リシニ 御心地サハヤカニナラセタマヒケレハ 御快気ノ程ヲ祝セラレ 寶樹山常泉寺ノ𦾔号ヲ改テ今ノ寺山号ヲ賜ヒシト云 是ニヨレハ専海ハ寛永ノ頃ノ住僧ニシテ宗泉ヨリ先代ナルヘシ
精大明神社
神体金幣ニテ光成卿ノ霊ヲ祭ル 蹴鞠ノ神ナリトノミ云傳フ 光成卿トイヘルハイカナル人ニヤ 蹴鞠ノ宗匠難波飛鳥井両家ニハ聞エサル人ナリ 按ニ諸神記ニ中御門西洞院東頬滋野井小社三座是蹴鞠神也 此地大納言成通卿旧跡トアリ 成通卿ハ蹴鞠ノ名人ニテ凡人ノシワサニアラサル由『著聞集』等ニモ記シタリハ モシクハ是ヲ誤テ光成卿ナト云傳ヘシニヤ 又近江國志賀郡松本ト云地ニ精大明神社アリ 祭礼猿田彦命ニテ蹴鞠ノ神ナリト云 当社ハ恐クハ是ヲウツセシモノニテ光成卿ヲ配祀セルナラン
稲荷社
般若堂 文殊普賢ノ外十六善神ヲ置 又不動及二童子アリ 不動ハ智證大師ノ作又傳教大師ノツクレル辨天元三大師降魔ノ像アリ
地蔵堂
長命水趾 此井ノ水ヲ般若水ト呼フ則前ニ云ル御手洗ノ跡也
奈岐木 菓子所大久保主水カ植シモノナリ 高二丈程周四尺モアルヘシ 樹根ニ此木ヲ植ル顛末ヲ鋳セル碑ヲ立
■ 『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館)
寶寿山長命寺
遍照院と号す 天台宗東叡山に属せり 本尊ハ等身の釋迦如来 脇士ハ文殊普賢 般若十六善神等の像を安す
牛嶋辨財天 同じ堂内に安す 傳教大師の作なり
長命水 同じ堂の後の方にあり 一に般若水と云
自在庵𦾔址 堂の右竹藪の中にあり 誹諧師水國ここに庵室をむすひて住たりしといへり 今其地に芭蕉翁の句を彫たる碑を建てあり
殊更当寺ハ雪の名所にて前に隅田川の流れをうけて風色たらすといふをなし
■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
長命寺
牛御前社の北に隣りて、門は西向きなり、天台宗東叡山末、寶寿山遍照院と号す、寺伝云、当寺古は寶樹山常泉寺と唱へしに、寛永年中(1624-1644年)、大猶院殿此邊御鷹狩に成らせ給ひて、御不例おはしませし時、中根壱岐守当寺の井水を汲て、後手水に奉りしかば、御なやみ頓に御本復あり、よりて寺山号を、今のごとくに改められしと、又紫一本には、これを、東照宮の御事績となし、寺もその比なでは寺号もなく、ただ草庵なりしなど、いとうきなる伝へなれど、何れゆへある寺号とはみヘたり、開山起立の年代詳ならず、中興を弘誓院権僧正玄照和尚と云、寶暦十三年(1763年)四月廿二日寂を示せり、本尊釋迦如来を安置す。
辨天不動相殿 門を入て正面にあり
精大明神社 門を入て右の方にあり、祭神詳ならず。
長命水 辨天堂の側にあり、則前にしるせる、大猶院殿御手水に用ひ給ひしと云井なり。
地蔵堂 門を入て右の方にあり、西國二十二番観音の寫を相殿とす。
■ 『東京名所図会 [第14] (本所区之部)(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
長命寺
長命寺は。向島須崎町八十八番地即ち牛島神社の北隣に在り。寶寿山と号し。遍照院と称す。天台宗にして。延暦寺の末なり。当寺初は常泉寺といひしが。寛永年間(1624-1644年)将軍家家光公放鷹の途次。微恙ありて寺に憩ひ。住持孝徳をして境内の盤石水を加め。服薬して頓に快癒せしを以て。長命水の名を賜ふ。因て是より長命寺と改む。
長命水今尚現存し。洗心養神と刻したる石標の傍に屋代弘賢のしるしたる碑を建たり。(中略)本堂は二十九年焼失後の新築にて。別に盤若堂と芭蕉堂あり。芭蕉堂殊に雅なり。
■ 『本所区史』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
長命寺
長命寺は向島須崎町八十八番地即ち牛島神社の北隣に在り寶壽山と号遍照院と称した。
天台宗にして延暦寺の末である。当寺初は常泉寺といったが寛永年間(1624-1644年)将軍家家光公放鷹の途次微恙の為めに寺に憩ひ、住持孝徳の差出した境内の般若水を以て服薬した処頓に快癒したので長命水の名を賜はった。因て是より長命寺と改めたのである。
長命水は今尚現存し洗心養神と刻した石標の傍に屋代弘賢のしるした碑を建てたとある。
り。(中略)本堂は二十九年焼失後の新築にて。別に盤若堂と芭蕉堂あり。芭蕉堂殊に雅なり。
元禄の昔、芭蕉松尾桃青は西行宗祇の遺風を慕ひ、未だ五七五の野風を楽しとして生涯を過ごしたが、即ち彼芭蕉は誹諧道中興開山といふべきであらう。
芭蕉の門人に青流といふ人が居り、或時宗祇法師の墓参をなしその墓前に於て、既に祇空しとて名を祇空と更め、向島の地に草庵をむすんで居たが、ふと雲水の心動き剃髪して諸国を遊歴し、享保十八年(1733年)四月廿三日享年六十八にして箱根湯本に没し、早雲寺に葬られた。
祇空の門人に自在庵祇徳といふ人があった。この人は浅草蔵前の札差であったが隠遁の志深く、享保年間(1716-1736年)に祇空の庵址近き長命寺中に草庵をしつらへ、庵室に芭蕉翁の像を安置し、三昧の外に他事なかった。これ即ち長命寺芭蕉堂の起原である。
■ 『墨田区史 本編』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
長命寺
天台宗延暦寺の末寺で古くは宝樹山常泉寺と号していたというが、開基者・開山者および創建の年などは明らかではなく、一説には慶長年間(1596-1615年)に孝徳または宗泉によって創立されたとする。
中興開山は誓院権僧正玄照和尚で、本尊は阿弥陀如来を安置する。
長命寺の寺号については、寛永(1624-1644年)のころ三代将軍家光が墨東の地に鷹狩を行った時、急病となってこの寺に立ち寄り寺内の井戸の水で薬を服用してたちまちに快癒したので、寺号常泉寺を改めて長命寺としたと伝えられており、また「紫の一本」や「墨水消夏録」はこれを徳川家康の事跡とし、当寺は名もない小庵であったので長命寺の寺号を与えたのであると述べている。
寺内には長命水が今もその姿を残していて、これが家光の用いた名水とされているが、このほか古くは弁天堂や芭蕉堂もあった。
芭蕉堂は宝暦年中(1751-1764年)に俳人祇徳が建てた自在庵という庵で、のちに能阿によって再興され長命寺芭蕉堂と通称されていたものである。
長命寺はまた雪景色の美しさで江戸名所のひとつに数えられていた。(中略)『江戸名所花暦』にも「長命寺隅田川の堤曲行の角にあり。境内に芭蕉の碑あり。この辺に佇みて左右をかへり見れば、雪の景色いはんかたなし。」と述べられている。
寺内には東京都指定の橘守部の墓、成島柳北の碑があり、また弁財天は隅田川七福神のひとつである。
■ 『すみだの史跡文化財散歩 P.35』(墨田区資料/PDF)
長命寺(向島5-4-4)
天台宗延暦寺末で、古くは宝寿山常泉寺と号していたそうですが、創建年等は不明です。寛永のころ3代将軍家光がこの辺りに臆狩りに来た時、急に腹痛をおこしましたが、住職
が加持した庭の井の水で薬を服用したところ痛みが治まったので、長命寺の寺号を与えたといいます。
■ 松尾芭蕉「いざさらば」の句碑 <区登録文化財>
「いさゝらは 雪見にころふ所まて」
碑陰には、3世自在庵祇徳の文で、芭蕉や祇空、祇徳の略伝等が述べられています。
■ 「長命水石文」の碑
この寺が長命の寺号を賜った経緯と井戸が長命水と名付けられたことを、時の住職最空が記しています。書は国学者の屋代弘賢で、天保3年(1832)の建碑です。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』隅田川向島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営地下鉄浅草線・メトロ半蔵門線「押上駅」駅で徒歩約15分。
隅田川にかかる「桜橋」経由で今戸方面からも歩けます。


【写真 上(左)】 桜橋
【写真 下(右)】 桜橋からの隅田川
第13番弘福寺のすぐお隣りにあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標


【写真 上(左)】 門扉の三諦星紋
【写真 下(右)】 山内幼稚園ゾーン
山内門寄りは言問幼稚園で、山内入口の門柱と寺号標、そして門扉に輝く天台宗の宗紋・三諦星(さんたいせい)がなければほとんど寺院とわかりません。
平日昼間は園児の声で賑やかで主門は閉められていますが、通用門からお参りはできるようです。
圓舎の並びには「よいこのおじぞうさま」も御座されます。


【写真 上(左)】 よいこのおじぞうさま
【写真 下(右)】 本堂ゾーン
園庭を抜けると本堂前、俄然名刹の趣がでてきます。
本堂向かって右手が庫裏で、その前に傳教大師童像と辨財天碑が置かれています。


【写真 上(左)】 傳教大師童像
【写真 下(右)】 辨財天碑


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝。
コンクリ身舎ながら整った寺院建築で、向拝にはしっかり水引虹梁、雲形の木鼻、繋ぎ虹梁、蟇股を備え、向拝見上げには寺号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 横からの向拝


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 辨財天のお姿
本堂は通常は閉扉のようですが、お正月期間の七福神ご開扉期間は開扉されます。
辨財天は八臂坐像のお姿です。


【写真 上(左)】 長命水
【写真 下(右)】 長命水石文
本堂向かって左手の隅田川寄りの一角が文化財の宝庫。
本堂すぐよこには長命水と長命水石文。
芭蕉の「いざさらば」句碑、橘守部の墓、太田蜀山人の歌碑、鶴沢清六の塚と成島柳北の碑などがこのエリアに点在します。

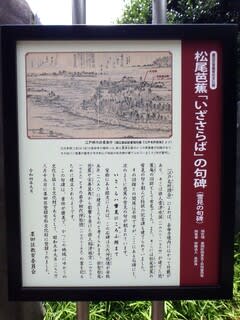
【写真 上(左)】 芭蕉の「いざさらば」句碑
【写真 下(右)】 同 説明板


【写真 上(左)】 橘守部の墓
【写真 下(右)】 太田蜀山人の歌碑


【写真 上(左)】 鶴沢清六の塚と成島柳北の碑
【写真 下(右)】 庚申地蔵尊
万治二年(1659年)造立の庚申地蔵尊石像も御座し、「出羽三山の碑」は墨田区登録文化財に指定されています。


【写真 上(左)】 出羽三山の碑
【写真 下(右)】 隅田川側からの入口
御朱印は庫裏にて拝受しました。
複数の御朱印を快く授与いただけました。
〔 長命寺の御朱印 〕

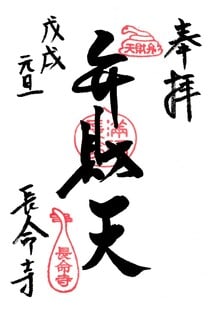
【写真 上(左)】 御本尊・阿弥陀如来の御朱印
【写真 下(右)】 辨財天の御朱印
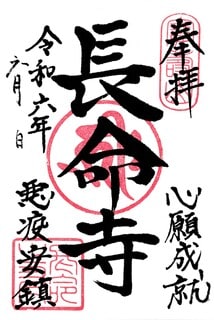
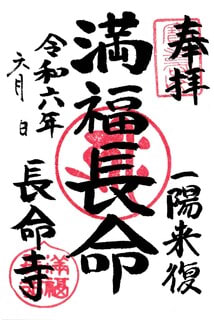
【写真 上(左)】 寺号の御朱印
【写真 下(右)】 同
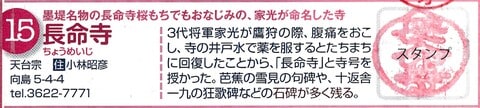
■ 墨田区お寺めぐり第15番のスタンプ
■ 第19番 清滝山 金長院 正王寺
(しょうおうじ)
葛飾区堀切5-29-14
真言宗豊山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:
司元別当:(下千葉村)八王子権現社(現・葛飾氷川神社の境内社)/(下千葉村)氷川社(現・葛飾氷川神社)
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第59番、荒綾八十八ヶ所霊場第15番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第59番、(京成)東三十三観音霊場)第3番
第19番は葛飾区堀切の正王寺で、朱塗りの山門から「赤門寺」とも呼ばれています。
下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
正王寺は治承二年(1178年)、(下千葉村)八王子権現社(現・葛飾氷川神社の境内社)の別当として法印侔義(正治元年(1199年)寂)が創建という古刹です。
青戸村寶持院末の新義真言宗寺院で、御本尊は阿弥陀如来です。
『葛飾区寺院調査報告』記載の『清滝山正王寺八王子宮神縁起』によると、源頼朝公は山王廿一社のうち八王子権現を深く尊信し、関西よりこの地に勧請、御鎮座といいます。
天文七年(1538年)、国府台合戦(後北条氏と里見氏など房総諸将との戦い)の戦火を受け荒廃しましたが、慶長年間(1596-1615年)に山城国の法印源榮(承応元年(1652年)寂)が中興して開山と伝わります。
慶安年間(1648-1652年)、徳川3代将軍家光公が鷹狩の際に八王子権現社を拝せられ、当社の由緒を尋ねられたところ源頼朝公の勧請であることを知り、大いに尊崇されて荘園を寄附したといいます。
家光公の来山(1648-1652年)と法印源榮(承応元年(1652年)寂)の年代が重なるので、おそらく家光公から荘園を賜ったのが法印源榮で、その功績により中興開山になったとみられます。
また、当山の住僧は、徳川四天王のひとり本多忠勝ゆかりの家系ともいいます。
八王子権現社は徳川家綱公の代、慶安二年(1649年)にも御朱印をくだされています。
数度にわたる水禍で古記録を失い由緒は不詳ですが、『葛飾区寺院調査報告』には本堂、山門、客殿、庫裏を備え、御本尊に室町時代の作とみられる阿弥陀如来立像、不動明王立像、聖観世音菩薩立像、弘法興教両大師像、弘法大師坐像などの寺宝を安するとあります。
うち、聖観世音菩薩立像は(京成)東三十三観音霊場)第3番の札所本尊と思われます。
なお、正王寺は(下千葉村)氷川社(現・葛飾氷川神社)の別当も務めていました。
葛飾氷川神社境内縁起書によると、氷川社は正治元年(1199年)武蔵国一の宮氷川神社を勧請、下千葉村の鎮守として奉斎とのことです。

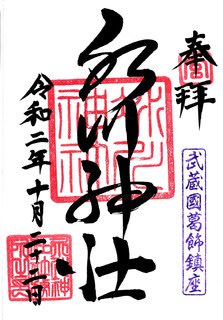
【写真 上(左)】 葛飾氷川神社
【写真 下(右)】 葛飾氷川神社の御朱印
八王子神社は現在、葛飾氷川神社の境内末社ですが(大正年間氷川神社へ勧請)、頼朝公ゆかりの由緒もあってか末社らしからぬ存在感を放たれ、御朱印も授与されています。

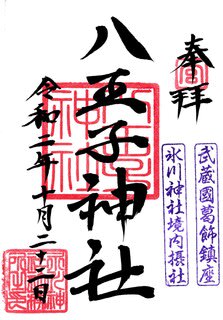
【写真 上(左)】 八王子神社
【写真 下(右)】 八王子神社の御朱印
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻三』(国立国会図書館)
(下千葉村)八王子社 別当正王寺
新義真言宗 青戸村寶持院末 清龍山金長院ト号ス
開山俊義正治元年三月十四日寂ス 中興源榮承応元年九月十六日寂セリ 本尊彌陀
■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
(千葉村)八王子権現社 別当正王寺
八王子権現社
下千葉の内、西南の方にあり、勧請の年歴詳ならず。
別当正王寺
清龍山金長院と号す。新義真言宗、青戸村寶持院の末なり。
開基は俊義法印にて、此人正治元年三月十四日寂すといへば、古き草創なる事知らる。
中興を源榮法印と云、承応元年九月十六日化す、客殿八間に六間、本尊阿彌陀如来を安置す。
氷川社
同じ邊にあり、正王寺持。
■ 『葛飾区寺院調査報告 上』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
正王寺
治承二年(1178年)五月、法印俊義の開山と伝えられる。
天文七年(1538年)国府台の合戦による兵火に焼失して荒廃したが、慶長年間(1596-1614年)山城国の人法印源栄が再興し、中興開基となった。
その後数回にわたる水禍のため古記録を失い、由緒は明らかでないが、当寺がもと別当職を勤めた八王子社(隣接する現氷川神社)の縁起には、次のように記されている。
清滝山正王寺八王子宮神縁起
武蔵国葛飾郡下千葉村清滝山正王寺は、治承二年(1178年)の創建(中略)人皇八十二代後鳥羽院の御宇、右大将頼朝卿、山王廿一社の内なる八王子権現を深く尊信なし給ひ、坂西より此地に移し、当寺に鎮座し奉り(中略)慶安年間(1648-1652年)、三代将軍家光公御鷹狩の刻、境内を通らせられ、八王子の宮を拝せられ、神録を御訊問ありしに、征夷大将軍の始祖たる源右幕下の勧請たりし事を聞召され、恭も五石の荘園を寄附し給ふ。
当寺の住僧は、山城国の産にして、将軍の親臣本多図書忠勝候の紙支層なり。
なお当寺の山門は朱色のため、一般に赤門寺と呼んでいる。
本堂 山門 客殿・庫裏
寺宝
阿彌陀如来立像(本尊) 寄木造 蓮華座 室町時代の作か
不動明王立像 寄木造 両童子 江戸時代の作
聖観世音菩薩立像 寄木造 江戸時代の作
弘法興教両大師像 寄木造 椅子に座し 江戸時代の作
天部坐像 江戸時代の作
弘法大師坐像 椅子に座す 江戸時代の作であろう
紙本着色弥勒菩薩造 江戸時代の作
正岡子規遺墨二点
-------------------------
最寄りは京成本線「堀切菖蒲園」駅で徒歩約5分。
下町らしい住宅密集地に、切妻屋根桟瓦葺の朱塗りの四脚門で山号扁額を掲げ、門前には寺号標を置いています。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 寺号標

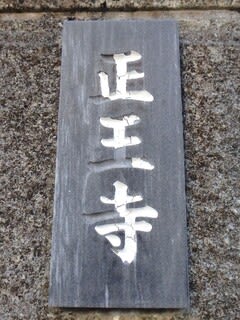
【写真 上(左)】 山門扁額
【写真 下(右)】 寺号表札
門前からすでに古刹らしい落ち着きをみせていますが、山内もよく整備されきもちのよい参拝ができます。


【写真 上(左)】 斜めからの本堂
【写真 下(右)】 本堂
階段上の本堂は、入母屋造桟瓦葺流れ向拝の堂々たる構え。
堂前の十三重石塔がいいアクセントとなっています。
天水鉢には家光公とのゆかりを示すがごとく、葵紋が刻まれています。


【写真 上(左)】 天水鉢
【写真 下(右)】 向拝
コンクリ身舎の近代建築ですが、水引虹梁、雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に虹梁、中備に蟇股と寺社建築に則った意匠で、向拝見上には寺号扁額が掲げられています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 庭園
山内に大師堂があります。
切妻造桟瓦葺妻入りで、柱には「弘法大師堂」の堂号と「南無大師遍照金剛」の御寶号が掲げられています。

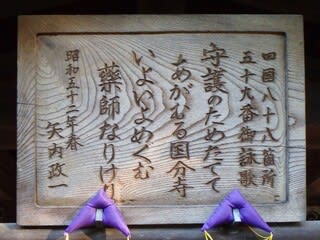
【写真 上(左)】 大師堂
【写真 下(右)】 大師堂札所板
見上げに掲げられた札所板には「四国八十八箇所五十九番」の御詠歌が掲げられており、荒川辺八十八ヶ所霊場第59番あるいは南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第59番の札所ですが、荒綾八十八ヶ所霊場第15番の札所も兼ねているかと思われます。
薬師如来を称える御詠歌で、本四国八十八ヶ所霊場第59番札所の金光山 国分寺(札所本尊:薬師如来)を示す内容かと思います。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
〔 天王寺の御朱印 〕
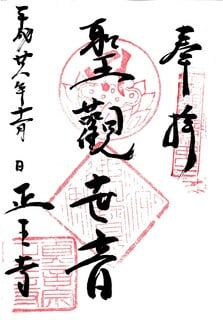
中央に「聖観世音」の揮毫と、聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。
右の札所印は不明瞭ですが「東観音第三番」とも読めるので、(京成)東三十三観音霊場第3番の札所印かもしれません。
左には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
■ 第20番 榎木山 善福院
(ぜんぷくいん)
葛飾区四つ木3-4-29
真言宗智山派
御本尊:聖観世音菩薩
札所本尊:
司元別当:(若宮村)若宮八幡社(現・若宮八幡宮)(葛飾区四つ木)
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第67番、荒綾八十八ヶ所霊場第25番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第43番、葛西三十三観音霊場第15番、新葛西三十三観音霊場第15番
第20番は墨田区四つ木の善福院です。
下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
善福院は、(若宮村)若宮八幡社の別当で新義真言宗、寺嶋村蓮花寺の末でした。
善福院じたいは永正十六年(1519年)祐誉法印が東照宮若王寺と号して創建とも伝わりますが、若宮八幡社の社歴はそれよりも古いので、こちらから追ってみます。
文治五年(1189年)7月源頼朝公は奥州征伐を決意、伊豆山走湯権現の僧侶で頼朝公の師僧ともいわれる専光坊良暹を伊豆山から呼び戻し、留守中の安寧維持と戦勝祈願を託しました。
自身も奥州発向の折、若宮八幡社に参詣し源家の武運長久を祈りました。
その際、手みずから榎の枝根を逆に地に挿して宣うに、この度の戦に利あればこの榎は根付いて繁るべしと。
奥州を収めて凱陣なったとき、この榎は見事に根付いて盛んに繁っていたため、頼朝公は改めて鶴岡八幡宮を勧請し、この地の領主・葛西三郎清重に命じて社容を整えたといいます。
『新編武蔵風土記稿』には「ヨリテ別当寺ヲ榎木山ト号スト云(中略)年歴テ再建修理等中絶シ空ク狐狸ノ住家トナリシヲ 御入國ノ後伊奈備前守中興スト云」とあるので、流れからすると、善福院は源頼朝公の治世にすでに若宮八幡社の別当として存在し、永正十六年(1519年)祐誉法印が東照宮若王寺と号して創建(中興)したとみられます。
天正十八年(1590年)、家康公関東入国後の関東郡代伊奈備前守による若宮八幡社中興の際に、別当の当山も整備されたとみられます。
元和二年(1616年)4月、家康公は薨去し、同年12月に久能山に東照社(現・久能山東照宮)が創建されました。
当時、「東照宮若王寺」を号していた当山は、東照宮の神号をはばかり善福院と改め寺号は唱えなくなったといいます。
御本尊は『新編武蔵風土記稿』で薬師如来、『葛西志』で大日如来、『葛飾区寺院調査報告』で聖観世音菩薩とありますが、拝受した御朱印の尊格は十一面観世音菩薩でした。
また、『新編武蔵風土記稿』には「観音堂 正観音ヲ安ス 葛西三十三番札所第十五番ナリ」とあり、こちらは葛西三十三観音霊場第15番であったことがわかります。
(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
なお、現在も再編された新葛西三十三観音霊場の第15番札所です。
末社として稲荷社が御鎮座と伝わります。
若宮八幡宮は若宮村の鎮守で、別当であった当山は明治初期の神仏分離を乗り越え存続しました。
しかし大正元年、荒川放水路の開削により現在地に移転しています。
関東大震災や幾度の水難を経て、現本堂は昭和44年の落慶です。
比較的情報の少ない寺院ですが、『ガイド』には寺嶋村蓮花寺末から京都智積院末に変更とあるので、相応の寺格を有するとみられ、当地のおもだった霊場の札所を兼務しています。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻二』(国立国会図書館)
(若宮村)若宮八幡社 別当善福院
新義真言宗寺嶋村蓮花寺末 榎木山ト号ス
昔ハ東照院若王寺ト称セシヲ 御神号ヲ避テ今ノ如ク善福院ト改メ寺号ハ唱ヘズ云
本尊薬師
観音堂 正観音ヲ安ス 葛西三十三番札所第十五番ナリ
(若宮村)若宮八幡社
村ノ鎮守ナリ
相伝フ当社ハ右大将頼朝文治五年泰衡征伐トシテ奥州ニ発向ノ時 軍功アランコトヲ祈願シ手ツカラ榎ノ策ヲサカシマニ挿 此行利アランニハ此木必生ヒ榮フヘシト誓ヒシニ 果シテ勝利ノ後枝葉盛ニ生ヒ茂リ今ノ世マテモ社頭ニ残レリ ヨリテ別当寺ヲ榎木山ト号スト云(中略)年歴テ再建修理等中絶シ空ク狐狸ノ住家トナリシヲ 御入國ノ後伊奈備前守中興スト云(中略)
末社稲荷社
■ 『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館)
若宮八幡宮
若宮村にあり 別当ハ真言宗にして善福寺と号す
社伝云往古文治五年七月右大将源頼朝卿 奥州泰衡征伐として発向あるにより同十八日伊豆國より専光坊の阿闍梨を召て潜に泰衡征伐の立願の旨を告らす(中略)当社に参詣ありて源家繁盛武運長久の祈念あり
又手自榎の策を逆に地に指誓て云く 此度の軍利あらハ枝根を生して栄ゆへしと●
竟に奥州ををさめて凱陣あら●●ハ 其後鶴岡八幡宮を勧請し此地ハ葛西三郎清重乃領地たるにより清重に命じて社頭を経営せしめ(以下略)
■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
(若宮村)若宮八幡社 別当 善福院
(若宮八幡社)の側に住居す。新義真言宗、寺島村蓮華寺末 榎木山若王寺と号す。
古は東照院号せしが、後に東照宮の御神号を避て、今の寺山号に改められしと云。
本尊大日如来を安置す。
■ 『葛飾区寺院調査報告 上』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
善福院
真言宗智山派。榎木山と号し、古くは寺島村蓮華寺の末、後には京都智積院の末であった。
永正十六年(1519年)祐誉法印の創立。はじめ東照宮若王寺と号したが、徳川家康公の神号をはばかり、善福院と改めたという。明治維新前までは付近の若宮村若宮八幡宮の別当職を勤めた。大正元年、荒川放水路開削工事のため、現在地に移転した。大正十二年九月の関東大震災で本堂が大破し、昭和九年、火災に焼失し、同十二年再建、さらに同二十二年九月の水害で破損し、同四十四年四月、現在の本堂が新築された。
本堂 客殿・庫裏 大師堂
寺宝
聖観世音菩薩立像(本尊) 寄木造蓮華座 江戸時代の作
弘法大師立像 寄木造 江戸時代の作か
興教大師坐像 寄木造 近時の補修か
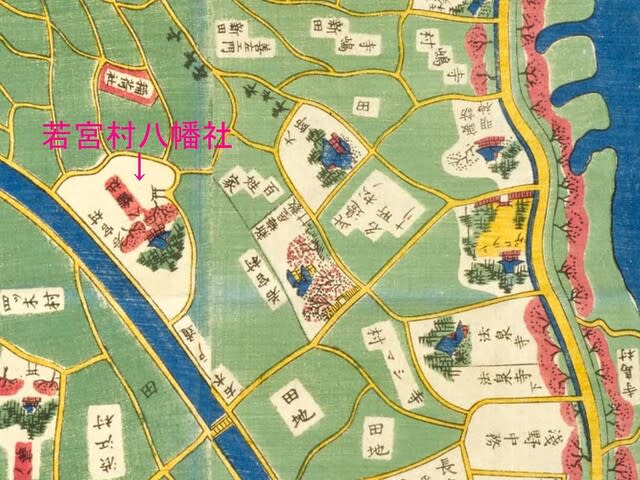
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』隅田川向島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは京成押上線「四ツ木」駅で徒歩約11分。
隅田川河畔の四つ木三丁目の住宅密集地にあります。


【写真 上(左)】 山門
【写真 下(右)】 院号標
築地塀の中央に切妻屋根桟瓦葺の山門、様式はおそらく薬医門かと思いますが写真が少なく確定できません。
門柱に院号標。


【写真 上(左)】 山内
【写真 下(右)】 天水鉢
山内は広くはないものの、手前右に大師堂、正面おくに本堂を配して、立体感ある伽藍構成です。
本堂前の天水鉢には真言宗智山派の宗紋・桔梗紋。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 向拝
本堂は入母屋造でおそらく銅本棒葺と思われ流れ向拝。
大棟、降り棟、隅棟、掛瓦も整って端正な印象。
身舎に設えられた縦長の花頭窓がいいアクセントになっています。
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股を置き、向拝見上げには山号扁額を掲げています。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 大師堂
大師堂は銅板葺の宝形造で基盤上に宝珠を置いています。
こちらも格子文様が効果的につかわれてきっちり端正なイメージ。
向拝見上げに「大師堂」濃醇扁額、向拝扉には真如親王様のお大師さまが描かれた立派な千社札が打たれています。


【写真 上(左)】 大師堂の千社札
【写真 下(右)】 大師堂の扁額
当山は荒川辺、荒綾、南葛(いろは大師)、隅田川の4つの弘法大師霊場の札所で、おそらくこちらの大師堂が霊場拝所とみられます。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
〔 善福院の御朱印 〕
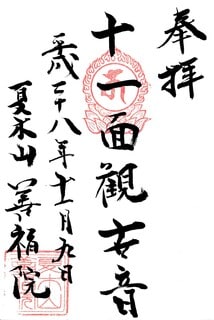
中央に「十一面観世音」の揮毫と、十一面観世音菩薩のお種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左には山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。
→ ■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-8へつづきます。
※札所および記事リストは→ こちら。
【 BGM 】
■ 言い出しかねて -TRY TO SAY- 当山ひとみ
■ By the side of love - 今井優子
■ ebb and flow - LaLa(歌ってみた)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-6
■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-5からのつづきです。
※札所および記事リストは→ こちら。
『荒川辺八十八ヵ所と隅田川二十一ヵ所霊場案内』(新田昭江氏著/1991年)を『ガイド』と略記し、適宜引用させていただきます。
■ 第15番 金剛山(常在山) 寶蔵寺
(ほうぞうじ)
墨田区八広6-9-17
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:
司元別当:(木下村)山王社
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第68番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第75番、新葛西三十三観音霊場第12番(旧・法花寺)、墨田区お寺めぐり第10番
第15番は墨田区八広の寶蔵寺です。
下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
寶蔵寺は慶長十九年(1614年)に朝応和尚が創建した真言宗寺院で寺島蓮花寺の末寺でした。(『ガイド』では安永年間(1772-1780年)創立)
御本尊は阿弥陀如来。客殿に不動明王を安していたようです。
境内に祀る稲荷社は、おそらく鎮守とみられ、『葛西志』にも境内社として記載されています。
山号を「常在山」としている資料もありますが、『新編武蔵風土記稿』『葛西志』などでは「金剛山」としています。
もとは南葛西郡大木村字木下にありましたが明治43年の出水に遭い、さらに荒川放水路開設のために大正8年、西方に約550mほどの現在地に移転しています。
江戸時代は木下村の山王社(慶長十九年(1614年)御鎮座)の別当を務めていました。
情報があまりない寺院ですが、荒川辺霊場、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)などの札所となっているので、真言密寺として相応のポジションを担っていたことがわかります。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻三』(国立国会図書館)
(木下村)寶蔵寺
新義真言宗 寺嶋村蓮華寺末 金剛山ト号ス 本尊ハ不動ナリ
(木下村)山王社
慶長十九年(1614年)ノ鎮座ナリ 寶蔵寺持下同シ
稲荷社
■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
(木之下村)寶蔵寺
山王社と同じ邊にあり。当寺も慶長十九年(1614年)の起立なりと云、新義真言宗、寺島村蓮華寺末、金剛山と号す。
本尊不動尊 客殿に安す。
稲荷社 境内にあり。
(木之下村)山王社
村の南へよりてあり、慶長十九年(1614年)の鎮座と云、寶蔵寺持。
■ 『墨田区史 本編』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
宝蔵寺(金剛山 吾嬬町西九丁目10番地)
慶長十九年(1614年)に朝応和尚が創建した寺院で新義真言宗に属し、寺島蓮花寺の末寺である。
もと南葛飾郡大木村字木下に所在し、その後明治四十三年の出水にあい、さらに荒川放水路開設のために西方約五五0mほどの現在地に大正八年に移転した。
本尊は阿弥陀如来である。
-------------------------
最寄りは京成押上線「八広」駅で徒歩約3分。
荒川の流れに近いこのあたりは、住宅と町工場が密集する下町らしい街並みです。
曳舟川通り(新四ツ木橋)とゆりのき橋通りが交差する「更正橋」五叉路のすぐそばのゆりのき通り沿いにあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
大通りの沿道なので門前はやや雑然としていますが、意外に広い山内に入ると札所寺院らしい落ち着きをみせています。
門柱に寺号標。


【写真 上(左)】 隅田川二十一ヶ所霊場の札所標
【写真 下(右)】 新葛西三十三観音霊場の札所標
参道右手には石佛群と札所標があります。
札所標は隅田川二十一ヶ所霊場第15番と新葛西三十三観音霊場第12番(旧・法花寺)のもので、いずれも稀少な遺構です。


【写真 上(左)】 覆屋
【写真 下(右)】 地蔵尊と弘法大師像
本堂向かって右手の覆屋には、石佛の地蔵尊立像と弘法大師坐像。
弘法大師坐像の台座には「第七十五番」とあるので、おそらく南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第75番の札所本尊とみられます。


【写真 上(左)】 ”いろは大師”の札所本尊
【写真 下(右)】 天水鉢
本堂前の桔梗紋(真言宗智山派の宗紋)入の天水鉢は、錆を帯びて風合いがあります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
階段上の本堂は近代建築ながら、屋根頂部に露盤と宝珠を置いているのでおそらく宝形造かと思われます。
銅板葺きで流れ向拝。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に桔梗紋を配した蟇股を置いています。
向拝格子扉のうえに寺号扁額。
御朱印は本堂向かって左側の庫裏にて拝受しました。
〔 寶蔵寺の御朱印 〕
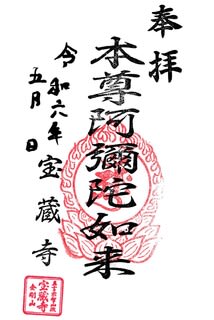
中央に「本尊阿彌陀如来」の印判。御寶印(蓮華座+火焔宝珠)のお種子は胎蔵大日如来の「アーンク」(荘厳体・五点具足の阿字)。
当山の御本尊は『新編武蔵風土記稿』『葛西志』では不動明王、『墨田区史』では阿弥陀如来とあり、胎蔵大日如来ではない模様なので、尊格を代表する通種子(本不生)の意で使われているのかもしれません。
霊場札所の札所印はとくに捺されていないとのことでした。

■ 墨田区お寺めぐり第10番のスタンプ
■ 第16番 恵日山(孤竹山) 正覚寺
(しょうがくじ)
墨田区八広3-5-2
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:
司元別当:(大畑村)稲荷社(現・三輪里稻荷神社)(墨田区八広)
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第69番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第49番、墨田区お寺めぐり第14番
第16番は墨田区八広の正覚寺です。
下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
正覚寺は、慶長十四年(1609年)に長養法印が開創、中興開山は快厳(宝暦五年(1755年)寂)と伝わり東葛西領上小松村正福寺末の真言宗寺院です。
御本尊は、『新編武蔵風土記稿』『墨田区史』には薬師如来、『葛西志』には阿弥陀如来とありますが、現在の御本尊は薬師如来のようです。
資料類には山号は「恵日山」とありますが、『新編武蔵風土記稿』には「狐竹山明王院」とあり、御朱印の揮毫も「狐竹山」でした。
江戸時代は大畑村の鎮守・稲荷社の別当でした。
『葛西志』によると稲荷社の御鎮座は慶長十九年(1614年)なので、正覚寺とほぼ同時期の創建とみられます。
(大畑村)稲荷社は、現在の三輪里稲荷神社とみられます。

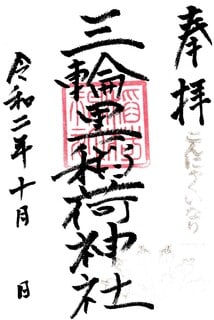
【写真 上(左)】 三輪里稲荷神社
【写真 下(右)】 三輪里稲荷神社の御朱印
当社公式Webには「慶長十九年(1614年)出羽国(山形県)湯殿山の大日坊が、かつての大畑村の総鎮守として羽黒大神の御分霊を勧請し、三輪里稻荷大明神として御鎮座」とあります。
御祭神は倉稲魂命。
初午の日にのどの患いや風邪に神験あらたかな湯殿山秘法のこんにゃくの護符を授けることから、俗に「こんにゃく稲荷」と呼ばれ参詣客を集めていたようです。
正覚寺開山の長養法印と三輪里稻荷大明神を勧請の大日坊との関係はよくわかりませんが、稲荷社の本地は十一面観世音菩薩で、別当・正覚寺と神仏混淆状態にあったことがうかがわれます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻三』(国立国会図書館)
(大畑村)正覚寺
新義真言宗 寺嶋村蓮花寺末 狐竹山明王院ト号ス 中興僧快巌宝暦五年(1755年)六月十七日寂
本尊薬師
(大畑村)稲荷社
村ノ鎮守ナリ 本地十一面観音 正覚寺持
■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
(大畑村)正覚寺
(稲荷社)社地の並にあり。新義真言宗、東葛西領上小松村、正福寺の末なり。
恵日山と号す。当寺も鎮守稲荷と同時の草創なりしと云、本尊阿弥陀如来を安置す。
(大畑村)稲荷社
村の中ほどにあり、慶長十九年(1614年)の鎮座にして、此村の鎮守なりと云、正覚寺持。
■ 『墨田区史 本編』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
正覚寺(恵日山 吾嬬町西六丁目91番地)
新義真言宗で上小松正福寺の末、慶長十四年(1609年)に長養法印が開創し中興開山は快厳である。
本尊薬師如来を安置し八月六日を縁日と定めている。
■ 『すみだの史跡文化財散歩 P.58』(墨田区資料/PDF)
慶長19年(1614)に出羽国(山形県)湯殿山の修験者大日坊が、羽黒大神の分霊を大畑村(現在地)の鎮守として勧請し、三輪里稲荷大明神と称したのが始まりと伝えられていま
す。
初午の日に、湯殿山秘法のこんにゃくの護符を授けることから、俗に「こんにゃく稲荷」と乎ばれていました。
■ 三輪里稻荷神社公式Web
御祭神は倉稲魂命。当社は、慶長十九年(1614年)出羽国(山形県)湯殿山の大日坊が、かつての大畑村の総鎮守として羽黒大神の御分霊を勧請し、三輪里稻荷大明神として御鎮座いたしました。
現在は三輪里稻荷神社、通称“こんにゃくいなり”として八広の地をお守りしてます。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』隅田川向島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは京成押上線「京成曳舟」駅で徒歩約9分。
八広のメイン通り・八広中央通りに面してあります。
すぐ北側はかつて別当を務めた三輪里稻荷神社ですが、参道は別にあるので隣り合った感じはありません。
あるいは明治の神仏分離時に一線を画したのかもしれません。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
すっきりとまとまった近代的な山内で、入口門柱に寺号標。
参道をいくと左手に立派な大師堂があります。
おそらく切妻造銅板葺妻入で、水引虹梁、木鼻、斗栱、身蟇股を備えています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 大師堂
堂碑の碑文によると、昭和59年の弘法大師1150年御遠忌事業として建立されたとのこと。
堂内には弘法大師坐像が御座されています。
台座に札番はないですが、おそらく荒川辺、南葛八十八ヶ所(いろは大師)、墨田川霊場の3つの弘法大師霊場の札所本尊とみられます。


【写真 上(左)】 弘法大師像
【写真 下(右)】 札所標
堂宇横には「二十一ヶ所大師」と刻まれた石碑があり、こちらはおそらく稀少な隅田川霊場の札所標です。
本堂向かって右手には石塔や石佛群(如意輪観世音菩薩・地蔵尊など)があります。
コンクリで固められた山内ですが、緑が多く落ち着きがあります。


【写真 上(左)】 石佛群
【写真 下(右)】 本堂
本堂は陸屋根の近代建築ですが、屋根上の相輪と向拝の扁額が効いて風格があります。
向拝鉄扉にうえに寺号扁額を掲げています。
驚いたことにこの鉄扉が開きました。
堂内は絢爛たる装いで、前面に護摩壇、背面に両界曼荼羅、御内陣正面お厨子前にはおそらく御前立の右手施無畏印、左手に薬壺をもたれる薬師如来坐像が御座されていました。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 庫裏
御朱印は本堂向かって左側の庫裏にて拝受しました。
〔 正覚寺の御朱印 〕
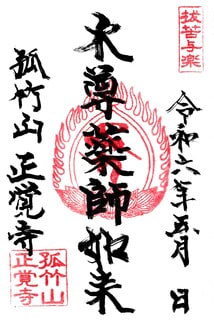
中央に「本尊薬師如来」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
霊場札所印は捺されていない模様です。

■ 墨田区お寺めぐり第14番のスタンプ
■ 第17番 瑞松山 栄隆院 霊光寺
(れいこうじ)
墨田区吾妻橋1-9-11
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:
司元別当:
他札所:新葛西三十三観音霊場第24番、江戸東方四十八地蔵霊場第40番、墨田区お寺めぐり第22番
第17番は墨田区吾妻橋の霊光寺、隅田川霊場唯一の浄土宗寺院です。
下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
霊光寺は、木食重譽上人霊光和尚を開山として寛文七年(1667年)に創建、当初は霊光庵を号しましたが、寶永三年(1706年)増上寺の末寺となり現号を号したといいます。
御本尊の阿弥陀如来は、増上寺中興の観智国師の持念佛と伝わります。
増上寺の公式Webは、「増上寺第12世・観智国師(源誉存応上人)(元和六年(1620年)寂)は、徳川家康公と増上寺の寺檀関係を結ばれ、増上寺および近世浄土宗の発展に寄与された方」とあります。
『寺社書上』にも、観智国師と家康公の邂逅の逸話が記されています。
当山の御本尊・阿弥陀如来は、天照太神の御作という縁起が伝わります。
この縁起は『寺社書上』にも記されています。読解不能の箇所もありますが、縁起概略を辿ってみます。
慶長十五年(1610年)、源誉存応上人(観智国師)は後陽成天皇(1571- 1617年)に参内し講説をおこなったところ天皇は大いに敬まわれて普光観智國師の号を賜りました。
観智国師が関東帰国の前に伊勢太神宮に参詣された時、神宮の神主は阿弥陀如来の像を国師に奉じたといいます。
内宮の宝殿に御座し、代々安置してきた尊像との由。
国師は帰国の後、こちらの尊像を持念佛に奉じ、のちに家康公の使僧もつとめた弟子の林應にこの尊像を授けたといいます。
林應和尚より四代の住持・十譽和尚は、ある夜霊夢にて御本尊の阿弥陀如来が御声を発せられるのを聴き、観智国師が伊勢太神宮から相伝されたこの尊像が天照太神の御作と確信し、後世に御本尊縁起として伝えられたようです。
『寺社書上』には恵心僧都作の御前立本尊(阿弥陀如来座像)、弘法大師御作の十一面観世音菩薩・辨才天、興教大師御作の不動明王などの寺宝が記されています。
しかし、関東大震災、東京大空襲で伽藍はことごとく焼失したためか、上記の寺宝についてのその後の情報は不明のようです。
当山は葛西三十三観音霊場第24番の札所となっています。
この霊場は天保九年(1838年)刊とされる『東都歳事記』に載っているので、江戸時代からの観音霊場札所です。(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
文政十二年(1829年)頃の編纂とされる『寺社書上』には「観音堂本尊 十一面観世音 弘法大師之作」とあるので、こちらが札所本尊であった可能性があります。
また、当山は江戸東方四十八地蔵霊場第40番の札所でもあり、こちらの札所本尊は「元日地蔵菩薩」と伝わります。(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
こちらも『東都歳事記』に記載がある江戸時代からの地蔵尊霊場です。
『寺社書上』には「石匣塔上ニ金佛地蔵尊安置」とあり、こちらが札所本尊の「元日地蔵菩薩」と思われ、下記の「元日地蔵菩薩縁起」(山内掲示)にもその旨が記されています。
現在は立像石佛として再興され、山内に奉安されています。
『ガイド』によると、こちらの地蔵尊は昭和62年初春の奉安とのこと。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『寺社書上 [121] 中ノ郷寺社書上 一』(国立国会図書館)
江戸増上寺末
本所中之郷
浄土宗 瑞松山栄隆院霊光寺
右霊光寺ハ寛文七年(1667年)之起立
本尊 阿彌陀如来立像 下品之印木像
天照大神宮之御作也 縁起有之
右本尊ハ増上寺中興観智国師之持念佛也
観音勢至 二菩薩
前立本尊 阿彌陀如来座像 上品之印 恵心僧都作
法祖 善導大師 座像
宗祖 圓光大師 座像
当寺開山之像 号聲蓮社十譽願値本阿霊光上人
金佛善光寺如来 三尊厨子入
不動明王 興教大師之作 縁起有之
観音堂本尊 十一面観世音 弘法大師之作 縁起有之
釈迦涅槃木像
当寺鎮守 辨才天 弘法大師之作
焔魔王木像
妙説観世音石像
石匣塔上ニ金佛地蔵尊安置 一基
右ハ近年再興した門之内西ノ方ニ有
矢野稲荷大明神
小鍛冶稲荷大明神
本尊縁起
当寺の本尊阿弥陀如来者天照太神の御作也 先師某に語て曰く ●尊像ハ三縁山増上寺中興貞蓮社慈昌源譽普光観智國師存應大和尚より弟子代々伝持之像也 國師俗称ハ武州由木乃人平山左衛門尉李重之御也 十五歳の時増上寺十代感譽上人を師として顕密の教ヲ究メ 天正十二年(1584年)に増上寺に住シ賜フ(中略)大将軍家康公武州江府乃御城に入在ス時 増上寺ハ今の龍ノ口に有シ時 ●●は将軍御馬にて門前を通り在ス 源譽門●出て御城入を見給ふに 御馬ヲ不進 公左右ヲ御覧●さ●れハ 寺門に老僧立て有り 人を使うハして問給ふ 何●の事何と号スと尋在ス 源譽●寺ハ浄土宗三縁山増上寺 名ハ存應と応り 家康公聞召則テ 寺に御入在て 師ハ感譽の弟子●参河にて聞及ひぬ 明日ハ寺に来て●を食りせん● 御契物在て御城に入 翌日此所増上寺ニ御入在りて 御●食在ス 則十念を受師檀乃物在て大イに崇信在ス
後陽成天皇慶長十五年(1610年)七月十九日入宮封御説法盛に浄●乃奥義安心乃秘要を講説在ス 天皇大に敬悦在して賜普光観智國師之号ヲ洛陽に在ス事三旬 京都の道俗化を受候事 甚多シ 國師帰国節 伊勢太神宮江参詣の時 神主敬●して●阿弥陀如来乃像を國師に捧ぬ 神主の曰ク此尊像ハ 内宮乃宝殿に在し●兵乱の砌 出し●り 某代々安置し候へども今師に奉●
國師帰国の後弟子林應と云僧に授給ふ ●林應和尚 力ハ数十人力にて道の早き事ハ凡人の●● 駿河の國御用之節ハ 此僧を使僧となし給ふに(中略)林應和尚より代々相伝て汝●四代の末第●●故説授のため國師之名号相添(中略)
十譽或夜夢を感候事 ●意に伊勢太神宮江参り宝前●信敬し念佛して神前の御を● 自然●開き閉に此如来在ス 本尊御聲を出し告て曰ク 汝我●頼って能ク念佛を我能ク護て不捨と曰ふ● 夢覚候 其御相好と安置乃本尊と先師物語と符合せり 天照太神の御作成事無疑 惟は阿弥陀如来の利益事 尊像をして言●出し(以下読解できず)
■ 『東京名所図会 [第14] (本所区之部)(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
霊光寺
霊光寺は同町(中之郷竹町)十三番地に在り。瑞松山と号す。浄土宗にして芝増上寺の末なり。開山は木食重譽上人霊光和尚にて。初め草庵なりしが。寶永三年(1706年)寺院に列せり。
本尊阿彌陀如来は。増上寺の観智國師京都よりの帰途。伊勢にて得たるものなりといふ。
■ 『本所区史』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
霊光寺
霊光寺は同町(中之郷竹町)十三番地に有り瑞松山と号し、浄土宗にして芝増上寺の末である。開山は木食重譽上人霊光和尚で、初め草庵であったが寛永三年(1626年)寺院に列した。
本尊阿彌陀如来は増上寺の観智國師京都よりの帰途伊勢にて得たものなりと伝説されて居る。
■ 元日地蔵菩薩縁起(山内掲示)
当寺は今を去る寛文七未年(西暦1667年)の創建で霊光庵と称していたが、寶永参戌年(西暦1706年)増上寺末に列し、霊光寺と改め山号を瑞松山、院号を栄隆院と定めた。
境内に何時のころからか石の地蔵菩薩が安置されていた(年号不詳)が、「江戸府内中郷寺社書上」には文政拾壱子年(西暦1828年)ころ金佛の地蔵菩薩を再興と記されている。(中略)昭和四拾年本堂、書院、庫裏等を完成した(中略)説法印の元日地蔵菩薩を建立することとした。
元日地蔵菩薩は「東都歳事記」等によれば江戸東方四拾八所四拾番札所の地蔵菩薩であるが名称の由来は不明である。
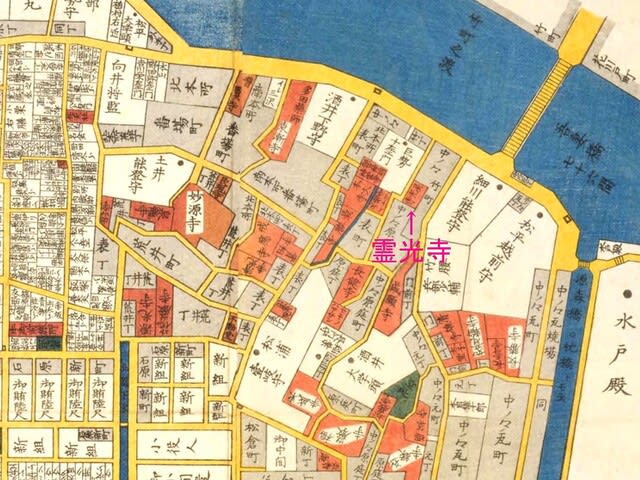
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本所絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営地下鉄浅草線「本所吾妻橋」駅で徒歩約6分。
メトロ鉄銀座線・東武スカイツリーライン「浅草」駅からも徒歩10分程度で歩けます。
「浅草」駅から隅田川を吾妻橋で渡ってのアプローチの方が風情があるかもしれません。
第6番遍照院から浅草通りを挟んだ対面にあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 門柱の寺号
浅草通りに面して寺号が刻まれた門柱。
すぐ前に駐車場と、その奥にこ洒落た住宅のような建物がありますが、その建物の一部に千鳥破風を配した向拝が設けられています。
都心のお寺然とした、たたずまいです。
門柱右手には石佛立像の「元日地蔵菩薩」が御座し、石碑の縁起書もおかれていました。

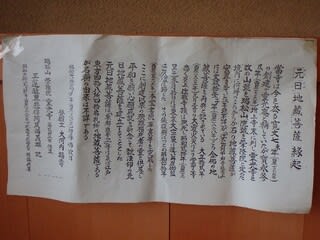
【写真 上(左)】 元日地蔵菩薩
【写真 下(右)】 元日地蔵菩薩縁起


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 扁額
山内にも立派な寺号標があり、向拝上には山号扁額も掲げられていました。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
〔 霊光寺の御朱印 〕
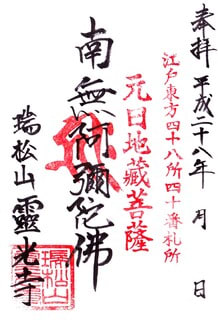
中央に六字御名号(南無阿彌陀佛)の揮毫と阿弥陀如来のお種子「キリーク」の印。
右には「元日地蔵菩薩」の印と「江戸東方四十八所四十番札所」の札所印。
左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
「江戸東方四十八地蔵霊場」の札所印は他寺ではみたことがなく、たいへん稀少な御朱印です。
→ ■ 希少な札所印
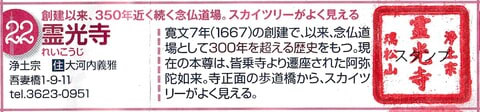
■ 墨田区お寺めぐり第22番のスタンプ
→ ■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-7へつづきます。
※札所および記事リストは→ こちら。
【 BGM 】
■ 滴 - 今井美樹
■ Love is all/愛を聴かせて - 椎名恵
■ Musunde Hiraku - Kalafina
※札所および記事リストは→ こちら。
『荒川辺八十八ヵ所と隅田川二十一ヵ所霊場案内』(新田昭江氏著/1991年)を『ガイド』と略記し、適宜引用させていただきます。
■ 第15番 金剛山(常在山) 寶蔵寺
(ほうぞうじ)
墨田区八広6-9-17
真言宗智山派
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:
司元別当:(木下村)山王社
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第68番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第75番、新葛西三十三観音霊場第12番(旧・法花寺)、墨田区お寺めぐり第10番
第15番は墨田区八広の寶蔵寺です。
下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
寶蔵寺は慶長十九年(1614年)に朝応和尚が創建した真言宗寺院で寺島蓮花寺の末寺でした。(『ガイド』では安永年間(1772-1780年)創立)
御本尊は阿弥陀如来。客殿に不動明王を安していたようです。
境内に祀る稲荷社は、おそらく鎮守とみられ、『葛西志』にも境内社として記載されています。
山号を「常在山」としている資料もありますが、『新編武蔵風土記稿』『葛西志』などでは「金剛山」としています。
もとは南葛西郡大木村字木下にありましたが明治43年の出水に遭い、さらに荒川放水路開設のために大正8年、西方に約550mほどの現在地に移転しています。
江戸時代は木下村の山王社(慶長十九年(1614年)御鎮座)の別当を務めていました。
情報があまりない寺院ですが、荒川辺霊場、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)などの札所となっているので、真言密寺として相応のポジションを担っていたことがわかります。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻三』(国立国会図書館)
(木下村)寶蔵寺
新義真言宗 寺嶋村蓮華寺末 金剛山ト号ス 本尊ハ不動ナリ
(木下村)山王社
慶長十九年(1614年)ノ鎮座ナリ 寶蔵寺持下同シ
稲荷社
■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
(木之下村)寶蔵寺
山王社と同じ邊にあり。当寺も慶長十九年(1614年)の起立なりと云、新義真言宗、寺島村蓮華寺末、金剛山と号す。
本尊不動尊 客殿に安す。
稲荷社 境内にあり。
(木之下村)山王社
村の南へよりてあり、慶長十九年(1614年)の鎮座と云、寶蔵寺持。
■ 『墨田区史 本編』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
宝蔵寺(金剛山 吾嬬町西九丁目10番地)
慶長十九年(1614年)に朝応和尚が創建した寺院で新義真言宗に属し、寺島蓮花寺の末寺である。
もと南葛飾郡大木村字木下に所在し、その後明治四十三年の出水にあい、さらに荒川放水路開設のために西方約五五0mほどの現在地に大正八年に移転した。
本尊は阿弥陀如来である。
-------------------------
最寄りは京成押上線「八広」駅で徒歩約3分。
荒川の流れに近いこのあたりは、住宅と町工場が密集する下町らしい街並みです。
曳舟川通り(新四ツ木橋)とゆりのき橋通りが交差する「更正橋」五叉路のすぐそばのゆりのき通り沿いにあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
大通りの沿道なので門前はやや雑然としていますが、意外に広い山内に入ると札所寺院らしい落ち着きをみせています。
門柱に寺号標。


【写真 上(左)】 隅田川二十一ヶ所霊場の札所標
【写真 下(右)】 新葛西三十三観音霊場の札所標
参道右手には石佛群と札所標があります。
札所標は隅田川二十一ヶ所霊場第15番と新葛西三十三観音霊場第12番(旧・法花寺)のもので、いずれも稀少な遺構です。


【写真 上(左)】 覆屋
【写真 下(右)】 地蔵尊と弘法大師像
本堂向かって右手の覆屋には、石佛の地蔵尊立像と弘法大師坐像。
弘法大師坐像の台座には「第七十五番」とあるので、おそらく南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第75番の札所本尊とみられます。


【写真 上(左)】 ”いろは大師”の札所本尊
【写真 下(右)】 天水鉢
本堂前の桔梗紋(真言宗智山派の宗紋)入の天水鉢は、錆を帯びて風合いがあります。


【写真 上(左)】 本堂
【写真 下(右)】 斜めからの本堂
階段上の本堂は近代建築ながら、屋根頂部に露盤と宝珠を置いているのでおそらく宝形造かと思われます。
銅板葺きで流れ向拝。


【写真 上(左)】 向拝
【写真 下(右)】 扁額
水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に桔梗紋を配した蟇股を置いています。
向拝格子扉のうえに寺号扁額。
御朱印は本堂向かって左側の庫裏にて拝受しました。
〔 寶蔵寺の御朱印 〕
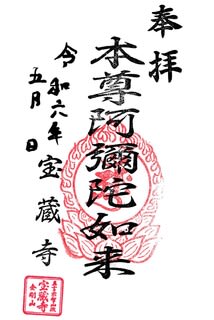
中央に「本尊阿彌陀如来」の印判。御寶印(蓮華座+火焔宝珠)のお種子は胎蔵大日如来の「アーンク」(荘厳体・五点具足の阿字)。
当山の御本尊は『新編武蔵風土記稿』『葛西志』では不動明王、『墨田区史』では阿弥陀如来とあり、胎蔵大日如来ではない模様なので、尊格を代表する通種子(本不生)の意で使われているのかもしれません。
霊場札所の札所印はとくに捺されていないとのことでした。

■ 墨田区お寺めぐり第10番のスタンプ
■ 第16番 恵日山(孤竹山) 正覚寺
(しょうがくじ)
墨田区八広3-5-2
真言宗智山派
御本尊:薬師如来
札所本尊:
司元別当:(大畑村)稲荷社(現・三輪里稻荷神社)(墨田区八広)
他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第69番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第49番、墨田区お寺めぐり第14番
第16番は墨田区八広の正覚寺です。
下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
正覚寺は、慶長十四年(1609年)に長養法印が開創、中興開山は快厳(宝暦五年(1755年)寂)と伝わり東葛西領上小松村正福寺末の真言宗寺院です。
御本尊は、『新編武蔵風土記稿』『墨田区史』には薬師如来、『葛西志』には阿弥陀如来とありますが、現在の御本尊は薬師如来のようです。
資料類には山号は「恵日山」とありますが、『新編武蔵風土記稿』には「狐竹山明王院」とあり、御朱印の揮毫も「狐竹山」でした。
江戸時代は大畑村の鎮守・稲荷社の別当でした。
『葛西志』によると稲荷社の御鎮座は慶長十九年(1614年)なので、正覚寺とほぼ同時期の創建とみられます。
(大畑村)稲荷社は、現在の三輪里稲荷神社とみられます。

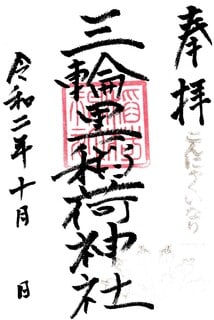
【写真 上(左)】 三輪里稲荷神社
【写真 下(右)】 三輪里稲荷神社の御朱印
当社公式Webには「慶長十九年(1614年)出羽国(山形県)湯殿山の大日坊が、かつての大畑村の総鎮守として羽黒大神の御分霊を勧請し、三輪里稻荷大明神として御鎮座」とあります。
御祭神は倉稲魂命。
初午の日にのどの患いや風邪に神験あらたかな湯殿山秘法のこんにゃくの護符を授けることから、俗に「こんにゃく稲荷」と呼ばれ参詣客を集めていたようです。
正覚寺開山の長養法印と三輪里稻荷大明神を勧請の大日坊との関係はよくわかりませんが、稲荷社の本地は十一面観世音菩薩で、別当・正覚寺と神仏混淆状態にあったことがうかがわれます。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻三』(国立国会図書館)
(大畑村)正覚寺
新義真言宗 寺嶋村蓮花寺末 狐竹山明王院ト号ス 中興僧快巌宝暦五年(1755年)六月十七日寂
本尊薬師
(大畑村)稲荷社
村ノ鎮守ナリ 本地十一面観音 正覚寺持
■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
(大畑村)正覚寺
(稲荷社)社地の並にあり。新義真言宗、東葛西領上小松村、正福寺の末なり。
恵日山と号す。当寺も鎮守稲荷と同時の草創なりしと云、本尊阿弥陀如来を安置す。
(大畑村)稲荷社
村の中ほどにあり、慶長十九年(1614年)の鎮座にして、此村の鎮守なりと云、正覚寺持。
■ 『墨田区史 本編』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
正覚寺(恵日山 吾嬬町西六丁目91番地)
新義真言宗で上小松正福寺の末、慶長十四年(1609年)に長養法印が開創し中興開山は快厳である。
本尊薬師如来を安置し八月六日を縁日と定めている。
■ 『すみだの史跡文化財散歩 P.58』(墨田区資料/PDF)
慶長19年(1614)に出羽国(山形県)湯殿山の修験者大日坊が、羽黒大神の分霊を大畑村(現在地)の鎮守として勧請し、三輪里稲荷大明神と称したのが始まりと伝えられていま
す。
初午の日に、湯殿山秘法のこんにゃくの護符を授けることから、俗に「こんにゃく稲荷」と乎ばれていました。
■ 三輪里稻荷神社公式Web
御祭神は倉稲魂命。当社は、慶長十九年(1614年)出羽国(山形県)湯殿山の大日坊が、かつての大畑村の総鎮守として羽黒大神の御分霊を勧請し、三輪里稻荷大明神として御鎮座いたしました。
現在は三輪里稻荷神社、通称“こんにゃくいなり”として八広の地をお守りしてます。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』隅田川向島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは京成押上線「京成曳舟」駅で徒歩約9分。
八広のメイン通り・八広中央通りに面してあります。
すぐ北側はかつて別当を務めた三輪里稻荷神社ですが、参道は別にあるので隣り合った感じはありません。
あるいは明治の神仏分離時に一線を画したのかもしれません。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 寺号標
すっきりとまとまった近代的な山内で、入口門柱に寺号標。
参道をいくと左手に立派な大師堂があります。
おそらく切妻造銅板葺妻入で、水引虹梁、木鼻、斗栱、身蟇股を備えています。


【写真 上(左)】 参道
【写真 下(右)】 大師堂
堂碑の碑文によると、昭和59年の弘法大師1150年御遠忌事業として建立されたとのこと。
堂内には弘法大師坐像が御座されています。
台座に札番はないですが、おそらく荒川辺、南葛八十八ヶ所(いろは大師)、墨田川霊場の3つの弘法大師霊場の札所本尊とみられます。


【写真 上(左)】 弘法大師像
【写真 下(右)】 札所標
堂宇横には「二十一ヶ所大師」と刻まれた石碑があり、こちらはおそらく稀少な隅田川霊場の札所標です。
本堂向かって右手には石塔や石佛群(如意輪観世音菩薩・地蔵尊など)があります。
コンクリで固められた山内ですが、緑が多く落ち着きがあります。


【写真 上(左)】 石佛群
【写真 下(右)】 本堂
本堂は陸屋根の近代建築ですが、屋根上の相輪と向拝の扁額が効いて風格があります。
向拝鉄扉にうえに寺号扁額を掲げています。
驚いたことにこの鉄扉が開きました。
堂内は絢爛たる装いで、前面に護摩壇、背面に両界曼荼羅、御内陣正面お厨子前にはおそらく御前立の右手施無畏印、左手に薬壺をもたれる薬師如来坐像が御座されていました。


【写真 上(左)】 扁額
【写真 下(右)】 庫裏
御朱印は本堂向かって左側の庫裏にて拝受しました。
〔 正覚寺の御朱印 〕
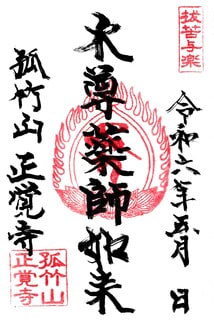
中央に「本尊薬師如来」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。
左に山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
霊場札所印は捺されていない模様です。

■ 墨田区お寺めぐり第14番のスタンプ
■ 第17番 瑞松山 栄隆院 霊光寺
(れいこうじ)
墨田区吾妻橋1-9-11
浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
札所本尊:
司元別当:
他札所:新葛西三十三観音霊場第24番、江戸東方四十八地蔵霊場第40番、墨田区お寺めぐり第22番
第17番は墨田区吾妻橋の霊光寺、隅田川霊場唯一の浄土宗寺院です。
下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。
霊光寺は、木食重譽上人霊光和尚を開山として寛文七年(1667年)に創建、当初は霊光庵を号しましたが、寶永三年(1706年)増上寺の末寺となり現号を号したといいます。
御本尊の阿弥陀如来は、増上寺中興の観智国師の持念佛と伝わります。
増上寺の公式Webは、「増上寺第12世・観智国師(源誉存応上人)(元和六年(1620年)寂)は、徳川家康公と増上寺の寺檀関係を結ばれ、増上寺および近世浄土宗の発展に寄与された方」とあります。
『寺社書上』にも、観智国師と家康公の邂逅の逸話が記されています。
当山の御本尊・阿弥陀如来は、天照太神の御作という縁起が伝わります。
この縁起は『寺社書上』にも記されています。読解不能の箇所もありますが、縁起概略を辿ってみます。
慶長十五年(1610年)、源誉存応上人(観智国師)は後陽成天皇(1571- 1617年)に参内し講説をおこなったところ天皇は大いに敬まわれて普光観智國師の号を賜りました。
観智国師が関東帰国の前に伊勢太神宮に参詣された時、神宮の神主は阿弥陀如来の像を国師に奉じたといいます。
内宮の宝殿に御座し、代々安置してきた尊像との由。
国師は帰国の後、こちらの尊像を持念佛に奉じ、のちに家康公の使僧もつとめた弟子の林應にこの尊像を授けたといいます。
林應和尚より四代の住持・十譽和尚は、ある夜霊夢にて御本尊の阿弥陀如来が御声を発せられるのを聴き、観智国師が伊勢太神宮から相伝されたこの尊像が天照太神の御作と確信し、後世に御本尊縁起として伝えられたようです。
『寺社書上』には恵心僧都作の御前立本尊(阿弥陀如来座像)、弘法大師御作の十一面観世音菩薩・辨才天、興教大師御作の不動明王などの寺宝が記されています。
しかし、関東大震災、東京大空襲で伽藍はことごとく焼失したためか、上記の寺宝についてのその後の情報は不明のようです。
当山は葛西三十三観音霊場第24番の札所となっています。
この霊場は天保九年(1838年)刊とされる『東都歳事記』に載っているので、江戸時代からの観音霊場札所です。(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
文政十二年(1829年)頃の編纂とされる『寺社書上』には「観音堂本尊 十一面観世音 弘法大師之作」とあるので、こちらが札所本尊であった可能性があります。
また、当山は江戸東方四十八地蔵霊場第40番の札所でもあり、こちらの札所本尊は「元日地蔵菩薩」と伝わります。(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))
こちらも『東都歳事記』に記載がある江戸時代からの地蔵尊霊場です。
『寺社書上』には「石匣塔上ニ金佛地蔵尊安置」とあり、こちらが札所本尊の「元日地蔵菩薩」と思われ、下記の「元日地蔵菩薩縁起」(山内掲示)にもその旨が記されています。
現在は立像石佛として再興され、山内に奉安されています。
『ガイド』によると、こちらの地蔵尊は昭和62年初春の奉安とのこと。
-------------------------
【史料・資料】
■ 『寺社書上 [121] 中ノ郷寺社書上 一』(国立国会図書館)
江戸増上寺末
本所中之郷
浄土宗 瑞松山栄隆院霊光寺
右霊光寺ハ寛文七年(1667年)之起立
本尊 阿彌陀如来立像 下品之印木像
天照大神宮之御作也 縁起有之
右本尊ハ増上寺中興観智国師之持念佛也
観音勢至 二菩薩
前立本尊 阿彌陀如来座像 上品之印 恵心僧都作
法祖 善導大師 座像
宗祖 圓光大師 座像
当寺開山之像 号聲蓮社十譽願値本阿霊光上人
金佛善光寺如来 三尊厨子入
不動明王 興教大師之作 縁起有之
観音堂本尊 十一面観世音 弘法大師之作 縁起有之
釈迦涅槃木像
当寺鎮守 辨才天 弘法大師之作
焔魔王木像
妙説観世音石像
石匣塔上ニ金佛地蔵尊安置 一基
右ハ近年再興した門之内西ノ方ニ有
矢野稲荷大明神
小鍛冶稲荷大明神
本尊縁起
当寺の本尊阿弥陀如来者天照太神の御作也 先師某に語て曰く ●尊像ハ三縁山増上寺中興貞蓮社慈昌源譽普光観智國師存應大和尚より弟子代々伝持之像也 國師俗称ハ武州由木乃人平山左衛門尉李重之御也 十五歳の時増上寺十代感譽上人を師として顕密の教ヲ究メ 天正十二年(1584年)に増上寺に住シ賜フ(中略)大将軍家康公武州江府乃御城に入在ス時 増上寺ハ今の龍ノ口に有シ時 ●●は将軍御馬にて門前を通り在ス 源譽門●出て御城入を見給ふに 御馬ヲ不進 公左右ヲ御覧●さ●れハ 寺門に老僧立て有り 人を使うハして問給ふ 何●の事何と号スと尋在ス 源譽●寺ハ浄土宗三縁山増上寺 名ハ存應と応り 家康公聞召則テ 寺に御入在て 師ハ感譽の弟子●参河にて聞及ひぬ 明日ハ寺に来て●を食りせん● 御契物在て御城に入 翌日此所増上寺ニ御入在りて 御●食在ス 則十念を受師檀乃物在て大イに崇信在ス
後陽成天皇慶長十五年(1610年)七月十九日入宮封御説法盛に浄●乃奥義安心乃秘要を講説在ス 天皇大に敬悦在して賜普光観智國師之号ヲ洛陽に在ス事三旬 京都の道俗化を受候事 甚多シ 國師帰国節 伊勢太神宮江参詣の時 神主敬●して●阿弥陀如来乃像を國師に捧ぬ 神主の曰ク此尊像ハ 内宮乃宝殿に在し●兵乱の砌 出し●り 某代々安置し候へども今師に奉●
國師帰国の後弟子林應と云僧に授給ふ ●林應和尚 力ハ数十人力にて道の早き事ハ凡人の●● 駿河の國御用之節ハ 此僧を使僧となし給ふに(中略)林應和尚より代々相伝て汝●四代の末第●●故説授のため國師之名号相添(中略)
十譽或夜夢を感候事 ●意に伊勢太神宮江参り宝前●信敬し念佛して神前の御を● 自然●開き閉に此如来在ス 本尊御聲を出し告て曰ク 汝我●頼って能ク念佛を我能ク護て不捨と曰ふ● 夢覚候 其御相好と安置乃本尊と先師物語と符合せり 天照太神の御作成事無疑 惟は阿弥陀如来の利益事 尊像をして言●出し(以下読解できず)
■ 『東京名所図会 [第14] (本所区之部)(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
霊光寺
霊光寺は同町(中之郷竹町)十三番地に在り。瑞松山と号す。浄土宗にして芝増上寺の末なり。開山は木食重譽上人霊光和尚にて。初め草庵なりしが。寶永三年(1706年)寺院に列せり。
本尊阿彌陀如来は。増上寺の観智國師京都よりの帰途。伊勢にて得たるものなりといふ。
■ 『本所区史』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)
霊光寺
霊光寺は同町(中之郷竹町)十三番地に有り瑞松山と号し、浄土宗にして芝増上寺の末である。開山は木食重譽上人霊光和尚で、初め草庵であったが寛永三年(1626年)寺院に列した。
本尊阿彌陀如来は増上寺の観智國師京都よりの帰途伊勢にて得たものなりと伝説されて居る。
■ 元日地蔵菩薩縁起(山内掲示)
当寺は今を去る寛文七未年(西暦1667年)の創建で霊光庵と称していたが、寶永参戌年(西暦1706年)増上寺末に列し、霊光寺と改め山号を瑞松山、院号を栄隆院と定めた。
境内に何時のころからか石の地蔵菩薩が安置されていた(年号不詳)が、「江戸府内中郷寺社書上」には文政拾壱子年(西暦1828年)ころ金佛の地蔵菩薩を再興と記されている。(中略)昭和四拾年本堂、書院、庫裏等を完成した(中略)説法印の元日地蔵菩薩を建立することとした。
元日地蔵菩薩は「東都歳事記」等によれば江戸東方四拾八所四拾番札所の地蔵菩薩であるが名称の由来は不明である。
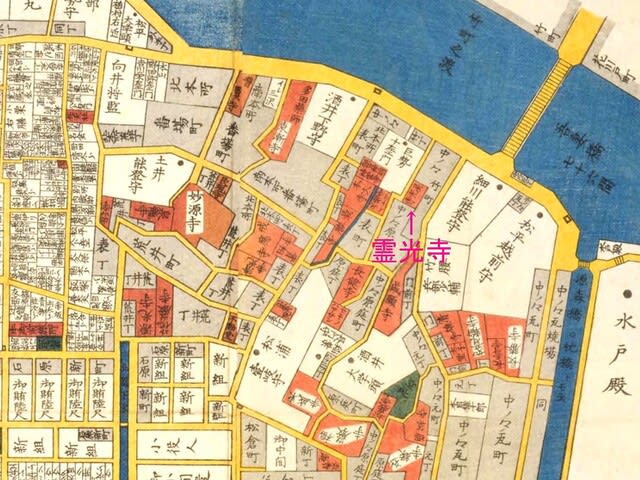
原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本所絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)
-------------------------
最寄りは都営地下鉄浅草線「本所吾妻橋」駅で徒歩約6分。
メトロ鉄銀座線・東武スカイツリーライン「浅草」駅からも徒歩10分程度で歩けます。
「浅草」駅から隅田川を吾妻橋で渡ってのアプローチの方が風情があるかもしれません。
第6番遍照院から浅草通りを挟んだ対面にあります。


【写真 上(左)】 山内入口
【写真 下(右)】 門柱の寺号
浅草通りに面して寺号が刻まれた門柱。
すぐ前に駐車場と、その奥にこ洒落た住宅のような建物がありますが、その建物の一部に千鳥破風を配した向拝が設けられています。
都心のお寺然とした、たたずまいです。
門柱右手には石佛立像の「元日地蔵菩薩」が御座し、石碑の縁起書もおかれていました。

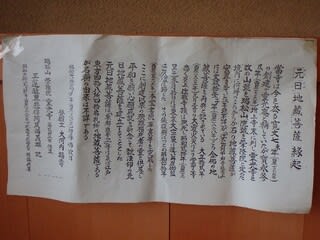
【写真 上(左)】 元日地蔵菩薩
【写真 下(右)】 元日地蔵菩薩縁起


【写真 上(左)】 寺号標
【写真 下(右)】 扁額
山内にも立派な寺号標があり、向拝上には山号扁額も掲げられていました。
御朱印は庫裏にて拝受しました。
〔 霊光寺の御朱印 〕
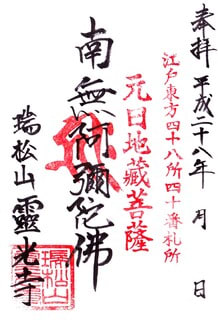
中央に六字御名号(南無阿彌陀佛)の揮毫と阿弥陀如来のお種子「キリーク」の印。
右には「元日地蔵菩薩」の印と「江戸東方四十八所四十番札所」の札所印。
左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。
「江戸東方四十八地蔵霊場」の札所印は他寺ではみたことがなく、たいへん稀少な御朱印です。
→ ■ 希少な札所印
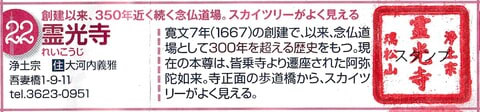
■ 墨田区お寺めぐり第22番のスタンプ
→ ■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-7へつづきます。
※札所および記事リストは→ こちら。
【 BGM 】
■ 滴 - 今井美樹
■ Love is all/愛を聴かせて - 椎名恵
■ Musunde Hiraku - Kalafina
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




