■Baby Hold On / The Grass Roots (Dunhill / 東芝)
1960年代後半から急速に主流となった「アルバムによるロックの鑑賞」も、しかし現実的にはラジオによるヒット曲の流布が必要とされていましたから、その最中に活動していた歌手やグループには様々な紆余曲折が興味深く残されています。
例えば本日ご紹介のグラス・ルーツは我国のポップスファンには絶対の存在として、その頃にヒット曲を連発していたアメリカのグループなんですが、洋楽雑誌等々に掲載される写真は主に4人組でありながら、実際に聞こえてくる楽曲にはホーンセクションやストリングス、幾つもの打楽器や複数のキーボード&ギター等々が使われていたのですから、彼等は決してバンドではなく、コーラスグループという受け取られ方が一般的だったんじゃ~ないでしょうか。
少なくともサイケおやじは、そんなふうに思っていましたし、基本的にグラス・ルーツがやっていた音楽はロックではなく、ポップスであればこそ、なにもそこに違和感を覚える必要もなかったでしょう。
ところが昭和45(1970)年にヒットした「Baby Hold On」の日本盤シングルのジャケ写を見たサイケおやじは、ちょいとショックを覚えました。
何故ならば、グラス・ルーツと名乗るグループが、そこではきっちり楽器を演奏しながらのライプステージと思われる写真が使われてたんですねぇ~~!?
実はこれまでも拙ブログでは度々書いてきていますが、1970年代頃までの大衆音楽は、レコードやオーディオ機器、さらには特定の商品を売るための手段であった側面があり、それゆえに殊更ラジオをメインとしたリスナーを瞬時に惹きつけるための楽曲の良さが求められていました。
そこで音楽出版社は有能なソングライターを発掘育成し、レコード制作の現場担当者はそこで魅力的な楽曲を手に入れ、最初っから売ることを目的とした歌や演奏を出していたわけですが、もちろん言うまでもなく、その全てが成功していたわけではありません。
むしろヒットせず、消えていったものが大多数の中において、思惑どおりに売れてしまえば、後はレコードの中での主役が、いよいよスタアとして稼ぐ順番になるのです。
つまりレコード産業の中には成功へのチャンスが幾つもあるわけで、ひとつでも芸能的な才能やセンスや天性の資質があれば、そういう業界のシステムを受け入れる気持次第で、自らを開花させる事が出来るというわけですが……。
さて、そういう観点からグラス・ルーツというグループを考察してみると、残されたレコードを聴くかぎり、1965年とされる公式デビュー当時と1970年前後の全盛期とでは、音楽性が異なっている事に気がつきます。
それはちょいと乱暴な括りかもしれませんが、フォークロックからバブルガムポップスへの転進であり、冒頭に述べたようなロック音楽鑑賞の主流には逆行しつつも、実はそれこそが大衆音楽の保守本流というシングルヒットの世界で大輪の花を咲かせる行き方でありました。
そしてその転換期に発売された大ヒット曲こそが、日本でもテンプターズがカパーして人気を集めた1967年の「今日を生きよう / Let's Live For Today」だったと思われます。
しかし当時発売されていたレコードを聴くかぎり、このあたりの流れからグラス・ルーツと名乗るグループが本当に実在していたのかはイマイチ、明確ではないでしょう。
何故ならばそこで聞かれる演奏パートには、明らかに同時代のハリウッドポップスと共通する音の構成やニュアンスがありますから、お馴染みのスタジオミュージシャンが参集している事は隠しようもなく、また肝心のリードボーカルの声質が楽曲によって微妙に異なっているのですから、それはもはや説明不要の現実でしょう。
実は後になって様々に調べたサイケおやじか知るところでは、最初のグラス・ルーツはサーファン&ホットロッドが流行していた1960年代前半から既にハリウッドの音楽業界では裏方をやっていたP.F.スローンとスティーヴ・バリのプロジェクトであり、主にP.F.スローンが歌い、その頃に発売されたシングル盤の名義は「グラスルーツ = Grassroots」になっています。
そして巡業用の実体化したバンドで歌うことになったのが、ビル・フルトンというサンフランシスコのローカルスタアだったという真相から、デビューLP「ホエン・ウァー・ユー・ホエン・アイ・ニーデッド・ユー」を聴くと、そこには異なった声質のボーカリストが複数参加している事は明らか!?
それでも個人的にはP.F.スローンとビル・フルトンの歌い方や基本的な声の響きは良く似ている!? と言うよりも、似せているというべきでしょうか。とにかくアルバムを通して、極力違和感が無いように仕上げているのは流石だと思います。もしかしたら、二人ともボブ・ディランやエルヴィス・プレスリーの物真似とかも好きで、上手かったのかもしれませんねぇ~♪
このアルバムはちょい前にCD化されていますし、内容も秀逸な歌ばかりですから、西海岸ポップスが好きな皆様には最高に楽しめると思います。
で、肝心のグラス・ルーツとしては、前述した「今日を生きよう / Let's Live For Today」の大ヒットから再びボーカリストが交代したというのが定説ですが、演奏パートは未だバンドサウンドを基本にしていますから、プロアマを問わず、カパーするのも、それほど困難ではありません。
ところが翌年にヒットさせた「真夜中の誓い / Midnight Confessions」になると、これがガラリと変わって、モータウンの制作? と思われても反論し難いほどの強いピートとホーン&ストリングを前面に出したアレンジが!??!
ちなみにこの頃のグラス・ルーツのメンバーはウォーレン・エントナー(g,vo)、クリード・ブラットン(g)、ロブ・グリル(b,vo)、リック・クーンス(ds) という4人組になっていて、件のジャケ写に登場しているのは、この顔ぶれかと推察するところです。
しかし現実的には、この4名だけではレコードに刻まれた歌とサウンドのイメージを再現する事など、到底無理……。
そこで興味深いのが、その頃の彼等が実演していたステージ用のアレンジで、全盛期を録った音質良好なテープでも発掘されないものか、長年望み続けている次第です。
ただし結論から言うと、その「真夜中の誓い / Midnight Confessions」からはプロデューサーのクレジットにP.F.スローンが消え、スティーヴ・バリの単独作業になったことから、おそらくはスタジオレコーディングの現場でも、全く別なボーカリストが起用されていたことも想像しています。
そして、だとすれば、ライプ音源が出たとしても、レコードとは違う声質の歌が聞かれ、演奏も所謂ハコバンっぽい、チープなものになっているのでは?
そんなこんなを思いつつ、じっくり楽しむグラス・ルーツも悪くありません。
特にご紹介した「Baby Hold On」はイントロから景気の良いドラムスとピアノ、さらにベースのコンビネーションが抜群で、これぞっ! ツカミはOK!
もう、これはほとんどモータウンサウンドであり、キャッチーな曲メロを存分に活かすブラスとストリングの存在も最高ですし、ボーカルの前ノリも若々しくて、これがヒットしなかったら世の中は闇ですよねぇ~~♪
サイケおやじは、今でもこれを聴くと、ウキウキ感が抑えられません。
ということで、気になるグラス・ルーツ存在の真相なんですが、おそらくはデビュー期と全盛期ではボーカリストが異なるばかりではなく、巡業用のバンドも幾つか、同時並行的に活動していのではないでしょうか。
掲載ジャケ写のライプ風景からして、これはGS全盛期の我国でも、例えば地方の体育館とか、ボーリング場の特設会場とか、そんな場所でのライプを共通認識されられるカットであり、和みます。
あぁ~、良い時代でした♪♪~♪














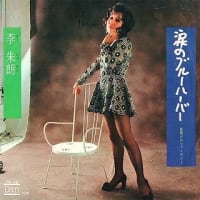

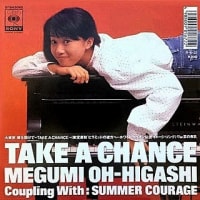










例の、確たる実態を持たない音楽芸能集合体の
一つだったのですね。
表題曲と似た感じ「燃ゆる瞳」のシングル盤を購入し、毎日聴いていたのを懐かしく思い出します。
そういえば、他にヒット曲もいくつかあったと思いますが、
グループのことについては、ほとんど知りませんでした。
http://www.youtube.com/watch?v=3_mO8tW_Sqw&list=AL94UKMTqg-9BFXy7T5WLLB-f5W7jhpjr4&index=7&feature=plcp
レコード・ジャケット上の「ダンヒル・シリーズ」という言葉になぜか注目。結構、売れっ子アーティストを抱えたレーベルだったような気がします。
コメント&ご紹介、ありがとうございます。
アップされている映像、キーボードがメンバー入りしていますから、おそらく1972年頃のテレビ出演かと思います。
そしてバレバレですが、如何にも半分以上は「口パク」ですし、テレビトラックという専用カラオケを使っていますよね。
まあ、それが当時のポップス系バンドでは珍しくもなかったのです。
さてダンヒルというレーベルは、ルー・アドラーという西海岸ハリウッドポップスを隆盛に導いた有名プロデューサーが設立した会社で、ママス&パパスやスリー・ドッグ・ナイト等々の大ヒットも作っていますが、1970年代中頃に活動停止になったと思われます。
またその頃、グラス・ルーツも解散、もしくは別プロジェクトとして他のレコード会社から再スタートしていますので、「ダンヒル≒グラス・ルーツ」という側面も否定出来ないような……(微笑)。