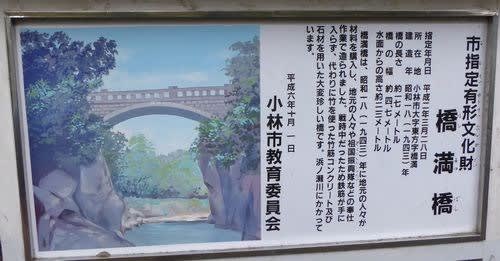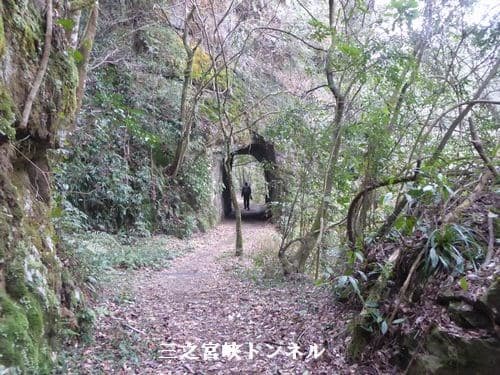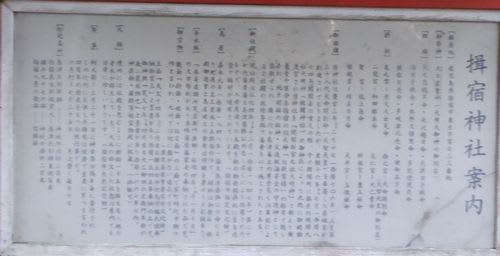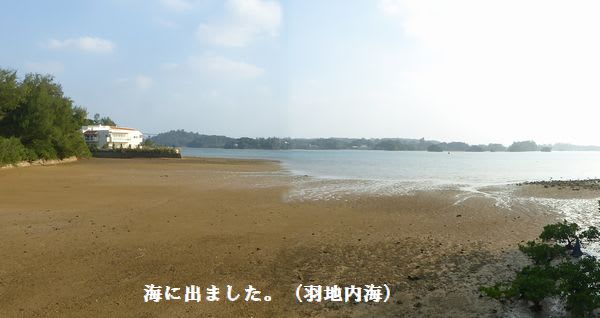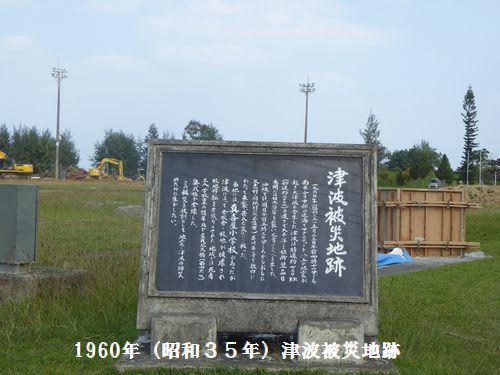3/19(日) 唐津・虹ノ松原ツーデーウオーク2日目20kmに参加。
8:00 また今日も30kmとフライングスタートします。


今日は、鏡山登山がコースに入っています。30kは、頂上まで行きますが、20kmコースは、中腹までです。


鏡山の国道が20k、30kの分岐点です。ここから鏡山の中腹まで上り坂です。



チェックポイント手前の所から虹ノ松原が一望できます。

第1回のチェックポイントが、ぽんぽこ村です。ここでは、みかんのジェリーを頂きました。


ぽんぽこ村には、たくさんのベコニアがありました。


西九州道を潜った所から下りになります。
民家には、白木蓮、黄梅、八重の梅など綺麗な花が咲いています。天気もいいし、青空に映え綺麗です。



野田の湯(温泉)の所が2回目のチェックポイント。5~6年前は、ここで水を汲み、帰りに野田温泉に入ったことがあります。確か、65歳以上は、安かったと記憶しています。



チェックポイントを過ぎるとコースは田園地帯です。ここで30kmのトップの方から抜かれました。ちょっとついていこうかと思いましたが、すぐ無理とわかり、いつものようにマイペースで歩きます。



ある民家の前に来ました。ここでは、個人的にお接待をされています。子の接待に感激し、お礼を書きました。





4回目のチェックポイントは、五反田改善センター。ここで約15km地点。
チェックポイントのすぐ近くには、「大村神社」があります。 大村神社の社伝によれば、西暦752年(天平勝宝4年)、真備は広嗣の逝去の地大村に無怨寺を建立し慰霊の趣を表し、
広嗣は無怨寺大明神として崇められたという。無怨寺大明神は、明治期の神仏分離令によって、大村神社と改称されている。


関の清次と五輪の塔があります。
これは、謡曲「籠太鼓(ろうだいこ)」のモデルになりました。説明文を見ると。
関の清治は大村の里(現在の五反田地区)豪族であるが、親友の浜窪治郎の密告のため牢獄に繋がれた。強力な彼は、牢を破って脱出し行方を暗ました。探索の手は厳しく、妻は狂死し、
子は舌を噛み切って息たえた。これを聞き清治は自首して出たが、領主は妻子の者どもが死に至るまで清治の所在を白状しなかった貞節と孝行を称えて、その罪を許した。哀惜の情にたえず、
清治は自らの刃に伏してその後を追った。時人塔を建てて霊を弔った。程なくその側に一本の松が芽生えた。葉が三つあるので「三つ葉の松塚」「関清治松」と言う。


これからは、玉島川沿いに歩きます。一昨日の「せっかくウオーク」でもここを歩きました。


黒田橋の欄干には、玉島川の鮎がデザインされています。玉島川は、古くは万葉集に詠われた歴史ある川で、神功皇后が鮎釣りをして戦勝を占ったという故事により、「鮎」の漢字発祥の地
とも言われています。


浜玉町市街地にやってきました。もうゴールまではあと少しです。子供たちが「ひきやま公園」へ案内しています。先ほどの無人の接待所の子供さんもここにいるのかな?
ここが5回目のチェックポイント。
ひきやま公園には、7月に行われる「浜崎祇園祭子供山笠」が展示されています。
浜崎祇園祭は、諏訪神社の祇園社(本殿左奥)の祭礼です。起源は明らかではありませんが、
江戸時代中期の宝暦三年(1753)に、漁師の網元・中村屋久兵衛が疫病退散、五穀豊饒を祈念して、博多櫛田宮の祇園山笠を模した山笠三台を造ったと伝えられています。(浜崎祇園祭HPより)



12:10 ゴールの浜玉公民館に到着しました。


参加者は、2日間で1190人でした。


2日目20kmのGPSです。