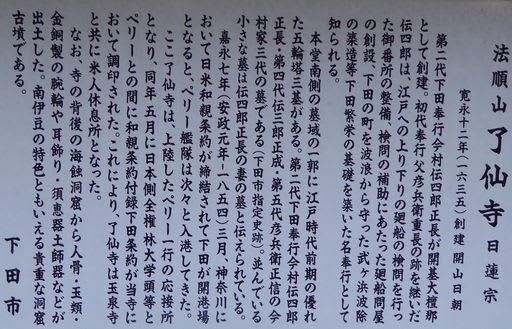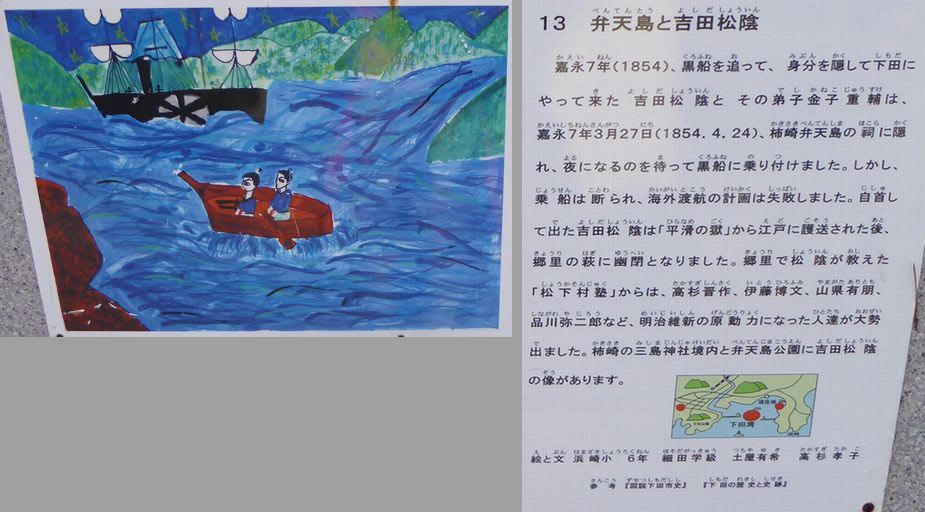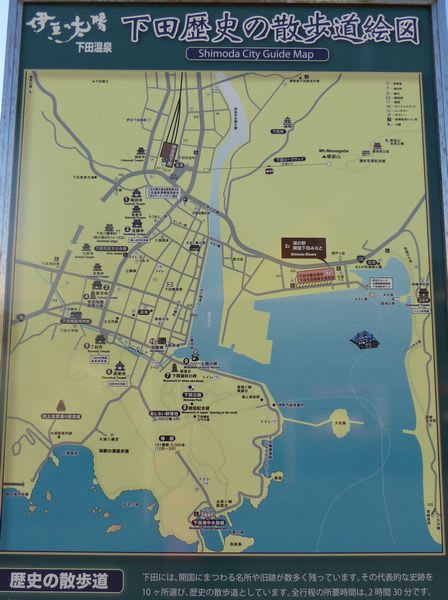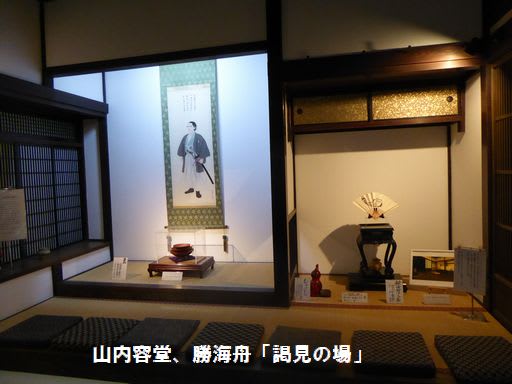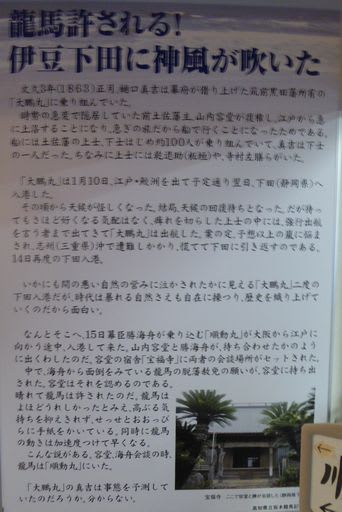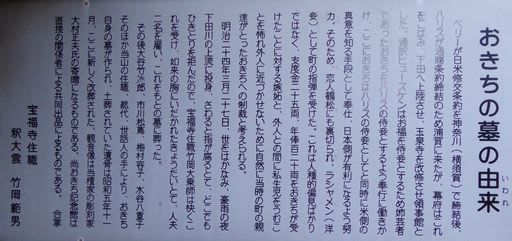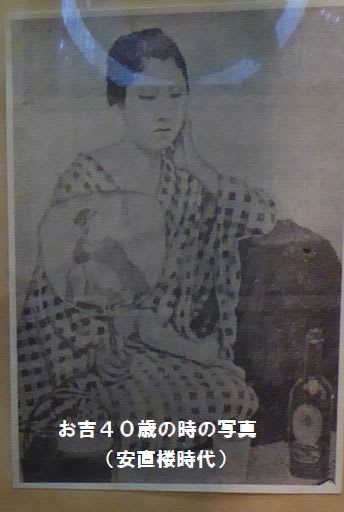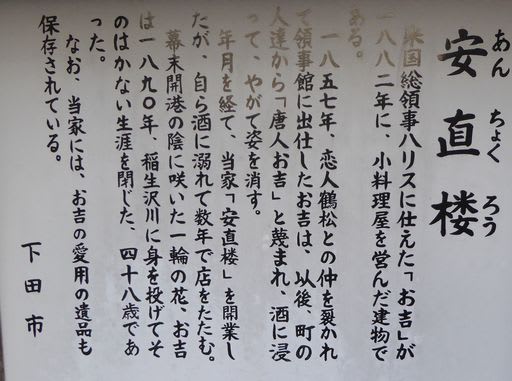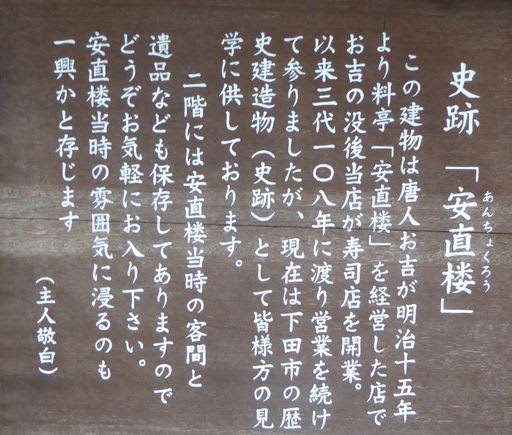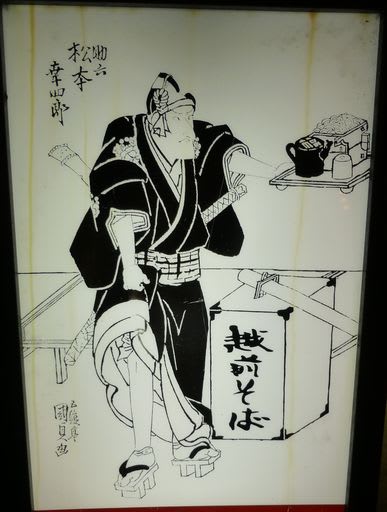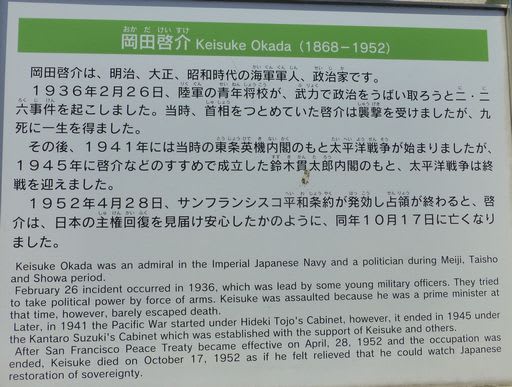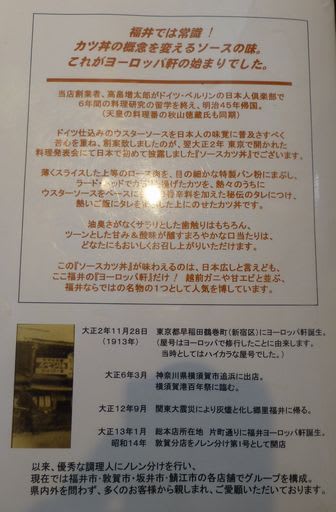以前所属していたSNSに福井・鯖江のYさんがおられました。
彼が紹介したのが、「橘 曙覧(たちばな あけみ)」。
橘 曙覧(1812~1868)は、幕末の福井に生まれた歌人、国学者です。心豊かな歌を詠み、「橘曙覧遺稿志濃夫廼舎歌集」を残しています。
歌の中で最も親しまれているのが、「独楽吟(どくらくぎん)」52首の連作。生活の中にある素朴な「たのしみ」を読み込んだ歌は、多くの人の共感を得ています。
ガイドブックを見ていたら、「橘曙覧記念文学館」があるそうで、ここに行ってみました。
九十九橋を渡り、愛宕坂を上っていくとこの記念館がありました。




入場料は、100円ですが、JAFカードを提示すると半額の50円です。残念ながら館内は撮影禁止です。
「独楽吟」
たのしみは 草のいほりの筵(むしろ)敷(しき)ひとりこゝろを靜めをるとき
たのしみは すびつのもとにうち倒れゆすり起(おこ)すも知らで寝し時
たのしみは 珍しき書(ふみ)人にかり始め一ひらひろげたる時
たのしみは 紙をひろげてとる筆の思ひの外に能くかけし時
たのしみは 百日(ももか)ひねれど成らぬ歌のふとおもしろく出(いで)きぬる時
たのしみは 妻子(めこ)むつまじくうちつどひ頭(かしら)ならべて物をくふ時
たのしみは 物をかゝせて善き價惜(をし)みげもなく人のくれし時
たのしみは 空暖(あたた)かにうち(はれ)し春秋の日に出でありく時
たのしみは 朝おきいでゝ昨日まで無(なか)りし花の咲ける見る時
たのしみは 心にうかぶはかなごと思ひつゞけて煙草(たばこ)すふとき
たのしみは 意(こころ)にかなふ山水のあたりしづかに見てありくとき
たのしみは 尋常(よのつね)ならぬ書(ふみ)に畫(ゑ)にうちひろげつゝ見もてゆく時
たのしみは 常に見なれぬ鳥の來て軒遠からぬ樹に鳴(なき)しとき
たのしみは あき米櫃に米いでき今一月はよしといふとき
たのしみは 物識人(ものしりびと)に稀にあひて古(いに)しへ今を語りあふとき
たのしみは 門(かど)賣りありく魚買(かひ)て煮(に)る鐺(なべ)の香を鼻に嗅ぐ時
たのしみは まれに魚煮て兒等(こら)皆がうましうましといひて食ふ時
たのしみは そゞろ讀(よみ)ゆく書(ふみ)の中に我とひとしき人をみし時
たのしみは 雪ふるよさり酒の糟あぶりて食(くひ)て火にあたる時
たのしみは 書よみ倦(うめ)るをりしもあれ聲知る人の門たゝく時
たのしみは 世に解(とき)がたくする書の心をひとりさとり得し時
たのしみは 錢なくなりてわびをるに人の來(きた)りて錢くれし時
たのしみは 炭さしすてゝおきし火の紅(あか)くなりきて湯の煮(にゆ)る時
たのしみは 心をおかぬ友どちと笑ひかたりて腹をよるとき
たのしみは 晝寝せしまに庭ぬらしふりたる雨をさめてしる時
たのしみは 晝寝目ざむる枕べにことことと湯の煮(にえ)てある時
たのしみは 湯わかしわかし埋火(うづみび)を中にさし置(おき)て人とかたる時
たのしみは とぼしきまゝに人集め酒飲め物を食へといふ時
たのしみは 客人(まらうど)えたる折しもあれ瓢(ひさご)に酒のありあへる時
たのしみは 家内(やうち)五人(いつたり)五たりが風だにひかでありあへる時
たのしみは 機(はた)おりたてゝ新しきころもを縫(ぬひ)て妻が着する時
たのしみは 三人の兒どもすくすくと大きくなれる姿みる時
たのしみは 人も訪ひこず事もなく心をいれて書(ふみ)を見る時
たのしみは 明日物くるといふ占(うら)を咲くともし火の花にみる時
たのしみは たのむをよびて門(かど)あけて物もて來つる使(つかひ)えし時
たのしみは 木芽(きのめ)煮(にや)して大きなる饅頭(まんぢゆう)を一つほゝばりしとき
たのしみは つねに好める燒豆腐うまく煮(に)たてゝ食(くは)せけるとき
たのしみは 小豆の飯の冷(ひえ)たるを茶漬(ちやづけ)てふ物になしてくふ時
たのしみは いやなる人の來たりしが長くもをらでかへりけるとき
たのしみは 田づらに行(ゆき)しわらは等が耒(すき)鍬(くは)とりて歸りくる時
たのしみは 衾(ふすま)かづきて物がたりいひをるうちに寝入(ねいり)たるとき
たのしみは わらは墨するかたはらに筆の運びを思ひをる時
たのしみは 好き筆をえて先(まづ)水にひたしねぶりて試(こころみ)るとき
たのしみは 庭にうゑたる春秋の花のさかりにあへる時々
たのしみは ほしかりし物錢ぶくろうちかたぶけてかひえたるとき
たのしみは 神の御國の民として神の(をしへ)をふかくおもふとき
たのしみは 戎夷(えみし)よろこぶ世の中に皇國(みくに)忘れぬ人を見るとき
たのしみは 鈴屋大人(すすのやうし)の後(のち)に生れその御諭(みさとし)をうくる思ふ時
たのしみは 數ある書(ふみ)を辛くしてうつし竟(をへ)つゝとぢて見るとき
たのしみは 野寺山里日をくらしやどれといはれやどりけるとき
たのしみは 野山のさとに人遇(あひ)て我を見しりてあるじするとき
たのしみは ふと見てほしくおもふ物辛くはかりて手にいれしとき
1994年6月、今上天皇、皇后がアメリカを訪問した折、ビル・クリントン大統領が歓迎の挨拶の中で、この中の歌の一首「たのしみは朝おきいでて昨日まで無かりし花の咲ける見る時」を
引用してスピーチをしたことで、その名と歌は再び脚光を浴びることになりました。
曙覧は、家族を大事にしていました。歌にもその思いが表れています。庭園に入ると幼くして亡くした三女健子との仲むつましい姿が銅像になっています。
曙覧は、この自分の家を「藁屋」と称しました。その藁屋に、彼の学を伝え聞いて1865年福井藩主「松平春嶽」が家老の「中根雪江」を案内に出仕を求めに
やってきました。春嶽は、いい人材をどんどん活用してきた方です。他にも熊本藩「横井小楠」を政治顧問として迎えたり、土佐の脱藩浪士「坂本龍馬」と接したり身分などもろとも
しませんでした。今日、学力テストが小、中学校で行われていますが、福井県は常に上位クラスです。このような春嶽の教えが現代にも活きているのでは、ないでしょうか?
因みに我が福岡県は、全国36位でした。




橘 曙覧記念文学館を出て、さらに愛宕坂を上ります。
5分ぐらいの所に「足羽(あすわ)神社」があります。この神社は、「継体天皇」をお祀りしています。
継体天皇は、応神天皇五世皇孫で越前の治水事業を行い、平野を開き諸産業を興された男大迹王(すおのみこと)が越前から第26代天皇として即位され
発たれる時に「末永くこの国の守り神とならん」と自ら生き御霊を鎮めて旅立たれました。それより継体天皇が主祭神として祀られています。
境内には、見事な樹齢360年の「しだれ桜」と参道の「タカオモミジ」は、天然記念物になっています。




足羽神社を上っていくと「継体天皇の像」があると聞き、また坂を上りました。(結構この坂はきついです)
長い階段を上り詰めた所に継体天皇像がありました。天皇は、越前平野の方を見られているそうです。また、山頂には古墳もありました。



足羽山を下りていくと「百坂」というのがあります。勾配がきつくゆっくり下りないと足を踏み外しそうです。
百坂を下りた森の中の左内公園内に「橋本左内の像」がありました。
橋本左内は、幕末の歴史物には、よく出てきます。実家は医者でしたが、のちに松平春嶽の側近として活躍し、将軍の後継問題では、一橋慶喜を推しましたが、
時の大老「井伊直助」らが推す紀州、徳川慶福(のちの家茂)と対立しました。(安政の大獄)
安政の大獄後、左内は捕えられ、斬首されました。時に26歳でした。左内や、龍馬などが生きていたら日本もまた違う行き方をしていたかもしれません。


駆け足で福井の町を見て廻りましたが、まだまだ見るべきところがあります。また次回福井に行ったときにでも訪ねたいと思います。
【追記】ホテルで地元の新聞を見ていますとこんな記事がありました。

福井にもクマがいるんですね。知りませんでした。