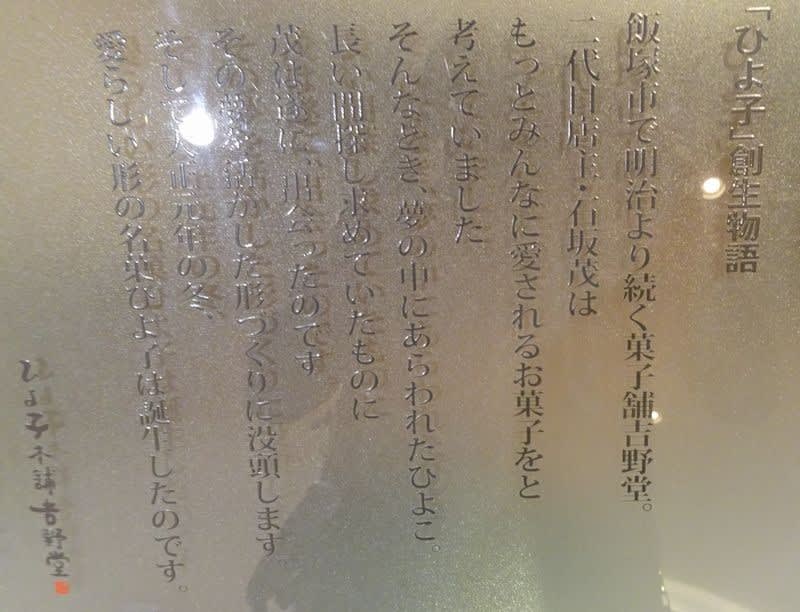5/12(火) 坂本駅に到着後、比叡山延暦寺に向かいました。
バスでケーブルカー乗り場まで行こうかと思いましたが、坂本の門前町の地図を見ると、歩いていきたくなりました。

坂本は比叡山に抱かれた扇状地。比叡山に源を発する大宮川や藤木川(権現川)が琵琶湖に注ぎ込み、目前には銀色に輝く琵琶湖が広がっています。
比叡山を挟んで京都市の東隣に位置し、琵琶湖に面していたことから、かつては東国や北陸からの物資運搬の重要幹線として大変重要な役割を果たした港町でもありました。
現在では世界文化遺産の比叡山延暦寺をはじめ日吉大社、西教寺を擁する門前町として、また延暦寺の里坊のまちとして、その歴史的価値が再評価されています。


お昼時ですが、中高生が下校しています。このあたりに学校があるのでしょうか?




公人屋敷(旧岡本邸)は、江戸時代に延暦寺の僧侶でありながら妻帯(さいたい)と名字帯刀(みょうじたいとう)を認められた「公人(くにん)」が住んでいた住居のひとつです。
内部が原型をとどめないほど改装されている住居が多い中、岡本家の家屋は全体に公人屋敷としての旧状をよくとどめた社寺関係大型民家の特徴を示す住宅として残されてきました。


1636年6月1日三代将軍徳川家光は、600年ぶりに新しい統一通貨をつくるよう幕府に命じました。
江戸の芝、浅草とここ近江坂本の三か所が銭造地に選ばれました。

平安の昔、最澄(伝教大師)が延暦二四年(805年)中国浙江省天台山から持ち帰った一握りの茶種。
比叡山の麓、大津の里に蒔かれ育ったのが日本茶の祖と謂われています。
平安時代初期に編纂された勅撰史書「日本後記」には「815年4月15日唐崎行幸の途中、嵯峨天皇が梵釈寺(大津市滋賀里)を過ぎたところで、永忠(えいちゅう)から茶のもてなしを受けた」と記述されており、これが、文献に残る日本での喫茶記録第一号となっています。この出来事は最澄上人がここ日吉茶園にお茶を植えてから、10年後だったそうです。
そういえば、福岡博多の崇福寺には、栄西禅師が中国(南宋)よりお茶の種子を請来し、茶樹の栽培、喫茶の方法を伝え、その普及に大いに貢献し、後に茶祖と称されました。
栄西禅師が京、栂尾高山寺の明恵上人に茶の種を分けてあげた話は有名な事です。




歩いていると、石積みが多いことに気づきます。延暦寺のふもと坂本町穴太(あのう)に残る石垣集団「穴太衆」があります。
穴太とは、大津市坂本付近に今も残る地名。室町時代の末頃、この地に居住し、延暦寺の土木営繕的な御用を勤めていた人々は「穴太衆」(あのうしゅう)と呼ばれ、織田信長の安土城を始め、
江戸時代初期、各地の石垣普請に従事した。大小の整形していない自然石を巧みに積み上げたもので、堅固に積むことから、城の石垣などに利用されたという。延暦寺の門前に開けた坂本の町には、
同寺の里坊が点在しているが、その町並み景観を特色付けているのが、この穴太衆積み石垣である。市指定史跡。





旧竹林院は、庭園が見事です。


福岡にも山王という地名に「日吉神社」がありますが、この日吉大社が本宮だったのですね。
日吉大社は、全国各地にある3,800余りの「山王(さんのう)さん」の総本宮。比叡山連峰 八王子山(牛尾山・378m)の麓に広がり、延暦寺の門前町坂本の鎮守神。
「山王七社」「山王二十一社」ともいわれ、摂社・末社が多くあります。創祀は古事記に記されるほど古く、地主神である大山咋神(おおやまくいのかみ)とその妻、
鴨玉依姫神(かもたまよりひめのかみ)を祀ったのが始まりです。その後、延暦寺の発展とともに整備されました。
境内は、東本宮と西本宮の2区域からなります。東本宮は神体山の八王子山(378m)に鎮座する大山咋神を祀ったものです。山頂付近には金大巌(こがねのおおいわ)と呼ばれる大きな
磐座(いわくら)や迫力ある懸造りの奥宮などがあります。
中世には、織田信長公の焼き討ちによって以前の構造物は、すべて灰燼に帰しましたが、その後復興によって今日の姿となっています。
西本宮は大津京遷都にあたって奈良県の三輪山より大己貴神(おおなむちのかみ)を勧請したもので、宇佐神宮の姫神をまつる宇佐宮、加賀国一宮である白山比咩神社から勧請した白山宮などが
あります。東本宮・西本宮ともに本殿は日吉造(ひえづくり)といわれる特殊な建築で、国宝です。
このほか、石の橋で重要文化財に指定されたのは珍しいといわれる日吉三橋(ひよしさんきょう)、猿の彫刻がある朱色の西本宮楼門、山王の「山」という文字を表した山王鳥居など、
重要文化財が多くあります。ご社殿の大半は織田信長による比叡山焼き討ち以後、江戸時代初期に再建、建立されたものです。
大宮川の渓流が流れる清風の森に、見事な建築美を誇る数多くの社殿が点在し、特に秋は周囲の紅葉に壮麗な社殿が映えてさらに美しい眺めになります。
また、「山王さん」と呼ばれて広く親しまれている例祭(山王祭)は、湖国三大祭の1つです。3月の第1日曜・27日・30日、4月3日・12日から15日に行われ、特に、4月13日の宵宮落し神事は
期間中最も勇壮な神事です。
〈国宝〉西本宮本殿 東本宮本殿
〈重文〉西本宮拝殿 東本宮拝殿 摂社樹下宮本殿及び拝殿 摂社宇佐宮本殿及び拝殿 摂社白山宮本殿及び拝殿 摂社牛尾宮本殿及び拝殿 摂社三宮宮本殿及び拝殿 西本宮楼門 日吉三橋
東本宮楼門 山王金銅装御輿 〈史跡・名勝〉日吉大社境内



今回は、時間がないので日吉神社見学はスルーしますが、いつか時間があるときに特に秋口に行ってみたいですね。



求法寺(ぐぼうじ)走井堂


学生さんの姿が多かったのは、ここに学校があったのですね。


ケーブルカー乗り場にやってきました。


運賃は、片道870円に値上がりしていました。
現在、気温は20度ですが、比叡山は16度と4度も低いです。


(比叡山延暦寺へ続く)