今回は一番人間に近いともいわれる『チンパンジー』の紹介です。

野毛山動物園のチンパンジーです
2016年9月4日にチンパンジーの赤ちゃん(男の子)が誕生しました。
子供のチンパンジーのかわいい姿を見たいと思ったのですが、母親が抱きかかえたまま見せてくれません。

チンパンジーは動物園で人気があるようです。
遠くから見ていると小柄に見えるが、立ち上がると1.5~1.7m程になり、人の身長とほぼ同じくらいの高さがあります。
ゴリラやオランウータンに比べると小さいですが、飼育下の大きい雄では、体重が90kgを超えるものもあるそうです。

チンパンジーはセネガルからガーナ、ナイジェリアなどの西アフリカの他、カメルーンやコンゴ、中央アフリカ、ウガンダ、タンザニアなどに分布し、生息地によっていくつかの亜種に別けられています。

知能も大変高く、道具を使うほか、簡単なものなら道具を作ることもできるようです。
今は子育てに必死なので、動こうともしませんでした。

動作や顔の表情は、人に近いものがあります。
毛色は亜種によって多少の違いがあり増すが、おおむね全身黒色で、顔には毛がなく、成獣では黒いか黒っぽい色をしています。

こちらはズーラシアのチンパンジーです。
ゴリラに比べると樹上性が強く、移動は地上ですることが多いです。
チンパンジーが後ろ足で立って歩くのは、物を持っている場合や、芸をするなどの特別な場合以外は、あまり見かけることはないそうです。
しかし、樹上や地上での行動はすばやく、跳躍力にもすぐれています。

動作を見ていると、他の動物より明らかに人に近い動きをしてくれます。
果実や木の葉、草の根、樹皮など、植物質のものを主に食べますが、昆虫やシロアリなどのほか、コウモリやリスなどの動物質のものも食べます。

チンパンジーの群れは、複数のオスと複数のメス、子どもを含む数10頭で構成されています。

チンパンジーは熱帯雨林などに生息していると思われていることが多いが、生息環境は多様で、サバンナや雑木林などのほか、標高2700m程の高地の森林にも生息しています。
昼間に活動し、夜間は高さ9~12m程の木の上に巣をつくって休むが、巣の高さは3m程のものから、中には40mを超える高さにつくられているものも見られます。
しばらく眺めていると、性質は陽気で、人と同じような笑いの表情を見せ、声をたてて笑うこともあります。

次回は『オオツノヒツジ』の紹介です。

野毛山動物園のチンパンジーです
2016年9月4日にチンパンジーの赤ちゃん(男の子)が誕生しました。
子供のチンパンジーのかわいい姿を見たいと思ったのですが、母親が抱きかかえたまま見せてくれません。

チンパンジーは動物園で人気があるようです。
遠くから見ていると小柄に見えるが、立ち上がると1.5~1.7m程になり、人の身長とほぼ同じくらいの高さがあります。
ゴリラやオランウータンに比べると小さいですが、飼育下の大きい雄では、体重が90kgを超えるものもあるそうです。

チンパンジーはセネガルからガーナ、ナイジェリアなどの西アフリカの他、カメルーンやコンゴ、中央アフリカ、ウガンダ、タンザニアなどに分布し、生息地によっていくつかの亜種に別けられています。

知能も大変高く、道具を使うほか、簡単なものなら道具を作ることもできるようです。
今は子育てに必死なので、動こうともしませんでした。

動作や顔の表情は、人に近いものがあります。
毛色は亜種によって多少の違いがあり増すが、おおむね全身黒色で、顔には毛がなく、成獣では黒いか黒っぽい色をしています。

こちらはズーラシアのチンパンジーです。
ゴリラに比べると樹上性が強く、移動は地上ですることが多いです。
チンパンジーが後ろ足で立って歩くのは、物を持っている場合や、芸をするなどの特別な場合以外は、あまり見かけることはないそうです。
しかし、樹上や地上での行動はすばやく、跳躍力にもすぐれています。

動作を見ていると、他の動物より明らかに人に近い動きをしてくれます。
果実や木の葉、草の根、樹皮など、植物質のものを主に食べますが、昆虫やシロアリなどのほか、コウモリやリスなどの動物質のものも食べます。

チンパンジーの群れは、複数のオスと複数のメス、子どもを含む数10頭で構成されています。

チンパンジーは熱帯雨林などに生息していると思われていることが多いが、生息環境は多様で、サバンナや雑木林などのほか、標高2700m程の高地の森林にも生息しています。
昼間に活動し、夜間は高さ9~12m程の木の上に巣をつくって休むが、巣の高さは3m程のものから、中には40mを超える高さにつくられているものも見られます。
しばらく眺めていると、性質は陽気で、人と同じような笑いの表情を見せ、声をたてて笑うこともあります。

次回は『オオツノヒツジ』の紹介です。





















































































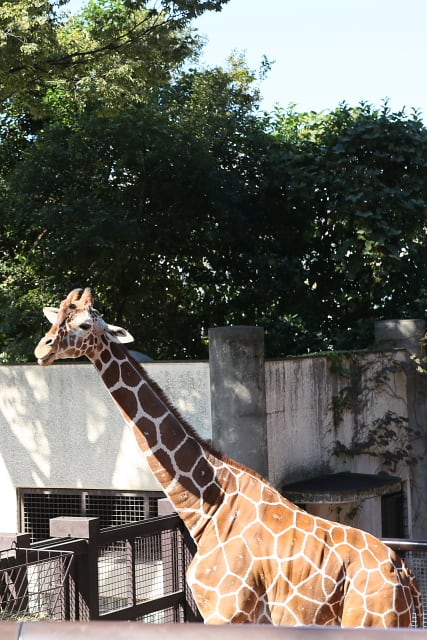











































































 )
)