1609年薩摩軍は3千ほどの兵と千艘余の船で琉球を攻め、首里城を占拠した。
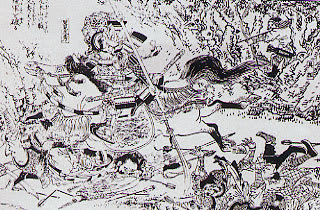
写真は、薩摩軍による琉球侵攻の絵図。
琉球侵攻の理由は、琉球が奥州に漂着した琉球船送還について、江戸幕府へ謝礼の使いを実行しなかったことや豊臣秀吉の朝鮮出兵時における兵糧米の要求を断ったことなどが挙げられている。

写真は、沖縄本島北山・“今帰仁城”跡の光景。
薩摩軍は奄美の島々を難なく制した後、沖縄本島の北部前線基地であった“今帰仁城”を陥落させ、その後首里・那覇を攻めたが、往時の琉球でも戦国時代を戦い抜いてきた薩摩軍に抗する力はなく、簡単に降伏させられた。
首里城は占拠され、時の“尚寧王”や家臣たちは捕虜の身となり、薩摩経由で駿府・江戸まで連れて行かれた。
その後帰国を許されたが、尚寧王は薩摩への忠誠を誓う起請文へ署名させられ、琉球は薩摩藩を介した幕藩体制下に組込まれていた。
以降琉球王国は薩摩藩の徹底的な監視の下に、実質的には薩摩藩の支配下に置かれながら、形式的には独立国として清国との朝貢体制を維持することが至上命令となった。清国や周辺諸国に対しては、交易のメリットを維持するために、朝貢体制下の琉球王国として振舞わされた。
このように琉球王国は約270年間にわたり、表向きは中国の支配下にありながら、内実は薩摩と徳川幕府の従属国であると云う微妙な国際関係に中で存続していた。
やがて明治維新によって成立した日本政府は、1879年軍隊を派遣して首里城から“国王尚泰”を追放し、沖縄県の設置を宣言したことにより、琉球王国は滅亡した。
第二尚氏王統は、初代“尚円王”から数えて19代目の“尚泰王”まで約400年の長きにわたり存続したが・・・・・。
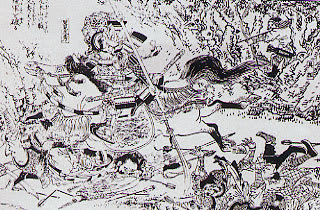
写真は、薩摩軍による琉球侵攻の絵図。
琉球侵攻の理由は、琉球が奥州に漂着した琉球船送還について、江戸幕府へ謝礼の使いを実行しなかったことや豊臣秀吉の朝鮮出兵時における兵糧米の要求を断ったことなどが挙げられている。

写真は、沖縄本島北山・“今帰仁城”跡の光景。
薩摩軍は奄美の島々を難なく制した後、沖縄本島の北部前線基地であった“今帰仁城”を陥落させ、その後首里・那覇を攻めたが、往時の琉球でも戦国時代を戦い抜いてきた薩摩軍に抗する力はなく、簡単に降伏させられた。

首里城は占拠され、時の“尚寧王”や家臣たちは捕虜の身となり、薩摩経由で駿府・江戸まで連れて行かれた。
その後帰国を許されたが、尚寧王は薩摩への忠誠を誓う起請文へ署名させられ、琉球は薩摩藩を介した幕藩体制下に組込まれていた。
以降琉球王国は薩摩藩の徹底的な監視の下に、実質的には薩摩藩の支配下に置かれながら、形式的には独立国として清国との朝貢体制を維持することが至上命令となった。清国や周辺諸国に対しては、交易のメリットを維持するために、朝貢体制下の琉球王国として振舞わされた。

このように琉球王国は約270年間にわたり、表向きは中国の支配下にありながら、内実は薩摩と徳川幕府の従属国であると云う微妙な国際関係に中で存続していた。
やがて明治維新によって成立した日本政府は、1879年軍隊を派遣して首里城から“国王尚泰”を追放し、沖縄県の設置を宣言したことにより、琉球王国は滅亡した。

第二尚氏王統は、初代“尚円王”から数えて19代目の“尚泰王”まで約400年の長きにわたり存続したが・・・・・。







































































































