昨日は、茨城県の結城市に行って来ました。
結城市は、2013年11月30日に仕事で行った事があります。
その時は車で行ったのですが、街中を見た時に良い街だなぁと思い、
いずれ行ってみようと思っていた街です。
ここのところ、新型コロナウイルスの外出自粛で、出掛けられませんでしたし、
今月予定されていた大人の休日俱楽部パスは中止になっています。
そんな事で、自粛が解除になっている近県から行こうかと思った次第です。
結城市には宇都宮市からJR宇都宮線で小山に行って、水戸線に乗り換えます。
電車に乗っている時間は30分程度ですが、水戸線の本数が少ないので不便です。
車で行く事も考えたのですが、何となく出掛けた雰囲気になるのは電車です。
午前8時33分に宇都宮駅を出て、結城駅に着いたのは9時15分でした。
本の僅かの乗車時間でしたが^^
結城市は結城紬で有名ですが、僕は余り織物に興味がありません。
鎌倉時代から城下町の基礎を形成している古い城下町です。
結城氏の初代当主である結城朝光は小山氏の出身ですが、
母親の寒川尼が源頼朝の乳母だった事などから、
鎌倉幕府の有力な御家人になります。
室町時代に幕府と争い、
結城合戦と呼ばれる内乱を起こして敗れたため、衰退しますが、
戦国末期に、徳川家康の次男秀康が結城氏を継いで一時盛んになります。
秀康が越前に移封された後、
少し間が空きますが水野家が城主となって明治維新まで続きました。
駅から歩いて、
地元の方から金仏と呼ばれている阿弥陀如来像のある時宗の常光寺に行きました。
この寺は遊行上人二世の他阿が創建したと伝えられる寺です。
次に結城朝光の墓のある称名寺に行きました。
その後、市の中心部にある健田須賀神社に寄りました。
7年前に行った時の会場が神社の近くにあるのに驚きました。
そこから、住吉神社に行ったら、社殿の塗装が終わったばかりとの事で、
地元の方が様子を見に来ていました。
その方から教わって、1907年(明治40年)に行われた
陸軍特別大演習の時に、大本営が置かれた跡を見て、
結城城址公園の近くの玉日姫の墓に行きました。
玉日姫は、色々な説がありますが、親鸞の妻と伝えられる女性です。
結城城址公園は余り昔を偲ぶ遺跡などはありませんでしたが、
紫陽花が咲いていて綺麗でした。
城址公園から、那須の殺生石の魔力を取り除いたと言われる源翁和尚の墓を見て、
和尚が創建した安穏寺に行きました。
この寺は、本堂の建設中で、鴟尾のある立派な本堂になりそうです。
そこから、日蓮宗の妙国寺に寄ってから弘経(ぐぎょう)寺に行きました。
この寺は、結城秀康が早逝した娘の菩提を弔うために建てた寺で、
一度も焼失していないので、創建当時の姿を伝える寺です。
さすがに本堂は迫力のある建物だと思いました。
最後に孝顕寺に寄りましたが、ここも本堂は建設されたばかりの感じでした。
少し急ぎ過ぎたかなと思いながら歩きましたが、
結城の街中には、明治時代頃からの見世蔵が何軒も残っていました。
川越のような集積はありませんが、
まだ実際に使われている蔵が多く、歴史を感じました。
回った寺院の多くも立派な山門があって、見応えがありました。
また、江戸時代の与謝蕪村が、10年近く滞在した事から、
市内各所に句碑が建てられていました。
いずれにしても、結城市は思ったより良い街でした。
これだけ古い建物が残っているのは、多分戦災に遭わなかったからだと思います。
今回行けなかった所もありますので、出来ればまた行ってみたいと思いました。
昨日の写真をアップしましたので、宜しければご覧下さい。
http://photozou.jp/photo/album/2882708
結城市は、2013年11月30日に仕事で行った事があります。
その時は車で行ったのですが、街中を見た時に良い街だなぁと思い、
いずれ行ってみようと思っていた街です。
ここのところ、新型コロナウイルスの外出自粛で、出掛けられませんでしたし、
今月予定されていた大人の休日俱楽部パスは中止になっています。
そんな事で、自粛が解除になっている近県から行こうかと思った次第です。
結城市には宇都宮市からJR宇都宮線で小山に行って、水戸線に乗り換えます。
電車に乗っている時間は30分程度ですが、水戸線の本数が少ないので不便です。
車で行く事も考えたのですが、何となく出掛けた雰囲気になるのは電車です。
午前8時33分に宇都宮駅を出て、結城駅に着いたのは9時15分でした。
本の僅かの乗車時間でしたが^^
結城市は結城紬で有名ですが、僕は余り織物に興味がありません。
鎌倉時代から城下町の基礎を形成している古い城下町です。
結城氏の初代当主である結城朝光は小山氏の出身ですが、
母親の寒川尼が源頼朝の乳母だった事などから、
鎌倉幕府の有力な御家人になります。
室町時代に幕府と争い、
結城合戦と呼ばれる内乱を起こして敗れたため、衰退しますが、
戦国末期に、徳川家康の次男秀康が結城氏を継いで一時盛んになります。
秀康が越前に移封された後、
少し間が空きますが水野家が城主となって明治維新まで続きました。
駅から歩いて、
地元の方から金仏と呼ばれている阿弥陀如来像のある時宗の常光寺に行きました。
この寺は遊行上人二世の他阿が創建したと伝えられる寺です。
次に結城朝光の墓のある称名寺に行きました。
その後、市の中心部にある健田須賀神社に寄りました。
7年前に行った時の会場が神社の近くにあるのに驚きました。
そこから、住吉神社に行ったら、社殿の塗装が終わったばかりとの事で、
地元の方が様子を見に来ていました。
その方から教わって、1907年(明治40年)に行われた
陸軍特別大演習の時に、大本営が置かれた跡を見て、
結城城址公園の近くの玉日姫の墓に行きました。
玉日姫は、色々な説がありますが、親鸞の妻と伝えられる女性です。
結城城址公園は余り昔を偲ぶ遺跡などはありませんでしたが、
紫陽花が咲いていて綺麗でした。
城址公園から、那須の殺生石の魔力を取り除いたと言われる源翁和尚の墓を見て、
和尚が創建した安穏寺に行きました。
この寺は、本堂の建設中で、鴟尾のある立派な本堂になりそうです。
そこから、日蓮宗の妙国寺に寄ってから弘経(ぐぎょう)寺に行きました。
この寺は、結城秀康が早逝した娘の菩提を弔うために建てた寺で、
一度も焼失していないので、創建当時の姿を伝える寺です。
さすがに本堂は迫力のある建物だと思いました。
最後に孝顕寺に寄りましたが、ここも本堂は建設されたばかりの感じでした。
少し急ぎ過ぎたかなと思いながら歩きましたが、
結城の街中には、明治時代頃からの見世蔵が何軒も残っていました。
川越のような集積はありませんが、
まだ実際に使われている蔵が多く、歴史を感じました。
回った寺院の多くも立派な山門があって、見応えがありました。
また、江戸時代の与謝蕪村が、10年近く滞在した事から、
市内各所に句碑が建てられていました。
いずれにしても、結城市は思ったより良い街でした。
これだけ古い建物が残っているのは、多分戦災に遭わなかったからだと思います。
今回行けなかった所もありますので、出来ればまた行ってみたいと思いました。
昨日の写真をアップしましたので、宜しければご覧下さい。
http://photozou.jp/photo/album/2882708










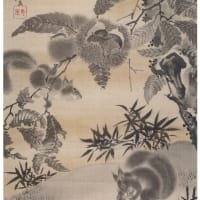














私も結城市に出掛けて見て、なんでこんな所に玉日の墓と称するものが在るのだろうか?と不思議に感じましたね。結城合戦も絵巻物があり興味深い。コロナが終息したら、また出掛けてみたい所です。
井頭山人さんのお住まいからは結城は近いでしょうね。
今回初めて、ゆっくりと街中を歩きましたが、良い街だと思いました。
玉日姫の墓には驚きました。
帰宅後、少し調べてみたのですが、
玉日姫と恵信尼は同一人物との説もあるようです。
玉日姫が九条兼実の娘とありましたので、どのような経過から結婚したのかと思いましたが、法然が関係したとの説があるのですね。
面白いと思いました。
ともかく、結城は面白かったです。
なるほど。
玉日と恵信尼を同一人物にしたがっているのは本願寺ですか。
色々な思惑があるのでしょうね。