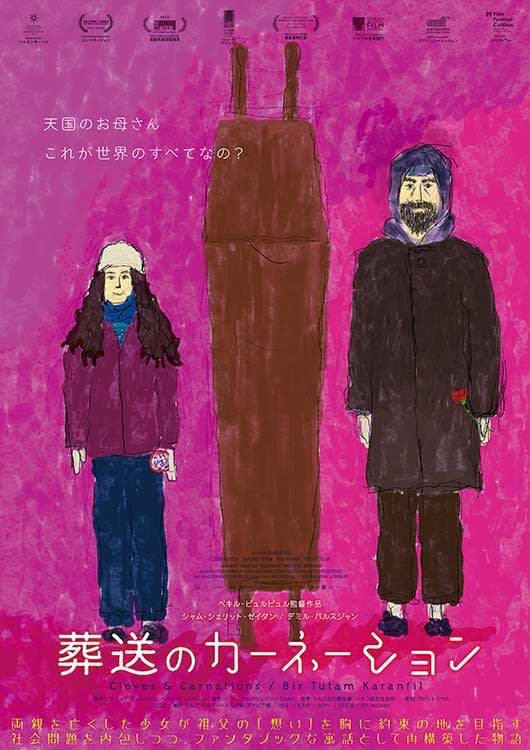映画はとても良かったけど、うーん、
これはわたしは「オールドボーイ」や「お嬢さん」ほどは好きじゃないかなぁ。
以前、ポーランド映画「イーダ」を撮った監督の、次の映画を楽しみにしてたのに
それが2人の男女間を描き込んだ映画「コールドウォー」で、
そっちはなんとなくつまんなかったことを思い出した。
メロドラマは好きなんだけど、男女間の閉じた部分が大きくて男女の気持ちがお互いだけに向いてて
息苦しい感じの恋愛物が好きじゃないのかも。
「別れる決心」は中国映画とかで見るベタでアナログな情感のかわりに
賢くて上手い技巧が見えてしまう。計算され尽くした隙のあり方(なさ)が窮屈なのよね。
エログロ暴力アリの映画だとうますぎても舌を巻くだけだけど
恋愛もの、メロドラマは巧すぎると、むしろなんかついていけない感じがする。
ちょろっと計算外の安っぽいゆるい感傷が見えた方が落ち着いてみられるのです。
パク・チャヌク巧すぎ問題。
お話は、
「男が山頂から転落死した事件を追う刑事ヘジュンと、被害者の妻ソレは捜査中に出会った。取り調べが進む中で、お互いの視線は交差し、それぞれの胸に言葉にならない感情が湧き上がってくる。いつしかヘジュンはソレに惹かれ、彼女もまたヘジュンに特別な想いを抱き始める。やがて捜査の糸口が見つかり、事件は解決したかに思えた。しかし、それは相手への想いと疑惑が渦巻く“愛の迷路”のはじまりだった・・・・・・。」公式サイトより
監督の言葉「本作は、大人のための映画です。喪失の物語を悲劇的なものとして語るのではなく、繊細さとエレガンスとユーモアをもって表現しようとしました。大人たちに語りかけるような形で…」
俳優の演技、心理描写やそれぞれの愛の描き方以外にも、演出から音楽、風景、インテリア、
小道具の使い方まで、画面の隅々にまで考えられている丁寧な映画でした。
そして二十歳の時のわたしが見たとしても二十歳なりに良さはわかっただろうけど、
やっぱり今の方がずっとよくわかるなと確信がある。
たとえば、映画の後半、主人公の「崩壊した」というセリフに、
はっと、わたしの気持ちは立ち止まったんだけど、(上に貼った予告編の中にもあります)
「崩壊」という言葉はなかなか大きいし手強い。
人が自分自身について「崩壊」という大きな言葉を使うことは日常の中ではあまりない。
でも、わたしの大学の卒論はフィッツジェラルドの短編「崩壊」だったのです。
それ以来35年も経って、この「別れる決心」の主人公のセリフ「崩壊した」を聞き、
普通に流れていた外の世界がいきなり全部止まったような気持ちにさせられるとは。
たとえば気持ちが弱って日に何度も理由なく涙ぐむようになるとようなときには、
実はもう35年前から自分はすっかり「崩壊」してて、
それを何十年もかけてわかって行ってる最中でしかなかったのでは?
その頃からずっと消化試合しかしてないのでは?と思うけど、
こういうのは全部フィッツジェラルドの影響だろうな。
この映画を見ていて、そうして世界が止まっていた瞬間に、
わたし自身の過去のある関係が心の中にゆらゆらと浮かびあがり、
それがそのときのわたしの静止した世界で唯一動いているものに思えたりした。
自分だけでなく相手も崩壊させてしまったかもしれない関係のことを思い出したのでした。
映画の中では、自分のよって立つところのものを取り返しがつかないほど損なってしまった、
という文脈で言われる台詞ですが、
よって立つところのもの、誇りの元、矜持、つまりアイデンティティのことよね。
自分がもう元の自分ではいられないと知った男の台詞だった。
アイデンティティの崩壊は破滅。それで、この男は遠くへ行き静かな破滅の日を送ります。
ところが、またその「崩壊」の元になった女と再会してしまい、また運命が動き出す。
ヒロインが、とてもミステリアスなんだけど、思わせぶりな人が好きじゃないので
あまり好感は持てず、あっさりメロメロになる主人公に、
男ってアホやな〜などと思いました。(主語でかくてすみません笑)
監督のいう通り繊細さとエレガンスとユーモアのある映画なのに、馬鹿な感想ですみません。
でも大人の恋愛のわかる人には、誰にでもおすすめしたい名作ではありました。