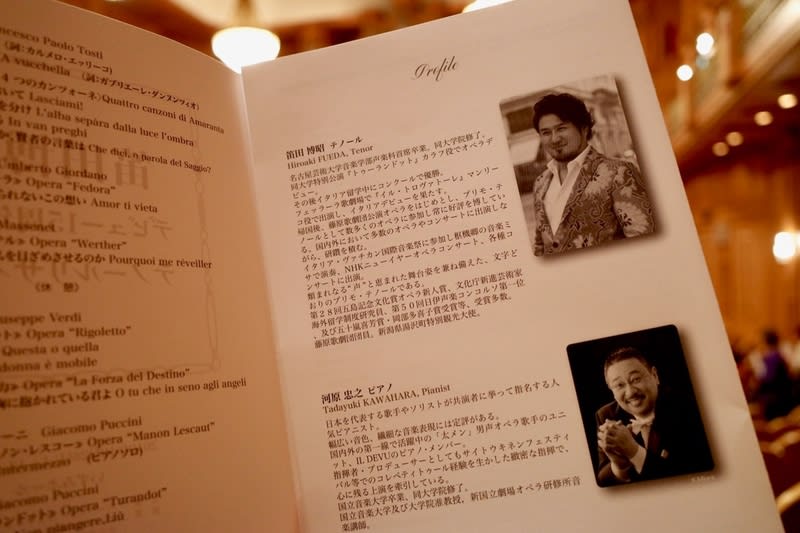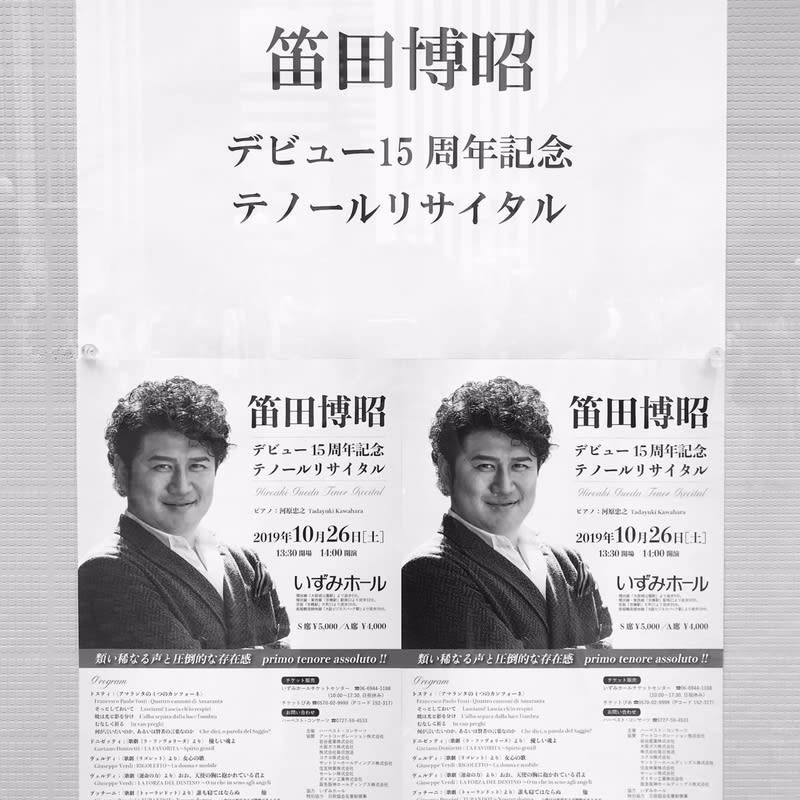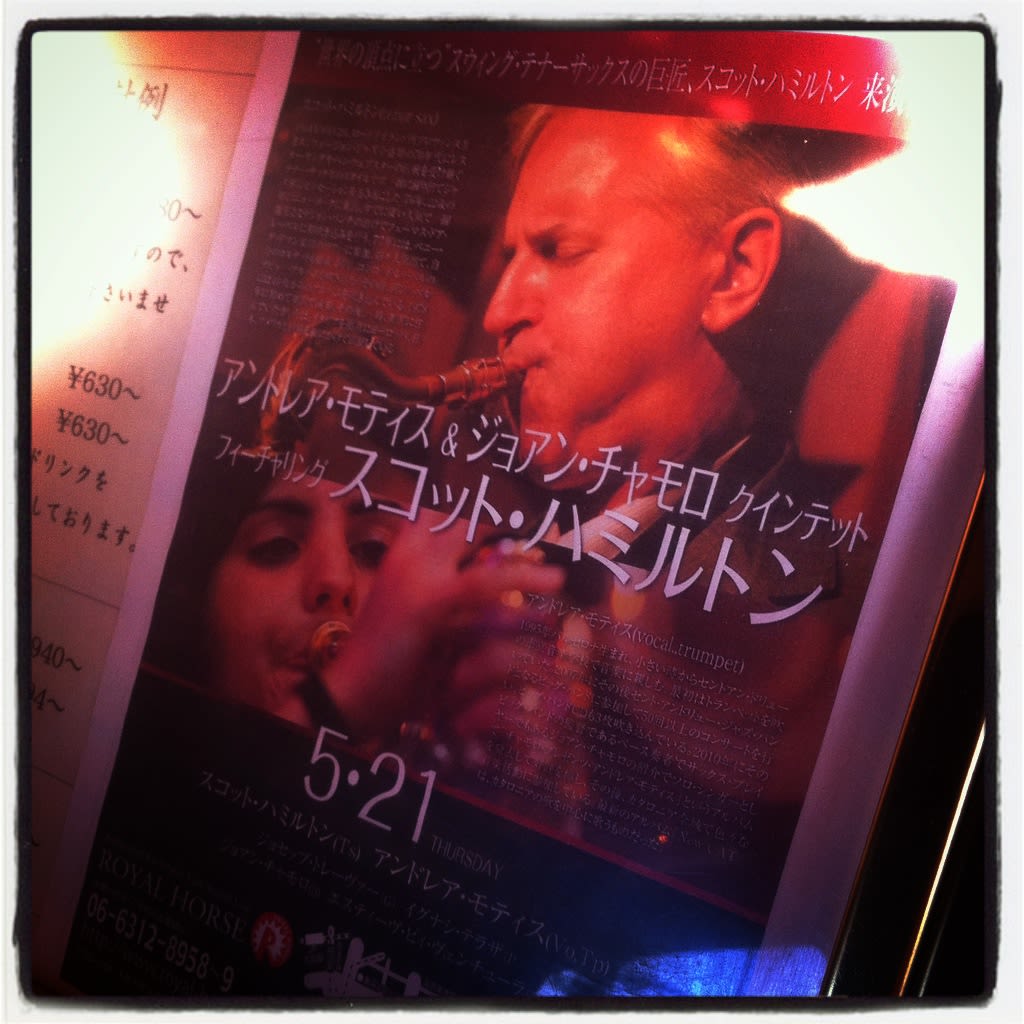音があまり拾えなくて音楽がわからないんだと思ってたけど
多彩な音を全部拾ってしまうと情報量の多さに脳が固まってしまうから
そうなる前にブロックしてしまってるのかもしれない、と気付きました。
音楽に対して情報量のキャパがすごく低いのだと思う。
ずっと聴いてるとすぐいっぱいになって処理できなくなって、
処理できないと音楽の判断もできないし、音楽としての自分の判断も持てない。
そうして40歳くらいにはもう新しい音楽が聴けなくなってた。
鬱や年をとったことも関係あると思うけど、情報処理にはエネルギーが必要で
それがかなり足りなくなってたんですね。
それで音楽の中身を把握するのが苦手。
音が入ってこないと聴こえてるんだけど、なんかよくわからなくなるのです。
でも数日ぶりとか数週間ぶりに音楽を聴くと、特に好きなわけじゃない曲でも、
なんて美しいんだと聴き入ってしまう。
今聞いてるのはモーツァルトのヴァイオリンソナタ。
この時代のソナタはピアノが主でバイオリンは伴奏程度のものだったと言われても、
バイオリンを美しいなぁと聴いてしまう。
ピアノよりバイオリンやチェロの方がわたしの耳に入りやすいのはピアノの音の多さや広さが、
わたしの音楽に弱い脳では処理がついて行けないのよね多分。
音楽のわからない人です。
もうすっかりあきらめて、今はほぼクラシックしか聴きません。
クラシックはわからないものもその気になるまで待ってくれるし
その気になったらじっくり聴いて、何年もかけてもわかるようになれる。
多彩な音を全部拾ってしまうと情報量の多さに脳が固まってしまうから
そうなる前にブロックしてしまってるのかもしれない、と気付きました。
音楽に対して情報量のキャパがすごく低いのだと思う。
ずっと聴いてるとすぐいっぱいになって処理できなくなって、
処理できないと音楽の判断もできないし、音楽としての自分の判断も持てない。
そうして40歳くらいにはもう新しい音楽が聴けなくなってた。
鬱や年をとったことも関係あると思うけど、情報処理にはエネルギーが必要で
それがかなり足りなくなってたんですね。
それで音楽の中身を把握するのが苦手。
音が入ってこないと聴こえてるんだけど、なんかよくわからなくなるのです。
でも数日ぶりとか数週間ぶりに音楽を聴くと、特に好きなわけじゃない曲でも、
なんて美しいんだと聴き入ってしまう。
今聞いてるのはモーツァルトのヴァイオリンソナタ。
この時代のソナタはピアノが主でバイオリンは伴奏程度のものだったと言われても、
バイオリンを美しいなぁと聴いてしまう。
ピアノよりバイオリンやチェロの方がわたしの耳に入りやすいのはピアノの音の多さや広さが、
わたしの音楽に弱い脳では処理がついて行けないのよね多分。
音楽のわからない人です。
もうすっかりあきらめて、今はほぼクラシックしか聴きません。
クラシックはわからないものもその気になるまで待ってくれるし
その気になったらじっくり聴いて、何年もかけてもわかるようになれる。