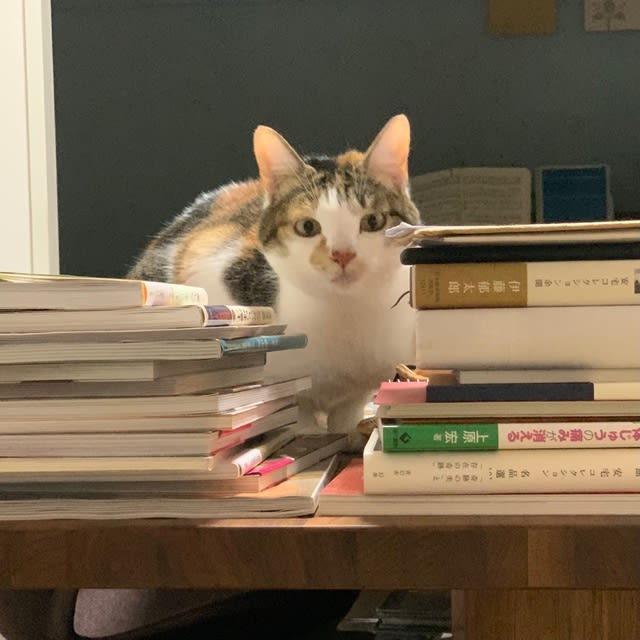スイスワインを輸入している友達が月に一度毎回テーマを決めて
間借りワインバーをやるんだけど、そのテーマが
建築家だったり食べ物だったり映画だったりの中、
今回は原田マハの「楽園のカンヴァス」。
小説の舞台がスイスのバーゼルで、その友達はバーゼルにいたことがあったのでした。
バーではバーゼルの話を写真も見せてもらいながら色々聞いて楽しかったです。
この本は文庫本がうちの本棚にも積読されてたので、
いい機会だと読み始めて割とすぐに読み終わりました。
ルソーの隠されてきた絵に関するミステリー、みたいな話で
普段ミステリーっぽいモノをあまり読まないけど、逆にそれが新鮮だったかも。
原田マハさんの小説は文学としては物足りない作家だけど
美術をテーマにした小説の一つのジャンルを自分のものにしてるのはすごいし面白いと思う。
ニューヨーク近代美術館のキュレーター、ティム・ブラウンはある日スイスの大邸宅に招かれる。そこで見たのは巨匠ルソーの名作「夢」に酷似した絵。持ち主は正しく真贋判定した者にこの絵を譲ると告げ、手がかりとなる謎の古書を読ませる。リミットは7日間。ライバルは日本人研究者・早川織絵。ルソーとピカソ、二人の天才がカンヴァスに籠めた想いとは――。山本周五郎賞受賞作。
(新潮社のサイトより)
ルソーは日曜画家の税関吏と紹介され、正規に勉強していない特徴的、個性的な絵で
素朴派というグループに分類される画家。
最近ではヘタウマと評されたりもしてて、
確かにわたしも若い頃はそういう解説や批評を読んでなるほどと思っていたけど
今となっては心底、そういう説明はもうどうでもいい。
ああ、言葉もいらずにただ感動して感じ味わうって、
一通りの言葉や思考を通ってきてやっとできることなんだなぁと、
ルソーの絵を、年と共にどんどん好きになってきて、そう思う。
そういえば高校の時、美術の授業で油絵の模写をやらされて、
絵は好きな絵を選べたのでわたしはデュフィで、友だちはルソーを選んだ。
授業としては油絵の基本を知りながら慣れようという趣旨だったはずだけど、
デュフィやルソーは基本を学ぶには変化球すぎたよね。
でも好きに選ばせてくれる先生だった。今思うといい先生だったな。
その時にも、ルソーの良さも少しはわかるつもりだったけど、
かといってそんなに好きとは思えなくて、それを選ぶ友だちを面白い子だなぁと思ってた。
それがその時から40年経って、今のわたしはデュフィよりルソーの方が好きかもしれない。
デュフィのセンスや洒脱さや自由で晴れやかな色彩より、
ルソーの真面目で不器用な感じが好ましいのよね。
小説を読んで、ますますルソーを好ましく思いようになった。
間借りワインバーをやるんだけど、そのテーマが
建築家だったり食べ物だったり映画だったりの中、
今回は原田マハの「楽園のカンヴァス」。
小説の舞台がスイスのバーゼルで、その友達はバーゼルにいたことがあったのでした。
バーではバーゼルの話を写真も見せてもらいながら色々聞いて楽しかったです。
この本は文庫本がうちの本棚にも積読されてたので、
いい機会だと読み始めて割とすぐに読み終わりました。
ルソーの隠されてきた絵に関するミステリー、みたいな話で
普段ミステリーっぽいモノをあまり読まないけど、逆にそれが新鮮だったかも。
原田マハさんの小説は文学としては物足りない作家だけど
美術をテーマにした小説の一つのジャンルを自分のものにしてるのはすごいし面白いと思う。
ニューヨーク近代美術館のキュレーター、ティム・ブラウンはある日スイスの大邸宅に招かれる。そこで見たのは巨匠ルソーの名作「夢」に酷似した絵。持ち主は正しく真贋判定した者にこの絵を譲ると告げ、手がかりとなる謎の古書を読ませる。リミットは7日間。ライバルは日本人研究者・早川織絵。ルソーとピカソ、二人の天才がカンヴァスに籠めた想いとは――。山本周五郎賞受賞作。
(新潮社のサイトより)
ルソーは日曜画家の税関吏と紹介され、正規に勉強していない特徴的、個性的な絵で
素朴派というグループに分類される画家。
最近ではヘタウマと評されたりもしてて、
確かにわたしも若い頃はそういう解説や批評を読んでなるほどと思っていたけど
今となっては心底、そういう説明はもうどうでもいい。
ああ、言葉もいらずにただ感動して感じ味わうって、
一通りの言葉や思考を通ってきてやっとできることなんだなぁと、
ルソーの絵を、年と共にどんどん好きになってきて、そう思う。
そういえば高校の時、美術の授業で油絵の模写をやらされて、
絵は好きな絵を選べたのでわたしはデュフィで、友だちはルソーを選んだ。
授業としては油絵の基本を知りながら慣れようという趣旨だったはずだけど、
デュフィやルソーは基本を学ぶには変化球すぎたよね。
でも好きに選ばせてくれる先生だった。今思うといい先生だったな。
その時にも、ルソーの良さも少しはわかるつもりだったけど、
かといってそんなに好きとは思えなくて、それを選ぶ友だちを面白い子だなぁと思ってた。
それがその時から40年経って、今のわたしはデュフィよりルソーの方が好きかもしれない。
デュフィのセンスや洒脱さや自由で晴れやかな色彩より、
ルソーの真面目で不器用な感じが好ましいのよね。
小説を読んで、ますますルソーを好ましく思いようになった。