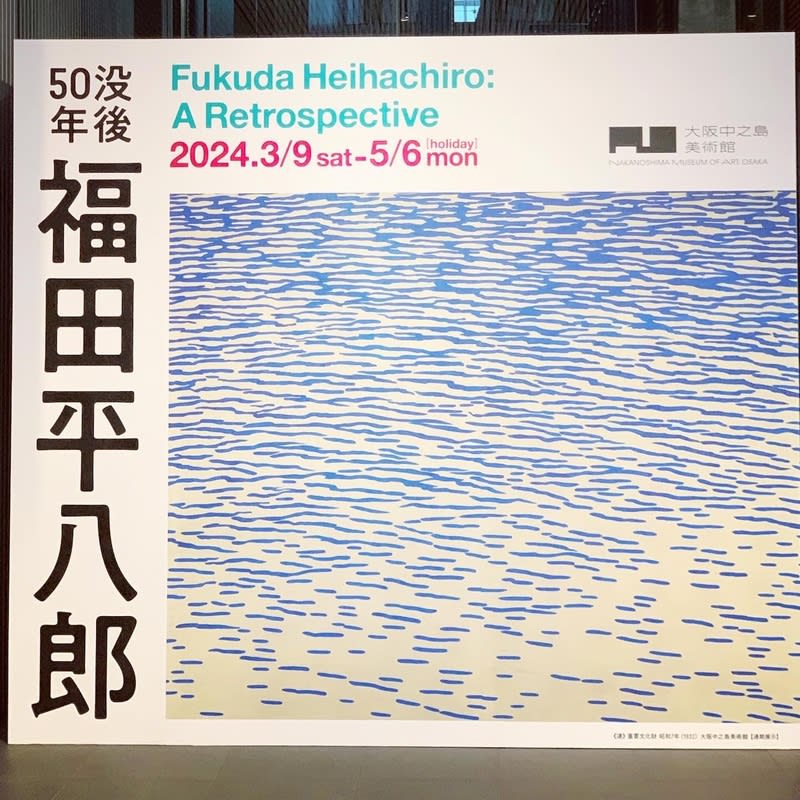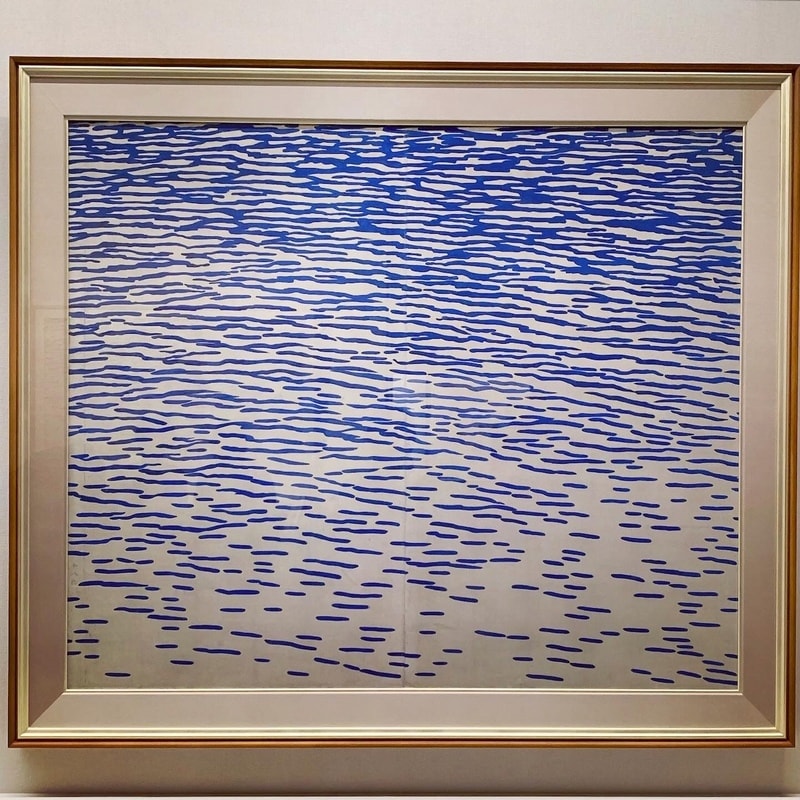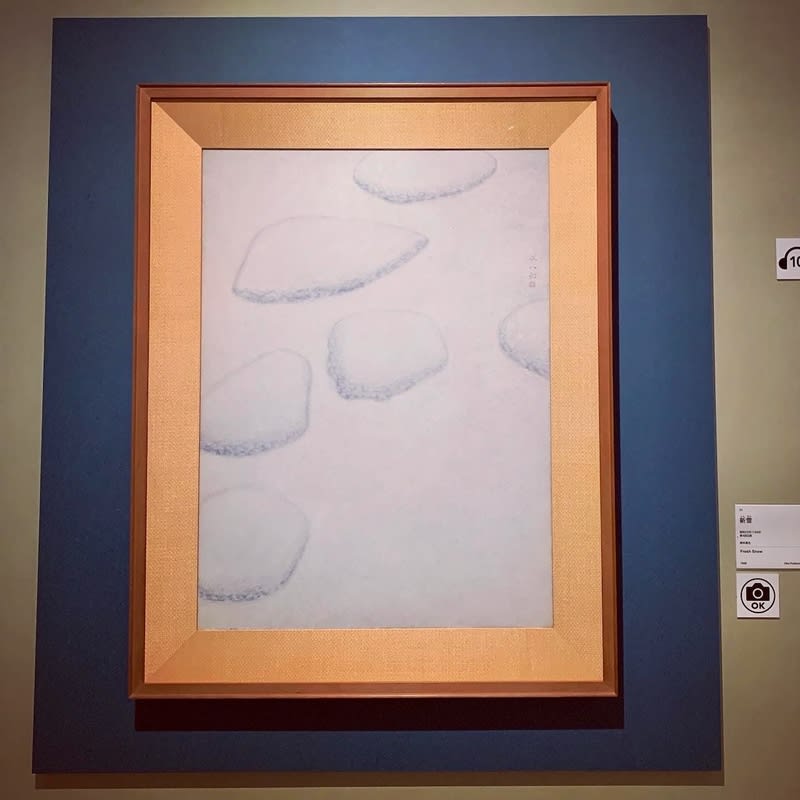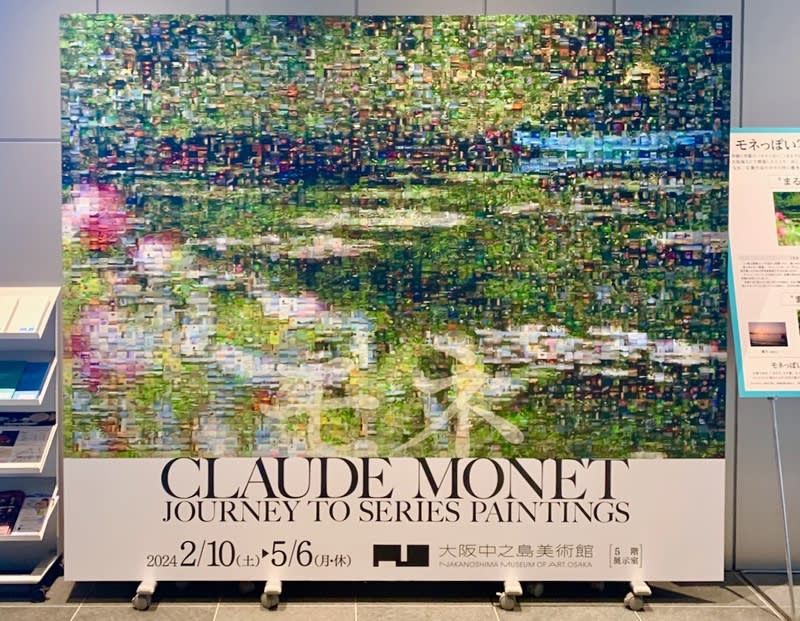1年ちょっと前に見た、ネオ狂言?赤塚不二夫?イタリア仮面劇?
一体何かよくわからないままお誘いを受けて見に行ったけど、
どう言うものなのかのお話のあと、前半は古典の狂言で「茸(くさびら)」。
これはとても賑やかな話ですごく楽しくカラフルな狂言ですが、
後半を見た後で古典の洗練がよくわかった。笑

後半は狂言「茸」から設定だけを残し、登場人物は漫画のキャラで「ネオ狂言ポルチーニ」
漫画やアニメを知る人たちにはたまらないくすぐりの数々だったけど、ちょっと盛り込みすぎかな。
せっかく狂言師がやっているのだからもう少し狂言の要素を残してもよかったのにと思いました。
解説で洗練によって失くしたもののことを話されていて、
あえて洗練から遠く離れたのだということはわかったけど、
でも失くしたものを取り戻すために「洗練」を全部捨てなくても良いのではと思ってしまう。
わたしは古典が好きだなと思う。
とっつきにくくても、わかればわかるほど面白くなるもんね。
でも大変意欲的な取り組みだとは思うので、また見たいものです。
一体何かよくわからないままお誘いを受けて見に行ったけど、
どう言うものなのかのお話のあと、前半は古典の狂言で「茸(くさびら)」。
これはとても賑やかな話ですごく楽しくカラフルな狂言ですが、
後半を見た後で古典の洗練がよくわかった。笑

後半は狂言「茸」から設定だけを残し、登場人物は漫画のキャラで「ネオ狂言ポルチーニ」
漫画やアニメを知る人たちにはたまらないくすぐりの数々だったけど、ちょっと盛り込みすぎかな。
せっかく狂言師がやっているのだからもう少し狂言の要素を残してもよかったのにと思いました。
解説で洗練によって失くしたもののことを話されていて、
あえて洗練から遠く離れたのだということはわかったけど、
でも失くしたものを取り戻すために「洗練」を全部捨てなくても良いのではと思ってしまう。
わたしは古典が好きだなと思う。
とっつきにくくても、わかればわかるほど面白くなるもんね。
でも大変意欲的な取り組みだとは思うので、また見たいものです。