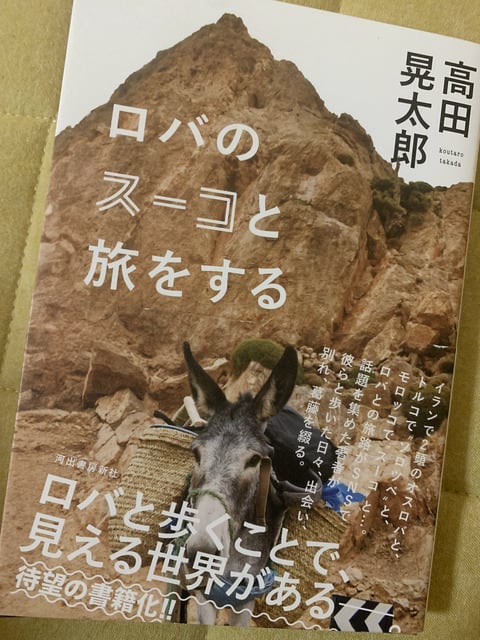ジュークボックス・ミュージカルというそうです、既存の曲を使ったミュージカル。
でもミュージカル映画ということも知らずに見たので、最初のうちは、
ああこりゃ時間潰し程度の映画かなと思った。
ポスターを見ると余命2ヶ月の妻が不器用な夫と初恋の人を探す旅に出るようなことが書いてあるけど、
この夫は不器用なんてものじゃなく、亭主関白という言葉でも甘い、すっごいモラハラ野郎。
きっと妻のありがたみがわかって反省したりして大団円でベタに泣かせるんだろうと思ったし、
こんなひどいモラ野郎ヒロインが許してもわたしは許さん!と思った。
さらに最初から最後まで昭和か!と突っ込みたい古き良き(←褒めてない)家父長制の価値観に貫かれてて
そういうとこは最後までうーむ、と思わせたけど、結局泣いて笑ってまた泣いてしまったから困った。笑
映画はベッタベタのベタ。最近見た「落下の解剖学」や「瞳を閉じて」のような深みや繊細さはどこにもなく、
ため息の出る美しくとことん考えられ作られた画面もない。それでもこれもまた映画なのよね。
漫画もラノベもトルストイも源氏物語も本であるのと同じく、映画の幅も驚くほど広いものやなぁと毎回驚く。
そして、それぞれにそれぞれの領域でちゃんと良いものがあるのよね。
この映画はホームドラマでもあり、ロードムービーでもあり、夫婦の話でもあり、
でもどれもベタで特別な物語は全然ないです。
それなのに最後まで見せるのはこのジュークボックス・ミュージカルの音楽の力もあるかなと思う。
最初に歌と踊りが始まって、え、これってミュージカル映画!?とわかったときは、
なんか古臭い愛の歌が歌われるのでちょっとがっかりした。でもずっと聴いてると、
途中にわたしの知ってる(そらで歌える)歌が2曲あって、
これってもしかしてそのシーンの時代のヒット曲?とやっと気づく。
わたしは87年からソウルに1年いて大学生だったのでその時の流行の歌はよく聴いていたのです。
そう思うと歌がベタでやや古臭いのも納得がいくし、わたしの知ってる2曲のように、
映画を見ている人がどの歌にも馴染みがあったら、そりゃどっぷりはまるだろう。
だから韓国の人とその他の国の人ではこの映画に対するはまり方は違うと思う。
ベタな話だし、家父長制の価値観を美談にするのはやめてほしいけど、
これは日本でリメイクしてほしいなぁと思います。
日本の70年代からの誰もが知るヒット曲で彩ったベタな映画を見てみたい。
音楽監督は「サニー永遠の仲間たち」や「スウィングキッズ」の人ということで、そりゃええやろと納得。
そういえば、映画の中で生前葬的なシーンがあるけど、わたしも生前葬はやってみたい。
でももっとおしゃれなやつにするぞー!と思ってます。
飲み物はシャンパンだけのシャンパン葬(ノンアルは用意します)、かっこいいー!
お金貯めなくては・・・
あとこの妻の人が怒りっぽくていつも不機嫌な夫に全然めげずにおしゃべりし続けるのみて、
自分もこれくらいおおらかで呑気だったらいろいろうまくいったのかもしれないなぁ、
などと苦い過去を思い出したりもしました。