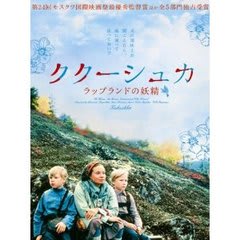こういうパフォーマンスの感想はどう書けばいいんだろう。
現代アートもそうだけど、感想書くの難しいです。
というか、これ半年も前のことなんだけど、なんとなく、
あ、書いてなかった、と思って、思い出しながら書きます。笑
(記憶はかなり怪しいです、すみません)
これはもともと写真家ホンマタカシが関西で何かやるっていうので
伊丹でやってたのを見に行ったら、それは本公演の前段階の
プレイベント的なパフォーマンスで、
本公演はまだ作ってる途中で、少しあと、ということだったのです。
で、そのプレがとても面白かったので、本公演は友達を誘っていきました。
プレの時はね、面白いかどうか、どんなものなのか
さっぱりわからないものには、人を誘えないのでひとりで行ったけど。
ホンマタカシの写真の意味は少しわかります。
雑誌の特集だけでも美術手帳や芸術新潮、ブルータスなどずっと読んで来たし
それらを、かなりいい感じにまとめた本も読んで、
それはとても勉強になったし面白かった。
(ホンマタカシについてはこちら→「たのしい写真」2012/11/11のブログ)
でも、だから彼の写真の意味はわかるけど、実はよさはあんまりわかんない。
いや、わかってるんだけど、
写真の位置づけやその値打ちが理屈ではわかっていても、
なんだかまだ納得できないままなもので。
最近よく、ちょっと面白い本屋おしゃれな本の
カタログ的な物撮り写真をやってて、そういうの見ても
ああ、ホンマタカシだなぁとは思うけど。
さて、このパフォーマンスですが、
コンタクトゴンゾというのはパフォーマンス的なアート集団?で、
プレの時はですね、暗い舞台に男たちが数人、大体1対1で、
小突き合いぶつかり合い、時には殴り合うという
緊迫感のある動きをしている3、40分くらいのパフォーマンスの後
ホンマタカシさんとコンタクトゴンゾの人たちが
一列に並んで椅子に座ってのトークをするという形でした。
こう文字で書いても意味わからないですね。
動画を探してみたけど中々いいのがないなぁ。
まあこんな感じかな↓contact Gonzo / Museum of Modern Art
この動画にはないけど、特にプレの時のパフォーマンス後半の真っ暗闇の中で
使い捨てカメラを撮ったり投げたりフラッシュ光らせながらする部分が
すごくよかったのです。
音と、人の動きや息にゆれる空気、たまにピカッと一瞬光るフラッシュ。
なんかムンムンする緊迫感と生々しさと熱気のようなものに
体が少し熱くなる感じがしました。
本公演もよかったけど、
個人的にはこのプレの時のシンプルで凝縮された緊張感の方が好みかな。
でも本公演ではプレにはなかった仕掛けがいろいろありました。
会場内に小さな小屋があって、その中に熊の着ぐるみがいて何かしてたり、
前回同様なパフォーマーの体のぶつけ合いの中に、
巨大なパチンコみたいなので会場の隅から果物を飛ばしてぶつけるとか、
ホンマタカシの撮った動画や写真も、いくつかのやりかたで使われていました。
プレにはいなかった女性メンバーがいて、そこは微妙に違和感があったかな。
女性性はどこにも出してないつもりだろうけど、小柄な女性で、
男性たちは彼女には、やはり同じテンションと力では向かえないはずで
そこに緊迫感を歪める微妙なゆるさが出ちゃうような気がして。
さて、同行の人は、人の心拍数に自分が左右されるのは不快なところがある
と言ってたけど、その不快さが快感だったりする、とわたしは思いました。
その不快さって、他人に支配される不快さですよね。
自分でコントロールできないことへの不快さ。
でも、それはつまり、負けている、と思うからなのかなと。
わたしは元々、支配ということには過敏なくらいなんだけど
こういう場所で(現実とは違う世界で)、外側のものに巻き込まれて
自分の意志の及ばないところに連れて行かれるのは楽しめる。
映画を見てる間、別の世界に入り込んでるのと同じようなことかな。
夢、みたいなものだと思えるから、積極的に入り込みたいくらいです。
違う感覚に支配されるのは面白い。
また、それ以上に、こういうパフォーマンスが
どちらかと云えば嫌いだった自分がすっかりかわったことも面白かった。
そしてこれ、プレ行っといてよかった。
プレでホンマタカシさんの話聞いといてよかった。
本公演は説明的なものはあまりなかったので、
現代アートと写真の文脈を知らずに見るよりは
ある程度知ってみる方が楽しめたのではと思います。
さらに、おまけのびっくり、がっくりがあって、
帰宅後Twitterで知ったんだけど
あの、着ぐるみの熊、終わった後に、頭の部分を脱いでて、
その後ろ姿だけちょっろっと見た記憶があるんですけど
なんとあの熊の中身はホンマタカシその人だったと!やられた!
ホンマタカシは本公演では表に出てこないのかなぁと思ってたのに
そういう可能性に気づきもしなかった自分が悔しいです。笑
現代アートもそうだけど、感想書くの難しいです。
というか、これ半年も前のことなんだけど、なんとなく、
あ、書いてなかった、と思って、思い出しながら書きます。笑
(記憶はかなり怪しいです、すみません)
これはもともと写真家ホンマタカシが関西で何かやるっていうので
伊丹でやってたのを見に行ったら、それは本公演の前段階の
プレイベント的なパフォーマンスで、
本公演はまだ作ってる途中で、少しあと、ということだったのです。
で、そのプレがとても面白かったので、本公演は友達を誘っていきました。
プレの時はね、面白いかどうか、どんなものなのか
さっぱりわからないものには、人を誘えないのでひとりで行ったけど。
ホンマタカシの写真の意味は少しわかります。
雑誌の特集だけでも美術手帳や芸術新潮、ブルータスなどずっと読んで来たし
それらを、かなりいい感じにまとめた本も読んで、
それはとても勉強になったし面白かった。
(ホンマタカシについてはこちら→「たのしい写真」2012/11/11のブログ)
でも、だから彼の写真の意味はわかるけど、実はよさはあんまりわかんない。
いや、わかってるんだけど、
写真の位置づけやその値打ちが理屈ではわかっていても、
なんだかまだ納得できないままなもので。
最近よく、ちょっと面白い本屋おしゃれな本の
カタログ的な物撮り写真をやってて、そういうの見ても
ああ、ホンマタカシだなぁとは思うけど。
さて、このパフォーマンスですが、
コンタクトゴンゾというのはパフォーマンス的なアート集団?で、
プレの時はですね、暗い舞台に男たちが数人、大体1対1で、
小突き合いぶつかり合い、時には殴り合うという
緊迫感のある動きをしている3、40分くらいのパフォーマンスの後
ホンマタカシさんとコンタクトゴンゾの人たちが
一列に並んで椅子に座ってのトークをするという形でした。
こう文字で書いても意味わからないですね。
動画を探してみたけど中々いいのがないなぁ。
まあこんな感じかな↓contact Gonzo / Museum of Modern Art
この動画にはないけど、特にプレの時のパフォーマンス後半の真っ暗闇の中で
使い捨てカメラを撮ったり投げたりフラッシュ光らせながらする部分が
すごくよかったのです。
音と、人の動きや息にゆれる空気、たまにピカッと一瞬光るフラッシュ。
なんかムンムンする緊迫感と生々しさと熱気のようなものに
体が少し熱くなる感じがしました。
本公演もよかったけど、
個人的にはこのプレの時のシンプルで凝縮された緊張感の方が好みかな。
でも本公演ではプレにはなかった仕掛けがいろいろありました。
会場内に小さな小屋があって、その中に熊の着ぐるみがいて何かしてたり、
前回同様なパフォーマーの体のぶつけ合いの中に、
巨大なパチンコみたいなので会場の隅から果物を飛ばしてぶつけるとか、
ホンマタカシの撮った動画や写真も、いくつかのやりかたで使われていました。
プレにはいなかった女性メンバーがいて、そこは微妙に違和感があったかな。
女性性はどこにも出してないつもりだろうけど、小柄な女性で、
男性たちは彼女には、やはり同じテンションと力では向かえないはずで
そこに緊迫感を歪める微妙なゆるさが出ちゃうような気がして。
さて、同行の人は、人の心拍数に自分が左右されるのは不快なところがある
と言ってたけど、その不快さが快感だったりする、とわたしは思いました。
その不快さって、他人に支配される不快さですよね。
自分でコントロールできないことへの不快さ。
でも、それはつまり、負けている、と思うからなのかなと。
わたしは元々、支配ということには過敏なくらいなんだけど
こういう場所で(現実とは違う世界で)、外側のものに巻き込まれて
自分の意志の及ばないところに連れて行かれるのは楽しめる。
映画を見てる間、別の世界に入り込んでるのと同じようなことかな。
夢、みたいなものだと思えるから、積極的に入り込みたいくらいです。
違う感覚に支配されるのは面白い。
また、それ以上に、こういうパフォーマンスが
どちらかと云えば嫌いだった自分がすっかりかわったことも面白かった。
そしてこれ、プレ行っといてよかった。
プレでホンマタカシさんの話聞いといてよかった。
本公演は説明的なものはあまりなかったので、
現代アートと写真の文脈を知らずに見るよりは
ある程度知ってみる方が楽しめたのではと思います。
さらに、おまけのびっくり、がっくりがあって、
帰宅後Twitterで知ったんだけど
あの、着ぐるみの熊、終わった後に、頭の部分を脱いでて、
その後ろ姿だけちょっろっと見た記憶があるんですけど
なんとあの熊の中身はホンマタカシその人だったと!やられた!
ホンマタカシは本公演では表に出てこないのかなぁと思ってたのに
そういう可能性に気づきもしなかった自分が悔しいです。笑