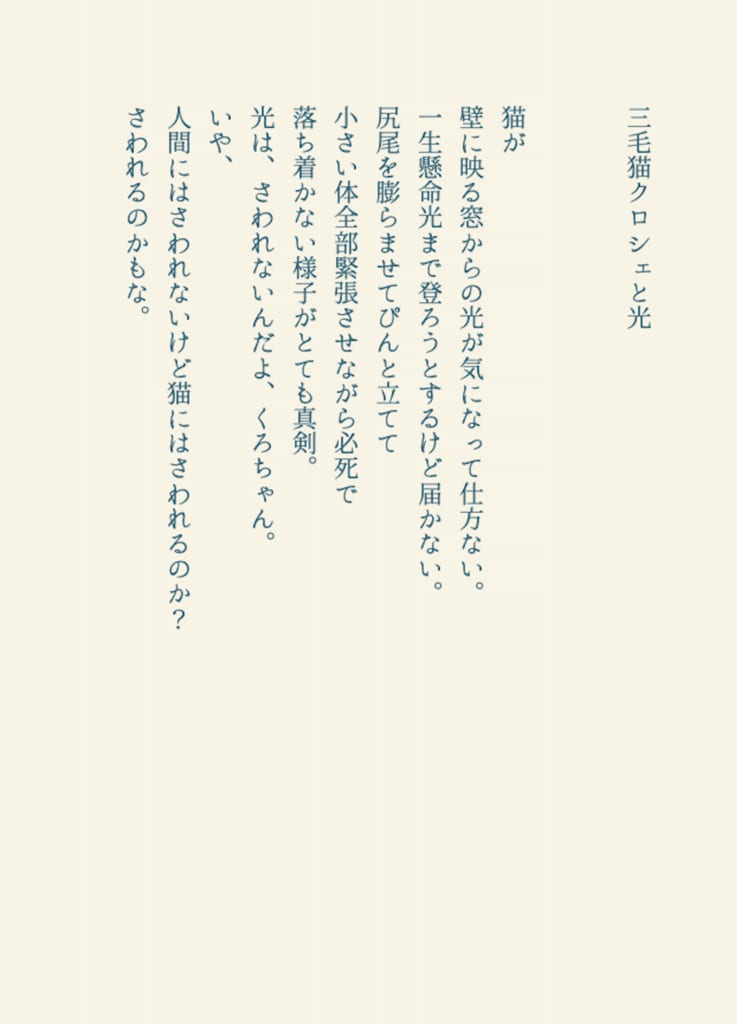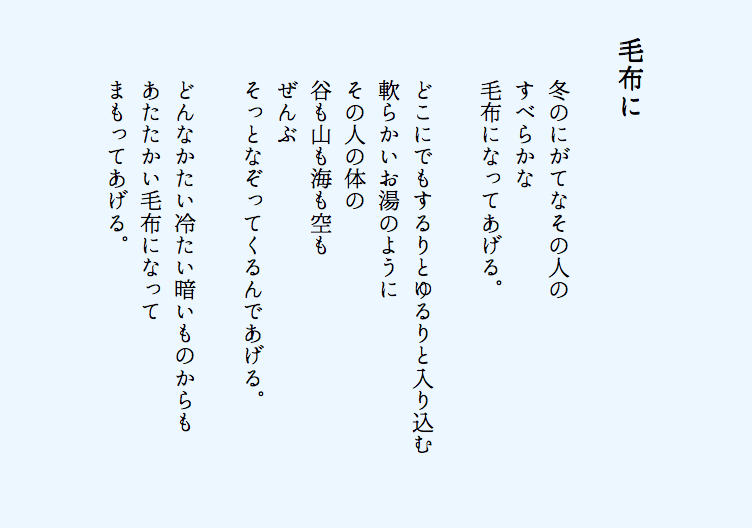先週、書きかけの途中までアップしたのが
一応終わったので改めて全文載せようと思ったら
長すぎて無理だった。
分割して載せます・・・。
長いので無理して読まないでいいです(笑)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
よく、肩をかじられた。
肩をかじるとミントの匂いがするって。
肩はスペアミント。
首筋はペパーミント。
そんなはずないじゃん、何でミントなんだよ、と言うと
だってそうなんだもん。
ね、今度うちの店でおいしいモヒート飲ませてあげる。
今年はプランターでミント育ててるから
特別おいしいモヒートなんだよ。
わたしは、こっちの方が好きだけど、と
また肩をかむ。
ミツはバーテンをしている。
背があまりに高いので、カウンターの中にいても
偉そうすぎて、なんか決まらないんだけどね~といいつつ
もう10年近くなる。
ミツの店は駅からは近いけど、小さな建物の細い隙間の奥を
階段を下りて行く地下の店だ。
そうきくと、おしゃれな隠れ家バーみたいだけど
それが全然違って、さびれた居酒屋みたいな入り口なので
あまり流行ってはいないらしい。
とはいうものの、ミツの店には実は行ったことがない。
ないけど、店の出来事を全部ミツが話してくれるので
ぼくは会ったことのないたくさんの人のことを知っている。
だからミツが何か言うと
さすが加藤さんだね。とか
長井さん、そりゃまずいだろ。とか
ヘぇ、すぎちゃん、頑張ったね~、とか
ああ、カナちゃんたち仲直りしたんだね、とか
相づちをうつことができるくらいだ。
ぼくはドーナツの移動販売をやってる。
自転車に乗って、朝揚げたドーナツをビジネス街で売るのである。
ワゴン車で売ればもっと儲かるかと思うけど
ワゴン車を改造するお金がないし、何か許可とかいるようだったら面倒だし
ひとりでそんなにたくさんのドーナツ揚げられないし、で
自転車販売でいいや、と思ってる。
家の台所で、フライパンを2つ並べてドーナツを揚げるんだけど
大体一日40個くらいかな、作るのは。
それ以上だと自転車に上手く乗せられないし
台所にずっといるのも疲れるから多くて40個。
40個全部売れたら6000円の売り上げになる。
結構売り切れる日が多い。雨の日とかダメだけど。
でも週に5日働いても、それだけじゃ一人暮らしは無理。
それでミツの家にいる。
ミツのところに来る前、ぼくは結婚してた。
いや、正確には今も婚姻状態にあるし子どももいる。
その頃は妻の実家の会社で営業の仕事をしてて、
十分以上のお給料をもらってたけど
その頃のことは、もうあんまり覚えていないな。
いいことも悪いこともあっただろうけど。
ミツは子どものピアノの先生だった。
ぼくより4つ年上で、その頃は30歳くらいだったか、
いろんな家に出張レッスンしにいくのが仕事で、バーテンはまだしていなかった。
ぼくの息子は3歳で、ぼくはまだ早いと思ったけど
妻の意向でピアノを始めることになり
公園ママの口コミでお願いしたのがミツだった。
最初の印象はあんまりない。
年上だとわかってたし、背も高すぎる。
それにいくらぼくだって
子どものピアノの先生をどうこういう気持ちで見たりしない。
息子はピアノに全く興味がなく、ミツを手こずらせたが
一年目の発表会を見ると、妻は大満足でミツにお礼をすると言い張り
有名フレンチレストランの夕食を予約してきた。
でも当日、息子が熱を出し、キャンセルするのも店に悪いからと
ぼくとミツにふたりで行かせたのだった。
そして、その夜からぼくはミツのところにいるのである。
唐突だったし、子どももいるのにひどい男だと言われる。
全くその通りだなぁと思う。
その夜、何かドラマチックなことがあったわけではなく
ロマンチックな流れになったわけでもなく
レストランからの帰り道、駅までの間にミツの家があって
そこで急お腹が痛くなっただけのことだった。
トイレを貸してもらうことになって、かなり長い間そこから出られなかった。
そりゃ、恥ずかしくて困ったけど仕方ない。
熱い昆布茶を入れてもらって、トイレに何度かこもりながらも、
なんとなく話が弾んで、朝になってしまった。
結婚して以来、朝帰りなどしたことがなかった。
仕事は妻の父親と一緒だから、ぼくの行動は全部把握されてたし
妻の父親は若い頃アメリカに住んでいたことがあるせいか
家庭を何より大事にする人で、家族で夕食を食べられる時間に仕事が終わるよう
いつも上手くスケジュールを組んだ。
ぼくは営業だから、取引先と食事をすることも多かったけど
義父がそんなだから、取引先もこの会社は夜が早いと言うのが暗黙の了解で
あまり遅くまで付き合わされることはなかったのだった。
そこへ、朝帰りである。
朝になり、ミツがさすがに眠そうな顔になってきて、
帰らなきゃと思いつつ、あれこれ説明が面倒だな、と思うと
中々立ち上がることができず、
ミツもミツで、ぐずぐずしているぼくに無理に帰れとも言わないので
そのまま何となくとミツの家に住み着いてしまったのだった。
もちろん、ミツの家に居着くようになってからはいろいろあったけど
とにかくミツは何も言わず、ぼくはぼくで家族からできるだけ逃げ回って
何も解決しないまま10年が過ぎた。
自分でも、なんてだらしない男だろうと思う。
だらしないというか、情けない男だな。その結果ひどい男。
まわり中に迷惑をかけた。
ぼくが転がり込んでから、ミツはピアノの先生ができなくなってしまった。
そりゃそうだ、公園ママの口コミはすごいのだ。
それで、ピアノの先生の他に、
ときどきピアノのあるレストランで演奏してたツテで、
家から電車で20分くらいの小さなバーでアルバイトをはじめた。
最初はそこのピアノを弾きながら雑用をしていたのだけど
バーテンダーがやめたのをきっかけに、彼女がずっとカウンターの中で
バーテンをするようになったのだった。
その後、改装の時にピアノは売ってしまって
彼女はもう、家でしかピアノを弾かなくなってしまった。
ぼくは自分がだらしなく居着いたせいで
彼女の人生がどんどん薄暗くなっていくようで申し訳なくてかわいそうで仕方ない。
仕方ないと思いつつも、ドーナツを揚げながら半日だけ働いて
後は本を読んだりしてるだけの生活を変えることもできないのだった。
それから10年くらいたったが、ミツと二人きりの時、彼女は随分甘えん坊になる。
はたから見たら見苦しい眺めだろうなぁと思う。
40歳過ぎの女と、それより少し若い甲斐性のない男が、
手入れされてない雑草ぼうぼうの庭のある古い平屋で
ミッちゃん、タァちゃんと呼び合って、
毎日窓辺のソファに並んで腰掛け、見つめながらおしゃべりしたり
何となく手を握り合ったりしてるのだ。
ミツがぼくのどこを気にいったのかわからないけど
なぜかぼくみたいなダメ男は案外モテて、結婚する前もよく告白とかされたものだ。
ダメ男ではあるけど、二股かけたり、浮気したりしたことはない。
いや、ミツのことが、妻からみたら浮気ということになるのだろうか。
そう思うと、またミツがかわいそうになる。
ぼくの自分勝手な思い込みじゃなければいいけど、
だからといってミツが不幸とも思えない。
ミツは朝方仕事から戻るとお化粧を落としながら
店での話を全部してくれる。
ぼくはノロノロとドーナツの準備をしながら
相づちをうちながら、彼女の話を聞く。
そして揚げたての一番おいしそうなのを
丁寧に入れたブラックコーヒーと一緒にミツにあげる。
すると、タァちゃんのドーナツ、毎朝一番に揚げたてを食べられるなんて
タァちゃんのドーナツのファンの人に申し訳ないな、と必ず言う。
ぼくのドーナツには確かに常連さんがいるけど、ファンと言う程のものでもない。
雨が降ると、まあいいか、となるのか買いにきてくれないし
自分で言うのもなんだけど、ぼくのドーナツは特別ではない。
普通の、普通程度においしいドーナツでだけど
その辺のチェーン店より特においしいとも思えない程度だ。
何しろ研究とか探求とかが苦手なぼくだから
これで売れるなら、これでいいや、と思ってしまい
普通のドーナツの域から決して出ないのだ。
ぼくがミツを好きになったのはミツの家に居着いてしばらくしてからだった。
最初は、とにかく家に帰るのが億劫で、責められたりするのが面倒で
ずるずるミツのところにいただけだった。
ミツと初めて寝たのも、一週間以上経ってからだったろうか。
それまで、ずっと居間のソファで寝てたし
ミツのこともピアノの先生なので、先生と呼んでいたし
夜になっても、なぜかそういうことを考えなかった。
最初の夜は、お腹を壊しトイレに何度も駆け込みながら明けたのだ。
ロマンチックな展開になるわけがない。
でも、ミツの家で妻の家族から隠れながら、
何も起こらないままの一週間が経ってしまった頃、
もう家に帰ってどんな言い訳をしても信じてもらえないだろうな、と思うと
ふと、やけくそな気持ちになって
まだピアノの先生をしてて夜は家にいたミツを抱いた。
ミツは全然抵抗しなかった。
ぼくのこと、好きなの?と聞くと
好きじゃないとこんなことしないでしょ、と答えた。
いつから?
昆布茶飲んでる時。
たくさんピアノ弾くと肩が凝るって言ったら
マッサージしてくれたでしょ。
あれが最高によかった。こんなマッサージ上手い人なら好きになって大丈夫と思った。
体の気持ちがあんなにわかるなら、心の気持ちも絶対通じるって思ったの。
それに、あなたの肩、ミントの匂いがする。気持ちいい匂い。
そうか。先生の体の気持ち、もっとよくわかるようになるよ。
そして、もう一度抱いた。
ぼくのマッサージの上手さは折り紙付きだ。
子どもの頃から上手かった。
母も姉もぼくに肩をもませるのが好きだったし
大人になると、肩こりの女の子は競ってぼくに
背中を揉んでほしがった。
でも、ミツはぼくとは対称的に、絶望的に下手だ。
自分はひどい肩こりのくせにどうすれば、そんなにツボを外せるのか、
ぼくにはさっぱりわからない。
人間の、体の気持ちはわからないのよ、とミツは言い訳する。
ピアノならわかるんだけどねぇ、と。
確かに、毎朝ピアノを開けて最初に弾く時のミツの指は
ベテランのマッサージ師の指みたいに見える。
ぽろんぽろんと弾き始め、デタラメに即興でばららばららと弾いていく。
おはよう、起きてる?そろそろ目を覚まして。と口に出さずに語りかけながら
ゆっくりとピアノをほぐしていくのだ。
ツボを一つも外さず、ピアノの求めるところを探しながらほぐしてやり
開いてやり、ピアノの目を覚まさせる。
それが人間にも出来たら、ミツのマッサージはぼくのよりずっと上だよ、と言うと
人間はこんなに応えてくれないからねぇ、と歌うようにいいながら
次の瞬間には、完全に目が覚めてミツに向き直っているピアノに没頭してしまう。
そういう風にいわれると、ミツにそんなつもりはなかったのはわかってるけど
迷惑ばかりかけて、苦労ばかりさせて、さびしい思いもさせて、
しかも呑気に幸せな自分が申し訳なくなる。
一文無しでそのまま居着いたぼくを、ミツは養わなくてはいけなかったけど
数週間のうちにピアノの先生は全部断られ、
(それもひどい憎悪を込めて、だ。主婦の敵というヤツだな)
すぐに今のバーで働くようになったのだった。
家を出てミツと暮らしてみると、妻の家族から連絡が来るのは怖いし面倒だったけど
なんだか無期限の夏休みみたいなゆったりした気分になって
ぼくも働かなきゃなぁと思いつつ、中々働く気になれなかった。
幸せで、その幸せがミツを好きにさせるのか
ミツが好きだから幸せなのか、わからないけど
まあ両方だろう。ぼくは満ち足りていたのだ。お金はなかったけど。
ミツの家はミツが音大を卒業する年に事故でなくなったご両親から相続したものだ。
両親は別の家に住んでいて
この家はミツの祖父母が存命中に住んでいた家ということで
何年も誰も住んでなくて荒れていたのだそうだ。
家自体は小さい平屋で相当古く住み心地いいとはいえないけど
駅の近くのいい場所にあるので、土地に良い値がつく。
そのせいで相続の時、売ってしまおうと言う弟とちょっともめたらしく
それ以降、あまり行き来してなかったようだ。
ぼくが来てからは、きっとぼくのせいで、親戚にもそっぽむかれてる。
もちろん、ぼくの方の親戚だって同様だけど
ぼくの甥っ子だけは時々訪ねてくれる。
甥っ子と言っても妻の兄の子どもだから、ぼくとは血がつながっていない。
家には内緒で来ているようだ。
そりゃそうだろう。ミツの作ったご飯なんか食べて
のんびりおしゃべりしてるなんて、妻の家に知られたらオオゴトだ。
県トップの進学校に通う高校生で、かしこくてやさしい。
ぼくはマッサージのコツなど教えてやったりする。
ミツとは将棋を指したりしている。
甥は将棋部でミツも将棋好きで話が合う。
おばさんの将棋の手はきれいだ、といつも彼は言う。
それを聞くと、ぼくは自分が何も間違ったことをしていないような気になり
ほっとするのだ。
もちろん、間違ってないのはミツだけで
ぼくなんか間違いだらけのダメ男だってわかっているけど。
甥っ子が来ると、
ミツが喜んで作ってくれるご馳走を食べながら
息子の消息を聞いたりする。
ぼくだって妻にも息子にも、やっぱり申し訳ない気持ちで一杯なのだ。
だからといって、どうすればいいのかわからないので
結局そのまま逃げてるままなんだけど。
甥っ子がいるときミツは、明るく常識的な
普通の家の奥さんのように振る舞う。
ソファで僕の横にも座らない。
だって、不潔、と思われたくないもん。
たったひとりのタァちゃんの味方なんだもんね、という。
常識がないのは僕の方だ。
確かに、彼はマジメでやさしい高校生なんだから
ぼくらみたいな事情がなくても
自分の親くらいの年の、
40歳にもなるいい大人が甘え合っているのを見るのはイヤだろう。
そうは言ってもミツのぼくを見る目はいつも甘いし
ぼくがミツに話しかける声もきっと甘くて
高校生をちょっとどぎまぎさせたり
軽い嫌悪感を感じさせたりしてるかもしれないなと思う。
でも、ぼくもできるだけ、常識的なおじさんのフリをしようと思うようになった。
ぼくはともかく、ミツには何も間違ったところはなくて
本当に珍しいいい女なのだということを
ぼく以外の誰か一人でも知っていてほしかったのだ。
朝、ミツに揚げたてのドーナツを食べさせて少しゆっくりした後
ぼくはドーナツの移動販売に出かけ
ミツは目の下にクマを作ったまま眠る。
雨がひどい日は時々、移動販売をさぼって
ミツと一緒に朝寝したりする。
一日4時間くらいしか眠らないミツと違って
ぼくはいくらでも眠れるのだ。
でも数ヶ月前から、ミツの睡眠時間が長くなって来たのに
ぼくは中々気付かなかった。
ミツが仕事に行く時の化粧が濃くなってきたのも
ずっと気付かずにいた。
ある晴れた5月初めの午後、
ゴールデンウィーク前の金曜日で
ビジネス街で商売してるぼくにとっては
明日から長い休みという、うきうきする仕事帰りだったのだけど
家に帰るとミツがお化粧もせずにぼんやりしていたのだった。
ミツ。ミッちゃん、どうしたの。具合悪いの?
あ、タァちゃん、お帰り。
何でもないよ。頭痛が少しするだけ。
きっと雨が降るのよ、低気圧に弱いからなぁ、わたしの頭。
その日もそれから支度して、ミツは仕事に出かけた。
その夜、ミツはミントの鉢を一つ持って帰ってきた。
夏になったらおいしいモヒート作ってあげる。
ミントは消化にいいのよ。
すっとする匂いだけど、わたしはリフレッシュというより
リラックスするな、この匂い。と、
タァちゃんの肩の匂いと同じ匂いだもん、と言いながら
くんくん小さな葉っぱの匂いをかいだ。
今作ってよ、と言うと
モヒートは夏でしょう。
夏になったら、いっぱい作ってあげる、と笑った。
ゴールデンウィークもミツの仕事は関係ない。
ずっと働いていた。
ミントの鉢も元気いっぱいで、わさわさと大きな葉っぱを茂らせ出していた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(後編に続く)→
モヒートとドーナツ後編