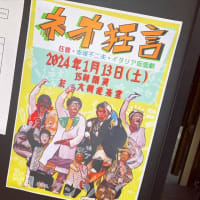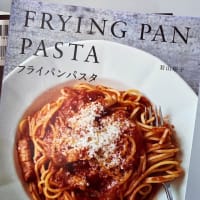こういうタイトルってここ数年の流行りなのかな?、
著者の北村紗衣さんはTwitterで昔からフォローしてて
彼女の書評や映画評も時々見てきたので読んでみました。
100本のうち50本以上は見ているけど、見てない映画も結構あって、見てみたいなぁ。
レンタルビデオのツタヤがあった時代なら、お店になくても取り寄せで、時間はかかっても
案外安く古い映画でもなんでも借りることができたけど
今は配信になければ見られない時代になっちゃった。
わたしはアマゾンプライムには入ってるけどネットフリックスも他のも入ってないので
観たくてもみられない映画が案外多い。この本の中の多くもそうだと思うから、それは残念。
20歳前後まで何度も死にたいと思ったことのある著者が、
その後もっと大変の人生になってももう死にたいと思うことがなくなったのが、
>楽しそうな映画が多すぎて死んでいるヒマがありません。人生の目的は死ぬまでひたすら楽しいことをすることだと思えるようなりました。(略)人生の役に立つと思って映画を見ているわけではないのですが、どういうわけかひとりでに映画は私が生き抜くのを助けてくれるようになりました。
ということで、映画の力すごいな。
そしてこういう映画を見て大人になれたらよかったなと思う外国の映画を
22のテーマで100本紹介されています。
わたしは映画自体はもちろんだけど、この本が若い頃にあればよかったなと思います。
だって、例えば若い頃に「紳士は金髪がお好き」を何度も見たけど
それをフェミニズムの観点から見たことは一度もなかったのでした。
>ふたりともセクシーで、自分の性欲や性的魅力、モテっぷりに居心地の悪さを感じていませんが、この映画にはそうした女性の性的な自信や自己主張を断罪するようなところもありません。
なのにわたしはこれをシスターフッド映画であるとは思わず、
女性をめぐる男たちの話のように見ていた気がします。
それはわたしのせいだけではなく、古い映画はずっとやっぱり主役は男たちだったのです。
一昨年か、林真理子が浅丘ルリ子の人生を書いた「RURIKO」を読んだけど(面白かった!)
そこにも、女優が添え物やお飾りの花、あるいは主人公の相手役でしかなく
本当の主役になる映画は、以前はなかったことがよく書かれています。
浅丘ルリ子(異常にかわいい)でさえ、小林旭や誰かの相手役という扱いが長かったのよね。
今回初めてそういうフェミニズムの視点で考えて、とても興味深かった。
大好きな映画「ホリデイ」はロマンチックなラブコメとして何度も見ていて
特にジュード・ロウの優しさ誠実さに毎回感銘を受けるんだけど、
男女関係に関する大事なメッセージがあるというふうには見てなかった。
紳士だからというより、性的同意や男女の平等が大事ということが
ちゃんと盛り込まれている映画なのだと書かれていて、うれしくなりました。
家のインテリアやハンナ夫妻の様子などに関心を持った「ハンナ・アーレント」では
>しかしながらこの映画には希望もあります。それはある程度の知的好奇心さえあれば学歴などを問わずに深く考えることが可能であり、深く考える人にはそれを信頼して助けてくれる人も出てくる、という可能性が示されていることです(中略)考え続けることが闘う道なのです。
と書かれていて、確かに最後まで彼女を理解して寄り添ってくれる夫や友人がいたことを思い出します。
「未来を花束にして」の邦題のダメさは「嘆かわしい」と書いてくれてほんとそうよね!
>いくら平和的に頼んでも、モードのような女性たちにはそもそも議論の席につく権利すら認められていないので、議会に影響を及ぼすことができず、無視されるだけです。無視されないために女性たちは先鋭化しました。暴力は良くないことですが、過去の政治運動を考えるときに、「抗議活動は平和的」であって当然だという考え方では通用しないこともある・・・ということをこの映画は教えてくれます。
この映画を見て、一見過激な抵抗運動や活動が、どれだけ切実な思いでなされたのかに気づき
その後のわたしの考え方はここに書かれているように変わったのでした。
「グロリア」もいい映画だけど、わたしは大人の責任や子育てについては考えてなかったなぁ。
>子育てというのは家事や料理がうまいというようなことより、大人として未成年者が保護を求めてきた時に、責任をもって対処できるかということだ、というのがこの映画がさりげなく示唆していることだと思います。
「マダム・イン・ニューヨーク」については言葉というものについて書かれている。
>外国語を学ぶ際に、意思疎通だけできればいい、ただの技術だ・・・という考え方と、言語はそれを取り巻く文化や自己表現の手法などを含めた全人格の教育だという考え方があると思うのですが、シャシは最初はおそらく前者のツールとしての言語を学ぼうとして、最後は後者のような解放の手段としての言語に至るという過程を経ています。
若い映画好きな人に読んでほしい本ですね。
著者の北村紗衣さんはTwitterで昔からフォローしてて
彼女の書評や映画評も時々見てきたので読んでみました。
100本のうち50本以上は見ているけど、見てない映画も結構あって、見てみたいなぁ。
レンタルビデオのツタヤがあった時代なら、お店になくても取り寄せで、時間はかかっても
案外安く古い映画でもなんでも借りることができたけど
今は配信になければ見られない時代になっちゃった。
わたしはアマゾンプライムには入ってるけどネットフリックスも他のも入ってないので
観たくてもみられない映画が案外多い。この本の中の多くもそうだと思うから、それは残念。
20歳前後まで何度も死にたいと思ったことのある著者が、
その後もっと大変の人生になってももう死にたいと思うことがなくなったのが、
>楽しそうな映画が多すぎて死んでいるヒマがありません。人生の目的は死ぬまでひたすら楽しいことをすることだと思えるようなりました。(略)人生の役に立つと思って映画を見ているわけではないのですが、どういうわけかひとりでに映画は私が生き抜くのを助けてくれるようになりました。
ということで、映画の力すごいな。
そしてこういう映画を見て大人になれたらよかったなと思う外国の映画を
22のテーマで100本紹介されています。
わたしは映画自体はもちろんだけど、この本が若い頃にあればよかったなと思います。
だって、例えば若い頃に「紳士は金髪がお好き」を何度も見たけど
それをフェミニズムの観点から見たことは一度もなかったのでした。
>ふたりともセクシーで、自分の性欲や性的魅力、モテっぷりに居心地の悪さを感じていませんが、この映画にはそうした女性の性的な自信や自己主張を断罪するようなところもありません。
なのにわたしはこれをシスターフッド映画であるとは思わず、
女性をめぐる男たちの話のように見ていた気がします。
それはわたしのせいだけではなく、古い映画はずっとやっぱり主役は男たちだったのです。
一昨年か、林真理子が浅丘ルリ子の人生を書いた「RURIKO」を読んだけど(面白かった!)
そこにも、女優が添え物やお飾りの花、あるいは主人公の相手役でしかなく
本当の主役になる映画は、以前はなかったことがよく書かれています。
浅丘ルリ子(異常にかわいい)でさえ、小林旭や誰かの相手役という扱いが長かったのよね。
今回初めてそういうフェミニズムの視点で考えて、とても興味深かった。
大好きな映画「ホリデイ」はロマンチックなラブコメとして何度も見ていて
特にジュード・ロウの優しさ誠実さに毎回感銘を受けるんだけど、
男女関係に関する大事なメッセージがあるというふうには見てなかった。
紳士だからというより、性的同意や男女の平等が大事ということが
ちゃんと盛り込まれている映画なのだと書かれていて、うれしくなりました。
家のインテリアやハンナ夫妻の様子などに関心を持った「ハンナ・アーレント」では
>しかしながらこの映画には希望もあります。それはある程度の知的好奇心さえあれば学歴などを問わずに深く考えることが可能であり、深く考える人にはそれを信頼して助けてくれる人も出てくる、という可能性が示されていることです(中略)考え続けることが闘う道なのです。
と書かれていて、確かに最後まで彼女を理解して寄り添ってくれる夫や友人がいたことを思い出します。
「未来を花束にして」の邦題のダメさは「嘆かわしい」と書いてくれてほんとそうよね!
>いくら平和的に頼んでも、モードのような女性たちにはそもそも議論の席につく権利すら認められていないので、議会に影響を及ぼすことができず、無視されるだけです。無視されないために女性たちは先鋭化しました。暴力は良くないことですが、過去の政治運動を考えるときに、「抗議活動は平和的」であって当然だという考え方では通用しないこともある・・・ということをこの映画は教えてくれます。
この映画を見て、一見過激な抵抗運動や活動が、どれだけ切実な思いでなされたのかに気づき
その後のわたしの考え方はここに書かれているように変わったのでした。
「グロリア」もいい映画だけど、わたしは大人の責任や子育てについては考えてなかったなぁ。
>子育てというのは家事や料理がうまいというようなことより、大人として未成年者が保護を求めてきた時に、責任をもって対処できるかということだ、というのがこの映画がさりげなく示唆していることだと思います。
「マダム・イン・ニューヨーク」については言葉というものについて書かれている。
>外国語を学ぶ際に、意思疎通だけできればいい、ただの技術だ・・・という考え方と、言語はそれを取り巻く文化や自己表現の手法などを含めた全人格の教育だという考え方があると思うのですが、シャシは最初はおそらく前者のツールとしての言語を学ぼうとして、最後は後者のような解放の手段としての言語に至るという過程を経ています。
若い映画好きな人に読んでほしい本ですね。